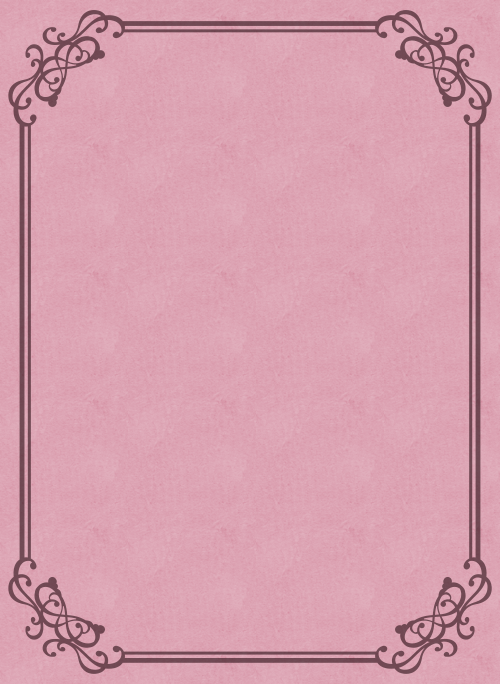恐る恐るバルコニーに戻ると、王子が手すりをよじ登ろうとしているところだった。
「うわああっ。ちょっと! 何してんの! 死なないで!」
私が叫びアッシュが背後から王子の体を羽交い締めにして、仰向けにコンクリートの床に倒れこんだ。
すぐさま王子の上に馬乗りになり
「何やってんだ。馬鹿野郎!」
と彼の肩をがくがくと揺さぶる。
「ち、ち、違う。死ぬつもりなんかない! 君たちを追おうとして……先回りしようと思ったんだ」
「バカ! 当たりどころが悪かったら死ぬぞ!」
「はっはっは。僕は王子だぞ?」
「王子だって死ぬ! バカじゃねーの!?」
「え……そうなの……?」
王子は驚いているようだった。
「大丈夫? 起きて」
私は手を差し伸べた。
しかし王子はその手を払うと隅っこへ移動し、子供のように膝を抱えた。
「なんだ、そのいじけたポーズは」
「アッシュ。こういうタイプとのコミュニケーションのコツを教えるわ。ここにいるのは10歳の子供だと思うのよ」
「はあああああ? どこからどう見ても大人じゃねえか」
「しっ。せっかく私たちに心を開きかけてるんだから。だって追おうとしてくれてたわけでしょ」
「……そうだったな」
私は王子の傍らにしゃがみ込み、その顔を覗き込んだ。
「何か悩み事があるなら話してみて」
王子はぷい、と顔をそむけた。
「……言っても仕方ない」
「わからないわよ。力になれるかもしれない」
王子は「無理だよ」とさらに拗ねた態度をとる。
「あーのーなー。さっきからエラが親切に聞いてやってんだから、とっとと言いやがれ。もたもたすんなら蹴りいれるぞ」
アッシュがこめかみに青筋をたてる。
「わわっ。わかったよ。僕、実は好きな子がいるんだ。でも身分違いで結婚できない」
王子は思い切ったようにそう言った。
「はあああ? それ、エラに全く関係ないだろ! 文句が言いたいなら親父に言え!」
「アッシュ! 怒鳴っちゃダメ。王子が心を閉ざしちゃう」
「むう」
「そんな事じゃないかなと思っていたのよ。うちにも王子みたいな人たちがいてね。何かあるたびに八つ当たりばかりしているの。だから、きっと、そうなんだろうな、って。どんな子なの?」
沈んでいた王子の顔が、ふっ、と和らいだ。
「金物屋の娘だ。お忍びで行った祭りで知り合った。ピンク色の巻き髪に親しみやすい丸い顔。甘い声。見るからに女の子って感じの、可愛い子なんだ」
ピンク色の巻き髪……。
悪役に出てきそうな造形だなあ、と思ったけれど、言わないでおく。
「ただ、その子との結婚は無理だ。資産家だが庶民だし……王子の妃にはふさわしくない」
「うーん。でも、それ王様たちに言った? 案外許してくれるかもよ。だって結婚相手を見つけてくればいいんでしょう?」
「絶対に無理だよ。許可を取るまでもない。だって僕には王子としての責任がある。運命には逆らえない。何も持ってない君にはわからないさ」
ちょっと待って。
今あなた、聞き捨てならないことを言いましたね?
「何言ってるの……責任なら私の方があなたなんかよりよっぽど感じてるわ!」
私は王子の襟首を掴んでぐらぐら揺らした。
「でもね……それが何よ……運命はね、落ちてくるもんじゃない。自ら掴み取るものなの!」
王子は不思議そうに瞳をパチパチさせている。
「それにね、お飾りの妻なんて、普通じゃないわよ? いくら王子だってあり得ないわ。結婚は好きな人とするべきよ」
と言った瞬間、頭が急速回転し始めた。
「そうよ……私ったら何を考えてたんだろう……結婚って、好きな人とするものよ……義務とか責任なんて関係ないわ……それなのに私ったら、確定事項として、会ったこともない人との結婚を受け入れていた……なんて事……私、最初っから間違えてたんだわ」
「エラ、大丈夫か?」
ゾーンに入った私を心配してか、アッシュが声をかけてきた。
「大丈夫。自分のバカさ加減に呆れてるだけ。でも、もうスッキリしたわ」
私は王子の目を真っすぐに見た。
「私はあなたとは結婚できません。だってこれっぽっちも好きじゃないもの。多分一生好きにならないと思うわ。全然好みじゃないし、むしろこの手を好む女性がいるのか心配になってくるレベルというか」
「なっ……」
アッシュが王子の頭をぽかんとはたく。
「傷ついた顔すんな。自業自得だ」
「はい……」
王子は素直に言うと首をすくめる。
「これは一応善意で言っておくけど、その性格、若いうちに治さないと大変よ? 金物屋の娘さんも今のあなたじゃ、好きになってもらえる可能性は低いと思うわ」
「はああああ?」
「黙って聞け」
「はい……」
「まあただ、王子だからなあ。肩書きに引っかかる女はいるんじゃないの? 贅沢できそうだし」
「でもここまで性格が捻じ曲がってるのよ? 浮気していいとか言いながら実際したらわーわー怒りまくるタイプじゃない? 優しくもないくせに束縛が強いとか夫としては最悪だと思うの」
「し、失礼な! 俺はデリカシーの塊だぞ! 四方八方に気を使いまくって消耗してるのがわからないのか……!」
「いきなりお飾りの妻とか言い出す男がデリカシーを語るな」
「……すみません」
王子は肩を落としこう言った。
「そもそも相手に合わせてまで結婚したいとは思わないからな。やっぱり俺は適当な相手を選ぶよ。その代わり、お飾りの妻とかはもう言わない。ひどい目にあったからな」
「んー、そうなの? 勿体ないなあ」
私は王子に語りかけた。
「自慢じゃないけど、私、18年間恋をしたことがないの……そんなの、夢物語と思ってたわ。でもあなたには好きな人がいる。この奇跡を放っておくの? 恋する人を失っていいの? 運命に流されるだけの頑張れない王子なんて、誰も応援してくれないわ。そうでしょ?」
私はさっきのアッシュを思い出していた。
彼女は私の目的を叶えるという責務を負っている。
しかしその私が侮辱されているのを見れば、自らの感情を優先した。
役割を捨てても、私の尊厳を守ろうとしてくれた。
あの時……本当はとっても嬉しかった。
私のために怒ってくれたことが……味方してくれたことが、物語よりも私を優先してくれたことが涙が出るほど嬉しかった。
王子が嬉しそうに笑う。
「へえ。お前18年間、男いないの? ぷぷっ。モテなさそうとは思ったが想像以上だったな」
「見下せる立場か。ああなんかもう、こいつと話しても無駄って気がしてきたわ。帰ろうぜ。エラ」
「待って……! 行かないで!」
「いてほしいなら、それらしい態度を取れ!」
「はい……」
王子の声のトーンが変わる。
「確かに……愛は何よりも尊いのかもしれない。そんな気がしてきた」
「王様に相談するべきよ。そもそも、認められるわけがない、って言うのが思い込みかもしれないし、もしダメでもOK もらえるまで粘ればいいじゃない。本気で愛する相手に出会えたのなら、手放しちゃダメ。だってそれは奇跡だもの」
私は真剣だった。
トラックにはねられた時、私には別れを惜しむ人がいなかった。
きっと私がいなくなっても、家族以外で悲しむ人はいないだろう。
そういう人間関係を築いてこなかったことがとてつもなく残念だった。
「あなたの恋を応援しているわ。だから頑張って(性格は治さなきゃだめだけどね)」
王子はまじまじと私を見た。
そして
「でも……」
「この流れで納得しねえのかよ。空気を読め!」
アッシュが叫ぶ。
「さっさと王のところに行け。今言った通りのことをやれ。俺が爆発する前に行動しろ!」
「わ、わ、わかった!」
王子ははじかれたように立ち上がる。
そしてドタバタと窓に向かって走り、振り返った。
「ありがとう。エラ。アッシュ」
その笑顔は憑き物が落ちたように晴れ晴れとしていた。
「うわああっ。ちょっと! 何してんの! 死なないで!」
私が叫びアッシュが背後から王子の体を羽交い締めにして、仰向けにコンクリートの床に倒れこんだ。
すぐさま王子の上に馬乗りになり
「何やってんだ。馬鹿野郎!」
と彼の肩をがくがくと揺さぶる。
「ち、ち、違う。死ぬつもりなんかない! 君たちを追おうとして……先回りしようと思ったんだ」
「バカ! 当たりどころが悪かったら死ぬぞ!」
「はっはっは。僕は王子だぞ?」
「王子だって死ぬ! バカじゃねーの!?」
「え……そうなの……?」
王子は驚いているようだった。
「大丈夫? 起きて」
私は手を差し伸べた。
しかし王子はその手を払うと隅っこへ移動し、子供のように膝を抱えた。
「なんだ、そのいじけたポーズは」
「アッシュ。こういうタイプとのコミュニケーションのコツを教えるわ。ここにいるのは10歳の子供だと思うのよ」
「はあああああ? どこからどう見ても大人じゃねえか」
「しっ。せっかく私たちに心を開きかけてるんだから。だって追おうとしてくれてたわけでしょ」
「……そうだったな」
私は王子の傍らにしゃがみ込み、その顔を覗き込んだ。
「何か悩み事があるなら話してみて」
王子はぷい、と顔をそむけた。
「……言っても仕方ない」
「わからないわよ。力になれるかもしれない」
王子は「無理だよ」とさらに拗ねた態度をとる。
「あーのーなー。さっきからエラが親切に聞いてやってんだから、とっとと言いやがれ。もたもたすんなら蹴りいれるぞ」
アッシュがこめかみに青筋をたてる。
「わわっ。わかったよ。僕、実は好きな子がいるんだ。でも身分違いで結婚できない」
王子は思い切ったようにそう言った。
「はあああ? それ、エラに全く関係ないだろ! 文句が言いたいなら親父に言え!」
「アッシュ! 怒鳴っちゃダメ。王子が心を閉ざしちゃう」
「むう」
「そんな事じゃないかなと思っていたのよ。うちにも王子みたいな人たちがいてね。何かあるたびに八つ当たりばかりしているの。だから、きっと、そうなんだろうな、って。どんな子なの?」
沈んでいた王子の顔が、ふっ、と和らいだ。
「金物屋の娘だ。お忍びで行った祭りで知り合った。ピンク色の巻き髪に親しみやすい丸い顔。甘い声。見るからに女の子って感じの、可愛い子なんだ」
ピンク色の巻き髪……。
悪役に出てきそうな造形だなあ、と思ったけれど、言わないでおく。
「ただ、その子との結婚は無理だ。資産家だが庶民だし……王子の妃にはふさわしくない」
「うーん。でも、それ王様たちに言った? 案外許してくれるかもよ。だって結婚相手を見つけてくればいいんでしょう?」
「絶対に無理だよ。許可を取るまでもない。だって僕には王子としての責任がある。運命には逆らえない。何も持ってない君にはわからないさ」
ちょっと待って。
今あなた、聞き捨てならないことを言いましたね?
「何言ってるの……責任なら私の方があなたなんかよりよっぽど感じてるわ!」
私は王子の襟首を掴んでぐらぐら揺らした。
「でもね……それが何よ……運命はね、落ちてくるもんじゃない。自ら掴み取るものなの!」
王子は不思議そうに瞳をパチパチさせている。
「それにね、お飾りの妻なんて、普通じゃないわよ? いくら王子だってあり得ないわ。結婚は好きな人とするべきよ」
と言った瞬間、頭が急速回転し始めた。
「そうよ……私ったら何を考えてたんだろう……結婚って、好きな人とするものよ……義務とか責任なんて関係ないわ……それなのに私ったら、確定事項として、会ったこともない人との結婚を受け入れていた……なんて事……私、最初っから間違えてたんだわ」
「エラ、大丈夫か?」
ゾーンに入った私を心配してか、アッシュが声をかけてきた。
「大丈夫。自分のバカさ加減に呆れてるだけ。でも、もうスッキリしたわ」
私は王子の目を真っすぐに見た。
「私はあなたとは結婚できません。だってこれっぽっちも好きじゃないもの。多分一生好きにならないと思うわ。全然好みじゃないし、むしろこの手を好む女性がいるのか心配になってくるレベルというか」
「なっ……」
アッシュが王子の頭をぽかんとはたく。
「傷ついた顔すんな。自業自得だ」
「はい……」
王子は素直に言うと首をすくめる。
「これは一応善意で言っておくけど、その性格、若いうちに治さないと大変よ? 金物屋の娘さんも今のあなたじゃ、好きになってもらえる可能性は低いと思うわ」
「はああああ?」
「黙って聞け」
「はい……」
「まあただ、王子だからなあ。肩書きに引っかかる女はいるんじゃないの? 贅沢できそうだし」
「でもここまで性格が捻じ曲がってるのよ? 浮気していいとか言いながら実際したらわーわー怒りまくるタイプじゃない? 優しくもないくせに束縛が強いとか夫としては最悪だと思うの」
「し、失礼な! 俺はデリカシーの塊だぞ! 四方八方に気を使いまくって消耗してるのがわからないのか……!」
「いきなりお飾りの妻とか言い出す男がデリカシーを語るな」
「……すみません」
王子は肩を落としこう言った。
「そもそも相手に合わせてまで結婚したいとは思わないからな。やっぱり俺は適当な相手を選ぶよ。その代わり、お飾りの妻とかはもう言わない。ひどい目にあったからな」
「んー、そうなの? 勿体ないなあ」
私は王子に語りかけた。
「自慢じゃないけど、私、18年間恋をしたことがないの……そんなの、夢物語と思ってたわ。でもあなたには好きな人がいる。この奇跡を放っておくの? 恋する人を失っていいの? 運命に流されるだけの頑張れない王子なんて、誰も応援してくれないわ。そうでしょ?」
私はさっきのアッシュを思い出していた。
彼女は私の目的を叶えるという責務を負っている。
しかしその私が侮辱されているのを見れば、自らの感情を優先した。
役割を捨てても、私の尊厳を守ろうとしてくれた。
あの時……本当はとっても嬉しかった。
私のために怒ってくれたことが……味方してくれたことが、物語よりも私を優先してくれたことが涙が出るほど嬉しかった。
王子が嬉しそうに笑う。
「へえ。お前18年間、男いないの? ぷぷっ。モテなさそうとは思ったが想像以上だったな」
「見下せる立場か。ああなんかもう、こいつと話しても無駄って気がしてきたわ。帰ろうぜ。エラ」
「待って……! 行かないで!」
「いてほしいなら、それらしい態度を取れ!」
「はい……」
王子の声のトーンが変わる。
「確かに……愛は何よりも尊いのかもしれない。そんな気がしてきた」
「王様に相談するべきよ。そもそも、認められるわけがない、って言うのが思い込みかもしれないし、もしダメでもOK もらえるまで粘ればいいじゃない。本気で愛する相手に出会えたのなら、手放しちゃダメ。だってそれは奇跡だもの」
私は真剣だった。
トラックにはねられた時、私には別れを惜しむ人がいなかった。
きっと私がいなくなっても、家族以外で悲しむ人はいないだろう。
そういう人間関係を築いてこなかったことがとてつもなく残念だった。
「あなたの恋を応援しているわ。だから頑張って(性格は治さなきゃだめだけどね)」
王子はまじまじと私を見た。
そして
「でも……」
「この流れで納得しねえのかよ。空気を読め!」
アッシュが叫ぶ。
「さっさと王のところに行け。今言った通りのことをやれ。俺が爆発する前に行動しろ!」
「わ、わ、わかった!」
王子ははじかれたように立ち上がる。
そしてドタバタと窓に向かって走り、振り返った。
「ありがとう。エラ。アッシュ」
その笑顔は憑き物が落ちたように晴れ晴れとしていた。