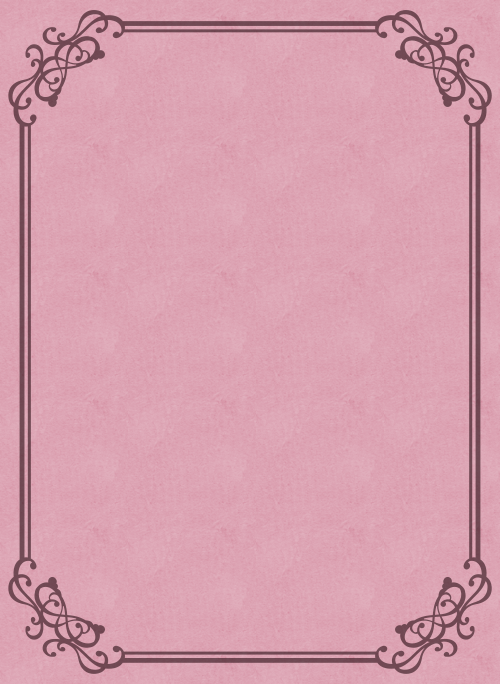「お前な。俺のお姫様にさっきから何言ってんだ。お前を愛するつもりはない? お飾りの妻? はあああ? 寝言も休み休み言え!」
私は両目を大きく見開いた。
「ちょっと、アッシュ、いつから聞いてたの?」
「最初から!」
そうか。
この人は私を水晶玉でずっと見ていられる人だった。
物陰でずっと見ていてくれたのね。
「無礼な。僕を誰だと思ってる! 王子だぞ!」
腫れた頬を撫でながら王子は言った。
「甘ったれのクソガキだろ?! 何が王子だ。うるせーよ。バーカ」
「なんだとう?」
いきり立つ王子にアッシュは人差し指をくいと曲げて言う。
「やるのか? 受けてたつぜ」
そして王子の前に頬を突き出した。
「先に手を出したからな。ハンデとして5発殴られてやるよ。絶対に抵抗しないから、さあ、やれ」
背が高いとはいえ、女性VS男性なのに、明らかにアッシュの方が強く見える。
きっと殴られた後にボコボコにするんだろうな、という未来まで見えた。
しかし。
「ちょっと、ダメよ、アッシュ。あなたの綺麗な顔が傷ついちゃう」
私は焦って彼女を止めた。
せっかくの恵まれた資産は大事にしてもらいたい。
「数日で治るさ。さあ、やれ!」
「いや、それは……できない。僕は……平和主義なんだ!」
王子は、真っ赤な顔をしてそう言った。
「情けねえやつだな」
アッシュは私の腕をつかむと「さあ、帰るぞ」
グイグイ引っ張る。
「ちょ、待って」
「こんなところにいられるか」
アッシュはかんかんに怒っていて、引っ張る力もものすごく強い。
私は何度も王子を振り返ったが、彼は魂が抜けたように呆然としていた。
バルコニーを出て大股で歩くアッシュに私は言う。
「お願い。アッシュ。止まって」
やっとアッシュは立ち止まってくれた。
私はゆっくりと彼女の腕をふりほどく。
「君は物語の主人公だ。誰よりも幸せになる義務がある。俺がそうさせてやる。たとえ運命を捻じ曲げてでも」
「私のために怒ってくれてありがとう。でも、私、戻るね」
「はあ? あんなやつのところに? ダメだ。行かせない」
アッシュはとんでもないという風に眉毛をあげた。
「戻るの。もう決めてるの」
「なんでだよ!」
「私がシンデレラだからよ。この話に責任があるの。逃げられないわ」
「……君は物語の主人公だ。誰よりも幸せにならなきゃ。あいつじゃ無理だ」
「逃げても何も変わらない」
私のためにこんなに怒ってくれるアッシュに申し訳ないなと思いつつも私は一歩も引かなかった。
アッシュは、ぼりぼりと長く綺麗な髪をかきまぜて苦悩を示した後、きっぱりと言った。
「自分が犠牲になればいいとか思うなよ。物語を成立させるために」
「私は誰かの犠牲になんかならないから安心して。私ほど自分の幸せに対して貪欲な人間はいないと思うから」
「くそう。ツッコミどころがたくさんあるけど、多分説得できない」
アッシュは溜め息まじりにこう言った。
「わかった。その代わり俺も行く」
「心強いわ」
私はホッとして笑顔を見せた。
私は両目を大きく見開いた。
「ちょっと、アッシュ、いつから聞いてたの?」
「最初から!」
そうか。
この人は私を水晶玉でずっと見ていられる人だった。
物陰でずっと見ていてくれたのね。
「無礼な。僕を誰だと思ってる! 王子だぞ!」
腫れた頬を撫でながら王子は言った。
「甘ったれのクソガキだろ?! 何が王子だ。うるせーよ。バーカ」
「なんだとう?」
いきり立つ王子にアッシュは人差し指をくいと曲げて言う。
「やるのか? 受けてたつぜ」
そして王子の前に頬を突き出した。
「先に手を出したからな。ハンデとして5発殴られてやるよ。絶対に抵抗しないから、さあ、やれ」
背が高いとはいえ、女性VS男性なのに、明らかにアッシュの方が強く見える。
きっと殴られた後にボコボコにするんだろうな、という未来まで見えた。
しかし。
「ちょっと、ダメよ、アッシュ。あなたの綺麗な顔が傷ついちゃう」
私は焦って彼女を止めた。
せっかくの恵まれた資産は大事にしてもらいたい。
「数日で治るさ。さあ、やれ!」
「いや、それは……できない。僕は……平和主義なんだ!」
王子は、真っ赤な顔をしてそう言った。
「情けねえやつだな」
アッシュは私の腕をつかむと「さあ、帰るぞ」
グイグイ引っ張る。
「ちょ、待って」
「こんなところにいられるか」
アッシュはかんかんに怒っていて、引っ張る力もものすごく強い。
私は何度も王子を振り返ったが、彼は魂が抜けたように呆然としていた。
バルコニーを出て大股で歩くアッシュに私は言う。
「お願い。アッシュ。止まって」
やっとアッシュは立ち止まってくれた。
私はゆっくりと彼女の腕をふりほどく。
「君は物語の主人公だ。誰よりも幸せになる義務がある。俺がそうさせてやる。たとえ運命を捻じ曲げてでも」
「私のために怒ってくれてありがとう。でも、私、戻るね」
「はあ? あんなやつのところに? ダメだ。行かせない」
アッシュはとんでもないという風に眉毛をあげた。
「戻るの。もう決めてるの」
「なんでだよ!」
「私がシンデレラだからよ。この話に責任があるの。逃げられないわ」
「……君は物語の主人公だ。誰よりも幸せにならなきゃ。あいつじゃ無理だ」
「逃げても何も変わらない」
私のためにこんなに怒ってくれるアッシュに申し訳ないなと思いつつも私は一歩も引かなかった。
アッシュは、ぼりぼりと長く綺麗な髪をかきまぜて苦悩を示した後、きっぱりと言った。
「自分が犠牲になればいいとか思うなよ。物語を成立させるために」
「私は誰かの犠牲になんかならないから安心して。私ほど自分の幸せに対して貪欲な人間はいないと思うから」
「くそう。ツッコミどころがたくさんあるけど、多分説得できない」
アッシュは溜め息まじりにこう言った。
「わかった。その代わり俺も行く」
「心強いわ」
私はホッとして笑顔を見せた。