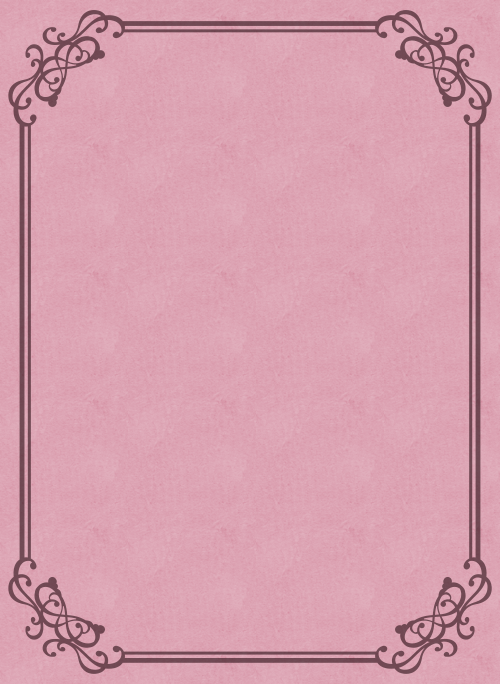忘れられない記憶と、忘れちゃった記憶。
切なくて苦しい恋心。
───────
水城 茜
みずき あかね
加藤 康樹
かとう こうき
───────
「いいなぁ、こうちゃんは絵が上手くて」
私の幼なじみの加藤 康樹は、絵の具で絵を描く。
いつも夕方からこうちゃんの絵が見たくて見に行くんだよね。
「なんで?描きたいもの描いてるだけだけど」
「私も絵上手くなりたいなあって、なんかこうちゃんって器用だよね、やりたいことすんなり見つけてさ、それも上手いって、なんかずるい」
「ずるいってなんだよ、好きなことやったらいいじゃん、ほらネイル好きだろ?極めたらいいんじゃねえの」
「そうだけど、自分でやるのはいいんだけどさ。ほら、裕子って高校の時の友達いたじゃん?裕子にさー、ネイル出来るなら私にもして欲しい、お願い出来ない!?って言われちゃって、私はただの自己満でしてるだけなのに、人になんかできないよ」
「俺が変わりに教えようか」
「えっ、こうちゃんネイルも出来んの!?」
「やった事ないけど茜に試しにやってみっか?」
「教えて欲しい!ネイルセット家から待ってきていい?」
私とこうちゃんの家は隣同士だ。
いわゆる親同士も知り合いの仲のいい幼なじみってやつだ。
「持ってきてみ」
こうちゃんは、子供の頃から優しくて、私が落ち込んだりした時もすごい慰めてくれて。
ほんとに優しい幼なじみ。
私の大切な家族みたいな存在。
異性の関係には1度もなったことない、なるとも思ってない。
だってお互い、意識したことなんてないから。
そうなるきっかけがあったとしても、私たちはならない気がする。
「ネイルセット持ってきたよ」
私は家から急いでネイルセットを取りに帰って持ってきた。
「どんなネイルにする?」
「どんなのが出来るの?」
「筆も細いのと太いのあるし、ちゃんと揃えてるみたいだから、基本なんでも出来ると思う。普段書いてるような空とかもできるかも」
やっぱり、こうちゃんはすごいなあ。
「夕日、できる?茜色のカラーあるの、私じゃ出来なくて、教えてもらえないかな」
「いいよ、やってみよ」
ネイルの仕方を私の手を使って、教えてもらった。
こうちゃんの教え方はとても丁寧だった。
「まずベースのカラーを決めて、夕日を書くなら紺色とか先に塗ってもいいかも、それから白色を下半分にモコモコに見えるように塗って、それから初めに決めた茜色を細い筆で分度器みたいに丸を半分にして書く」
「な、なるほど…」
あっという間に両手塗り終わってしまって、でも私は何も習得出来ずにいた。
とりあえず、最後に細い筆で茜色を載せるってことだけ分かった。
「自分の足にやってみようかな」
「いいね、やってみなよ。見守るわ俺」
そう言って私は靴下を抜いて裸足になった。
ちょっぴり足が臭くないかなって心配になったけど、意外と大丈夫だった。
今は夏で、外はすごい数のセミが鳴いている。
「今日のセミやけにうるさいね」
エアコンは冷房がついているけど、外の音が中まで聞こえてきて、セミの鳴き声は気持ち的に暑く感じた。
「早く秋になって欲しいよな、暑いし」
こうちゃんは、秋になって欲しいと言った。
「夏って、暑いしセミもうるさいし嫌だよね」
「俺はセミの鳴き声、割と夏だなって感じがして好きだけどな、ちょっと鬱陶しいけど。それに8月に茜の誕生日あるし」
「夏好きなんだね、私の誕生日何が関係あるの?私、自分の誕生日迎えても、もう嬉しくない。だってうちら22歳になるんだよ?おばさんだよ。こうちゃんもおじさんだよ」
「それはまだ早いだろ。確かに高校生とか見ると戻りてえとか思うけどな」
「戻りたいよね、あの頃に」
✱✱✱✱✱✱✱
「こうちゃんの卵焼き、もーらいっ」
「あ、最後に食べようと思ってたのに、とるなよ」
「先に食べないこうちゃんが悪い」
私はよく、こうちゃんのお弁当の中身を勝手に食べてた。
「仲良いねあんたら」
裕子と私とこうちゃんの3人でご飯を食べていたから、裕子がいつも私たちにほんと仲良いねって毎回言われてた。
「だって保育園からの仲だもん、そりゃ仲良いよ。ねっ、こうちゃん」
「まあ、卵焼き取られるのもいい加減慣れたな」
「じゃあこれから卵焼きは私が貰いまーす」
「俺のお弁当だろ」
「はいはい。喧嘩は、よそでして」
✱✱✱✱✱✱✱
「裕子、元気にしてる?」
「そっか、こうちゃんは裕子ともうしばらく会ってないんだっけ」
そう言いながら、私は自分の足にベースカラーの紺色を塗る。
「高校卒業してみんなで打ち上げ行った時以来かな」
「4年くらい前か、だいぶ昔だね」
「茜と3人でご飯食べてた時が懐かしいよ」
ベースカラーを塗り終えて、専用のLEDライトで硬化する。
こうちゃんは、ベットの上に乗って床で作業してる私のことを見てる。
「ここから、どうやるんだっけ」
硬化し終えると、やり方なんて全部忘れた。
「やっば覚えられなかったか」
「私じゃ、無理だね…やっぱ、こうちゃん器用すぎる」
「貸してみ、ベットの上のりな、塗りやすいから」
私はこうちゃんと座る場所を交換し、私はベットの上で体操座りをして、つま先だけ差し出してる。
「塗るよ?」
「お願いします」
その一言で、こうちゃんは、私の足に塗り始めた。
なんだか冷たい感触がつま先に伝わって、ちょっと変な感じがした。
こうちゃんが私の足をじっくり見ながら、ネイルを塗っていて、目線が真剣なのに、私だけ変な感じしてきちゃって、自分が分からなくなった。
なに、このドキドキ。
「ねえ、こうちゃん」
「どした?」
「ううん、…なんでもない」
こうちゃんは、何も感じ取ってないよね。
平気だよね。
なんだが、心臓がバクバクしてきて、心がはりさけそう。
こうちゃんって、まつ毛こんなに長かったっけ。
鼻筋も通ってて、そういえばこうちゃんってモテてたんだっけ。
「茜…?調子悪い?顔赤くない?」
まって、私って顔赤い??
「ちょっとあつい、?かも…おかしいな、エアコン効いてるのに」
「熱ある?」
こうちゃんの手は止まっていると思ったら
いつの間にかネイルが完成していた。
そんなこうちゃんは、私の前髪を上にあげ、おでこをくっつけて熱があるかの確認をしてきた。
「こうちゃん大丈夫だよ私」
「あついよ、茜、熱あるってねたほうがいいよ。このまま横になりな」
そう言って、私の足と脇の下に手を入れると、体を持ち上げられ、ベットに横にさせられた。
「こうちゃん、熱じゃないよ私。私ね、こうちゃんにドキドキしてる今」
「急に何言って」
そんな彼に向かって何言ってもだめだと感じた私は、腕を引いて私の上に来るように引っ張った。
「…こうちゃん、キスしちゃだめ?」
こうちゃんの腕を掴んで、私は上にいるこうちゃんを見上げながら、そう言った。
自分の行動に、すごく驚いたし、まず、ドキドキしてる自分が自分じゃない感じがして、少し恥ずかしかった。
「忘れられなくなっても知らないぞ」
「こうちゃんとの関係、続けられなくなっちゃうかな」
「さぁな、俺はいいけど」
そっか、こうちゃんは、モテてたから沢山遊んでるんだ。
初めてじゃないんだ、こういう経験。
「私、初めてなの、でもこうちゃんなら、優しいこうちゃんなら預けられる気がする、だからだめ?」
「優しくする」
そう言ってこうちゃんは私に優しくキスをした。
何度何度も、ソフトなキスをすると、段々と長いディープキスへと変わった。
経験がない私は、どこで息吸ったり吐いたりしていいかわからなくて、キスが途切れる度に、っはぁっと息を吐いていた。
「可愛い、茜」
その言葉で心臓がドクドクとしているのが、より感じた。
「こうちゃん好き」
好きって言う言葉が出るのは、自分でも意外だった。
「俺も」
俺もと、同意してくれたものの、こうちゃんは好きとは言ってくれなかった。
「最後までする?茜、湿ってるけど」
私の下着はぬるぬるだった。
「こうちゃん、約束して欲しい、明日には元通りって」
「約束できなかったら?」
「ここで終わり」
「もう1回キスしていい?」
「話聞いてる?ねぇ…んっ…」
そこから記憶があいまいで、思い出せるのは、「痛くない?」って聞かれたことと、奥まで彼を感じたあの感覚だけだった。
幸せだった。
彼のぬくもりが、まだ私の体の中に残ってる感じがして、幸福を感じた。
起き上がると隣でこうちゃんは寝ていて、私たちは服は着ていた。
もしかして、夢…?
「こうちゃん、起きて」
「ん、…なんだよ」
「私たち寝ちゃった?」
「寝てたな」
「そうじゃなくて、シちゃった?」
私がそう聞くと、彼はほっぺにキスをして。
「茜ちゃんにはひみつ」
そう口にした。
✱✱✱✱✱✱
保育園の頃のことを私は思い出した。
「こうちゃん…?」
隣で寝てる子と手をこっそり繋いでこうちゃんがキスしてるところを見てしまった。
それを見た私に、『茜ちゃんにはひみつ』と言った。
保育園の頃、他の子にキスしてるこうちゃんを見てから、当時好きだった私は我慢しなきゃって好きな気持ち隠すことで、自分にも嘘ついて好きな気持ち忘れてたってこと。
きっとこの気持ちは、また忘れなきゃいけないこと。
こうちゃんには、きっと他の女の子がいて、私じゃだめなこと。
思い出したら辛くなった。
たくさんの気持ちが溢れ出てきて、その場で泣いてしまった。
わんわんとなく私に、「どしたどした」とこうちゃんが声をかけながら、私の背中をさする。
「ううん、いいの、ありがとう、私大丈夫!ごめんね、次会った時にはもう忘れるから、またね」
私はこうちゃんの部屋を急いででた。
きっと、しばらく会えない、この気持ちが消えるまで。