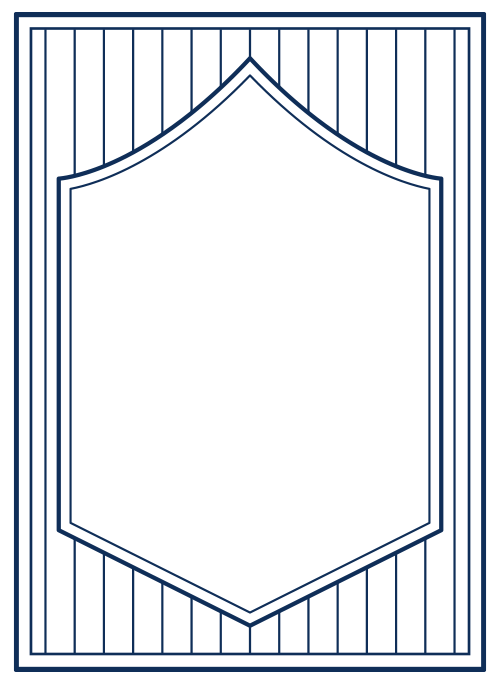あの日、私たちは二人で、叩き壊した。
二人の間にあった何か。築き上げた何か、育てた何か、見て見ぬふりをした何か、それでいてお互いの間に確かにあった何かを。
「綾音さー、こんな所でうじうじしてないでさっさとカレシに訊けよ」
「わーかってるってばあ。でもさ、訊いて『そうだよ』とか『別れよう』って言われたらどうしたらいいのよぉー」
「そん時はそん時だろ」
「充希くんってば、他人事《ひとごと》だからってテキトーすぎー」
私は恨みがましい目で、さっきからフライドポテトをひたすら口に入れ続ける充希くんを睨みつけた。ちょっとそれ、私のじゃん。充希くんが要らないっていうからSサイズにしたのに。
その日、私は充希くんを大学近くのファストフード店に呼び出した。充希くんは大学の近くに下宿していて、家庭教師のバイトしかしてないから日曜日は暇なのだ。
日曜の午後の店内は混雑している。子供がハンバーガーセットに付いたおまけのおもちゃを取り出してはしゃぐのを、母親がたしなめている。かと思えば別の席では高校生位の男の子たちが部活の話なんかをしている。私たちみたいな大学生同士の客もいて、適度な喧噪に満ちていた。
充希くんが、はあ、とこれみよがしな溜息をついた。あっという間に空っぽになってしまったポテトの袋に長い指を伸ばして、短いやつが残ってないか確認する。
「休みの日に俺をこんな所に呼び出しておいて、テキトーって何だよ。ちゃんと話聴いてやってんじゃん」
「そうだけどさあ、返事がテキトーだって言ってんの。だって、先輩に直接訊けないから充希くんに訊いてるのにさあ、男の心理ってヤツを。なのに全然参考になんないんだもん」
アイスティーに差したストローを啜ったら、ズズッと嫌な音がした。もう、早く氷溶けないかな。そしたらもうちょっと飲めるのに。そう思いながらガツガツとストローで氷を突いていたら、充希くんが呆れたように笑った。
「その先輩の心理なんてわかんねーよ。俺、二股なんか掛けた事ねーし」
充希くんが、袋から出てきた小指の先ほどのカリカリのポテトを摘まみ上げた。
「そうだね。充希くんはそんなことしなさそう」
私はへへ、と眉を下げて笑うと、充希くんが口に入れようとした最後のポテトを横からかっさらう。
私が飲食店のバイトを終えた帰りに充希くんに電話をした時、外には悔しいくらい綺麗な月が昇っていた。
「もしもし、充希くん?」
「……何だよ、綾音か。こんな時間にどうした」
「充希くん、あのさぁ、先輩に振られちゃった……」
「あー、とうとう」
「とうとう、って何よぉ。先輩、私の他にも彼女いたんだよ。やっぱりあの日に見ちゃったのは彼女だったんだー。問い詰めたらあっさり白状してさ」
「……」
「どういうことなの、って訊いたら、『知らなかったの?』だよ? ねえ、信じられる?」
「……」
「『綾音ちゃんはわかってて付き合ってるんだと思ってた』だって。そんなわけないっての!」
充希くんはずっとだんまりを決め込む。だからか余計に、私の方はヒートアップする一方だ。
「先輩があんな人だったなんて! 優しい人だと思ってたのに」
「……」
「ねぇ、ちょっと、充希くん聴いてる?」
「……綾音の言う『優しい』って何だよ」
不意に電話越しに届いた声音の低さに私は驚いて肩を揺らした。思わずスマホをぎゅっと握り直す。これまで聞いたことのない冷たさだった。
「どうせ、休みの日は遊園地とか映画とかオシャレなカフェに連れて行ってくれて、可愛い可愛いって言ってくれて、バイトで失敗しても庇ってくれる、とかそんなんだろ」
充希くんの声は珍しく怒気を含んでいた。私はすぐに言い返したけど、初めて聴く声音に怯んで少しだけ弱々しくなってしまった。
「そうだよ、先輩はいっつもそうしてくれたんだもん。何よ、充希くんはそんなことしたことないんでしょ」
「ほっとけよ。大体な、こんな夜遅くに掛けてくんなよ。デリカシーないのかよ。綾音は、カノジョ持ちが休みの日の夜に何してるのか考えつかねーのかよ」
「あ……そうだね」
ここに至って私はようやくそのことに思い至って、頬が赤くなった。充希くんはいつも私の話を聞いてくれるから、ついそのことを忘れそうになる。でも彼には歳下の彼女がいるのだった。
「ごめん、切るね。カノジョちゃんにも謝っておいてね!」
電話を掛けた時の勢いはいつの間にか無くなっていたけれど、私は見えない相手に向かって笑みを作る。
じゃあまた大学で、とその笑顔のまま続けようとしたのに、ぽつりと零れた声に遮られた。
「……どこにいんの、今」
「ん? 駅のホーム、の端っこ。星が沢山見えるんだー」
「最寄り?」
「うん。この時間だとね、車両の編成数が減るから、ホームの端っこの方は電車が止まらないんだ」
「待ってろ」
「うん? なあにー、来てくれるの? ちゃんと帰れるって。ダメだよ、夜はこれからなんだから。カノジョを追い返したら、頭をはたいてやるんだから」
「とにかくそこで待ってろ」
「はいはーい、うん、もうすぐしたら帰るよー」
屋根の途切れたホームの端で、私は空を見上げる。充希くんの声は耳を素通りして、たださっきの鋭さが消えたことにほっとして笑い声を上げた。
どうしたってまだここから立ち上がれそうにない。だから充希くんが来ても来なくてもどっちだって良かった。
だから充希くんがホームに現れた時、私はちょっとぽかんとしてしまった。充希くんは息を荒くして、憮然とした顔を崩しもせずに私を見下ろす。悪いことをしたのは私じゃないのに、今にも怒られそうな気がする。けれど怖いと思うよりも驚きの方が大きくて、私はベンチに座ったまま、彼をまじまじと見てしまう。本当に来たの? なんて失礼なことを思いもした。
「綾音」
「あれー、充希くん、もしかしてカノジョを本当に追い返してきちゃったの? ダメじゃん。よし、そこに座って。はたいてやるー」
だけど私はそんなことはせずに、へらりと笑って再び星空を見上げた。
あれは何座かな。
充希くんがため息をついて隣に腰掛けた。色落ちしたジーンズに包まれた長い脚がホームに投げ出される。
「あー、充希くんも星が見たくなった? 綺麗だよねえ。あれ、何座かなあ。夏はさ、はっきり形がわかるものが少ないと思わない? 星座なんて中学の授業以来だもん、わかんないね」
「綾音」
「あれとさあ、あれと……繋げたらハートになると思わない? 充希くん。ハートだよ」
私はデタラメにいくつかの星を選ぶと、指先で空にハートを描いてみせた。我ながら二十歳も過ぎて子供じみた発想だ。それに大体、ガラでもない。
だけど、回らない頭では何だかそんなことしか思いつかなかった。
「先輩とは、ハートにならなかったなあ……どうやっても繋がらなかったよ」
「綾音」
鼻の奥が不意につんとして、私はきゅっと目を瞑った。
「充希くん……」
きっと充希くんは呆れているに違いない。バイト先の先輩にコクってOKもらえた! って大喜びした日も私は真っ先に彼に報告したけれど、充希くんは今と同じような顔をして私のことを見ていたのだった。
目の縁に溜まったものが零れ落ちないようにもう一度空を見上げる。
鼻は相変わらず痛むし、喉にはさっきからどろりとしたものがつっかえている。息が苦しい。胸には五寸釘、ってそれじゃ私、呪われているみたい。
こうしてみると風邪に似ているな、って思ったらちょっと笑えた。鼻水も出るかもしれない。ティッシュ、持っていたっけ。
不意に視界から星も月も消えて、元々真っ暗だった夜が、もっと真っ暗になった。
頭が充希くんの肩口に押し当てられる。
がっしりした肩と大きくて骨張った手の温もりを感じたら、思ったよりも少しだけしか涙は出なかった。
そうして、大学四年の夏の終わりに私はフリーになった。
後期に入ってからも、充希くんとは変わらなかった。大学で会えば学食を一緒に食べたり、同じ講義には並んで出席したりした。充希くんの彼女は別の大学だから、学食中に彼女と鉢合わせとか、彼女がキャンパス内で待ってる、とかいうことはなかった。
いや、実際はあったのかもしれないけれど、少なくとも私はまったく気づかなかった。そこのところ、充希くんは上手かったのかもしれない。
近所のファミレスで、ドリンクバーをこれ以上ないほど有効利用しながら、集めた資料を読んだり、それを元に卒論を書いたり、愚痴ったり、入社予定の会社の話をしたりもした。充希くんは決まって「腹、壊すぞ」と私のパフェを見て顔をしかめたけれど、私は笑って取り合わなかった。
バイトも辞めなかった。相変わらず先輩とは顔を合わせたし、じくじくと傷むものがなかったわけじゃないけれど、それは覚悟していたよりも小さな傷みだったし、悔しかったから意地でも辞めてなんかやらなかった。
充希くんは「綾音らしいな」って肩をすくめて笑ったけど、細められた目が心臓に悪いということを、私は決して口にしなかった。
もう間もなく翌年度が始まるという日、私は引っ越しの作業要員として充希くんに呼び出された。充希くんは地元に残る私とは違って、春からは誰もが羨む大企業で社会人のスタートを切るのだ。
充希くんの部屋は段ボールが積み上げられていて、でも良くみると中身はまだ空っぽで、私は思わず声を上げて笑った。
「充希くん、全然進んでないじゃん」
「だから綾音を呼んだんだろ、ほら、早く手伝え」
「手伝うったって、無駄に段ボールだけ先に組み立てられたら、作業する場所ないじゃん」
「いや、何かやった気分になるだろ」
「なんないって! もう。もっとさあ考えようよ」
充希くんの部屋は一人暮らしの学生に良くある1Kだった。私は今日はじめてお邪魔したけど、段ボールの山(ただし中身はない)に埋もれているせいで、充希くんの部屋にどれくらいの物があるのか見当もつかなかった。
「綾音に言われたくねー」
「ちょっと何その態度、手伝いに来てやったのに! 大体カノジョちゃんはどうしたの。そっちに来てもらえば良かったんじゃん。それとも別れちゃったとか?」
充希くんはさっさと本を段ボールに詰めていく。私はそれを横目にぶつぶつ言いながら食器を新聞紙に包んでいった。新聞紙は実家から持ってきたものだ。充希くんがそんな殊勝な物を持っているはずがない。
「いいからやれ」
ドスの効いた声が狭い部屋に響いて、私は首をすくめて作業に集中した。
「……別れてねぇよ」
背後で吐き捨てるように呟かれた声に、私は「そっか、良かった」と静かに笑った。
二人で黙々と作業に没頭して、すっかり日が暮れた頃にようやく荷物のほとんどを段ボールに詰め終えた。思ったよりも少なかった。と言っても私は実家暮らしだから、これが一人暮らしの男子学生の荷物の量として普通なのか良くわからない。
「わぁー、綺麗になったねえ」
段ボールの山を部屋の端に寄せて、軽くワイパーをかける。段ボールの他には、部屋にはローテーブルとベッド、パソコンデスク位のものしかなくなった。カーテンもライトもとうに外してしまったけど、窓の外の照明のおかげで部屋内はほの明るかった。
充希くんは一旦実家に帰って、明日またここに寄って引っ越し業者に荷物を引き渡す予定らしい。
「充希くんも今日までかあ」
寂しくなるね、とは言わないでおきたかった。友人って、こんな時あっけないなあなんて、他人事みたいに思った。充希くんは地元じゃなかったから、そんなに郷愁もないかもしれないけど。大学を出てしまえば、ここに帰ってくることなんてないんだろうな。
そう思って、不意に、圧倒的な熱と質量を持ったものが喉元までせり上がった。
「ねー、最後になんか奢ってよ。手伝ってやったんだし!」
せり上がったものを無理やり飲み下す。胸を反らして充希くんを見ると、彼がふっと目を逸らした。
「仕方ねーな、缶コーヒーなら奢ってやる」
「何言ってんの、もう夜だよ!? 夕食どきですよ! どっかいこ!」
「じゃあファミレスな」
充希くんがかすかに笑う。いつかのように胸がひりつく。
けれど同時に私はほっと胸を撫で下ろしてもいた。もちろんそれはコーヒーから食事にランクアップしたからではなくて。
「充希くん、ドリンクバーつけてね」
「おい」
「パフェもだよ」
「腹、苦しくなるんじゃねーの」
「終電までいよ。そしたらたくさん食べられるし。あ、パンケーキも食べたいな」
「……食い意地張りすぎ。太るぞ」
「いいの、充希くんの奢りだし、最後だもん」
それまで呆れた様子で聞いていた充希くんは、その瞬間衝かれたような顔をした。だから私はことさら笑ってみせた。
「……さ、行こ!」
私は充希くんを見上げ、それからすっと視線を外して玄関へ身体を向け──
──ようとした次の瞬間、ぐいと腕を引かれた。
感じたのは柔らかな唇の感触だった。柔らかいのに、荒々しい。こんな男の人は知らない。私はうろたえてたたらを踏んだ。こんなの、充希くんじゃない。
──私たちじゃない。
目を閉じる間もなく、彼のシルエットの向こうに窓から差し込む薄明かりをぼんやりと捉える。でもすぐに腰を引き寄せられて何も見えなくなった。
私は呆然と充希くんのキスを受け止めた。
気が付けば段ボールの山の隙間でフローリングの床に背中を押し付けられていて、私はその衝撃に思わず唇を噛みしめた。
充希くんの細い目が、更に細められて、私を真上からひたりと射すくめる。
彼が白いTシャツの上に羽織ったグレーのパーカーの紐が、視界の中でゆらゆらと揺れていた。
何もかもが、痛かった。
硬い床に押し付けられた背も、揺さぶられる度に段ボールに当たる頭も、充希くんの顔が歪むのも、カーテンさえない夜の部屋で細く上げた声も、互いの荒い吐息さえ。
充希くんの汗ばむ首筋の向こうに、少しだけ開けた窓の網戸からさわりと部屋に吹く風を感じた気がした。
涙が出るかと思ったけれど、今度は一粒も流れなかった。
それが充希くんと過ごした最後の日だった。結局、一緒に夕食を食べに行くことはなかった。
今でも、ときどき思い出す。
会社でパソコンを叩きながら、満員電車に揺られながら、夜道を一人歩きながら、自分の部屋で硬い床に横たわりながら。
充希くんの苦しそうな顔、ぽたりと肌に落ちた汗、浅い呼吸。私の名前を呼ぶ声。
思い出しては何度でも胸を押さえる。
あのとき私は、充希くんが壊したのだと思った。
だけど違う、本当は二人で、壊した。壊して、修復の仕方もわからないまま遠ざけてしまった、二人の間にあったもの。
その破片だけが今も私の胸に刺さったまま、抜けない。
二人の間にあった何か。築き上げた何か、育てた何か、見て見ぬふりをした何か、それでいてお互いの間に確かにあった何かを。
「綾音さー、こんな所でうじうじしてないでさっさとカレシに訊けよ」
「わーかってるってばあ。でもさ、訊いて『そうだよ』とか『別れよう』って言われたらどうしたらいいのよぉー」
「そん時はそん時だろ」
「充希くんってば、他人事《ひとごと》だからってテキトーすぎー」
私は恨みがましい目で、さっきからフライドポテトをひたすら口に入れ続ける充希くんを睨みつけた。ちょっとそれ、私のじゃん。充希くんが要らないっていうからSサイズにしたのに。
その日、私は充希くんを大学近くのファストフード店に呼び出した。充希くんは大学の近くに下宿していて、家庭教師のバイトしかしてないから日曜日は暇なのだ。
日曜の午後の店内は混雑している。子供がハンバーガーセットに付いたおまけのおもちゃを取り出してはしゃぐのを、母親がたしなめている。かと思えば別の席では高校生位の男の子たちが部活の話なんかをしている。私たちみたいな大学生同士の客もいて、適度な喧噪に満ちていた。
充希くんが、はあ、とこれみよがしな溜息をついた。あっという間に空っぽになってしまったポテトの袋に長い指を伸ばして、短いやつが残ってないか確認する。
「休みの日に俺をこんな所に呼び出しておいて、テキトーって何だよ。ちゃんと話聴いてやってんじゃん」
「そうだけどさあ、返事がテキトーだって言ってんの。だって、先輩に直接訊けないから充希くんに訊いてるのにさあ、男の心理ってヤツを。なのに全然参考になんないんだもん」
アイスティーに差したストローを啜ったら、ズズッと嫌な音がした。もう、早く氷溶けないかな。そしたらもうちょっと飲めるのに。そう思いながらガツガツとストローで氷を突いていたら、充希くんが呆れたように笑った。
「その先輩の心理なんてわかんねーよ。俺、二股なんか掛けた事ねーし」
充希くんが、袋から出てきた小指の先ほどのカリカリのポテトを摘まみ上げた。
「そうだね。充希くんはそんなことしなさそう」
私はへへ、と眉を下げて笑うと、充希くんが口に入れようとした最後のポテトを横からかっさらう。
私が飲食店のバイトを終えた帰りに充希くんに電話をした時、外には悔しいくらい綺麗な月が昇っていた。
「もしもし、充希くん?」
「……何だよ、綾音か。こんな時間にどうした」
「充希くん、あのさぁ、先輩に振られちゃった……」
「あー、とうとう」
「とうとう、って何よぉ。先輩、私の他にも彼女いたんだよ。やっぱりあの日に見ちゃったのは彼女だったんだー。問い詰めたらあっさり白状してさ」
「……」
「どういうことなの、って訊いたら、『知らなかったの?』だよ? ねえ、信じられる?」
「……」
「『綾音ちゃんはわかってて付き合ってるんだと思ってた』だって。そんなわけないっての!」
充希くんはずっとだんまりを決め込む。だからか余計に、私の方はヒートアップする一方だ。
「先輩があんな人だったなんて! 優しい人だと思ってたのに」
「……」
「ねぇ、ちょっと、充希くん聴いてる?」
「……綾音の言う『優しい』って何だよ」
不意に電話越しに届いた声音の低さに私は驚いて肩を揺らした。思わずスマホをぎゅっと握り直す。これまで聞いたことのない冷たさだった。
「どうせ、休みの日は遊園地とか映画とかオシャレなカフェに連れて行ってくれて、可愛い可愛いって言ってくれて、バイトで失敗しても庇ってくれる、とかそんなんだろ」
充希くんの声は珍しく怒気を含んでいた。私はすぐに言い返したけど、初めて聴く声音に怯んで少しだけ弱々しくなってしまった。
「そうだよ、先輩はいっつもそうしてくれたんだもん。何よ、充希くんはそんなことしたことないんでしょ」
「ほっとけよ。大体な、こんな夜遅くに掛けてくんなよ。デリカシーないのかよ。綾音は、カノジョ持ちが休みの日の夜に何してるのか考えつかねーのかよ」
「あ……そうだね」
ここに至って私はようやくそのことに思い至って、頬が赤くなった。充希くんはいつも私の話を聞いてくれるから、ついそのことを忘れそうになる。でも彼には歳下の彼女がいるのだった。
「ごめん、切るね。カノジョちゃんにも謝っておいてね!」
電話を掛けた時の勢いはいつの間にか無くなっていたけれど、私は見えない相手に向かって笑みを作る。
じゃあまた大学で、とその笑顔のまま続けようとしたのに、ぽつりと零れた声に遮られた。
「……どこにいんの、今」
「ん? 駅のホーム、の端っこ。星が沢山見えるんだー」
「最寄り?」
「うん。この時間だとね、車両の編成数が減るから、ホームの端っこの方は電車が止まらないんだ」
「待ってろ」
「うん? なあにー、来てくれるの? ちゃんと帰れるって。ダメだよ、夜はこれからなんだから。カノジョを追い返したら、頭をはたいてやるんだから」
「とにかくそこで待ってろ」
「はいはーい、うん、もうすぐしたら帰るよー」
屋根の途切れたホームの端で、私は空を見上げる。充希くんの声は耳を素通りして、たださっきの鋭さが消えたことにほっとして笑い声を上げた。
どうしたってまだここから立ち上がれそうにない。だから充希くんが来ても来なくてもどっちだって良かった。
だから充希くんがホームに現れた時、私はちょっとぽかんとしてしまった。充希くんは息を荒くして、憮然とした顔を崩しもせずに私を見下ろす。悪いことをしたのは私じゃないのに、今にも怒られそうな気がする。けれど怖いと思うよりも驚きの方が大きくて、私はベンチに座ったまま、彼をまじまじと見てしまう。本当に来たの? なんて失礼なことを思いもした。
「綾音」
「あれー、充希くん、もしかしてカノジョを本当に追い返してきちゃったの? ダメじゃん。よし、そこに座って。はたいてやるー」
だけど私はそんなことはせずに、へらりと笑って再び星空を見上げた。
あれは何座かな。
充希くんがため息をついて隣に腰掛けた。色落ちしたジーンズに包まれた長い脚がホームに投げ出される。
「あー、充希くんも星が見たくなった? 綺麗だよねえ。あれ、何座かなあ。夏はさ、はっきり形がわかるものが少ないと思わない? 星座なんて中学の授業以来だもん、わかんないね」
「綾音」
「あれとさあ、あれと……繋げたらハートになると思わない? 充希くん。ハートだよ」
私はデタラメにいくつかの星を選ぶと、指先で空にハートを描いてみせた。我ながら二十歳も過ぎて子供じみた発想だ。それに大体、ガラでもない。
だけど、回らない頭では何だかそんなことしか思いつかなかった。
「先輩とは、ハートにならなかったなあ……どうやっても繋がらなかったよ」
「綾音」
鼻の奥が不意につんとして、私はきゅっと目を瞑った。
「充希くん……」
きっと充希くんは呆れているに違いない。バイト先の先輩にコクってOKもらえた! って大喜びした日も私は真っ先に彼に報告したけれど、充希くんは今と同じような顔をして私のことを見ていたのだった。
目の縁に溜まったものが零れ落ちないようにもう一度空を見上げる。
鼻は相変わらず痛むし、喉にはさっきからどろりとしたものがつっかえている。息が苦しい。胸には五寸釘、ってそれじゃ私、呪われているみたい。
こうしてみると風邪に似ているな、って思ったらちょっと笑えた。鼻水も出るかもしれない。ティッシュ、持っていたっけ。
不意に視界から星も月も消えて、元々真っ暗だった夜が、もっと真っ暗になった。
頭が充希くんの肩口に押し当てられる。
がっしりした肩と大きくて骨張った手の温もりを感じたら、思ったよりも少しだけしか涙は出なかった。
そうして、大学四年の夏の終わりに私はフリーになった。
後期に入ってからも、充希くんとは変わらなかった。大学で会えば学食を一緒に食べたり、同じ講義には並んで出席したりした。充希くんの彼女は別の大学だから、学食中に彼女と鉢合わせとか、彼女がキャンパス内で待ってる、とかいうことはなかった。
いや、実際はあったのかもしれないけれど、少なくとも私はまったく気づかなかった。そこのところ、充希くんは上手かったのかもしれない。
近所のファミレスで、ドリンクバーをこれ以上ないほど有効利用しながら、集めた資料を読んだり、それを元に卒論を書いたり、愚痴ったり、入社予定の会社の話をしたりもした。充希くんは決まって「腹、壊すぞ」と私のパフェを見て顔をしかめたけれど、私は笑って取り合わなかった。
バイトも辞めなかった。相変わらず先輩とは顔を合わせたし、じくじくと傷むものがなかったわけじゃないけれど、それは覚悟していたよりも小さな傷みだったし、悔しかったから意地でも辞めてなんかやらなかった。
充希くんは「綾音らしいな」って肩をすくめて笑ったけど、細められた目が心臓に悪いということを、私は決して口にしなかった。
もう間もなく翌年度が始まるという日、私は引っ越しの作業要員として充希くんに呼び出された。充希くんは地元に残る私とは違って、春からは誰もが羨む大企業で社会人のスタートを切るのだ。
充希くんの部屋は段ボールが積み上げられていて、でも良くみると中身はまだ空っぽで、私は思わず声を上げて笑った。
「充希くん、全然進んでないじゃん」
「だから綾音を呼んだんだろ、ほら、早く手伝え」
「手伝うったって、無駄に段ボールだけ先に組み立てられたら、作業する場所ないじゃん」
「いや、何かやった気分になるだろ」
「なんないって! もう。もっとさあ考えようよ」
充希くんの部屋は一人暮らしの学生に良くある1Kだった。私は今日はじめてお邪魔したけど、段ボールの山(ただし中身はない)に埋もれているせいで、充希くんの部屋にどれくらいの物があるのか見当もつかなかった。
「綾音に言われたくねー」
「ちょっと何その態度、手伝いに来てやったのに! 大体カノジョちゃんはどうしたの。そっちに来てもらえば良かったんじゃん。それとも別れちゃったとか?」
充希くんはさっさと本を段ボールに詰めていく。私はそれを横目にぶつぶつ言いながら食器を新聞紙に包んでいった。新聞紙は実家から持ってきたものだ。充希くんがそんな殊勝な物を持っているはずがない。
「いいからやれ」
ドスの効いた声が狭い部屋に響いて、私は首をすくめて作業に集中した。
「……別れてねぇよ」
背後で吐き捨てるように呟かれた声に、私は「そっか、良かった」と静かに笑った。
二人で黙々と作業に没頭して、すっかり日が暮れた頃にようやく荷物のほとんどを段ボールに詰め終えた。思ったよりも少なかった。と言っても私は実家暮らしだから、これが一人暮らしの男子学生の荷物の量として普通なのか良くわからない。
「わぁー、綺麗になったねえ」
段ボールの山を部屋の端に寄せて、軽くワイパーをかける。段ボールの他には、部屋にはローテーブルとベッド、パソコンデスク位のものしかなくなった。カーテンもライトもとうに外してしまったけど、窓の外の照明のおかげで部屋内はほの明るかった。
充希くんは一旦実家に帰って、明日またここに寄って引っ越し業者に荷物を引き渡す予定らしい。
「充希くんも今日までかあ」
寂しくなるね、とは言わないでおきたかった。友人って、こんな時あっけないなあなんて、他人事みたいに思った。充希くんは地元じゃなかったから、そんなに郷愁もないかもしれないけど。大学を出てしまえば、ここに帰ってくることなんてないんだろうな。
そう思って、不意に、圧倒的な熱と質量を持ったものが喉元までせり上がった。
「ねー、最後になんか奢ってよ。手伝ってやったんだし!」
せり上がったものを無理やり飲み下す。胸を反らして充希くんを見ると、彼がふっと目を逸らした。
「仕方ねーな、缶コーヒーなら奢ってやる」
「何言ってんの、もう夜だよ!? 夕食どきですよ! どっかいこ!」
「じゃあファミレスな」
充希くんがかすかに笑う。いつかのように胸がひりつく。
けれど同時に私はほっと胸を撫で下ろしてもいた。もちろんそれはコーヒーから食事にランクアップしたからではなくて。
「充希くん、ドリンクバーつけてね」
「おい」
「パフェもだよ」
「腹、苦しくなるんじゃねーの」
「終電までいよ。そしたらたくさん食べられるし。あ、パンケーキも食べたいな」
「……食い意地張りすぎ。太るぞ」
「いいの、充希くんの奢りだし、最後だもん」
それまで呆れた様子で聞いていた充希くんは、その瞬間衝かれたような顔をした。だから私はことさら笑ってみせた。
「……さ、行こ!」
私は充希くんを見上げ、それからすっと視線を外して玄関へ身体を向け──
──ようとした次の瞬間、ぐいと腕を引かれた。
感じたのは柔らかな唇の感触だった。柔らかいのに、荒々しい。こんな男の人は知らない。私はうろたえてたたらを踏んだ。こんなの、充希くんじゃない。
──私たちじゃない。
目を閉じる間もなく、彼のシルエットの向こうに窓から差し込む薄明かりをぼんやりと捉える。でもすぐに腰を引き寄せられて何も見えなくなった。
私は呆然と充希くんのキスを受け止めた。
気が付けば段ボールの山の隙間でフローリングの床に背中を押し付けられていて、私はその衝撃に思わず唇を噛みしめた。
充希くんの細い目が、更に細められて、私を真上からひたりと射すくめる。
彼が白いTシャツの上に羽織ったグレーのパーカーの紐が、視界の中でゆらゆらと揺れていた。
何もかもが、痛かった。
硬い床に押し付けられた背も、揺さぶられる度に段ボールに当たる頭も、充希くんの顔が歪むのも、カーテンさえない夜の部屋で細く上げた声も、互いの荒い吐息さえ。
充希くんの汗ばむ首筋の向こうに、少しだけ開けた窓の網戸からさわりと部屋に吹く風を感じた気がした。
涙が出るかと思ったけれど、今度は一粒も流れなかった。
それが充希くんと過ごした最後の日だった。結局、一緒に夕食を食べに行くことはなかった。
今でも、ときどき思い出す。
会社でパソコンを叩きながら、満員電車に揺られながら、夜道を一人歩きながら、自分の部屋で硬い床に横たわりながら。
充希くんの苦しそうな顔、ぽたりと肌に落ちた汗、浅い呼吸。私の名前を呼ぶ声。
思い出しては何度でも胸を押さえる。
あのとき私は、充希くんが壊したのだと思った。
だけど違う、本当は二人で、壊した。壊して、修復の仕方もわからないまま遠ざけてしまった、二人の間にあったもの。
その破片だけが今も私の胸に刺さったまま、抜けない。