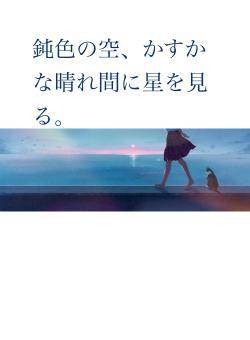そして、日曜日がやってきた。
約束の時間になって、僕は紫之宮神社へ向かった。
すっかり青々とした葉に彩られた参道を進み、桜の木がある能舞台へ向かうと、そこには白いワンピースの女の子の姿。
さらに、足元には小さな黒い影。千鳥さんと黒猫だ。
青葉となったみずみずしい桜の木の下で、黒猫とじゃれ合う彼女は、相変わらず浮世離れした美しさを放っている。制服でないから余計そう思うのだろうか。それとも、ほかになにか理由があるのだろうか。
僕は足を止めて、絵画のようなその光景に魅入った。
風が彼女の髪やワンピースの裾をさらうたび、光がこぼれるように白い肌がちらつく。
柔らかな光に包まれたその横顔に見惚れていると、おもむろに桜が振り向いた。目が合う。
「あっ、汐風くんみーつけたっ!」
千鳥さんは僕に気付くと、嬉しそうに僕を指さした。その瞬間、心臓が大きく脈を打った。
桜の木が揺れ、木の葉が音を立てる。一瞬、なにかが脳裏を掠めたような気がして、動きを止める。
なんだ、今の。なんか、覚えがあるような……。
「おーい、汐風くん?」
ぼんやりしていると、桜がもう一度声をかけてくる。我に返った。
「あ、うん。今行く」
形の見えない違和感のようなものが気になりつつも、僕はそれを頭の隅に追いやって、一歩先の砂利を踏んだ。
「今日はネコ太郎もいますよー」
僕が行くのが待ちきれなかったのか、桜の木の下にしゃがみ込んでいた彼女が、黒猫の前足を握って僕に手を振る仕草をする。可愛い。
……というかちょっと待って。
「ネコ太郎って……いつのまにコイツ、そんな名前がついたんだ?」
「今付けた!」
弾ける笑顔で彼女が答える。
「……え、じゃあせめてネコはとってあげたら?」
言われなくてもこいつ、猫だし。
「えっ! なんで? ネコ太郎可愛いじゃん。ねぇ? ネコ太郎?」
桜は黒猫――もといネコ太郎に問いかける。ネコ太郎はにゃあと鳴いた。
「いや……猫にネコって。というかその子、メスじゃない?」
「えっ!? うそ!?」
その驚愕した顔が面白くて、僕は耐えきれずに噴き出した。
「ふふっ……うそ。知らない」
「えー! なんだよー!」
桜が笑う。彼女が笑うと、まるで周囲の光が弾けるようだと思う。不思議なひとだ。いつ見ても。
「まぁいいや。それより今日、晴れてよかったね」
「ねっ! 晴天! 嬉しい!」
無邪気な笑顔を向ける彼女につられて、僕も微笑む。
「じゃあ、行く?」
「うん!」
僕たちはネコ太郎をひと撫ですると、神社を出て駅方面へと向かった。
今日はこれからJR宇都宮線を使って、宇都宮駅へ向かう。そして、市内の映画館でデート予定の涼太と志崎さんの様子を見守るといったものだ。
「……で、ふたりの援助って具体的になにするの?」
「うん! それはまぁこれから話すけど。……あ、でもその前にちょっと喉乾いたから、カフェ入ろうよ。行ってみたいところがあるんだ。駅前のお店なんだけどね、大正時代に銀行だった建物をそのまま使ってるんだって!」
話題を逸らされてしまった気がするが、まぁ彼女が楽しそうだからいいか、と僕はそれ以上追求することなく、彼女を追いかけた。
カフェは、駅の通りから一本入った路地裏に立っていた。大きな石造りの二階建ての建物で、店内はカウンター席とテーブル席が数席用意されている。天井が高く、照明も明る過ぎず、落ち着いた雰囲気のカフェだ。
かつて銀行だったときの名残りか、壁には大きな時計があるが、時は刻まれていない。壊れているようだった。
僕たちはこのカフェで早お昼を食べることにして、オムライスをふたつと、シフォンケーキをひとつ頼んだ。
料理を待ちながら、千鳥さんはどこか落ち着かないようで、そわそわしていた。
「どうかしたの?」と訊ねると、千鳥さんは「あ、うん」と、どこか不自然に頬を掻く。しばらく様子をうかがっていると、千鳥さんは僕の視線に観念したように話し出した。
「あのさ……実はね、今日……涼太くんと彩ちゃんのデートを見守るっていう話で呼び出したんだけど……あれ、うそなんだ」
「は!? うそ!?」
僕が驚きの声を上げると、千鳥さんは慌てて弁明を始めた。
「いや! うそって言っても、ふたりは本当にデートしてるんだよ!? ただ……今日呼び出したのは、そのためじゃなくて……汐風くんとふたりで話がしたくて」
「話?」
「その……私の名前のこと」
千鳥さんは、うかがうような上目遣いで僕を見る。
「それって……」
ごくりと息を呑む。
ずっと気になっていたことだ。
彼女が学校で名乗っている『千鳥夢』という名前と、僕に名乗った『千鳥桜』という名前。それについて、僕はずっと聞きたくても聞けずにいた。
「汐風くんには、ちゃんと話しておきたいなと思って」
千鳥さんは小さな声で呟く。
「私……名前がふたつあるんだ」
千鳥さんの告白は、こういうものだった。
千鳥さんの戸籍上の名前は『千鳥夢』だという。しかし、その名前とはべつに、もうひとつ付けられた名前があるらしい。
それが、『桜』だった。
その名前は最愛の姉が付けてくれたものだと、彼女がかつてそう言っていたことを思い出す。
しかし、公的機関である学校では、戸籍上の名前を使わざるを得ないため、このような混乱する事態になってしまったのだとか。
「説明が遅くなってごめんなさい。……混乱したよね」
「……いや。でも、それならそうと、もっと早く言ってくれたらよかったのに」
千鳥さんの肩がわずかに上がる。手を握り込んで、力が入ったのだろう。見て分かった。
「うん……そうだよね。私もそう思う。あのときちゃんと説明できれば良かったんだけど……学校のみんなは私のことを千鳥夢だと思ってるし、名前がふたつあるなんてふつうじゃないから……その、こんなこと話したら、みんなにどう思われるかなって……ちょっと、怖くて」
「あ……」
その言葉で、彼女にとってこの告白がどれだけ勇気がいることだったのか察した。
最悪だ。また、不用意な発言をしてしまった。
「……いや、ごめん。君が悩んでることも知らずに」
「ううん。汐風くんが謝ることじゃないから」
「……あのさ、ひとつだけ聞いてもいい?」
「なに?」
彼女の話を聞いても、僕のなかではまだ解けない疑問がひとつだけあった。
「千鳥さんは、どうして僕に『桜』のほうを名乗ったの?」
僕に対しても、みんなと同じように『千鳥夢』だと名乗っていれば、こんなことにはならなかった。彼女が僕にわざわざ『桜』と名乗った理由が、なにかあるのだろう。
「それは……」
千鳥さんは目を泳がせ、口を閉ざした。話したくないことだったかもしれない。もしくは、話せないか。
「あ……ごめん。無理には聞く気はないから」
慌てて言うと、彼女はようやく顔を上げた。その眼差しは、思いのほかしっかりとしていた。
「……ううん、話す。話せるところまでは、汐風くんに聞いてほしいから」
彼女はそう、はっきりと口にする。僕は姿勢を正して、彼女の言葉を待った。
「私が君に『桜』だって名乗ったのは、私は、じぶんのことを『桜』だと思ってるから」
「……それは、夢って名前がきらいってこと?」
訊ねると、彼女は首を横に振る。
「ううん。きらいじゃないよ。大好き……。だけど……だけど、ずっと夢でいるのは、苦しいんだ」
「苦しい……?」
僕は眉を寄せる。
「夢って名乗るのも、夢って呼ばれるのも、苦しい……」
千鳥さんは言葉を詰まらせながら、途切れ途切れに言った。
肩が震えている。今にも泣き出してしまいそうな彼女の姿に、僕も胸が痛んだ。
どういうことなのだろう?
眼差しで訴えると、彼女はそれ以上の追求を拒むように目を伏せた。
「……ごめん。これ以上は、話しちゃいけないって言われてるから言えない」
「…………」
それ以降、口を閉ざしてしまった彼女に、僕はどうしたらいいのか分からなくなる。
これ以上詳しく聞くことはできない。だけど、これだけでは彼女がなにを抱えているのか分からない。
ほかになにか、彼女にしてあげられることはないだろうか。
彼女は勇気を出して、僕にこの秘密を打ち明けてくれたのだ。その気持ちに応えたい。
顔を上げて千鳥さんを見ると、彼女は心もとなげな顔をしていた。
その顔を見て、気付いた。
……違う。気持ちに応えたいとか、そういうことじゃない。気の利いた言葉なんて、彼女は求めていない。
彼女が求めているのは、あのとき……僕が凪と向き合ったあのとき、凪に言われて救われたあの言葉だ。
「……ありがとう」
「え?」
千鳥さんが僕を見る。驚いた顔をしていた。
「なんで、汐風くんがお礼を言うの?」
「……えっと、うまく言えないけど、これが今、君の話を聞いた素直な感想。なんていうかさ、嬉しかったんだ……君が僕にこの話をしたいと思ってくれたこと自体が」
正直な想いを伝えると、千鳥さんは顔を歪ませた。
「僕も同じだったから。親友に電話したとき、怖かった。でもね、勇気を出して話したら、ありがとうって言われたんだ」
お前、だれ? って言われるかと思った。僕のことなんて、凪のなかではもう存在しない人間になっているかもと。
だけど、それは僕の勝手な思い込み。
凪は僕のことをちゃんと覚えていてくれた。後悔してくれていた。
この胸を抉った傷は、消えない。傷痕となって、この先もきっと、一生消えることはないだろう。
だけどもう、疼くことはないのだ。僕はそう、確信している。
「千鳥さん。お願いがあるんだ」
「お願い……?」
僕は頷く。
「ふたりのときだけでいいから、君のことを……桜って呼びたい」
「え……」
千鳥さんは大きな瞳をさらに大きくして、僕を見つめる。
「君の名前を呼びたい」
そう、まっすぐに告げると、彼女は目尻に溜まっていた涙を拭って、嬉しそうにはにかんだ。
「うんっ……私も、汐風くんには呼んでほしい。私の名前」
まるで花が咲いたような笑顔だった。
ようやくいつもどおりの彼女の笑顔が戻ってきて、僕は安堵する。やっぱり、彼女には笑顔がいちばん似合う。
話に区切りがついたところで、タイミング良く料理が運ばれてきた。
「うわぁっ!! 美味しそう!」
ソースたっぷりのオムライスを前に、桜はやっぱり瞳をきらきらさせて喜んでいた。
僕は、ただのオムライスを大袈裟に喜んで食べる彼女を飽きもせず眺めていた。
「……それで、今日の予定だけど」
オムライスを食べながら、僕は彼女に問いかける。
「このあとどうする?」
千鳥さんが弾かれたように顔を上げる。
「えっ、このあとも付き合ってくれるの?」
「まぁ……ここまできたんだしね。どうせだから付き合うよ」
「じゃあ私、海が見てみたい!」
「え、海?」
「うんっ」
突飛な提案に、僕は思わず目を丸くする。
「う、海か……。だけど海はさすがに、今からだと厳しくないかな」
「そうなの?」
「桜、今日もお昼には戻らないといけないんだよね?」
「うん」
それだとやはり無理だ。
ここは栃木県。海はない。近隣の海だと茨城県だが、電車ではかなり時間がかかってしまう。
そう説明すると、桜は途端にしょぼくれてしまった。あんなに嬉しそうに食べていたオムライスを、今度はしょぼくれたままもそもそと食べ始める彼女に苦笑しつつ、僕はスマホを開く。
「……あのさ、今日は無理だけど、またべつの日に行こうよ。たとえば、一日外出を許可されたときとか」
そう提案すると、彼女の手が止まった。
「一日外出なら行ける!?」
「うん。行ける」
「分かった! 約束だよ。ぜったい行こうね! うそついたら針千本だからね!?」
と、桜が小指を差し出してくる。
僕も笑いながら、その小さな小指にじぶんの小指を絡めた。
「うん、約束」
それから、僕たちはしばらくカフェでのんびりしたあと、街中のショップをいくつか見て回ってから、紫之宮神社へ戻った。
相変わらず桜の木の周辺に生息する黒猫とじゃれ合いつつ、そろそろ彼女を病院へ送らなければいけない時間だろうかとスマホを見たとき、メッセージが一件届いていることに気付いた。
「あれ、涼太からだ」
「えっ、なになに。なんだって?」
呟くと、それまで黒猫を撫でていた桜が立ち上がり、僕のいる能舞台へとやってくる。
「私にも見せてー」
桜は無遠慮に僕の手のなかを覗き込んでくる。その拍子に、彼女の二の腕が直に僕の腕に触れた。
「っ!」
僕のすぐ真下に、千鳥さんの小さな頭部がある。不意に、千鳥さんが僕を見上げた。彼女の蒼ざめた瞳と目が合った瞬間、心臓が今までにないほど大きな音を立てる。
「汐風くん、どうしたの?」
「えっ……あ、う、ううん。なんでもない」
僕は慌てて顔を逸らし、涼太からのメッセージを開いた。
内容は、今日晴れて志崎さんと付き合うことになったというおめでたい報告だった。
「えー! すごい! 彩ちゃん、告白したんだ!」
メッセージを見るなり、桜が興奮気味に歓声を上げる。
「君のところにも志崎さんからメッセージきてるんじゃない?」
何気なく訊くと、彼女は苦笑いをして言った。
「あー……私、スマホ持ってないから」
「あ、そっか。ごめん……」
「ううん、べつに」
彼女の反応に、特別気にした素振りはない。
「……ねぇ、スマホがないって、不便じゃない?」
「うーん……そうでもないかなぁ。病院では、あっても使えないしね。スマホ自体そもそも持ってたことないから、ない生活が当たり前だけど」
「そっか」
「まぁでも、興味はあるけどね。ゲームとかできるんでしょ? あと、好きなひととメッセージ交換とか話したりもできるから、スマホは恋する乙女には必須のアイテムだって彩ちゃんが言ってた」
「ふふっ……」
思わず小さく噴き出す。
「えっ、なんで笑うの?」
桜は不思議そうに首を傾げる。
「いや、なんか意外で。志崎さんって大人しいイメージだったから。そんなこと言うんだね」
「うんっ、彩ちゃん、結構面白いんだよ」
志崎さんは、僕の前ではあまり口数は多くない。
クラスが違うということもあって、桜を通して知り合うまで、僕は彼女の存在すら知らなかった。
「ふたりは、仲が良いんだね」
「うんっ!」
ふたりのときは、桜も志崎さんもお互い僕や涼太の知らない一面も見せているのかもしれない。
親友というやつなのだろう。僕にとっての凪のような。
「彩ちゃんといると、すごく楽しいんだ。なんとなく、お姉ちゃんといたときを思い出すの」と、桜は少しだけ寂しげに空を見上げた。
「……いた?」
いる、ではなく、いた。そう、桜は言った。意味深な言い回しに、僕は違和感を覚える。訊ねてから彼女の顔を見て、意図を察する。しまったと思った。
「……お姉ちゃん、もう死んじゃったんだ」
やっぱり。また、地雷を踏んでしまった。
「……そう、だったんだ。辛いね」
桜は頷いて、それから空を見上げた。
「うん、辛い。……でもね、寂しくはないよ。きっとお姉ちゃんは、すぐに新しい命として生まれてくる。それが人間の赤ちゃんか、仔猫か、お花かは分からないけど……お姉ちゃん、私のことが大好きだったから、きっとすぐ近くに生まれてくる気がしてる!」
「……そっか」
「それにね! 今は君がいるから」
「……え」
空を見上げていた桜が、ふっと僕を見る。
「今は、君といるときがただただ楽しいんだよ」
心臓が、また大きく跳ねた。今日はなにかと忙しい僕の心臓だ。
「……え、なに、いきなり」
「君と出会ってからね、私の人生、すごく目まぐるしいんだ。学校に行ったり、友だちと笑いあって、お弁当交換をして……こんなふうに休みの日に遊びに行くなんてさ、なんか、私の人生じゃないみたいだよ!」
大袈裟だよ、と言いたくなるけれど、彼女の顔を見てやめた。
これは彼女の心からの言葉なのだ。
彼女の当たり前の世界は、僕の当たり前とは違う。逆もまた然りだ。
「私今、すごく生きてるって感じがする!」
「……そっか」
無邪気な笑顔につられるように、僕も笑みを浮かべる。
「君はどう? 汐風くん」
まっすぐな瞳で問いかけられ、考える。答えは考えるまでもなかった。
「……うん。僕もそう。僕も、君のおかげですごく……すごく、生きてるって感じがする」
本心を言うと、彼女は嬉しそうにはにかみながら、言った。
「私といっしょだね!」
彼女がどうして名前をふたつも持っているのか、彼女がどんな病と向き合っているのか。
彼女について、僕は知らないことばかりだ。
だけど、今はただ、この時間がずっと続けばいいと思った。
***
桜と出かけた翌週の金曜日。
朝、僕はいつもより少しだけ早く登校すると、一組の教室に入る前に二組の教室を覗いた。
今日こそはと期待して覗いたものの、教室に思い描いていた人物の姿はない。
代わりに志崎さんの姿を見つけて、小さく手を振った。志崎さんは鋭く僕の意図に気付いてくれたようで、残念そうな顔をして首を横に振った。
諦めて一組の教室に入り、鞄を机に置く。鞄のチャックを開けると、内ポケットに入った小さな包みがちらりと見えて、僕はひとつため息をついた。
「おはよ、汐風」
不意に、頭の上から声が降ってきて顔を上げる。
「あ、涼太。おはよう」
「なぁ、千鳥さんって、今日も休みなの?」
と、涼太は自席につくなり僕のほうを見て、訊ねてくる。
「あぁ、うん。そうみたい」
「そっかぁ。結局、今週は一度も来なかったな」
「うん……」
桜は、いっしょに出かけたあの週末以降、一度も学校に来ていないのだ。
最後に会った日から、もう一週間が経とうとしている。
無断欠席というわけではなく、病欠という連絡がきているらしいが、なにぶん彼女はスマホを持っていない。連絡がつかないため、彼女の体調を確認することもできない。
僕はため息混じりに机のなかにしまっておいた文庫本を取り出し、栞が挟んであるページを開いた。
「あれ、今こんな展開だったっけ……」
つい数週間前までは、あんなに続きが気になっていた本なのに、今ではどこまで読んだか栞を挟んでいたにもかかわらず首を傾げてしまう。
近頃、読書をする時間がめっきり減った。
朝のホームルームまでの時間は涼太と話をして過ごし、昼休みは涼太や桜、それから桜の友だちである志崎さんと過ごすのが、すっかり当たり前になりつつあるからだ。
入学当初は、このクラスのだれとも仲良くなる気なんてなかった。
だれも信用できなかったし、友だちがほしいなんてカケラも思っていなかった。というか、僕にそういった人間関係を築くことは無理だと諦めていた。
それが、いつの間にかこんなことになっているのだから、人生とは分からないものだ。
何気なく手に持っていた栞を見つめる。
栞には、桜の花びらがラミネート加工されている。手作り感満載の古い栞だ。
この栞は、蝶々さんが作ってくれたオリジナルの栞だ。昔、少しだけ蝶々さんの家に住んでいたことがあった。そのときに、蝶々さんが作ってくれたのだ。
ほかに栞を持っていなかったので、なんとなくそのまま使っているだけだったが、この栞を見るたび僕はなぜだか桜を思い出すようになった。
この栞が彼女と関係があるかと言えば、ない。共通点があるとすれば、それは彼女と同じ名前の花が使われているということ。
ただ、それだけ。
だけど、そんな些細な繋がりすら嬉しく思えた。
そういえば、この栞はまだ桜に見せたことがない。見せてあげたら、大袈裟に目を輝かせて喜びそうだ。私も作る、などと言い出すかもしれない。
彼女が登校しなくなって、まだたった一週間。だけど、今日も会えないのだと思うと、途端に目に映る景色が色褪せてしまったように見える。
つくづくじぶんらしくない、と思う。なのだけど、今のじぶんをそれほどいやだと思わないのは、なんでだろう。
「なぁ汐風、ちょっといいか? ……って、なににやけてんの?」
栞を眺めたまま、結局読書をせずに考えごとをしていると、涼太が僕の視界を遮った。
「……にやけてないし。つーかなに、課題は見せないよ」
若干苛つきを露わにしつつ返事をすると、涼太は口を尖らせて言った。
「分かってるよ! そんなことじゃないって」
涼太は僕から文庫本をぶん取ると、興奮気味に言った。
「俺、昨日思い出したんだよ!」
僕は涼太から、取られた本を取り返そうと手を伸ばす。
しかし、涼太は僕に本を返そうとしない。相当話を聞いてほしいらしい。
「思い出したって、なにを」
手を伸ばしたまま、仕方なく聞き返す。
「ほら、前にさ、小学生のときに同じクラスだった千鳥さんの話しただろ?」
「あぁ……そういえばそんな話もしたな」
たしか、彼女が転校してきた初日くらいにした話だ。
「あれ、やっぱり夢ちゃんだったんだよ!」
手が、止まった。
「あの頃、夢ちゃんなかなか学校来られてなかったんだよ。だから記憶が曖昧だったんだけどさ、思い出してみたら、完全に面影が彼女だったんだよな」
「なにそれ……つまり、小学校が千鳥さんと同じだったってこと?」
「そ! 今思えば、夢ちゃんが転校してきたときから、なーんか違和感があったんだよな。なんかどっかで会ったことあるような気がするなって! それで見て、この写真」
確認しようと思って、久しぶりに昨日押入れから引っ張り出してきたんだよ、と、涼太がスマホ画面を見せてくる。
画面には、小学校の卒業アルバムが映っていた。写真はクラス全体の集合写真で、三十人近く映っている。そのなかのひとりを中心に、涼太が画面を拡大していく。涼太の指先によって、ゆっくりと外野が切り取られていく。それに呼応するように、僕の心臓はどくどくと早まっていく。
「次に夢ちゃんと会ったら聞こうと思ってたんだけど、なかなか来ないからさぁ……」
想定外の話に、言葉が出てこない。
拡大された画像には、カメラに向かって笑顔でピースをする桜の姿。
正真正銘、千鳥桜だった。