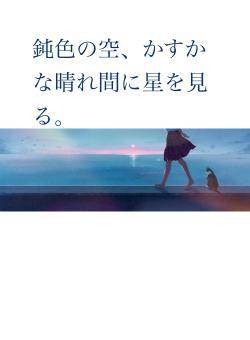――三月中旬。
春一番が吹いたその日、僕は、叔母の家がある栃木県の田舎町にやってきていた。
『春はパステル色』なんて、よく分からないポスターのキャッチコピーを横目に、僕は切符回収箱に切符を放り込む。
時代に取り残されてしまったような無人駅の改札を過ぎ、外へ出た途端、まだ冷たい風が吹き付けてきて、僕は思わず目を細めた。
叔母である蝶々さんの家は、たしか駅前の通りをまっすぐ行った商店街の途中にあったはずだ。
駅に着いたら迎えに行くから電話をしてと言われたけれど、蝶々さんの家にはこれまで何度も来たことがある。
おそらく歩いているうちに道を思い出すだろう。
そう思いながら、蝶々さんにメッセージを打つ。
『駅に着いた。歩いていけそうだから迎えは大丈夫』
スマホをポケットにしまい、ごろごろとキャリーケースを引きながら歩き出す。
駅を出ると、正面には二股の分かれ道。
たしか、どちらの道も最終的には商店街に繋がっていたはず。僕は適当に右手側の道を進んだ。
ずっと昔から時が止まっているように思える商店街。
いったいだれが買うんだろうと思うような古い洋服店や居酒屋、花屋、文具屋、昭和レトロな喫茶店を横目に、僕は淡々と歩く。
通りの少し先には、これから僕が通う高校の門構えが見えた。
この春から僕は、この街にある私立高校、さくらの森高校へと進学する。
さくらの森高校を選んだ理由は特にないが、強いて言えば、家から適度に遠く、通うのが困難だったから。
ただ、親には本当のことは言えないので、校風に惹かれたからとうそをついた。
ネットには、比較的生徒の個性を尊重する自由な校風と、制服が可愛いところが特徴だと書かれている。
校風はありがちだし、制服だって可愛いとは言っても、ネットで見た限り男子はふつうの学ランだし、女子もいたってふつうのセーラー服にしか見えない。僕には。
でも、そんなことはどうだっていい。
僕はただ、あの街を出られたらそれでよかったのだから。
道を歩いていると、少し先の道路の真ん中に、黒い物体が見えた。
「……?」
なんだろう、と目を凝らす。
すると突然、黒い物体に大きな金色の目玉が見えた。ぱちぱち、と瞬きをするそれを見て、なんだ、と息をつく。
「猫か」
見たところ、まだ仔猫のようだ。黒猫は道路のどまんなかで、呑気に耳のうしろを脚でかいていた。脇に避ける気はなさそうだ。車の通りが少ないとはいえ、道路のまんなかにいるというのに。
少しひやひやして、
「おーい、そこ、道路だから危ないぞ」
と声をかけてみると、黒猫はぴたりと動きを止めた。
おもむろにこちらに向かって、
「にゃあ」
と鳴く。
そしてまた、のんびりと毛繕いを始める。
猫語で「うるせえ」とでも言われた気分になった。
「……なんだよ」
いけ好かないお猫さまだな。
ほっとこう、と思い直し、再び歩き出す。しばらく商店街を進んでいると、てんてんてん、と目の前をなにかが横切っていく。
見ると、やはりあの黒猫だ。
「……あ、お前」
歩きかたがうさぎのようで、思わず笑みが漏れる。
「なんだよ、お前。着いてきたのか?」
もう一度話しかけてみると、黒猫はちらりと僕を見てから、再びてんてんと歩き出す。
――なんだ、今の意味深な視線は。
黒猫は、意志を持ってどこかへ向かっているように見えた。
――着いてこい、的な?
なんとなく気になって、ついて行ってみることにした。
黒猫は迷わず道を進み、途中、通りを曲がって、狭い横道を進んでいく。そのまま黒猫を追いかけていると、次第に汗ばんできた。上着を脱ぎ、小脇に抱えて再び黒猫を追う。
ふと、顔を上げると、道の先に小さな神社が見えた。
大きな朱色の鳥居には、『紫之宮神社』とある。
「シノミヤ神社……?」
きれいな名前だな、と思いながらそろりと敷地の中に足を踏み入れた。
苔むした石に落ちる木漏れ日、松の枝でさえずる小鳥、香しい芳香の花々。
鳥居を抜けた先にあったのは、現実離れした美しい世界だった。
無意識のうちに、ため息が出ていた。
右手には、能舞台。その脇には、大きな一本の桜の木がある。上から覆うように枝が広がり、薄紅色の桜が舞台を彩っている。
「――桜……」
ふと、ぼんやりとした既視感を覚えて、呟く。
口を開けたまま満開の桜に魅入っていると、「にゃあ」という声が聞こえた。
「……あ、お前」
見ると、黒猫は我が物顔で舞台に上がっていた。ころころと背中を舞台の床に擦り付けている。
「自由だな、お前」
苦笑混じりに言ったときだった。ふと、視界の端になにか動くものを見た気がして、舞台の縁に目をやる。
風に舞った桜の花びらが数枚、空へ抜ける。
息を呑んだ。
桜の木の下に少女がいた。
神様がもし、春をひとの姿にしたとしたら、きっと彼女のような容姿をしているのだろう。そんなことを思ってしまうほど、桜の下に佇む少女は美しい。
少女は、清楚な白いワンピースをまとっていた。ドレープ感のあるスカートが、風を含んでふわりとふくらむ。
春休みだし、きっと観光客だろう。目の前のそれはなにも特別な光景ではないはずなのに、僕は彼女から目が離せなくなる。
ふと視線を感じたのか、彼女が振り返る。次の瞬間、視線が交錯した。
彼女がなにかを発しようと、口を開く。
「あっ……」
それを認識した瞬間、僕は反射的に、彼女から目を逸らした。目を逸らしてから、しまった、と思う。さすがにあからさまに顔を背けてしまった。変に思われたに違いない。
気まずさから、僕はその場を去ろうと回れ右をする。
「ねぇ、君」
風が葉を鳴らす音が耳を抜けていく。声をかけられている。そう気付いたものの、僕は気付かないふりをして足を進める。
「ねぇねぇ」
大方、写真を撮って、か、道を教えて、か、そんなことだろう。だから逃げる。僕は映えるカメラテクニックなんて知らないし、道を教えられるほどこの土地に詳しくもない。僕は、そういう世界にいたことのない人間だ。それらについて訊ねるならば、僕では不適切だ。
「ねぇってば」
それに、相手は女の子だ。どう話せばいいのかなんて、分かるはずもない。
「君だよ、君!」
「…………」
さすがに無視できず、足を止めて振り返る。見ると、白いワンピースの少女が、僕のほうへ駆けてきていた。
「えっと……僕?」
そりゃそうだろう、とでもいうように、少女は頷く代わりの瞬きをする。
近くで見ると、さらに美しさが際立っていた。
くっきり二重の瞳を縁取るまつ毛は長く、瞬きのたびぱちぱちと音が聞こえてくるようだった。白目は青白く澄んでいて、唇は果実のように赤くみずみずしい。
その果実のような唇が、言葉を紡ぐ。
「ねぇ、君。ひとり? こんなところでなにしてるの?」
「えっと……」
一昔前のナンパを受けたような気分だ。
「……ね、猫を追いかけてて」
咄嗟に、さっき見かけた猫を理由にした。実際あの黒猫を追いかけてここへ来たのだから、うそではない。
「猫?」
首を傾げる少女に、僕はちらりと彼女の後方の舞台を見る。
僕の視線を辿るように少女が顔を向ける。そして、舞台の上に転がる黒猫を見た。
「わっ! ほんとだ、猫だっ! 可愛い〜!!」
少女は弾けた声を上げて、黒猫の元へ駆けていった。勢いよく迫ってくる少女に黒猫は一瞬身構えたものの、悪意はないことを悟ったのか、すぐに警戒を解いて毛繕いを始めた。
少女は黒猫の前まで行き、その頭へ手を伸ばそうとして、怯えたように手を引っこめた。
どうしたのだろう。動物が苦手なのだろうか。まるで、生き物に触れたことのない子どものような反応だ、と思った。
なんとなく観察していると、少女が再び僕を見た。
「え」
僕は反射的に身構えた。いやな予感がする。
「ねぇ君、この子、抱っこすることできる?」
「え?」
「私、猫見るの初めてなの! 触りたいけど、その……ちょっと怖いっていうか……」
「猫が初めて?」
そんなひといるのか。この歳で?
驚いていると、少女は懇願するように顔の前で手を合わせた。
「ねぇ、お願い! 君、この子を抱っこしてみせてよ」
「僕が!?」
「うん! 一度でいいから、猫ちゃんのこと触ってみたいの。お願いお願い!」
僕だってべつに、猫が得意ってわけじゃない。飼っていたこともないし、正しい抱きかたも知らない。だが、ここまで言われてできないというのもなんだか癪だ。
「……仕方ないな」
仕方なく少女と黒猫の元へ向かう。
思いのほか黒猫は大人しく、僕がすぐ目の前まで来ても逃げる様子はない。
うしろ側からそっと脇に手を入れ、恐る恐る抱き上げてみると、黒猫はぴんと前足を伸ばして、前ならえの姿勢になった。
無事抱っこできたことにほっとしつつ、僕は黒猫を少女に差し出す。黒猫は前ならえの体勢のまま、少女をじっと見つめていた。
「はい、どうぞ」
「わぁあ、可愛い! 待って、そのままね、そのまま……」
ちょん、と少女が指の先で黒猫の眉間を撫でた。黒猫は一瞬怖がるように目を瞑ったが、すぐにごろごろと喉を鳴らし始めた。
「きゃあ〜!! 可愛い!」
少女の甲高い声に、黒猫の耳がうしろ側へと折れる。少女の声に驚いたのだろう。覗いてみると、さっきまで閉じていた瞳孔は少し開いていた。
「あんまり高い声出したら猫が驚くから、静かにしてあげて」
「あっ、そっか。分かった!」
少女は僕の指摘を素直に受け入れ、静かに黒猫を可愛がり始める。だが、少女が黒猫を受け取る気配はない。
どうやら、彼女は黒猫を触りたいだけで受け取る気はないようだ。このまま前ならえをさせておくのも可哀想なので、僕は仔猫の抱きかたを赤ちゃんを抱くようなかたちに変える。
「へぇ〜猫ってすごいふわふわなんだねぇ。耳のうしろとかすごいさらさらしてるー」
本気で感動している様子の彼女に、僕は思わず訊ねた。
「……本当に猫見るの初めてなんだ?」
「うん、初めて」
彼女は黒猫へ視線を落とし、ふにゃっとした顔のまま僕の問いに答えた。
「野良猫とかを見かけたこととかもないの?」
「野良猫……うーん、テレビでしかないかなぁ。あ、でもライオンとかゾウならナマで見たことあるよ! 動物園に連れて行ってもらったことはあるから!」
「動物園?」
「うん。でも猫は動物園にはいないじゃん?」
そりゃいないだろう、と心のなかでツッコミを入れる。
「いたっていいのにねぇ」
と、少女は真顔で言う。
「……いや、まぁ……」
たしかに、動物園に猫はいない。だって、いたところで猫なんてなんの真新しさもないし、わざわざお金を払って猫を見に来る客もいないだろう。
……と思うけれど、改めて考えるとたしかに不思議な気もする。
猫も動物だ。動物園にいても、べつに変じゃない。猫好きも多いし、巷には猫カフェだってあるくらいなのだから。
だけど。
「……そんなこと、疑問に思ったこともなかった」
呟くと、彼女はころころと笑った。
「そっかぁ」
「…………」
柔らかな雰囲気の彼女を見つめながら、なんというか、不思議な気分になる。
「あ、ねぇ、君、名前なんて言うの?」
パッと彼女が顔を上げ、僕を見た。至近距離で目が合い、心臓が跳ねる。
「えっ、僕?」
「うん。私はね、千鳥桜。桜って呼んでよ。君の名前は?」
「……僕は、錦野」
とりあえず苗字だけ答えると、彼女――千鳥さんは、なにかを待つように微笑んだ。彼女の意図に気付いていないわけではないけれど、それでも僕が黙りこくっていると、じわじわと千鳥さんの眉間に皺が寄っていく。
「え、もしかして下の名前は教えてくれないの? あ、もしかして、ニシキノって名前? ニシ、キノくん?」
「……いや、違うけど……」
「じゃあ下の名前、教えてよ!」
まっすぐな眼差しで見つめられ、ため息をつく。
「……汐風」
「しお……かぜ? ……君、汐風って名前なの?」
驚いた顔をして振り返る千鳥さんに、少し暗い気分になった。
いつか言われた言葉が蘇る。
『しおかぜって変な名前だよな』
奥歯に力が入った。
「……そうだよ。変な名前だろ」
「…………」
黙り込む少女のとなりで、僕は小さくため息を漏らす。
……だから言いたくなかったんだ。『汐風』なんて、変な名前だから。
『生ぐせー名前だよな!』
『ぴったりじゃん!』
昔、クラスメイトにからかわれたいやな記憶が飛び出して、胸の辺りがざわめいた。
無意識のうちに、手に力がこもっていたらしい。それまで僕の腕のなかで大人しくしていた黒猫が、ぴょんっと僕の手をすり抜けて逃げていく。
どうやら僕は、猫にまできらわれる体質らしい。まぁいいけど。
「……それじゃあ、僕はこれで」
猫にならって、逃げるように彼女に背を向ける……が。
「あ、ちょっと待ってよ!」
逃げる僕を引き止めるように服の袖を指先で掴まれ、足を止める。
振り返り、小さく「なに?」と答える。少しぶっきらぼうな言いかたになった。
僕の反応に、彼女は少しだけ戸惑うそぶりを見せてから、言った。
「いや、あのさ……もったいぶるからどんな名前かと思ったけど、汐風ってすごくきれいな名前じゃん」
「……え」
思っていた反応と違うものが返ってきて、僕は思わず足を止めた。
「君がなにを気にしてるのか知らないけど、汐風って、すごくいい名前だと思う。名前を付けてくれたひとの思いがすごく伝わってくる感じがする」
驚いた。
そんなことを言われるのは初めてだ。いつも、変だとバカにされてきたのに。
「……そう、かな」
「うん! そうだよ!」
屈託のない笑顔に、僕もうっかりつられそうになるが、かろうじて、
「べつに、そんなことないでしょ」
と返す。
なんだか落ち着かない。
「ねぇ、私、君のこと名前で呼びたい! 汐風くんって呼んでもいい?」
唐突過ぎて、反応ができなかった。
「ダメ?」
呆気にとられていると、彼女はずいっと顔を寄せて、もう一度確かめてくる。至近距離で目が合って、僕は思わず目を逸らした。
「……まぁ、好きにして」
「やった!」
喜ぶ彼女を、僕は不思議な気分で眺める。どうしてそんなに喜んでいるのか、分からない。
だって僕たちは、知り合いでもなんでもない。もう二度と会うこともないだろうし、名前を呼ばれることなんてまずないだろう。
……だけど、もし彼女と僕に次があるのなら。
彼女になら名前を呼ばれてもいいかもしれない、と思った。彼女の声は、なんだか耳に馴染むのだ。例えるならそう、海辺の町に響く波音とか、暑い夏の日に涼をくれる風鈴のように。
「さて! それじゃ私はそろそろ帰ろっかな! またね、汐風くん!」
彼女は笑顔で手を振り、神社を出ていく。
そのうしろ姿を見送りながら、僕は小さく苦笑する。
「……変なひと」
ぽつりと呟いたとき、ポケットの中のスマホが振動した。画面を見ると、蝶々さんだった。
「あっ」
そういえば、駅に着いたと報告してからしばらく経つ。心配して、電話をかけてきてくれたのだろう。
僕は慌てて神社をあとにした。