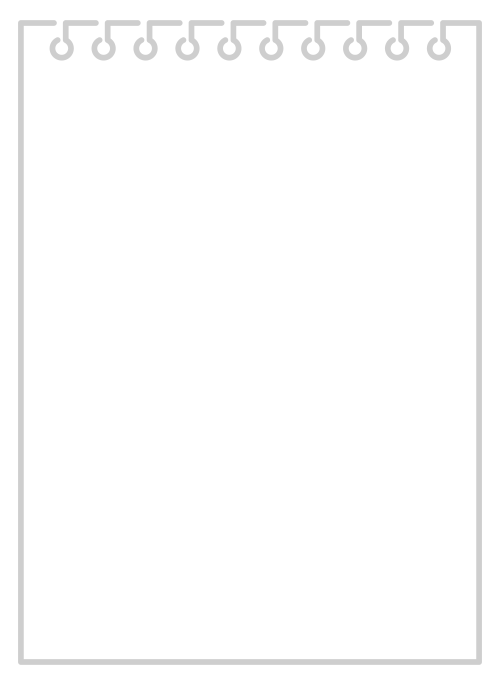こんな風に誰かと体温を近づけて、心を寄り添わせたのはいつぶりだろう。
「詩音さん。好きだったと伝えるのは、もう遅いですか? 恋人や好きな人がいたり、しますか?」
「……いない、です」
「今からでも、間に合いますか?」
「どうかな……」
私は彼が好きだろうか?
ぼんやりと自問する。
好意が嬉しい。ピアノの才能が素晴らしいと思う。努力を尊敬する。
格好いいと思う。好ましいと思う。
惹かれずにいられないオーラとか、フェロモンみたいなのがある。好きか嫌いかで言うと好き寄りの好きだ。好き好き好きだ。もう、寄りとかじゃなくて好きだ。ああ、酔っている。
「私が、ダメなんだと思う」
「詩音さんはダメじゃないです」
「そう言って欲しくて言っちゃった。欲しがっちゃいました」
「……じゃあ、もっと欲しがってください」
お互いの指と指を絡めるように手を繋がれると、ひとりぼっちの自分が嘘みたいに思えた。
飛べない私を抱きかかえて、攫って飛んでいってくれそうで。
身を委ねたいという想いと、そんな想いへの反発が同時に湧く。
――赤ちゃんみたい。私はバブちゃんですか。
上の部屋に向かうエレベーターは狭い長方形のようで、酩酊した私の脳は自分が誰かに贈られるプレゼントになったように錯覚した。
私が生きて何かをする時に、それを喜ぶ誰かがいる。
つまり、それが大事なことなんじゃないだろうか。私は、そう思っていた。
左右に道が分かれている時、誰かが「右に行ったら悲しい。左に行ってほしい」と言う。だから左に行く。
――でもそれって、『私の人生』と言えるんだろうか。
「詩音さん。好きだったと伝えるのは、もう遅いですか? 恋人や好きな人がいたり、しますか?」
「……いない、です」
「今からでも、間に合いますか?」
「どうかな……」
私は彼が好きだろうか?
ぼんやりと自問する。
好意が嬉しい。ピアノの才能が素晴らしいと思う。努力を尊敬する。
格好いいと思う。好ましいと思う。
惹かれずにいられないオーラとか、フェロモンみたいなのがある。好きか嫌いかで言うと好き寄りの好きだ。好き好き好きだ。もう、寄りとかじゃなくて好きだ。ああ、酔っている。
「私が、ダメなんだと思う」
「詩音さんはダメじゃないです」
「そう言って欲しくて言っちゃった。欲しがっちゃいました」
「……じゃあ、もっと欲しがってください」
お互いの指と指を絡めるように手を繋がれると、ひとりぼっちの自分が嘘みたいに思えた。
飛べない私を抱きかかえて、攫って飛んでいってくれそうで。
身を委ねたいという想いと、そんな想いへの反発が同時に湧く。
――赤ちゃんみたい。私はバブちゃんですか。
上の部屋に向かうエレベーターは狭い長方形のようで、酩酊した私の脳は自分が誰かに贈られるプレゼントになったように錯覚した。
私が生きて何かをする時に、それを喜ぶ誰かがいる。
つまり、それが大事なことなんじゃないだろうか。私は、そう思っていた。
左右に道が分かれている時、誰かが「右に行ったら悲しい。左に行ってほしい」と言う。だから左に行く。
――でもそれって、『私の人生』と言えるんだろうか。