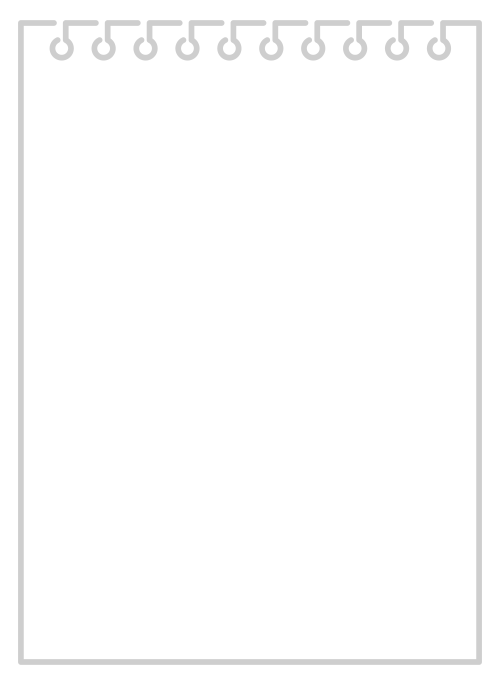こうして弾いていると、ピアノを弾いている自分が当たり前に思える。
けれど、弾かないでいた期間を振り返ると、その期間はピアノを弾かない自分が当たり前に思っていた。
――現実の地に足を付けていたくない。
それは、「いい子ね」と言われて出しそびれてしまった、私の本音だ。
この手を力いっぱい伸ばして、夢を掴もうとしてみたかった。
この足を限界まで動かして、どこまで歩けるか挑戦してみたかった。
目の前にいる彼と切磋琢磨して、悔しがったり励まし合ったりしたかった。
――そんな色褪せた切望の欠片を胸の奥に見つけた私は、後悔の色で欠片が塗りたくられる前に見て見ぬふりをした。
「ピアノは、楽しいですね。大河さん。ありがとう」
「なぜお礼を?」
「ふふっ、……どうしてでしょう」
この感情を思い出してしまって、明日からどうしよう。
苦い理性をカクテルで押し流して、私は現実から目を背けた。
「詩音さん」
「はい」
「ピアノ、久しぶりなんですね」
「12年ぶり、かな」
連弾して、飲んで。
夢中で音を紡いで曲に酔いしれて、どちらからともなく顔を寄せて。
小鳥が挨拶を交わすように、唇を合わせた。
啄むようにキスを繰り返す彼の髪に指を埋めると、彼が色っぽい吐息を零して、大人な感じがした。
極上の触り心地をした髪を撫でると、彼が夢を見せてくれる。
「詩音さん。明日出発ですけど、僕と一緒に海外、行きます?」
「明日は会社です」
「明日じゃなくてもいいです」
「母が入院してるんです」
現実を振り切りたい。私は首を振って「この話は嫌」と子供みたいに駄々をこねた。
足首に何かが絡まっている気がして、靴を脱いでしまいたくなる。
でも、私は25年間、お行儀のいい子の模範みたいなのが根っこに染みついてしまっている。
地に足が付いていないと錯覚することはできても、地面から足を離しきれていない。
――だから、何もかも違う別種の生き物みたいになっちゃった。
「私、ピアノが好きでした。ふふっ、あなたのおかげで、思い出せました。今夜は、夢みたい」
この夢が覚めなければいいのに。
でも、覚めてしまう。そんな感覚が、強い。
お金を貯めて、ピアノを買おうかな。
無職になりそうだけど……物価もあがるし、病気の母を支えないといけないし。
ああ、現実を忘れようとしても、気づいたら現実ばかり見てしまう。
忘れてしまいたい。もっと逃避したい。
溺れなきゃ。
浸らなきゃ。この目の前の快楽に。
私に夢を見せて。楽しくさせて。助けて。助けて。助けてよ。
音の波を両手で立てて心を溺れさせようと没頭していると、後ろから柔らかに抱擁される。
「詩音さん――ピアノに飢えていたみたいに、そんな風に夢中で……なんか、ぐっと来る……」
「ぐっと?」
「むらむらする」
熱に浮かされるように手を握られて甘噛みするように指先にキスされると、くらりと眩暈がした。
「大河さんのストレートな言い方は、海外仕込み?」
「影響は受けているかもしれません」
彼にあてられたように、身体の芯がポッと火が燈ったみたいに、熱くなる。
「……上に部屋を取ってるから、行きませんか?」
色香が溢れる声で誘われて、胸がどきんと音を立てた。
逡巡は、一秒に満たなかった。
「私、経験浅いですよ」
「僕も初めて……いえ」
「ん?」
「気にしないでください」
けれど、弾かないでいた期間を振り返ると、その期間はピアノを弾かない自分が当たり前に思っていた。
――現実の地に足を付けていたくない。
それは、「いい子ね」と言われて出しそびれてしまった、私の本音だ。
この手を力いっぱい伸ばして、夢を掴もうとしてみたかった。
この足を限界まで動かして、どこまで歩けるか挑戦してみたかった。
目の前にいる彼と切磋琢磨して、悔しがったり励まし合ったりしたかった。
――そんな色褪せた切望の欠片を胸の奥に見つけた私は、後悔の色で欠片が塗りたくられる前に見て見ぬふりをした。
「ピアノは、楽しいですね。大河さん。ありがとう」
「なぜお礼を?」
「ふふっ、……どうしてでしょう」
この感情を思い出してしまって、明日からどうしよう。
苦い理性をカクテルで押し流して、私は現実から目を背けた。
「詩音さん」
「はい」
「ピアノ、久しぶりなんですね」
「12年ぶり、かな」
連弾して、飲んで。
夢中で音を紡いで曲に酔いしれて、どちらからともなく顔を寄せて。
小鳥が挨拶を交わすように、唇を合わせた。
啄むようにキスを繰り返す彼の髪に指を埋めると、彼が色っぽい吐息を零して、大人な感じがした。
極上の触り心地をした髪を撫でると、彼が夢を見せてくれる。
「詩音さん。明日出発ですけど、僕と一緒に海外、行きます?」
「明日は会社です」
「明日じゃなくてもいいです」
「母が入院してるんです」
現実を振り切りたい。私は首を振って「この話は嫌」と子供みたいに駄々をこねた。
足首に何かが絡まっている気がして、靴を脱いでしまいたくなる。
でも、私は25年間、お行儀のいい子の模範みたいなのが根っこに染みついてしまっている。
地に足が付いていないと錯覚することはできても、地面から足を離しきれていない。
――だから、何もかも違う別種の生き物みたいになっちゃった。
「私、ピアノが好きでした。ふふっ、あなたのおかげで、思い出せました。今夜は、夢みたい」
この夢が覚めなければいいのに。
でも、覚めてしまう。そんな感覚が、強い。
お金を貯めて、ピアノを買おうかな。
無職になりそうだけど……物価もあがるし、病気の母を支えないといけないし。
ああ、現実を忘れようとしても、気づいたら現実ばかり見てしまう。
忘れてしまいたい。もっと逃避したい。
溺れなきゃ。
浸らなきゃ。この目の前の快楽に。
私に夢を見せて。楽しくさせて。助けて。助けて。助けてよ。
音の波を両手で立てて心を溺れさせようと没頭していると、後ろから柔らかに抱擁される。
「詩音さん――ピアノに飢えていたみたいに、そんな風に夢中で……なんか、ぐっと来る……」
「ぐっと?」
「むらむらする」
熱に浮かされるように手を握られて甘噛みするように指先にキスされると、くらりと眩暈がした。
「大河さんのストレートな言い方は、海外仕込み?」
「影響は受けているかもしれません」
彼にあてられたように、身体の芯がポッと火が燈ったみたいに、熱くなる。
「……上に部屋を取ってるから、行きませんか?」
色香が溢れる声で誘われて、胸がどきんと音を立てた。
逡巡は、一秒に満たなかった。
「私、経験浅いですよ」
「僕も初めて……いえ」
「ん?」
「気にしないでください」