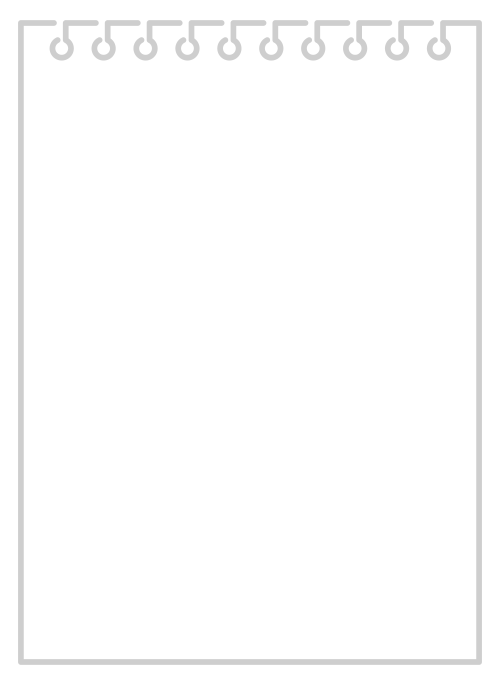日常から一歩踏み出して、非日常の中にいる。
車で10分程度の距離にあるホテルは、高瀬川と歌舞伎の修練場が近くにある。
赤いモニュメントに目を奪われながら中に入ると、レストランにスタインリッヒのアップライトピアノがあった。
「詩音さん。ここ、2時間貸切りました。夕食もお礼にどうぞ――ピアノも」
「そんなによくしてもらっていいんですか? 申し訳なくなります」
「僕、詩音さんが好きなんです」
「好きって……海外のノリですね?」
「ラブの方ですよ」
「軽いですね? 大河さんはイケメンなので、そういうことを言われると女子は勘違いする人続出だと思います」
鱧のフリットライムクリームチーズに、オレンジの酸味が豚の甘みを引き立てる豚バラ肉のソテー。白い花で飾られた爽やかなパスタ――夕食は見た目がおしゃれで、味もおいしい。
デザートで出されたクラゲ型グラス入りの綿菓子はエルダーフラワーやレモンシロップでマリネしたメロン果実、レモンゼリーを凍らせて削ったシェイブアイスで飾られていて、可愛い。
瓶入りのラムネ水を注ぐと、パチパチキャンディーを仕込んだ綿菓子がパチパチと音をはじけさせて、ほどけていく。
「軽くないです。冗談じゃないんですよ。僕、こういうの経験があまりなくて……ムードとかわからなくて、困ったな」
「今、もしかして口説いてました?」
「口説いてたんですよ」
「遊び人なんですね、大河さん」
「いや、遊びじゃないんです……でも、そう思われちゃいますよね」
大河さんは困り顔をして、カクテルを勧めてくれた。
何種類かのメニューから選んだミモザは甘い果汁感が爽やかで、シャンパンのキリッと引き締まった酸味が癖になる。
体温が上がっていって大胆になれる感じがして、私はピアノの前で鍵盤を愛でた。
「弾いても構いませんか? 私、弾きたいんです」
私の指は自然と動く。
ブランクがあっても、体は動いてくれる。快感だ。
『詩音ちゃん。ピアノにはまりすぎないで』
1位を取った私に、母親が言った声が蘇る。
『音楽の世界は大変よ。普通が一番。無難でいいの。才能があるって言われて、勘違いしたらダメ。現実の地に足をつけて、皆と同じ人生を歩きましょう。パパの真似なんか、もうしないで。ママ、ピアノは嫌い』
あの日、母親は、私を祝ってくれなかった。代わりに、震える手で私を抱きしめて言ったのだった。
『ママとパパ、離婚するの……』
「そうだ。遊びじゃないってわかってもらえるように、説明してみてもいいですか? ピアノをお楽しみいただきながらでいいですから」
現実の大河さんの声がする。
「……どうぞ……?」
ありがとうございます、と折り目正しくお礼を言って、彼が話し出す。
確かに、遊び人という気配ではない。
「僕の家は音楽一家で、僕は才能がないって言われて育ったんです。兄がとても優秀で、比べられていて、僕はずっと褒められたことがありませんでした」
可愛らしい仔犬のワルツを奏でながら、思い出す。
捨てられた仔犬みたいだった1歳年下の大河さんは、自信がなさそうで、鍵盤を叩く力が弱かった。
でも、機械みたいに正確に楽譜通りに音を追いかけていた。
ミスがなくて、すごいと思った。たくさん練習したんだと思った。
「詩音さん。ピアノ教室で、詩音さんがピアノ上手だね、いっぱい練習してるんだねって声をかけてくれたでしょう。初めて努力を他人に認めてもらえて、嬉しかったんです」
「私じゃないですけど」
「どうして他人のふり、するんです?」
彼が後ろに立って、私の手に自分の手を重ねた。
背中と手が熱い。心臓の鼓動が落ち着かなくなる。
よく覚えている。最初は、捨て犬が懐いてきたみたいだった。
それが、可愛い弟のようになった。そして、ライバルになって。
『僕が1位になったら、キスしてもいい?』
大阪大会の順番待ちをしている時に、真剣に手を握って問われて、意識した。
私はその時、彼が自分のことが好きだと気付いて、興奮した。異性に想いを寄せられるのは初めてだった。
その日、私が奏でたのはピアノ協奏曲第2番 第2楽章。
ショパンが初恋相手を思って書いたアダージョで、私は曲を奏でながら、「初恋とはこんな感じなのかな」と想ったのだった。
感情が乗りに乗った一曲は、絶賛された。
あの時の拍手は、快感だった。天才だと言われて、将来が楽しみだと称えられて、酔いしれた。
「詩音さんは覚えてますか。僕、あの時……」
「ううん。それ、私じゃない。別人です」
将来を期待された私は、あの一曲を最後にいなくなった。
私はママの実家にお引越しをした。
ピアノのない家だった。そこからは、ママの求める『普通』の人生を歩んだ。
ピアノに触れるのが罪みたいに思いこんで、全く近寄ることがなかった。
もう、過去なんだ。彼が好きだった詩音はどこにもいない。
ここにいるのは、明日にも会社から切られそうな、しがない会社員でしかない。
「大河さんの知ってる詩音という子は、私じゃないです。他人です」
「なんでそんなことを言うんですか。急にいなくなって、それきりで……心配してました。ピアノを続けてたら、いつかコンクールで会えるかと思ったんですけど……」
「大河さん。ごめんなさい」
自分の声が、他人みたいに聞こえる。
「大河さん。私、そういうお話よりも、楽しく過ごしたい。今夜という時間は限られてるのだもの」
……刻一刻、時間が過ぎていく。
日常に戻るのが、怖い。
この時間が貴重で、大切で、終わってほしくない。
「大河さん。ピアノを弾いても?」
「ええ、どうぞ」
「一緒に弾きましょうか?」
「……いいんですか? 詩音さんと弾けて嬉しいです」
花が咲くように微笑まれて、胸がきゅんとする。