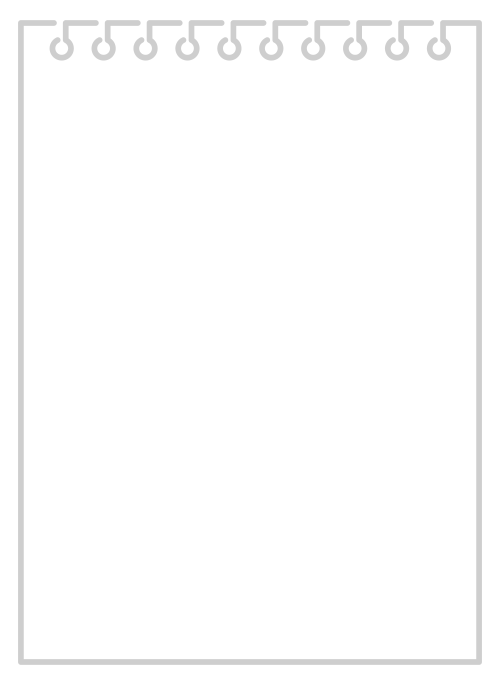コンクールの出番待ちの時みたいに緊張しながら、スマホの時刻を見る。
6月18日、18時30分。
通知欄には『未来からの手紙』という流行りのアプリの通知がある。
「変な通知を送ってくるのが面白い」と同僚が勧めてきたアプリだ。
『未来からの手紙』は、「詩音さんへ。世の中はチャンスの奪い合いです。他人に譲ってはいけません」と知らせていた。
メッセージに首をかしげた私に、男性が声をかけてくる。
「すみません。並んでますか? この駅ピアノでのストリートピアノの動画撮りたくて――明日には海外に行くから、ラストチャンスなんです。弾くの無理かな……」
「あ――いえ。どうぞ」
声の主に視線を向けた私は、目を疑った。
相手は、美男子だ。オーバーサイズの黒ジャケットとパンツの装いが似合っている。
私は、彼を知っている。たぶん彼は私のことがわからないだろうけど、中学卒業まで同じピアノ教室で、コンクールにも一緒に出たことがあった。
名前は、火乃朗 大河さん。24歳。
12歳で全日本学生音楽コンクール大阪大会2位になったのを皮切りに、音楽事務所ピアノオーディションなどで優勝。
ハンガリー国立リスト音楽院ピアノ科に留学。
留学中に、マスタープレイヤーズ大賞国際コンクール、マリア・カナルス国際コンクール、ヴィオッティ国際コンクール、カントゥ国際ピアノコンチェルトコンクールなどで上位に入り、聴衆賞も受賞している。
――天才ピアニストだ。
通行人も彼に気付いて、ざわざわしている。
「火乃朗 大河だ」
「本物? これから弾くの?」
「演奏楽しみにしてます。では……」
離れようとした私の腕を彼が掴んで、名前を呼ぶ。
「詩音さん?」
「え……」
どきりとする。大河さんは、私を覚えていたようだった。
「ピアノ教室で一緒でしたよね? 大阪大会で1位になった鏑木詩音さん……違う?」
「……人違いです」
咄嗟に嘘をついたのは、成功して有名になった彼と自分の現状に、あまりにも差があると感じたから。
「人違い……? 失礼しました」
「いえ。演奏がんばってください」
「あ、待って……一緒に弾きませんか?」
「はっ……?」
挨拶して去ろうとすると、彼は私をピアノの前に引っ張って行った。
そして、大きな黒袖から覗く白い指先で鍵盤を叩いた。連弾の誘いだ。
ポーン、と低く響く音は、浮ついた私の心を引っ掴まえて、静かで美しい物語世界の入り口を見せてくれた。
たった1音で心を掴んでしまう、鮮やかで奥深い音だった。
曲は、組曲マ・メール・ロワ、第1曲、眠れる森の美女のパヴァーヌ。
連弾相手の返事を待つように、出だしのメロディが奏でられる。
――弾く……?
私が続きを奏でないと、進まない。
静寂を恐れて音を紡げば、指は動いた。
――弾ける。
ワクワクした。
――私、弾ける。指が動く。覚えてる……!
宝石の粒を溶かして固めたような、きらめく音が耳をくすぐる。
現実がどこかに吹き飛ばされて、彼の音楽が鮮やかに優しく私を包み込む。
自分の音が彼の音と一緒に響き合うのが、奇跡のよう。
心地よい音楽に体が自然と揺れて、数日前にカットしたばかりの栗色の髪が頬にかかる。
指が滑らかに鍵盤の上で踊るのが、嬉しくて仕方ない。
雨だれのように音が連なって、世俗に縮こまって乾いていた心が潤っていく。
すぐ隣にいる彼の息づかいに――ドキドキする。
――ワァッ……、
曲を終えると歓声と拍手が湧いた。
まだ夢から覚めたくないと思った。
でも、気づけばもう19時。駅ピアノの演奏可能時間は、終わりだ。
「ばっちり撮れましたよ、大河さん」
カメラを持っている人が、大河さんに話しかけてくる。マネージャーさんだろうか。
大河さんは大人っぽく品のある微笑みを湛えて、私に頭を下げた。
「突然の申し出を引き受けてくださって、ありがとうございました。楽しい連弾でした。後日、配信サイトに動画を載せてもよろしいですか?」
「あ……は、はい」
お礼に食事にも誘ってくれる。いい人だ。
それに、耳元で「食事場所にピアノがありますよ」と囁いてくる。
私がまだ日常に戻りたくないのを理解されているみたいだ。
「いらっしゃいませんか?」
誘われた声は、柔らかで耳に心地いい。
ずっと話していたくなる。
高級車に促されるまま乗り込むと、覆いかぶさるようにしてシートベルトを留めてくれる。距離が近くて、少し緊張した。
「詩音さん、でいいんですよね? 見えてしまってるのですが、これ、なんですか?」
「え?」
大河さんは、私のスマホに目を瞬かせた。また通知が来ていた。
『詩音さんへ。仕事が終わったら、明日の仕事に備えて早く寝ましょう』
「彼氏ですか?」
「ああ、大河さん。これ、アプリなんですよ。人間じゃないんです」
「へえ……このアプリ、面白いんですか?」
画面を覗き込む大河さんの顔が、吐息が感じられるほど近い。
バイレードのブランシュに似た、透明感ある香りがする。
「面白くないかも、しれませんね」
「あっ。近かったですね、すみません」
視線を逸らしてスマホを胸に伏せると、彼はハッとした顔で距離を取った。
照れている彼を見ていると、私も恥ずかしくなってくる。耳が熱い。
車が動き出すと、低めの車高ならではの振動が心地よかった。
6月18日、18時30分。
通知欄には『未来からの手紙』という流行りのアプリの通知がある。
「変な通知を送ってくるのが面白い」と同僚が勧めてきたアプリだ。
『未来からの手紙』は、「詩音さんへ。世の中はチャンスの奪い合いです。他人に譲ってはいけません」と知らせていた。
メッセージに首をかしげた私に、男性が声をかけてくる。
「すみません。並んでますか? この駅ピアノでのストリートピアノの動画撮りたくて――明日には海外に行くから、ラストチャンスなんです。弾くの無理かな……」
「あ――いえ。どうぞ」
声の主に視線を向けた私は、目を疑った。
相手は、美男子だ。オーバーサイズの黒ジャケットとパンツの装いが似合っている。
私は、彼を知っている。たぶん彼は私のことがわからないだろうけど、中学卒業まで同じピアノ教室で、コンクールにも一緒に出たことがあった。
名前は、火乃朗 大河さん。24歳。
12歳で全日本学生音楽コンクール大阪大会2位になったのを皮切りに、音楽事務所ピアノオーディションなどで優勝。
ハンガリー国立リスト音楽院ピアノ科に留学。
留学中に、マスタープレイヤーズ大賞国際コンクール、マリア・カナルス国際コンクール、ヴィオッティ国際コンクール、カントゥ国際ピアノコンチェルトコンクールなどで上位に入り、聴衆賞も受賞している。
――天才ピアニストだ。
通行人も彼に気付いて、ざわざわしている。
「火乃朗 大河だ」
「本物? これから弾くの?」
「演奏楽しみにしてます。では……」
離れようとした私の腕を彼が掴んで、名前を呼ぶ。
「詩音さん?」
「え……」
どきりとする。大河さんは、私を覚えていたようだった。
「ピアノ教室で一緒でしたよね? 大阪大会で1位になった鏑木詩音さん……違う?」
「……人違いです」
咄嗟に嘘をついたのは、成功して有名になった彼と自分の現状に、あまりにも差があると感じたから。
「人違い……? 失礼しました」
「いえ。演奏がんばってください」
「あ、待って……一緒に弾きませんか?」
「はっ……?」
挨拶して去ろうとすると、彼は私をピアノの前に引っ張って行った。
そして、大きな黒袖から覗く白い指先で鍵盤を叩いた。連弾の誘いだ。
ポーン、と低く響く音は、浮ついた私の心を引っ掴まえて、静かで美しい物語世界の入り口を見せてくれた。
たった1音で心を掴んでしまう、鮮やかで奥深い音だった。
曲は、組曲マ・メール・ロワ、第1曲、眠れる森の美女のパヴァーヌ。
連弾相手の返事を待つように、出だしのメロディが奏でられる。
――弾く……?
私が続きを奏でないと、進まない。
静寂を恐れて音を紡げば、指は動いた。
――弾ける。
ワクワクした。
――私、弾ける。指が動く。覚えてる……!
宝石の粒を溶かして固めたような、きらめく音が耳をくすぐる。
現実がどこかに吹き飛ばされて、彼の音楽が鮮やかに優しく私を包み込む。
自分の音が彼の音と一緒に響き合うのが、奇跡のよう。
心地よい音楽に体が自然と揺れて、数日前にカットしたばかりの栗色の髪が頬にかかる。
指が滑らかに鍵盤の上で踊るのが、嬉しくて仕方ない。
雨だれのように音が連なって、世俗に縮こまって乾いていた心が潤っていく。
すぐ隣にいる彼の息づかいに――ドキドキする。
――ワァッ……、
曲を終えると歓声と拍手が湧いた。
まだ夢から覚めたくないと思った。
でも、気づけばもう19時。駅ピアノの演奏可能時間は、終わりだ。
「ばっちり撮れましたよ、大河さん」
カメラを持っている人が、大河さんに話しかけてくる。マネージャーさんだろうか。
大河さんは大人っぽく品のある微笑みを湛えて、私に頭を下げた。
「突然の申し出を引き受けてくださって、ありがとうございました。楽しい連弾でした。後日、配信サイトに動画を載せてもよろしいですか?」
「あ……は、はい」
お礼に食事にも誘ってくれる。いい人だ。
それに、耳元で「食事場所にピアノがありますよ」と囁いてくる。
私がまだ日常に戻りたくないのを理解されているみたいだ。
「いらっしゃいませんか?」
誘われた声は、柔らかで耳に心地いい。
ずっと話していたくなる。
高級車に促されるまま乗り込むと、覆いかぶさるようにしてシートベルトを留めてくれる。距離が近くて、少し緊張した。
「詩音さん、でいいんですよね? 見えてしまってるのですが、これ、なんですか?」
「え?」
大河さんは、私のスマホに目を瞬かせた。また通知が来ていた。
『詩音さんへ。仕事が終わったら、明日の仕事に備えて早く寝ましょう』
「彼氏ですか?」
「ああ、大河さん。これ、アプリなんですよ。人間じゃないんです」
「へえ……このアプリ、面白いんですか?」
画面を覗き込む大河さんの顔が、吐息が感じられるほど近い。
バイレードのブランシュに似た、透明感ある香りがする。
「面白くないかも、しれませんね」
「あっ。近かったですね、すみません」
視線を逸らしてスマホを胸に伏せると、彼はハッとした顔で距離を取った。
照れている彼を見ていると、私も恥ずかしくなってくる。耳が熱い。
車が動き出すと、低めの車高ならではの振動が心地よかった。