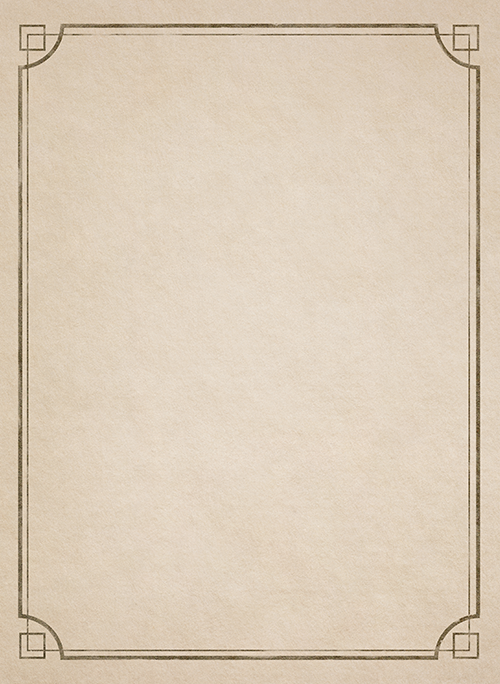私の名前は結衣。小さいころから今に至るまで、ずっと同じ地元に住んでいた。そして、その地元にある高校に通う女子高校生だ。ただ、今はそんなことはどうでもよかった。私の心は、人生初めての引っ越しという大きな現実を前に揺れていたからだ。
私は今、幼馴染の彼と向かい合って座っている。彼の名前は拓也。彼とは幼稚園の頃からずっと一緒で、数え切れない思い出が詰まった大切な存在だ。短く整えられた髪と鋭い瞳、すっと通った鼻筋と端正な顔立ちを持つ彼は、長身で筋肉質な身体を持つ。そんな拓也は、知らない人からすると冷たい印象を与えてしまうらしい。知らない人とは積極的に絡んでいかない姿勢。どこかぶっきらぼうに捉えられても仕方がない話し方。確かに、その体格や話し方は、どこか怖いと思わせる要素があるのかもしれない。
だけど、私は彼を深く知っている。昔から、私の世話を焼いてくれて、細かな気配りをしてくれる彼は、優しさを兼ね備えた、まさに理想の男性といえる。
来週には私はこの町を離れて新しい環境に飛び込むことになる。彼もそのことを知っている。ただ、これまでその話題に深く触れずに、彼と一緒に過ごしていた。
部屋の中は静まり返っていて、聞こえるのは部屋に置いてある時計の針が刻む音だけだった。その時計も、小学校のときに私が拓也に送ったものだ。それを今でも使っている彼は、それを私に言うことはないが、時計が壊れそうになるたびに修理をして使い続けているのだろう。
満月の光が窓から差し込み、拓也の顔を優しく照らしていた。そんな彼の顔を見ると、胸がぎゅっと締め付けられるような気持ちになった。
「来週には引っ越すんだね。」
拓也が絞り出すように言ったその言葉が、私の心に深く響いた。ずっと一緒にいたい、でもそうはできないという現実が、私たちの間に冷たく横たわっている。私も微笑んでみせたが、その笑顔には少しの緊張が混じっていたことを自覚していた。
「うん、私。新しい環境で頑張るよ。」
言葉にしながら、私は拓也の目を見つめた。その瞳の中には、私に対するたくさんの思いが詰まっているように感じた。私はその思いを受け止めたくて、でもそれができない自分の無力さを感じていた。
「結衣なら大丈夫だろ?」
彼の言葉は、私を勇気づけるためのものだったとわかっている。彼は私の強さを信じてくれている。新しい環境でもきっと友達を作り、楽しく過ごせると。そんな彼の言葉に、私は小さく頷いた。けれど、視線を彼から外すことで、心の中の不安を隠すしかなかった。
「奇麗だね。」
拓也が言ったその言葉に、私は窓の外を見た。満月の光が庭を照らし、その美しさが心に染み渡る。けれど、その美しい景色を見るのも、今週で最後だと考えると、胸が痛んだ。
「でも、私がこの風景を見るのも、今週で最後。」
私が彼にそう伝えると、私たちの間に再び沈黙が訪れた。この静けさが、私の心の中の混乱をさらに浮き彫りにするようだった。私はここで言わなければならないことを決意し、彼に向き直った。
「…改めて、言わなきゃいけないことがあるの。」
声が震えているのが自分でもわかった。けれど、この感情を伝えなければ、きっと一生後悔すると思ったからだ。視線を逸らし、もう一度彼の目を見つめた。
「ずっと前から、好きだったの。ずっと、拓也のことが好きだった。幼馴染じゃなくて、恋人として。」
心の底からの告白。その言葉を口に出した瞬間、私は自分の心が軽くなるのを感じた。彼の反応を待ちながら、私は彼がどう感じているのかを一瞬で読み取ろうとした。
「知ってる、こんなタイミングで言うのはズルいって。でも、言わなきゃ後悔すると思って…、私と付き合ってください!」
私は、ずるい女だ。こんな言い方をすると、拓也は断ることができないと長い付き合いで、知っているのだ。その言葉が部屋の中に響き渡った瞬間、私は彼の返事を待つ緊張に包まれた。彼の目が揺れ動くのを見て、私の心も揺れ動いた。そして、彼の口から出てきた言葉は、予想もしないものだった。
「結衣。僕たちは、幼馴染だ。僕は、結衣と恋人になるなんて嫌だ。」
その言葉が私の心に突き刺さった。知っていた。彼がどこか私のことを真剣に考えていて、そして、何かを考えていることを。だけど、私は心のどこかで、彼が私の告白を受け入れてくれると思い込んでいたのだろう。彼の言葉に、一瞬で目の前が真っ暗になった。涙が頬を伝って落ちるのを感じながら、私はその場に立ち尽くしていた。彼の言葉が私にとってどれだけ重く、どれだけ辛いものであったか。私たちの関係が壊れる瞬間を感じながら、私はその場を去った。彼の元を離れることが、こんなにも苦しいとは思わなかった。
拓也の家には、私のために用意された部屋があった。拓也の両親が、私がよく泊まりに来ることを考えて作ってくれた部屋だった。私は無意識に、その割り当てられた自分の部屋に戻っていた。
部屋に入ると、思い出が一気に押し寄せてきた。この部屋で過ごした数え切れない夜、拓也と一緒に宿題をしたり、映画を見たり、ただ話をして過ごしたりした時間。壁にかかった写真や、机の上に並べられた小物が、私たちの思い出を鮮明に蘇らせる。
私はベッドに腰を下ろし、深く息を吸い込んだ。拓也の家の匂いが私の心を落ち着けてくれる。手を伸ばして、机の上に置かれた写真立てを手に取った。そこには、つい最近、私たちが高校の文化祭で撮った写真が飾られていた。楽しそうに笑う私たちの姿が、今では遠い過去のように感じられる。
「これから、どうすればいいんだろう…」
私は心の中でつぶやいた。拓也と過ごした時間がこんなにも大切だったことを、改めて感じた。彼に告白して、振られたことの痛みが、私の心を締め付ける。でも、その痛みを乗り越えて、私は新しい生活を始めなければならない。
明日から新しい環境に飛び込むことへの不安が、胸に広がる。新しい学校、新しい友達、新しい生活。そのすべてが、私には未知のものだ。
私は眩暈を感じた。そのまま、ベッドに横たわった。ベッドに横たわった私は、天井を見つめながら深い息をついた。拓也に告白し、振られた瞬間の出来事が何度も頭の中で繰り返される。そのたびに胸が締め付けられ、涙が自然とこぼれてきた。私は彼のことが好きだった。ずっと、ずっと前から。
私は、どうしてこんな女なんだろう。溢れ出てくる涙と、小さくつぶやいたその言葉は、誰にも届くことはない。でも、心の中で叫び続けている声が抑えられなかった。彼が私を拒絶した理由は、彼自身の優しさからだということも理解していた。彼は、私が新しい環境で自分の存在が負担にならないように考えた結果なのかもしれない。それでも、その優しさが今はただ痛みとなって私を苦しめていた。
私の初恋は、心の深いところに刻まれる。私は彼のことが本当に好きだった。彼の優しさ、彼の強さ、彼のすべてが私にとって大切なものだった。そのすべてが、今は遠いものに感じられる。拓也との思い出が鮮明に蘇るたびに、心の中の痛みが増していく。あの公園で一緒に遊んだ日々、学校の帰り道で話したこと、困ったときには、彼が相談に乗ってくれたこと。今となっては、そのすべてが思い出すだけで苦しいだけの思い出となってしまった。
拓也が言ってくれた「結衣なら大丈夫だろ?」という言葉が、私の脳裏で繰り返された。彼が私を信じてくれているのなら、私も自分を信じなければならない。
それでも、私はこの途方もない痛みを乗り越えることができそうにない。私はただ、泣き続けることで心の中の感情を吐き出すしかなかった。
私は今、幼馴染の彼と向かい合って座っている。彼の名前は拓也。彼とは幼稚園の頃からずっと一緒で、数え切れない思い出が詰まった大切な存在だ。短く整えられた髪と鋭い瞳、すっと通った鼻筋と端正な顔立ちを持つ彼は、長身で筋肉質な身体を持つ。そんな拓也は、知らない人からすると冷たい印象を与えてしまうらしい。知らない人とは積極的に絡んでいかない姿勢。どこかぶっきらぼうに捉えられても仕方がない話し方。確かに、その体格や話し方は、どこか怖いと思わせる要素があるのかもしれない。
だけど、私は彼を深く知っている。昔から、私の世話を焼いてくれて、細かな気配りをしてくれる彼は、優しさを兼ね備えた、まさに理想の男性といえる。
来週には私はこの町を離れて新しい環境に飛び込むことになる。彼もそのことを知っている。ただ、これまでその話題に深く触れずに、彼と一緒に過ごしていた。
部屋の中は静まり返っていて、聞こえるのは部屋に置いてある時計の針が刻む音だけだった。その時計も、小学校のときに私が拓也に送ったものだ。それを今でも使っている彼は、それを私に言うことはないが、時計が壊れそうになるたびに修理をして使い続けているのだろう。
満月の光が窓から差し込み、拓也の顔を優しく照らしていた。そんな彼の顔を見ると、胸がぎゅっと締め付けられるような気持ちになった。
「来週には引っ越すんだね。」
拓也が絞り出すように言ったその言葉が、私の心に深く響いた。ずっと一緒にいたい、でもそうはできないという現実が、私たちの間に冷たく横たわっている。私も微笑んでみせたが、その笑顔には少しの緊張が混じっていたことを自覚していた。
「うん、私。新しい環境で頑張るよ。」
言葉にしながら、私は拓也の目を見つめた。その瞳の中には、私に対するたくさんの思いが詰まっているように感じた。私はその思いを受け止めたくて、でもそれができない自分の無力さを感じていた。
「結衣なら大丈夫だろ?」
彼の言葉は、私を勇気づけるためのものだったとわかっている。彼は私の強さを信じてくれている。新しい環境でもきっと友達を作り、楽しく過ごせると。そんな彼の言葉に、私は小さく頷いた。けれど、視線を彼から外すことで、心の中の不安を隠すしかなかった。
「奇麗だね。」
拓也が言ったその言葉に、私は窓の外を見た。満月の光が庭を照らし、その美しさが心に染み渡る。けれど、その美しい景色を見るのも、今週で最後だと考えると、胸が痛んだ。
「でも、私がこの風景を見るのも、今週で最後。」
私が彼にそう伝えると、私たちの間に再び沈黙が訪れた。この静けさが、私の心の中の混乱をさらに浮き彫りにするようだった。私はここで言わなければならないことを決意し、彼に向き直った。
「…改めて、言わなきゃいけないことがあるの。」
声が震えているのが自分でもわかった。けれど、この感情を伝えなければ、きっと一生後悔すると思ったからだ。視線を逸らし、もう一度彼の目を見つめた。
「ずっと前から、好きだったの。ずっと、拓也のことが好きだった。幼馴染じゃなくて、恋人として。」
心の底からの告白。その言葉を口に出した瞬間、私は自分の心が軽くなるのを感じた。彼の反応を待ちながら、私は彼がどう感じているのかを一瞬で読み取ろうとした。
「知ってる、こんなタイミングで言うのはズルいって。でも、言わなきゃ後悔すると思って…、私と付き合ってください!」
私は、ずるい女だ。こんな言い方をすると、拓也は断ることができないと長い付き合いで、知っているのだ。その言葉が部屋の中に響き渡った瞬間、私は彼の返事を待つ緊張に包まれた。彼の目が揺れ動くのを見て、私の心も揺れ動いた。そして、彼の口から出てきた言葉は、予想もしないものだった。
「結衣。僕たちは、幼馴染だ。僕は、結衣と恋人になるなんて嫌だ。」
その言葉が私の心に突き刺さった。知っていた。彼がどこか私のことを真剣に考えていて、そして、何かを考えていることを。だけど、私は心のどこかで、彼が私の告白を受け入れてくれると思い込んでいたのだろう。彼の言葉に、一瞬で目の前が真っ暗になった。涙が頬を伝って落ちるのを感じながら、私はその場に立ち尽くしていた。彼の言葉が私にとってどれだけ重く、どれだけ辛いものであったか。私たちの関係が壊れる瞬間を感じながら、私はその場を去った。彼の元を離れることが、こんなにも苦しいとは思わなかった。
拓也の家には、私のために用意された部屋があった。拓也の両親が、私がよく泊まりに来ることを考えて作ってくれた部屋だった。私は無意識に、その割り当てられた自分の部屋に戻っていた。
部屋に入ると、思い出が一気に押し寄せてきた。この部屋で過ごした数え切れない夜、拓也と一緒に宿題をしたり、映画を見たり、ただ話をして過ごしたりした時間。壁にかかった写真や、机の上に並べられた小物が、私たちの思い出を鮮明に蘇らせる。
私はベッドに腰を下ろし、深く息を吸い込んだ。拓也の家の匂いが私の心を落ち着けてくれる。手を伸ばして、机の上に置かれた写真立てを手に取った。そこには、つい最近、私たちが高校の文化祭で撮った写真が飾られていた。楽しそうに笑う私たちの姿が、今では遠い過去のように感じられる。
「これから、どうすればいいんだろう…」
私は心の中でつぶやいた。拓也と過ごした時間がこんなにも大切だったことを、改めて感じた。彼に告白して、振られたことの痛みが、私の心を締め付ける。でも、その痛みを乗り越えて、私は新しい生活を始めなければならない。
明日から新しい環境に飛び込むことへの不安が、胸に広がる。新しい学校、新しい友達、新しい生活。そのすべてが、私には未知のものだ。
私は眩暈を感じた。そのまま、ベッドに横たわった。ベッドに横たわった私は、天井を見つめながら深い息をついた。拓也に告白し、振られた瞬間の出来事が何度も頭の中で繰り返される。そのたびに胸が締め付けられ、涙が自然とこぼれてきた。私は彼のことが好きだった。ずっと、ずっと前から。
私は、どうしてこんな女なんだろう。溢れ出てくる涙と、小さくつぶやいたその言葉は、誰にも届くことはない。でも、心の中で叫び続けている声が抑えられなかった。彼が私を拒絶した理由は、彼自身の優しさからだということも理解していた。彼は、私が新しい環境で自分の存在が負担にならないように考えた結果なのかもしれない。それでも、その優しさが今はただ痛みとなって私を苦しめていた。
私の初恋は、心の深いところに刻まれる。私は彼のことが本当に好きだった。彼の優しさ、彼の強さ、彼のすべてが私にとって大切なものだった。そのすべてが、今は遠いものに感じられる。拓也との思い出が鮮明に蘇るたびに、心の中の痛みが増していく。あの公園で一緒に遊んだ日々、学校の帰り道で話したこと、困ったときには、彼が相談に乗ってくれたこと。今となっては、そのすべてが思い出すだけで苦しいだけの思い出となってしまった。
拓也が言ってくれた「結衣なら大丈夫だろ?」という言葉が、私の脳裏で繰り返された。彼が私を信じてくれているのなら、私も自分を信じなければならない。
それでも、私はこの途方もない痛みを乗り越えることができそうにない。私はただ、泣き続けることで心の中の感情を吐き出すしかなかった。