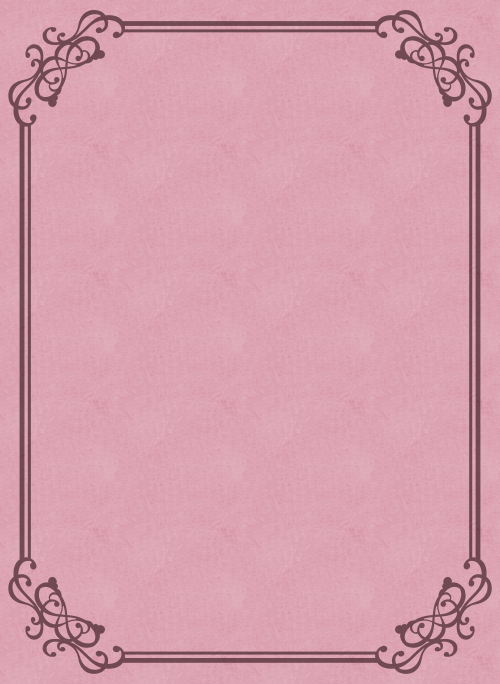石段を駆け上がった。
そこには、泣き崩れた君の姿。
「なんでついて来たの」
当然、聞かれることなんてわかってた。
偶然にも、君が告白して振られるところを見てしまったのだ。
体が勝手に君を追っていた、なんて言ったら
君は、怒るだろうか。
「僕は君が好きだ」
同情で言ったんだと、思われるのだろうか。
紛れもなく、本当に、君が好きなのは確かだ。
「そんなこと誰も聞いてないよ……。でも、ありがとう」
そう言いながら苦しそうに笑う君を見ると、自分まで辛くなった。
「ちょ、……っと!なに……急に……っ……」
僕が君を抱きしめたのだ。
「離してっ……!」
「いいから、じっとしてて」
強く強く、君を抱きしめた。
“大丈夫だよ”
その思いを伝えるように。
「なんでこういう時に限って、優しくするの…っ…?」
泣きながらも抵抗していたはずの君が
僕の腕の中に収まって、静かになった。
「泣いてるなんて、君らしくないよ」
「……う、うる…さい。
……勝手に涙が出てくるの」
悲しいから泣くんでしょ。そんなの僕でも分かってる。
「無邪気に笑ってなよ。泣いてる君なんて、君らしくない」
「あんたみたいなの、一番好きじゃない」
「……そこまで言われちゃうと
基本、無関心な僕でも傷付くなぁ……」
「好きじゃないけど……。もう少し、もう少しだけ。このままでいさせて……」
「……うん。今日だけ、特別だよ……」
そう言うと、そのまま泣きつかれて外にいるというのに、僕の腕の中で眠ってしまった。
仕方なく、送っていく事にした。
お姫様抱っこをして、僕に寄りかかって君は寝ていた。
家の人に事情を説明して、部屋に入ると
いかにも女の子の部屋だった。
ベットに下ろし、布団をかけてあげると
手だけが僕から離れなかった。
すーすーと寝息をたてて無防備に寝ている。
そんな君がただ愛おしかった。
そこには、泣き崩れた君の姿。
「なんでついて来たの」
当然、聞かれることなんてわかってた。
偶然にも、君が告白して振られるところを見てしまったのだ。
体が勝手に君を追っていた、なんて言ったら
君は、怒るだろうか。
「僕は君が好きだ」
同情で言ったんだと、思われるのだろうか。
紛れもなく、本当に、君が好きなのは確かだ。
「そんなこと誰も聞いてないよ……。でも、ありがとう」
そう言いながら苦しそうに笑う君を見ると、自分まで辛くなった。
「ちょ、……っと!なに……急に……っ……」
僕が君を抱きしめたのだ。
「離してっ……!」
「いいから、じっとしてて」
強く強く、君を抱きしめた。
“大丈夫だよ”
その思いを伝えるように。
「なんでこういう時に限って、優しくするの…っ…?」
泣きながらも抵抗していたはずの君が
僕の腕の中に収まって、静かになった。
「泣いてるなんて、君らしくないよ」
「……う、うる…さい。
……勝手に涙が出てくるの」
悲しいから泣くんでしょ。そんなの僕でも分かってる。
「無邪気に笑ってなよ。泣いてる君なんて、君らしくない」
「あんたみたいなの、一番好きじゃない」
「……そこまで言われちゃうと
基本、無関心な僕でも傷付くなぁ……」
「好きじゃないけど……。もう少し、もう少しだけ。このままでいさせて……」
「……うん。今日だけ、特別だよ……」
そう言うと、そのまま泣きつかれて外にいるというのに、僕の腕の中で眠ってしまった。
仕方なく、送っていく事にした。
お姫様抱っこをして、僕に寄りかかって君は寝ていた。
家の人に事情を説明して、部屋に入ると
いかにも女の子の部屋だった。
ベットに下ろし、布団をかけてあげると
手だけが僕から離れなかった。
すーすーと寝息をたてて無防備に寝ている。
そんな君がただ愛おしかった。