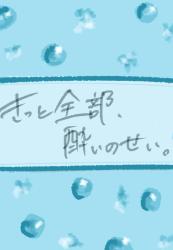かっこいい。かっこいい。かっこいい。
気が付くと、何度も何度も同じセリフが胸の中で騒いでいた。私の視線は当然の事ながら彼にある。校庭でサッカーをしている、彼に。
「夏樹! パス!」
チームメイトの1人が彼にパスを出したので私は固唾を飲んでフェンスをギュッ、と握った。
入れ……! 入れ……!!
きっと彼よりも、チームメイトよりも、誰よりも、私がそう願っていたと思う。トンッ、とサッカーボールが彼の足先に当たる。そのままそれは大きく弧を描き、吸い込まれるようにゴールシュートに放り込まれた。
「夏樹ー! ナイスシュート!」
チームメイトが口々に言う。Tシャツの胸元を引っ張って、額に浮かんだ汗を拭う彼はまるで英雄だった。なのに「パスが良かったんだよ」と少しだけ自分の凄みを下げていた。目尻にシワを寄せて、輪の中でとても楽しそうに笑う彼を私は全力で網膜に焼き付けていた。
────中学2年。私は彼に恋をしている。
彼を見ていると周りの喧騒が全部シャットアウトされて。心臓が信じられないくらいドキドキして。今ここは2人だけの空間なんじゃないか、って錯覚に陥る。”夢中になる”っていうのはまさにこういうことだと思う。
彼との出会いは小学1年生の時。私と彼はたまたま同じクラスになった。今では考えられないけど当時の私は好き、なんて感情まだよく知らなかったし、彼のことを特別かっこいい、という目では見ていなかった。でも、いつからか好きになってた。きっかけなんて自分でもよく分からない。気が付いたら私は彼が好きで。授業中も休み時間も当たり前のように目で追っていた。そのおかげでか私の成績は中の下。きっと彼を好きじゃなかったら中の上ぐらいは、いってたと思う。
***
「おはよー、また見てたのー?」
「おはよう、てへへ…、うん」
教室に入ると友達のユキちゃんが呆れ顔で私の緩みきった頬をつねった。
「もうー、好きって伝えればいいのにー」
「だって……」
「だって、なによ?」
「……」
詰め寄られて私は、口を噤んだ。
「だって、の続きはー?」
催促されて、私は泣く泣く口を開いた。
「……恥ずかしいんだもん」
「乙女か!」
弱弱しい声に派手なツッコミが放り込まれる。それは先程彼が決めたシュートと同じくらい綺麗で無駄のないものだった。ユキちゃんは私が彼に長年抱く特別な感情を知っている。私が毎朝サッカー部の朝練を見る為に苦手な早起きを頑張っていることも、包み隠さず”恋バナ”として話していた。
「でもさー、もし付き合えたらもっと近くであの顔面見られるんだよ? 手繋いだりも出来るんだよ?」
「うぅ…、そうかもしれないけど…」
ユキちゃんは日々私の背中を押そう、としてくれている。でも私はこめかみに手を当てて唸ることしか出来なかった。彼の容姿はとてもかっこいい。目鼻立ちがはっきりしていて、キリッとしている。無意識にこちらが目で追ってしまう程の魅力を常に放っている。そして彼は私の初恋であり、すごくすごく大好きな人。正直、”恋”なんて安直な言葉で括りたくないぐらい大好き。この先彼以外にこんなに好きになる人なんて絶対いないと断言出来る。だからこそ。私は彼にこの気持ちを伝えることは一生ない、という自負があった。
だって、こんな…彼と1回も喋ったことない女、振られるに決まってる。それが常に念頭にあるから私は、1歩踏み出せない。この気持ちをいつまでも大切にしたいから、彼を密かに想っているだけで…
それだけで十分なのだ。
「あ、そういえば今日席替えあるね。隣になっちゃったらどうするー?」
「あはは、それねぇ…毎回5回はそれ妄想するけど、なったことないから」
寂しく笑みを浮かべる私。彼の隣なんて特等席は恐れ多くて祈ることすらまともに出来ないけどせめて近くに、ぐらいは期待してしまう。そんな期待は毎回当然の如く玉砕されちゃうんだけどね。
彼の席に視線を移す。私は今1番右の後ろの席で彼は今1番左の前の席。前回の席替えから1ヶ月。教室内で私と彼の距離は誰よりも遠い位置にあった。せめてこの1ヶ月間この苦行に耐えた私にご褒美が欲しい所なんだけど…
「あ、夏樹ー!さっき見たぞー、華麗にシュート決めてたなー」
クラスメイトの声で後方に目を向けると朝練終わりの彼が教室に入ってきた。肩にかけたスクールバッグを机の上に置いているそのほんのちょっとの動作ですらかっこよくて見入ってしまう。
「やめろよ、恥ずかしいなー」
からかう男友達の背中を軽く小突く彼。
あぁ……いいなぁ。
心の中で本音がポロリ。男友達が心底羨ましい、と思った。彼からあんなふうにボディタッチして貰えるなんて。私も男に生まれたかった。きっと男に生まれてたとしても私は彼を好きになっていたに違いない。そしたら今流行りの青春BL物語が始まっていたかもしれないなと、また1つ頭の中が気持ちの悪い妄想を紡ぎあげていくのであった。
それから、席替えは朝のHRで行われた。先生お手製のあみだくじに前から順番に名前を書いていく。私は1番最後に回ってきた為選択肢はなかった。余っている1箇所に名前を書いて先生の所に持っていく。大丈夫!余り物には福ある、っていうし!そう自分を慰めながら。
「はーい、じゃあ書いてくぞー」
黒板にクラスメイト全員の名前が書き出されて、席順が発表されていく。逐一黒板に当たるチョークがコツコツと豪快に音を立てていて、時折名前を書かれた当人が「マジかー」と不満の声を漏らしたり「よっしゃー」などの歓喜の声を上げていた。
きっと私だけだ。自分の名前よりも彼の名前が書かれるのを心待ちにしているのは。ドキドキ、と心臓が早鐘を打つ。隣になれば国語の時間時々ペアを組むことがあるからその時に必然的にお話が出来るかもしれない。自分からじゃ告白どころか話しかける勇気すらないけど、好きな人にアプローチ1つ出来ないこのチキン女にとって ”彼に話しかけてもいい状況”は常に喉から手が出るほど欲していた。
「はっ……」
その時、私は息を飲んだ。【佐々木 夏樹】の文字が今先生の手によって書かれたのだ。私の名前はまだ書かれていない。無意識に両手を組んで祈っていた。
近くがいい…! 彼の近くがいい……!!!
子供が物欲をあらわにする一点張りのように何度も唱える。
「じゃあ移動して下さい」
先生の合図で私は我に返った。ちょっと…心が追いついてないみたい。どこかボー、とする身体を無理矢理立ち上げ、私は新しい席へ移動した。
「全員席着いたかー? 今日から1ヶ月この席でいくからなー」
茫然自失。
移動し終わった私は机の下で足をキュッ、と閉じて上履きの中、つま先まで丸めた。彼の隣にはなれなかった。でも……
彼の真後ろには、なれた……。
やば。どうしよう。彼が目の前にいる……。
心臓が鳴り止まないよ……。未だかつてこんな近くの席になったことはなかった。ちょっと手を伸ばせば簡単に届く距離。彼の男らしい大きな背中が視界を埋める。たちまち頬が緩みそうになった。慌てて周りに見られないようにそっと下を向いて、なんとか顔に出ないように、とじっと堪えた。それでもポっ、と顔が赤くなるのを感じる。テンションが上がって、そんな度胸無い癖に無性に彼の背中をシャーペンでつつきたくなった。
───────そんな夢を見ていた。
「……んっ」
目が覚めると私の身体は自室のベッドに仰向けで横たわっていた。正確に言うと21歳の私が、目尻から涙を垂れ流しながら横たわっていた。
「ぐすんっ…」
時刻は深夜2時。鼻を啜った。ぼんやりと天井を眺めながら私は頬についた涙の筋を手の甲で押さえる。
楽しかったなぁ…あの頃。
懐かしさで胸がやられた私はゴロン、と寝返りを打った。
ここ数日、眠りにつくと私は必ず学生時代の夢を見る。正確に言うと中学2年の夏。席替えがあった日の夢。
あの頃、私は彼のことが好きで好きで仕方なかった。私の学生時代は彼のおかげで毎日幸せだった。高校が離れた時は正直死ぬほど嫌だったけど、でもあの小中で紡いだ片想いの軌跡があれば十分だって、自分に何とか言い聞かせた。”学校”という接点を無くした私はせめて”SNS”で繋がりを持とうと何度も彼の名前を検索した。そしてやっと自分の力で見つける事が出来た彼のアカウント。女の子みたいに可愛い桜のアイコン。今まで話しかけることすら出来なかったのに、フォローリクエストを送ることが出来た。数時間後にフォロバされた時は言葉では言い表せないくらい喜んだ。
時々私のくだらない投稿にいいねを押してくれたりもした。彼からのいいね通知は、いつもスクショしてしまう。あぁ、画面越しに彼とちゃんと接点があるんだぁ…って嬉しくて。高校生になっても大学生になっても彼を好きな気持ちには変わりなかった。中学卒業以来、もうずっと顔も見てないし声も聞いてないのに。胸がはち切れそうになるくらいいつもいつも大好きで……大好きで…大好きで……。
だから───────…
死んだ、なんて…………やめてよ。
今日午前10時30分。ブレーキとアクセルの操作を誤ったことで軽乗用車が歩道に突っ込み、信号待ちをしていた21歳の男性 佐々木夏樹さんが巻き込まれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと佐々木さんは大学に向かうところだったらしく───────…
先週、彼の訃報を耳にした。最近私がSNSにあげた写真…彼、いいねくれてたなぁ。嬉しかったなぁ。そんな歓喜に浸りながら、録画しておいたドラマを見ていた最中での事だった。中学の同級生の子から
「ねぇ、ニュース見た?」
そんなメッセージが送られてきて。何事かと検索したら痛々しい文面が私の大好きな人の名前と共に綴られていた。いつだって私にトキメキを与えてくれていたその苗字と名前を目にした時、トキメキなどとは程遠い動悸がした。そしてまず、思ったのは、
” 嘘 で し ょ ? ”
だった。
彼の訃報を聞いて以来。
私は大学には行けていない。ご飯もろくに喉を通らない。朝から晩まで自室に籠って、ただただ……このベッドに横たわっていた。当然の気の沈みようだった。何年もストーカー並に目で追っていたのだ。口では想っているだけで十分、とか言いながら何度「もし付き合えたら」なんて気持ちの悪い妄想を繰り返しただろう。
…当然だ。
悲しくて当然だ。
涙が止まらなくて当然だ。
20代になって。ふと思ったことがある。
学生時代なんて、思い返せばいつも教室にいた。数歩歩けば誰とでも話せるようなそんな小さな箱に収まってたんだから、ちょっと勇気出して。歩いて。彼の所まで行って。肩をトントンって叩いて。「好き」って伝えればよかった。たった2文字でよかったのに、たった2文字すらも、当時の私は躊躇した。
振られたらどうしよう。もし告白して彼が男友達に面白おかしく言いふらして、からかわれて。私学校で居場所なくしたらどうしよう、とか彼がそんなことする人じゃないって分かってるから好きになってるのにそんなことばっかり考えて私は勇気が出せなかった。
もし私があの頃勇気を出して告白して、仮にうまくいってたとしたら運命ちょっと変わったのかな。なんてここ数日はそんな可能性ばかり考えていた。事故があったあの日あの時間、もし朝から私と通話してて、家を出る時間が少しずれて、彼があの場所に向かう時間が少しだけずれて。そしたら運命が変わって…、彼は…今もこの世界のどこかで生きていられたのだろうか。
徐々に夢の記憶が脳内を支配していく。
彼がサッカーをやってる姿。
席替えで前後になった時の喜び。
全部私が経験したこと。夢だけど夢じゃない記憶。ただ見ていただけなのに、幸せで溢れていた。そう。ただ……見ていただけだったのだ。あの頃の自分は───────…
あーぁ…、もう二度と伝えられない今になって、後悔しても遅いのに…。
拳を強く握って、もう一度仰向けに横たわった。
時刻は午前二時。丑三つ時。
私はもう一度眠りについた。
───────それから夢を見た。
かっこいい。かっこいい。かっこいい。
気がつくと、そんな単調なセリフを胸に抱く中学2年の私が学校の校庭にいた。
ただ、好きな人を少し遠くから見ているだけの日々を送っていた。
「夏樹! パス!」
私は願う。
入れ……! 入れ……!!と。
もちろん入ることは、知っている。
「夏樹ー! ナイスシュート!」
「パスが良かったんだよ」とチームメイトに言う彼の姿が、ぼんやりと滲む。
本来なら私はここで教室に戻る。すると友達のユキちゃんがやって来て、「もうー、好きって伝えればいいのにー」と毎度の如く告白を促してくる。そうして私は…、口癖のようにこう思うんだ。
私は彼を密かに想っているだけで十分なのだ
と。
……そんな訳、ないのにね。
鼻の奥がツン、とした。当たり前のように生きている彼の姿に、溢れ出した涙が収まらなかった。辛すぎて、苦しすぎて、悔しすぎて、立っていられなくなって私はその場にしゃがみこんだ。
「うぅー…」
人目も気にせず嗚咽がポロポロと溢れていく。
想ってるだけで十分な訳ないよ。本当は違うよ…。……付き合いたかった。平日だけじゃなくて休みの日も会いたかった。どこかへ遊びに行きたかった。その顔面を誰よりも近くで見ていられる場所にいたかった。大好きだった。
「……っ」
はっ、と我に返る。
ダメだ……泣いてちゃダメだ…。
泣き喚くそんな自分に鞭打って立ち上がった。夢の中でも後悔するなんて、嫌だ、と心が死ぬほど叫んでいた。私は涙を拭いながら昇降口に移動する。今までにないくらい心臓が跳ねる。きっと現実で告白することを選んでいたのなら同じように胸を弾ませていたのだろう。今だけの……夢だけの特別な感情に私はひたすら身を任せた。
下駄箱に身体を預けて、彼が来るのを待つ。緊張の渦に巻かれながら、私はしみじみと考えるのであった。
人には、任意で「好き」という想いを抱くことが出来る。そしてそれを、任意で相手に伝えることも出来る。
あくまでも「任意」
やってもやらなくても。どっちでもいいことなんだよね。
20歳の時。
成人式で久しぶりに会った友達が来月結婚するんだ、ってとても幸せそうに教えてくれたあの時。「おめでとう」と、口にする傍ら、私はふいに考えてしまった。
『夏樹、今度結婚するんだって』
私もいつか人伝いに彼の”幸せ”を耳にする日が来るのだろうか、と。そしたらきっと私は少しだけ胸を軋ませて。
『えっ!? マジ!?』
強がって笑顔を浮かべながら、偶然彼の結婚を耳にした、ただの”第三者”になるんだろうなと。
……正直そんなシチュエーションは考えるだけで吐き気がした。彼が私じゃない誰かのものになるとか、たとえ妄想でも嫌で嫌でたまらなくなったのだ。
でもそんなシチュエーションに、きっと私はまっしぐらだったことだろう。21歳になっても長年抱いてきた気持ちを伝えなかったのは紛れもなく私だ……。
「好き」は、当人は死ぬまで一生持っていられる感情かもしれない。でも
「好きを伝えたい相手」は、ある日突然、居なくなってしまうかもしれない。
そんな悲しい知恵を学ぶことになるなんて。21歳で知ることになるなんて思ってもみなかった。知りたくなかった。
あっ…
その時。前方から彼がやってきて私は背筋を伸ばした。当時何処へ行くにも必ず持ち歩いていた手鏡はあの頃のまま胸ポケットに入っていたのでそれで身だしなみを整えた。
伝えなきゃ。声……掛けなきゃ。
「てか今度の週末遊び行こーぜ」
「おーいいなー」
今伝えなきゃ、後に後悔することを私は知っている。もう、ここでしか伝えられないことを、悲しいことに知ってしまっているのだ。
「……っ、夏樹くん!!!」
声を張り上げた。多分この先二度と出すことのない勇気を、ありったけ出して今までずっと躊躇ってきた1歩を踏み出す。
夢だ、って分かってる。でも。
伝えたかった───────…
パチリ、と目が会う。彼の口から私の名前が溢れた。
夢のようだった……
「……広瀬?」
当然だった。大好きな人に名前を呼ばれちゃ心臓もこうなる。大好きな人に見つめられたら……、こうなるに決まってる。彼が私を見ていた。その瞳は紛れもなくクラスメイトの女子Fぐらいのモブキャラを見つめる瞳だったと思う。彼にとって私という存在はきっとその程度のもの。でも私にとっての彼は、いないと物語が一切進んでくれないヒーローポジションなんだ。
額から輪郭を伝って顎先に汗が流れていく。
セミの鳴き声がダイレクトに鼓膜に直撃する。
夏の涼やかな匂いが鼻腔を撫でる。
そして視界の先には私を見つめる大好きな人の姿。
私を取り囲む環境全てが、あの日あの時間に私を誘ってくれていた。歯止めをかけるものなんて、今この瞬間……もう何もない。
「……好き」
ずーっと抱いてきた特別な気持ちをこの時、生まれて初めて口にした。でも彼のところまで上手く届かなかった気がして。だからもう一度。肺に大きく息を貯めて。声を張り上げた。
「ずっと…っ、大好きでした……っ!!」
違う。これじゃない。口にしてすぐ、私は全力で首を振って否定した。
「大好きです!!」
過去形になんて、したくない恋だった。実ろうが実らまいが、ずっとしていたい恋だった。彼がこの世に居ようが居まいが、過去形にしない絶対的自信が私にはあった。
「大好き」がドバッ、と一気に洪水のように溢れていく。
「私の初恋は夏樹くんで、ちょっと気持ち悪いって思われちゃうかもだけど、休み時間も授業中もずっと目で追っちゃうくらい夏樹くんのことが好きで…っ」
息が続かない。1度言葉を止めてもう1度息を吸い込む。その感情はとても一息に収まりきらないほどだった。
「1度も話したことないのに、すごく…すごくすごく好きで…っ、」
口にしてしまえば最後。
はなからそれはシャボン玉に封じ込められた想いであったかのように、少しの刺激で簡単に壊れて、歯止めが効かなくって、溢れていく。そのくらい脆い箱の中でずっと、培ってきた私の大切な大切な感情だった。世界中探したってどこにも無いかけがえのない感情だ。
「何が…どこがっ、そんなに好きなんだろう、ってよく考えてた…。そしたら数え切れないくらい好きになる要素が見つかって…」
どこかゆったりと毎日が流れていた学生時代。
あの頃、私は毎日彼に夢中で。彼を想わない日はなかった。一生分の恋心を私は常に、彼に注いでいた。喋ったことないのにキモいよね。いきなりモブキャラがでしゃばっちゃってびっくりしたよね。だけどね……
モブキャラだって、恋するんだよ。
「何度も何度も、”あぁ…私は夏樹くんがどうしようもなく好きなんだ” って自覚させられたの……」
喉の奥がヒリヒリと痛かった。この夢が覚めれば彼がいない現実がある。これは、もう二度と叶わない恋。でも私は、”あなたに恋した私”を……、生涯誇りに思う。恋をすることの喜びを教えてくれたのは紛れもなく夏樹くんなのだから───────…
「だから…っ、だから……」
「広瀬」
紡ぎかけた言葉を彼が制した。いつの間にか地面に張り付いていた私の視線がゆっくりと上がる。視線の先で私を見つめる夏樹くんは……
「サンキューな」
白い歯を出して、ニッと。世界で1番かっこよく、優しく、穏やかに、微笑んでくれた。
それは私の網膜に、すでに焼き付きまくっているどの夏樹くんとも一致しない笑顔だった。私の為だけに、作ってくれた表情に他ならなかった。
────私の初恋は、今宵そうして終止符が打たれた。
けたたましいアラームで目が覚めた翌朝。
頬を伝った涙を、
強く、強く、拭った。
” 前を向こう ”
明日は大学に行こう。行ける気がする。
彼を好きになった自分を誇りに思おう。
この恋心を一生大切にしよう。
そして。
もしまたあの夢を見ることがあれば、何度でも伝えよう。
君に「好きだ」と───────。
【終】
気が付くと、何度も何度も同じセリフが胸の中で騒いでいた。私の視線は当然の事ながら彼にある。校庭でサッカーをしている、彼に。
「夏樹! パス!」
チームメイトの1人が彼にパスを出したので私は固唾を飲んでフェンスをギュッ、と握った。
入れ……! 入れ……!!
きっと彼よりも、チームメイトよりも、誰よりも、私がそう願っていたと思う。トンッ、とサッカーボールが彼の足先に当たる。そのままそれは大きく弧を描き、吸い込まれるようにゴールシュートに放り込まれた。
「夏樹ー! ナイスシュート!」
チームメイトが口々に言う。Tシャツの胸元を引っ張って、額に浮かんだ汗を拭う彼はまるで英雄だった。なのに「パスが良かったんだよ」と少しだけ自分の凄みを下げていた。目尻にシワを寄せて、輪の中でとても楽しそうに笑う彼を私は全力で網膜に焼き付けていた。
────中学2年。私は彼に恋をしている。
彼を見ていると周りの喧騒が全部シャットアウトされて。心臓が信じられないくらいドキドキして。今ここは2人だけの空間なんじゃないか、って錯覚に陥る。”夢中になる”っていうのはまさにこういうことだと思う。
彼との出会いは小学1年生の時。私と彼はたまたま同じクラスになった。今では考えられないけど当時の私は好き、なんて感情まだよく知らなかったし、彼のことを特別かっこいい、という目では見ていなかった。でも、いつからか好きになってた。きっかけなんて自分でもよく分からない。気が付いたら私は彼が好きで。授業中も休み時間も当たり前のように目で追っていた。そのおかげでか私の成績は中の下。きっと彼を好きじゃなかったら中の上ぐらいは、いってたと思う。
***
「おはよー、また見てたのー?」
「おはよう、てへへ…、うん」
教室に入ると友達のユキちゃんが呆れ顔で私の緩みきった頬をつねった。
「もうー、好きって伝えればいいのにー」
「だって……」
「だって、なによ?」
「……」
詰め寄られて私は、口を噤んだ。
「だって、の続きはー?」
催促されて、私は泣く泣く口を開いた。
「……恥ずかしいんだもん」
「乙女か!」
弱弱しい声に派手なツッコミが放り込まれる。それは先程彼が決めたシュートと同じくらい綺麗で無駄のないものだった。ユキちゃんは私が彼に長年抱く特別な感情を知っている。私が毎朝サッカー部の朝練を見る為に苦手な早起きを頑張っていることも、包み隠さず”恋バナ”として話していた。
「でもさー、もし付き合えたらもっと近くであの顔面見られるんだよ? 手繋いだりも出来るんだよ?」
「うぅ…、そうかもしれないけど…」
ユキちゃんは日々私の背中を押そう、としてくれている。でも私はこめかみに手を当てて唸ることしか出来なかった。彼の容姿はとてもかっこいい。目鼻立ちがはっきりしていて、キリッとしている。無意識にこちらが目で追ってしまう程の魅力を常に放っている。そして彼は私の初恋であり、すごくすごく大好きな人。正直、”恋”なんて安直な言葉で括りたくないぐらい大好き。この先彼以外にこんなに好きになる人なんて絶対いないと断言出来る。だからこそ。私は彼にこの気持ちを伝えることは一生ない、という自負があった。
だって、こんな…彼と1回も喋ったことない女、振られるに決まってる。それが常に念頭にあるから私は、1歩踏み出せない。この気持ちをいつまでも大切にしたいから、彼を密かに想っているだけで…
それだけで十分なのだ。
「あ、そういえば今日席替えあるね。隣になっちゃったらどうするー?」
「あはは、それねぇ…毎回5回はそれ妄想するけど、なったことないから」
寂しく笑みを浮かべる私。彼の隣なんて特等席は恐れ多くて祈ることすらまともに出来ないけどせめて近くに、ぐらいは期待してしまう。そんな期待は毎回当然の如く玉砕されちゃうんだけどね。
彼の席に視線を移す。私は今1番右の後ろの席で彼は今1番左の前の席。前回の席替えから1ヶ月。教室内で私と彼の距離は誰よりも遠い位置にあった。せめてこの1ヶ月間この苦行に耐えた私にご褒美が欲しい所なんだけど…
「あ、夏樹ー!さっき見たぞー、華麗にシュート決めてたなー」
クラスメイトの声で後方に目を向けると朝練終わりの彼が教室に入ってきた。肩にかけたスクールバッグを机の上に置いているそのほんのちょっとの動作ですらかっこよくて見入ってしまう。
「やめろよ、恥ずかしいなー」
からかう男友達の背中を軽く小突く彼。
あぁ……いいなぁ。
心の中で本音がポロリ。男友達が心底羨ましい、と思った。彼からあんなふうにボディタッチして貰えるなんて。私も男に生まれたかった。きっと男に生まれてたとしても私は彼を好きになっていたに違いない。そしたら今流行りの青春BL物語が始まっていたかもしれないなと、また1つ頭の中が気持ちの悪い妄想を紡ぎあげていくのであった。
それから、席替えは朝のHRで行われた。先生お手製のあみだくじに前から順番に名前を書いていく。私は1番最後に回ってきた為選択肢はなかった。余っている1箇所に名前を書いて先生の所に持っていく。大丈夫!余り物には福ある、っていうし!そう自分を慰めながら。
「はーい、じゃあ書いてくぞー」
黒板にクラスメイト全員の名前が書き出されて、席順が発表されていく。逐一黒板に当たるチョークがコツコツと豪快に音を立てていて、時折名前を書かれた当人が「マジかー」と不満の声を漏らしたり「よっしゃー」などの歓喜の声を上げていた。
きっと私だけだ。自分の名前よりも彼の名前が書かれるのを心待ちにしているのは。ドキドキ、と心臓が早鐘を打つ。隣になれば国語の時間時々ペアを組むことがあるからその時に必然的にお話が出来るかもしれない。自分からじゃ告白どころか話しかける勇気すらないけど、好きな人にアプローチ1つ出来ないこのチキン女にとって ”彼に話しかけてもいい状況”は常に喉から手が出るほど欲していた。
「はっ……」
その時、私は息を飲んだ。【佐々木 夏樹】の文字が今先生の手によって書かれたのだ。私の名前はまだ書かれていない。無意識に両手を組んで祈っていた。
近くがいい…! 彼の近くがいい……!!!
子供が物欲をあらわにする一点張りのように何度も唱える。
「じゃあ移動して下さい」
先生の合図で私は我に返った。ちょっと…心が追いついてないみたい。どこかボー、とする身体を無理矢理立ち上げ、私は新しい席へ移動した。
「全員席着いたかー? 今日から1ヶ月この席でいくからなー」
茫然自失。
移動し終わった私は机の下で足をキュッ、と閉じて上履きの中、つま先まで丸めた。彼の隣にはなれなかった。でも……
彼の真後ろには、なれた……。
やば。どうしよう。彼が目の前にいる……。
心臓が鳴り止まないよ……。未だかつてこんな近くの席になったことはなかった。ちょっと手を伸ばせば簡単に届く距離。彼の男らしい大きな背中が視界を埋める。たちまち頬が緩みそうになった。慌てて周りに見られないようにそっと下を向いて、なんとか顔に出ないように、とじっと堪えた。それでもポっ、と顔が赤くなるのを感じる。テンションが上がって、そんな度胸無い癖に無性に彼の背中をシャーペンでつつきたくなった。
───────そんな夢を見ていた。
「……んっ」
目が覚めると私の身体は自室のベッドに仰向けで横たわっていた。正確に言うと21歳の私が、目尻から涙を垂れ流しながら横たわっていた。
「ぐすんっ…」
時刻は深夜2時。鼻を啜った。ぼんやりと天井を眺めながら私は頬についた涙の筋を手の甲で押さえる。
楽しかったなぁ…あの頃。
懐かしさで胸がやられた私はゴロン、と寝返りを打った。
ここ数日、眠りにつくと私は必ず学生時代の夢を見る。正確に言うと中学2年の夏。席替えがあった日の夢。
あの頃、私は彼のことが好きで好きで仕方なかった。私の学生時代は彼のおかげで毎日幸せだった。高校が離れた時は正直死ぬほど嫌だったけど、でもあの小中で紡いだ片想いの軌跡があれば十分だって、自分に何とか言い聞かせた。”学校”という接点を無くした私はせめて”SNS”で繋がりを持とうと何度も彼の名前を検索した。そしてやっと自分の力で見つける事が出来た彼のアカウント。女の子みたいに可愛い桜のアイコン。今まで話しかけることすら出来なかったのに、フォローリクエストを送ることが出来た。数時間後にフォロバされた時は言葉では言い表せないくらい喜んだ。
時々私のくだらない投稿にいいねを押してくれたりもした。彼からのいいね通知は、いつもスクショしてしまう。あぁ、画面越しに彼とちゃんと接点があるんだぁ…って嬉しくて。高校生になっても大学生になっても彼を好きな気持ちには変わりなかった。中学卒業以来、もうずっと顔も見てないし声も聞いてないのに。胸がはち切れそうになるくらいいつもいつも大好きで……大好きで…大好きで……。
だから───────…
死んだ、なんて…………やめてよ。
今日午前10時30分。ブレーキとアクセルの操作を誤ったことで軽乗用車が歩道に突っ込み、信号待ちをしていた21歳の男性 佐々木夏樹さんが巻き込まれ、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察によりますと佐々木さんは大学に向かうところだったらしく───────…
先週、彼の訃報を耳にした。最近私がSNSにあげた写真…彼、いいねくれてたなぁ。嬉しかったなぁ。そんな歓喜に浸りながら、録画しておいたドラマを見ていた最中での事だった。中学の同級生の子から
「ねぇ、ニュース見た?」
そんなメッセージが送られてきて。何事かと検索したら痛々しい文面が私の大好きな人の名前と共に綴られていた。いつだって私にトキメキを与えてくれていたその苗字と名前を目にした時、トキメキなどとは程遠い動悸がした。そしてまず、思ったのは、
” 嘘 で し ょ ? ”
だった。
彼の訃報を聞いて以来。
私は大学には行けていない。ご飯もろくに喉を通らない。朝から晩まで自室に籠って、ただただ……このベッドに横たわっていた。当然の気の沈みようだった。何年もストーカー並に目で追っていたのだ。口では想っているだけで十分、とか言いながら何度「もし付き合えたら」なんて気持ちの悪い妄想を繰り返しただろう。
…当然だ。
悲しくて当然だ。
涙が止まらなくて当然だ。
20代になって。ふと思ったことがある。
学生時代なんて、思い返せばいつも教室にいた。数歩歩けば誰とでも話せるようなそんな小さな箱に収まってたんだから、ちょっと勇気出して。歩いて。彼の所まで行って。肩をトントンって叩いて。「好き」って伝えればよかった。たった2文字でよかったのに、たった2文字すらも、当時の私は躊躇した。
振られたらどうしよう。もし告白して彼が男友達に面白おかしく言いふらして、からかわれて。私学校で居場所なくしたらどうしよう、とか彼がそんなことする人じゃないって分かってるから好きになってるのにそんなことばっかり考えて私は勇気が出せなかった。
もし私があの頃勇気を出して告白して、仮にうまくいってたとしたら運命ちょっと変わったのかな。なんてここ数日はそんな可能性ばかり考えていた。事故があったあの日あの時間、もし朝から私と通話してて、家を出る時間が少しずれて、彼があの場所に向かう時間が少しだけずれて。そしたら運命が変わって…、彼は…今もこの世界のどこかで生きていられたのだろうか。
徐々に夢の記憶が脳内を支配していく。
彼がサッカーをやってる姿。
席替えで前後になった時の喜び。
全部私が経験したこと。夢だけど夢じゃない記憶。ただ見ていただけなのに、幸せで溢れていた。そう。ただ……見ていただけだったのだ。あの頃の自分は───────…
あーぁ…、もう二度と伝えられない今になって、後悔しても遅いのに…。
拳を強く握って、もう一度仰向けに横たわった。
時刻は午前二時。丑三つ時。
私はもう一度眠りについた。
───────それから夢を見た。
かっこいい。かっこいい。かっこいい。
気がつくと、そんな単調なセリフを胸に抱く中学2年の私が学校の校庭にいた。
ただ、好きな人を少し遠くから見ているだけの日々を送っていた。
「夏樹! パス!」
私は願う。
入れ……! 入れ……!!と。
もちろん入ることは、知っている。
「夏樹ー! ナイスシュート!」
「パスが良かったんだよ」とチームメイトに言う彼の姿が、ぼんやりと滲む。
本来なら私はここで教室に戻る。すると友達のユキちゃんがやって来て、「もうー、好きって伝えればいいのにー」と毎度の如く告白を促してくる。そうして私は…、口癖のようにこう思うんだ。
私は彼を密かに想っているだけで十分なのだ
と。
……そんな訳、ないのにね。
鼻の奥がツン、とした。当たり前のように生きている彼の姿に、溢れ出した涙が収まらなかった。辛すぎて、苦しすぎて、悔しすぎて、立っていられなくなって私はその場にしゃがみこんだ。
「うぅー…」
人目も気にせず嗚咽がポロポロと溢れていく。
想ってるだけで十分な訳ないよ。本当は違うよ…。……付き合いたかった。平日だけじゃなくて休みの日も会いたかった。どこかへ遊びに行きたかった。その顔面を誰よりも近くで見ていられる場所にいたかった。大好きだった。
「……っ」
はっ、と我に返る。
ダメだ……泣いてちゃダメだ…。
泣き喚くそんな自分に鞭打って立ち上がった。夢の中でも後悔するなんて、嫌だ、と心が死ぬほど叫んでいた。私は涙を拭いながら昇降口に移動する。今までにないくらい心臓が跳ねる。きっと現実で告白することを選んでいたのなら同じように胸を弾ませていたのだろう。今だけの……夢だけの特別な感情に私はひたすら身を任せた。
下駄箱に身体を預けて、彼が来るのを待つ。緊張の渦に巻かれながら、私はしみじみと考えるのであった。
人には、任意で「好き」という想いを抱くことが出来る。そしてそれを、任意で相手に伝えることも出来る。
あくまでも「任意」
やってもやらなくても。どっちでもいいことなんだよね。
20歳の時。
成人式で久しぶりに会った友達が来月結婚するんだ、ってとても幸せそうに教えてくれたあの時。「おめでとう」と、口にする傍ら、私はふいに考えてしまった。
『夏樹、今度結婚するんだって』
私もいつか人伝いに彼の”幸せ”を耳にする日が来るのだろうか、と。そしたらきっと私は少しだけ胸を軋ませて。
『えっ!? マジ!?』
強がって笑顔を浮かべながら、偶然彼の結婚を耳にした、ただの”第三者”になるんだろうなと。
……正直そんなシチュエーションは考えるだけで吐き気がした。彼が私じゃない誰かのものになるとか、たとえ妄想でも嫌で嫌でたまらなくなったのだ。
でもそんなシチュエーションに、きっと私はまっしぐらだったことだろう。21歳になっても長年抱いてきた気持ちを伝えなかったのは紛れもなく私だ……。
「好き」は、当人は死ぬまで一生持っていられる感情かもしれない。でも
「好きを伝えたい相手」は、ある日突然、居なくなってしまうかもしれない。
そんな悲しい知恵を学ぶことになるなんて。21歳で知ることになるなんて思ってもみなかった。知りたくなかった。
あっ…
その時。前方から彼がやってきて私は背筋を伸ばした。当時何処へ行くにも必ず持ち歩いていた手鏡はあの頃のまま胸ポケットに入っていたのでそれで身だしなみを整えた。
伝えなきゃ。声……掛けなきゃ。
「てか今度の週末遊び行こーぜ」
「おーいいなー」
今伝えなきゃ、後に後悔することを私は知っている。もう、ここでしか伝えられないことを、悲しいことに知ってしまっているのだ。
「……っ、夏樹くん!!!」
声を張り上げた。多分この先二度と出すことのない勇気を、ありったけ出して今までずっと躊躇ってきた1歩を踏み出す。
夢だ、って分かってる。でも。
伝えたかった───────…
パチリ、と目が会う。彼の口から私の名前が溢れた。
夢のようだった……
「……広瀬?」
当然だった。大好きな人に名前を呼ばれちゃ心臓もこうなる。大好きな人に見つめられたら……、こうなるに決まってる。彼が私を見ていた。その瞳は紛れもなくクラスメイトの女子Fぐらいのモブキャラを見つめる瞳だったと思う。彼にとって私という存在はきっとその程度のもの。でも私にとっての彼は、いないと物語が一切進んでくれないヒーローポジションなんだ。
額から輪郭を伝って顎先に汗が流れていく。
セミの鳴き声がダイレクトに鼓膜に直撃する。
夏の涼やかな匂いが鼻腔を撫でる。
そして視界の先には私を見つめる大好きな人の姿。
私を取り囲む環境全てが、あの日あの時間に私を誘ってくれていた。歯止めをかけるものなんて、今この瞬間……もう何もない。
「……好き」
ずーっと抱いてきた特別な気持ちをこの時、生まれて初めて口にした。でも彼のところまで上手く届かなかった気がして。だからもう一度。肺に大きく息を貯めて。声を張り上げた。
「ずっと…っ、大好きでした……っ!!」
違う。これじゃない。口にしてすぐ、私は全力で首を振って否定した。
「大好きです!!」
過去形になんて、したくない恋だった。実ろうが実らまいが、ずっとしていたい恋だった。彼がこの世に居ようが居まいが、過去形にしない絶対的自信が私にはあった。
「大好き」がドバッ、と一気に洪水のように溢れていく。
「私の初恋は夏樹くんで、ちょっと気持ち悪いって思われちゃうかもだけど、休み時間も授業中もずっと目で追っちゃうくらい夏樹くんのことが好きで…っ」
息が続かない。1度言葉を止めてもう1度息を吸い込む。その感情はとても一息に収まりきらないほどだった。
「1度も話したことないのに、すごく…すごくすごく好きで…っ、」
口にしてしまえば最後。
はなからそれはシャボン玉に封じ込められた想いであったかのように、少しの刺激で簡単に壊れて、歯止めが効かなくって、溢れていく。そのくらい脆い箱の中でずっと、培ってきた私の大切な大切な感情だった。世界中探したってどこにも無いかけがえのない感情だ。
「何が…どこがっ、そんなに好きなんだろう、ってよく考えてた…。そしたら数え切れないくらい好きになる要素が見つかって…」
どこかゆったりと毎日が流れていた学生時代。
あの頃、私は毎日彼に夢中で。彼を想わない日はなかった。一生分の恋心を私は常に、彼に注いでいた。喋ったことないのにキモいよね。いきなりモブキャラがでしゃばっちゃってびっくりしたよね。だけどね……
モブキャラだって、恋するんだよ。
「何度も何度も、”あぁ…私は夏樹くんがどうしようもなく好きなんだ” って自覚させられたの……」
喉の奥がヒリヒリと痛かった。この夢が覚めれば彼がいない現実がある。これは、もう二度と叶わない恋。でも私は、”あなたに恋した私”を……、生涯誇りに思う。恋をすることの喜びを教えてくれたのは紛れもなく夏樹くんなのだから───────…
「だから…っ、だから……」
「広瀬」
紡ぎかけた言葉を彼が制した。いつの間にか地面に張り付いていた私の視線がゆっくりと上がる。視線の先で私を見つめる夏樹くんは……
「サンキューな」
白い歯を出して、ニッと。世界で1番かっこよく、優しく、穏やかに、微笑んでくれた。
それは私の網膜に、すでに焼き付きまくっているどの夏樹くんとも一致しない笑顔だった。私の為だけに、作ってくれた表情に他ならなかった。
────私の初恋は、今宵そうして終止符が打たれた。
けたたましいアラームで目が覚めた翌朝。
頬を伝った涙を、
強く、強く、拭った。
” 前を向こう ”
明日は大学に行こう。行ける気がする。
彼を好きになった自分を誇りに思おう。
この恋心を一生大切にしよう。
そして。
もしまたあの夢を見ることがあれば、何度でも伝えよう。
君に「好きだ」と───────。
【終】