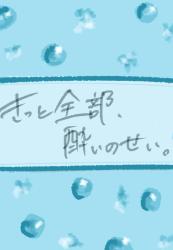20時を過ぎた夏の公園は、うるさいくらいに鈴虫が泣きわめいていた。10歳未満は使用禁止と注意書きされているシーソーに22歳の私が腰掛ける。ギー、と音を立てて向こう側が宙に浮いた。
やだ。これじゃ私の体重が重いみたいじゃない。
そんな憤りがスっ、と浮かぶけど…まぁいいか。誰もいないし。そう思って構うことはなかった。あまりに静かすぎて、実は今この世界に私だけしかいないんじゃないか、なんてありもしない妄想で思考を散らそうと試みるけど無理だった。
「ぐすんっ…」
鈴虫の鳴き声に私の鼻をすする音が混じった。今の今まで頑張って堪えてたのに。1度涙が溢れてしまえば最後。とうとう嗚咽まで顔を出し始め、私は1人……涙を流していた。
最初のうちは手の甲で涙を拭ってたけどそれも疲れて、今はただ頬を伝って地面に吸収されていくばかりの雫の感覚を徹底的に無視していた。私の涙で水たまりが出来るかな、と一瞬思ったけどそこまでの水量が私の涙腺から出てくることは無さそう。小雨程度のシミが地面に広がっていくばかりだった。
あーあ。どこで間違えちゃったんだろう。
返却された答案用紙。赤くチェックを入れられたところを執念深く考え直すかのような作業が無意識のうちに始まった。
位置情報アプリを交換したところから、かな。
そもそも想いを伝えたところから、かな。
無数に浮かぶ原因に顔を歪めた。
────遡ること6年前の春。
当時私は中学2年で、「第2ボタンもらいに行こうよ!」という誘いを受け、友達のみっちゃんと一緒に校門前でその日卒業を迎えた先輩達を出待ちしていた。友達は部活の先輩に同性の”推し”という存在がいるみたいで、その先輩が目当てらしかった。
私も私で、せっかく第2ボタンをねだってもいいのならねだりたい相手がいた。
それが中条先輩。
受験の時に校舎で迷子になっていた時に助けて貰って以来、私がずっと密かに想いを寄せていた人だった。先輩は明るくていつも元気でクラスのムードメーカー的存在。控えめに言って太陽のような人だと思う。交友関係も広くて、男女平等に接してくれる。
他学年だから廊下ですれ違うくらいしか接点はなかったけど、すれ違う度に先輩は「もう迷子になるなよー」って無邪気に私をからかってきた。迷子になった受験の日の私に、何度感謝したことか。あれがなかったら、きっとすれ違ったとて先輩は私を知らないし、私も先輩を好きになることはなかったと思う。
「あっ! 3年生来たよ!」
興奮気味のみっちゃんの声に顔を上げる。下級生からの花束を抱えた3年生達がチラホラとこちらへ向かってやって来ていた。
「飛鳥、私ちょっと行ってくるね!」
「うん」
みっちゃんは目当ての人物を見つけたみたいでタタっ、と走っていった。
「先輩! 第2ボタンください!」
「しょうがないなー」
なんとも和やかなやり取りが微かにこちらにまで聞こえてくる。残された私は先輩の姿を探した。
「あっ……」
手に力が入る。
先輩だ……!
分かっていたことだったけど、男友達と列を成して歩いてきている。邪魔しちゃ悪いかな……。そんな遠慮にやられそうになるけど、これで会うのは最後になってしまうかもしれない。そう思ったら必然的に勇気が湧いてきた。
「絶対連絡しろよー」
「分かってる、って」
「あの……! 先輩…っ」
震える足を1歩踏み出して、先輩の目の前に。いつもラフな感じなのに今日は髪型がビシっ、と決まってていつにも増してかっこよかった。
「おぉ! 飛鳥じゃん! わり。先行っててー」
「おぉー」
先輩は一緒にいた友達に先に行くように促して、私と2人だけの時間を作ってくれた。
「もう迷子になるなよー」
嬉しそうに頬を緩めて私の頭の上に手のひらを置く先輩。
…その笑顔が大好きだった。
次の瞬間。
スっ、と口から溢れ出したのは…
” 第 2 ボ タ ン く だ さ い ! ”
じゃなくて、
「好きです…っ」
もっとストレートで真っ直ぐそうな言葉だった。
「えっ……?」
さっきまでの笑顔のまま顔を硬直させる先輩。ゆっくりと私の頭から重みが去っていく。
「ずっと好きでした…、付き合ってください」
ガバッ! と頭を下げた。スカートが引きちぎれそうなぐらいギュッ、と握る。
やば。言っちゃった。
下唇を噛み締めて私はただ先輩の返事を待った。……正直振られるつもりだった。玉砕覚悟でダメ元で告白したようなものだった。だから……
「うん、いいよ」
そんな返事が返ってくるなんて夢にも思わなくて私は顔を上げて目を見開いた。
「え……っ」
「なんだよー、そっちから告ったんだろ?」
「そう……ですけど…」
「ん。よろしくな」
ニカッ、と眩しい笑顔を浮かべて、私を見つめる先輩。
「はい!!」
あとから聞けば先輩も私のことが前々から気になっていたみたいで卒業式の数週間後、卒アルを取りに学校に訪れる予定があったらしく、そこで告白するつもりだったらしい。
「俺から言おうと思ったのに、先越されちゃった」と、不貞腐れる姿はまるで子供みたいだった。
先輩との交際は夢みたいで。幸せだった。
私は受験の年だったけど、恋愛がネックになって勉強に身が入らない、なんてことは絶対になかったし、むしろ先輩と同じ大学に行く為に塾に通ったり過去問を解いたり、まだ夏休みにも入ってない時期から受験勉強に励んでいた。
デートの時はとびっきり可愛くお化粧して、オシャレして、どうやったら先輩にもっと好きになってもらえるかな、って考えたりして。毎日が楽しくて浮ついててキラキラしてた。
でも、交際して1年が経った頃から次第に心のきしみは増えていったように思う。
週に何度かしている通話は交際当初から続いてるものだった。でもサークルの方がちょっと忙しくなってきたみたいで、断られがちになった。それだけならまだ良かったけど朝からの1日デートの予定を半日にして欲しい、って頼まれたり。そういうことが増えていった。
大学生だし、きっと忙しいんだ、って言い聞かせてたけど、少しずつ。少しずつ。でも着実に歪みは大きくなっていったように思う。決定的なのは、多分先輩がサークルで沖縄に旅行に行くんだ、って話をされた時。すごく楽しそうに話してくれたけど、水を差すみたいに私は聞いてしまった。
「それって、女の子いるの?」って。
それで「いるよ」って返事が来ることは分かってたし、別にいるからと言って誠実な先輩がその子とどうこうなる、って本気で思ってた訳じゃない。でも…つい言ってしまった。「行かないで」と。もはやワガママに近い束縛だった。
数日後。先輩は沖縄旅行に行った。
もちろん女の子も交えたサークルの繋がりで。
私の「行かないで」には応じてくれなかった。少し困ったように眉を下げて「もう行く、って返事しちゃったよ…」と言われただけだった。
そんな出来事を経て、私は少しずつ気持ち悪くなっていった。
彼のインスタのストーリーが更新される度ストーカーのように何度も覗いて。たった3秒程度の動画でも何度も何度も繰り返し見て。女の子がいないか確認したりするのが癖になった。
ある時はちょっと映りこんだだけのただの通行人であろう女の子にまで嫉妬する始末。たとえ女の子が彼のそばにいたとしても彼女が閲覧出来る場所で先輩がその子の存在をひけらかす訳ないのにね。
それからも些細な雑談の中で今度友達とどこどこ行くんだ、って話をされると口をついて「それって女の子いるの?」って反射的に聞いちゃったり、「いる」と言われれば、「行かないで」と言ってみたり。「友達だし大丈夫だよ」と言われれば、「分かった」と引き下がって。いや。引き下がったフリをしてた。
だからやっぱり不安は拭えなくて。
先輩のSNSや位置情報アプリを逐一気にしたりしてた。相手のいる場所や行動を知ることが出来るツールは不安を拭えるかもしれないけど1周回ればそれは知っていないと不安になりうるものだった。
”好き”が”執着”に変わっていっているのは誰が見ても明白だった。
─────そうして今日に至る。
今さっき、先輩に呼び出されて振られてしまった。
この公園で。
『別れよう』
大好きな人の声でその言葉が私宛に紡がれている、だなんて信じたくなかった。受け入れたくなかった。でも信じて受け入れたからこそ、私は今この公園のシーソーに1人で股がっている。
「こんなはずじゃなかったんだけどな…」
涙混じりにポツリ、と呟く。こんなめんどくさくて重い女の子になるはずじゃなかった。言い訳じゃないけど”好き”が増す度、比例して”嫉妬”も溢れてきて。本当に、どうしようもなかったんだ。自分でも自分が制御出来なくなってた。
無論それは私が先輩を好きだからこそ、の暴走のようなものだけど。でもそれもなんだか取ってつけたような言い訳としか思えなかった。
「別れたくなかったな…」
夜の闇に吸収されていくその本音は情けなくて本当に弱弱しいものだった。別れを拒めば、きっと優しい先輩は考え直してくれたかもしれない。でも、もう苦しめたくなかった。
「はぁ…どうしよっかな」
ひとしきり涙を流してスマホで時間を確認すれば22時を回っていた。
そろそろ帰ろう。
一瞬そう思ったけど歯止めがかかる。
そうだ、散々泣いたんだった。どうしよう。こんなに赤く腫れた目じゃ、家に帰れない。きっとお母さんに何か気付かれる。こんなみっともなくて惨めな姿見られたくなかった。
帰ろうとして少しだけ浮かした腰がまた重くなる。ギー、とシーソーがまた少しこちらへ傾く。
────その時だった。
「ほら、言わんこっちゃない」
突然降りかかるように聞こえたその声に、私は振り返る。そこには近所に住む幼馴染の涼太がいた。白いパーカーにジーンズ。片手にはすぐそこのコンビニ袋が握られている。どうせ小腹がすいた、とかで肉まんでも求めて買い物に行ってたんだろう。ほら。肉まんの香りがほのかに鼻腔に届き始める。
「あいつとは最初から合わないと思ってたよ。俺は」
今日私が先輩に振られたことも。最近上手くいっていなかったことも何もかも分かったようにサラッと、そう言った彼は「よいしょ」とシーソーに跨った。
私の身体が限界まで宙に浮く。向こうの方が体重が重いらしい。当然か。背格好も肉付きも何もかも私の方が劣っている。
「なによ……」
不貞腐れたように私はボヤく。すると彼が場違いに意地悪な笑顔を浮かべた。
「どうせ振られたんだろ?」
「…っ」
図星過ぎて、言葉を失った。
「なんで分かるの」
「あ、当たった?」
当てずっぽうだったなら、上手いこと交わしとけば良かった。そう後悔してももう遅い。悔しくてシーソーの手すりをギュッ、と握る。夜風に当てられて少しだけ冷静を取り戻した心を掻き乱された気分だった。
「私今めっちゃ傷ついてんだけど」
「見りゃ分かる」
「じゃあなんでそんなひどい言い方すんの」
先輩と付き合ったって言ったら、涼太「良かったな」って喜んでくれたじゃん。あいつとは最初から合わないと思ってたよ。って何……? 嘘……? 堰が切れたように私の思いは溢れ出した。
「私今傷心してるの! 失恋して傷心してるの! あー、あんたみたいなやつじゃなくて優しく慰めてくれるような素敵な男の人が今ここにいてくれればいいのに!」
嫌味ったらしく、存分に悪意を投げつける。むしゃくしゃして。そして頬がくすぐったい。涙の跡が何重にも重なって、頬に積み重なる。強く叫んだからか、喉の奥がヒリヒリする。
悲しすぎて。悲しすぎて。心の中にぽっかり空いた穴に虚無だけが溜まっていく。
「ぐすん……っ、どうしたら良かったの…嫉妬しちゃうだもんしょうがないじゃん…女の子いるとこ行って欲しくないんだもん、しょうがないじゃん…あんたに…っ、なにが分かんの……っ」
情緒不安定とはまさに今の私のことだろう。感情がぐちゃぐちゃになっていく。
先輩が大好きだった。
先輩ことが好きな自分も大好きだった。
でもだんだん大好きじゃなくなった。
付き合いたての感じた胸のときめきがここ数ヶ月どこにも見当たらないないのが何よりも証拠だった。
「分かんねぇよ、何も」
ギー、とシーソーが傾く。宙ぶらりんだった足が地面にゆっくりと着地した。帰るのかな。涼太だってきっと今ビックリして呆れてるに違いない。ドン引き案件だ。幼馴染がこんな束縛女メンヘラ女だったなんて。
────そう思った矢先のこと。
「でも、お前の失恋を心の底から喜んでる奴ならここにいる」
声は真横から。いつの間にか涼太は場所を移動して、すぐそばに居た。彼の言葉が遅れて脳内へやってくる。
「は……はぁ?」
乾いた笑みがこぼれ落ちた。
「意味分かんない。自分が何言ってるか分かってる?」
「分かってる」
あまりに飄々と返されて、私は苛立ちが抑えきれなかった。人の不幸を喜ぶとか最悪すぎる。
「そのドSの思考回路、どうにかした方がいいよ」
逃げるようにシーソーから降りて、立ち上がって、彼に背を向けた。
「もう帰る。二度と話しかけてこないで」
もう、こんな奴知らない!
幼馴染なんて今日限りなんだから!
全身から湧き上がる怒りを全て、重力のまま足に垂れ流す。怪獣のように足を踏み鳴らしながら私はその場を後にした。
「……何よ」
そこまで鈍感じゃない。
今が夜で良かった。
ポツリとそう呟いた私の顔面はきっとすごく赤くなってるに違いないから。
【終】
やだ。これじゃ私の体重が重いみたいじゃない。
そんな憤りがスっ、と浮かぶけど…まぁいいか。誰もいないし。そう思って構うことはなかった。あまりに静かすぎて、実は今この世界に私だけしかいないんじゃないか、なんてありもしない妄想で思考を散らそうと試みるけど無理だった。
「ぐすんっ…」
鈴虫の鳴き声に私の鼻をすする音が混じった。今の今まで頑張って堪えてたのに。1度涙が溢れてしまえば最後。とうとう嗚咽まで顔を出し始め、私は1人……涙を流していた。
最初のうちは手の甲で涙を拭ってたけどそれも疲れて、今はただ頬を伝って地面に吸収されていくばかりの雫の感覚を徹底的に無視していた。私の涙で水たまりが出来るかな、と一瞬思ったけどそこまでの水量が私の涙腺から出てくることは無さそう。小雨程度のシミが地面に広がっていくばかりだった。
あーあ。どこで間違えちゃったんだろう。
返却された答案用紙。赤くチェックを入れられたところを執念深く考え直すかのような作業が無意識のうちに始まった。
位置情報アプリを交換したところから、かな。
そもそも想いを伝えたところから、かな。
無数に浮かぶ原因に顔を歪めた。
────遡ること6年前の春。
当時私は中学2年で、「第2ボタンもらいに行こうよ!」という誘いを受け、友達のみっちゃんと一緒に校門前でその日卒業を迎えた先輩達を出待ちしていた。友達は部活の先輩に同性の”推し”という存在がいるみたいで、その先輩が目当てらしかった。
私も私で、せっかく第2ボタンをねだってもいいのならねだりたい相手がいた。
それが中条先輩。
受験の時に校舎で迷子になっていた時に助けて貰って以来、私がずっと密かに想いを寄せていた人だった。先輩は明るくていつも元気でクラスのムードメーカー的存在。控えめに言って太陽のような人だと思う。交友関係も広くて、男女平等に接してくれる。
他学年だから廊下ですれ違うくらいしか接点はなかったけど、すれ違う度に先輩は「もう迷子になるなよー」って無邪気に私をからかってきた。迷子になった受験の日の私に、何度感謝したことか。あれがなかったら、きっとすれ違ったとて先輩は私を知らないし、私も先輩を好きになることはなかったと思う。
「あっ! 3年生来たよ!」
興奮気味のみっちゃんの声に顔を上げる。下級生からの花束を抱えた3年生達がチラホラとこちらへ向かってやって来ていた。
「飛鳥、私ちょっと行ってくるね!」
「うん」
みっちゃんは目当ての人物を見つけたみたいでタタっ、と走っていった。
「先輩! 第2ボタンください!」
「しょうがないなー」
なんとも和やかなやり取りが微かにこちらにまで聞こえてくる。残された私は先輩の姿を探した。
「あっ……」
手に力が入る。
先輩だ……!
分かっていたことだったけど、男友達と列を成して歩いてきている。邪魔しちゃ悪いかな……。そんな遠慮にやられそうになるけど、これで会うのは最後になってしまうかもしれない。そう思ったら必然的に勇気が湧いてきた。
「絶対連絡しろよー」
「分かってる、って」
「あの……! 先輩…っ」
震える足を1歩踏み出して、先輩の目の前に。いつもラフな感じなのに今日は髪型がビシっ、と決まってていつにも増してかっこよかった。
「おぉ! 飛鳥じゃん! わり。先行っててー」
「おぉー」
先輩は一緒にいた友達に先に行くように促して、私と2人だけの時間を作ってくれた。
「もう迷子になるなよー」
嬉しそうに頬を緩めて私の頭の上に手のひらを置く先輩。
…その笑顔が大好きだった。
次の瞬間。
スっ、と口から溢れ出したのは…
” 第 2 ボ タ ン く だ さ い ! ”
じゃなくて、
「好きです…っ」
もっとストレートで真っ直ぐそうな言葉だった。
「えっ……?」
さっきまでの笑顔のまま顔を硬直させる先輩。ゆっくりと私の頭から重みが去っていく。
「ずっと好きでした…、付き合ってください」
ガバッ! と頭を下げた。スカートが引きちぎれそうなぐらいギュッ、と握る。
やば。言っちゃった。
下唇を噛み締めて私はただ先輩の返事を待った。……正直振られるつもりだった。玉砕覚悟でダメ元で告白したようなものだった。だから……
「うん、いいよ」
そんな返事が返ってくるなんて夢にも思わなくて私は顔を上げて目を見開いた。
「え……っ」
「なんだよー、そっちから告ったんだろ?」
「そう……ですけど…」
「ん。よろしくな」
ニカッ、と眩しい笑顔を浮かべて、私を見つめる先輩。
「はい!!」
あとから聞けば先輩も私のことが前々から気になっていたみたいで卒業式の数週間後、卒アルを取りに学校に訪れる予定があったらしく、そこで告白するつもりだったらしい。
「俺から言おうと思ったのに、先越されちゃった」と、不貞腐れる姿はまるで子供みたいだった。
先輩との交際は夢みたいで。幸せだった。
私は受験の年だったけど、恋愛がネックになって勉強に身が入らない、なんてことは絶対になかったし、むしろ先輩と同じ大学に行く為に塾に通ったり過去問を解いたり、まだ夏休みにも入ってない時期から受験勉強に励んでいた。
デートの時はとびっきり可愛くお化粧して、オシャレして、どうやったら先輩にもっと好きになってもらえるかな、って考えたりして。毎日が楽しくて浮ついててキラキラしてた。
でも、交際して1年が経った頃から次第に心のきしみは増えていったように思う。
週に何度かしている通話は交際当初から続いてるものだった。でもサークルの方がちょっと忙しくなってきたみたいで、断られがちになった。それだけならまだ良かったけど朝からの1日デートの予定を半日にして欲しい、って頼まれたり。そういうことが増えていった。
大学生だし、きっと忙しいんだ、って言い聞かせてたけど、少しずつ。少しずつ。でも着実に歪みは大きくなっていったように思う。決定的なのは、多分先輩がサークルで沖縄に旅行に行くんだ、って話をされた時。すごく楽しそうに話してくれたけど、水を差すみたいに私は聞いてしまった。
「それって、女の子いるの?」って。
それで「いるよ」って返事が来ることは分かってたし、別にいるからと言って誠実な先輩がその子とどうこうなる、って本気で思ってた訳じゃない。でも…つい言ってしまった。「行かないで」と。もはやワガママに近い束縛だった。
数日後。先輩は沖縄旅行に行った。
もちろん女の子も交えたサークルの繋がりで。
私の「行かないで」には応じてくれなかった。少し困ったように眉を下げて「もう行く、って返事しちゃったよ…」と言われただけだった。
そんな出来事を経て、私は少しずつ気持ち悪くなっていった。
彼のインスタのストーリーが更新される度ストーカーのように何度も覗いて。たった3秒程度の動画でも何度も何度も繰り返し見て。女の子がいないか確認したりするのが癖になった。
ある時はちょっと映りこんだだけのただの通行人であろう女の子にまで嫉妬する始末。たとえ女の子が彼のそばにいたとしても彼女が閲覧出来る場所で先輩がその子の存在をひけらかす訳ないのにね。
それからも些細な雑談の中で今度友達とどこどこ行くんだ、って話をされると口をついて「それって女の子いるの?」って反射的に聞いちゃったり、「いる」と言われれば、「行かないで」と言ってみたり。「友達だし大丈夫だよ」と言われれば、「分かった」と引き下がって。いや。引き下がったフリをしてた。
だからやっぱり不安は拭えなくて。
先輩のSNSや位置情報アプリを逐一気にしたりしてた。相手のいる場所や行動を知ることが出来るツールは不安を拭えるかもしれないけど1周回ればそれは知っていないと不安になりうるものだった。
”好き”が”執着”に変わっていっているのは誰が見ても明白だった。
─────そうして今日に至る。
今さっき、先輩に呼び出されて振られてしまった。
この公園で。
『別れよう』
大好きな人の声でその言葉が私宛に紡がれている、だなんて信じたくなかった。受け入れたくなかった。でも信じて受け入れたからこそ、私は今この公園のシーソーに1人で股がっている。
「こんなはずじゃなかったんだけどな…」
涙混じりにポツリ、と呟く。こんなめんどくさくて重い女の子になるはずじゃなかった。言い訳じゃないけど”好き”が増す度、比例して”嫉妬”も溢れてきて。本当に、どうしようもなかったんだ。自分でも自分が制御出来なくなってた。
無論それは私が先輩を好きだからこそ、の暴走のようなものだけど。でもそれもなんだか取ってつけたような言い訳としか思えなかった。
「別れたくなかったな…」
夜の闇に吸収されていくその本音は情けなくて本当に弱弱しいものだった。別れを拒めば、きっと優しい先輩は考え直してくれたかもしれない。でも、もう苦しめたくなかった。
「はぁ…どうしよっかな」
ひとしきり涙を流してスマホで時間を確認すれば22時を回っていた。
そろそろ帰ろう。
一瞬そう思ったけど歯止めがかかる。
そうだ、散々泣いたんだった。どうしよう。こんなに赤く腫れた目じゃ、家に帰れない。きっとお母さんに何か気付かれる。こんなみっともなくて惨めな姿見られたくなかった。
帰ろうとして少しだけ浮かした腰がまた重くなる。ギー、とシーソーがまた少しこちらへ傾く。
────その時だった。
「ほら、言わんこっちゃない」
突然降りかかるように聞こえたその声に、私は振り返る。そこには近所に住む幼馴染の涼太がいた。白いパーカーにジーンズ。片手にはすぐそこのコンビニ袋が握られている。どうせ小腹がすいた、とかで肉まんでも求めて買い物に行ってたんだろう。ほら。肉まんの香りがほのかに鼻腔に届き始める。
「あいつとは最初から合わないと思ってたよ。俺は」
今日私が先輩に振られたことも。最近上手くいっていなかったことも何もかも分かったようにサラッと、そう言った彼は「よいしょ」とシーソーに跨った。
私の身体が限界まで宙に浮く。向こうの方が体重が重いらしい。当然か。背格好も肉付きも何もかも私の方が劣っている。
「なによ……」
不貞腐れたように私はボヤく。すると彼が場違いに意地悪な笑顔を浮かべた。
「どうせ振られたんだろ?」
「…っ」
図星過ぎて、言葉を失った。
「なんで分かるの」
「あ、当たった?」
当てずっぽうだったなら、上手いこと交わしとけば良かった。そう後悔してももう遅い。悔しくてシーソーの手すりをギュッ、と握る。夜風に当てられて少しだけ冷静を取り戻した心を掻き乱された気分だった。
「私今めっちゃ傷ついてんだけど」
「見りゃ分かる」
「じゃあなんでそんなひどい言い方すんの」
先輩と付き合ったって言ったら、涼太「良かったな」って喜んでくれたじゃん。あいつとは最初から合わないと思ってたよ。って何……? 嘘……? 堰が切れたように私の思いは溢れ出した。
「私今傷心してるの! 失恋して傷心してるの! あー、あんたみたいなやつじゃなくて優しく慰めてくれるような素敵な男の人が今ここにいてくれればいいのに!」
嫌味ったらしく、存分に悪意を投げつける。むしゃくしゃして。そして頬がくすぐったい。涙の跡が何重にも重なって、頬に積み重なる。強く叫んだからか、喉の奥がヒリヒリする。
悲しすぎて。悲しすぎて。心の中にぽっかり空いた穴に虚無だけが溜まっていく。
「ぐすん……っ、どうしたら良かったの…嫉妬しちゃうだもんしょうがないじゃん…女の子いるとこ行って欲しくないんだもん、しょうがないじゃん…あんたに…っ、なにが分かんの……っ」
情緒不安定とはまさに今の私のことだろう。感情がぐちゃぐちゃになっていく。
先輩が大好きだった。
先輩ことが好きな自分も大好きだった。
でもだんだん大好きじゃなくなった。
付き合いたての感じた胸のときめきがここ数ヶ月どこにも見当たらないないのが何よりも証拠だった。
「分かんねぇよ、何も」
ギー、とシーソーが傾く。宙ぶらりんだった足が地面にゆっくりと着地した。帰るのかな。涼太だってきっと今ビックリして呆れてるに違いない。ドン引き案件だ。幼馴染がこんな束縛女メンヘラ女だったなんて。
────そう思った矢先のこと。
「でも、お前の失恋を心の底から喜んでる奴ならここにいる」
声は真横から。いつの間にか涼太は場所を移動して、すぐそばに居た。彼の言葉が遅れて脳内へやってくる。
「は……はぁ?」
乾いた笑みがこぼれ落ちた。
「意味分かんない。自分が何言ってるか分かってる?」
「分かってる」
あまりに飄々と返されて、私は苛立ちが抑えきれなかった。人の不幸を喜ぶとか最悪すぎる。
「そのドSの思考回路、どうにかした方がいいよ」
逃げるようにシーソーから降りて、立ち上がって、彼に背を向けた。
「もう帰る。二度と話しかけてこないで」
もう、こんな奴知らない!
幼馴染なんて今日限りなんだから!
全身から湧き上がる怒りを全て、重力のまま足に垂れ流す。怪獣のように足を踏み鳴らしながら私はその場を後にした。
「……何よ」
そこまで鈍感じゃない。
今が夜で良かった。
ポツリとそう呟いた私の顔面はきっとすごく赤くなってるに違いないから。
【終】