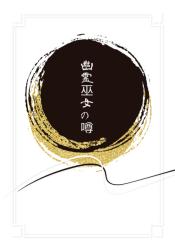「お邪魔します」
「……しまーす」
まだ少し緊張気味の直樹は涼佑の後ろで、辛うじて挨拶のようなものを口にする。柄にもなく、緊張してるのかと思うと、涼佑は何だか少しだけ面白く感じた。奥から真奈美が静かに歩いて来て、「どうぞ」とやはり無表情で上がるよう促した。それに答えるようにもう一度「お邪魔します」と小さく言って靴を脱ぎ、そのまま二人は彼女について行く。少し歩くと、真奈美が何かに気が付いたように「あ」と零して足を止め、振り返る。
「飲み物、麦茶しか無いんだけど」
「え? あ、だいじょぶ」
「そう」
それだけで会話を切ると、真奈美はまた少し歩いてから「あ」と言って振り返った。
「お菓子、甘いのしか無いの」
「だ、だいじょぶ。な? 直樹」
「あ、ああ。そんなの、全然!」
「そう」
それだけ言うとまた歩き出す。そして、また「あ」と言って真奈美は振り返る。毎回申し訳なさそうに僅かに眉を寄せている表情で断りを入れてくるので、涼佑達の方が却って恐縮していた。
「私の部屋、座布団二枚しか無くて……」
「分かった。分かったから、青谷。おもてなししてくれるのは嬉しいけど、オレらそういうの全然気にしないから。もう全部大丈夫だから」
「そうなの? でも……」
「もう本当、そんな気、遣わなくていいから。終わったら、すぐ帰るし」
そう言うと、真奈美は意外そうに「え!?」と一瞬驚き、少し困った顔をして微かに俯く。予想外の反応に、今度は涼佑達が少々驚く番だった。
「夕飯は食べていかないの? 今日、その、友達が来るから、少し多めに作ろうと思ってて……」
少し恥ずかしそうにもじもじしながら言う真奈美は、いつも涼佑が見かけるミステリアスな高嶺の花ではなく、普通の女の子だ。可愛らしいとは思うけど、やはりそれ以上の感情は湧いてこないことに涼佑が自身に対して密かに失望していると、その背後にいる直樹は明らかに真奈美を意識していますという顔つきで「あ、そうなん? じ、じゃあ、しょうがないから食べてくか。な? 涼佑」とわざわざ涼佑の隣に来てまで目配せしてきた。その行動に苦笑を零して、涼佑は気を利かせることにした。
「じゃあ、お言葉に甘えて。というか、夕飯、青谷が作ってるんだ」
「私の両親、共働きで帰りが遅いから。もうすぐ祖母がデイサービスから帰って来るし、夕飯一緒になっちゃうんだけど、大丈夫?」
「うん、全然。むしろ、オレらがいていいの?」
「うん。おばあちゃん、お客さん好きだから」
思わず零したのだろう。学校にいる時とは違う、私生活の彼女が顔を覗かせたような優しい笑みに、涼佑はちょっと意外だなと思った。青谷ってそういう顔するんだ、と新たな一面を見て感慨深いような気がした。自分の表情に真奈美自身も気付いたのか、はっとした顔をして慌てて「こっち」と二階へ続く階段を登り始める。恥ずかしかったのか、いきなり早足になった真奈美の後を涼佑達も同じように早足で追いかけた。
二階に続く階段を上がってすぐの部屋が彼女のもののようで、階段を上がりきった真奈美はドアを開ける。中には既に絢と友香里もいて、二人とも出された麦茶を飲みつつ、大福を頬張っていた。涼佑達が来たと分かると、絢は持っていた大福の残りを頬張り、指に付いた粉を近くにあったティッシュで拭ってから立ち上がって迎えた。
「はっほひは。……むぐ。玄関からここまで十分って、遅くない? 真奈美」
「ごめん。ちょっと話したいことあったから。りょ……新條君達も夕飯食べて行くって」
「お、新條達も? おばあちゃん、益々喜ぶね」
「うん」
絢と友香里はきっともう何度も来ているのだろう。勝手知ったるという態度で好きなように過ごしていたらしく、絢の手元には少女漫画、友香里は文庫の小説を読んでいたようだ。「良かったね」と笑顔を見せる絢に、真奈美もほんのり嬉しそうな顔をして頷く。彼女は涼佑達を入室させるとドアを閉め、友香里は一人分空けて二人の席を作ってくれた。部屋の真ん中に置かれたテーブルを囲むように彼らが座ったところで、友香里が少々得意げに言う。
「新條君達、真奈美の手料理食べるの初めてでしょ? 真奈美は料理上手なんだよ。お母さんと一緒に休みの日は料理教室行ってるんだって」
「や、やめてよ、友香里。そんな、大したこと無いの。だから、あんまり期待しないでね」
「青谷は料理、好きなんだ?」
「……うん。だから、上手くなりたくて」
真奈美のような子が料理教室に通っているというのは、涼佑にとっては意外だった。彼の聞くところによれば、いつもオカルト関係の本を読んでいる姿が目立っていたようなので、それ以外の普通の趣味には興味が無いのかと思っていた。
「へぇ、何か意外だなぁ。青谷がそういう趣味あるの」
「おい、直樹。失礼だろ」
咄嗟に窘めようとした涼佑だが、絢も友香里も一斉に「分かる~!」と共感する。自分一人だけ乗れなかった波に涼佑は戸惑い、困惑して周囲を見回した。そんな彼を置いて、絢達と直樹は盛り上がる。
「岡島の言うこと分かるわぁ。確かに真奈美って、学校じゃそういう雰囲気じゃないし」
「本人は隠してるつもり無いみたいなんだけどね」
「……そうなの?」
真奈美本人は不思議そうにきょとんとしていた。この場で気にしているのは自分だけのような気がして、涼佑は何だか損した気分になってしまった。
「だって真奈美ってば、いつも学校だとオカルト系の本とか占いの本とかばっかり読んでるじゃん」
「あれは、研究だから……」
「研究? 青谷はオカルト研究してるってこと?」
直樹の質問に、真奈美はこくりと頷く。
「私、別に幽霊とか信じてる訳じゃなくて、むしろ逆だから、自分なりに研究してる」
「逆って?」
「霊とか神様って、本当にいるのかなって思う方」
これも涼佑にとっては意外だった。てっきり真奈美のようなオカルトが好きな子は幽霊や神様を信じているから、もっと知りたがるものだと思っていたからだった。そこで絢が補足のように付け足す。
「真奈美のオカルトに対する姿勢って、凄く納得できるの。ただ何も考えないで、信じてるやつの方がヤバい感じしない? 私、そういうやつはキライ。でも、真奈美はそういうキャラとは違うから。本当、誤解されまくって嫌になる」
「オカルト研究してるからって、別に悪いことしてないのにね。いつの間にか色んな噂されるようになっちゃって……」
「それな~。真奈美にも、友香里や私にも本当迷惑!」
自分にも少し覚えがあった涼佑はドキッとした。今までの彼女に関する噂を初め、先程考えたことも含めて自分は真奈美に対して無意識の偏見をしていたのではないか、という考えに至る。本当に失礼なことをしていたのは自分の方なんじゃないかと、涼佑は些か衝撃を受けた顔をして考え込んでしまう。そんな中、友香里が苦い記憶でも思い出したのか、眉間に少し皺を寄せて話し出した。
「一回、本当に困ったのは、心霊スポットにあった物を勝手に持って来て、『曰く付きの物だから預かって欲しい』って真奈美に言ってきた時だったね」
「そうそう! 真奈美をからかう為だけに頼んできたみたいだけど、ああいうのマジ迷惑だから、あたし言ってやったんだ。『じゃあ、あんた、頭からガソリンかけて火点けてやるから表出ろ』って」
「ヤクザかよ、お前」
「だって頭に来たんだもんっ! 曰く付きの物を他人に渡すってそのくらいのことしてるのと一緒なんだからね!」
「絢がちゃんと説明したら向こうも分かってくれたみたいで、真奈美をからかうの止めてくれたけど、あの時の絢はちょっと言い過ぎ」
友香里に注意された絢は不満そうに頬を膨らませる。今まで彼女らと関わりが無かった涼佑から見て、案外と華やかな見た目の絢より一見、大人しく見える友香里の方が強いのかと確信した。
そこへいつの間に部屋を出ていたのか、小さな盆に麦茶と大福を乗せて持って来た真奈美が入ってくる。涼佑と直樹の分をテーブルに置き、それをそれぞれが受け取る中、もう一人分用意されていることに気が付いた。てっきり彼女の分かと思っていた涼佑だが、自分の前に置いても一向に手を付ける気配が無いので、不思議に思った彼は何気なく訊いた。
「食べないの? それ」
涼佑の疑問に真奈美は特に気にした風も無く「うん」と頷き、続けて「これは巫女さんの分だから」と返ってきた。それだけ聞いても今の状況とどうにも噛み合わず、大福を食べつつ思わず直樹と一緒に首を傾げる涼佑。真奈美の言っていることがよく分かっていない彼らに、丁度、麦茶を飲み干した絢が説明してくれる。
「あんたらが来る前に話し合ったんだけどね。今回、新條に付きまとってる、っていうか、憑いてる霊は結構厄介な奴みたい。だから、真奈美の手に負えないかもしれないから、大抵の霊を祓ってくれる巫女さんに頼ろうってことになったの」
「ん? 巫女さん? 住職とか宮司とかじゃなくて?」
「今から来てもらうのか?」
結構話し込んでいたせいで、もうすぐ日が沈もうとしている時間だ。今から最寄りの神社からここに来て貰うには、なかなかの距離があって迷惑を掛けてしまうのではと涼佑は危惧する。八野坂町の神社は涼佑達が住まう住宅地の更に向こう側だ。ここまで来てもらうのは悪いと涼佑が考えていると、絢は噴き出すのを堪えるような顔で否定した。
「違う違う。そっちは生きてる方の巫女さんでしょ」
「『生きてる方』?」
意図せず見事に直樹と同時に質問を投げ掛けてしまった涼佑は、恥ずかしいような気まずいような気がして思わず隣にいる直樹と顔を見合わせてしまう。そんな彼らに構わず、絢は続ける。
「あたしらが言ってるのは都市伝説の方の巫女さん。聞いたこと無い? 悪霊を祓ってもらいたい人が儀式で呼び出して、自分に憑依させると、あっという間にどんな悪霊も祓ってくれるっていう幽霊の巫女さん」
「知らん」
「オレも知らん」
聞いたことも無いと二人が気持ち良く言い切ると、絢は一度カーペットに額を付けて萎えた。しかし、すぐに立ち直ったようで、元の姿勢に戻る。
「んじゃ、いいよ。別に知らなくても。とにかく今回はその巫女さんを新條に憑依させる儀式をやります!」
「やんのは良いんだけどさ、それ、本当に効果あんの?」
直樹の不信そうな態度と目つきに、珍しくやや興奮したように嬉しそうな顔をした真奈美が言った。
「絶対、大丈夫」
「……しまーす」
まだ少し緊張気味の直樹は涼佑の後ろで、辛うじて挨拶のようなものを口にする。柄にもなく、緊張してるのかと思うと、涼佑は何だか少しだけ面白く感じた。奥から真奈美が静かに歩いて来て、「どうぞ」とやはり無表情で上がるよう促した。それに答えるようにもう一度「お邪魔します」と小さく言って靴を脱ぎ、そのまま二人は彼女について行く。少し歩くと、真奈美が何かに気が付いたように「あ」と零して足を止め、振り返る。
「飲み物、麦茶しか無いんだけど」
「え? あ、だいじょぶ」
「そう」
それだけで会話を切ると、真奈美はまた少し歩いてから「あ」と言って振り返った。
「お菓子、甘いのしか無いの」
「だ、だいじょぶ。な? 直樹」
「あ、ああ。そんなの、全然!」
「そう」
それだけ言うとまた歩き出す。そして、また「あ」と言って真奈美は振り返る。毎回申し訳なさそうに僅かに眉を寄せている表情で断りを入れてくるので、涼佑達の方が却って恐縮していた。
「私の部屋、座布団二枚しか無くて……」
「分かった。分かったから、青谷。おもてなししてくれるのは嬉しいけど、オレらそういうの全然気にしないから。もう全部大丈夫だから」
「そうなの? でも……」
「もう本当、そんな気、遣わなくていいから。終わったら、すぐ帰るし」
そう言うと、真奈美は意外そうに「え!?」と一瞬驚き、少し困った顔をして微かに俯く。予想外の反応に、今度は涼佑達が少々驚く番だった。
「夕飯は食べていかないの? 今日、その、友達が来るから、少し多めに作ろうと思ってて……」
少し恥ずかしそうにもじもじしながら言う真奈美は、いつも涼佑が見かけるミステリアスな高嶺の花ではなく、普通の女の子だ。可愛らしいとは思うけど、やはりそれ以上の感情は湧いてこないことに涼佑が自身に対して密かに失望していると、その背後にいる直樹は明らかに真奈美を意識していますという顔つきで「あ、そうなん? じ、じゃあ、しょうがないから食べてくか。な? 涼佑」とわざわざ涼佑の隣に来てまで目配せしてきた。その行動に苦笑を零して、涼佑は気を利かせることにした。
「じゃあ、お言葉に甘えて。というか、夕飯、青谷が作ってるんだ」
「私の両親、共働きで帰りが遅いから。もうすぐ祖母がデイサービスから帰って来るし、夕飯一緒になっちゃうんだけど、大丈夫?」
「うん、全然。むしろ、オレらがいていいの?」
「うん。おばあちゃん、お客さん好きだから」
思わず零したのだろう。学校にいる時とは違う、私生活の彼女が顔を覗かせたような優しい笑みに、涼佑はちょっと意外だなと思った。青谷ってそういう顔するんだ、と新たな一面を見て感慨深いような気がした。自分の表情に真奈美自身も気付いたのか、はっとした顔をして慌てて「こっち」と二階へ続く階段を登り始める。恥ずかしかったのか、いきなり早足になった真奈美の後を涼佑達も同じように早足で追いかけた。
二階に続く階段を上がってすぐの部屋が彼女のもののようで、階段を上がりきった真奈美はドアを開ける。中には既に絢と友香里もいて、二人とも出された麦茶を飲みつつ、大福を頬張っていた。涼佑達が来たと分かると、絢は持っていた大福の残りを頬張り、指に付いた粉を近くにあったティッシュで拭ってから立ち上がって迎えた。
「はっほひは。……むぐ。玄関からここまで十分って、遅くない? 真奈美」
「ごめん。ちょっと話したいことあったから。りょ……新條君達も夕飯食べて行くって」
「お、新條達も? おばあちゃん、益々喜ぶね」
「うん」
絢と友香里はきっともう何度も来ているのだろう。勝手知ったるという態度で好きなように過ごしていたらしく、絢の手元には少女漫画、友香里は文庫の小説を読んでいたようだ。「良かったね」と笑顔を見せる絢に、真奈美もほんのり嬉しそうな顔をして頷く。彼女は涼佑達を入室させるとドアを閉め、友香里は一人分空けて二人の席を作ってくれた。部屋の真ん中に置かれたテーブルを囲むように彼らが座ったところで、友香里が少々得意げに言う。
「新條君達、真奈美の手料理食べるの初めてでしょ? 真奈美は料理上手なんだよ。お母さんと一緒に休みの日は料理教室行ってるんだって」
「や、やめてよ、友香里。そんな、大したこと無いの。だから、あんまり期待しないでね」
「青谷は料理、好きなんだ?」
「……うん。だから、上手くなりたくて」
真奈美のような子が料理教室に通っているというのは、涼佑にとっては意外だった。彼の聞くところによれば、いつもオカルト関係の本を読んでいる姿が目立っていたようなので、それ以外の普通の趣味には興味が無いのかと思っていた。
「へぇ、何か意外だなぁ。青谷がそういう趣味あるの」
「おい、直樹。失礼だろ」
咄嗟に窘めようとした涼佑だが、絢も友香里も一斉に「分かる~!」と共感する。自分一人だけ乗れなかった波に涼佑は戸惑い、困惑して周囲を見回した。そんな彼を置いて、絢達と直樹は盛り上がる。
「岡島の言うこと分かるわぁ。確かに真奈美って、学校じゃそういう雰囲気じゃないし」
「本人は隠してるつもり無いみたいなんだけどね」
「……そうなの?」
真奈美本人は不思議そうにきょとんとしていた。この場で気にしているのは自分だけのような気がして、涼佑は何だか損した気分になってしまった。
「だって真奈美ってば、いつも学校だとオカルト系の本とか占いの本とかばっかり読んでるじゃん」
「あれは、研究だから……」
「研究? 青谷はオカルト研究してるってこと?」
直樹の質問に、真奈美はこくりと頷く。
「私、別に幽霊とか信じてる訳じゃなくて、むしろ逆だから、自分なりに研究してる」
「逆って?」
「霊とか神様って、本当にいるのかなって思う方」
これも涼佑にとっては意外だった。てっきり真奈美のようなオカルトが好きな子は幽霊や神様を信じているから、もっと知りたがるものだと思っていたからだった。そこで絢が補足のように付け足す。
「真奈美のオカルトに対する姿勢って、凄く納得できるの。ただ何も考えないで、信じてるやつの方がヤバい感じしない? 私、そういうやつはキライ。でも、真奈美はそういうキャラとは違うから。本当、誤解されまくって嫌になる」
「オカルト研究してるからって、別に悪いことしてないのにね。いつの間にか色んな噂されるようになっちゃって……」
「それな~。真奈美にも、友香里や私にも本当迷惑!」
自分にも少し覚えがあった涼佑はドキッとした。今までの彼女に関する噂を初め、先程考えたことも含めて自分は真奈美に対して無意識の偏見をしていたのではないか、という考えに至る。本当に失礼なことをしていたのは自分の方なんじゃないかと、涼佑は些か衝撃を受けた顔をして考え込んでしまう。そんな中、友香里が苦い記憶でも思い出したのか、眉間に少し皺を寄せて話し出した。
「一回、本当に困ったのは、心霊スポットにあった物を勝手に持って来て、『曰く付きの物だから預かって欲しい』って真奈美に言ってきた時だったね」
「そうそう! 真奈美をからかう為だけに頼んできたみたいだけど、ああいうのマジ迷惑だから、あたし言ってやったんだ。『じゃあ、あんた、頭からガソリンかけて火点けてやるから表出ろ』って」
「ヤクザかよ、お前」
「だって頭に来たんだもんっ! 曰く付きの物を他人に渡すってそのくらいのことしてるのと一緒なんだからね!」
「絢がちゃんと説明したら向こうも分かってくれたみたいで、真奈美をからかうの止めてくれたけど、あの時の絢はちょっと言い過ぎ」
友香里に注意された絢は不満そうに頬を膨らませる。今まで彼女らと関わりが無かった涼佑から見て、案外と華やかな見た目の絢より一見、大人しく見える友香里の方が強いのかと確信した。
そこへいつの間に部屋を出ていたのか、小さな盆に麦茶と大福を乗せて持って来た真奈美が入ってくる。涼佑と直樹の分をテーブルに置き、それをそれぞれが受け取る中、もう一人分用意されていることに気が付いた。てっきり彼女の分かと思っていた涼佑だが、自分の前に置いても一向に手を付ける気配が無いので、不思議に思った彼は何気なく訊いた。
「食べないの? それ」
涼佑の疑問に真奈美は特に気にした風も無く「うん」と頷き、続けて「これは巫女さんの分だから」と返ってきた。それだけ聞いても今の状況とどうにも噛み合わず、大福を食べつつ思わず直樹と一緒に首を傾げる涼佑。真奈美の言っていることがよく分かっていない彼らに、丁度、麦茶を飲み干した絢が説明してくれる。
「あんたらが来る前に話し合ったんだけどね。今回、新條に付きまとってる、っていうか、憑いてる霊は結構厄介な奴みたい。だから、真奈美の手に負えないかもしれないから、大抵の霊を祓ってくれる巫女さんに頼ろうってことになったの」
「ん? 巫女さん? 住職とか宮司とかじゃなくて?」
「今から来てもらうのか?」
結構話し込んでいたせいで、もうすぐ日が沈もうとしている時間だ。今から最寄りの神社からここに来て貰うには、なかなかの距離があって迷惑を掛けてしまうのではと涼佑は危惧する。八野坂町の神社は涼佑達が住まう住宅地の更に向こう側だ。ここまで来てもらうのは悪いと涼佑が考えていると、絢は噴き出すのを堪えるような顔で否定した。
「違う違う。そっちは生きてる方の巫女さんでしょ」
「『生きてる方』?」
意図せず見事に直樹と同時に質問を投げ掛けてしまった涼佑は、恥ずかしいような気まずいような気がして思わず隣にいる直樹と顔を見合わせてしまう。そんな彼らに構わず、絢は続ける。
「あたしらが言ってるのは都市伝説の方の巫女さん。聞いたこと無い? 悪霊を祓ってもらいたい人が儀式で呼び出して、自分に憑依させると、あっという間にどんな悪霊も祓ってくれるっていう幽霊の巫女さん」
「知らん」
「オレも知らん」
聞いたことも無いと二人が気持ち良く言い切ると、絢は一度カーペットに額を付けて萎えた。しかし、すぐに立ち直ったようで、元の姿勢に戻る。
「んじゃ、いいよ。別に知らなくても。とにかく今回はその巫女さんを新條に憑依させる儀式をやります!」
「やんのは良いんだけどさ、それ、本当に効果あんの?」
直樹の不信そうな態度と目つきに、珍しくやや興奮したように嬉しそうな顔をした真奈美が言った。
「絶対、大丈夫」