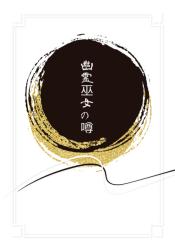約束通りに元の民家へ戻って来た一同は、何か有益な情報が得られたか互いに確認し合うも、収穫はなしと言っても良かった。何せ彼らが事情を話し、この村について何か訊いても、村人達は皆何かしら作業していたり、座っていたりして、こちらに近付こうとすると、皆躓いて転んでしまい、そのまま死んでしまう。涼佑と直樹は律儀にもその度、まじまじと見てしまい、何度人が死ぬところを見たのか数えたくもない。合流する頃には、二人共真っ青な顔で民家の玄関内に座り込んでいた。
二人を心配した友香里が「大丈夫?」と訊くと、涼佑は勿論、流石の直樹もいつもの軽口を叩く余裕も無いようで、ただ無言で首を振るばかり。霧が出始めていたせいでこれ以上、調査の範囲を広げてしまうと、次は上手く合流できるかどうかも分からない為、巫女さんと絢で意見を交わした結果、ここからは全員で行動した方が良いだろうという結論に行き着いた。
「じゃあ、私、村の一番奥まで行ってみたい」
「正気かっ!? 真奈美ぃっ!」
何やらわくわくしている様子の真奈美を見て、思わず声を上げる直樹。たとえ、好きな子でも今の発言は彼にとって死刑宣告も同義なのだろう。信じられないものを見る目で真奈美を見つめている。しかし、彼女の意見に意外にも絢が賛成の意を示した。
「ああ、それ。私もそうしよっかなって思ってた」
「何故に!? 三十字以内で理由を述べよぉっ!」
「夢って端っことか奥の方は作り込みが甘い傾向にあるから、もしかしたら出られるかもって思ったから」
三十字以内では決して無いが、思わぬところで希望の糸口が提示され、途端に直樹は「神様仏様絢様ぁ!」と絢を拝み始めた。それに彼女がすげなく「拝んだって、効果無いよ」と言い、鬱陶しそうにぺしぺしと手で拝みまくっている直樹の頭を払った。それすら有り難そうに甘んじて受けている直樹を不気味に思ったのか、絢が冷めた目を向けながら数歩引いたところで、真奈美は涼佑と友香里にも何か意見は無いかと確認する。
「私はこういうのはよく分からないから、二人に付いて行くよ」
「正直、オレもだ」
「今回、オレの出番は無さそうな感じだし」とどこか少し寂しげに巫女さんを見つめる涼佑。その意図を汲んでなのか、関係は無いのか、やはりよく分からないいつもの無表情で、真奈美は「分かった」とだけ返事をした。
みくにも村の奥へ行くことを伝えると、少し不安そうな顔をしたが、「皆で行くから大丈夫だよ」と絢に言われると安心したのか、花が咲いたように笑って頷いた。その無邪気な笑顔にいくらか癒された直樹は思わず「可愛いなぁ~」と破顔し、恥ずかしがったみくに隠れられていた。内気なみくの姿に絢達も可愛い可愛いと持て囃すので、却って居心地は悪いだろうなと、涼佑は幼い頃、親戚の家に行った時のことを思い出し、内心で苦笑いしていた。
みくがきっかけで精神的にいくらか回復した一同は、それからも少し休んで肉体的な疲労を取ってから――魂だけの存在で肉体的な疲労という表現はおかしいが――出発することになった。
「涼佑」
民家の玄関で休み、皆が和やかな会話をしている中、いつの間に隣に来ていたのか、巫女さんに袖の端をぐい、と涼佑は引っ張られる。直樹達から意識を逸らして彼女の方へ向くと、巫女さんは真剣な面持ちのまま、小声でひそひそと忠告してきた。
「これから村の奥へ行くが、その道中でも着いても油断するなよ」
「? 何だよ? 『油断』って」
未だに向こうの和やかな雰囲気から抜け出せていない涼佑に巫女さんは構わず、注意を促す。
「ここは安定した現実と違って、何が起こるか予測できない夢の世界だ。なるべく私から離れるんじゃないぞ」
「さっきの行動だって、本当は褒められたものじゃない」と渋い顔をする巫女さん。先程、二手に分かれたことを言っているのだろう。不満そうに唇を尖らせて、彼女は尚も言い募った。
「本来、こういう場合、宿主であるお前と守護霊である私が離れて行動するなど、あってはならないことなんだ」
「……そう、なのか?」
「お前に何かあった時、守れないだろ」
「宿主を守れない守護霊なんて、存在理由が無い」ときっぱり言い切る彼女の言葉と先程実際に移した行動を併せて考えた涼佑は思わず、ふふ、と笑ってしまった。その声に何か勘違いしたらしく、きっと睨み付けてくる巫女さんに涼佑は慌てて弁明する。
「別にそういう意味じゃないよ、巫女さん」
「じゃあ、どういう意味だ? え?」
怒りながら距離を詰めて来る巫女さんに追い立てられ、玄関の隅に追いやられた涼佑は「これは思ったより、怒ってるかもしれないな」とどこか呑気に考えていた。不意に顔の横へ叩き付けるようにして置かれた彼女の手に、びくっと驚きで身を震わせた。まさか女の子から壁ドンをされるとは思っていなかった涼佑は、ただただ現状に驚くばかりだ。しかし、そんな巫女さんの威圧に負けじと、涼佑もしっかりと彼女の目を見て自分の意見を言った。
「いや、それでも巫女さんはオレの言うことを優先してくれたんだなって思って」
巫女さんと自分では持っている知識も経験もかなり差がある筈なのに、それでも自分を信じて行動させてくれた。それが嬉しいんだと精一杯涼佑が伝えると、今度は巫女さんが驚く番だった。その驚きのまま、ゆっくり離れた巫女さんへ涼佑は笑顔を浮かべ、「ありがとう、巫女さん」と礼を言う。その態度と言葉で漸く自分の勘違いに気付いた巫女さんは、「そ、そうか」と恥ずかしそうにそっぽを向く。ぽそりと「すまん」と謝るその頬や耳が少し赤くなっていることに涼佑は気付いたが、そこを指摘するときっとまた怒られるので、黙っておくことにした。
巫女さんの勘違いが解消されたところで、仕切り直しの意味で咳払いをし、再度彼女に油断しないよう言われた涼佑は、微妙に笑いを堪えつつも「分かったよ」と返事をした。
「じゃあ、そろそろ行く?」
「うん、そうだね」
休息も充分に取れたところでまた外へ出た一行は、村の奥を目指す。二手に分かれた時より周囲に漂う霧はだいぶ濃くなり、普段見えている筈の範囲すら白い霧に隠されている。はぐれないようにと、絢は殆ど無意識に隣にいるみくの手を握った。
霧の粒子が肌に纏わり付く度、どこかぞっとするような怖気を感じる。それは単純にしっとりとした冷たさからなのか、それとも別の何かがあるのか。涼佑には全くと言って良い程分からないが、先頭を歩いている巫女さんが刀の柄に手を掛けたまま、周囲への警戒を怠っていないところを見ると、決して気を抜いてはいけない状況なのだと気を引き締める。そうやって慎重に畦道を進んでいると、いつの間にか、涼佑と直樹には見覚えのある場所に来ていた。
「涼佑、ここ……」
「思い出すなよ、直樹」
しかし、『それ』を見た瞬間、二人は思い出さざるを得ない。『それ』は畦道より一段低い田んぼの縁にある芝生の上に置かれていた。所々に乾いた泥が付いている『それ』。付着している泥の一部はまだ乾いておらず、むしろ数秒前まで誰かが泥の付いた手で触れていたように、水分を含んでいる。中にはまだいくつかの苗がちょこんちょこんと並んでいる光景を見て、涼佑と直樹は震え上がり、咄嗟に目を背ける。最初に出会った男が小脇に抱えていたダンボール箱。彼の末路が一瞬、瞼の裏にちらつき、二人は恐怖を振り払おうと頭を振って、前を行く真奈美達の背中を見つめた。
二人を心配した友香里が「大丈夫?」と訊くと、涼佑は勿論、流石の直樹もいつもの軽口を叩く余裕も無いようで、ただ無言で首を振るばかり。霧が出始めていたせいでこれ以上、調査の範囲を広げてしまうと、次は上手く合流できるかどうかも分からない為、巫女さんと絢で意見を交わした結果、ここからは全員で行動した方が良いだろうという結論に行き着いた。
「じゃあ、私、村の一番奥まで行ってみたい」
「正気かっ!? 真奈美ぃっ!」
何やらわくわくしている様子の真奈美を見て、思わず声を上げる直樹。たとえ、好きな子でも今の発言は彼にとって死刑宣告も同義なのだろう。信じられないものを見る目で真奈美を見つめている。しかし、彼女の意見に意外にも絢が賛成の意を示した。
「ああ、それ。私もそうしよっかなって思ってた」
「何故に!? 三十字以内で理由を述べよぉっ!」
「夢って端っことか奥の方は作り込みが甘い傾向にあるから、もしかしたら出られるかもって思ったから」
三十字以内では決して無いが、思わぬところで希望の糸口が提示され、途端に直樹は「神様仏様絢様ぁ!」と絢を拝み始めた。それに彼女がすげなく「拝んだって、効果無いよ」と言い、鬱陶しそうにぺしぺしと手で拝みまくっている直樹の頭を払った。それすら有り難そうに甘んじて受けている直樹を不気味に思ったのか、絢が冷めた目を向けながら数歩引いたところで、真奈美は涼佑と友香里にも何か意見は無いかと確認する。
「私はこういうのはよく分からないから、二人に付いて行くよ」
「正直、オレもだ」
「今回、オレの出番は無さそうな感じだし」とどこか少し寂しげに巫女さんを見つめる涼佑。その意図を汲んでなのか、関係は無いのか、やはりよく分からないいつもの無表情で、真奈美は「分かった」とだけ返事をした。
みくにも村の奥へ行くことを伝えると、少し不安そうな顔をしたが、「皆で行くから大丈夫だよ」と絢に言われると安心したのか、花が咲いたように笑って頷いた。その無邪気な笑顔にいくらか癒された直樹は思わず「可愛いなぁ~」と破顔し、恥ずかしがったみくに隠れられていた。内気なみくの姿に絢達も可愛い可愛いと持て囃すので、却って居心地は悪いだろうなと、涼佑は幼い頃、親戚の家に行った時のことを思い出し、内心で苦笑いしていた。
みくがきっかけで精神的にいくらか回復した一同は、それからも少し休んで肉体的な疲労を取ってから――魂だけの存在で肉体的な疲労という表現はおかしいが――出発することになった。
「涼佑」
民家の玄関で休み、皆が和やかな会話をしている中、いつの間に隣に来ていたのか、巫女さんに袖の端をぐい、と涼佑は引っ張られる。直樹達から意識を逸らして彼女の方へ向くと、巫女さんは真剣な面持ちのまま、小声でひそひそと忠告してきた。
「これから村の奥へ行くが、その道中でも着いても油断するなよ」
「? 何だよ? 『油断』って」
未だに向こうの和やかな雰囲気から抜け出せていない涼佑に巫女さんは構わず、注意を促す。
「ここは安定した現実と違って、何が起こるか予測できない夢の世界だ。なるべく私から離れるんじゃないぞ」
「さっきの行動だって、本当は褒められたものじゃない」と渋い顔をする巫女さん。先程、二手に分かれたことを言っているのだろう。不満そうに唇を尖らせて、彼女は尚も言い募った。
「本来、こういう場合、宿主であるお前と守護霊である私が離れて行動するなど、あってはならないことなんだ」
「……そう、なのか?」
「お前に何かあった時、守れないだろ」
「宿主を守れない守護霊なんて、存在理由が無い」ときっぱり言い切る彼女の言葉と先程実際に移した行動を併せて考えた涼佑は思わず、ふふ、と笑ってしまった。その声に何か勘違いしたらしく、きっと睨み付けてくる巫女さんに涼佑は慌てて弁明する。
「別にそういう意味じゃないよ、巫女さん」
「じゃあ、どういう意味だ? え?」
怒りながら距離を詰めて来る巫女さんに追い立てられ、玄関の隅に追いやられた涼佑は「これは思ったより、怒ってるかもしれないな」とどこか呑気に考えていた。不意に顔の横へ叩き付けるようにして置かれた彼女の手に、びくっと驚きで身を震わせた。まさか女の子から壁ドンをされるとは思っていなかった涼佑は、ただただ現状に驚くばかりだ。しかし、そんな巫女さんの威圧に負けじと、涼佑もしっかりと彼女の目を見て自分の意見を言った。
「いや、それでも巫女さんはオレの言うことを優先してくれたんだなって思って」
巫女さんと自分では持っている知識も経験もかなり差がある筈なのに、それでも自分を信じて行動させてくれた。それが嬉しいんだと精一杯涼佑が伝えると、今度は巫女さんが驚く番だった。その驚きのまま、ゆっくり離れた巫女さんへ涼佑は笑顔を浮かべ、「ありがとう、巫女さん」と礼を言う。その態度と言葉で漸く自分の勘違いに気付いた巫女さんは、「そ、そうか」と恥ずかしそうにそっぽを向く。ぽそりと「すまん」と謝るその頬や耳が少し赤くなっていることに涼佑は気付いたが、そこを指摘するときっとまた怒られるので、黙っておくことにした。
巫女さんの勘違いが解消されたところで、仕切り直しの意味で咳払いをし、再度彼女に油断しないよう言われた涼佑は、微妙に笑いを堪えつつも「分かったよ」と返事をした。
「じゃあ、そろそろ行く?」
「うん、そうだね」
休息も充分に取れたところでまた外へ出た一行は、村の奥を目指す。二手に分かれた時より周囲に漂う霧はだいぶ濃くなり、普段見えている筈の範囲すら白い霧に隠されている。はぐれないようにと、絢は殆ど無意識に隣にいるみくの手を握った。
霧の粒子が肌に纏わり付く度、どこかぞっとするような怖気を感じる。それは単純にしっとりとした冷たさからなのか、それとも別の何かがあるのか。涼佑には全くと言って良い程分からないが、先頭を歩いている巫女さんが刀の柄に手を掛けたまま、周囲への警戒を怠っていないところを見ると、決して気を抜いてはいけない状況なのだと気を引き締める。そうやって慎重に畦道を進んでいると、いつの間にか、涼佑と直樹には見覚えのある場所に来ていた。
「涼佑、ここ……」
「思い出すなよ、直樹」
しかし、『それ』を見た瞬間、二人は思い出さざるを得ない。『それ』は畦道より一段低い田んぼの縁にある芝生の上に置かれていた。所々に乾いた泥が付いている『それ』。付着している泥の一部はまだ乾いておらず、むしろ数秒前まで誰かが泥の付いた手で触れていたように、水分を含んでいる。中にはまだいくつかの苗がちょこんちょこんと並んでいる光景を見て、涼佑と直樹は震え上がり、咄嗟に目を背ける。最初に出会った男が小脇に抱えていたダンボール箱。彼の末路が一瞬、瞼の裏にちらつき、二人は恐怖を振り払おうと頭を振って、前を行く真奈美達の背中を見つめた。