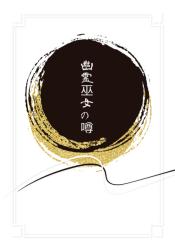「え?」と振り返った時にはもう夏神はこちらへ見向きもしないで、近くの女子グループの中に入れて貰っていた。グループのメンバー全員が嬉しそうな顔で歓迎している。聞き間違いかと逡巡しつつも、今更夏神に訊くのは気が引けたので、涼佑は首を傾げつつも廊下へ出て行った。
夜。夕食も入浴も済ませ、後は寝るだけとなった時、唐突に直樹から電話が掛かってきた。やっぱり怖いのかと思った涼佑は、若干苦笑しつつ、電話に出る。
「どした? 直樹」
「………………いや、あの、うん。――今回の怪異なんだけどさ」
「うん」
「その…………巫女さんから何か対策みたいなの、聞いてない?」
直樹の言いたいことを伝えると、巫女さんは無常にも淡々とした口調で言った。
「頑張って転ばないようにする、だな」
なるほど、と納得できないまま、納得の常套句を発して涼佑がそっくりそのまま伝えると、直樹は電話の向こうで嘆いた。
「根性論しか無いのっ!? なんでっ!?」
「何か便利な道具とか出てこないの!?」と喚く直樹にまた巫女さんからの有難い助言をもらった涼佑は、またそのまま伝える。
「泣いてる暇あったら、体を鍛えろって」
「突然の筋肉!? 根性論の次は筋肉って、巫女さんって本当に女子なの……? 筋骨隆々の男だったりしない? 涼佑、騙されてない?」
「いや、ちゃんと女子だから、大丈夫」
「ちゃんと女子だから??」
電話の向こうで困惑しかしていない直樹。涼佑もよく分からなかったので、詳しく訊くと、巫女さんは「仕方ないな」と言って説明してくれた。体を鍛えて体型や体幹がしっかりしてくると同時に自信に繋がり、それが精神も強くするということらしい。精神が強く安定していれば、霊的なものに対抗できる力が備わり、抗いやすくなるということだ。
「それに体型が締まると、女にモテるぞ」
「おい、涼佑。スクワットやんぞっ!」
「現金かよ」
モテると聞いて一気にやる気を出し始めた直樹は、早速スクワットを始めたらしく、電話の向こうから「ふんっ! ふんっ!」と聞きたくもない気合いの声が聞こえてくる。スクワットをやるなら、電話切ってくれと思う涼佑だが、そう声を掛けると、「切んなよ!」と何故か止められる。お互いの筋トレ中の掛け声なんて、正直聞きたくないと思うのだが、直樹曰く、「一人の部屋でひたすら筋トレするとか怖くて無理」のようなので、涼佑も渋々付き合ってやっていた。
どのくらいひたすら鍛えていたのか、足ががくがくしてきた辺りで二人は止めた。さっき風呂に入ったばかりなのにもう汗だくだ。もう一回入浴してこようと、直樹に声を掛ける。
「風呂入ってくるから、電話切っていい?」
「ふざけんなよ。俺も入るから絶対切んなよ」
「なんでだよ。スマホ壊れるから風呂場に持ち込みたくない」
「お前この時間に一人で風呂って、お前ふざけんなよ。一人で入れる訳ねぇだろうが……!」
「なんで静かに逆ギレしながら、小学生みたいなこと言ってんだよ」
「こんな時間」という単語に、何気なくスマホの画面を見ると、もう二十三時を表示している。この時間に浴室を使う家族はいないので、シャワーを浴びるには最適だが、直樹と通話したまま入るのははばかられる。何より涼佑にとって、湿気の多い場所にスマホを持って行くのが嫌だった。いくらジップロックにスマホを入れればいいとはいえ、先代はそれが原因で中に湿気が入り込んでお亡くなりになったのだから、当然だろう。もうお互い高校生なのだから、いい加減聞き分けて欲しい。直樹が尚も喚いているうちにさっさと替えの下着と寝巻きを用意した涼佑は「んじゃ、風呂入ってくる」とだけ言って電話を切った。
「うーわっ、あいつ。マジで切りやがった! 最悪! サイテー! りょーちゃんってば、信じられないっ! アタシとは遊びだったのねっ!」
訳の分からないことを通話が切れたばかりのスマホに喚き散らしていると、寝室に行った筈の母に乱入され「夜中に大きな声出すんじゃないよっ!」と怒られ、気分を沈めながらも直樹はのろのろとシャワーを浴びる準備をし始めた。
替えの下着とパジャマ。唯一の心の拠り所であるスマホを持って、そろそろと階段を下る。直樹以外の家族は皆自室に引っ込んでいるので当然だが、一階は電灯が全て消えており、真っ暗だ。「畜生、なんでこんな時に限って誰もいないんだよ」と心中で毒づくも、救いの手が差し伸べられる筈も無く、依然として真っ暗闇の中へ突入するように階段を下るしかない。さっきまでは涼佑と電話で繋がっていたから心に多少の余裕が生まれていたが、今はもう誰とも繋がっていない、本当に一人なのだと実感すると、底冷えのする闇の中に自ら身を沈めるようで、直樹はぞっとした。
加えて、さっきまで涼佑と話していた怪異のこともある。転ぶと死ぬ村。もし、夢の中で転んでしまったら、死んでしまうなんて話を聴いてしまってはもう怖いなんてもんじゃない。視界の端に幽霊っぽいものを見たら、その場で死ぬんじゃないかと思う程の緊張感にずっと襲われている。戦々恐々とした足取りで、直樹は通りがかった居間の電灯を点けずに真っ直ぐ脱衣所へ向かう。彼の家は今時珍しい古い日本家屋なので、廊下はやたら広いし、丁度居間の裏側に脱衣所と浴室があるせいで、廊下の電灯を点けないと本当に真っ暗だ。はっきり言って、最近の洋風の家なんかとは比べものにならない程、雰囲気が段違いに怖い。
元は前の家主がちょっとした旅館のように小さな宿泊施設として経営していたものだったのだが、直樹の父が大層気に入ってからは水回りを使いやすくリフォームし、壁紙を変えただけの家だ。台所や浴室は新しくなっていてあまり恐怖は感じないのだが、それ以外は元のままなので、正直直樹は少し苦手だった。
「ああ、早くこんな家、出て行きたい」と思いつつ、何とか無事に脱衣所まで辿り着くと、脱衣所の壁にそろそろとおっかなびっくり、手を這わせて電灯のスイッチを押した。途端に明るくなるいつもの脱衣所の光景に、直樹は少しだけほっとする。いつものように洗濯機の蓋を閉めて着替えを置く。脱衣所の引き戸を閉めて服を脱ごうと着ているパジャマの裾を掴んだ時だった。
何となく、すぐ傍にある洗面所の鏡を見る。そこには少しだけ顔色の悪い自分と背景に折り戸が開けられている浴室が見える。湿気を逃がす為に開けられている折り戸の向こう。家族のうち誰かしらのシャンプーやらボディソープやらが置かれている棚がある。丁度直樹の目線より少し高い位置に白く長いものがあった。鏡越しに直樹はそれを見た。真っ白なドレスを着た背の高い女がこちらに背を向けて立っている。一瞬、それを視界の端に入れた直樹は、「ぴ」と小さく悲鳴を零してその場に倒れ込んだ。気絶した重い体が引き戸に当たり、そのまま床に向かってずり落ちるようにして彼の体は凭れ掛かった。
しかし、悲しいことに、よりによって、直樹は妹が新しく買ったばかりの真っ白な大判のボディタオルを幽霊と見間違って気絶してしまったのだった。
「さて、シャワー浴びたし、寝るか」
「お、寝るのか。いよいよだな、涼佑」
一方で、シャワーを浴び終えた涼佑は濡れた髪を粗方タオルで拭くと、新しいタオルを枕に敷いて寝る体勢に入る。絢が聞いたらきっと卒倒する行動だろうが、涼佑にとっては洗髪後のいつもの行動だ。部屋の電灯を消して巫女さんに「おやすみ」を言う涼佑に、彼女も同じように返した。
夜。夕食も入浴も済ませ、後は寝るだけとなった時、唐突に直樹から電話が掛かってきた。やっぱり怖いのかと思った涼佑は、若干苦笑しつつ、電話に出る。
「どした? 直樹」
「………………いや、あの、うん。――今回の怪異なんだけどさ」
「うん」
「その…………巫女さんから何か対策みたいなの、聞いてない?」
直樹の言いたいことを伝えると、巫女さんは無常にも淡々とした口調で言った。
「頑張って転ばないようにする、だな」
なるほど、と納得できないまま、納得の常套句を発して涼佑がそっくりそのまま伝えると、直樹は電話の向こうで嘆いた。
「根性論しか無いのっ!? なんでっ!?」
「何か便利な道具とか出てこないの!?」と喚く直樹にまた巫女さんからの有難い助言をもらった涼佑は、またそのまま伝える。
「泣いてる暇あったら、体を鍛えろって」
「突然の筋肉!? 根性論の次は筋肉って、巫女さんって本当に女子なの……? 筋骨隆々の男だったりしない? 涼佑、騙されてない?」
「いや、ちゃんと女子だから、大丈夫」
「ちゃんと女子だから??」
電話の向こうで困惑しかしていない直樹。涼佑もよく分からなかったので、詳しく訊くと、巫女さんは「仕方ないな」と言って説明してくれた。体を鍛えて体型や体幹がしっかりしてくると同時に自信に繋がり、それが精神も強くするということらしい。精神が強く安定していれば、霊的なものに対抗できる力が備わり、抗いやすくなるということだ。
「それに体型が締まると、女にモテるぞ」
「おい、涼佑。スクワットやんぞっ!」
「現金かよ」
モテると聞いて一気にやる気を出し始めた直樹は、早速スクワットを始めたらしく、電話の向こうから「ふんっ! ふんっ!」と聞きたくもない気合いの声が聞こえてくる。スクワットをやるなら、電話切ってくれと思う涼佑だが、そう声を掛けると、「切んなよ!」と何故か止められる。お互いの筋トレ中の掛け声なんて、正直聞きたくないと思うのだが、直樹曰く、「一人の部屋でひたすら筋トレするとか怖くて無理」のようなので、涼佑も渋々付き合ってやっていた。
どのくらいひたすら鍛えていたのか、足ががくがくしてきた辺りで二人は止めた。さっき風呂に入ったばかりなのにもう汗だくだ。もう一回入浴してこようと、直樹に声を掛ける。
「風呂入ってくるから、電話切っていい?」
「ふざけんなよ。俺も入るから絶対切んなよ」
「なんでだよ。スマホ壊れるから風呂場に持ち込みたくない」
「お前この時間に一人で風呂って、お前ふざけんなよ。一人で入れる訳ねぇだろうが……!」
「なんで静かに逆ギレしながら、小学生みたいなこと言ってんだよ」
「こんな時間」という単語に、何気なくスマホの画面を見ると、もう二十三時を表示している。この時間に浴室を使う家族はいないので、シャワーを浴びるには最適だが、直樹と通話したまま入るのははばかられる。何より涼佑にとって、湿気の多い場所にスマホを持って行くのが嫌だった。いくらジップロックにスマホを入れればいいとはいえ、先代はそれが原因で中に湿気が入り込んでお亡くなりになったのだから、当然だろう。もうお互い高校生なのだから、いい加減聞き分けて欲しい。直樹が尚も喚いているうちにさっさと替えの下着と寝巻きを用意した涼佑は「んじゃ、風呂入ってくる」とだけ言って電話を切った。
「うーわっ、あいつ。マジで切りやがった! 最悪! サイテー! りょーちゃんってば、信じられないっ! アタシとは遊びだったのねっ!」
訳の分からないことを通話が切れたばかりのスマホに喚き散らしていると、寝室に行った筈の母に乱入され「夜中に大きな声出すんじゃないよっ!」と怒られ、気分を沈めながらも直樹はのろのろとシャワーを浴びる準備をし始めた。
替えの下着とパジャマ。唯一の心の拠り所であるスマホを持って、そろそろと階段を下る。直樹以外の家族は皆自室に引っ込んでいるので当然だが、一階は電灯が全て消えており、真っ暗だ。「畜生、なんでこんな時に限って誰もいないんだよ」と心中で毒づくも、救いの手が差し伸べられる筈も無く、依然として真っ暗闇の中へ突入するように階段を下るしかない。さっきまでは涼佑と電話で繋がっていたから心に多少の余裕が生まれていたが、今はもう誰とも繋がっていない、本当に一人なのだと実感すると、底冷えのする闇の中に自ら身を沈めるようで、直樹はぞっとした。
加えて、さっきまで涼佑と話していた怪異のこともある。転ぶと死ぬ村。もし、夢の中で転んでしまったら、死んでしまうなんて話を聴いてしまってはもう怖いなんてもんじゃない。視界の端に幽霊っぽいものを見たら、その場で死ぬんじゃないかと思う程の緊張感にずっと襲われている。戦々恐々とした足取りで、直樹は通りがかった居間の電灯を点けずに真っ直ぐ脱衣所へ向かう。彼の家は今時珍しい古い日本家屋なので、廊下はやたら広いし、丁度居間の裏側に脱衣所と浴室があるせいで、廊下の電灯を点けないと本当に真っ暗だ。はっきり言って、最近の洋風の家なんかとは比べものにならない程、雰囲気が段違いに怖い。
元は前の家主がちょっとした旅館のように小さな宿泊施設として経営していたものだったのだが、直樹の父が大層気に入ってからは水回りを使いやすくリフォームし、壁紙を変えただけの家だ。台所や浴室は新しくなっていてあまり恐怖は感じないのだが、それ以外は元のままなので、正直直樹は少し苦手だった。
「ああ、早くこんな家、出て行きたい」と思いつつ、何とか無事に脱衣所まで辿り着くと、脱衣所の壁にそろそろとおっかなびっくり、手を這わせて電灯のスイッチを押した。途端に明るくなるいつもの脱衣所の光景に、直樹は少しだけほっとする。いつものように洗濯機の蓋を閉めて着替えを置く。脱衣所の引き戸を閉めて服を脱ごうと着ているパジャマの裾を掴んだ時だった。
何となく、すぐ傍にある洗面所の鏡を見る。そこには少しだけ顔色の悪い自分と背景に折り戸が開けられている浴室が見える。湿気を逃がす為に開けられている折り戸の向こう。家族のうち誰かしらのシャンプーやらボディソープやらが置かれている棚がある。丁度直樹の目線より少し高い位置に白く長いものがあった。鏡越しに直樹はそれを見た。真っ白なドレスを着た背の高い女がこちらに背を向けて立っている。一瞬、それを視界の端に入れた直樹は、「ぴ」と小さく悲鳴を零してその場に倒れ込んだ。気絶した重い体が引き戸に当たり、そのまま床に向かってずり落ちるようにして彼の体は凭れ掛かった。
しかし、悲しいことに、よりによって、直樹は妹が新しく買ったばかりの真っ白な大判のボディタオルを幽霊と見間違って気絶してしまったのだった。
「さて、シャワー浴びたし、寝るか」
「お、寝るのか。いよいよだな、涼佑」
一方で、シャワーを浴び終えた涼佑は濡れた髪を粗方タオルで拭くと、新しいタオルを枕に敷いて寝る体勢に入る。絢が聞いたらきっと卒倒する行動だろうが、涼佑にとっては洗髪後のいつもの行動だ。部屋の電灯を消して巫女さんに「おやすみ」を言う涼佑に、彼女も同じように返した。