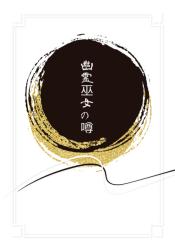「ごめん」と謝った涼佑達は理恵の嗚咽が響く教室を後にして、真奈美達の許へ戻ろうと廊下を振り返った。しゅる、と耳元で衣擦れの音がした瞬間、またしても涼佑は首を物凄い力で締め付けられる。いきなり呼吸が塞がれてしまい、よろけた彼は壁に体当たりをするようにして蹲った。突然、蹲ってしまった涼佑に最初は不思議そうにしていた直樹も、彼が自分の首を押さえている様子を見てすぐ異変に気が付いた。気が動転して自分の首を掻きむしる涼佑の手を何とか退かして見てみる。そこには誰かの制服のリボンタイが巻き付いており、喉に食い込む程の力で締め上げていた。以前の蔦より細いせいか、巫女さんの刀が入り込む隙間が無い。これではたとえ交代したとしても、刀で断ち切ることは難しいだろう。直樹も自分の指くらいが入る隙間が無いか、苦しさから暴れる涼佑を落ち着かせようと声を掛けながら確認しつつ、指を実際に入れ込ませようとしてみるが、やはり不可能だった。どうすればいいのか全く分からなく、涼佑が死んでしまうかもしれないという不安と恐怖から自然と彼も呼吸が浅くなる。それ以上、どうしたらいいのか分からない直樹はおろおろと戸惑うことしかできない。そうしている間に涼佑はあらぬものを見ていた。
直樹の背後に真っ黒い影が立っている。『それ』はただ涼佑を見下ろし、まるで死にかけの虫を愉悦に満ちて見つめている時のような明確な悪意を感じた。今まで『それ』を目にした時はただただ恐怖に支配されていた涼佑だったが、今この瞬間だけは何故、自分がこんな目に遭わなければいけないのかと理不尽な現実に怒りすら湧いてくる。しかし、彼は『それ』を憎しみの込められた目で睨むも、それ以上は何もできずに涼佑の意識は闇の中に溶けていった。
はっと目を覚ました時、涼佑は一瞬自分が死んだのかと思ったが、そうではなかった。意識を失う直前に巫女さんと交代できたのか、今彼の目の前に広がるのは、いつか見たあの異空間。真っ暗な空間には他の何の色も無く、ただ目の前にぽつんと木製のドアが一枚あるだけだった。真奈美がこの光景を見ていたら、きっとすぐにそれが望の部屋のドアだと分かっただろうが、そんなことは知らない涼佑は開けようかどうしようか逡巡する。しかし、こうしてぐずぐずしている間に巫女さんに危機が迫っているのかもしれないと思うと、殆ど後先考えることも無く、開けてしまった。
涼佑の意識が失われる直前に交代できた巫女さんは、忌々しげに首元に短刀を宛がい、無理矢理リボンタイを切る。前と同じように首筋から血を流しながらも、彼女は周囲への警戒を怠らなかった。いつの間にか目の前にいた筈の直樹の姿はかき消えている。否、直樹だけではない。今、この学校から生きている人間の気配は一つとして感じなかった。力を失ったリボンタイをその辺に投げ捨てた彼女は短刀をしまい、腰に提げた刀を抜き、構える。この空間に引きずり込まれた時から肌で痛い程に感じる標的の気配を辿り、巫女さんは理恵達の教室を開けた。
影、基望はそこにいた。机や椅子、教卓も何も無い教室の真ん中でぽつんと棒立ちになり、こちらをじっと見つめていた。その足は溶け、黒い水のように周囲に広がっている。泥で作った人形のように曖昧なシルエットでしか存在していないようなものなのに、びりびりと痺れすら感じる憎悪と殺意が伝わってくる。その髪や指先に相当する部分からぼたぼたと黒い水を落としつつ、望は待ちわびたとでも言うかのように、嗤った。
目の前で無理矢理見せられている光景に、魂だけの存在である涼佑ですら吐き気を覚え、それを抑えるのに必死だった。
一刻でも早く望を成仏させる為にドアを開けた涼佑を迎えたのは、あの葬祭場だった。それも、望に告白された時そのままの光景が忠実に再現されている。一瞬、望の意図が全く読めず、困惑する涼佑の前であの時のように望が告白する。何故、ここで再現をするのかと思っていると、彼女の前に立っている涼佑の姿をした『何か』は優しい微笑みを浮かべて言った。
「うん。オレも好きだよ。望」
「………………は?」
耳を疑う。その『何か』の返答を聞いた途端、この空間がただの再現ではないと気が付いた。幻影の自分の回答に同じく、幻影の望は応える。
「ほんと? えへへ。嬉しいっ。でも、ごめんね。涼佑くん。こんな日に告白なんて」
「別に良いよ。むしろ、こんな人生最悪の日に望から告白してもらえるなんて、オレはなんて運が良いんだろう。受けない理由は無いよ」
「………………………………………………うえっ」
目の前で望を優しく抱き寄せ、額にキスまでしてみせる自分の幻影に心底気持ち悪くなった涼佑は思わず、自らの口を手で覆う。何だこれ何だこれ何だこれ何だこれ。頭の中はその一文だけに侵されているように、それしか考えられない。有り得ない。自分の祖母の葬式に告白されて、こんな返答をする奴はまずいない。どれだけ自分に都合の良い夢を見ているんだ、この女は。そんな怒りと気持ち悪さから涼佑は思わず頭を掻きむしって大声で喚き、苛立ちを発散するように地団駄を踏む。
「ふざっけんなよっ!!!! 気持ち悪ぃ!!」
その声が合図だったかのようにふっと光景が消えて、葬祭場の扉だけが残る。少し休んで漸く吐き気が収まってきてから涼佑は、ドアに近付いた。開けようと手を掛けた時、ドアの表面に何か書いてあることに気が付いた。そこには赤い文字で
幸せになるはずだった
とだけ書いてある。何が幸せだ、と再び自分の心の底から憎しみが湧いてくるのを涼佑は感じていた。とても告白に相応しくない日を選び、相手の都合も考えずに勝手に自分の都合で告白して、振られたら逆恨みのようにつけ回した挙げ句、こんな幻影を見せ付けてくる。最悪の女だ。軽蔑し、吐き捨てるように涼佑は言った。
「こんな奴、オレの手でケリを付けてやる」
胸の辺りがむかむかして思わず、ぐしゃりと握り潰すようにして押さえる。あまりのことに抑えきれない怒りに任せ、涼佑は次のドアを開けた。
びゅっと顔面目がけて伸ばすというより、最早飛ばしてきた望の腕を刀でいなして巫女さんは何とか避ける。そのまま圧し切ろうとしたが、それより早く腕は芯を失って落ちた。今の感触から外側は液体だが、骨組みのような芯が無ければ、動かすことはできないようだ。こいつの思念を止めるにはその芯を断ち切るしかないと判断した彼女は、体勢を低くし、走って一気に距離を詰めようとする。しかし、望もまた半液体の腕を伸ばして阻止しようとし、それを悉くいなして巫女さんは肉薄した。
「消えろ」
首に相当する部位を斬ろうと一閃する。だが、それよりも一瞬早く自ら首を外して躱される。しかし、それを想定していた巫女さんは返す刃で袈裟斬りにした。今度は確かな手応えがあり、切られた断面から黒い水がまるで血のように勢いよく噴き上がる。傷口を気にするように自らの肩を押さえた望を、今度は細い注連縄で拘束し、結界を浴びせてやる。電撃を浴びたように全身を痙攣させて仰け反る望を容赦なく蹴り付けた巫女さんは、水溜まりに倒れた彼女の首にもう一度刃を宛がった。
「お前の核は、どこだ。吐け。吐かなければ殺すぞ」
どちらにせよ、これ以上、思念として生かすつもりはない。自らの形を失う程の恨みを持っている霊が正直に吐くとも思えないが、巫女さんは形ばかりの慈悲をやることにしたのだ。望は何も答えない。もう人の言葉を失ったのか、教える気が無いのか分からないが、巫女さんは決して結界を結ぶ指を緩めない。
「魂を直接痛め付けられるのは、痛いなんてもんじゃないだろ。さっさと吐け。私の手を煩わせるな」
何故、これ程までにこの少女に怒りを感じているのか、巫女さんにはよく分からなかった。よく分からないが、やることはいつもと一緒だ。人の理を外れた者の魂を甚振り、蹂躙し、核を差し出させて消滅させるだけ。そうやってこれまでにも何十人、何百人と存在を抹消してきたのだ。手慣れたものである。
不意に彼女は頭を殴られた。無理矢理首を捻られたのではないかと錯覚する程の強い力に側頭部を打たれ、望と同じように黒い水溜まりの中に倒れる。すぐさま起き上がろうとするが、一瞬上下が分からなくなって取り乱しそうになったが、刀を支えにして上体を起こし、攻撃が来た方を見やる。何もいない。それどころか、さっきまで痛め付けていた望の本体すらいない。消滅した訳ではない。現に巫女さんは依然として妖域の中にいる。その証拠に先程まで浸かっていた黒い水は引いていない。
「逃げたか、隠れたか。ちっ、小賢しい真似を……!」
頭から被った水がドロドロとしていて気持ち悪い。水だというのに実際の感触は泥に近いものだ。濡れて貼り付く前髪を視界が晴れれば何でもいいとばかりに雑に振り払って、巫女さんは再び刀を構え直した。
直樹の背後に真っ黒い影が立っている。『それ』はただ涼佑を見下ろし、まるで死にかけの虫を愉悦に満ちて見つめている時のような明確な悪意を感じた。今まで『それ』を目にした時はただただ恐怖に支配されていた涼佑だったが、今この瞬間だけは何故、自分がこんな目に遭わなければいけないのかと理不尽な現実に怒りすら湧いてくる。しかし、彼は『それ』を憎しみの込められた目で睨むも、それ以上は何もできずに涼佑の意識は闇の中に溶けていった。
はっと目を覚ました時、涼佑は一瞬自分が死んだのかと思ったが、そうではなかった。意識を失う直前に巫女さんと交代できたのか、今彼の目の前に広がるのは、いつか見たあの異空間。真っ暗な空間には他の何の色も無く、ただ目の前にぽつんと木製のドアが一枚あるだけだった。真奈美がこの光景を見ていたら、きっとすぐにそれが望の部屋のドアだと分かっただろうが、そんなことは知らない涼佑は開けようかどうしようか逡巡する。しかし、こうしてぐずぐずしている間に巫女さんに危機が迫っているのかもしれないと思うと、殆ど後先考えることも無く、開けてしまった。
涼佑の意識が失われる直前に交代できた巫女さんは、忌々しげに首元に短刀を宛がい、無理矢理リボンタイを切る。前と同じように首筋から血を流しながらも、彼女は周囲への警戒を怠らなかった。いつの間にか目の前にいた筈の直樹の姿はかき消えている。否、直樹だけではない。今、この学校から生きている人間の気配は一つとして感じなかった。力を失ったリボンタイをその辺に投げ捨てた彼女は短刀をしまい、腰に提げた刀を抜き、構える。この空間に引きずり込まれた時から肌で痛い程に感じる標的の気配を辿り、巫女さんは理恵達の教室を開けた。
影、基望はそこにいた。机や椅子、教卓も何も無い教室の真ん中でぽつんと棒立ちになり、こちらをじっと見つめていた。その足は溶け、黒い水のように周囲に広がっている。泥で作った人形のように曖昧なシルエットでしか存在していないようなものなのに、びりびりと痺れすら感じる憎悪と殺意が伝わってくる。その髪や指先に相当する部分からぼたぼたと黒い水を落としつつ、望は待ちわびたとでも言うかのように、嗤った。
目の前で無理矢理見せられている光景に、魂だけの存在である涼佑ですら吐き気を覚え、それを抑えるのに必死だった。
一刻でも早く望を成仏させる為にドアを開けた涼佑を迎えたのは、あの葬祭場だった。それも、望に告白された時そのままの光景が忠実に再現されている。一瞬、望の意図が全く読めず、困惑する涼佑の前であの時のように望が告白する。何故、ここで再現をするのかと思っていると、彼女の前に立っている涼佑の姿をした『何か』は優しい微笑みを浮かべて言った。
「うん。オレも好きだよ。望」
「………………は?」
耳を疑う。その『何か』の返答を聞いた途端、この空間がただの再現ではないと気が付いた。幻影の自分の回答に同じく、幻影の望は応える。
「ほんと? えへへ。嬉しいっ。でも、ごめんね。涼佑くん。こんな日に告白なんて」
「別に良いよ。むしろ、こんな人生最悪の日に望から告白してもらえるなんて、オレはなんて運が良いんだろう。受けない理由は無いよ」
「………………………………………………うえっ」
目の前で望を優しく抱き寄せ、額にキスまでしてみせる自分の幻影に心底気持ち悪くなった涼佑は思わず、自らの口を手で覆う。何だこれ何だこれ何だこれ何だこれ。頭の中はその一文だけに侵されているように、それしか考えられない。有り得ない。自分の祖母の葬式に告白されて、こんな返答をする奴はまずいない。どれだけ自分に都合の良い夢を見ているんだ、この女は。そんな怒りと気持ち悪さから涼佑は思わず頭を掻きむしって大声で喚き、苛立ちを発散するように地団駄を踏む。
「ふざっけんなよっ!!!! 気持ち悪ぃ!!」
その声が合図だったかのようにふっと光景が消えて、葬祭場の扉だけが残る。少し休んで漸く吐き気が収まってきてから涼佑は、ドアに近付いた。開けようと手を掛けた時、ドアの表面に何か書いてあることに気が付いた。そこには赤い文字で
幸せになるはずだった
とだけ書いてある。何が幸せだ、と再び自分の心の底から憎しみが湧いてくるのを涼佑は感じていた。とても告白に相応しくない日を選び、相手の都合も考えずに勝手に自分の都合で告白して、振られたら逆恨みのようにつけ回した挙げ句、こんな幻影を見せ付けてくる。最悪の女だ。軽蔑し、吐き捨てるように涼佑は言った。
「こんな奴、オレの手でケリを付けてやる」
胸の辺りがむかむかして思わず、ぐしゃりと握り潰すようにして押さえる。あまりのことに抑えきれない怒りに任せ、涼佑は次のドアを開けた。
びゅっと顔面目がけて伸ばすというより、最早飛ばしてきた望の腕を刀でいなして巫女さんは何とか避ける。そのまま圧し切ろうとしたが、それより早く腕は芯を失って落ちた。今の感触から外側は液体だが、骨組みのような芯が無ければ、動かすことはできないようだ。こいつの思念を止めるにはその芯を断ち切るしかないと判断した彼女は、体勢を低くし、走って一気に距離を詰めようとする。しかし、望もまた半液体の腕を伸ばして阻止しようとし、それを悉くいなして巫女さんは肉薄した。
「消えろ」
首に相当する部位を斬ろうと一閃する。だが、それよりも一瞬早く自ら首を外して躱される。しかし、それを想定していた巫女さんは返す刃で袈裟斬りにした。今度は確かな手応えがあり、切られた断面から黒い水がまるで血のように勢いよく噴き上がる。傷口を気にするように自らの肩を押さえた望を、今度は細い注連縄で拘束し、結界を浴びせてやる。電撃を浴びたように全身を痙攣させて仰け反る望を容赦なく蹴り付けた巫女さんは、水溜まりに倒れた彼女の首にもう一度刃を宛がった。
「お前の核は、どこだ。吐け。吐かなければ殺すぞ」
どちらにせよ、これ以上、思念として生かすつもりはない。自らの形を失う程の恨みを持っている霊が正直に吐くとも思えないが、巫女さんは形ばかりの慈悲をやることにしたのだ。望は何も答えない。もう人の言葉を失ったのか、教える気が無いのか分からないが、巫女さんは決して結界を結ぶ指を緩めない。
「魂を直接痛め付けられるのは、痛いなんてもんじゃないだろ。さっさと吐け。私の手を煩わせるな」
何故、これ程までにこの少女に怒りを感じているのか、巫女さんにはよく分からなかった。よく分からないが、やることはいつもと一緒だ。人の理を外れた者の魂を甚振り、蹂躙し、核を差し出させて消滅させるだけ。そうやってこれまでにも何十人、何百人と存在を抹消してきたのだ。手慣れたものである。
不意に彼女は頭を殴られた。無理矢理首を捻られたのではないかと錯覚する程の強い力に側頭部を打たれ、望と同じように黒い水溜まりの中に倒れる。すぐさま起き上がろうとするが、一瞬上下が分からなくなって取り乱しそうになったが、刀を支えにして上体を起こし、攻撃が来た方を見やる。何もいない。それどころか、さっきまで痛め付けていた望の本体すらいない。消滅した訳ではない。現に巫女さんは依然として妖域の中にいる。その証拠に先程まで浸かっていた黒い水は引いていない。
「逃げたか、隠れたか。ちっ、小賢しい真似を……!」
頭から被った水がドロドロとしていて気持ち悪い。水だというのに実際の感触は泥に近いものだ。濡れて貼り付く前髪を視界が晴れれば何でもいいとばかりに雑に振り払って、巫女さんは再び刀を構え直した。