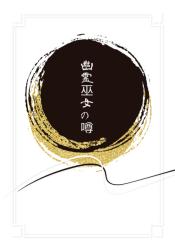死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ね死ねみんな死ね
最初のページはそんな言葉が狂ったように書き連ねてあった。赤いジェルボールペンで殴り書きされたようなその言葉の羅列は、如何に書いた本人の情緒が崩れていたかが分かる。本当に生前の樺倉望から発されたものなのかと疑いたくなるような出だしだ。真奈美が知っている樺倉望とは、いつも本当に凄く大人しい女生徒だった。教室の隅でただただ外の景色を眺めているような、どことなく影の薄い子だ。これを見るまで彼女は密かに望を自分と同じようなタイプの生徒だと思っていたが、そうではなかったようだ。その後のページにも彼女の恨みが綴られている。
この世は地獄だ。何も面白くない。何も楽しくない。全てが退屈で退屈でつまらない。あの女もウザ過ぎて吐き気がする。死ね。みんな死んでしまえ。私を楽しませられない木偶の坊なら、責任を持って死ねよ。親も教師もみんな首吊って死んじまえ。生まれて来たくて、生まれて来た訳じゃない。
最後の一文には、真奈美も少し同調してしまった。真奈美達のような学生でも生きている以上、そんなに楽しいことばかりではない。どんなにささやかなことが原因でも、それが自分の心を追い詰める辛く苦しいことならば、真奈美達にとってはいつだって真剣な問題となる。それは到底、他人に測れるものではない。真奈美もオカルトの研究等と変わったことをしていると、心ない言葉を言われたり、好奇の目で見られることが多いので、そういった周囲の目を気にする辛さというものは分かるつもりだ。そういった辛さや苦しみから逃れる為にストレス発散の為にこういったことを書き散らすのは、ストレス解消法として確かに存在する方法だが、これはそれとは明らかに違うものだと、普段鈍感と言われる真奈美でも分かった。その後のページも同じような恨み言が続き、あるページから少し様子が変わってきた。
あの人に出会った。あの人なら私をこの退屈な世界から救ってくれるかもしれない。あんな優しい人に今まで出会ったことが無い。きっとあの人も私のことを好きになってくれる。いや、絶対そうに決まってる。私も大好き。私の王子様。
「うわぁ……」
真奈美の口からついそんな声が漏れる。赤裸々な内容になってきたので、純粋にこの内容に引いていた。高校生にもなって王子様は無いだろう、という思いと何だか見ている方が羞恥心を煽られるものだと真奈美は自分の顔が熱くなるのを感じていた。もうさっさと終わらせたいと思うが、どこに重要なことが書かれているのか分からない為、一ページずつ確実に読むしかない。次のページも同じような熱いを通り越して暑苦しい程の恋文が続き、またあるページで真奈美の手が止まった。
どうして? 私の何がいけないの? 私はあの人に相応しいはずなのにどうして? あの人も私のことが好きだって言ってくれたのにどうして? あの人なら、私を救ってくれると思っていたのに。許せない。絶対に許せない。私の気持ちをもてあそびやがって。
そこまで読んで真奈美はふと、ページの端を押さえている自分の手元に何か書かれていることに気が付いた。そっと手を退かして、その一文を読む。
復讐してやる
「これね」
ここまで全て読んできて、望の身勝手さを十二分に理解した彼女は、冷ややかな表情でその一文を見ていた。
時を少し遡り、真奈美達が音を立てずに望の部屋へ向かってすぐのこと。友香里は居住まいを正すように座布団へ座り直したところへ、望の母が三人分のお茶を盆に載せて持ってきた。余程、注意力が無くなっているのか、お茶の入っている容器は湯飲みだったり、ティーカップだったり、果ては普段使いであろうマグカップに入れられてテーブルに並べられた。テーブルに並べられて初めて気が付いたのか、彼女は力なく顔を上げ、友香里の隣を見やる。
「ごめんなさいね、こんなものしか無くて。あら、あの子達は……?」
「あ、手ぶらでは何ですからお菓子を買いに行きましたよ」
「あら。そうなの」
友香里の嘘を望の母はあっさり信じた。本来の精神状態でなら、他人の家に行ってから手土産を買って来るなど、そんな非常識なことをする客として違和感を覚えるだろうが、望の母はそれどころではないらしい。『よそのお母さん』という仮面を被るのにも苦労している様子で、それ以上、追及はされなかった。内心、弱っている人を騙しているような心持ちがして、友香里は罪悪感から顔を伏せてしまう。
「あの、望、ちゃんのことなんですけど……」
『望ちゃん』という単語を出した瞬間、みるみるうちに彼女の目は潤み、それは大粒の涙となっていくつも頬を伝った。ほんの少しの間、そうしていたかと思うと、わっと望の母はテーブルに突っ伏して号泣し始めた。
「ごめんなさい……っ! ごめんなさい、望ぃ! 私が……全部私が悪いの……っ! なんにもっ、あの子が悩んでるなんて、なんにも気付かなかったバカな私を許してぇええ……っ!!」
縋るような悲痛な泣き声を聞かされて、友香里は捨て置ける程、冷酷にはなれなかった。むしろ、こんなに自分の母を泣かせ、苦しませる望に腹が立ちさえした。自分にできることは本当に何も無い。けれど、これくらいはしてもいいだろうと、彼女は泣いている望の母の背中をおずおずと撫で始めた。子供を失った母の辛さは、まだ高校生の友香里にはよく分からない。けれど、自分が死んだらきっと自分の母も同じように泣くのだろうと思うと、慰めずにはいられなかった。彼女が泣いている間、真奈美達が戻って来たら大変だと思った彼女は、そっと廊下への引き戸を閉めた。
暫くそうしていると、そのうち望の母は少し落ち着いたのか、涙声で「ありがとう」と言い、友香里の手から離れる。泣いている間、友香里が手繰ったティッシュ箱から一枚取って、涙を拭う。
「ごめんなさい、みっともないところ見せちゃって。はぁ……ほんと、ダメな母親ね」
「いえ、そんなことないです。こういう時は、みんな辛くて当たり前ですから」
友香里の言葉に望の母は意外そうに瞠目したが、それはすぐに羨望の眼差しに変わる。
「優しいのね、あなた。――ごめんなさい、あなたのお名前を知らなくて」
「あ、私、遠藤友香里です」
「友香里ちゃん……。ええ、望もそうだったのよ。あなたと同じように心の優しい子でね。私、何度もあの子に助けられてきたの」
「望ちゃんも、お母さんのこと、大好きだったんだと思います。だから、分からないようにしてたんだと思いますよ」
「分からないように?」
「……さっき、おばさん。『気付かなかった』って言ってましたけど、それは望ちゃんがそうしてたんじゃないかなって思います。お母さんに迷惑とか心配かけないようにって」
「そうかしら」
「きっとそうですよ」
その言葉に望の母は「そうよね」と少しだけ表情が明るくなる。その変化を逃さずに友香里は「そうですよっ」と努めて彼女の明るさを後押しするように言った。
「少しでもおばさんに心配掛けないようにって、隠してたんだと思います。だから、おばさんもその気持ちに応えてあげたら良いんじゃないかなって、私、思います」
「望の気持ちに応える……。そうね。あなたがそう言うなら、そうなんでしょうね」
「望ちゃんの気持ちに応える為にも、強く生きて行かなきゃいけません。だから、元気出してください」
「ええ、ありがとう。友香里ちゃんみたいな子に会えて良かった」
少しだけ吹っ切れたような顔をする望の母を見て、友香里は内心ほっと胸を撫で下ろした。玄関で見た彼女は、今にも死んでしまいそうな程、精神的に追い詰められていたように見えたからだ。
最初のページはそんな言葉が狂ったように書き連ねてあった。赤いジェルボールペンで殴り書きされたようなその言葉の羅列は、如何に書いた本人の情緒が崩れていたかが分かる。本当に生前の樺倉望から発されたものなのかと疑いたくなるような出だしだ。真奈美が知っている樺倉望とは、いつも本当に凄く大人しい女生徒だった。教室の隅でただただ外の景色を眺めているような、どことなく影の薄い子だ。これを見るまで彼女は密かに望を自分と同じようなタイプの生徒だと思っていたが、そうではなかったようだ。その後のページにも彼女の恨みが綴られている。
この世は地獄だ。何も面白くない。何も楽しくない。全てが退屈で退屈でつまらない。あの女もウザ過ぎて吐き気がする。死ね。みんな死んでしまえ。私を楽しませられない木偶の坊なら、責任を持って死ねよ。親も教師もみんな首吊って死んじまえ。生まれて来たくて、生まれて来た訳じゃない。
最後の一文には、真奈美も少し同調してしまった。真奈美達のような学生でも生きている以上、そんなに楽しいことばかりではない。どんなにささやかなことが原因でも、それが自分の心を追い詰める辛く苦しいことならば、真奈美達にとってはいつだって真剣な問題となる。それは到底、他人に測れるものではない。真奈美もオカルトの研究等と変わったことをしていると、心ない言葉を言われたり、好奇の目で見られることが多いので、そういった周囲の目を気にする辛さというものは分かるつもりだ。そういった辛さや苦しみから逃れる為にストレス発散の為にこういったことを書き散らすのは、ストレス解消法として確かに存在する方法だが、これはそれとは明らかに違うものだと、普段鈍感と言われる真奈美でも分かった。その後のページも同じような恨み言が続き、あるページから少し様子が変わってきた。
あの人に出会った。あの人なら私をこの退屈な世界から救ってくれるかもしれない。あんな優しい人に今まで出会ったことが無い。きっとあの人も私のことを好きになってくれる。いや、絶対そうに決まってる。私も大好き。私の王子様。
「うわぁ……」
真奈美の口からついそんな声が漏れる。赤裸々な内容になってきたので、純粋にこの内容に引いていた。高校生にもなって王子様は無いだろう、という思いと何だか見ている方が羞恥心を煽られるものだと真奈美は自分の顔が熱くなるのを感じていた。もうさっさと終わらせたいと思うが、どこに重要なことが書かれているのか分からない為、一ページずつ確実に読むしかない。次のページも同じような熱いを通り越して暑苦しい程の恋文が続き、またあるページで真奈美の手が止まった。
どうして? 私の何がいけないの? 私はあの人に相応しいはずなのにどうして? あの人も私のことが好きだって言ってくれたのにどうして? あの人なら、私を救ってくれると思っていたのに。許せない。絶対に許せない。私の気持ちをもてあそびやがって。
そこまで読んで真奈美はふと、ページの端を押さえている自分の手元に何か書かれていることに気が付いた。そっと手を退かして、その一文を読む。
復讐してやる
「これね」
ここまで全て読んできて、望の身勝手さを十二分に理解した彼女は、冷ややかな表情でその一文を見ていた。
時を少し遡り、真奈美達が音を立てずに望の部屋へ向かってすぐのこと。友香里は居住まいを正すように座布団へ座り直したところへ、望の母が三人分のお茶を盆に載せて持ってきた。余程、注意力が無くなっているのか、お茶の入っている容器は湯飲みだったり、ティーカップだったり、果ては普段使いであろうマグカップに入れられてテーブルに並べられた。テーブルに並べられて初めて気が付いたのか、彼女は力なく顔を上げ、友香里の隣を見やる。
「ごめんなさいね、こんなものしか無くて。あら、あの子達は……?」
「あ、手ぶらでは何ですからお菓子を買いに行きましたよ」
「あら。そうなの」
友香里の嘘を望の母はあっさり信じた。本来の精神状態でなら、他人の家に行ってから手土産を買って来るなど、そんな非常識なことをする客として違和感を覚えるだろうが、望の母はそれどころではないらしい。『よそのお母さん』という仮面を被るのにも苦労している様子で、それ以上、追及はされなかった。内心、弱っている人を騙しているような心持ちがして、友香里は罪悪感から顔を伏せてしまう。
「あの、望、ちゃんのことなんですけど……」
『望ちゃん』という単語を出した瞬間、みるみるうちに彼女の目は潤み、それは大粒の涙となっていくつも頬を伝った。ほんの少しの間、そうしていたかと思うと、わっと望の母はテーブルに突っ伏して号泣し始めた。
「ごめんなさい……っ! ごめんなさい、望ぃ! 私が……全部私が悪いの……っ! なんにもっ、あの子が悩んでるなんて、なんにも気付かなかったバカな私を許してぇええ……っ!!」
縋るような悲痛な泣き声を聞かされて、友香里は捨て置ける程、冷酷にはなれなかった。むしろ、こんなに自分の母を泣かせ、苦しませる望に腹が立ちさえした。自分にできることは本当に何も無い。けれど、これくらいはしてもいいだろうと、彼女は泣いている望の母の背中をおずおずと撫で始めた。子供を失った母の辛さは、まだ高校生の友香里にはよく分からない。けれど、自分が死んだらきっと自分の母も同じように泣くのだろうと思うと、慰めずにはいられなかった。彼女が泣いている間、真奈美達が戻って来たら大変だと思った彼女は、そっと廊下への引き戸を閉めた。
暫くそうしていると、そのうち望の母は少し落ち着いたのか、涙声で「ありがとう」と言い、友香里の手から離れる。泣いている間、友香里が手繰ったティッシュ箱から一枚取って、涙を拭う。
「ごめんなさい、みっともないところ見せちゃって。はぁ……ほんと、ダメな母親ね」
「いえ、そんなことないです。こういう時は、みんな辛くて当たり前ですから」
友香里の言葉に望の母は意外そうに瞠目したが、それはすぐに羨望の眼差しに変わる。
「優しいのね、あなた。――ごめんなさい、あなたのお名前を知らなくて」
「あ、私、遠藤友香里です」
「友香里ちゃん……。ええ、望もそうだったのよ。あなたと同じように心の優しい子でね。私、何度もあの子に助けられてきたの」
「望ちゃんも、お母さんのこと、大好きだったんだと思います。だから、分からないようにしてたんだと思いますよ」
「分からないように?」
「……さっき、おばさん。『気付かなかった』って言ってましたけど、それは望ちゃんがそうしてたんじゃないかなって思います。お母さんに迷惑とか心配かけないようにって」
「そうかしら」
「きっとそうですよ」
その言葉に望の母は「そうよね」と少しだけ表情が明るくなる。その変化を逃さずに友香里は「そうですよっ」と努めて彼女の明るさを後押しするように言った。
「少しでもおばさんに心配掛けないようにって、隠してたんだと思います。だから、おばさんもその気持ちに応えてあげたら良いんじゃないかなって、私、思います」
「望の気持ちに応える……。そうね。あなたがそう言うなら、そうなんでしょうね」
「望ちゃんの気持ちに応える為にも、強く生きて行かなきゃいけません。だから、元気出してください」
「ええ、ありがとう。友香里ちゃんみたいな子に会えて良かった」
少しだけ吹っ切れたような顔をする望の母を見て、友香里は内心ほっと胸を撫で下ろした。玄関で見た彼女は、今にも死んでしまいそうな程、精神的に追い詰められていたように見えたからだ。