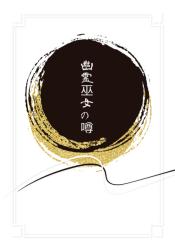家に帰ってから涼佑は宿題をさっさと終わらせて、巫女さんといざという時の為に打ち合わせをしておこうと、ノートとシャーペンを手にする。もちろん、カムフラージュ用に適当な動画を流しておく。もし、望が自分に襲いかかってきた時と説得する時にどういう行動を取るのが適切か、現在の望の状態を教えてもらうと共に打ち合わせておこうと思ったのだ。しかし、巫女さんの反応はあまり芳しくない。
「どうしたんだ? 巫女さん」
「……いや、望はいつもお前のことを見ていると言っただろう? だから、今ここでそういう話はどうしたって、あいつに筒抜けになるんだ。それでも良いんだったら、仕方ないが」
「あ、そう……なのか。――じゃあ、こういう話はできないな。本格的にオレにできることが無い……オレの問題なのに」
「いや、お前にもできることはあるぞ。涼佑」
「え、なに?」
申し訳なさと情けなさに彼が打ちひしがれていると、巫女さんはにっと笑って言った。
「しっかり食事と睡眠を摂って、健康でいることだ」
「何それ? そんなこと、いつもしてるじゃん」
「何か対策になるの?」と先を促す彼に巫女さんは「分かってないなぁ」と言いたげにふふんと鼻を鳴らして、説明する。彼女は案外と教えたがりだ。
「私の宿主であり、悪霊の憑依対象はどうしたって悪霊の影響で体調を崩しやすい。日々の生活によって肉体的にも疲労がある上に、精神的な疲労も普段の倍になる。憑依対象が弱ると、それだけ霊の念力の方が強くなって、対抗できなくなるんだぞ」
「念力? え? 霊ってそんな超能力者みたいなこと、できるの?」
「念力と言っても、少し違うな。霊は死んだ生き物の魂、もちろん肉体なんて無いだろ? それで何故、消えずにいられるのかというと、それは未練だとか執着だとか、要するに『思い』の力が残っているからさ。霊にとって、全てはこの『思い』の力で物を動かしたり、自然を操ったりする。肉体があれば、手でできることを霊は意思の力でやるってだけだ。それが生者にとっては超能力だとか、ポルターガイストだとか、そういう超常的な現象に見えるだけ。実際は肉体が無い分、行動手段が意思の力に移っただけだな」
「――昨日も出てきたけど、そんなに霊にとって、思いっていうのは大事なのか?」
「それが私含め、霊の存在理由だからな。それこそ、自分の存在全てを懸けてもいいと思える程、大事なものだ」
「だが、霊は基本的に生者には勝てない」と巫女さんは続ける。どういうことかと涼佑が先を促すと、彼女は少し寂しげな微笑みを浮かべた。
「肉体が無いからだよ。多くの場合、意思の力だけではそう長くは保たない。そのうち、跡形も無く消えたり、自然と成仏したりする。だが、この世から消える期間というのはその霊が持っている思いの強さによるな。存在の期間と霊の強さはもろに影響を受ける。生者は生命活動をしているだけで基本的に理性もあるし、思考力もある。だから、死者より圧倒的に持っているエネルギーが強い。そんな存在を引きずり込んで殺すには、そのエネルギーを削る必要性が出てくる」
「あっ、だから、霊って脅かしてくるのか。脅かして体力とかを消耗させたりするのが必要ってこと?」
涼佑が結論に辿り着くと、巫女さんは満足そうに笑んでうんうんと頷く。正解できて偉いなと言うような笑顔に、涼佑はまた何となくくすぐったいような感じが湧き起こった。巫女さんは時々、涼佑を慈しむような笑顔を見せるせいで、その度に彼はどう反応したら良いのか分からなくて、戸惑うばかりだった。だが、それも一瞬のことですぐに真剣な顔になった彼女は続けた。
「じゃあ、消えたくないと思う霊は何をすると思う?」
「へ? 消えたくない?」
「誰だってそう思うだろ。自分の力で成仏できない霊が自分の『思い』を遂げるまでどうしたら、存在が消えるという時間制限から逃れるのか。考えるものだろ」
また新たな問題に涼佑は特に捻ることも無く、素直に考えて答えた。
「……もしかして、それが、憑依?」
「そうだ。涼佑、お前はなかなかに物分かりが良いようだな。憑依をすると、霊はそれだけで生者から僅かながらエネルギーを取り込める。憑依した時は霊より生者の方が肉体的・精神的に強いが、憑依した霊が対象者を驚かせたり、不運に巻き込んだり、もっと強くなると呪ったりしていずれ対象者を乗っ取り、殺す。それが悪霊のやり口だ。逆に対象者と共存し、守るのが守護霊の性質だな」
「対象者と共存して守る……ん? でも、巫女さん。巫女さんはオレにお供え物を要求するよな? あれもエネルギーになってるのか?」
巫女さんは特殊な守護霊のせいか、生者と同じように食べ物からエネルギーを摂取してるのかと思った涼佑は内心少し不思議な感じがするが、彼女と食卓を一緒に囲んでいるようで、それはそれで嬉しいと思っていた。尤もらしい彼の意見を聞いた巫女さんは、何故か非常に言いにくそうに口をもごもごさせながら言う。
「ん~……むぅ。あれは、そうだなぁ。エネルギーを摂取、してるとも言えるっちゃあ、言えるが……ん~、まぁ、私が食べたいだけとも言えると言えば、言えるなぁ」
「食べたいだけじゃんっ!」
「んぉ……だって、この世にはまだまだ美味しい物が多いだろ? 私だって、食べたい!」
「……分かったよ。この件が終わったら、何か美味い物食べに行くか」
「やったぁー!」
大人なのか、子供なのかよく分からない巫女さんの反応に、涼佑は「仕方ないな」と自然と笑えた。
最初に涼佑から話を聞いた真奈美は、いつもの依頼と同じだと思っていた。ただ、話を聞いてそれっぽい簡単なおまじないのような儀式をやり、当人の不安を取り除いてやればいいと思っていたが、涼佑を通して巫女さんから話を聞いた彼女の頭を過ったのは、この依頼は少々手こずりそうだという考えだった。当時は彼女を涼佑に憑ければ、後は簡単に解決すると思っていただけに至った結論だ。真奈美は霊感がある訳ではない。何ならそれを信じてすらいない。しかし、それと同じように幽霊が本当にいないかどうか、自分の目で確認したことも無い。だから、答えを見付ける為にいつだって彼女は己の好奇心の赴くまま、あるかどうかも分からないものを見つめ続けることを選んだ。
さて、と出かける準備が整った彼女は玄関を出る直前に絢と友香里に連絡を取ってみることにした。今日は土曜日。幸いなことに登校日ではない。グループメイムで今から出ると送ると、すぐに返事が返って来た。友香里からは「分かった」の絵文字。絢からは「もう着いてる」とメッセージ。
「……早い」
前日、分かれるまで絢が一番口では面倒くさそうにぶつぶつ不満を漏らしていたが、何だかんだで一番やる気があるのも彼女なのだ。それに微かに笑みを零して真奈美は「なるべく急ぐね」と返し、家を出た。
絢達との待ち合わせ場所は真奈美の家に割と近いからという理由で、学校の校門前だ。いつも何かと少し遅れてしまう自分のことを考えてくれたのかと思うと、申し訳ないと彼女は思う。急ぐと言ってしまった手前、走らない訳にもいかず、真奈美は慣れない運動で息を切らしながら向かっていた。家の前のトンネルを抜け、道路沿いに走っていると学校が見えてくる。その頃には大分息が上がっていた真奈美は、少し歩こうかとスピードを緩める。結構な距離は稼いだだろうと思い、歩き始めた。そうして進んでいると、乱れた呼吸が整う頃にはもう校門が見えてくる。そこにスマホを操作しつつ、待っている絢の姿を捉えると、真奈美は小走りで近付いた。彼女の足音で気付いたのか、絢が顔を上げてこちらを見る。
「ごめん、待った?」
「あ、真奈美。ううん、あたしが早く来ちゃったから大丈夫。友香里もそのうち来ると思うよ」
「うん」
先程、小走りしたせいか、また少し息が上がっている真奈美の様子に気が付いた絢が話し掛けてくる。
「もしかして、走って来た?」
「……ふぅ。うん、待たせちゃいけないと思って」
「そんなん、いいのに。……ねぇ、真奈美。真奈美は今回の依頼、どう思ってる?」
「どう?」
絢の顔を改めて見返す真奈美。彼女は少し不安げで同時に、真奈美のことを心配しているようだった。それを真奈美が認識したと同時に絢は「私は正直、もう手を引いた方が良いんじゃないかなって思ってる」と神妙な顔でぽつりと言った。そこで漸く真奈美は先程の電話で彼女が厭にやる気を出していた理由が分かった。こんなことを友香里がいる時に話せば、彼女は絶対に反対するだろうと予想できたからだ。
「どうしたんだ? 巫女さん」
「……いや、望はいつもお前のことを見ていると言っただろう? だから、今ここでそういう話はどうしたって、あいつに筒抜けになるんだ。それでも良いんだったら、仕方ないが」
「あ、そう……なのか。――じゃあ、こういう話はできないな。本格的にオレにできることが無い……オレの問題なのに」
「いや、お前にもできることはあるぞ。涼佑」
「え、なに?」
申し訳なさと情けなさに彼が打ちひしがれていると、巫女さんはにっと笑って言った。
「しっかり食事と睡眠を摂って、健康でいることだ」
「何それ? そんなこと、いつもしてるじゃん」
「何か対策になるの?」と先を促す彼に巫女さんは「分かってないなぁ」と言いたげにふふんと鼻を鳴らして、説明する。彼女は案外と教えたがりだ。
「私の宿主であり、悪霊の憑依対象はどうしたって悪霊の影響で体調を崩しやすい。日々の生活によって肉体的にも疲労がある上に、精神的な疲労も普段の倍になる。憑依対象が弱ると、それだけ霊の念力の方が強くなって、対抗できなくなるんだぞ」
「念力? え? 霊ってそんな超能力者みたいなこと、できるの?」
「念力と言っても、少し違うな。霊は死んだ生き物の魂、もちろん肉体なんて無いだろ? それで何故、消えずにいられるのかというと、それは未練だとか執着だとか、要するに『思い』の力が残っているからさ。霊にとって、全てはこの『思い』の力で物を動かしたり、自然を操ったりする。肉体があれば、手でできることを霊は意思の力でやるってだけだ。それが生者にとっては超能力だとか、ポルターガイストだとか、そういう超常的な現象に見えるだけ。実際は肉体が無い分、行動手段が意思の力に移っただけだな」
「――昨日も出てきたけど、そんなに霊にとって、思いっていうのは大事なのか?」
「それが私含め、霊の存在理由だからな。それこそ、自分の存在全てを懸けてもいいと思える程、大事なものだ」
「だが、霊は基本的に生者には勝てない」と巫女さんは続ける。どういうことかと涼佑が先を促すと、彼女は少し寂しげな微笑みを浮かべた。
「肉体が無いからだよ。多くの場合、意思の力だけではそう長くは保たない。そのうち、跡形も無く消えたり、自然と成仏したりする。だが、この世から消える期間というのはその霊が持っている思いの強さによるな。存在の期間と霊の強さはもろに影響を受ける。生者は生命活動をしているだけで基本的に理性もあるし、思考力もある。だから、死者より圧倒的に持っているエネルギーが強い。そんな存在を引きずり込んで殺すには、そのエネルギーを削る必要性が出てくる」
「あっ、だから、霊って脅かしてくるのか。脅かして体力とかを消耗させたりするのが必要ってこと?」
涼佑が結論に辿り着くと、巫女さんは満足そうに笑んでうんうんと頷く。正解できて偉いなと言うような笑顔に、涼佑はまた何となくくすぐったいような感じが湧き起こった。巫女さんは時々、涼佑を慈しむような笑顔を見せるせいで、その度に彼はどう反応したら良いのか分からなくて、戸惑うばかりだった。だが、それも一瞬のことですぐに真剣な顔になった彼女は続けた。
「じゃあ、消えたくないと思う霊は何をすると思う?」
「へ? 消えたくない?」
「誰だってそう思うだろ。自分の力で成仏できない霊が自分の『思い』を遂げるまでどうしたら、存在が消えるという時間制限から逃れるのか。考えるものだろ」
また新たな問題に涼佑は特に捻ることも無く、素直に考えて答えた。
「……もしかして、それが、憑依?」
「そうだ。涼佑、お前はなかなかに物分かりが良いようだな。憑依をすると、霊はそれだけで生者から僅かながらエネルギーを取り込める。憑依した時は霊より生者の方が肉体的・精神的に強いが、憑依した霊が対象者を驚かせたり、不運に巻き込んだり、もっと強くなると呪ったりしていずれ対象者を乗っ取り、殺す。それが悪霊のやり口だ。逆に対象者と共存し、守るのが守護霊の性質だな」
「対象者と共存して守る……ん? でも、巫女さん。巫女さんはオレにお供え物を要求するよな? あれもエネルギーになってるのか?」
巫女さんは特殊な守護霊のせいか、生者と同じように食べ物からエネルギーを摂取してるのかと思った涼佑は内心少し不思議な感じがするが、彼女と食卓を一緒に囲んでいるようで、それはそれで嬉しいと思っていた。尤もらしい彼の意見を聞いた巫女さんは、何故か非常に言いにくそうに口をもごもごさせながら言う。
「ん~……むぅ。あれは、そうだなぁ。エネルギーを摂取、してるとも言えるっちゃあ、言えるが……ん~、まぁ、私が食べたいだけとも言えると言えば、言えるなぁ」
「食べたいだけじゃんっ!」
「んぉ……だって、この世にはまだまだ美味しい物が多いだろ? 私だって、食べたい!」
「……分かったよ。この件が終わったら、何か美味い物食べに行くか」
「やったぁー!」
大人なのか、子供なのかよく分からない巫女さんの反応に、涼佑は「仕方ないな」と自然と笑えた。
最初に涼佑から話を聞いた真奈美は、いつもの依頼と同じだと思っていた。ただ、話を聞いてそれっぽい簡単なおまじないのような儀式をやり、当人の不安を取り除いてやればいいと思っていたが、涼佑を通して巫女さんから話を聞いた彼女の頭を過ったのは、この依頼は少々手こずりそうだという考えだった。当時は彼女を涼佑に憑ければ、後は簡単に解決すると思っていただけに至った結論だ。真奈美は霊感がある訳ではない。何ならそれを信じてすらいない。しかし、それと同じように幽霊が本当にいないかどうか、自分の目で確認したことも無い。だから、答えを見付ける為にいつだって彼女は己の好奇心の赴くまま、あるかどうかも分からないものを見つめ続けることを選んだ。
さて、と出かける準備が整った彼女は玄関を出る直前に絢と友香里に連絡を取ってみることにした。今日は土曜日。幸いなことに登校日ではない。グループメイムで今から出ると送ると、すぐに返事が返って来た。友香里からは「分かった」の絵文字。絢からは「もう着いてる」とメッセージ。
「……早い」
前日、分かれるまで絢が一番口では面倒くさそうにぶつぶつ不満を漏らしていたが、何だかんだで一番やる気があるのも彼女なのだ。それに微かに笑みを零して真奈美は「なるべく急ぐね」と返し、家を出た。
絢達との待ち合わせ場所は真奈美の家に割と近いからという理由で、学校の校門前だ。いつも何かと少し遅れてしまう自分のことを考えてくれたのかと思うと、申し訳ないと彼女は思う。急ぐと言ってしまった手前、走らない訳にもいかず、真奈美は慣れない運動で息を切らしながら向かっていた。家の前のトンネルを抜け、道路沿いに走っていると学校が見えてくる。その頃には大分息が上がっていた真奈美は、少し歩こうかとスピードを緩める。結構な距離は稼いだだろうと思い、歩き始めた。そうして進んでいると、乱れた呼吸が整う頃にはもう校門が見えてくる。そこにスマホを操作しつつ、待っている絢の姿を捉えると、真奈美は小走りで近付いた。彼女の足音で気付いたのか、絢が顔を上げてこちらを見る。
「ごめん、待った?」
「あ、真奈美。ううん、あたしが早く来ちゃったから大丈夫。友香里もそのうち来ると思うよ」
「うん」
先程、小走りしたせいか、また少し息が上がっている真奈美の様子に気が付いた絢が話し掛けてくる。
「もしかして、走って来た?」
「……ふぅ。うん、待たせちゃいけないと思って」
「そんなん、いいのに。……ねぇ、真奈美。真奈美は今回の依頼、どう思ってる?」
「どう?」
絢の顔を改めて見返す真奈美。彼女は少し不安げで同時に、真奈美のことを心配しているようだった。それを真奈美が認識したと同時に絢は「私は正直、もう手を引いた方が良いんじゃないかなって思ってる」と神妙な顔でぽつりと言った。そこで漸く真奈美は先程の電話で彼女が厭にやる気を出していた理由が分かった。こんなことを友香里がいる時に話せば、彼女は絶対に反対するだろうと予想できたからだ。