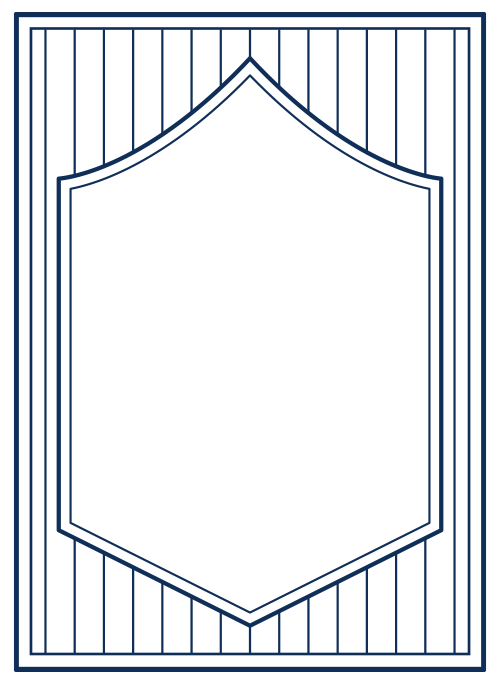桜を見て誰もが想う。
「美しい」「きれい」「ずっと見ていたい」
花見酒に酔う日には、こんな時間が永遠に続けばいいと。
そんな想いと裏腹に、桜は短い春を終えて儚く散る。
その一瞬。そのひととき。そこだけで美しく咲いたとて、そこに何の意味があるのか。
でもその一瞬を私が忘れることは決してない。
その日、私は新しい小説の構想を練ることに苦難していた。
「だめだ……何も出てこん」
真っ白な画面が目の前に広がり、そこには文字ひとつもでてこない。中身のない空虚な時間がただ過ぎていく。
もし、何もしないことで賞をもらえるコンテストがあったのなら、断言できる。あのときなら優勝できる。
そんな空っぽの私が、川のせせらぎとおだやかな桜の香りを求めて動き出したことは私にとって良い選択だったと言えるだろう。
河川のほとりをのらりくらくら。耳に聞こえる水の音。艶やかに連なる桜並木。少し歩けばアイデアなんてすぐに湧いてきそうな完璧なロケーション。
だが悲しいかな。現実はそんなに甘くない。
「歩くだけで湧くなら苦労しないな」
小さく吐く息とともに削りカスみたいな幸せも逃げていく気がする。発想の枯れた木には何も咲かず、桜の色さえ逃げていく。
そんな無機質な世界に――
ふと、風がなびく。
風に誘われ向けた視線の先、桜吹雪の奥。君がいた。
カメラを構えて、シャッターを切る君。
桜吹雪と相まって見えたその姿。正直言えば、とても綺……。
カシャ。
響く機械音で私の意識は現実へと引き戻される。彼女が構えるカメラの目はまっすぐこちらを見据えていた。
「……?」
えっ、もしかしてだけど。
「今撮りました?」
驚くほど率直な疑問。それを聞いた彼女は小首を傾げる。
「はい」
ただ一言、彼女はそう言った。まるで「何を当たり前のことを聞いているのか」とでも言いたげなその様子は私の頭をさらに混乱させる。
「ずいぶん、正直に白状しますね」
「はい。だって、そうじゃないと盗撮になってしまうじゃないですか」
「撮った時点で盗撮では?」
「あなたが認めれば、ただの撮影です」
「じゃあ、私が認めなかったら?」
少しの思案のあと、彼女が小さく微笑む。
「それなら、まぁ、忘れてください」
「意地でも持って帰る気だな!?」
「だってもう私の写真ですもの」
彼女は悪びれる気もないようで、この状況を楽しむように小さく微笑むばかり。やがて思い出したかのように、彼女は再びカメラを覗く。
水と桜にカメラと変わった美女。こういうとき、君はこれをシャッターチャンスと思うのだろう。
では私は?
「ふっ……ははっ……アハハハハ」
叩いても出てこなかった達者な一節が、枯れた木に小さく咲いた。盗撮魔の変なやつ。
でも、突然笑いだしたような私には、君を変なやつと思う資格なんてひとつもない。
やがて愉快な笑いも収まったころ、私は改めて彼女に声をかけた。
◇
それから私は毎日、そこへ足を運んだ。
理由は小説のインスピレーションを得るため。他意はない。
そりゃ少しは「彼女に会えるかもしれない」なんて下心はあったかもしれない。それは認めるさ。
でも決してそれが目的ではない。
逸る心にそう言い聞かせる中、私は彼女を見つけた。
「あら、また会いましたね。先生」
川に沿って設置された手すりに寄りかかり、彼女はこちらを見る。そして首をかしげて続けた。
「ストーカーですか?」
「言うじゃないか、盗撮魔」
「はて、何のことでしょう」
「うらやましい記憶力だ」
小さく微笑みながら、私は彼女と同じように手すりに寄りかかった。目の前には満開の桜が咲いている。彼女と出会ったとき、まだ三分咲きだった桜は見事なまでにその身を広げ、見る者全てを魅了するほどの美しさを見せていた。
「やっと咲いたな」
「はい。綺麗です」
彼女は私に対してずっと敬語を使っている。しかしその声色は出会ったときよりも少しほどけたような印象を受けた。だからこそ、私は彼女にこんな話をした。
「ときどき思うんだ」
彼女が耳を傾ける。
「桜は春になると花を咲かせる。こんなにも美しい花は他にないんじゃないかと思わせる。だけど、そんな花も季節が変わる前の短い間に散って消える」
私は小さく息を吐いて続ける。
「必死に生きて、物語を書いて、人を魅了して。だけど結局、それは一瞬の悦楽にすぎない。そこに何の意味があるんだろう」
こんな話を聞いても、彼女は私のことを優しく見つめていた。そして少しだけ顔を伏せ、考えこむ様子を見せる。やがて顔を上げた彼女はゆっくりと口を開いた。
「一瞬でもいいじゃないですか」
話し始めた彼女と目が合う。
「一瞬でもいい。その一瞬、こんなにも綺麗に咲かせた桜の美しさをきっと誰かが覚えてる。桜も、そう思ってくれた誰かのことをきっと覚えてる。だからまた、季節を跨いで桜を見に来たいって思えるし、桜もまた咲きたいって思える。そうやって想い想われることが繰り返されて、ただの一瞬が永遠になる。そういう考え方も悪くないとは思いませんか?」
変わらない微笑み。変わらない声。
私は妙に恥ずかしくなって、彼女から視線をそらした。顔を上げると、桜のきれいな桃色が心の底に染み渡るようで。
彼女の言葉はあのときの俺には少し、彩りが強すぎた。
「私より小説家が向いてるよ」
私の言葉に彼女が笑った。
「ふふっ……でしょう? でも、私も最近そう思えるようになったんですよ。永遠なんて得る必要がないと思ってたんですから」
「へぇ、その話も聞きたいね」
彼女は私と同じように桜を見上げる。
「それじゃあ、また会ったときにでも」
「それは楽しみだな」
ほんの数日の間柄。それでもこの数日の間、彼女との会話の中で私は心の中が少しずつ色づいていくのを確かに感じている。この一瞬が続いてほしい。そう思ったことを私は否定しない。
だがそれから、私が彼女に会うことはなかった。あの日以降、あの場所に言っても彼女は現れなかった。
満開だった桜も散り、葉桜すらなくなる。桜の木は見事な新緑に覆われる。
彼女は一体誰だったのか。物語を創れなくなった私が作り出した幻覚か。はたまた、桜に宿る精霊だったのか。それとも、ただ暇つぶしがしたかっただけの盗撮魔か。
まぁ、なんでもいい。
一瞬を永遠に。
それを願うなら。
「さぁ、やりますか」
真っ白だった画面に、次々と文字が咲き誇る。
書き続けよう。そうしていれば、いつか一瞬が永遠になると思うから。
◇
河川のほとりをのらりくらくら。耳に聞こえる水の音。艶やかに連なる桜並木。少し歩けばアイデアなんてすぐに湧いてきそうな完璧なロケーション。
ここを歩けば、色々な感情とアイデアが溢れてくる。
ふと、風がなびく。
風に誘われ向けた視線の先。そこにはまた、桜が咲いていた。
「美しい」「きれい」「ずっと見ていたい」
花見酒に酔う日には、こんな時間が永遠に続けばいいと。
そんな想いと裏腹に、桜は短い春を終えて儚く散る。
その一瞬。そのひととき。そこだけで美しく咲いたとて、そこに何の意味があるのか。
でもその一瞬を私が忘れることは決してない。
その日、私は新しい小説の構想を練ることに苦難していた。
「だめだ……何も出てこん」
真っ白な画面が目の前に広がり、そこには文字ひとつもでてこない。中身のない空虚な時間がただ過ぎていく。
もし、何もしないことで賞をもらえるコンテストがあったのなら、断言できる。あのときなら優勝できる。
そんな空っぽの私が、川のせせらぎとおだやかな桜の香りを求めて動き出したことは私にとって良い選択だったと言えるだろう。
河川のほとりをのらりくらくら。耳に聞こえる水の音。艶やかに連なる桜並木。少し歩けばアイデアなんてすぐに湧いてきそうな完璧なロケーション。
だが悲しいかな。現実はそんなに甘くない。
「歩くだけで湧くなら苦労しないな」
小さく吐く息とともに削りカスみたいな幸せも逃げていく気がする。発想の枯れた木には何も咲かず、桜の色さえ逃げていく。
そんな無機質な世界に――
ふと、風がなびく。
風に誘われ向けた視線の先、桜吹雪の奥。君がいた。
カメラを構えて、シャッターを切る君。
桜吹雪と相まって見えたその姿。正直言えば、とても綺……。
カシャ。
響く機械音で私の意識は現実へと引き戻される。彼女が構えるカメラの目はまっすぐこちらを見据えていた。
「……?」
えっ、もしかしてだけど。
「今撮りました?」
驚くほど率直な疑問。それを聞いた彼女は小首を傾げる。
「はい」
ただ一言、彼女はそう言った。まるで「何を当たり前のことを聞いているのか」とでも言いたげなその様子は私の頭をさらに混乱させる。
「ずいぶん、正直に白状しますね」
「はい。だって、そうじゃないと盗撮になってしまうじゃないですか」
「撮った時点で盗撮では?」
「あなたが認めれば、ただの撮影です」
「じゃあ、私が認めなかったら?」
少しの思案のあと、彼女が小さく微笑む。
「それなら、まぁ、忘れてください」
「意地でも持って帰る気だな!?」
「だってもう私の写真ですもの」
彼女は悪びれる気もないようで、この状況を楽しむように小さく微笑むばかり。やがて思い出したかのように、彼女は再びカメラを覗く。
水と桜にカメラと変わった美女。こういうとき、君はこれをシャッターチャンスと思うのだろう。
では私は?
「ふっ……ははっ……アハハハハ」
叩いても出てこなかった達者な一節が、枯れた木に小さく咲いた。盗撮魔の変なやつ。
でも、突然笑いだしたような私には、君を変なやつと思う資格なんてひとつもない。
やがて愉快な笑いも収まったころ、私は改めて彼女に声をかけた。
◇
それから私は毎日、そこへ足を運んだ。
理由は小説のインスピレーションを得るため。他意はない。
そりゃ少しは「彼女に会えるかもしれない」なんて下心はあったかもしれない。それは認めるさ。
でも決してそれが目的ではない。
逸る心にそう言い聞かせる中、私は彼女を見つけた。
「あら、また会いましたね。先生」
川に沿って設置された手すりに寄りかかり、彼女はこちらを見る。そして首をかしげて続けた。
「ストーカーですか?」
「言うじゃないか、盗撮魔」
「はて、何のことでしょう」
「うらやましい記憶力だ」
小さく微笑みながら、私は彼女と同じように手すりに寄りかかった。目の前には満開の桜が咲いている。彼女と出会ったとき、まだ三分咲きだった桜は見事なまでにその身を広げ、見る者全てを魅了するほどの美しさを見せていた。
「やっと咲いたな」
「はい。綺麗です」
彼女は私に対してずっと敬語を使っている。しかしその声色は出会ったときよりも少しほどけたような印象を受けた。だからこそ、私は彼女にこんな話をした。
「ときどき思うんだ」
彼女が耳を傾ける。
「桜は春になると花を咲かせる。こんなにも美しい花は他にないんじゃないかと思わせる。だけど、そんな花も季節が変わる前の短い間に散って消える」
私は小さく息を吐いて続ける。
「必死に生きて、物語を書いて、人を魅了して。だけど結局、それは一瞬の悦楽にすぎない。そこに何の意味があるんだろう」
こんな話を聞いても、彼女は私のことを優しく見つめていた。そして少しだけ顔を伏せ、考えこむ様子を見せる。やがて顔を上げた彼女はゆっくりと口を開いた。
「一瞬でもいいじゃないですか」
話し始めた彼女と目が合う。
「一瞬でもいい。その一瞬、こんなにも綺麗に咲かせた桜の美しさをきっと誰かが覚えてる。桜も、そう思ってくれた誰かのことをきっと覚えてる。だからまた、季節を跨いで桜を見に来たいって思えるし、桜もまた咲きたいって思える。そうやって想い想われることが繰り返されて、ただの一瞬が永遠になる。そういう考え方も悪くないとは思いませんか?」
変わらない微笑み。変わらない声。
私は妙に恥ずかしくなって、彼女から視線をそらした。顔を上げると、桜のきれいな桃色が心の底に染み渡るようで。
彼女の言葉はあのときの俺には少し、彩りが強すぎた。
「私より小説家が向いてるよ」
私の言葉に彼女が笑った。
「ふふっ……でしょう? でも、私も最近そう思えるようになったんですよ。永遠なんて得る必要がないと思ってたんですから」
「へぇ、その話も聞きたいね」
彼女は私と同じように桜を見上げる。
「それじゃあ、また会ったときにでも」
「それは楽しみだな」
ほんの数日の間柄。それでもこの数日の間、彼女との会話の中で私は心の中が少しずつ色づいていくのを確かに感じている。この一瞬が続いてほしい。そう思ったことを私は否定しない。
だがそれから、私が彼女に会うことはなかった。あの日以降、あの場所に言っても彼女は現れなかった。
満開だった桜も散り、葉桜すらなくなる。桜の木は見事な新緑に覆われる。
彼女は一体誰だったのか。物語を創れなくなった私が作り出した幻覚か。はたまた、桜に宿る精霊だったのか。それとも、ただ暇つぶしがしたかっただけの盗撮魔か。
まぁ、なんでもいい。
一瞬を永遠に。
それを願うなら。
「さぁ、やりますか」
真っ白だった画面に、次々と文字が咲き誇る。
書き続けよう。そうしていれば、いつか一瞬が永遠になると思うから。
◇
河川のほとりをのらりくらくら。耳に聞こえる水の音。艶やかに連なる桜並木。少し歩けばアイデアなんてすぐに湧いてきそうな完璧なロケーション。
ここを歩けば、色々な感情とアイデアが溢れてくる。
ふと、風がなびく。
風に誘われ向けた視線の先。そこにはまた、桜が咲いていた。