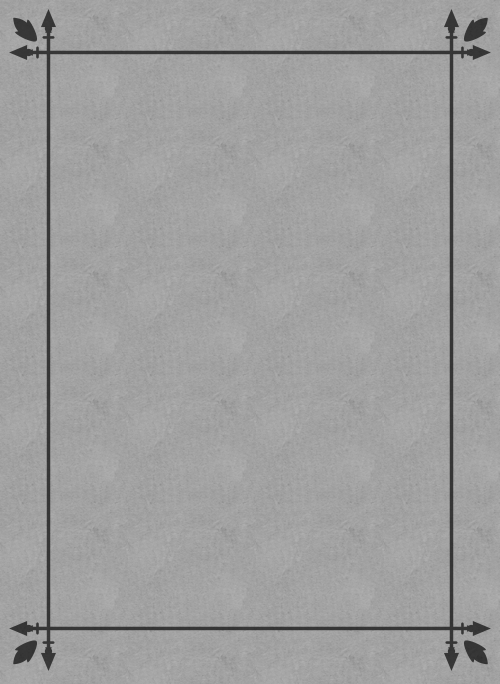一行が盛り上がりを見せた修学旅行の初日が終わり2日目に突入していた。
2日目と3日目は完全な自由時間ということもあり、2年生一行は朝早くから旅館を飛び出していた。
そんな中、昨夜は中々寝付けなかったアオトは、真っ昼間に目を覚ましていた。
今はたった1人で食堂に座り昼食を口にしていた。
「……星宮、少しは元気になったかなぁ」
アオトはせっかくの京都だというのに、普通のカレーライスを食べながらスマホを眺めた。
ハルカから連絡は来ていないが、昨日の別れ際の様子を見る限りは多少は本調子になった気がしていた。
だが、アオトは気がかりだった。
聴けていないことが多すぎる。気になることが多すぎる。疑問が頭の中に渦を巻き、いくら思考を繰り返しても整理をつけられない。まるで、深い泥沼にハマっていくような感覚だった。
「しかも、執筆も全く進まないし……」
この数週間、ハルカとの関係性がギクシャクしていた彼の執筆は、全くと言っていいほど進展していなかった。
現状は80,000文字弱で停滞しており、オリジナルでストーリーを考えようにも思いついていない。
小説を書きたいという意欲は確かにあるのだが、そのきっかけとなる根本が覆された今、頭の中にモヤがかかってしまっていた。
「バッドエンドにはしたくないなぁ」
アオトはここ数週間で起きた数多の出来事を思い出して息を吐く。
彼としてはハッピーエンドを夢見ていたのだが、やはりハルカの内面や心情をより知りたくなっており、それどころではなくなっていた。
そもそも、恋愛経験が全くない彼からすれば、これまでハルカと過ごしてきた時間こそが異様であり、今のような孤独を極める状態こそが正常なのである。
故に、それほど焦りはなかったのだが、アオトはハルカの事を想う自分の気持ちにも理解し始めていた。
そんな事を考えながらも、アオトが黙々とカレーを食べすすめていると、
「……ん? 星宮からだ」
スマホからLINEの通知が鳴った。
佐山から何か連絡があるかと思いここ数日は通知をオンにしていたが、その相手はまさかのハルカだった。
アオトはおもむろにトーク画面を開く。
『降谷くん、今は友達と清水寺に来てるよ!』
メッセージの内容は、清水寺を背景にハルカを含めた数人の女子が映った一枚の写真と、なんて事ない報告だった.
文面からはそこはかとない愛嬌を感じさせた。
——昨日話していた通り、女友達とかと過ごす時は自分を偽ってるんだろうな。
アオトは昨夜、ハルカの自然な笑顔を目の当たりにしていたので、写真に映る彼女の表情に違和感があった。
『随分と楽しそうだな』
『うんっ! すっごく楽しいよ~! 降谷くんはどこにいるのかな?』
『旅館の食堂でカレーを食ってる』
『はぁ? 修学旅行の自由時間なのに、旅館にいるの!?』
文面だけで驚愕が伝わってきた。
『おう。佐山がサッカー部の連中も回ることが決まった瞬間から、俺のひとりぼっちは確定していたんだよ』
朝一番に笑顔で旅館から走り出していく佐山の姿が頭の中に思い浮かぶ。
『悲しいね。でも、昨日は私と過ごせたでしょ? 色々とお話もできたし!』
『そうだな。できればもっと話したかったけどな』
『きっと私のことを知れば知るほど幻滅するよ』
『しないよ』
アオトは即答する。
嘘偽りない本音だった。
できればもっと話をしたいというのもそうだ。
佐山とは既に結託できているので、明日の夜の肝試しで現実となる。
『あっ、それと、前々から描き続けてたイラストを送るね! 仕上げだけスマホでやっちゃったけど割といい感じでしょ?』
『ああ。相変わらず上手だな。本当に綺麗な絵を描いてくれて嬉しいよ』
今のアオトの返信は本心だった。本当にハルカのイラストは素晴らしいと心の底から思っている。
そんなハルカが描いたイラストは昨夜の旅館裏での一幕だった。
月明かりが照らす夜。幻想的な大木の下に置かれたベンチに腰掛ける2人の男女。
その横顔は笑顔を満ちている。
『ありがとー、降谷くんも執筆頼んだよ! コンテストまでは後2ヶ月もないから、また何かあったら連絡して! 私はいつでも協力するから、絶対にすごい小説を完成させようね! またねー』
ハルカからは、可愛らしいウサギのスタンプと共に勢いのあるメッセージが送られてきた。
ものの数秒で行き来する言葉の数々。
テンポの良いやりとりは以前までと何ら変わりない。
むしろ、アオトにとっては昨夜を通して少しでもハルカの知れたので、気持ち的には幾分が楽だった。
「……コンテストかぁ……最近はすっかり忘れてたな」
アオトはスマホを伏せてテーブルに両肘をつき首を垂らす。
戦意喪失とは少し違うが、ここ最近はやる気が著しく欠落していた。
ただ、せっかく描いてくれたイラストを無碍にするのは少々気が引けたし、ハルカと会話を交わすことでやる気がみなぎっていた。
しかし、やはり続きの話を書くのが厳しいのも事実だった。
ハルカとお出掛けもといデートに行けてないのに、恋愛小説を書くというのは彼にとって至難だからだ。
「うーん……」
考え込みながらもカレーライスを食べ終えたアオトは、ハルカから送られてきたイラストを凝視しながら悩む。
すると、背後から足音が聞こえてきた。
彼はおもむろに振り向いたが、既にその人物は彼の眼前にまで迫ってきていた。
「——それ綺麗な絵だね!」
「し、白銀さんっ!?」
アオトは笑顔のカスミから唐突に声をかけられたことで驚くと同時に、反射的に後退しようとして机に背をぶつけてしまう。
あまりの痛みを感じて情けなく顔を歪めた。
「あっ、ご、ごめん! アオく……ふ、降谷くん、大丈夫?」
カスミは笑顔から一転してアオトを憂うような柔和な顔つきになった。
「だ、大丈夫だ。それで……俺に何か用か?」
「うん! 明日、予定が無ければ二人で観光しようよ!」
「え? 俺と?」
「そう、降谷くんと」
「なんで?」
アオトの心の中には少しばかりの疑念があった。
彼はハルカとの一件があってからやや心傷気味なこともあり、どうしても唐突な誘いには乗りづらかったのだ。
「え? 何でって……ボクがそうしたいからだよ?」
カスミはなぜアオトが疑問を呈したのかわかっていない様子だった。
口元に手を当てて首を傾げている。
「……意味がわからないな。もう仲の良い友達はたくさんできてるだろうし、思い出作りにそいつらと一緒に行動したらどうだ?」
アオトは至極真っ当な事を言った。
いくらカスミが転校してきたばかりとはいえ、愛らしい小動物のような容姿と明るい性格のおかげで、既に彼女はクラスと人気者だったからだ。
当然、孤独を極めて退屈な日々を過ごす彼とは相容れない存在だった。もちろん、それはハルカも同様だ。普通に考えたら相容れないはずの両者だった。
「ボクは降谷くんと回りたいの。ダメ?」
「ダメじゃないけど……本当に俺なんかでいいのか? バイトをしてないから大金なんて持ってないし、見ての通り根暗だぞ。それに、話しても楽しくないだろうしな」
上目遣いでカスミからお願いされたことで、純情なアオトは一瞬心が揺らぎかけたが、そんなバカな自分に鞭打つようにして現実的な言葉を言い放つ。
しかし、彼の言葉を聞いた彼女はすぐさま頬をぷっくりと膨らませ、勢いよく首を横に振る。
「そんなことないと思うよ?」
「……そうか?」
「うん。ボクはわかるよ。降谷くんはそんな人じゃないってね!」
アオトからすればかなり関係の浅いカスミだったが、なぜか彼女は確信めいた言い方をしていた。
まるで昔馴染みのような口振りだ。
「そう言ってくれるのはありがたいね。で、白銀さんはどうしてここに?」
「たまたまだよ。昨日は疲れちゃったのか朝起きたら体調が悪かったんだ。だから、今日は旅館で休んでたんだ」
カスミは食堂の窓から外の景色を眺めていた。羨望の眼差しを送っていることから、本当は出かけたかったのだとわかる。
「ふーん」
「興味なさそー」
「……そんなことないぞ?」
「嘘だー!」
アオトは本当に興味がなかったので、そんな安直な嘘はカスミによって容易く見破られた。
彼女はさながら名探偵の如く、ビシッと指を差している。更にはその勢いのあまりポニーテールが揺れている。
——昨日もそうだったが、殆ど話したことがないのに随分とフランクなやつだな。星宮の八方美人とは違うんだろうけど、みんなに平等に接することができるタイプだろうな。
アオトはカスミが持つコミュニケーション能力の高さに脱帽していた。
小説とイラストという共通点がなくとも、こうして話しかけてくるなんて、アオトからすれば信じ難い事実だった。
アオトが1人で思考をしていると、隣に座るカスミは本題を思い出したのか、目を剥いて彼に視線を送った。
「そうそう、降谷くんって、サッカー部の佐山くんと幼馴染って言ってたでしょ?」
「そうだな。あいつとは昔からの付き合いだ」
アオトはカスミがなぜ自分と佐山との関係を聞いてきたのかよくわからなかったが、隠すことでもないので正直に答える。
「そう……他には幼馴染はいなかったの?」
カスミはおずおずとアオトに尋ねる。
彼女が何を知りたかったのか、アオトはよく理解できない。
「まあ、佐山以外にも一応いたぞ。短い付き合いだったけど、仲の良かった男友達が1人だけな」
「男友達なの?」
「ああ。あの時はまだ5歳くらいだったと思うけど、そいつは男らしくて強気な性格だったな。佐山とはまた違う明るさを持ってたよ」
アオトは金ちゃんのことを頭の中に想起しながら答えた。
全ての細かい出来事をはっきりと覚えているわけではないが、金ちゃんの性格と時折見せる悲しげな顔だけは忘れていなかった。
「……あれ?」
「ん?」
「そ、その男友達は今どこにいるのかな?」
「わからない。多分、もう近くにはいないと思う」
金ちゃんの行く末をアオトは何も知らなかった。
元気にやっていることを願うしかない。
「そう……じゃ、じゃあ! 忘れちゃってるだけで他に女の子の知り合いとかはいなかった?」
カスミは間髪入れずに質問をぶつけていく。
物事が思い通りにいかずに焦燥感に駆られているように見えるが、彼女の心情などアオトには全くわからなかった。
「俺に女の知り合いなんて殆どいないぞ」
アオトは即答する。
「殆どってことは少しくらいはいるんだよね?」
カスミはアオトに問いかけながらも、ここにきてようやく彼の隣に腰を下ろした。
「まあ、ほんの少しだけどな」
「ちなみに……その中にボクは含まれてない?」
「……? 白銀さんとは少し前に出会ったばかりだし、こうして話をしたのは3回目とかだからな」
考え込む素振りを見せたアオトの頭の中には、母親や祖母などの親族以外だとハルカの姿しか思い浮かんでいなかった。
どうあがいても、カスミの姿は出てこない。
そもそも知り合ったばかりの彼女が、彼の過去の記憶に入り込んでくることなどあり得ない話だった。
「ふーん……わかったよ! とにかく、明日は2人で色んなところに行こうよ!」
「拒否権は?」
「ないよ。ボクは降谷くんのことを知りたいんだ。絶対に後悔させないから、明日はボクに付き合ってくれると嬉しいな」
「……わかったよ。ちなみに今日これからじゃダメなのか?」
アオトは食堂の壁掛け時計をチラ見した。
「実は昨日のバス移動のせいで酔っちゃってクタクタなんだ……残念だけど、また明日だね」
「そっか、お大事にな。無理はするなよ?」
「うん。ありがと」
アオトは何の気なしに言葉をかけただけだったのだが、当のカスミは照れ臭そうに笑って彼から目を背けると、おもむろに立ち上がり踵を返す。
「それじゃあまたね。明日のお昼前に旅館前に集合だよ!」
「ああ、また明日」
アオトは不器用な笑顔を作ると、静かな足取りで立ち去るカスミに手を振り見送った。
「……はぁ」
またも1人になったアオトは溜め息を吐く。
彼はハルカとの一件のせいで、カスミのことも信用できない自分が嫌になっていた。
同時に、カスミの発言1つ1つが気になっていた。
関係が浅いのに積極的な距離の詰め方と、まるで自分の昔の事を把握しているかのような口振りと質問の数々。
熟考して思い返してみても明らかに怪しかった。
「悪いやつじゃないといいけどな」
アオトは空になった食器を下げて食堂を後にすると、部屋で1人執筆作業にとりかかりはじめた。
一旦、カスミのことは忘れて、スマホのテキストデータに意識を注ぐ。
昨夜の出来事のみならず、ここ数週間で起きた様々なイベントを余す事なく、それでいて隠す事なく文字に変換していく。
経験した事しか書けない彼にとっては、今できる精一杯の執筆だった。
やがて、夕方になり、続々と生徒たちが旅館へと帰ってくる頃。
彼の小説は、これまでの単なる恋愛の妄想だけではなく、拗れゆく人間関係を忠実に表現した、より現実味のある内容に仕上がっていたのだった。
◇◇◇◇
修学旅行の3日目。
場所は昼下がりの活気あふれる京都市内。
アオトは約束の相手と2人並んで市街地を歩いていた。
「今更だけど、どこか行く場所は決まっていたりするのか?」
「昨日、お部屋に戻ってから色々と調べたんだけど、やっぱり京都と言えば歴史だよね。有名な観光スポットもたくさんあるし、スマホで調べながら適当に巡ってみようよ!」
そう答えるカスミは華やかな笑みを浮かべたまま、アオトの左手側の肩に寄り添って距離縮める。
ダボダボのブラウンがかった色味のカーディガンが、ポニーテールと共に揺れている。
意外にも強引な部分があるんだなと、アオトは思う。
「そうだな」
「……昨日は変な質問ばっかりしちゃったけど、今日はせっかくだしたくさん楽しもうね! アオくん」
「おう。まあ、俺はアオくんじゃないんだけどな」
「そうだったね……降谷くん」
カスミはアオトの呼び方を訂正したが、その瞳は曇りなく、言葉は澱みなかった。
そんな彼女の思考がわからないアオトは、溜め息混じりに呟く。
「……アオくん、か」
その呟きは、彼女の耳に届く事なく雑踏の中に紛れて消えていった。
やがて、アオトはカスミのリードに従い、京都の街並みを巡っていく。
2人で並んで石畳の道を歩きながら、京都らしい歴史を感じさせる建物や、古い木造の町屋、緑が茂る庭園を持つ古刹に目を向ける。その風景はまるで時を超えたような雰囲気を醸し出している。
また、秋ということもあり、鮮やかな紅葉が枝を彩り、古い寺院の門から漏れる静けさが心を穏やかに包み込んでいた。
そして、街角には古い茶屋や和菓子店が立ち並び、そこから漂う緑茶や和菓子の香りが、訪れる人々に京都の伝統と風情を感じさせる。道行く人々は着物姿で、古都ならではの風情を漂わせており、建物の一つ一つには、歴史や伝統が刻まれ、そこに触れるだけで、京都ならではの神秘的な魅力が感じられた。
そのどれもが彼にとっては新鮮だった。
彼は内心で不安を感じながらも、隣を歩くカスミの楽しい笑顔に心を奪われ、気が付けば一緒に過ごす時間を楽しんでいた。
彼女の明るさが周囲を明るく照らし、アオトの心にはほのかな希望を灯しているように感じられた。
「……白銀さん」
時刻は夕方になる頃。
人混みの少ないやや外れた通り。
アオトは斜め前を歩き、ずっとにこやかな様子のカスミに声をかけた。
「どしたの?」
立ち止まったカスミは身を翻してアオトの方を向いた。彼女は男勝りな無尽蔵な体力があるのか、未だ元気そうにしているが、当のアオトはインドアな性分が災いして疲れ切っていた。
「今夜は肝試しがあるみたいだし、そろそろ旅館に戻らないか?」
アオトにとって今夜の肝試しは正念場だった。
それは小説の今後の展開についてもそうだが、何よりもハルカとの関係が大きく左右される場でもあるのだ。
「そうだったね。じゃあ、最後に少しだけそこの公園で話してからにしない?」
カスミはいつもの明るく楽観的な口調ではあったが、その瞳は真っ直ぐだった。
まるで、覚悟を決めた兵士のように……言葉には力強い意志が込められていた。
「わかった」
アオトはカスミの後を追って、小さな公園へと向かった。
彼女は迷うことなく錆びついたブランコに乗ると、小さく揺れながら夕暮れ空を見上げている。
ここはブランコや滑り台、鉄棒や水飲み場などがあるだけの何の変哲もない公園だったが、その光景を眺めたアオトはどこかノスタルジックな気持ちに駆られていた。
「今日は……楽しかった。ありがとう」
年季を感じさせる公園の設備時計を一瞥したアオトは、おもむろに口を開く。
照れ臭い言葉ではあったが、初めての映画デートの際に、ハルカから言われたアドバイスを思い出したのだ。
思った事ははっきりと相手に伝える……と。
「ボクの方こそありがとうだよっ! 今夜の肝試しもたくさん楽しめるといいね」
カスミはパァッと花が咲いたような満面の笑みを浮かべた。
しかし、裏表が無さすぎるその表情は、やや心傷気味のアオトの気持ちを疑心暗鬼にする。
「そうだな」
アオトは心象を曇らせながらも端的に相槌を打つ。
「ねぇ、降谷くんは肝試しに参加する相手は決まってるの? 確か、あれって相手が決まっていない人はくじ引きだったよね?」
カスミは恥ずかしがった様子で尋ねた。
「……決まってないな」
アオトは逡巡しながらも嘘をつく。否、それは嘘であり真実でもあった。
本当は決まりきったようなものだった。
内々で佐山と立てた計画が実現すればの話だが。
「え! じゃあ、ボクとペア組まない?」
「悪い」
嬉々とした声色でカスミが誘ってきたが、アオトは間を置かずに断りを入れた。
「……ちなみに、どうして?」
「……」
カスミの問いかけに対してアオトは口を真一文字に閉じる。
「言いたくない?」
「そういうわけじゃないが。あまり深く聞かないでくれると助かる」
アオトは、しょんぼりしているカスミに誤解を抱かせないように優しく宥めた。
「……そう」
アオトの思惑など知らないためか、カスミは物悲しそうに口元に力を込める。
「白銀さん。俺からも1ついいか?」
「どうしたの?」
「もし、答えたくないのであればそれでいいんだが……白銀さんは、どうして俺のことを誘ってくれたんだ?」
アオトは今日という日を楽しく過ごしながらも、心の内ではネガティブな疑念が僅かに残り続けていた。
「昨日も言ったでしょ? ボクが一緒に過ごしたかったからだよ」
「それじゃあ具体的にはどうしてだ?」
アオトはわからなかった。どうして彼女が転校初日から今に至るまで、フランクな態度で距離を詰めてきたのか。
「具体的にかぁ……」
カスミは小さく揺れるブランコの動きを足で止めてアオトを横目で見る。
考え込むような顔つきだ。
「できれば、教えてほしい」
「んー……わかったよっ。じゃあ、まずは降谷くんが思い出せるように、ボクの子供の頃の話でもしようかな」
カスミは再びブランコを漕ぎ始めると、今度はぽつぽつと言葉を紡いでいく。
「子供の頃、ボクはこんな小さな普通の公園が遊び場だったんだ」
子供をあやすようなその柔らかな語り口は、アオトの耳にスッと入ってくる。
彼女の子供の頃の話を聞いて、何を思い出すのか、何がわかるのか、それは今の彼では理解が及ばなかった。
「大切な友達がいてね、すぐ離れ離れになっちゃったけど、それはボクにとってはかけがえなくて、今でも忘れられない思い出なんだよ。あの時は家に帰るのが本当に嫌だったから、尚更ね?」
「そうか」
端的なアオトの相槌は、錆びついたブランコが揺れる音でかき消される。
カスミは尚も言葉を続けるが、俯きがちなその瞳は確かに潤んでいた。
「あの時のボクは家に居場所がなかったんだ」
「どうしてだ?」
「みんな助けてくれなかったんだよ。お酒を飲んで暴れるパパのせいで、ママはずっと怖くて震えてて、保育園の先生もボクの話を信じてくれなくて、近所のおばさんも笑って流すだけ……でも、1人だけボクが苦しんでることに気付いてくれた人がいたんだ。ずっと誰も助けてくれなかったから、ボクは必死に明るく振る舞って強がってたのにだよ。それって凄いと思わない?」
アオトはブランコを漕ぐカスミのことを目で追った。
そして気がついた。彼女の頬が涙で濡れていることに。
「そう、だな……その人は、きっと凄く優しいんだろうな」
アオトは同情を示して答える。
「うん。だから、とっても嬉しかった。あの時にボクは決めたんだよ。必ずまた会って、絶対に恩返しをするってね。その人はボクにとっての命の恩人なんだ」
「会えるといいな」
「うんっ!」
アオトが微笑むようにして言葉を返すと、カスミも小さく笑いながら嬉しそうに答えた。
その最中、アオトは視線を落として考え込む。
彼は、自分はカスミの過去の話を全く知らないはずなのに、記憶の片隅をくすぐられるような妙な既視感を覚えていた。
まるで……自分もその過去の世界に深く関わっているんじゃないかと思うくらいに。
「ねぇ」
「……?」
思考を続けるアオトだったが、カスミに声をかけられることで我に返る。
カスミはブランコから飛び降りており、小さな歩幅で、柔らかい足取りで、アオトの前にやってきていた。
彼は目の前に立つ彼女の姿を見上げると、彼女が夕焼けを背景に頬を染めていることに気がついた。
刹那の合間に、過去の記憶が頭の中を駆け巡った。
その瞬間、互いの思考が重なり、アオトとカスミは視線を交わして息を呑む。
そして、アオトは記憶の中枢から手繰り寄せたある人物を名前を口にしようとした。
ここには決しているはずのない……幼い子供だった、あの頃を共に過ごしたあの子の名前だ。
「降谷くん」
「……」
名前を呼ばれたアオトは、息を呑み首肯する。
これからカスミの口から紡がれる言葉への期待が胸に宿る。
心臓は彼女にも聞こえてしまいそうなほど大きく高鳴り、2人の間にはえも言えぬ緊張感のある空気が流れていた。
しかし、そんな2人が味わう特別な時間は、突然の来訪者によって徒労に終わる。
「——あー、疲れたねぇ~」
「だね~、もうそろ帰る? 今日は肝試しだしね」
「そうしよっか。ちょっと休憩したら帰ろーかー」
「さんせーい!」
高めのテンションで公園に立ち入ってきたのは、5名の女子生徒たちだった。
彼女らはブランコにいるアオトとカスミには気づかずに、斜め向かいに位置する離れたベンチに向かっている。
「あれ? 晴香ちゃんはいないのかな?」
カスミがぽかんとした顔でアオトを見る。
それもそのはずだ。あの女子たちは普段はハルカを筆頭につるんでいるため、その中心にハルカがいないのは不思議だった。
「確かに……あの辺の女子と星宮は結構仲良くしてたはずだけどな」
疑問に思ったアオトが頷いたその時。
何を感じ取ったのか、5人の女子のうちの1人がおもむろに背後を振り返ると、アオトとカスミの姿を見つけて「あっ!」っと叫んだ。
同時に他の4人もアオトとカスミがブランコにいることに気がつき、ニヤニヤと興味ありげな笑みを浮かべながらにじり寄ってくる。
「あーあー! かすみん! まさか、降谷くんと付き合ってるの!?」
「ボ、ボク!?」
1人の女子が肘で小突くと、カスミは慌てふためく。
「かすみんしかいないじゃーん。で、どうなの!」
「ボクは……べ、別にそんな関係じゃないよ!?」
「あら~、顔真っ赤にしちゃって! 降谷くんはどうなのさー」
「え? 俺?」
唐突に話を振られたアオトは間抜けな顔になる。
「うわぁ! 喋った!」
「声初めて聞いたね」
「珍獣かなんかだと思ってないか?」
アオトは溜め息混じりに言う。
彼は目の前に立つクラスメイト、5人の名前を把握していなかったので、向こうから認識されていることにも内心は驚いていた。
「珍獣と同じだよ? みんな声聞いたことないし……ってか、意外にも良い声してるね。近くで見るとやっぱりルックスも悪くないかも……」
「そりゃどうも……」
「《《アオくん》》! 謙遜しないで喜んでもいいんだよ?」
ぶっきらぼうなアオトの返事に被せるようにして、カスミは急に立ち上がり前に躍り出た。
彼女らの発言に強く同意をしているのか、首を縦にぶんぶん振っている。
「え!? 今、アオくんって呼んだ!?」
「ね! 呼んだよね! うわぁ……やっぱり2人ってそうなんだ。いやぁ、降谷くんってば意外にもモテモテだねぇ」
女子たちはなぜか拍手すると、カスミは照れ臭そうに顔を赤くして笑う。
手のひらを横に振っていることから、多分彼女は別にアオトのことを好きではなさそうだった。ただ、どこか並々ならぬ思いを抱いているのは確実だった。
そんな収拾がつかない展開の連続に、アオトは辟易していた。
彼からすれば、カスミが自分のことをアオくんと呼ぶのは2度目なので気にしない。
そんなことよりも、聞き逃せないワードが散見されたので、彼は自ら聞いてみることにした。
「なぁ、モテモテってどういうことだ? 誰かと勘違いしてないか?」
「ほんっとに申し訳ないんだけど、あたしたちも最初は勘違いかと思ったよね?」
「冗談かネタだと思ってたんだけど……ところがどっこい、降谷くんの事をいいなって思う人がもう1人いるんですっ!」
彼女らはごくごくナチュラルに失礼な事を言っていたが、かくいうアオトは気にも止めず続けて質問する。
「ふーん……誰だ?」
「あ、やっぱ気になる?」
「まあ……一応、興味がないといえば嘘になる」
アオトが真剣な眼差しを彼女らに送る。
恋愛経験がないアオトは別に恋愛恐怖症なわけではない。単に前向きになっておらず、縁遠かっただけだ。
「ふふふふふふふふふふ……知りたい?」
「知りたい」
アオトは知りたかった。朴訥な自分に好意を持つのはどんな相手なのか。
「本当に?」
「知りたい」
アオトは食い気味に答える。
焦りはないが好奇心は高い。
どうしても前のめりになってしまう。
そろそろ教えてくれるだろうか……と、アオトは息を呑む。
しかし、そんな彼の意に反して、
「教え……ない! ごめんね~、さすがにうちらだけの恋バナは教えられないわ~」
女子たちは口で雑なドラムホールを奏でてから、期待を裏切ってきた。
爽快な顔つきだ。アオトを焦らして楽しんでいたのだろう。
「……まあ、そうだよな。人にそういう話をするのって勇気がいることだし、そんな内緒話を無碍にはできないよな」
「そういうことー、大事な友達だからね! 勝手に言いふらしたりはしないよ」
女子の1人は至極真っ当な事を言ったが、それを守れる友達と守れない友達とでは大きく異なってくるので、きっとアオトに好意を寄せているというその友達は、さぞみんなから好かれているのだろう。
「かすみんがいる前でライバルを作るような発言もできないしね」
「ラ、ライバルって、ボクは別にそんな風に思ってるわけじゃ……」
カスミは唇を尖らせる。文句を言いたげな様子だ。
「……よくわからないけど、もう帰ろうぜ」
アオトはブランコから立ち上がり呆れ混じりに息を吐く。
一連のやり取りは結局終着点が見つからないまま、これにて終わりを迎えたが、彼女らはおもむろにスマホを見ると一様に考え込み始める。
「そだねー。晴香の事も気になるしねー」
「LINEは返ってきてるけど、元気かな?」
「んー、晴香って割と体弱い方だからねぇ……ちょっと心配かも」
「星宮は体調不良かなんかか?」
「うん。降谷くんは何か知ってたりする?」
「いや、特には」
アオトはポケットからスマホを取り出したが、ハルカからの連絡は入っていなかった。
「そっかー」
「……星宮が体調不良になったのは今朝からか?」
自分なんかが聞くのはどうかと思ったが、アオトは彼女らに詳細を尋ねた。
「ううん、昨日? いや、一昨日の夜からかな? まあ、最近の晴香は張り詰めた感じだったしねー」
「言われてみると、晴香って普段から気が休まってないっていうか、いつでもどこでも明るい感じだよね。それが晴香らしいって言われたらそうなんだけど……でも、愚痴も弱音も聞いたことがないから心配になる時は多いよね」
1人が言うと、もう1人が同調した。
それは、傍目から見てもハルカが疲弊していることを表している。
「ねー、しかも、なんかこうちょっとだけ距離を感じるから、あたしたちとしてはもっとリラックスしてほしいかな。愚痴なら聞くし、相談にも乗るし、何でもいいから悩みがあるなら言ってほしいし」
口振りからして、彼女らはハルカが自分を偽るとまではいかなくとも、どこか心を開ききっていなくて、本当の姿を曝け出していないということに気が付いているようだ。
それは別に察しが良いというわけではなく、彼女らから見た星宮晴香という存在は、それほど親しい友人だということだ。
故によく見ているし、心のうちを理解している。
同時にもっと仲良くなりたいとも思っているはずだ。
アオトが初日の夜にハルカから聞かされたカミングアウトとは、少しばかり認識に齟齬があるようだった。
ハルカに何が起きて彼女の思考を歪ませたのか、それはアオトにはわからなかったが、とにかく彼女が変に取り繕う必要はなく、交友関係には問題がなさそうだとわかる。
そうとわかれば、アオトのやることは決まっていた。
彼は思考を中断してスマホを手に取る。
『今夜の肝試し、もし、体調が良さそうなら来てほしい』
アオトはそれだけメッセージを送ると、すぐ隣に佇んでいたカスミに目を向ける。
気がつけば、5人の女子たちは既に踵を返して公園からいなくなっていた。
「……白銀さん、色々と積もる話もあるだろうけど、いったん旅館に戻ろうか」
「うん……でも、ボクはきちんと言葉にして伝えるからね」
カスミは覚悟を決めたように力強く首肯した。
「ああ」
アオトはカスミと並んで旅館への帰路に就く。
その際、互いに思っていたことは一緒だった。
しかし、改まると妙な緊迫感が生まれてしまい、その話については自然と流れていった。
◇◇◇◇◇
雑木林は夜の暗さに包まれ、微かな月明かりが木々の間から差し込んでいる。
地面には落ち葉が敷き詰められ、足音が響くたびにカサカサと音を立てる。
乾いた秋の夜風は、陰険で暗い雰囲気を一層引き立てる。
そんな中、アオトは俯きがちになりながらも、斜め前方に佇むハルカの後ろ姿を横目で見ていた。
浴衣ではなく私服だ。上にはかなりオーバーサイズなチャコール色のパーカーに下はジーンズ。映画を見た時とは違い、この時期なら特に違和感のない格好だった。
かくいうアオトも同様で、上は厚手の黒いジャケットに、下は普通のスラックスを履いていた。全身黒だ。
ちなみに、浴衣姿なのはテンションの高い佐山だけだった。
「……」
アオトな周囲を見ることで自分を落ち着かせようとしたが、やはり心臓は僅かに高鳴り続けており、それは恐怖とは無縁の感情だった。
周囲にはもう10名ほどの生徒しかいない。
ペアが決まったカップルや仲の良い男女は序盤で出発しており、今はペアの決まっていない男女のクジ引き中だった。
彼ら彼女らは、さして肝試しに興味はないのか、退屈そうに順番を待つだけだった。
「——アオト」
「佐山」
アオトに声をかけてきたのは友人の佐山だった。
彼は青との耳に顔を近づけると、こそこそと小さな声で言う。
「根回しはしておいたぜ。次くらいに呼ばれるから、そん時に星宮さんと話してこいよ」
「サンキュー」
「おう」
佐山は礼を言ったアオトにウインクを見せると、そのまま踵を返して離れていく。
どっかの変態男の後輩だからキザに見える瞬間もあるが、それでもその内面に見え隠れする彼の人の良さがアオトは好きだった。
「……白銀さんもまだペアが決まってないのか」
アオトは佐山から視点を移して、今度は少し離れた位置にいるカスミの姿を捉えた。
彼女は考え込んだような深刻な顔つきだった。
彼には彼女が何を考えているのかわかっていたが、今それを解消してあげることはできなかった。
だが、また話す。そう約束した。
「ふぅ.…」
再びアオトは息を吐く。
今度は単純な深呼吸だ。
息を吐く度に、緊張が少しずつ和らいでいく。
その時、肝試しの順番が回ってきた。
佐山の友人であろう男子生徒が、ガサゴソとクジ箱の中を右手で漁ると、2枚の紙を開いてその名を読み上げる。
「降谷と星宮さんのペアねー。何度も言ってるけど、かなり暗いし足元がぬかるんでるから気をつけてなぁ」
大勢の中であればハルカとペアを組む相手が誰なのか、そこに興味が向くのだが、幸いなことに周囲に残された生徒は10名を切っていた。
ただ、当のハルカはというと、アオトとペアになることをここで初めて知ったからか、驚いた表情で彼に目を向けていた。
ハルカの表情には驚きが顕著に表れており、微笑みはない。
むしろ、緊張感を示すかのように視線がきょろきょろと動き、明らかに動揺している様が見て取れる。
アオトは出来レースみたいなことをして申し訳ないと思いつつも、そんなハルカのことを落ち着かせるために距離を詰める。
「星宮、よろしく」
「……うん」
ハルカは弱々しく返事をする。
「体調は平気か?」
「大丈夫……LINEが来てびっくりしてたけど、まさか全部仕組んでたの?」
「さあ?」
ハルカは瞳を細めながら疑ってきたが、アオトは素知らぬ顔で惚ける。
そして、雑木林の入り口へ向けて先んじて歩き出す。
「んじゃ、いってらー」
男子生徒が2人に1個の懐中電灯を渡す。
同時にテンポよくクジを引き、次のペアを告げる。
「次は、おっ、佐山と白銀さんか。準備しておけよー」
「俺の出番か! 白銀さん、よろしくぅ!」
「よ、よろしく……」
「ありゃ? 俺ってば嫌われてる?」
背後から呑気な佐山と元気のないカスミの声が聞こえてきたが、アオトは左隣に立つハルカと共に雑木林の中へ足を踏み入れた。
雑木林の中はより陰険な雰囲気が漂っていた。
夏に取り残された虫が小さく鳴き、夜風に煽られて木々が揺れる。
ただ、佐山の情報によると、ゴールは一直線に十分くらい進んだ先の開けた道らしく、道中に教員が潜んでいたりするわけでもないとのこと。
つまり、単なる思い出作りの場として設けられているイベントなので、ゴールするその時までは2人きりということだ。
あらかじめそれを知っていたアオトは、ゆったりとした足取りで歩みを進めていく。
「……寒くないか?」
「うん」
ハルカは手を前にして肩を縮こまらせて答える。
寒がっているというよりは、アオトに遠慮しているように見えた。
ただ、様相はいつもの明るい雰囲気を残している。
「星宮」
「何かな?」
ハルカは作り物の笑顔を張り付けるが、アオトにはそれが偽物だとすぐにわかった。
「星宮は……本当の星宮はどんなやつなんだ?」
歩みを進めながら尋ねる。
「どういうこと?」
ハルカは快活な様子は見せずに言葉を返す。
「本当の姿を偽ってるとか何とか言ってただろ。素の姿はどんな感じなんだ? 前みたいな、ただテンションが低くて元気がない感じではないだろ?」
「……1人の時はずっとあんな感じだよ」
「じゃあ、どうしてそこまでして自分を取り繕うんだ?」
表面的な彼女の一部分は理解したつもりだったが、核心に迫る彼女の内面については何も知らなかった。
あまり他人に関心がないアオトだったが、どういうわけかハルカのことを知ってみたくなっていた。
「前も言ったけど、みんながそういう私を望んでいるから。そうしないと嫌われるから。そうしないと私が満足できないから……結局、私は誰かに嫌われたくなくて、誰かに認められたいんだよ。そうしないと生きられないの。悪い?」
「悪くない。ただ、理由が知りたい」
「理由……」
ハルカはぼそりと口にした。
アオトに真意を明かすことを躊躇しているのか、それともそんな心象ではないのか、口元には少しばかり力が入って迷いがあるように見えた。
「教えてくれないか」
アオトは優しい声色で再度聞く。今度はその目を捉えて離さない。
「……いいよ」
ハルカは決意を固めたのか、ふと立ち止まり自身の胸に手を当てる。そして、何を思ったのか、肌寒い気温だというのに上に着ていたパーカーを脱ぎ始めた。
ハルカはパーカーを地面にそのまま放り投げた。
下にはタンクトップを着ており、彼女の肌が露わになる。
刹那。アオトは言葉を失った。
「っ!」
その肌には生々しい深い傷跡が無数に刻まれていたからだ。
あたかも過去の凄惨な出来事がそのまま彼女の肌に刻み込まれたように、それらの傷跡は静かに彼女の人生を語っているようだった。
「……醜いでしょ? 全部、子供の頃にパパから虐待された時につけられた傷だよ。きみが見た右肘の火傷の痕はほんの一部に過ぎないんだよ。どう? 引いた?」
ハルカは悲しげな笑みを浮かべてアオトの目を真っ直ぐ見つめる。
「……」
息を呑むアオトは言葉が出てこなかった。
醜いとか汚いとかそういう話ではなく、単純にハルカの肉体に刻まれた痛々しい傷を思うと涙が溢れそうになっていた。
だが、何も言わないアオトの様子を見た彼女は、途端に寂しそうに嘆息すると、
「やっぱり……見せるんじゃなかった」
アオトに背中を向けて膝を丸めた。
泣いているのか、膝の間に顔を埋めて鼻を鳴らしている。
「悪い」
「……何が?」
「俺は……星宮が苦しんでいることにずっと気付けなかった」
アオトはハルカと過ごした出来事を振り返ってみると、虐待という言葉が連想される彼女の仕草や所作が思い出された。
「きっと辛かったよな。俺には想像もつかない経験をたくさんしたはずだ」
「……降谷くんにわかる? 私の痛みが」
「わからない」
「じゃあ——」
「——でも、理解してあげることはできる。そして、寄り添ってあげることも……」
アオトは右手に持つ懐中電灯を投げ捨てると、しゃがみ込むハルカに自身が羽織っていたジャケットをかけた。
らしくないことをしている自覚はあったが、それでも、今にも消えてなくなりそうな彼女のことを放っておけなくなっていた。
「っ……!」
ハルカは驚嘆して勢いよくアオトに視線を向けた。
「誰も星宮を幻滅したりはしない。それは別に俺だけじゃなくて、いつも一緒にいる友達もそうだ」
「……あの子たちはわかんないよ? 今日もどうせ私がいないところで悪口言ってたんだろうし」
「5人組のことなら心配いらない。むしろ、星宮が悩み事も相談事も愚痴も聞かせてくれないから、自分たちが信頼されてないんじゃないかって憂いてたくらいだ」
アオトはつい数時間前のやりとりを思い出す。
確かに彼女らはハルカのことを心配していた。ハルカがどう思うかは別として、向こうはハルカのことを大切な友達だと認識していたのは確かだった。
「うそ」
「本当だ」
「……どうして、どうして降谷くんは、そこまでして私の事を知りたがってるの?」
ハルカは静かに立ち上がると、肩にかけられたジャケットと一緒に自分の身を抱きしめた。背の高いアオトのことを見上げて瞳を潤ませる。
それは怯えか、単なる疑念か、とにかく複雑な感情が入り混じった表情だった。
「俺が恋愛小説を書きたいって思ったのと同じだ」
「え?」
「俺は、興味が湧いた物事はとことん追求したいタイプなんだ。星宮は何を思って俺に話しかけてくれたのか、星宮はどうして俺にイラストを描いてくれるのか、星宮はどうして自分を偽っているのか……全部知ってみたくなったんだ」
アオトはハルカのことを知りたかった。
邪な思いではなく、単純に星宮晴香という人間が気になっていた。心に残り続けていた。だから、追求を重ねた。そしてようやく知ることができた。
「……ねぇ、それってさ……」
ハルカはハッとした顔つきになる。
何かに気付いたようだったが、アオトにはさっぱりだった。
「ううん……なんでもない。でも、ありがとう。私、降谷くんのおかげで変われた気がする」
「そりゃ良かった」
ハルカが何か言い淀んだ気がしたが、アオトは感謝を伝えてきた彼女に笑顔で返す。不器用だった彼の笑顔はいつしか自然な笑顔になっていた。
彼の笑顔を見た彼女も一緒に笑い、陰険な2人の間に立ち込めていた妙な空気感は、一瞬にして振り払われていた。
今はまるで、爽やかな草原の上にいるかのような雰囲気だった。
「……あーあ……子供の頃に降谷くんと出会ってたら、私に手を差し伸べてくれたのかなぁ~」
ハルカは冗談めかして言った。
「どうだろうな」
「きっと、降谷くんなら気付いてくれたよ。ね?」
「……まあ、子供の頃に一緒に遊ぶような仲だったなら、どうにかしてやることができたかもな」
アオトは幼い頃の記憶を想起する。
もしも、あの時にハルカとも出会うことができていたら、もしかすると……。
「うん、私もそう思うよ。それじゃあ、ゴールまで歩こっか。楽しくおしゃべりしながらね!」
「ああ。その前にジャケットを返してくれ」
「えー、せっかくかけてくれたのにー?」
ぶつくさ言うハルカは既にジャケットに袖を通し終えており、前のジップを閉めてボタンまで止めていた。
サイズが合っていないため着せられている感が出ているが、彼女自身はそれはもう満足そうだった。
「俺が寒いんだよ」
「パーカー着ていいよ?」
「地面がぬかるんでるせいで泥だらけだろ……まあ、いいけど」
アオトは地面に投げ捨てられていたチャコール色のパーカーを拾い上げると、軽く泥汚れを払ってからすっぽりと着た。オーバーサイズなだけあって着心地は良い。むしろ違和感がない。
それから、アオトとハルカは雑木林の陰険な雰囲気など気にも止めず、小説やイラストの話をしながらゴールを目指したのだった。
ゴールをした2人のことをハルカの友達が出迎えたが、彼女らは2人の服装が変わっていることには気付かなかった。
まあ、ハルカの表情が過去一で緩んでいたことから、すぐに怪しまれて言及はされていたが……運良く騒がしい佐山とカスミがゴールしてくれたため、話は流れていくことになったのだった。
◇◇◇◇◇
修学旅行が終わると、2年生には1週間の休みが与えられた。
すっかり夏が終わりを迎えたのがつい最近。
秋口かと思い肌寒くなったのもつい最近。
そんな束の間、既に北海道は初冬に突入しており、今日はついにはらはらと細かな雪が降り始めていた。
気温がまだ下がりきっていないので積もることはないが、やはり冬の冷気は特別だった。
「……寒っ」
「おいおい、そんな薄着じゃ風邪引くぜ? 子供ん頃みたいに丈夫じゃねぇんだからよ」
アオトは公園のベンチに腰掛けて曇天模様の空を眺めると、右隣に座る佐山が彼の肩を叩いて朗らかに笑う。
何枚も厚着をしている佐山に対して、アオトはチャコール色のパーカーを着ているだけだった。
「それより……まだ来ないのか? もう約束の時間は過ぎてるぞ?」
アオトは公園の時計を見た。時刻は午後3時。
「まあまあいいじゃねぇの。思い出の3人が懐かしの公園に集合するんだし、しかも女の子には俺たちにはわからない準備の時間が必要だろ?」
「それもそうか。にしても、驚いたな。お前が少し話しただけで気付くなんてな」
「んー、ちゃんとした確信はなかったんだけどよ、フィーリング的なやつですぐに分かったぜ。だって、笑った時の顔とか、肝試しすらリードしてくれる男勝りな部分は昔と一緒だったしな。お前はいつ気付いたんだよ」
佐山は至極当然かのように言っていたが、アオトは何度かヒントに近しい言葉を聞かされても最後までピンときていなかった。
だが、よくよく思い返せば、彼女があの頃の彼である証明となる言動は幾つもあった。
「俺は修学旅行の2日目に2人きりで話した時だな」
「ほー……お、来た」
そんな話を続けていると、佐山は公園の入り口からパタパタと走ってくる人影に目をやった。
「ご、ごめんね~! 待たせちゃったかな?」
「いいって事よ、金ちゃん……いや、銀ちゃん?」
「だーかーらー、かすみんでいいって言ってるでしょ!」
頬を膨らませてぷんすかと怒っているのは、金ちゃんこと白銀香澄だった。
茶化してくる佐山に反論する姿は昔とは違って、可愛らしさしかない。
「悪い悪い、かすみん」
「もう……アオくんもだよ」
カスミは呆れながら嘆息すると、立ったままアオトへ目を向ける。
「わかってるよ。それで、今日は何するんだっけ?」
「おいおい、忘れたのかよ」
「はぁぁぁ……ボクが酷い目にあってるのは気付いてくれたのに、あんまり興味がない時のアオくんって鈍感だよねぇ。この傷を見るまで信じてくれなかったし……」
カスミはダボっとした上着の右の袖口を捲り上げると、肘の辺りにある傷痕を見せてきた。
これはカスミが幼い頃に父親から受けていたDVの痕である。痛々しく残り、それはハルカの腕にあった傷と似ている。
しかし、大きな違いは、それが全身に及ぶか、それとも一部のみかだった。
「……冗談だっての。今日はみんなで遊ぶんだろ、この公園で」
アオトはほんのジョークのつもりだったのだが、本当にすっとぼけてると思われたのか佐山とカスミは呆れて溜め息を吐いていた。
「その通りだぜ。アオトは覚えてるか? 子供の頃に何して遊んだか」
佐山は唐突に立ち上がると、アオトを見下ろしながらビシッと指を差す。
「まあ、全部はさすがに思い出せないけど、子供がしそうな遊びはやり尽くしてたよな。半年しか一緒にいなかったけど、ほぼ毎日会ってたし」
「そうそう! みんなで鬼ごっこしたり、かくれんぼしたり、砂遊びもしたね。夜はこっそり線香花火をして近所のおじさんに怒られたんだっけ?」
カスミはアオトの左隣に座ると、彼のことを挟んで反対側にいる佐山と盛り上がりを見せ始める。
「あー! あそこの家だぞ。今はもう年食っちまったからわかんねぇけど、当時はもう雷親父って感じだったもんな!」
「怖かったよねぇ~! ぷっ……アオくんなんて泣いてたし」
「っるせぇ……」
カスミにバカにされて笑われたアオトはぶっきらぼうに言い返す。しかし、全て事実だったので具体的な反論はできなかった。
「かすみんはその度に慰めてたもんな。そういう男らしい一面があったから、俺たちは金ちゃんの性別が男だって思い込んでたんだよな」
「あの時のボクは髪もかなり短かったし、性格も男の子みたいだったもんね」
カスミはかなり変わった。短髪で男勝りで強気な性格だったが、今では真反対の女の子らしいルックスになっている。内面は名残があるが、かなり控えめになった。
「今じゃあ、小動物みてぇになっちまったけどなっ! な、アオト」
「……ん、まあ、そうだな」
「ア、アオくんは……どう思う?」
「え、ど、どうって?」
佐山に続き、カスミにも唐突に話を振られたアオトは、辿々しい口調で答える。
左隣からじーっと音が聞こえそうなほどの強い視線を感じ、右隣の佐山はニヤニヤと悪どい笑みを浮かべる始末だ。
「ボク、ちょっとは女の子らしくなれたかな? アオくんが小動物みたいな可愛い女の子が好きって言ってたからさ……」
カスミは自身の胸に手を当て顔を赤らめて俯く。
アオトは右隣に座る佐山に視線を送り助けを求めるが、彼は「素直に言え!」と口パクで合図を送っていた。
「あ……可愛いと思う、ぞ?」
アオトは思うがままに答える。
彼から見たカスミは昔の自分が思い描いた理想通りの容姿だった。
身長が低めで、愛嬌があって、にこやかな女の子だ。
「……っっ……あ、ありがと……」
「お、おう……」
「おーーーーー! アオト、お前、やればできんじゃねぇか!」
爆発しそうなほど顔を紅潮させるカスミと、なんて返せばいいかわからなくなるアオト、そして2人を見て楽しむ佐山。
高校2年生になる3人の男女は、この瞬間だけは間違いなく、あの頃のかけがえのない時間を共に過ごした子供に戻っていた。
「……うぅぅ……で、でも、アオくんは晴香ちゃんと付き合ってるんだよね?」
「え? いや、俺と星宮はそんな関係じゃないぞ」
アオトは落ち込むカスミの発言を真っ向から否定した。
「へ? だ、だって、噂になってたよ!? 2人が頻繁に会ってるって!」
「それは、あれだよ……例の小説の関係だよ。少し話しただろ」
アオトは2人だけには小説のことを伝えていた。
恥ずかしいというハルカの意向もあり、小説とイラストは見せてはいないが、隠す部分は上手く隠して、やんわりとハルカとの関係や事情も伝えている。
「なんだ……ふぅ一安心だよ……」
「んで、進捗はどうなんだよ。コンテストの結果発表が来月のクリスマスの日だったろ? 締切日はもっと早いんじゃねぇの?」
ほっと一息つくカスミを尻目に、佐山は心配そうな面持ちで確認してきた。
「今日が締切日だ」
「はぁ? お前、ちゃんと応募したのか?」
「したよ。テキストデータと星宮が描いてくれたイラストをまとめて、昨日の夜には応募済みだ」
昨夜、アオトは原稿を完成させて、ハルカと通話をしながら読み合わせを終えていた。本来はイラストの提出など不要だし、そもそも選考の対象外なのだが、せっかく書いたイラストということで一緒に送りつけることにしていた。
その枚数はなんと8枚。やる気を出したハルカは凄まじいほど筆が早く、まるで毎日絵を描き続けるプロのようなタッチでさらさらと書き上げていた。
「そうか、なら安心だな」
「あ、そうそう。関係ないんだけど、イラストと言えばさ、ボクがずっと好きだったイラストレーターさんがいるんだけど……昨日の夜に突然アカウントを消しちゃったんだよね。それもネットにある全部のアカウントだよ?」
今度は佐山がほっと一息ついた最中、カスミが不満そうにスマホを見ていた。
Twitterのページを見ているらしく、そこには【アカウントは削除済み】と記載がある。
「気分転換でもしたんじゃねぇーの?」
あまり興味がない佐山は適当に答える。
「そうかも……最近は面白いシリーズを投稿していたのに、ここ数週間はずっと音沙汰なかったんだよね~。昨日の夜もいきなりアカウントを消したし……はぁぁぁ、ファンだったのになぁ」
「そんなに好きだったのか? 俺でも知ってっかな? そういうイラストとか小説とかアニメとか漫画とか、全然詳しくねぇけどよ」
根っからのスポーツマンで国民的なアニメすらほぼ知らない佐山にはわからないと思うが。
「どうだろ? この人だよ」
「【すたぁ☆彡】? 聞いたことねぇわ」
案の定、佐山は間抜けな顔で首を傾げていた。
かくいうアオトも、イラストレーター事情には明るくないので、聞いたことがない名前だった。
「えー! Twitterで50万人以上もフォロワーがいた有名人だよ!? しかも、現役女子高生って噂だし!」
「ほー、そりゃすげぇな。確かに、そんな有名人が急にそんな真似したらおかしいって思うのも無理もないわな」
「でしょー? アオくんはどう思う? というか、知ってる?」
「知らないな。Twitterなんてやったことないし……」
カスミはノリノリで尋ねてきたが、アオトは本当に全く知らなかった。LINE以外にSNSは触っていないので当然だ。
「だよねぇ……まあ、またいつか復活したらその時はもっと好きになってると思うんだ!」
「なんでだよ?」
「アオくんに会った時がそうだったからだよ! 焦らすとは違うけど、やっぱり会いたい人に会えなくて辛くなっても、また再会できたら嬉しいもんっ!」
カスミは溌剌とした澱みのない笑みを浮かべた。
随分と素直に言葉をぶつけてくる。
思わずアオトは口角を緩めた。
「俺と再会したのも喜んでくれよなぁ?」
「嬉しいよ! 嬉しいけど……アオくんは抜かせないよ!」
「くぅぅっ! まあ、いいけどよ!」
「ちなみに話を戻すと、【すたぁ☆彡】さんはね——」
中央には寡黙で静かなアオトと、両端には騒がしくもあり楽しい2人が座り、そんな時間は子供の頃のまま何一つとして変わっていなかった。
2日目と3日目は完全な自由時間ということもあり、2年生一行は朝早くから旅館を飛び出していた。
そんな中、昨夜は中々寝付けなかったアオトは、真っ昼間に目を覚ましていた。
今はたった1人で食堂に座り昼食を口にしていた。
「……星宮、少しは元気になったかなぁ」
アオトはせっかくの京都だというのに、普通のカレーライスを食べながらスマホを眺めた。
ハルカから連絡は来ていないが、昨日の別れ際の様子を見る限りは多少は本調子になった気がしていた。
だが、アオトは気がかりだった。
聴けていないことが多すぎる。気になることが多すぎる。疑問が頭の中に渦を巻き、いくら思考を繰り返しても整理をつけられない。まるで、深い泥沼にハマっていくような感覚だった。
「しかも、執筆も全く進まないし……」
この数週間、ハルカとの関係性がギクシャクしていた彼の執筆は、全くと言っていいほど進展していなかった。
現状は80,000文字弱で停滞しており、オリジナルでストーリーを考えようにも思いついていない。
小説を書きたいという意欲は確かにあるのだが、そのきっかけとなる根本が覆された今、頭の中にモヤがかかってしまっていた。
「バッドエンドにはしたくないなぁ」
アオトはここ数週間で起きた数多の出来事を思い出して息を吐く。
彼としてはハッピーエンドを夢見ていたのだが、やはりハルカの内面や心情をより知りたくなっており、それどころではなくなっていた。
そもそも、恋愛経験が全くない彼からすれば、これまでハルカと過ごしてきた時間こそが異様であり、今のような孤独を極める状態こそが正常なのである。
故に、それほど焦りはなかったのだが、アオトはハルカの事を想う自分の気持ちにも理解し始めていた。
そんな事を考えながらも、アオトが黙々とカレーを食べすすめていると、
「……ん? 星宮からだ」
スマホからLINEの通知が鳴った。
佐山から何か連絡があるかと思いここ数日は通知をオンにしていたが、その相手はまさかのハルカだった。
アオトはおもむろにトーク画面を開く。
『降谷くん、今は友達と清水寺に来てるよ!』
メッセージの内容は、清水寺を背景にハルカを含めた数人の女子が映った一枚の写真と、なんて事ない報告だった.
文面からはそこはかとない愛嬌を感じさせた。
——昨日話していた通り、女友達とかと過ごす時は自分を偽ってるんだろうな。
アオトは昨夜、ハルカの自然な笑顔を目の当たりにしていたので、写真に映る彼女の表情に違和感があった。
『随分と楽しそうだな』
『うんっ! すっごく楽しいよ~! 降谷くんはどこにいるのかな?』
『旅館の食堂でカレーを食ってる』
『はぁ? 修学旅行の自由時間なのに、旅館にいるの!?』
文面だけで驚愕が伝わってきた。
『おう。佐山がサッカー部の連中も回ることが決まった瞬間から、俺のひとりぼっちは確定していたんだよ』
朝一番に笑顔で旅館から走り出していく佐山の姿が頭の中に思い浮かぶ。
『悲しいね。でも、昨日は私と過ごせたでしょ? 色々とお話もできたし!』
『そうだな。できればもっと話したかったけどな』
『きっと私のことを知れば知るほど幻滅するよ』
『しないよ』
アオトは即答する。
嘘偽りない本音だった。
できればもっと話をしたいというのもそうだ。
佐山とは既に結託できているので、明日の夜の肝試しで現実となる。
『あっ、それと、前々から描き続けてたイラストを送るね! 仕上げだけスマホでやっちゃったけど割といい感じでしょ?』
『ああ。相変わらず上手だな。本当に綺麗な絵を描いてくれて嬉しいよ』
今のアオトの返信は本心だった。本当にハルカのイラストは素晴らしいと心の底から思っている。
そんなハルカが描いたイラストは昨夜の旅館裏での一幕だった。
月明かりが照らす夜。幻想的な大木の下に置かれたベンチに腰掛ける2人の男女。
その横顔は笑顔を満ちている。
『ありがとー、降谷くんも執筆頼んだよ! コンテストまでは後2ヶ月もないから、また何かあったら連絡して! 私はいつでも協力するから、絶対にすごい小説を完成させようね! またねー』
ハルカからは、可愛らしいウサギのスタンプと共に勢いのあるメッセージが送られてきた。
ものの数秒で行き来する言葉の数々。
テンポの良いやりとりは以前までと何ら変わりない。
むしろ、アオトにとっては昨夜を通して少しでもハルカの知れたので、気持ち的には幾分が楽だった。
「……コンテストかぁ……最近はすっかり忘れてたな」
アオトはスマホを伏せてテーブルに両肘をつき首を垂らす。
戦意喪失とは少し違うが、ここ最近はやる気が著しく欠落していた。
ただ、せっかく描いてくれたイラストを無碍にするのは少々気が引けたし、ハルカと会話を交わすことでやる気がみなぎっていた。
しかし、やはり続きの話を書くのが厳しいのも事実だった。
ハルカとお出掛けもといデートに行けてないのに、恋愛小説を書くというのは彼にとって至難だからだ。
「うーん……」
考え込みながらもカレーライスを食べ終えたアオトは、ハルカから送られてきたイラストを凝視しながら悩む。
すると、背後から足音が聞こえてきた。
彼はおもむろに振り向いたが、既にその人物は彼の眼前にまで迫ってきていた。
「——それ綺麗な絵だね!」
「し、白銀さんっ!?」
アオトは笑顔のカスミから唐突に声をかけられたことで驚くと同時に、反射的に後退しようとして机に背をぶつけてしまう。
あまりの痛みを感じて情けなく顔を歪めた。
「あっ、ご、ごめん! アオく……ふ、降谷くん、大丈夫?」
カスミは笑顔から一転してアオトを憂うような柔和な顔つきになった。
「だ、大丈夫だ。それで……俺に何か用か?」
「うん! 明日、予定が無ければ二人で観光しようよ!」
「え? 俺と?」
「そう、降谷くんと」
「なんで?」
アオトの心の中には少しばかりの疑念があった。
彼はハルカとの一件があってからやや心傷気味なこともあり、どうしても唐突な誘いには乗りづらかったのだ。
「え? 何でって……ボクがそうしたいからだよ?」
カスミはなぜアオトが疑問を呈したのかわかっていない様子だった。
口元に手を当てて首を傾げている。
「……意味がわからないな。もう仲の良い友達はたくさんできてるだろうし、思い出作りにそいつらと一緒に行動したらどうだ?」
アオトは至極真っ当な事を言った。
いくらカスミが転校してきたばかりとはいえ、愛らしい小動物のような容姿と明るい性格のおかげで、既に彼女はクラスと人気者だったからだ。
当然、孤独を極めて退屈な日々を過ごす彼とは相容れない存在だった。もちろん、それはハルカも同様だ。普通に考えたら相容れないはずの両者だった。
「ボクは降谷くんと回りたいの。ダメ?」
「ダメじゃないけど……本当に俺なんかでいいのか? バイトをしてないから大金なんて持ってないし、見ての通り根暗だぞ。それに、話しても楽しくないだろうしな」
上目遣いでカスミからお願いされたことで、純情なアオトは一瞬心が揺らぎかけたが、そんなバカな自分に鞭打つようにして現実的な言葉を言い放つ。
しかし、彼の言葉を聞いた彼女はすぐさま頬をぷっくりと膨らませ、勢いよく首を横に振る。
「そんなことないと思うよ?」
「……そうか?」
「うん。ボクはわかるよ。降谷くんはそんな人じゃないってね!」
アオトからすればかなり関係の浅いカスミだったが、なぜか彼女は確信めいた言い方をしていた。
まるで昔馴染みのような口振りだ。
「そう言ってくれるのはありがたいね。で、白銀さんはどうしてここに?」
「たまたまだよ。昨日は疲れちゃったのか朝起きたら体調が悪かったんだ。だから、今日は旅館で休んでたんだ」
カスミは食堂の窓から外の景色を眺めていた。羨望の眼差しを送っていることから、本当は出かけたかったのだとわかる。
「ふーん」
「興味なさそー」
「……そんなことないぞ?」
「嘘だー!」
アオトは本当に興味がなかったので、そんな安直な嘘はカスミによって容易く見破られた。
彼女はさながら名探偵の如く、ビシッと指を差している。更にはその勢いのあまりポニーテールが揺れている。
——昨日もそうだったが、殆ど話したことがないのに随分とフランクなやつだな。星宮の八方美人とは違うんだろうけど、みんなに平等に接することができるタイプだろうな。
アオトはカスミが持つコミュニケーション能力の高さに脱帽していた。
小説とイラストという共通点がなくとも、こうして話しかけてくるなんて、アオトからすれば信じ難い事実だった。
アオトが1人で思考をしていると、隣に座るカスミは本題を思い出したのか、目を剥いて彼に視線を送った。
「そうそう、降谷くんって、サッカー部の佐山くんと幼馴染って言ってたでしょ?」
「そうだな。あいつとは昔からの付き合いだ」
アオトはカスミがなぜ自分と佐山との関係を聞いてきたのかよくわからなかったが、隠すことでもないので正直に答える。
「そう……他には幼馴染はいなかったの?」
カスミはおずおずとアオトに尋ねる。
彼女が何を知りたかったのか、アオトはよく理解できない。
「まあ、佐山以外にも一応いたぞ。短い付き合いだったけど、仲の良かった男友達が1人だけな」
「男友達なの?」
「ああ。あの時はまだ5歳くらいだったと思うけど、そいつは男らしくて強気な性格だったな。佐山とはまた違う明るさを持ってたよ」
アオトは金ちゃんのことを頭の中に想起しながら答えた。
全ての細かい出来事をはっきりと覚えているわけではないが、金ちゃんの性格と時折見せる悲しげな顔だけは忘れていなかった。
「……あれ?」
「ん?」
「そ、その男友達は今どこにいるのかな?」
「わからない。多分、もう近くにはいないと思う」
金ちゃんの行く末をアオトは何も知らなかった。
元気にやっていることを願うしかない。
「そう……じゃ、じゃあ! 忘れちゃってるだけで他に女の子の知り合いとかはいなかった?」
カスミは間髪入れずに質問をぶつけていく。
物事が思い通りにいかずに焦燥感に駆られているように見えるが、彼女の心情などアオトには全くわからなかった。
「俺に女の知り合いなんて殆どいないぞ」
アオトは即答する。
「殆どってことは少しくらいはいるんだよね?」
カスミはアオトに問いかけながらも、ここにきてようやく彼の隣に腰を下ろした。
「まあ、ほんの少しだけどな」
「ちなみに……その中にボクは含まれてない?」
「……? 白銀さんとは少し前に出会ったばかりだし、こうして話をしたのは3回目とかだからな」
考え込む素振りを見せたアオトの頭の中には、母親や祖母などの親族以外だとハルカの姿しか思い浮かんでいなかった。
どうあがいても、カスミの姿は出てこない。
そもそも知り合ったばかりの彼女が、彼の過去の記憶に入り込んでくることなどあり得ない話だった。
「ふーん……わかったよ! とにかく、明日は2人で色んなところに行こうよ!」
「拒否権は?」
「ないよ。ボクは降谷くんのことを知りたいんだ。絶対に後悔させないから、明日はボクに付き合ってくれると嬉しいな」
「……わかったよ。ちなみに今日これからじゃダメなのか?」
アオトは食堂の壁掛け時計をチラ見した。
「実は昨日のバス移動のせいで酔っちゃってクタクタなんだ……残念だけど、また明日だね」
「そっか、お大事にな。無理はするなよ?」
「うん。ありがと」
アオトは何の気なしに言葉をかけただけだったのだが、当のカスミは照れ臭そうに笑って彼から目を背けると、おもむろに立ち上がり踵を返す。
「それじゃあまたね。明日のお昼前に旅館前に集合だよ!」
「ああ、また明日」
アオトは不器用な笑顔を作ると、静かな足取りで立ち去るカスミに手を振り見送った。
「……はぁ」
またも1人になったアオトは溜め息を吐く。
彼はハルカとの一件のせいで、カスミのことも信用できない自分が嫌になっていた。
同時に、カスミの発言1つ1つが気になっていた。
関係が浅いのに積極的な距離の詰め方と、まるで自分の昔の事を把握しているかのような口振りと質問の数々。
熟考して思い返してみても明らかに怪しかった。
「悪いやつじゃないといいけどな」
アオトは空になった食器を下げて食堂を後にすると、部屋で1人執筆作業にとりかかりはじめた。
一旦、カスミのことは忘れて、スマホのテキストデータに意識を注ぐ。
昨夜の出来事のみならず、ここ数週間で起きた様々なイベントを余す事なく、それでいて隠す事なく文字に変換していく。
経験した事しか書けない彼にとっては、今できる精一杯の執筆だった。
やがて、夕方になり、続々と生徒たちが旅館へと帰ってくる頃。
彼の小説は、これまでの単なる恋愛の妄想だけではなく、拗れゆく人間関係を忠実に表現した、より現実味のある内容に仕上がっていたのだった。
◇◇◇◇
修学旅行の3日目。
場所は昼下がりの活気あふれる京都市内。
アオトは約束の相手と2人並んで市街地を歩いていた。
「今更だけど、どこか行く場所は決まっていたりするのか?」
「昨日、お部屋に戻ってから色々と調べたんだけど、やっぱり京都と言えば歴史だよね。有名な観光スポットもたくさんあるし、スマホで調べながら適当に巡ってみようよ!」
そう答えるカスミは華やかな笑みを浮かべたまま、アオトの左手側の肩に寄り添って距離縮める。
ダボダボのブラウンがかった色味のカーディガンが、ポニーテールと共に揺れている。
意外にも強引な部分があるんだなと、アオトは思う。
「そうだな」
「……昨日は変な質問ばっかりしちゃったけど、今日はせっかくだしたくさん楽しもうね! アオくん」
「おう。まあ、俺はアオくんじゃないんだけどな」
「そうだったね……降谷くん」
カスミはアオトの呼び方を訂正したが、その瞳は曇りなく、言葉は澱みなかった。
そんな彼女の思考がわからないアオトは、溜め息混じりに呟く。
「……アオくん、か」
その呟きは、彼女の耳に届く事なく雑踏の中に紛れて消えていった。
やがて、アオトはカスミのリードに従い、京都の街並みを巡っていく。
2人で並んで石畳の道を歩きながら、京都らしい歴史を感じさせる建物や、古い木造の町屋、緑が茂る庭園を持つ古刹に目を向ける。その風景はまるで時を超えたような雰囲気を醸し出している。
また、秋ということもあり、鮮やかな紅葉が枝を彩り、古い寺院の門から漏れる静けさが心を穏やかに包み込んでいた。
そして、街角には古い茶屋や和菓子店が立ち並び、そこから漂う緑茶や和菓子の香りが、訪れる人々に京都の伝統と風情を感じさせる。道行く人々は着物姿で、古都ならではの風情を漂わせており、建物の一つ一つには、歴史や伝統が刻まれ、そこに触れるだけで、京都ならではの神秘的な魅力が感じられた。
そのどれもが彼にとっては新鮮だった。
彼は内心で不安を感じながらも、隣を歩くカスミの楽しい笑顔に心を奪われ、気が付けば一緒に過ごす時間を楽しんでいた。
彼女の明るさが周囲を明るく照らし、アオトの心にはほのかな希望を灯しているように感じられた。
「……白銀さん」
時刻は夕方になる頃。
人混みの少ないやや外れた通り。
アオトは斜め前を歩き、ずっとにこやかな様子のカスミに声をかけた。
「どしたの?」
立ち止まったカスミは身を翻してアオトの方を向いた。彼女は男勝りな無尽蔵な体力があるのか、未だ元気そうにしているが、当のアオトはインドアな性分が災いして疲れ切っていた。
「今夜は肝試しがあるみたいだし、そろそろ旅館に戻らないか?」
アオトにとって今夜の肝試しは正念場だった。
それは小説の今後の展開についてもそうだが、何よりもハルカとの関係が大きく左右される場でもあるのだ。
「そうだったね。じゃあ、最後に少しだけそこの公園で話してからにしない?」
カスミはいつもの明るく楽観的な口調ではあったが、その瞳は真っ直ぐだった。
まるで、覚悟を決めた兵士のように……言葉には力強い意志が込められていた。
「わかった」
アオトはカスミの後を追って、小さな公園へと向かった。
彼女は迷うことなく錆びついたブランコに乗ると、小さく揺れながら夕暮れ空を見上げている。
ここはブランコや滑り台、鉄棒や水飲み場などがあるだけの何の変哲もない公園だったが、その光景を眺めたアオトはどこかノスタルジックな気持ちに駆られていた。
「今日は……楽しかった。ありがとう」
年季を感じさせる公園の設備時計を一瞥したアオトは、おもむろに口を開く。
照れ臭い言葉ではあったが、初めての映画デートの際に、ハルカから言われたアドバイスを思い出したのだ。
思った事ははっきりと相手に伝える……と。
「ボクの方こそありがとうだよっ! 今夜の肝試しもたくさん楽しめるといいね」
カスミはパァッと花が咲いたような満面の笑みを浮かべた。
しかし、裏表が無さすぎるその表情は、やや心傷気味のアオトの気持ちを疑心暗鬼にする。
「そうだな」
アオトは心象を曇らせながらも端的に相槌を打つ。
「ねぇ、降谷くんは肝試しに参加する相手は決まってるの? 確か、あれって相手が決まっていない人はくじ引きだったよね?」
カスミは恥ずかしがった様子で尋ねた。
「……決まってないな」
アオトは逡巡しながらも嘘をつく。否、それは嘘であり真実でもあった。
本当は決まりきったようなものだった。
内々で佐山と立てた計画が実現すればの話だが。
「え! じゃあ、ボクとペア組まない?」
「悪い」
嬉々とした声色でカスミが誘ってきたが、アオトは間を置かずに断りを入れた。
「……ちなみに、どうして?」
「……」
カスミの問いかけに対してアオトは口を真一文字に閉じる。
「言いたくない?」
「そういうわけじゃないが。あまり深く聞かないでくれると助かる」
アオトは、しょんぼりしているカスミに誤解を抱かせないように優しく宥めた。
「……そう」
アオトの思惑など知らないためか、カスミは物悲しそうに口元に力を込める。
「白銀さん。俺からも1ついいか?」
「どうしたの?」
「もし、答えたくないのであればそれでいいんだが……白銀さんは、どうして俺のことを誘ってくれたんだ?」
アオトは今日という日を楽しく過ごしながらも、心の内ではネガティブな疑念が僅かに残り続けていた。
「昨日も言ったでしょ? ボクが一緒に過ごしたかったからだよ」
「それじゃあ具体的にはどうしてだ?」
アオトはわからなかった。どうして彼女が転校初日から今に至るまで、フランクな態度で距離を詰めてきたのか。
「具体的にかぁ……」
カスミは小さく揺れるブランコの動きを足で止めてアオトを横目で見る。
考え込むような顔つきだ。
「できれば、教えてほしい」
「んー……わかったよっ。じゃあ、まずは降谷くんが思い出せるように、ボクの子供の頃の話でもしようかな」
カスミは再びブランコを漕ぎ始めると、今度はぽつぽつと言葉を紡いでいく。
「子供の頃、ボクはこんな小さな普通の公園が遊び場だったんだ」
子供をあやすようなその柔らかな語り口は、アオトの耳にスッと入ってくる。
彼女の子供の頃の話を聞いて、何を思い出すのか、何がわかるのか、それは今の彼では理解が及ばなかった。
「大切な友達がいてね、すぐ離れ離れになっちゃったけど、それはボクにとってはかけがえなくて、今でも忘れられない思い出なんだよ。あの時は家に帰るのが本当に嫌だったから、尚更ね?」
「そうか」
端的なアオトの相槌は、錆びついたブランコが揺れる音でかき消される。
カスミは尚も言葉を続けるが、俯きがちなその瞳は確かに潤んでいた。
「あの時のボクは家に居場所がなかったんだ」
「どうしてだ?」
「みんな助けてくれなかったんだよ。お酒を飲んで暴れるパパのせいで、ママはずっと怖くて震えてて、保育園の先生もボクの話を信じてくれなくて、近所のおばさんも笑って流すだけ……でも、1人だけボクが苦しんでることに気付いてくれた人がいたんだ。ずっと誰も助けてくれなかったから、ボクは必死に明るく振る舞って強がってたのにだよ。それって凄いと思わない?」
アオトはブランコを漕ぐカスミのことを目で追った。
そして気がついた。彼女の頬が涙で濡れていることに。
「そう、だな……その人は、きっと凄く優しいんだろうな」
アオトは同情を示して答える。
「うん。だから、とっても嬉しかった。あの時にボクは決めたんだよ。必ずまた会って、絶対に恩返しをするってね。その人はボクにとっての命の恩人なんだ」
「会えるといいな」
「うんっ!」
アオトが微笑むようにして言葉を返すと、カスミも小さく笑いながら嬉しそうに答えた。
その最中、アオトは視線を落として考え込む。
彼は、自分はカスミの過去の話を全く知らないはずなのに、記憶の片隅をくすぐられるような妙な既視感を覚えていた。
まるで……自分もその過去の世界に深く関わっているんじゃないかと思うくらいに。
「ねぇ」
「……?」
思考を続けるアオトだったが、カスミに声をかけられることで我に返る。
カスミはブランコから飛び降りており、小さな歩幅で、柔らかい足取りで、アオトの前にやってきていた。
彼は目の前に立つ彼女の姿を見上げると、彼女が夕焼けを背景に頬を染めていることに気がついた。
刹那の合間に、過去の記憶が頭の中を駆け巡った。
その瞬間、互いの思考が重なり、アオトとカスミは視線を交わして息を呑む。
そして、アオトは記憶の中枢から手繰り寄せたある人物を名前を口にしようとした。
ここには決しているはずのない……幼い子供だった、あの頃を共に過ごしたあの子の名前だ。
「降谷くん」
「……」
名前を呼ばれたアオトは、息を呑み首肯する。
これからカスミの口から紡がれる言葉への期待が胸に宿る。
心臓は彼女にも聞こえてしまいそうなほど大きく高鳴り、2人の間にはえも言えぬ緊張感のある空気が流れていた。
しかし、そんな2人が味わう特別な時間は、突然の来訪者によって徒労に終わる。
「——あー、疲れたねぇ~」
「だね~、もうそろ帰る? 今日は肝試しだしね」
「そうしよっか。ちょっと休憩したら帰ろーかー」
「さんせーい!」
高めのテンションで公園に立ち入ってきたのは、5名の女子生徒たちだった。
彼女らはブランコにいるアオトとカスミには気づかずに、斜め向かいに位置する離れたベンチに向かっている。
「あれ? 晴香ちゃんはいないのかな?」
カスミがぽかんとした顔でアオトを見る。
それもそのはずだ。あの女子たちは普段はハルカを筆頭につるんでいるため、その中心にハルカがいないのは不思議だった。
「確かに……あの辺の女子と星宮は結構仲良くしてたはずだけどな」
疑問に思ったアオトが頷いたその時。
何を感じ取ったのか、5人の女子のうちの1人がおもむろに背後を振り返ると、アオトとカスミの姿を見つけて「あっ!」っと叫んだ。
同時に他の4人もアオトとカスミがブランコにいることに気がつき、ニヤニヤと興味ありげな笑みを浮かべながらにじり寄ってくる。
「あーあー! かすみん! まさか、降谷くんと付き合ってるの!?」
「ボ、ボク!?」
1人の女子が肘で小突くと、カスミは慌てふためく。
「かすみんしかいないじゃーん。で、どうなの!」
「ボクは……べ、別にそんな関係じゃないよ!?」
「あら~、顔真っ赤にしちゃって! 降谷くんはどうなのさー」
「え? 俺?」
唐突に話を振られたアオトは間抜けな顔になる。
「うわぁ! 喋った!」
「声初めて聞いたね」
「珍獣かなんかだと思ってないか?」
アオトは溜め息混じりに言う。
彼は目の前に立つクラスメイト、5人の名前を把握していなかったので、向こうから認識されていることにも内心は驚いていた。
「珍獣と同じだよ? みんな声聞いたことないし……ってか、意外にも良い声してるね。近くで見るとやっぱりルックスも悪くないかも……」
「そりゃどうも……」
「《《アオくん》》! 謙遜しないで喜んでもいいんだよ?」
ぶっきらぼうなアオトの返事に被せるようにして、カスミは急に立ち上がり前に躍り出た。
彼女らの発言に強く同意をしているのか、首を縦にぶんぶん振っている。
「え!? 今、アオくんって呼んだ!?」
「ね! 呼んだよね! うわぁ……やっぱり2人ってそうなんだ。いやぁ、降谷くんってば意外にもモテモテだねぇ」
女子たちはなぜか拍手すると、カスミは照れ臭そうに顔を赤くして笑う。
手のひらを横に振っていることから、多分彼女は別にアオトのことを好きではなさそうだった。ただ、どこか並々ならぬ思いを抱いているのは確実だった。
そんな収拾がつかない展開の連続に、アオトは辟易していた。
彼からすれば、カスミが自分のことをアオくんと呼ぶのは2度目なので気にしない。
そんなことよりも、聞き逃せないワードが散見されたので、彼は自ら聞いてみることにした。
「なぁ、モテモテってどういうことだ? 誰かと勘違いしてないか?」
「ほんっとに申し訳ないんだけど、あたしたちも最初は勘違いかと思ったよね?」
「冗談かネタだと思ってたんだけど……ところがどっこい、降谷くんの事をいいなって思う人がもう1人いるんですっ!」
彼女らはごくごくナチュラルに失礼な事を言っていたが、かくいうアオトは気にも止めず続けて質問する。
「ふーん……誰だ?」
「あ、やっぱ気になる?」
「まあ……一応、興味がないといえば嘘になる」
アオトが真剣な眼差しを彼女らに送る。
恋愛経験がないアオトは別に恋愛恐怖症なわけではない。単に前向きになっておらず、縁遠かっただけだ。
「ふふふふふふふふふふ……知りたい?」
「知りたい」
アオトは知りたかった。朴訥な自分に好意を持つのはどんな相手なのか。
「本当に?」
「知りたい」
アオトは食い気味に答える。
焦りはないが好奇心は高い。
どうしても前のめりになってしまう。
そろそろ教えてくれるだろうか……と、アオトは息を呑む。
しかし、そんな彼の意に反して、
「教え……ない! ごめんね~、さすがにうちらだけの恋バナは教えられないわ~」
女子たちは口で雑なドラムホールを奏でてから、期待を裏切ってきた。
爽快な顔つきだ。アオトを焦らして楽しんでいたのだろう。
「……まあ、そうだよな。人にそういう話をするのって勇気がいることだし、そんな内緒話を無碍にはできないよな」
「そういうことー、大事な友達だからね! 勝手に言いふらしたりはしないよ」
女子の1人は至極真っ当な事を言ったが、それを守れる友達と守れない友達とでは大きく異なってくるので、きっとアオトに好意を寄せているというその友達は、さぞみんなから好かれているのだろう。
「かすみんがいる前でライバルを作るような発言もできないしね」
「ラ、ライバルって、ボクは別にそんな風に思ってるわけじゃ……」
カスミは唇を尖らせる。文句を言いたげな様子だ。
「……よくわからないけど、もう帰ろうぜ」
アオトはブランコから立ち上がり呆れ混じりに息を吐く。
一連のやり取りは結局終着点が見つからないまま、これにて終わりを迎えたが、彼女らはおもむろにスマホを見ると一様に考え込み始める。
「そだねー。晴香の事も気になるしねー」
「LINEは返ってきてるけど、元気かな?」
「んー、晴香って割と体弱い方だからねぇ……ちょっと心配かも」
「星宮は体調不良かなんかか?」
「うん。降谷くんは何か知ってたりする?」
「いや、特には」
アオトはポケットからスマホを取り出したが、ハルカからの連絡は入っていなかった。
「そっかー」
「……星宮が体調不良になったのは今朝からか?」
自分なんかが聞くのはどうかと思ったが、アオトは彼女らに詳細を尋ねた。
「ううん、昨日? いや、一昨日の夜からかな? まあ、最近の晴香は張り詰めた感じだったしねー」
「言われてみると、晴香って普段から気が休まってないっていうか、いつでもどこでも明るい感じだよね。それが晴香らしいって言われたらそうなんだけど……でも、愚痴も弱音も聞いたことがないから心配になる時は多いよね」
1人が言うと、もう1人が同調した。
それは、傍目から見てもハルカが疲弊していることを表している。
「ねー、しかも、なんかこうちょっとだけ距離を感じるから、あたしたちとしてはもっとリラックスしてほしいかな。愚痴なら聞くし、相談にも乗るし、何でもいいから悩みがあるなら言ってほしいし」
口振りからして、彼女らはハルカが自分を偽るとまではいかなくとも、どこか心を開ききっていなくて、本当の姿を曝け出していないということに気が付いているようだ。
それは別に察しが良いというわけではなく、彼女らから見た星宮晴香という存在は、それほど親しい友人だということだ。
故によく見ているし、心のうちを理解している。
同時にもっと仲良くなりたいとも思っているはずだ。
アオトが初日の夜にハルカから聞かされたカミングアウトとは、少しばかり認識に齟齬があるようだった。
ハルカに何が起きて彼女の思考を歪ませたのか、それはアオトにはわからなかったが、とにかく彼女が変に取り繕う必要はなく、交友関係には問題がなさそうだとわかる。
そうとわかれば、アオトのやることは決まっていた。
彼は思考を中断してスマホを手に取る。
『今夜の肝試し、もし、体調が良さそうなら来てほしい』
アオトはそれだけメッセージを送ると、すぐ隣に佇んでいたカスミに目を向ける。
気がつけば、5人の女子たちは既に踵を返して公園からいなくなっていた。
「……白銀さん、色々と積もる話もあるだろうけど、いったん旅館に戻ろうか」
「うん……でも、ボクはきちんと言葉にして伝えるからね」
カスミは覚悟を決めたように力強く首肯した。
「ああ」
アオトはカスミと並んで旅館への帰路に就く。
その際、互いに思っていたことは一緒だった。
しかし、改まると妙な緊迫感が生まれてしまい、その話については自然と流れていった。
◇◇◇◇◇
雑木林は夜の暗さに包まれ、微かな月明かりが木々の間から差し込んでいる。
地面には落ち葉が敷き詰められ、足音が響くたびにカサカサと音を立てる。
乾いた秋の夜風は、陰険で暗い雰囲気を一層引き立てる。
そんな中、アオトは俯きがちになりながらも、斜め前方に佇むハルカの後ろ姿を横目で見ていた。
浴衣ではなく私服だ。上にはかなりオーバーサイズなチャコール色のパーカーに下はジーンズ。映画を見た時とは違い、この時期なら特に違和感のない格好だった。
かくいうアオトも同様で、上は厚手の黒いジャケットに、下は普通のスラックスを履いていた。全身黒だ。
ちなみに、浴衣姿なのはテンションの高い佐山だけだった。
「……」
アオトな周囲を見ることで自分を落ち着かせようとしたが、やはり心臓は僅かに高鳴り続けており、それは恐怖とは無縁の感情だった。
周囲にはもう10名ほどの生徒しかいない。
ペアが決まったカップルや仲の良い男女は序盤で出発しており、今はペアの決まっていない男女のクジ引き中だった。
彼ら彼女らは、さして肝試しに興味はないのか、退屈そうに順番を待つだけだった。
「——アオト」
「佐山」
アオトに声をかけてきたのは友人の佐山だった。
彼は青との耳に顔を近づけると、こそこそと小さな声で言う。
「根回しはしておいたぜ。次くらいに呼ばれるから、そん時に星宮さんと話してこいよ」
「サンキュー」
「おう」
佐山は礼を言ったアオトにウインクを見せると、そのまま踵を返して離れていく。
どっかの変態男の後輩だからキザに見える瞬間もあるが、それでもその内面に見え隠れする彼の人の良さがアオトは好きだった。
「……白銀さんもまだペアが決まってないのか」
アオトは佐山から視点を移して、今度は少し離れた位置にいるカスミの姿を捉えた。
彼女は考え込んだような深刻な顔つきだった。
彼には彼女が何を考えているのかわかっていたが、今それを解消してあげることはできなかった。
だが、また話す。そう約束した。
「ふぅ.…」
再びアオトは息を吐く。
今度は単純な深呼吸だ。
息を吐く度に、緊張が少しずつ和らいでいく。
その時、肝試しの順番が回ってきた。
佐山の友人であろう男子生徒が、ガサゴソとクジ箱の中を右手で漁ると、2枚の紙を開いてその名を読み上げる。
「降谷と星宮さんのペアねー。何度も言ってるけど、かなり暗いし足元がぬかるんでるから気をつけてなぁ」
大勢の中であればハルカとペアを組む相手が誰なのか、そこに興味が向くのだが、幸いなことに周囲に残された生徒は10名を切っていた。
ただ、当のハルカはというと、アオトとペアになることをここで初めて知ったからか、驚いた表情で彼に目を向けていた。
ハルカの表情には驚きが顕著に表れており、微笑みはない。
むしろ、緊張感を示すかのように視線がきょろきょろと動き、明らかに動揺している様が見て取れる。
アオトは出来レースみたいなことをして申し訳ないと思いつつも、そんなハルカのことを落ち着かせるために距離を詰める。
「星宮、よろしく」
「……うん」
ハルカは弱々しく返事をする。
「体調は平気か?」
「大丈夫……LINEが来てびっくりしてたけど、まさか全部仕組んでたの?」
「さあ?」
ハルカは瞳を細めながら疑ってきたが、アオトは素知らぬ顔で惚ける。
そして、雑木林の入り口へ向けて先んじて歩き出す。
「んじゃ、いってらー」
男子生徒が2人に1個の懐中電灯を渡す。
同時にテンポよくクジを引き、次のペアを告げる。
「次は、おっ、佐山と白銀さんか。準備しておけよー」
「俺の出番か! 白銀さん、よろしくぅ!」
「よ、よろしく……」
「ありゃ? 俺ってば嫌われてる?」
背後から呑気な佐山と元気のないカスミの声が聞こえてきたが、アオトは左隣に立つハルカと共に雑木林の中へ足を踏み入れた。
雑木林の中はより陰険な雰囲気が漂っていた。
夏に取り残された虫が小さく鳴き、夜風に煽られて木々が揺れる。
ただ、佐山の情報によると、ゴールは一直線に十分くらい進んだ先の開けた道らしく、道中に教員が潜んでいたりするわけでもないとのこと。
つまり、単なる思い出作りの場として設けられているイベントなので、ゴールするその時までは2人きりということだ。
あらかじめそれを知っていたアオトは、ゆったりとした足取りで歩みを進めていく。
「……寒くないか?」
「うん」
ハルカは手を前にして肩を縮こまらせて答える。
寒がっているというよりは、アオトに遠慮しているように見えた。
ただ、様相はいつもの明るい雰囲気を残している。
「星宮」
「何かな?」
ハルカは作り物の笑顔を張り付けるが、アオトにはそれが偽物だとすぐにわかった。
「星宮は……本当の星宮はどんなやつなんだ?」
歩みを進めながら尋ねる。
「どういうこと?」
ハルカは快活な様子は見せずに言葉を返す。
「本当の姿を偽ってるとか何とか言ってただろ。素の姿はどんな感じなんだ? 前みたいな、ただテンションが低くて元気がない感じではないだろ?」
「……1人の時はずっとあんな感じだよ」
「じゃあ、どうしてそこまでして自分を取り繕うんだ?」
表面的な彼女の一部分は理解したつもりだったが、核心に迫る彼女の内面については何も知らなかった。
あまり他人に関心がないアオトだったが、どういうわけかハルカのことを知ってみたくなっていた。
「前も言ったけど、みんながそういう私を望んでいるから。そうしないと嫌われるから。そうしないと私が満足できないから……結局、私は誰かに嫌われたくなくて、誰かに認められたいんだよ。そうしないと生きられないの。悪い?」
「悪くない。ただ、理由が知りたい」
「理由……」
ハルカはぼそりと口にした。
アオトに真意を明かすことを躊躇しているのか、それともそんな心象ではないのか、口元には少しばかり力が入って迷いがあるように見えた。
「教えてくれないか」
アオトは優しい声色で再度聞く。今度はその目を捉えて離さない。
「……いいよ」
ハルカは決意を固めたのか、ふと立ち止まり自身の胸に手を当てる。そして、何を思ったのか、肌寒い気温だというのに上に着ていたパーカーを脱ぎ始めた。
ハルカはパーカーを地面にそのまま放り投げた。
下にはタンクトップを着ており、彼女の肌が露わになる。
刹那。アオトは言葉を失った。
「っ!」
その肌には生々しい深い傷跡が無数に刻まれていたからだ。
あたかも過去の凄惨な出来事がそのまま彼女の肌に刻み込まれたように、それらの傷跡は静かに彼女の人生を語っているようだった。
「……醜いでしょ? 全部、子供の頃にパパから虐待された時につけられた傷だよ。きみが見た右肘の火傷の痕はほんの一部に過ぎないんだよ。どう? 引いた?」
ハルカは悲しげな笑みを浮かべてアオトの目を真っ直ぐ見つめる。
「……」
息を呑むアオトは言葉が出てこなかった。
醜いとか汚いとかそういう話ではなく、単純にハルカの肉体に刻まれた痛々しい傷を思うと涙が溢れそうになっていた。
だが、何も言わないアオトの様子を見た彼女は、途端に寂しそうに嘆息すると、
「やっぱり……見せるんじゃなかった」
アオトに背中を向けて膝を丸めた。
泣いているのか、膝の間に顔を埋めて鼻を鳴らしている。
「悪い」
「……何が?」
「俺は……星宮が苦しんでいることにずっと気付けなかった」
アオトはハルカと過ごした出来事を振り返ってみると、虐待という言葉が連想される彼女の仕草や所作が思い出された。
「きっと辛かったよな。俺には想像もつかない経験をたくさんしたはずだ」
「……降谷くんにわかる? 私の痛みが」
「わからない」
「じゃあ——」
「——でも、理解してあげることはできる。そして、寄り添ってあげることも……」
アオトは右手に持つ懐中電灯を投げ捨てると、しゃがみ込むハルカに自身が羽織っていたジャケットをかけた。
らしくないことをしている自覚はあったが、それでも、今にも消えてなくなりそうな彼女のことを放っておけなくなっていた。
「っ……!」
ハルカは驚嘆して勢いよくアオトに視線を向けた。
「誰も星宮を幻滅したりはしない。それは別に俺だけじゃなくて、いつも一緒にいる友達もそうだ」
「……あの子たちはわかんないよ? 今日もどうせ私がいないところで悪口言ってたんだろうし」
「5人組のことなら心配いらない。むしろ、星宮が悩み事も相談事も愚痴も聞かせてくれないから、自分たちが信頼されてないんじゃないかって憂いてたくらいだ」
アオトはつい数時間前のやりとりを思い出す。
確かに彼女らはハルカのことを心配していた。ハルカがどう思うかは別として、向こうはハルカのことを大切な友達だと認識していたのは確かだった。
「うそ」
「本当だ」
「……どうして、どうして降谷くんは、そこまでして私の事を知りたがってるの?」
ハルカは静かに立ち上がると、肩にかけられたジャケットと一緒に自分の身を抱きしめた。背の高いアオトのことを見上げて瞳を潤ませる。
それは怯えか、単なる疑念か、とにかく複雑な感情が入り混じった表情だった。
「俺が恋愛小説を書きたいって思ったのと同じだ」
「え?」
「俺は、興味が湧いた物事はとことん追求したいタイプなんだ。星宮は何を思って俺に話しかけてくれたのか、星宮はどうして俺にイラストを描いてくれるのか、星宮はどうして自分を偽っているのか……全部知ってみたくなったんだ」
アオトはハルカのことを知りたかった。
邪な思いではなく、単純に星宮晴香という人間が気になっていた。心に残り続けていた。だから、追求を重ねた。そしてようやく知ることができた。
「……ねぇ、それってさ……」
ハルカはハッとした顔つきになる。
何かに気付いたようだったが、アオトにはさっぱりだった。
「ううん……なんでもない。でも、ありがとう。私、降谷くんのおかげで変われた気がする」
「そりゃ良かった」
ハルカが何か言い淀んだ気がしたが、アオトは感謝を伝えてきた彼女に笑顔で返す。不器用だった彼の笑顔はいつしか自然な笑顔になっていた。
彼の笑顔を見た彼女も一緒に笑い、陰険な2人の間に立ち込めていた妙な空気感は、一瞬にして振り払われていた。
今はまるで、爽やかな草原の上にいるかのような雰囲気だった。
「……あーあ……子供の頃に降谷くんと出会ってたら、私に手を差し伸べてくれたのかなぁ~」
ハルカは冗談めかして言った。
「どうだろうな」
「きっと、降谷くんなら気付いてくれたよ。ね?」
「……まあ、子供の頃に一緒に遊ぶような仲だったなら、どうにかしてやることができたかもな」
アオトは幼い頃の記憶を想起する。
もしも、あの時にハルカとも出会うことができていたら、もしかすると……。
「うん、私もそう思うよ。それじゃあ、ゴールまで歩こっか。楽しくおしゃべりしながらね!」
「ああ。その前にジャケットを返してくれ」
「えー、せっかくかけてくれたのにー?」
ぶつくさ言うハルカは既にジャケットに袖を通し終えており、前のジップを閉めてボタンまで止めていた。
サイズが合っていないため着せられている感が出ているが、彼女自身はそれはもう満足そうだった。
「俺が寒いんだよ」
「パーカー着ていいよ?」
「地面がぬかるんでるせいで泥だらけだろ……まあ、いいけど」
アオトは地面に投げ捨てられていたチャコール色のパーカーを拾い上げると、軽く泥汚れを払ってからすっぽりと着た。オーバーサイズなだけあって着心地は良い。むしろ違和感がない。
それから、アオトとハルカは雑木林の陰険な雰囲気など気にも止めず、小説やイラストの話をしながらゴールを目指したのだった。
ゴールをした2人のことをハルカの友達が出迎えたが、彼女らは2人の服装が変わっていることには気付かなかった。
まあ、ハルカの表情が過去一で緩んでいたことから、すぐに怪しまれて言及はされていたが……運良く騒がしい佐山とカスミがゴールしてくれたため、話は流れていくことになったのだった。
◇◇◇◇◇
修学旅行が終わると、2年生には1週間の休みが与えられた。
すっかり夏が終わりを迎えたのがつい最近。
秋口かと思い肌寒くなったのもつい最近。
そんな束の間、既に北海道は初冬に突入しており、今日はついにはらはらと細かな雪が降り始めていた。
気温がまだ下がりきっていないので積もることはないが、やはり冬の冷気は特別だった。
「……寒っ」
「おいおい、そんな薄着じゃ風邪引くぜ? 子供ん頃みたいに丈夫じゃねぇんだからよ」
アオトは公園のベンチに腰掛けて曇天模様の空を眺めると、右隣に座る佐山が彼の肩を叩いて朗らかに笑う。
何枚も厚着をしている佐山に対して、アオトはチャコール色のパーカーを着ているだけだった。
「それより……まだ来ないのか? もう約束の時間は過ぎてるぞ?」
アオトは公園の時計を見た。時刻は午後3時。
「まあまあいいじゃねぇの。思い出の3人が懐かしの公園に集合するんだし、しかも女の子には俺たちにはわからない準備の時間が必要だろ?」
「それもそうか。にしても、驚いたな。お前が少し話しただけで気付くなんてな」
「んー、ちゃんとした確信はなかったんだけどよ、フィーリング的なやつですぐに分かったぜ。だって、笑った時の顔とか、肝試しすらリードしてくれる男勝りな部分は昔と一緒だったしな。お前はいつ気付いたんだよ」
佐山は至極当然かのように言っていたが、アオトは何度かヒントに近しい言葉を聞かされても最後までピンときていなかった。
だが、よくよく思い返せば、彼女があの頃の彼である証明となる言動は幾つもあった。
「俺は修学旅行の2日目に2人きりで話した時だな」
「ほー……お、来た」
そんな話を続けていると、佐山は公園の入り口からパタパタと走ってくる人影に目をやった。
「ご、ごめんね~! 待たせちゃったかな?」
「いいって事よ、金ちゃん……いや、銀ちゃん?」
「だーかーらー、かすみんでいいって言ってるでしょ!」
頬を膨らませてぷんすかと怒っているのは、金ちゃんこと白銀香澄だった。
茶化してくる佐山に反論する姿は昔とは違って、可愛らしさしかない。
「悪い悪い、かすみん」
「もう……アオくんもだよ」
カスミは呆れながら嘆息すると、立ったままアオトへ目を向ける。
「わかってるよ。それで、今日は何するんだっけ?」
「おいおい、忘れたのかよ」
「はぁぁぁ……ボクが酷い目にあってるのは気付いてくれたのに、あんまり興味がない時のアオくんって鈍感だよねぇ。この傷を見るまで信じてくれなかったし……」
カスミはダボっとした上着の右の袖口を捲り上げると、肘の辺りにある傷痕を見せてきた。
これはカスミが幼い頃に父親から受けていたDVの痕である。痛々しく残り、それはハルカの腕にあった傷と似ている。
しかし、大きな違いは、それが全身に及ぶか、それとも一部のみかだった。
「……冗談だっての。今日はみんなで遊ぶんだろ、この公園で」
アオトはほんのジョークのつもりだったのだが、本当にすっとぼけてると思われたのか佐山とカスミは呆れて溜め息を吐いていた。
「その通りだぜ。アオトは覚えてるか? 子供の頃に何して遊んだか」
佐山は唐突に立ち上がると、アオトを見下ろしながらビシッと指を差す。
「まあ、全部はさすがに思い出せないけど、子供がしそうな遊びはやり尽くしてたよな。半年しか一緒にいなかったけど、ほぼ毎日会ってたし」
「そうそう! みんなで鬼ごっこしたり、かくれんぼしたり、砂遊びもしたね。夜はこっそり線香花火をして近所のおじさんに怒られたんだっけ?」
カスミはアオトの左隣に座ると、彼のことを挟んで反対側にいる佐山と盛り上がりを見せ始める。
「あー! あそこの家だぞ。今はもう年食っちまったからわかんねぇけど、当時はもう雷親父って感じだったもんな!」
「怖かったよねぇ~! ぷっ……アオくんなんて泣いてたし」
「っるせぇ……」
カスミにバカにされて笑われたアオトはぶっきらぼうに言い返す。しかし、全て事実だったので具体的な反論はできなかった。
「かすみんはその度に慰めてたもんな。そういう男らしい一面があったから、俺たちは金ちゃんの性別が男だって思い込んでたんだよな」
「あの時のボクは髪もかなり短かったし、性格も男の子みたいだったもんね」
カスミはかなり変わった。短髪で男勝りで強気な性格だったが、今では真反対の女の子らしいルックスになっている。内面は名残があるが、かなり控えめになった。
「今じゃあ、小動物みてぇになっちまったけどなっ! な、アオト」
「……ん、まあ、そうだな」
「ア、アオくんは……どう思う?」
「え、ど、どうって?」
佐山に続き、カスミにも唐突に話を振られたアオトは、辿々しい口調で答える。
左隣からじーっと音が聞こえそうなほどの強い視線を感じ、右隣の佐山はニヤニヤと悪どい笑みを浮かべる始末だ。
「ボク、ちょっとは女の子らしくなれたかな? アオくんが小動物みたいな可愛い女の子が好きって言ってたからさ……」
カスミは自身の胸に手を当て顔を赤らめて俯く。
アオトは右隣に座る佐山に視線を送り助けを求めるが、彼は「素直に言え!」と口パクで合図を送っていた。
「あ……可愛いと思う、ぞ?」
アオトは思うがままに答える。
彼から見たカスミは昔の自分が思い描いた理想通りの容姿だった。
身長が低めで、愛嬌があって、にこやかな女の子だ。
「……っっ……あ、ありがと……」
「お、おう……」
「おーーーーー! アオト、お前、やればできんじゃねぇか!」
爆発しそうなほど顔を紅潮させるカスミと、なんて返せばいいかわからなくなるアオト、そして2人を見て楽しむ佐山。
高校2年生になる3人の男女は、この瞬間だけは間違いなく、あの頃のかけがえのない時間を共に過ごした子供に戻っていた。
「……うぅぅ……で、でも、アオくんは晴香ちゃんと付き合ってるんだよね?」
「え? いや、俺と星宮はそんな関係じゃないぞ」
アオトは落ち込むカスミの発言を真っ向から否定した。
「へ? だ、だって、噂になってたよ!? 2人が頻繁に会ってるって!」
「それは、あれだよ……例の小説の関係だよ。少し話しただろ」
アオトは2人だけには小説のことを伝えていた。
恥ずかしいというハルカの意向もあり、小説とイラストは見せてはいないが、隠す部分は上手く隠して、やんわりとハルカとの関係や事情も伝えている。
「なんだ……ふぅ一安心だよ……」
「んで、進捗はどうなんだよ。コンテストの結果発表が来月のクリスマスの日だったろ? 締切日はもっと早いんじゃねぇの?」
ほっと一息つくカスミを尻目に、佐山は心配そうな面持ちで確認してきた。
「今日が締切日だ」
「はぁ? お前、ちゃんと応募したのか?」
「したよ。テキストデータと星宮が描いてくれたイラストをまとめて、昨日の夜には応募済みだ」
昨夜、アオトは原稿を完成させて、ハルカと通話をしながら読み合わせを終えていた。本来はイラストの提出など不要だし、そもそも選考の対象外なのだが、せっかく書いたイラストということで一緒に送りつけることにしていた。
その枚数はなんと8枚。やる気を出したハルカは凄まじいほど筆が早く、まるで毎日絵を描き続けるプロのようなタッチでさらさらと書き上げていた。
「そうか、なら安心だな」
「あ、そうそう。関係ないんだけど、イラストと言えばさ、ボクがずっと好きだったイラストレーターさんがいるんだけど……昨日の夜に突然アカウントを消しちゃったんだよね。それもネットにある全部のアカウントだよ?」
今度は佐山がほっと一息ついた最中、カスミが不満そうにスマホを見ていた。
Twitterのページを見ているらしく、そこには【アカウントは削除済み】と記載がある。
「気分転換でもしたんじゃねぇーの?」
あまり興味がない佐山は適当に答える。
「そうかも……最近は面白いシリーズを投稿していたのに、ここ数週間はずっと音沙汰なかったんだよね~。昨日の夜もいきなりアカウントを消したし……はぁぁぁ、ファンだったのになぁ」
「そんなに好きだったのか? 俺でも知ってっかな? そういうイラストとか小説とかアニメとか漫画とか、全然詳しくねぇけどよ」
根っからのスポーツマンで国民的なアニメすらほぼ知らない佐山にはわからないと思うが。
「どうだろ? この人だよ」
「【すたぁ☆彡】? 聞いたことねぇわ」
案の定、佐山は間抜けな顔で首を傾げていた。
かくいうアオトも、イラストレーター事情には明るくないので、聞いたことがない名前だった。
「えー! Twitterで50万人以上もフォロワーがいた有名人だよ!? しかも、現役女子高生って噂だし!」
「ほー、そりゃすげぇな。確かに、そんな有名人が急にそんな真似したらおかしいって思うのも無理もないわな」
「でしょー? アオくんはどう思う? というか、知ってる?」
「知らないな。Twitterなんてやったことないし……」
カスミはノリノリで尋ねてきたが、アオトは本当に全く知らなかった。LINE以外にSNSは触っていないので当然だ。
「だよねぇ……まあ、またいつか復活したらその時はもっと好きになってると思うんだ!」
「なんでだよ?」
「アオくんに会った時がそうだったからだよ! 焦らすとは違うけど、やっぱり会いたい人に会えなくて辛くなっても、また再会できたら嬉しいもんっ!」
カスミは溌剌とした澱みのない笑みを浮かべた。
随分と素直に言葉をぶつけてくる。
思わずアオトは口角を緩めた。
「俺と再会したのも喜んでくれよなぁ?」
「嬉しいよ! 嬉しいけど……アオくんは抜かせないよ!」
「くぅぅっ! まあ、いいけどよ!」
「ちなみに話を戻すと、【すたぁ☆彡】さんはね——」
中央には寡黙で静かなアオトと、両端には騒がしくもあり楽しい2人が座り、そんな時間は子供の頃のまま何一つとして変わっていなかった。