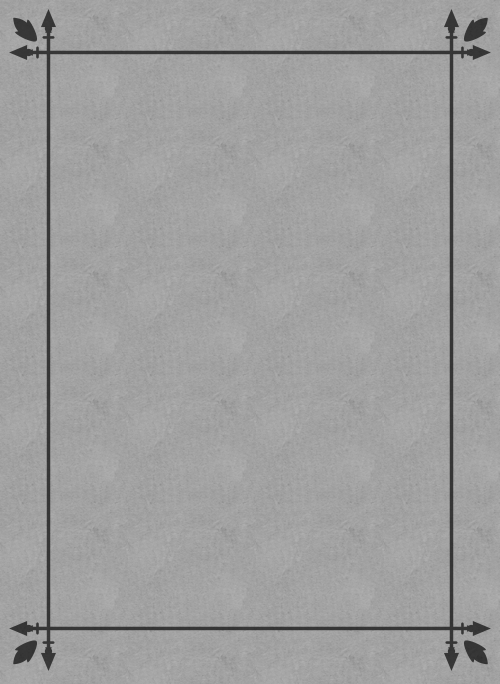ある日の放課後。
私は外が暗くなるまで教室に残っていた。
誤算だった。まさか家の鍵を忘れてママが帰ってくるまで入れなくなるなんて。
カフェとかカラオケに行って時間を潰すことも考えたけど、最近は勉強に力を入れていることもあって、その日は1人で勉強することにした。
既に他のみんなは下校していて、教室はおろか校内の生徒の殆どがいない。
だから、気が緩んでしまった。
普段は自室以外で表に出てこない負の感情が顔を出してしまった。
そして、あろうことか、その光景を誰かに見られてしまった。
私は焦燥感に駆られた。
逃げ行く覗き見犯を必死で追いかけた。でも、足が速くて捕まえられなかった。きっと運動部の生徒に違いない。
「……どうしよう」
8時を回ったところで、焦りながらも帰宅した私は、自室に入った瞬間に絶望感に襲われた。
もしも、あんな私の姿が喧伝されでもしたら、この先の高校生活は終わりを迎えることになる。
状況は最悪だし、頭が上手く回らない。
まずは落ち着かないと……。
ベッドの上で仰向けになって大きな深呼吸をした。
それから、何となく気分を鎮めるために部屋の掃除を始めた。
すると、小説とか教科書をしまっている本棚の奥に、手のひらサイズの懐かしい手帳を見つけた。
「これって……」
私は一目で思い出した。
これは、昔、入院していた時に病院のベッドの上で書いたものだった。
それは今すぐにでも忘れたい記憶だったし、内容は鮮明に覚えているけど、何をする気も起きない私は恐る恐るページをめくった。
あれはずっと昔の子供の頃。
パパがママに変なちょっかいをかけていた。
それは、別に顔を思いきりグーで殴ったり、足の骨が折れるほど強く蹴るとかそんなんじゃなくて……小さな棒状のもので頭を軽くぶってみたり、ちょっと尖ったペン先なんかで腕とか足を優しくツンツン刺してみたりする程度だった。
だから、特に疑問には思わなかった。
2人は仲が良かったし、ずっと優しかったから、きっと戯れ合ってるだけだろうって思ってた。
でも、それは最初だけだった。
何週間か経つと、パパはママが怯えている様子を見るのが楽しくなっちゃったのか、戯れあいは次第にエスカレートしていった。
パパはずっと笑っていた。
怖いくらいに笑っていた。
ママの肩を力強く殴打した時も、ママの頬が赤く腫れるくらいのビンタを見舞った時も……こっちには目もくれず、ただひたすらにママに暴力を振るう愉悦に浸っていた。
前までのパパは、朝6時に起きて仕事に行って、夜の6時に疲れて帰ってきて、みんなで晩御飯を食べて仲良く眠っていたのに、その時から1日のほとんどを家の中で過ごすようになった。
その度に、ママは涙を流しながら悲鳴をあげていたけど、閉め切った窓の外には声は響かないし、暴力でできた傷跡は服の下に隠れて誰も気付かなかった。
当時は子供だったから、何も分からなかった。
これが当たり前なんだって。普通なんだって。おかしくないんだって。そう思っていた。
だから、ママがそんな目に遭ってることなんて誰にも相談しなかったし、みんな同じなんだって思っていた。
でも、少しだけ不思議に思っ他時に、パパがいなくなった後に声をかけてみたこともある。
「ママ、大丈夫?」
ママは泣き腫らした顔に笑みを作り、大丈夫だよって言う。
今思えば、あの時のママは絶対に大丈夫じゃなかったのに、子供に怖い思いをさせないために頑張っていたんだと思う。
そんな日常が1ヶ月くらい続いたある日。
ついにママが痛がる素振りも見せなくなった。
エスカレートしすぎた戯れあいは、ママの心身を破壊してしまった。
ママは憔悴しきっていた。
1回だけ、電話で誰かに相談しているところを見たことがあったけど、電話が終わった後に凹んでいたから多分何かがダメだったんだと思う。
そういうのも重なって、ママはもう壊れちゃってた。
だから、パパの暴力の矛先は、当たり前みたいにこっちに向けられた。
段階を踏まないパパの戯れあいは、全部苦しかった。辛かった。痛かった。
部屋中に散乱した生米を口に入れられたり、トイレの水を飲まされたりもした。
部屋の中で転んで右肘の辺りを切っちゃった時は、血を止めて治すためだと言って、ライターの火で炙られたこともある。確かにそれで血は止まったけど、代わりに消えない傷が残って、失神するほどの激痛が走ったのを覚えている。病院にも連れていってもらえなくて、保育園を何日も休んだ。
それからは毎日のようにそんな残酷な日常が続いた。
包丁を向けられたりした時は泣き喚いて「助けて」「助けて」って叫んだけど、閉め切られた窓の向こうには届かなかったし、真っ暗で狭い部屋の中では逃げ場がなかった。
おかげで今では尖ったものを向けられると震えが止まらなくなるし、暗くて狭い部屋に行くとパニックになって身動きが取れなくなる。
パパは用意周到だったから、近所の人とか保育園の先生とか、ママのパート先の人には良い顔をして、あたかも自分が善人かのように振る舞っていた。
表裏一体とはこのことだろう。
酷く残忍な家庭での素顔は外では一切見せなかった。
家族3人でお出かけした時も、絶対にママの側から離れないし、携帯も取り上げていた。
ずっと辛かった。
逃げ出したかった。誰かに話したかった。
でも、言えなかった。当たり前だと思っていたから。
そんな日々が続くこと、半年くらい。
ついに私は行動に起こした。
夜中の1時。
その日もパパは狂気的な笑顔を浮かべながらママのことを殴り続けていた。罵詈雑言を浴びせて人格を否定し、酷い扱いを敷いていた。
私はパパに見つからないようにこっそり部屋を抜け出すと、2人がいるリビング以外の家の窓を全部割って回った。右手には濁った水が入れられて小さいペットボトルを持って、がむしゃらに家を駆け回りながら、「助けて!」と何度も叫び続けた。
パパは焦燥感を駆られたのか、私のことを捕まえて馬乗りになると、血が滲んだ拳でお腹を何度も殴りつけてきた。
ママは……私のことを助けることもできないほど衰弱していて、もう目がほとんど開いてなかった。でも、確かに泣いていた。
当時、まだ幼かった私は碌に抵抗もできず、ただひたすらに殴られ続けた。大人の男性の体格でそんな子供が手を挙げられたら、死ぬのは時間の問題だった。
私は痛みに顔を歪めながら、その間もずっと泣き叫び続けた。
そして、どのくらいの時間が経ったか覚えてないけど、多分5分くらいした時だった。
家の玄関扉が勢いよく開かれると、そこからゾロゾロと警察の人たちが家に入ってきた。
どうやら、私の作戦が成功したみたい。
窓ガラスが割れて、外に悲鳴が響いたことで近所の誰かが通報してくれたらしい。
警察の人たちはパパのことを羽交締めにして連行すると、すぐに救急車を呼んで私とママのことを病院に運んでくれた。
その前後はショックが大きすぎたのかよく覚えてないけど、気がついたら別の街に暮らしていて、パパはいなくなっていた。
幸い、私とママは全身の打撲と一部分の骨折だけで済んで、命に別状はなかった。特にママはパパからかなり手加減されていたみたいで、ちょうど言い訳のつくレベルの怪我や傷しかなかったらしい。
でも、私は小さな子供だったから、全身には殴打された青あざと刃物の切り傷、そして肘の辺りに火傷の痕が残ってしまった。
半袖を着たら肘の辺りの火傷痕が見えてしまうし、ショートパンツを履いたら腿の切り傷が露わになる。
水着なんて絶対に着れない。もってのほかだった。
とにかく、子供の頃はそれが正常なのか、異常なのか、それすらも訳がわからなかったけど、今は高校生になったからよくわかる。
あれは異常だ。
他の子達の肌は綺麗で、好きな服を着て、両親とお出掛けを楽しんでいる。
でも、私にはそれができない。
ママはいるけど、すっかり閉鎖的になっちゃって外へは連れて行ってくれなくなった。
私も同じだけど、ふとした拍子に当時のトラウマが今でも蘇るし、自分という人間を曝け出すのが怖くなっていた。
体と心はうまく連動しているみたいで、体を出したくないからこそ心も公にしたくなくなっていた。
だから、あれから私は自分を隠すようになってしまった。
自分を隠して、懸命に、懸命に……生きている。
「……」
読み終えた私はそっと手帳を閉じた。
まるで小説の中の世界のような、残忍さを思わせる内容だった。
「この後も大変だったんだよね」
私は小学校と中学校の9年間に経験したイジメを思い出す。
その時は閉鎖的で暗かった私は、地毛の明るい金髪を揶揄われ、傷を見せたくないからプールに入れないことを笑われ、汗をかいて暑くても上着を脱げないからバカにされ、事情を話したくない私に教師は詰めより、ママもトラウマから口を開けず俯くばかり……最悪だった。
当時、私が唯一信じられたのは自分の絵の世界だけ。
友達は全くいなかったから、私はずっと絵を描いていた。
今思えば、その時にたくさん絵を描いたおかげでイラストレーターになれたわけだけど……多分、そうなったのは誰かに認められたい欲求が強すぎたからだった。
そして、私は高校生になると同時に変わることにした。
明るい金髪を活かすために性格も明るくして、みんなに好かれるために八方美人になった。北海道の田舎に住んでいたけど、ママと一緒に札幌に越してきて。顔見知りが1人もいない高校を選んだ。
みんなとの人付き合いを完璧にこなして、周囲から認められるように快活な自分を演じ、偽り、ネットの世界でも有名になることで承認欲求を満たしていた。
そんな時、降谷くんに出会った。
隣の席に座る単なるクラスメイト。頭が良くて寡黙。何度か話したことはあったけど、どんな人なのかはよく知らなかった。
彼は恋愛小説を書いていた。
頭が良いから読める範疇ではあったけど、内容はダメダメだった。
でも、評価する私を見て一喜一憂し、普段の無口な姿とは違ってよく話す姿は印象に残った。
降谷くんに興味が湧いた。
デートに誘ってみると案外悪くなかった。不器用なところも彼らしく思えたし、気まずさはあんまりなかった。
勉強だって教えてくれた。暗記任せの横暴なやり方かと思ったけど、自習の時はちゃんと理解に繋がったし、最後は赤点回避を成し遂げて良い結果が出た。
降谷くんにますます興味が湧いた。途中、西園寺先輩のことが嫌いになったりしたけど、そのおかげで彼の優しさに触れることもできた。
初めてだった。誰かを想うなんて。
「……でも、それももう今日で終わりかな」
私はベッドに倒れ込む。
降谷くんの友人である佐山くんがバラしたら何もかもがおしまいだ。
明日からちゃんと学校に行けるかな
もう今日は疲れちゃった。
心身に疲弊を感じた私は、途端に頭痛に苛まれてしまい、気が付けば眠りの世界に堕ちていたのだった。
イラストを描く気力はもうない。
もしも私の噂が広まっていたらと思うと、学校に行くことすら怖くなる。
そして何よりも、私のことを信じてくれていた、みんなに幻滅されたくない。特に……降谷くんにはね。
◇◇◇◇◇
京都府へ修学旅行にやってきた一行は、美しい京都の街並みに圧倒されていた。
古い町並みが続く狭い路地や、石畳の道を歩くと、そこには歴史と伝統が息づく風景が広がっている。
紅葉の季節に近づきつつある中、古い町家や寺院の屋根には静かに色づき始めた葉が見える。街中には観光客や地元の人々が行き交い、古都ならではの賑やかさが漂っていた。
また、伝統的な味わい深い建物や街並みが調和し、京都ならではの風情が溢れている。さらに、静寂な雰囲気漂う庭園やお寺、神社など、歴史と文化が息づく場所も訪れ、修学旅行生たちは京都の魅力に心を奪われていく。
一行はそんな風景を眺めては一喜一憂し、スマホを片手に持ち記憶と記録に刻み込んでいく。
しかし、そんな一行の最後尾を歩くアオトからすれば、修学旅行なんて心底どうでもいいイベントだった。
というのも、3泊4日なのでその間は一度も家に帰れず、遠方の京都府で過ごすことになるからだ。
インドアな彼からすれば憂鬱でしかない。
唯一の救いと言えば、スマホを用いて執筆作業に取り掛かれることくらいだろうが、それでもたった1人見知らぬ土地で過ごすのは苦痛以外の何者でもなかった。
更に言うと、ここ最近はハルカとのLINEでのやり取りが全くなく、以前のような心底つまらない日常に逆戻りしてしまったのも気が乗らない要因の一つだった。
ハルカから返信が来ない理由は定かではなかったが、佐山からあの話を聞いたその時から音沙汰がなくなったのできっと関係しているのだろう。
そのせいで小説の執筆も進まないので、アオトはやることが完全になくなっていた。
それほどまでにアオトにとって小説の執筆というのは、最近では何よりも欠かせない習慣になっていたということだ。
「はぁぁぁ……」
ベンチに座るアオトは、深いため息をついた。
修学旅行の初日は一行で歴史的建造物を観光し、その後の2日目と3日目は完全な自由時間となる。そして、4日目には帰宅の準備が待っているが、それまでは1人で時間を潰さなければならない。
地獄……とまでは言わないが、やはり孤独を極める彼にとっては退屈と言わざるを得なかった。
唯一の友人である佐山はサッカー部の連中と一緒だし、アオトからすれば親しい部類に入るハルカだって仲の良いクラスメイトに囲まれている。
「帰りたい」
アオトがそんな思いに耽って俯いていると、突然隣に誰かが腰を下ろした。
「ん?」
「——アオく……間違えた、降谷くん。1人なの?」
アオトに声をかけてきたのはダークブルーのポニーテールを揺らすカスミだった。
「白銀さん、1人で過ごす俺のことを茶化しにきたのか?」
アオトは少し疑い深い様子で言う。
彼女が転校してきたその日こそ意味不明な会話を交わしたが、それ以降は単なるクラスメイトとして過ごしてきたので、彼からすれば唐突の出来事に驚いていた。
しかし、当のカスミは笑顔で否定する。
「そんなんじゃないよ。ただ、ボクも一人だったから声をかけてみただけ。それにしても……本当にアオくんにそっくりだよ。あっ、ちなみにアオくんっていうのは、明るくて笑顔が綺麗なボクの大好きな男の子のことね?」
「……見ての通り仏頂面で不気味な俺が、そのアオくんに似てるって?」
アオトはカスミの言葉に混乱しながらも、以前泣かせてしまったこともあり、少し戸惑いながらも口を開く。
彼女は彼のことを昔馴染みの”アオくん”の姿と重ねているのか、瞳の奥はキラキラと輝いている。
「うん。笑顔はわからないけど、雰囲気は似てるよ。まあ、降谷くんは一匹狼って感じかな?」
「俺はひとりぼっちなだけだ」
茶化してくるカスミに対してアオトはぶっきらぼうに言葉を返した。
不思議とほぼ初めて話す相手だというのに、彼は彼女との間にどことないシンパシーを感じていた。
「ごめんごめん。アオくんに似てたからついつい……」
「ふーん……そんなに似てるか?」
「うん。そっくりだよ。顔つきとか体格はもちろん昔とは違うけど、ボクはあの頃のアオくんを忘れたりはしないよ。また会いたいんだ。昔、助けてもらった恩を返すためにね!」
「へー」
特に興味のなかったアオトが淡白な返事をするのとほぼ同時。
アオトの友人である佐山の笑い声が遠くから聞こえてきた。
相変わらずゲラゲラとうるさいやつだと思いながらも、佐山の方を一瞥する。
「……相変わらず騒がしいやつだな」
「知り合い?」
「あいつは佐山。俺の数少ない友達だ」
「運動部って感じだね」
「ああ。見ての通り陽気な性格で、俺とは正反対だろ?」
アオトは沈黙を逃れるために何の気なしに友人のことを紹介したのだが、それを聞いたカスミはじっと瞳を細めて佐山に視線を向けていた。
それが何を意味するのか、アオトにはわからない。
「……うーん……降谷くんと佐山くんは友達なんだ。としかして、幼馴染とか?」
「まあ、そうだけど……まさか、佐山も知り合いに似てるとか言い出すんじゃないだろうな?」
素っ頓狂な事を言い出しそうなカスミに対して、アオトは溜め息混じりに聞き返す。
しかし、カスミにとっては彼の言葉が意味深いものだったのか、唐突に目が大きく見開かれ、驚きの表情を浮かべた。
そして、見るからに動揺した様子を見せながら口を開こうとする。
「——かすみん~、そろそろバス移動だってさー」
カスミが何かを言葉にしようとした瞬間だった。
彼女の友達がぱたぱたと駆け寄ってきた。
「う、うんっ、今行くよ! じゃあ、降谷くん……また話そーね! 絶対だよ!」
「……ああ、機会があればな」
カスミが立ち去り、取り残されたアオトの頬には秋の乾いた風が静かに吹きつけた。
彼はまだ彼女が言いかけた言葉の真意を理解できず、心の中には確かな疑問が渦巻いていた。
その時、彼はふと、幼い頃の記憶が蘇り、遠い過去の出来事が頭をよぎったが、その記憶の正体をはっきりと思い出すことができなかった。
「……まさか、な」
アオトは遠くなるカスミの後ろ姿を眺めた。
何の気の迷いか、彼は、あの時の幼馴染の少年を一度は想起したが、やはりルックスも苗字も、ひいては性別すらも違うことからすぐにその可能性は捨て去った。
「白銀、香澄……」
アオトは一人でにカスミの名前を口にした。
すると、今度はいつの間にやら隣に佐山が腰を下ろしており、彼は不思議そうな面持ちでアオトのことを覗き込んでいた。
「アオトぉ~、暗い顔してどうしたんだよ? あ、いつものことか?」
「……佐山か」
アオトは冗談混じりで煽ってくる佐山のことを睨みつける。
「んぁ? その様子だと、あれから星宮さんとは全然話してないみたいだな」
開口一番、佐山はアオトの耳元に顔を近づけて小声で囁いた。
声色はニヤリと笑った顔が浮かぶほど上擦っている。
「……まあ、そうだな。ちょっと避けられてる感じがするんだよ」
「そうかそうか。実は俺も同じなんだよ」
「佐山も?」
少しばかり口角を上げている佐山だったが、アオトからすればナイーブな問題だった。
「多分、俺がこそこそ覗き見してたってことがバレたんだろうなぁ。今思えばあん時に目ぇ合ったような気がするし。今もチラチラこっちを見てるだろ?」
佐山は少し離れた位置で友達と群がるハルカを横目でチラリと見た。
アオトもつられて確認すると、ちょうどハルカがこちらに視線を向けていた目が合った。
ハルカはハッと驚いたように口を開くとすぐに目を逸らした。
「ほんとだな……じゃあ、前の話は本当だったのか?」
アオトは驚愕の表情を露わにした。
少し考えていたことではあるが、今のハルカを見たら佐山の証言の現実味が増してきた。
「マジもマジ、大マジだよ。俺の脳裏には今でも焼き付いてるぜ。人当たりが良くて美人で人気者の星宮さんが弱気に愚痴ってたあの瞬間がな!」
「うーん……いやぁ、でも……やっぱり信じられないな」
アオトは信ぴょう性が高まりながらも、これまでのハルカのことを考えると佐山の証言を信じきれなかった。
ハルカは自分の小説を読んでくれて評価をしてくれたし、2人で映画を見に行ってくれた。その後はカフェで会話を交わしてコンテストへの参加を勧めてくれた。
勉強会を通して2人きりの時間を多く過ごし、協力してテストを乗り越えた。
自分のためにイラストを描いてくれて、一緒に頑張ろうとエールを送ってくれた。
そんな快活な彼女が、途端に元気をなくす姿なんて全く考えられなかった。
「お前の気持ちもよくわかるよ。だがよ、ここ最近よ星宮さんはちょっと様子がおかしいだろ? 皆勤賞だったのに急に学校を休んだり、早退もしてるって話じゃねぇか。友達は相変わらず多いみたいだけど、今も上手く笑えてねぇように見えるぜ」
慰めるような口振りの佐山の言葉には確かな信憑性があった。
隣の席だからアオトはよくわかっているが、確かに最近のハルカは休みがちで、登校してきても昼前には早退していることが多かった。
原因は体調不良だと担任は言っていたが、単なる体調不良ならLINEを返さないはずがないし辻褄が合わない。
ほぼ確実に彼女自身の何かに問題が生じたのだ。
「……確かにな」
「だから、上手く見守ってやれよ」
「……この前とは随分意見が違うじゃないか」
「俺だってよ、きつい練習の後は愚痴を吐くし、見知った人が亡くなったりしたら辛くなるんだよ。きっと星宮さんが弱気になって体調を崩してるってのもそれと一緒じゃねぇかなって思うんだよな」
佐山にしては珍しく論理的な思考回路で会話を広げた。
「まあ……概ね同感だ。星宮はきっと俺たちの見当もつかないような”何か”を抱えてるんだろうけどな」
「だな。ところでよぉ、さっき白銀さんとは何を話してたんだ?」
「……あー、それについても実は1つ聞きたい事があるんだ。佐山は、子供の頃の出来事って覚えてるか?」
アオトは鋭い佐山の言及をひらりと交わすと、話題を転換させて彼に尋ねた。
「子供の頃っていつのことだ?」
「俺とお前と金ちゃんの3人で遊んでた頃だよ」
「あーあー! 金ちゃんか。最後まで下の名前は知らなかったけど、苗字が金城だからそう呼んでたよな。随分と懐かしい話だな」
佐山は腕を組み何度も頷いた。
アオトと同じく、彼も件の”もう一人の存在”についてよく覚えているようだ。
「例えばの話だけど、最近俺のクラスに転校してきた女子生徒が、その金ちゃんって可能性はないよな?」
「ないない。ありえねぇよ。転校生の女子生徒って、白銀さんだろ。金ちゃんは短髪でイケイケ系の男気溢れるタイプだったろ? 正反対すぎてありえねぇよ」
アオトは恐る恐る尋ねたが、佐山は間髪入れずに真っ向から否定した。
やはり、あの小動物のようなカスミが金ちゃんと同じには到底見えないらしい。
かくいうアオトもそれは同感だった。
「悪い、変なこと聞いた」
「いいってことよ。それにしても、いきなり金ちゃんのことを思い出すなんて何があったんだよ。あいつは急に引っ越しちまってそれっきりだろ。当時はLINEなんて便利なもんはなかったし……もうお互いに成長したから会ってもわかんねぇと思うぜ? しかも、ありゃあ俺たちが5歳くらいの時の話だしな」
佐山の言うことはもっともだった。今や互いに見た目も性格も変わりすぎている。
幼い頃のアオトは、明るい性格だった。
昔から陽気な性格のままでいる佐山ならまだしも、今のアオトは真逆の暗い性格に変わり果てている。
更に顔つきも体つきも大人っぽくなり、多少なりとも子供の頃の面影があろうと、10数年越しに会った人が見てわかるはずがなかった。
「だよなぁ……さすがに会ってもわからないだろうな」
「やっぱ会ってみてぇのは確かだけどな!」
アオトの返事を受けた佐山は懐かしそうに微笑んで続ける。
「そうだな」
「懐かしいなぁ、マジで……」
感傷に浸りつくす佐山。
同様にアオトも徐々に昔の記憶を思い出し、懐かしい記憶に入り浸る。
「突然いなくなった前の日、泣いてたもんな。それだけ俺たちと離れ離れになりたくなかったってことなのかな?」
あの時の金ちゃんの顔は忘れない。
まるで絵本の世界の女の子のように、大粒の涙を流して泣き続けていた。
普段は勇ましく凛々しく、男らしかった金ちゃんが、あの時だけは泥だらけの手で俺の服の裾を握っていた。甘えん坊な妹ができたような感覚だったのをよく覚えている。
「かもな。んでよ、今話していて気づいたんだけどよ。多分、金ちゃんがいなくなった原因ってあれじゃねぇの?」
「あれってなんだよ」
「あれだよあれ。金ちゃんの体には生々しい青あざとか妙な怪我とか傷がたくさんあったろ? んで、それを不思議に思ったお前が、近くの交番に駆け込んだんだよ。覚えてないか?」
「覚えてる……あー、そういうことか」
アオトはふと思い出した。
そして、一つしか考えられない結論に辿り着く。
「そうそう。金ちゃんは強気な性格でいつも笑顔だったから、正直、俺は全く変化に気付かなかったけど……ありゃあ十中八九、DVを受けてたんだろうな」
佐山は腕を組み何度か頷き、渋い顔つきになっている。
「俺もそう思う。いち早く気付けて本当によかったよ」
「というか、アオトはなんで気付けたんだ? 時期的にもあん時は秋口で、金ちゃんはずっと肌を隠すような服ばかり着てただろ?」
「んーーー……金ちゃんとは、たまたま公園で出会ってから遊ぶようになって、結局は半年くらいしか一緒に過ごしてなかったわけだけど、日に日に笑顔が崩れていってたんだ。特に、夕方になって帰る頃には泣きそうな顔になってるのを見たことがある。きっと家に帰りたくなかったんだろうな。それを見てちょっとだけ不思議だなぁって当時の俺は考えたんだと思う」
「それにしても、よく気付けたな」
「まあ……他にも、鬼ごっこの時に服を引っ張ったら、偶然右腕の袖が捲れて傷が見えたりもしたし、そん時は佐山も一緒だったろ」
アオトにとっては、些細とまでは言わないがそれほど印象深い出来事ではなかったが、金ちゃんの腕や首元に青あざがあることに気が付き、何の気なしに交番へ向かった事は記憶に残っていた。
まさかそれがDVだったとは、当時の彼にはわからなかったが。
「あぁぁーーーーーー、あれか? 右腕の肘辺りにあった火傷痕だろ。結構、痛々しかったし、あの感じだと一生消えねぇだろうなぁ」
佐山は顎に手を当て口を開く。傷についてもよく覚えているのか、その位置と具合まではっきりと口にしていた。
対するアオトは、佐山ほど鮮明には覚えていなかったが、彼の言葉を聞くことでふと頭の中に疑念がよぎる。
「……右腕の肘辺りにあった火傷痕……? ん? 待てよ……最近、どこかで見た気がするな」
過去を懐かしむ佐山とは対照的に、アオトはつい最近の記憶の中でそれと近いと思しき痕跡を探した。
この短い時間では考えても何も閃かなかったが、確かにどこかで見た記憶があった。
「まあ、とにかくだ。金ちゃんは、あんな小動物みたいなか弱い女の子なわけねぇよ。な?」
「そうだな」
「おう。んじゃ、時間だから行くぜ。修学旅行、楽しめよ?」
佐山はそんなアオトの思考などつゆ知らず、遠方に見えるカスミに指を差すと、それだけ言い残して立ち去った。
どうやら既にこの場での自由時間が終わりバスや出発時刻らしい。
思いのほか、アオトは佐山と長話をしていたのか、周りに他の生徒の姿は見当たらなかった。
「……俺も行くか」
アオトは重い腰を上げてベンチから立ち上がると、のそのそとした足取りでバスへ向かう。
この後は旅館へ向かってから夕食を摂り、各々が入浴を済ませたら、就寝までの間は自由時間となる。
当然ながら夜も特に予定なんてなかったのだが、バスの座席に着いた時にLINEを開くと、数週間ぶりに件の相手からメッセージが届いていることに気がついた。
『降谷くん。今夜の8時、旅館の裏手でお話ししない? 待ってるね』
◇◇◇◇
星宮晴香は気分がすぐれなかった。
せっかくの修学旅行だというのに、数週間前から虫の居所が悪い。
彼女がそうなる要因は2つあった。
まずは1つ目。アオトと遊びに行けていないせいで、イラストが描けずに承認欲求を満たせていないこと。
そして2つ目。これは一つ目と大きく関係しており、佐山に自身の裏の顔を見られてしまったこと。
まとめると、全ては佐山という男子生徒のせいだった。
彼女はあまり彼のことを認知していないが、陽気で明るい性格でアオトの唯一の友人であることくらいは知っていた。
だからこそ、不安だった。
——佐山くんにあのことをバラされたら、降谷くんとの関係が途絶えてしまう。そうしたら、イラストを描くこともできなくなるし、誰かに認められて承認欲求を満たせなくなる。それだけは避けないと……!
今もハルカの視線の先には、ニヤニヤ笑う佐山と、そのすぐ側でボケェっとしているアオトの姿があった。
2人とも心を許し合っているのか、かなりリラックスしている。
少なくとも、ハルカの前でアオトはあんな顔を見せたことはなかった。
「……佐山くん、余計なことは言わないでよね……」
ハルカは佐山の様子をちらちらと確認する。
何となくでしかないが、佐山とアオトの表情を見る限り、自分に関する話をしているというのがわかった。
それもこれも、あの日の放課後のアレを佐山に見られたせいだ……ハルカは力強く歯を食いしばる。
普段は家の自室で不満や愚痴を吐き出すのだが、あの日は家の鍵を忘れてしまったので教室に残るしかなかった。
だから、ああやって1人きりの教室で叫んでいたのだが、まさか佐山に見られるだなんて彼女の予想外だった。
1つ良いことがあったとすれば、何の気の迷いか佐山が件の話をおかしな噂に昇華させて流布していないことくらいだろうか。
「はぁぁ……」
「ねぇねぇ、晴香、みんなで西園寺先輩にお土産買っていくかどうか悩んでるんだけど……」
ハルカが溜め息を吐くと、女友達が声をかけてきた。
「西園寺先輩か~、あの人なら変わり種の方が喜んでくれると思うよっ! 独特な感性持ってそうだし!」
ハルカはなんて事のない女子同士のやり取りにも対応しつつ、尚もその視線は佐山へと向けていた。
彼女からすれば変態男の西園寺なんて心底どうでもよかった。唯一、明確に嫌悪感を持つ相手でもあったからだ。
「ってかさぁ、さっきからずぅーっとどこ見てんの? あ、まさか佐山くん? チャラい見た目だけど確かにイケメンだよねぇ。でも意外かも、晴香ってどちらかというともっとクールな感じが好きでしょ?」
「え!? ち、違うよ! 違うからね!? 私、ほんっとにああいう感じはタイプじゃないから!」
女友達の煽りを間に受けたハルカは、あからさまに取り乱して否定したが、外向けの言葉遣いや態度を崩すわけにはいかず曖昧な反応になってしまった。
「怪しい取り乱し方だねぇ。じゃあ何、佐山くんと話してる冴えない降谷くんがいいの? まあ、彼も顔だけなら中の上って感じだけど、何せ暗いからなぁ~、1度も喋ってるとこ見たことないかも」
「……んー、佐山くんと降谷くんなら、断然降谷くんの方がいいかな」
ハルカは真面目な落ち着いたトーンで答える。
彼女にとっては愚問だった。考えるまでもなくアオトことを選択する。
それを聞いた周囲の女友達は驚いて固まっている。
表情からして、どうやら冗談のつもりでアオトのことを薦めていたようだ。
「へー……じゃあ、ますます晴香の好みがわからなくなるね。イケメンでも西園寺先輩はダメだったみたいだし、同い年の佐山くんもダメ。でも、根暗で静かな降谷くんならOKなんだ?」
「……OKってことは絶対にないただ、降谷くんは、悪い人ではないからね」
「席も隣だしたまに話してるもんね。テスト期間なんて図書室で二人で勉強してるなんて噂もあったし……ずっと気になってたんだけど、2人はぶっちゃけそういう関係ってこと?」
1人の女子がおずおずと口にすると、周囲の皆がキャーキャーと騒ぎ出して辺りには喧しい黄色い声が飛び交うことになる。
それほどまでに皆がハルカの恋愛事情について興味があるということだろう。
「確かに、降谷くんの下の名前ってアオトだし、ハルカと合わせたら、アオトとハルカでアオハルだよね! なんか運命って感じ!」
続け様に別の女子が満面の笑みを浮かべて言葉を続ける。
「でもでも、降谷くんと晴香じゃ全ッ然釣り合わないってー! あんなぶっきらぼうで冷たそうな人と付き合ったら、優しくて温厚な晴香が毒されちゃうよー」
「それもそうだねー。降谷くんってクールってよりはドライな感じで、何にも興味とかなさそうだし、デートとかしても気遣いできなさそうだもんね。ね、晴香?」
数名の女子はアオトが遠くにいるのをいいことに、思い思いの負の感情を言葉にした。
本人が聞いたら傷つくのは明白だったが、彼女たちは他者を虐げることでハルカの評価をより上の水準に持って行こうとしていた。
みんなが一様にニヤニヤと悪どい笑みを浮かべ、ハルカの返答を待っている。
しかし、当のハルカはそれが冗談だとわかっていようと、感情の昂りを抑えられなくなっていた。
彼女は誰にも聞こえないように小さく舌打ちをして口を開く。
「……ごめん。みんなさ、降谷くんの何を知ってるの?」
「え?」
ハルカが普段は表で見せない本気のトーンで言葉を紡ぐと、一同は素っ頓狂な顔つきになり固まった。
そんな彼女らの様子など気にすることなく、ハルカは一つ息を吐くと、
「降谷くんは優しいよ。少なくとも、他のどの男子よりもね。気遣いもできるよ。勉強も教えてくれたよ。誰かのためにそういうことができるのって優しいってことじゃないの? 違うかな?」
続け様に言い放つ。
最後に同意を求めたが、この場にいる女子全員が押し黙る。
数秒の沈黙。
その後、あまりの異様な空気に耐えかねた1人が空笑いを浮かべる。
「あ、あははは~! ご、ごめん! みんなほんの冗談のつもりだったんだけど……晴香、なんでそんなマジになってんの? ちょっと怖いって……ねぇ?」
普段は温厚で尚且つ人当たりが良く、声色も言葉も態度も柔らかなハルカの変わり様に対して、先ほどまで冗談めかしていた彼女たちは萎縮していた。
頬をひくつかせて、ギョッとした目つきでハルカのことを横目で見ている。
それとほぼ同時に、ハルカは表面上のいつもの自分を制御できなくなってることに気がつくと、すぐさま表情を取り繕って言葉を紡ぎ始める。
「やだなぁ! こっちも冗談だよ! そういうノリかと思ったんだけど違ったかな~?」
「な、なーんだ……それならよかった。晴香があんな怖い顔してるの初めて見たからびっくりしちゃったよ……ね?」
「う、うん」
「空気読めなくてごめんね! まあ、降谷くんとそういう関係じゃないのは本当だよ! 悪い人じゃないのも間違ってないしね! 彼は本当に優しいよ!」
皆がほっと胸を撫で下ろす様を見てハルカも安心すると、いつもの口調と形相で声色を高くして空気を一変させた。
そんな彼女が吐いた言葉に嘘はなかったが、真実でもなかった。
「……確かに、思い返してみると、降谷くんって嫌な顔せずペンを拾ってくれたり、黒板の板書を消す時もしれっと手伝ってくれたりするよね。本人は全くこっちに興味なさそうだけどね」
「そうそう! 降谷くんって意外にそういうとこあるかも! となると……やっぱり悪くないんじゃない? めちゃくちゃ無口な部分を除けばね。だよね、晴香?」
「うん。そうだね……」
晴香は同意を示しつつも、胸中では目の前の彼女らに呆れきっていた。
——私が一回顔色を変えたらすぐこうなるなんて、やっぱり誰も彼もが他人の本当の内面に興味がないのかな。
きっとそれは私が相手でも同じ。きっと、私がさっきみたいな態度を続けていたら、みんなはあっという間に離れていく。
だから、私は本当のことも言えず、ああやって冗談めかした答えを言って誤魔化すしかできない。
くだらないよね。他人をバカにして、上辺の付き合いだけで満足するなんて……。
でも、それは私も一緒か。もう更新はやめちゃったけど、ついこの前までネットに降谷くんを題材にしたイラストを投稿してたわけだし……あれも結局は無断で利用してバカにしてるってことだもんね。
ハルカは真実の思いは口にせず、そっと心の中にしまいこんだが、溢れ出てくる言葉は止まるところを知らなかった。
少しだけ1人になりたい。そう思っていた。
「ごめん、今日の夜は少し部屋を空けてもいい?」
ハルカは照れ臭そうな様子を演出して周囲に視線を送る。
柔らかな言葉と視線を用いることであえて自分に注目が集まるように仕向けた。
「いいけど……みんなで人生ゲームやる予定だよ?」
「私はちょっとだけ用事があるからごめんね? また明日時間作るからさ」
「用事……もしかして、告白とか?」
案の定、女友達の一人が勘違いしてくれたので、ハルカはここぞとばかりに言葉を紡ぐ。
「んー、恋愛の告白とかじゃないけど、今夜はそっとしてくれると助かるかな~」
「おーおー、凄いじゃん! 相手は誰なのか、結果はどうなったのか、その辺りはまた今度絶対に聞かせてよね!」
「うん。わかったよ。じゃあ、ちょっとお手洗いに行ってくるね」
思わせぶりな言葉だけを残したハルカは絶好のタイミングで集団を抜け出し、足早にトイレへと逃げ込んだ。
これは質問攻めから逃れて、尚且つ相手を勘違いさせる彼女の作戦だった。
「……はぁぁぁ……なんでイラストはバズってたのに、前みたいに満たされなくなったんだろ」
トイレの個室に逃げ込んだハルカは、首を垂らして頭を抱えた。
彼女は最近はもうイラストの投稿を辞めていた。
佐山に自分の本当の姿を覗き見されて以来、描いても描いても虚しくなるばかりで、何一つとして心が満たされなくなっていたからだ。
ハルカはその原因はわかっていた。
アオトだ。アオトに嫌われてしまうのが怖くなっていた。
好き……という気持ちはまだわからなかったが、もしも自分の本性がアオトにばれたらと思うと、何も手がつかなくなってしまったのだ。
学校も休みがちになり、登校しても早退を繰り返し、アオトから心配のLINEが来てもまともに返せない。
ハルカの精神は確実にすり減っていた。
彼女は過去の自分に起きたトラウマから逃げられず、傷ついた肉体を隠すのと同じくその心も閉ざしたままだ。
だから考えた。
「……降谷くんは、優しいよね。私の傷を癒してくれるかな」
ハルカは未読が溜まりに溜まったアオトとのメッセージ画面を開くと、数週間振りにアクションを起こした。
アオトが自分の誘いを蔑ろにするわけがない……と、ハルカは信じていたのだ。
◇◇◇◇◇
退屈な修学旅行の初夜。
時刻は午後8時を回ったところ。
「いた……」
旅館の裏手を歩くアオトは、前方に見覚えのある人影を発見した。
金色の髪のボブカット。部屋着である浴衣をきっちりと身に纏い、大木の下に置かれたベンチに腰を下ろしている。
何を隠そう、彼女は星宮晴香その人だった。
昼過ぎに佐山と別れてからすぐにLINEが飛んできて、彼は彼女からこんな時間に2人で会いたいと言われていた。
諸々の真意を知るためにも、こうしてのこのことやってきたアオトだったが、やはり妙な緊迫感と疑念に胸を支配されてこれ以上は足が進まなかった。
アオトは声をかけるために距離を詰めようとしたが、同時に佐山と交わした会話の内容を思い出して迷いが生じた。
彼女が俺に付き合ってくれていたのは何らかの打算があってのことだったら?
俺のことなんて眼中になくて、酷い言葉を浴びせてこられたら?
アオトの心の中では様々な疑念と、えも言えぬ不安がよぎる。
故に、彼は友人である佐山を頼ることにした。
右手に持つスマホは佐山との通話が繋がれており、暗転した画面の向こうでは彼がこちらのやり取りを聞けるようになっている。
彼はハルカに内緒でこんな盗聴みたいなことをするのは悪いと思ったが、どこか疑心暗鬼になっている今の心境ではそうせざるを得なかった。
「行くぞ」
アオトは小さな声で呟き覚悟を決めて前方に目をやると、ハルカの元へと歩みを進める。
彼女は大木の麓に置かれたベンチに腰を下ろしており、にひるな笑み浮かべて彼のことをじっと見つめている。
「降谷くん。きてくれたんだ。座ってよ」
ハルカはいつものような人当たりの良い雰囲気をその身に纏っていたが、どことなく異様さを醸し出しており、不自然さを思わせる固い表情だった。
「……」
アオトは一瞬ドギマギしかけたが、すぐに平静を取り繕ってハルカの隣に座る。
2人の間には、人ひとり分のスペースが空いている。
「降谷くん」
そよ風が木々とハルカの髪を僅かに揺らす。
風は少しばかり肌寒いからか、彼女は身を縮こまらせていた。
「……」
アオトはハルカを横目で見る。
右手には画面を下にした状態でスマホを持つ。
「……こんな場所に呼び出しちゃってごめんね」
「別に。俺の方こそ待たせたみたいで悪かったな。寒かったろ?」
「ううん。大丈夫だよ。中には長袖のTシャツを着てるしね」
からっと笑うハルカだったが、あまり実直な笑顔ではなさそうだった。
やはり、様子がおかしい。アオトは彼女の違和感にすぐに気が付くが、まずは話を聞いてみることにした。
「そうか。それで……俺に話があるのか?」
「……うん。実は降谷くんに私の本当の姿を知ってほしかったんだ」
「本当の姿?」
「そう。きっと、佐山くんから色々と聞いたと思うんだけど……私はみんなが思うような人間じゃないんだよ」
ぼつぽつと語り始めたハルカの眼差しは虚空を見つめていた。
「……」
アオトは僅かに首を垂らして話に聞き入ると、おもむろにスマホに指をかけて佐山との通話を切電した。
彼は真面目に話そうとしている彼女を見て、自分が盗聴まがいのことをしている事実を許せなくなっていたのだ。
そんなアオトの心中とは関係なく、ハルカは尚も言葉を続ける。
「私はね、臆病なんだ。みんなに嫌われちゃうのが怖いんだ。だから、必死に自分を隠して生きているんだ。佐山くんから変な話を聞かなかった? 私が放課後の教室で変なことを言ってたとか、1人で愚痴を吐いてたとか……どう?」
ハルカは寂しげな表情を俯かせると、涙ながらに言葉を紡いでいた。
「……聞いた。でも、そこで星宮が何をしていたのかまでは知らないし、佐山も周りに言いふらしてないみたいだぞ」
「でも、いつ言いふらすかわからないよね」
「佐山はそんなことしないと思う。少なくとも、噂を脚色して喧伝するような悪いやつじゃない」
事情は知らなくとも、ハルカが不安に思う気持ちはアオトにもわかった。そして、佐山がそんなやつではないことは誰よりもわかっていた。
「そう……」
「星宮は何をそんなに思い詰めているんだ? 学校にも来ないで、LINEも返してくれないなんて……急にどうしたんだよ」
アオトはおもむろに尋ねる。
様子のおかしいハルカを放っておけなかった。
「降谷くん、きみがそこまで知りたいなら教えてあげる。がっかりしないでね?」
「……ああ」
「私はね、きみが思うような、きみが小説の中で書いているような、理想的な女の子じゃないんだよ。みんなは私のことを性格が良くて、肌が綺麗で、この金髪が可愛いって言ってくれてるけど、実際は全然違う。性格は人から良く見られたくて取り繕ってるだけだし、肌なんて酷いもんだよ……金髪は地毛だし、そのせいで虐められたこともある」
ハルカは悲観的な面持ちで自分自身を卑下した。
それは澱みのない口振りだった。
「……聞いてもいいのかわからないけど、どうして自分を偽ってるんだ? あるがままで接すればいいだろ?」
アオトは語りかけるように尋ねる。
しかし、ハルカはそんな彼の言葉があまり気に入らなかったのか、僅かに眉を顰めていた。
「それができないから困ってるんだよ。私はみんなの前で本当の自分を曝け出せない。声も表情も性格も全部嘘まみれなんだよ。本当は明るく振る舞い続けるのは苦しいし、女の子らしい声も、みんなに向ける笑顔も頑張って作ってるんだよ。だって、そうしないとみんなが離れていくから……みんなが好きなのは、偽物の星宮晴香なんだよ」
「……でも、いつかは自分を曝け出さないとずっと状況は変わらないんじゃないか?」
「じゃあ逆に聞くけど、今の私と話していて楽しい?」
「え?」
唐突な問いかけに対してアオトは惚けたような声を上げる。
「楽しくないでしょ。面白い冗談なんて言わないし、テンポよく会話に参加したりもしないんだよ。降谷くん、本当の私は今の私だよ。テンションが低くて、ノリが悪い人をみんなは楽しいって感じると思う?」
ハルカは落胆したかのように肩を落とした。
膝の上では強く拳を握りこんでおり、やるせない様子が伺える。
だが、アオトからすれば、ハルカと過ごしたこれまでの時間はもちろんのこと、今を過ごすこの時間だって楽しく思えていた。
「……何言ってんだ、お前。バカなのか?」
「は?」
「まだまだ付き合いは短いけど、お前と過ごしてきたこれまでの時間も、今のお前と過ごすこの時間も……俺にとってはどっちも特別だ。俺に付き合ってくれるお前は天使のように見えたよ。それがいくら偽善だったとしてもな」
ハルカが素っ頓狂な顔つきになっていたが、アオトは気にせず思いの丈をぶつけた。
佐山が疑ったように、たとえ彼女に何らかの裏や大きな隠し事があったとしても、アオトはそれを上回るほどの密かな想いを胸に秘めていた。
「……うそ」
「嘘じゃない。佐山以外と碌に話せなかった俺が、こんなに口数多く話すことなんて珍しいんだからな? それに、お前は俺の小説を笑わないで読んでくれたしな。あの時は本当に嬉しかったんだ」
アオトは自分の高校生活が色付く瞬間を肌身で感じていた。
過ごした時間は短いが、それは顕著で、孤独を苦にしない彼がハルカと過ごす時間に喜びを覚えていたのだ。
「降谷くん……」
「だから……んー、あー、なんて言えばいいのかな……とにかく、俺に対してはありのままの星宮でいてくれていいってことだ」
「ふふっ、相変わらず口下手だね~」
言葉に詰まったアオトのことを茶化す。
先ほどとは一転してどこか楽しそうだ。
「ご愛嬌ってやつだ」
「それに、やっぱり優しいね。小説を読んでイラストを描いてあげただけなのに、私のことをここまで信頼してくれるなんて、将来は詐欺に引っかっちゃうよ?」
ハルカはごく自然な笑みを浮かべる。
「まあ、そん時はそん時だよ。それより……やっと普通に笑ったな」
「あ……」
「何で隠すんだよ」
ハルカが気恥ずかしそうに両手で顔を隠したので、アオトは冗談めかした口調で彼女の顔を覗き込む。
すると、彼女はぷんすか怒っているのか、赤面した頬を膨らませて彼のことを睨みつけた。
たわいもないやりとりだったが、ここ数週間はこんなやり取りすらなかったので、彼は確かな幸福を感じていた。
何よりも、アオトは目の前で怒っているハルカの姿が全く怖くなくて、むしろ可愛らしく思えているくらいだった。
「もう……」
「悪い悪い。それより、俺からも1つだけ聞きたいことがあったんだ」
アオトは軽く謝辞を挟んでから姿勢を直すと、少し視線を下に向けた。
「なにかな?」
「答えたくないなら構わないが……星宮の右腕の傷について教えてほしい」
「えっ……ど、どうして……どうして、それを知ってるの……?」
アオトの問いに対し、ハルカは血の気が引いたような表情になる。途端に取り乱しており、疑問を問いかける言葉には色が失い。
「……実は映画館で上着を脱いだ時に少し見えたんだ」
アオトはハルカがここまで動揺するとは思っていなかったので、内心は彼女の変わり様に驚いていた。
「汚いもの……見せちゃったね。ごめんなさい」
「いや、そういう意味で言ったわけじゃない。俺は気になったことがあるだけだ」
「……なに?」
ハルカは見るからに気分が優れない面持ちになり、呼吸も少しばかり荒くなっていた。
自分の身を両腕で力強く抱きしめており、明らかに何かを恐れている様子がわかる。
——今は聞かないほうがいいかもな。星宮の過去に何があったのかは気になるが……おそらく、安易に深掘りしていい記憶ではないだろうな。
アオトはそんなハルカの様子を見て心持ちを変えると、ゆっくりとベンチから立ち上がり彼女に背を向けた
「いや、やっぱりなんでもない。それより、そろそろ旅館に戻ろうか。風邪を引いたら修学旅行が台無しだからな」
「そ、そうだね。でも、私はもう少し夜風を浴びてから戻るから、降谷くんは先に戻ってて?」
「……わかった。またな」
「うん、またね」
アオトはハルカに手を振り別れを告げると、静かな足取りで旅館へと戻る。
道中、茂みの中に隠れてこそこそついてきた佐山を発見したが、彼は突然電話が切れたことを心配して遠くの木陰から見守ってくれていたらしい。
アオトは佐山には深い事情は伝えず、問題はなかったとだけ言い残し、部屋へ戻り眠りについたのだった。
私は外が暗くなるまで教室に残っていた。
誤算だった。まさか家の鍵を忘れてママが帰ってくるまで入れなくなるなんて。
カフェとかカラオケに行って時間を潰すことも考えたけど、最近は勉強に力を入れていることもあって、その日は1人で勉強することにした。
既に他のみんなは下校していて、教室はおろか校内の生徒の殆どがいない。
だから、気が緩んでしまった。
普段は自室以外で表に出てこない負の感情が顔を出してしまった。
そして、あろうことか、その光景を誰かに見られてしまった。
私は焦燥感に駆られた。
逃げ行く覗き見犯を必死で追いかけた。でも、足が速くて捕まえられなかった。きっと運動部の生徒に違いない。
「……どうしよう」
8時を回ったところで、焦りながらも帰宅した私は、自室に入った瞬間に絶望感に襲われた。
もしも、あんな私の姿が喧伝されでもしたら、この先の高校生活は終わりを迎えることになる。
状況は最悪だし、頭が上手く回らない。
まずは落ち着かないと……。
ベッドの上で仰向けになって大きな深呼吸をした。
それから、何となく気分を鎮めるために部屋の掃除を始めた。
すると、小説とか教科書をしまっている本棚の奥に、手のひらサイズの懐かしい手帳を見つけた。
「これって……」
私は一目で思い出した。
これは、昔、入院していた時に病院のベッドの上で書いたものだった。
それは今すぐにでも忘れたい記憶だったし、内容は鮮明に覚えているけど、何をする気も起きない私は恐る恐るページをめくった。
あれはずっと昔の子供の頃。
パパがママに変なちょっかいをかけていた。
それは、別に顔を思いきりグーで殴ったり、足の骨が折れるほど強く蹴るとかそんなんじゃなくて……小さな棒状のもので頭を軽くぶってみたり、ちょっと尖ったペン先なんかで腕とか足を優しくツンツン刺してみたりする程度だった。
だから、特に疑問には思わなかった。
2人は仲が良かったし、ずっと優しかったから、きっと戯れ合ってるだけだろうって思ってた。
でも、それは最初だけだった。
何週間か経つと、パパはママが怯えている様子を見るのが楽しくなっちゃったのか、戯れあいは次第にエスカレートしていった。
パパはずっと笑っていた。
怖いくらいに笑っていた。
ママの肩を力強く殴打した時も、ママの頬が赤く腫れるくらいのビンタを見舞った時も……こっちには目もくれず、ただひたすらにママに暴力を振るう愉悦に浸っていた。
前までのパパは、朝6時に起きて仕事に行って、夜の6時に疲れて帰ってきて、みんなで晩御飯を食べて仲良く眠っていたのに、その時から1日のほとんどを家の中で過ごすようになった。
その度に、ママは涙を流しながら悲鳴をあげていたけど、閉め切った窓の外には声は響かないし、暴力でできた傷跡は服の下に隠れて誰も気付かなかった。
当時は子供だったから、何も分からなかった。
これが当たり前なんだって。普通なんだって。おかしくないんだって。そう思っていた。
だから、ママがそんな目に遭ってることなんて誰にも相談しなかったし、みんな同じなんだって思っていた。
でも、少しだけ不思議に思っ他時に、パパがいなくなった後に声をかけてみたこともある。
「ママ、大丈夫?」
ママは泣き腫らした顔に笑みを作り、大丈夫だよって言う。
今思えば、あの時のママは絶対に大丈夫じゃなかったのに、子供に怖い思いをさせないために頑張っていたんだと思う。
そんな日常が1ヶ月くらい続いたある日。
ついにママが痛がる素振りも見せなくなった。
エスカレートしすぎた戯れあいは、ママの心身を破壊してしまった。
ママは憔悴しきっていた。
1回だけ、電話で誰かに相談しているところを見たことがあったけど、電話が終わった後に凹んでいたから多分何かがダメだったんだと思う。
そういうのも重なって、ママはもう壊れちゃってた。
だから、パパの暴力の矛先は、当たり前みたいにこっちに向けられた。
段階を踏まないパパの戯れあいは、全部苦しかった。辛かった。痛かった。
部屋中に散乱した生米を口に入れられたり、トイレの水を飲まされたりもした。
部屋の中で転んで右肘の辺りを切っちゃった時は、血を止めて治すためだと言って、ライターの火で炙られたこともある。確かにそれで血は止まったけど、代わりに消えない傷が残って、失神するほどの激痛が走ったのを覚えている。病院にも連れていってもらえなくて、保育園を何日も休んだ。
それからは毎日のようにそんな残酷な日常が続いた。
包丁を向けられたりした時は泣き喚いて「助けて」「助けて」って叫んだけど、閉め切られた窓の向こうには届かなかったし、真っ暗で狭い部屋の中では逃げ場がなかった。
おかげで今では尖ったものを向けられると震えが止まらなくなるし、暗くて狭い部屋に行くとパニックになって身動きが取れなくなる。
パパは用意周到だったから、近所の人とか保育園の先生とか、ママのパート先の人には良い顔をして、あたかも自分が善人かのように振る舞っていた。
表裏一体とはこのことだろう。
酷く残忍な家庭での素顔は外では一切見せなかった。
家族3人でお出かけした時も、絶対にママの側から離れないし、携帯も取り上げていた。
ずっと辛かった。
逃げ出したかった。誰かに話したかった。
でも、言えなかった。当たり前だと思っていたから。
そんな日々が続くこと、半年くらい。
ついに私は行動に起こした。
夜中の1時。
その日もパパは狂気的な笑顔を浮かべながらママのことを殴り続けていた。罵詈雑言を浴びせて人格を否定し、酷い扱いを敷いていた。
私はパパに見つからないようにこっそり部屋を抜け出すと、2人がいるリビング以外の家の窓を全部割って回った。右手には濁った水が入れられて小さいペットボトルを持って、がむしゃらに家を駆け回りながら、「助けて!」と何度も叫び続けた。
パパは焦燥感を駆られたのか、私のことを捕まえて馬乗りになると、血が滲んだ拳でお腹を何度も殴りつけてきた。
ママは……私のことを助けることもできないほど衰弱していて、もう目がほとんど開いてなかった。でも、確かに泣いていた。
当時、まだ幼かった私は碌に抵抗もできず、ただひたすらに殴られ続けた。大人の男性の体格でそんな子供が手を挙げられたら、死ぬのは時間の問題だった。
私は痛みに顔を歪めながら、その間もずっと泣き叫び続けた。
そして、どのくらいの時間が経ったか覚えてないけど、多分5分くらいした時だった。
家の玄関扉が勢いよく開かれると、そこからゾロゾロと警察の人たちが家に入ってきた。
どうやら、私の作戦が成功したみたい。
窓ガラスが割れて、外に悲鳴が響いたことで近所の誰かが通報してくれたらしい。
警察の人たちはパパのことを羽交締めにして連行すると、すぐに救急車を呼んで私とママのことを病院に運んでくれた。
その前後はショックが大きすぎたのかよく覚えてないけど、気がついたら別の街に暮らしていて、パパはいなくなっていた。
幸い、私とママは全身の打撲と一部分の骨折だけで済んで、命に別状はなかった。特にママはパパからかなり手加減されていたみたいで、ちょうど言い訳のつくレベルの怪我や傷しかなかったらしい。
でも、私は小さな子供だったから、全身には殴打された青あざと刃物の切り傷、そして肘の辺りに火傷の痕が残ってしまった。
半袖を着たら肘の辺りの火傷痕が見えてしまうし、ショートパンツを履いたら腿の切り傷が露わになる。
水着なんて絶対に着れない。もってのほかだった。
とにかく、子供の頃はそれが正常なのか、異常なのか、それすらも訳がわからなかったけど、今は高校生になったからよくわかる。
あれは異常だ。
他の子達の肌は綺麗で、好きな服を着て、両親とお出掛けを楽しんでいる。
でも、私にはそれができない。
ママはいるけど、すっかり閉鎖的になっちゃって外へは連れて行ってくれなくなった。
私も同じだけど、ふとした拍子に当時のトラウマが今でも蘇るし、自分という人間を曝け出すのが怖くなっていた。
体と心はうまく連動しているみたいで、体を出したくないからこそ心も公にしたくなくなっていた。
だから、あれから私は自分を隠すようになってしまった。
自分を隠して、懸命に、懸命に……生きている。
「……」
読み終えた私はそっと手帳を閉じた。
まるで小説の中の世界のような、残忍さを思わせる内容だった。
「この後も大変だったんだよね」
私は小学校と中学校の9年間に経験したイジメを思い出す。
その時は閉鎖的で暗かった私は、地毛の明るい金髪を揶揄われ、傷を見せたくないからプールに入れないことを笑われ、汗をかいて暑くても上着を脱げないからバカにされ、事情を話したくない私に教師は詰めより、ママもトラウマから口を開けず俯くばかり……最悪だった。
当時、私が唯一信じられたのは自分の絵の世界だけ。
友達は全くいなかったから、私はずっと絵を描いていた。
今思えば、その時にたくさん絵を描いたおかげでイラストレーターになれたわけだけど……多分、そうなったのは誰かに認められたい欲求が強すぎたからだった。
そして、私は高校生になると同時に変わることにした。
明るい金髪を活かすために性格も明るくして、みんなに好かれるために八方美人になった。北海道の田舎に住んでいたけど、ママと一緒に札幌に越してきて。顔見知りが1人もいない高校を選んだ。
みんなとの人付き合いを完璧にこなして、周囲から認められるように快活な自分を演じ、偽り、ネットの世界でも有名になることで承認欲求を満たしていた。
そんな時、降谷くんに出会った。
隣の席に座る単なるクラスメイト。頭が良くて寡黙。何度か話したことはあったけど、どんな人なのかはよく知らなかった。
彼は恋愛小説を書いていた。
頭が良いから読める範疇ではあったけど、内容はダメダメだった。
でも、評価する私を見て一喜一憂し、普段の無口な姿とは違ってよく話す姿は印象に残った。
降谷くんに興味が湧いた。
デートに誘ってみると案外悪くなかった。不器用なところも彼らしく思えたし、気まずさはあんまりなかった。
勉強だって教えてくれた。暗記任せの横暴なやり方かと思ったけど、自習の時はちゃんと理解に繋がったし、最後は赤点回避を成し遂げて良い結果が出た。
降谷くんにますます興味が湧いた。途中、西園寺先輩のことが嫌いになったりしたけど、そのおかげで彼の優しさに触れることもできた。
初めてだった。誰かを想うなんて。
「……でも、それももう今日で終わりかな」
私はベッドに倒れ込む。
降谷くんの友人である佐山くんがバラしたら何もかもがおしまいだ。
明日からちゃんと学校に行けるかな
もう今日は疲れちゃった。
心身に疲弊を感じた私は、途端に頭痛に苛まれてしまい、気が付けば眠りの世界に堕ちていたのだった。
イラストを描く気力はもうない。
もしも私の噂が広まっていたらと思うと、学校に行くことすら怖くなる。
そして何よりも、私のことを信じてくれていた、みんなに幻滅されたくない。特に……降谷くんにはね。
◇◇◇◇◇
京都府へ修学旅行にやってきた一行は、美しい京都の街並みに圧倒されていた。
古い町並みが続く狭い路地や、石畳の道を歩くと、そこには歴史と伝統が息づく風景が広がっている。
紅葉の季節に近づきつつある中、古い町家や寺院の屋根には静かに色づき始めた葉が見える。街中には観光客や地元の人々が行き交い、古都ならではの賑やかさが漂っていた。
また、伝統的な味わい深い建物や街並みが調和し、京都ならではの風情が溢れている。さらに、静寂な雰囲気漂う庭園やお寺、神社など、歴史と文化が息づく場所も訪れ、修学旅行生たちは京都の魅力に心を奪われていく。
一行はそんな風景を眺めては一喜一憂し、スマホを片手に持ち記憶と記録に刻み込んでいく。
しかし、そんな一行の最後尾を歩くアオトからすれば、修学旅行なんて心底どうでもいいイベントだった。
というのも、3泊4日なのでその間は一度も家に帰れず、遠方の京都府で過ごすことになるからだ。
インドアな彼からすれば憂鬱でしかない。
唯一の救いと言えば、スマホを用いて執筆作業に取り掛かれることくらいだろうが、それでもたった1人見知らぬ土地で過ごすのは苦痛以外の何者でもなかった。
更に言うと、ここ最近はハルカとのLINEでのやり取りが全くなく、以前のような心底つまらない日常に逆戻りしてしまったのも気が乗らない要因の一つだった。
ハルカから返信が来ない理由は定かではなかったが、佐山からあの話を聞いたその時から音沙汰がなくなったのできっと関係しているのだろう。
そのせいで小説の執筆も進まないので、アオトはやることが完全になくなっていた。
それほどまでにアオトにとって小説の執筆というのは、最近では何よりも欠かせない習慣になっていたということだ。
「はぁぁぁ……」
ベンチに座るアオトは、深いため息をついた。
修学旅行の初日は一行で歴史的建造物を観光し、その後の2日目と3日目は完全な自由時間となる。そして、4日目には帰宅の準備が待っているが、それまでは1人で時間を潰さなければならない。
地獄……とまでは言わないが、やはり孤独を極める彼にとっては退屈と言わざるを得なかった。
唯一の友人である佐山はサッカー部の連中と一緒だし、アオトからすれば親しい部類に入るハルカだって仲の良いクラスメイトに囲まれている。
「帰りたい」
アオトがそんな思いに耽って俯いていると、突然隣に誰かが腰を下ろした。
「ん?」
「——アオく……間違えた、降谷くん。1人なの?」
アオトに声をかけてきたのはダークブルーのポニーテールを揺らすカスミだった。
「白銀さん、1人で過ごす俺のことを茶化しにきたのか?」
アオトは少し疑い深い様子で言う。
彼女が転校してきたその日こそ意味不明な会話を交わしたが、それ以降は単なるクラスメイトとして過ごしてきたので、彼からすれば唐突の出来事に驚いていた。
しかし、当のカスミは笑顔で否定する。
「そんなんじゃないよ。ただ、ボクも一人だったから声をかけてみただけ。それにしても……本当にアオくんにそっくりだよ。あっ、ちなみにアオくんっていうのは、明るくて笑顔が綺麗なボクの大好きな男の子のことね?」
「……見ての通り仏頂面で不気味な俺が、そのアオくんに似てるって?」
アオトはカスミの言葉に混乱しながらも、以前泣かせてしまったこともあり、少し戸惑いながらも口を開く。
彼女は彼のことを昔馴染みの”アオくん”の姿と重ねているのか、瞳の奥はキラキラと輝いている。
「うん。笑顔はわからないけど、雰囲気は似てるよ。まあ、降谷くんは一匹狼って感じかな?」
「俺はひとりぼっちなだけだ」
茶化してくるカスミに対してアオトはぶっきらぼうに言葉を返した。
不思議とほぼ初めて話す相手だというのに、彼は彼女との間にどことないシンパシーを感じていた。
「ごめんごめん。アオくんに似てたからついつい……」
「ふーん……そんなに似てるか?」
「うん。そっくりだよ。顔つきとか体格はもちろん昔とは違うけど、ボクはあの頃のアオくんを忘れたりはしないよ。また会いたいんだ。昔、助けてもらった恩を返すためにね!」
「へー」
特に興味のなかったアオトが淡白な返事をするのとほぼ同時。
アオトの友人である佐山の笑い声が遠くから聞こえてきた。
相変わらずゲラゲラとうるさいやつだと思いながらも、佐山の方を一瞥する。
「……相変わらず騒がしいやつだな」
「知り合い?」
「あいつは佐山。俺の数少ない友達だ」
「運動部って感じだね」
「ああ。見ての通り陽気な性格で、俺とは正反対だろ?」
アオトは沈黙を逃れるために何の気なしに友人のことを紹介したのだが、それを聞いたカスミはじっと瞳を細めて佐山に視線を向けていた。
それが何を意味するのか、アオトにはわからない。
「……うーん……降谷くんと佐山くんは友達なんだ。としかして、幼馴染とか?」
「まあ、そうだけど……まさか、佐山も知り合いに似てるとか言い出すんじゃないだろうな?」
素っ頓狂な事を言い出しそうなカスミに対して、アオトは溜め息混じりに聞き返す。
しかし、カスミにとっては彼の言葉が意味深いものだったのか、唐突に目が大きく見開かれ、驚きの表情を浮かべた。
そして、見るからに動揺した様子を見せながら口を開こうとする。
「——かすみん~、そろそろバス移動だってさー」
カスミが何かを言葉にしようとした瞬間だった。
彼女の友達がぱたぱたと駆け寄ってきた。
「う、うんっ、今行くよ! じゃあ、降谷くん……また話そーね! 絶対だよ!」
「……ああ、機会があればな」
カスミが立ち去り、取り残されたアオトの頬には秋の乾いた風が静かに吹きつけた。
彼はまだ彼女が言いかけた言葉の真意を理解できず、心の中には確かな疑問が渦巻いていた。
その時、彼はふと、幼い頃の記憶が蘇り、遠い過去の出来事が頭をよぎったが、その記憶の正体をはっきりと思い出すことができなかった。
「……まさか、な」
アオトは遠くなるカスミの後ろ姿を眺めた。
何の気の迷いか、彼は、あの時の幼馴染の少年を一度は想起したが、やはりルックスも苗字も、ひいては性別すらも違うことからすぐにその可能性は捨て去った。
「白銀、香澄……」
アオトは一人でにカスミの名前を口にした。
すると、今度はいつの間にやら隣に佐山が腰を下ろしており、彼は不思議そうな面持ちでアオトのことを覗き込んでいた。
「アオトぉ~、暗い顔してどうしたんだよ? あ、いつものことか?」
「……佐山か」
アオトは冗談混じりで煽ってくる佐山のことを睨みつける。
「んぁ? その様子だと、あれから星宮さんとは全然話してないみたいだな」
開口一番、佐山はアオトの耳元に顔を近づけて小声で囁いた。
声色はニヤリと笑った顔が浮かぶほど上擦っている。
「……まあ、そうだな。ちょっと避けられてる感じがするんだよ」
「そうかそうか。実は俺も同じなんだよ」
「佐山も?」
少しばかり口角を上げている佐山だったが、アオトからすればナイーブな問題だった。
「多分、俺がこそこそ覗き見してたってことがバレたんだろうなぁ。今思えばあん時に目ぇ合ったような気がするし。今もチラチラこっちを見てるだろ?」
佐山は少し離れた位置で友達と群がるハルカを横目でチラリと見た。
アオトもつられて確認すると、ちょうどハルカがこちらに視線を向けていた目が合った。
ハルカはハッと驚いたように口を開くとすぐに目を逸らした。
「ほんとだな……じゃあ、前の話は本当だったのか?」
アオトは驚愕の表情を露わにした。
少し考えていたことではあるが、今のハルカを見たら佐山の証言の現実味が増してきた。
「マジもマジ、大マジだよ。俺の脳裏には今でも焼き付いてるぜ。人当たりが良くて美人で人気者の星宮さんが弱気に愚痴ってたあの瞬間がな!」
「うーん……いやぁ、でも……やっぱり信じられないな」
アオトは信ぴょう性が高まりながらも、これまでのハルカのことを考えると佐山の証言を信じきれなかった。
ハルカは自分の小説を読んでくれて評価をしてくれたし、2人で映画を見に行ってくれた。その後はカフェで会話を交わしてコンテストへの参加を勧めてくれた。
勉強会を通して2人きりの時間を多く過ごし、協力してテストを乗り越えた。
自分のためにイラストを描いてくれて、一緒に頑張ろうとエールを送ってくれた。
そんな快活な彼女が、途端に元気をなくす姿なんて全く考えられなかった。
「お前の気持ちもよくわかるよ。だがよ、ここ最近よ星宮さんはちょっと様子がおかしいだろ? 皆勤賞だったのに急に学校を休んだり、早退もしてるって話じゃねぇか。友達は相変わらず多いみたいだけど、今も上手く笑えてねぇように見えるぜ」
慰めるような口振りの佐山の言葉には確かな信憑性があった。
隣の席だからアオトはよくわかっているが、確かに最近のハルカは休みがちで、登校してきても昼前には早退していることが多かった。
原因は体調不良だと担任は言っていたが、単なる体調不良ならLINEを返さないはずがないし辻褄が合わない。
ほぼ確実に彼女自身の何かに問題が生じたのだ。
「……確かにな」
「だから、上手く見守ってやれよ」
「……この前とは随分意見が違うじゃないか」
「俺だってよ、きつい練習の後は愚痴を吐くし、見知った人が亡くなったりしたら辛くなるんだよ。きっと星宮さんが弱気になって体調を崩してるってのもそれと一緒じゃねぇかなって思うんだよな」
佐山にしては珍しく論理的な思考回路で会話を広げた。
「まあ……概ね同感だ。星宮はきっと俺たちの見当もつかないような”何か”を抱えてるんだろうけどな」
「だな。ところでよぉ、さっき白銀さんとは何を話してたんだ?」
「……あー、それについても実は1つ聞きたい事があるんだ。佐山は、子供の頃の出来事って覚えてるか?」
アオトは鋭い佐山の言及をひらりと交わすと、話題を転換させて彼に尋ねた。
「子供の頃っていつのことだ?」
「俺とお前と金ちゃんの3人で遊んでた頃だよ」
「あーあー! 金ちゃんか。最後まで下の名前は知らなかったけど、苗字が金城だからそう呼んでたよな。随分と懐かしい話だな」
佐山は腕を組み何度も頷いた。
アオトと同じく、彼も件の”もう一人の存在”についてよく覚えているようだ。
「例えばの話だけど、最近俺のクラスに転校してきた女子生徒が、その金ちゃんって可能性はないよな?」
「ないない。ありえねぇよ。転校生の女子生徒って、白銀さんだろ。金ちゃんは短髪でイケイケ系の男気溢れるタイプだったろ? 正反対すぎてありえねぇよ」
アオトは恐る恐る尋ねたが、佐山は間髪入れずに真っ向から否定した。
やはり、あの小動物のようなカスミが金ちゃんと同じには到底見えないらしい。
かくいうアオトもそれは同感だった。
「悪い、変なこと聞いた」
「いいってことよ。それにしても、いきなり金ちゃんのことを思い出すなんて何があったんだよ。あいつは急に引っ越しちまってそれっきりだろ。当時はLINEなんて便利なもんはなかったし……もうお互いに成長したから会ってもわかんねぇと思うぜ? しかも、ありゃあ俺たちが5歳くらいの時の話だしな」
佐山の言うことはもっともだった。今や互いに見た目も性格も変わりすぎている。
幼い頃のアオトは、明るい性格だった。
昔から陽気な性格のままでいる佐山ならまだしも、今のアオトは真逆の暗い性格に変わり果てている。
更に顔つきも体つきも大人っぽくなり、多少なりとも子供の頃の面影があろうと、10数年越しに会った人が見てわかるはずがなかった。
「だよなぁ……さすがに会ってもわからないだろうな」
「やっぱ会ってみてぇのは確かだけどな!」
アオトの返事を受けた佐山は懐かしそうに微笑んで続ける。
「そうだな」
「懐かしいなぁ、マジで……」
感傷に浸りつくす佐山。
同様にアオトも徐々に昔の記憶を思い出し、懐かしい記憶に入り浸る。
「突然いなくなった前の日、泣いてたもんな。それだけ俺たちと離れ離れになりたくなかったってことなのかな?」
あの時の金ちゃんの顔は忘れない。
まるで絵本の世界の女の子のように、大粒の涙を流して泣き続けていた。
普段は勇ましく凛々しく、男らしかった金ちゃんが、あの時だけは泥だらけの手で俺の服の裾を握っていた。甘えん坊な妹ができたような感覚だったのをよく覚えている。
「かもな。んでよ、今話していて気づいたんだけどよ。多分、金ちゃんがいなくなった原因ってあれじゃねぇの?」
「あれってなんだよ」
「あれだよあれ。金ちゃんの体には生々しい青あざとか妙な怪我とか傷がたくさんあったろ? んで、それを不思議に思ったお前が、近くの交番に駆け込んだんだよ。覚えてないか?」
「覚えてる……あー、そういうことか」
アオトはふと思い出した。
そして、一つしか考えられない結論に辿り着く。
「そうそう。金ちゃんは強気な性格でいつも笑顔だったから、正直、俺は全く変化に気付かなかったけど……ありゃあ十中八九、DVを受けてたんだろうな」
佐山は腕を組み何度か頷き、渋い顔つきになっている。
「俺もそう思う。いち早く気付けて本当によかったよ」
「というか、アオトはなんで気付けたんだ? 時期的にもあん時は秋口で、金ちゃんはずっと肌を隠すような服ばかり着てただろ?」
「んーーー……金ちゃんとは、たまたま公園で出会ってから遊ぶようになって、結局は半年くらいしか一緒に過ごしてなかったわけだけど、日に日に笑顔が崩れていってたんだ。特に、夕方になって帰る頃には泣きそうな顔になってるのを見たことがある。きっと家に帰りたくなかったんだろうな。それを見てちょっとだけ不思議だなぁって当時の俺は考えたんだと思う」
「それにしても、よく気付けたな」
「まあ……他にも、鬼ごっこの時に服を引っ張ったら、偶然右腕の袖が捲れて傷が見えたりもしたし、そん時は佐山も一緒だったろ」
アオトにとっては、些細とまでは言わないがそれほど印象深い出来事ではなかったが、金ちゃんの腕や首元に青あざがあることに気が付き、何の気なしに交番へ向かった事は記憶に残っていた。
まさかそれがDVだったとは、当時の彼にはわからなかったが。
「あぁぁーーーーーー、あれか? 右腕の肘辺りにあった火傷痕だろ。結構、痛々しかったし、あの感じだと一生消えねぇだろうなぁ」
佐山は顎に手を当て口を開く。傷についてもよく覚えているのか、その位置と具合まではっきりと口にしていた。
対するアオトは、佐山ほど鮮明には覚えていなかったが、彼の言葉を聞くことでふと頭の中に疑念がよぎる。
「……右腕の肘辺りにあった火傷痕……? ん? 待てよ……最近、どこかで見た気がするな」
過去を懐かしむ佐山とは対照的に、アオトはつい最近の記憶の中でそれと近いと思しき痕跡を探した。
この短い時間では考えても何も閃かなかったが、確かにどこかで見た記憶があった。
「まあ、とにかくだ。金ちゃんは、あんな小動物みたいなか弱い女の子なわけねぇよ。な?」
「そうだな」
「おう。んじゃ、時間だから行くぜ。修学旅行、楽しめよ?」
佐山はそんなアオトの思考などつゆ知らず、遠方に見えるカスミに指を差すと、それだけ言い残して立ち去った。
どうやら既にこの場での自由時間が終わりバスや出発時刻らしい。
思いのほか、アオトは佐山と長話をしていたのか、周りに他の生徒の姿は見当たらなかった。
「……俺も行くか」
アオトは重い腰を上げてベンチから立ち上がると、のそのそとした足取りでバスへ向かう。
この後は旅館へ向かってから夕食を摂り、各々が入浴を済ませたら、就寝までの間は自由時間となる。
当然ながら夜も特に予定なんてなかったのだが、バスの座席に着いた時にLINEを開くと、数週間ぶりに件の相手からメッセージが届いていることに気がついた。
『降谷くん。今夜の8時、旅館の裏手でお話ししない? 待ってるね』
◇◇◇◇
星宮晴香は気分がすぐれなかった。
せっかくの修学旅行だというのに、数週間前から虫の居所が悪い。
彼女がそうなる要因は2つあった。
まずは1つ目。アオトと遊びに行けていないせいで、イラストが描けずに承認欲求を満たせていないこと。
そして2つ目。これは一つ目と大きく関係しており、佐山に自身の裏の顔を見られてしまったこと。
まとめると、全ては佐山という男子生徒のせいだった。
彼女はあまり彼のことを認知していないが、陽気で明るい性格でアオトの唯一の友人であることくらいは知っていた。
だからこそ、不安だった。
——佐山くんにあのことをバラされたら、降谷くんとの関係が途絶えてしまう。そうしたら、イラストを描くこともできなくなるし、誰かに認められて承認欲求を満たせなくなる。それだけは避けないと……!
今もハルカの視線の先には、ニヤニヤ笑う佐山と、そのすぐ側でボケェっとしているアオトの姿があった。
2人とも心を許し合っているのか、かなりリラックスしている。
少なくとも、ハルカの前でアオトはあんな顔を見せたことはなかった。
「……佐山くん、余計なことは言わないでよね……」
ハルカは佐山の様子をちらちらと確認する。
何となくでしかないが、佐山とアオトの表情を見る限り、自分に関する話をしているというのがわかった。
それもこれも、あの日の放課後のアレを佐山に見られたせいだ……ハルカは力強く歯を食いしばる。
普段は家の自室で不満や愚痴を吐き出すのだが、あの日は家の鍵を忘れてしまったので教室に残るしかなかった。
だから、ああやって1人きりの教室で叫んでいたのだが、まさか佐山に見られるだなんて彼女の予想外だった。
1つ良いことがあったとすれば、何の気の迷いか佐山が件の話をおかしな噂に昇華させて流布していないことくらいだろうか。
「はぁぁ……」
「ねぇねぇ、晴香、みんなで西園寺先輩にお土産買っていくかどうか悩んでるんだけど……」
ハルカが溜め息を吐くと、女友達が声をかけてきた。
「西園寺先輩か~、あの人なら変わり種の方が喜んでくれると思うよっ! 独特な感性持ってそうだし!」
ハルカはなんて事のない女子同士のやり取りにも対応しつつ、尚もその視線は佐山へと向けていた。
彼女からすれば変態男の西園寺なんて心底どうでもよかった。唯一、明確に嫌悪感を持つ相手でもあったからだ。
「ってかさぁ、さっきからずぅーっとどこ見てんの? あ、まさか佐山くん? チャラい見た目だけど確かにイケメンだよねぇ。でも意外かも、晴香ってどちらかというともっとクールな感じが好きでしょ?」
「え!? ち、違うよ! 違うからね!? 私、ほんっとにああいう感じはタイプじゃないから!」
女友達の煽りを間に受けたハルカは、あからさまに取り乱して否定したが、外向けの言葉遣いや態度を崩すわけにはいかず曖昧な反応になってしまった。
「怪しい取り乱し方だねぇ。じゃあ何、佐山くんと話してる冴えない降谷くんがいいの? まあ、彼も顔だけなら中の上って感じだけど、何せ暗いからなぁ~、1度も喋ってるとこ見たことないかも」
「……んー、佐山くんと降谷くんなら、断然降谷くんの方がいいかな」
ハルカは真面目な落ち着いたトーンで答える。
彼女にとっては愚問だった。考えるまでもなくアオトことを選択する。
それを聞いた周囲の女友達は驚いて固まっている。
表情からして、どうやら冗談のつもりでアオトのことを薦めていたようだ。
「へー……じゃあ、ますます晴香の好みがわからなくなるね。イケメンでも西園寺先輩はダメだったみたいだし、同い年の佐山くんもダメ。でも、根暗で静かな降谷くんならOKなんだ?」
「……OKってことは絶対にないただ、降谷くんは、悪い人ではないからね」
「席も隣だしたまに話してるもんね。テスト期間なんて図書室で二人で勉強してるなんて噂もあったし……ずっと気になってたんだけど、2人はぶっちゃけそういう関係ってこと?」
1人の女子がおずおずと口にすると、周囲の皆がキャーキャーと騒ぎ出して辺りには喧しい黄色い声が飛び交うことになる。
それほどまでに皆がハルカの恋愛事情について興味があるということだろう。
「確かに、降谷くんの下の名前ってアオトだし、ハルカと合わせたら、アオトとハルカでアオハルだよね! なんか運命って感じ!」
続け様に別の女子が満面の笑みを浮かべて言葉を続ける。
「でもでも、降谷くんと晴香じゃ全ッ然釣り合わないってー! あんなぶっきらぼうで冷たそうな人と付き合ったら、優しくて温厚な晴香が毒されちゃうよー」
「それもそうだねー。降谷くんってクールってよりはドライな感じで、何にも興味とかなさそうだし、デートとかしても気遣いできなさそうだもんね。ね、晴香?」
数名の女子はアオトが遠くにいるのをいいことに、思い思いの負の感情を言葉にした。
本人が聞いたら傷つくのは明白だったが、彼女たちは他者を虐げることでハルカの評価をより上の水準に持って行こうとしていた。
みんなが一様にニヤニヤと悪どい笑みを浮かべ、ハルカの返答を待っている。
しかし、当のハルカはそれが冗談だとわかっていようと、感情の昂りを抑えられなくなっていた。
彼女は誰にも聞こえないように小さく舌打ちをして口を開く。
「……ごめん。みんなさ、降谷くんの何を知ってるの?」
「え?」
ハルカが普段は表で見せない本気のトーンで言葉を紡ぐと、一同は素っ頓狂な顔つきになり固まった。
そんな彼女らの様子など気にすることなく、ハルカは一つ息を吐くと、
「降谷くんは優しいよ。少なくとも、他のどの男子よりもね。気遣いもできるよ。勉強も教えてくれたよ。誰かのためにそういうことができるのって優しいってことじゃないの? 違うかな?」
続け様に言い放つ。
最後に同意を求めたが、この場にいる女子全員が押し黙る。
数秒の沈黙。
その後、あまりの異様な空気に耐えかねた1人が空笑いを浮かべる。
「あ、あははは~! ご、ごめん! みんなほんの冗談のつもりだったんだけど……晴香、なんでそんなマジになってんの? ちょっと怖いって……ねぇ?」
普段は温厚で尚且つ人当たりが良く、声色も言葉も態度も柔らかなハルカの変わり様に対して、先ほどまで冗談めかしていた彼女たちは萎縮していた。
頬をひくつかせて、ギョッとした目つきでハルカのことを横目で見ている。
それとほぼ同時に、ハルカは表面上のいつもの自分を制御できなくなってることに気がつくと、すぐさま表情を取り繕って言葉を紡ぎ始める。
「やだなぁ! こっちも冗談だよ! そういうノリかと思ったんだけど違ったかな~?」
「な、なーんだ……それならよかった。晴香があんな怖い顔してるの初めて見たからびっくりしちゃったよ……ね?」
「う、うん」
「空気読めなくてごめんね! まあ、降谷くんとそういう関係じゃないのは本当だよ! 悪い人じゃないのも間違ってないしね! 彼は本当に優しいよ!」
皆がほっと胸を撫で下ろす様を見てハルカも安心すると、いつもの口調と形相で声色を高くして空気を一変させた。
そんな彼女が吐いた言葉に嘘はなかったが、真実でもなかった。
「……確かに、思い返してみると、降谷くんって嫌な顔せずペンを拾ってくれたり、黒板の板書を消す時もしれっと手伝ってくれたりするよね。本人は全くこっちに興味なさそうだけどね」
「そうそう! 降谷くんって意外にそういうとこあるかも! となると……やっぱり悪くないんじゃない? めちゃくちゃ無口な部分を除けばね。だよね、晴香?」
「うん。そうだね……」
晴香は同意を示しつつも、胸中では目の前の彼女らに呆れきっていた。
——私が一回顔色を変えたらすぐこうなるなんて、やっぱり誰も彼もが他人の本当の内面に興味がないのかな。
きっとそれは私が相手でも同じ。きっと、私がさっきみたいな態度を続けていたら、みんなはあっという間に離れていく。
だから、私は本当のことも言えず、ああやって冗談めかした答えを言って誤魔化すしかできない。
くだらないよね。他人をバカにして、上辺の付き合いだけで満足するなんて……。
でも、それは私も一緒か。もう更新はやめちゃったけど、ついこの前までネットに降谷くんを題材にしたイラストを投稿してたわけだし……あれも結局は無断で利用してバカにしてるってことだもんね。
ハルカは真実の思いは口にせず、そっと心の中にしまいこんだが、溢れ出てくる言葉は止まるところを知らなかった。
少しだけ1人になりたい。そう思っていた。
「ごめん、今日の夜は少し部屋を空けてもいい?」
ハルカは照れ臭そうな様子を演出して周囲に視線を送る。
柔らかな言葉と視線を用いることであえて自分に注目が集まるように仕向けた。
「いいけど……みんなで人生ゲームやる予定だよ?」
「私はちょっとだけ用事があるからごめんね? また明日時間作るからさ」
「用事……もしかして、告白とか?」
案の定、女友達の一人が勘違いしてくれたので、ハルカはここぞとばかりに言葉を紡ぐ。
「んー、恋愛の告白とかじゃないけど、今夜はそっとしてくれると助かるかな~」
「おーおー、凄いじゃん! 相手は誰なのか、結果はどうなったのか、その辺りはまた今度絶対に聞かせてよね!」
「うん。わかったよ。じゃあ、ちょっとお手洗いに行ってくるね」
思わせぶりな言葉だけを残したハルカは絶好のタイミングで集団を抜け出し、足早にトイレへと逃げ込んだ。
これは質問攻めから逃れて、尚且つ相手を勘違いさせる彼女の作戦だった。
「……はぁぁぁ……なんでイラストはバズってたのに、前みたいに満たされなくなったんだろ」
トイレの個室に逃げ込んだハルカは、首を垂らして頭を抱えた。
彼女は最近はもうイラストの投稿を辞めていた。
佐山に自分の本当の姿を覗き見されて以来、描いても描いても虚しくなるばかりで、何一つとして心が満たされなくなっていたからだ。
ハルカはその原因はわかっていた。
アオトだ。アオトに嫌われてしまうのが怖くなっていた。
好き……という気持ちはまだわからなかったが、もしも自分の本性がアオトにばれたらと思うと、何も手がつかなくなってしまったのだ。
学校も休みがちになり、登校しても早退を繰り返し、アオトから心配のLINEが来てもまともに返せない。
ハルカの精神は確実にすり減っていた。
彼女は過去の自分に起きたトラウマから逃げられず、傷ついた肉体を隠すのと同じくその心も閉ざしたままだ。
だから考えた。
「……降谷くんは、優しいよね。私の傷を癒してくれるかな」
ハルカは未読が溜まりに溜まったアオトとのメッセージ画面を開くと、数週間振りにアクションを起こした。
アオトが自分の誘いを蔑ろにするわけがない……と、ハルカは信じていたのだ。
◇◇◇◇◇
退屈な修学旅行の初夜。
時刻は午後8時を回ったところ。
「いた……」
旅館の裏手を歩くアオトは、前方に見覚えのある人影を発見した。
金色の髪のボブカット。部屋着である浴衣をきっちりと身に纏い、大木の下に置かれたベンチに腰を下ろしている。
何を隠そう、彼女は星宮晴香その人だった。
昼過ぎに佐山と別れてからすぐにLINEが飛んできて、彼は彼女からこんな時間に2人で会いたいと言われていた。
諸々の真意を知るためにも、こうしてのこのことやってきたアオトだったが、やはり妙な緊迫感と疑念に胸を支配されてこれ以上は足が進まなかった。
アオトは声をかけるために距離を詰めようとしたが、同時に佐山と交わした会話の内容を思い出して迷いが生じた。
彼女が俺に付き合ってくれていたのは何らかの打算があってのことだったら?
俺のことなんて眼中になくて、酷い言葉を浴びせてこられたら?
アオトの心の中では様々な疑念と、えも言えぬ不安がよぎる。
故に、彼は友人である佐山を頼ることにした。
右手に持つスマホは佐山との通話が繋がれており、暗転した画面の向こうでは彼がこちらのやり取りを聞けるようになっている。
彼はハルカに内緒でこんな盗聴みたいなことをするのは悪いと思ったが、どこか疑心暗鬼になっている今の心境ではそうせざるを得なかった。
「行くぞ」
アオトは小さな声で呟き覚悟を決めて前方に目をやると、ハルカの元へと歩みを進める。
彼女は大木の麓に置かれたベンチに腰を下ろしており、にひるな笑み浮かべて彼のことをじっと見つめている。
「降谷くん。きてくれたんだ。座ってよ」
ハルカはいつものような人当たりの良い雰囲気をその身に纏っていたが、どことなく異様さを醸し出しており、不自然さを思わせる固い表情だった。
「……」
アオトは一瞬ドギマギしかけたが、すぐに平静を取り繕ってハルカの隣に座る。
2人の間には、人ひとり分のスペースが空いている。
「降谷くん」
そよ風が木々とハルカの髪を僅かに揺らす。
風は少しばかり肌寒いからか、彼女は身を縮こまらせていた。
「……」
アオトはハルカを横目で見る。
右手には画面を下にした状態でスマホを持つ。
「……こんな場所に呼び出しちゃってごめんね」
「別に。俺の方こそ待たせたみたいで悪かったな。寒かったろ?」
「ううん。大丈夫だよ。中には長袖のTシャツを着てるしね」
からっと笑うハルカだったが、あまり実直な笑顔ではなさそうだった。
やはり、様子がおかしい。アオトは彼女の違和感にすぐに気が付くが、まずは話を聞いてみることにした。
「そうか。それで……俺に話があるのか?」
「……うん。実は降谷くんに私の本当の姿を知ってほしかったんだ」
「本当の姿?」
「そう。きっと、佐山くんから色々と聞いたと思うんだけど……私はみんなが思うような人間じゃないんだよ」
ぼつぽつと語り始めたハルカの眼差しは虚空を見つめていた。
「……」
アオトは僅かに首を垂らして話に聞き入ると、おもむろにスマホに指をかけて佐山との通話を切電した。
彼は真面目に話そうとしている彼女を見て、自分が盗聴まがいのことをしている事実を許せなくなっていたのだ。
そんなアオトの心中とは関係なく、ハルカは尚も言葉を続ける。
「私はね、臆病なんだ。みんなに嫌われちゃうのが怖いんだ。だから、必死に自分を隠して生きているんだ。佐山くんから変な話を聞かなかった? 私が放課後の教室で変なことを言ってたとか、1人で愚痴を吐いてたとか……どう?」
ハルカは寂しげな表情を俯かせると、涙ながらに言葉を紡いでいた。
「……聞いた。でも、そこで星宮が何をしていたのかまでは知らないし、佐山も周りに言いふらしてないみたいだぞ」
「でも、いつ言いふらすかわからないよね」
「佐山はそんなことしないと思う。少なくとも、噂を脚色して喧伝するような悪いやつじゃない」
事情は知らなくとも、ハルカが不安に思う気持ちはアオトにもわかった。そして、佐山がそんなやつではないことは誰よりもわかっていた。
「そう……」
「星宮は何をそんなに思い詰めているんだ? 学校にも来ないで、LINEも返してくれないなんて……急にどうしたんだよ」
アオトはおもむろに尋ねる。
様子のおかしいハルカを放っておけなかった。
「降谷くん、きみがそこまで知りたいなら教えてあげる。がっかりしないでね?」
「……ああ」
「私はね、きみが思うような、きみが小説の中で書いているような、理想的な女の子じゃないんだよ。みんなは私のことを性格が良くて、肌が綺麗で、この金髪が可愛いって言ってくれてるけど、実際は全然違う。性格は人から良く見られたくて取り繕ってるだけだし、肌なんて酷いもんだよ……金髪は地毛だし、そのせいで虐められたこともある」
ハルカは悲観的な面持ちで自分自身を卑下した。
それは澱みのない口振りだった。
「……聞いてもいいのかわからないけど、どうして自分を偽ってるんだ? あるがままで接すればいいだろ?」
アオトは語りかけるように尋ねる。
しかし、ハルカはそんな彼の言葉があまり気に入らなかったのか、僅かに眉を顰めていた。
「それができないから困ってるんだよ。私はみんなの前で本当の自分を曝け出せない。声も表情も性格も全部嘘まみれなんだよ。本当は明るく振る舞い続けるのは苦しいし、女の子らしい声も、みんなに向ける笑顔も頑張って作ってるんだよ。だって、そうしないとみんなが離れていくから……みんなが好きなのは、偽物の星宮晴香なんだよ」
「……でも、いつかは自分を曝け出さないとずっと状況は変わらないんじゃないか?」
「じゃあ逆に聞くけど、今の私と話していて楽しい?」
「え?」
唐突な問いかけに対してアオトは惚けたような声を上げる。
「楽しくないでしょ。面白い冗談なんて言わないし、テンポよく会話に参加したりもしないんだよ。降谷くん、本当の私は今の私だよ。テンションが低くて、ノリが悪い人をみんなは楽しいって感じると思う?」
ハルカは落胆したかのように肩を落とした。
膝の上では強く拳を握りこんでおり、やるせない様子が伺える。
だが、アオトからすれば、ハルカと過ごしたこれまでの時間はもちろんのこと、今を過ごすこの時間だって楽しく思えていた。
「……何言ってんだ、お前。バカなのか?」
「は?」
「まだまだ付き合いは短いけど、お前と過ごしてきたこれまでの時間も、今のお前と過ごすこの時間も……俺にとってはどっちも特別だ。俺に付き合ってくれるお前は天使のように見えたよ。それがいくら偽善だったとしてもな」
ハルカが素っ頓狂な顔つきになっていたが、アオトは気にせず思いの丈をぶつけた。
佐山が疑ったように、たとえ彼女に何らかの裏や大きな隠し事があったとしても、アオトはそれを上回るほどの密かな想いを胸に秘めていた。
「……うそ」
「嘘じゃない。佐山以外と碌に話せなかった俺が、こんなに口数多く話すことなんて珍しいんだからな? それに、お前は俺の小説を笑わないで読んでくれたしな。あの時は本当に嬉しかったんだ」
アオトは自分の高校生活が色付く瞬間を肌身で感じていた。
過ごした時間は短いが、それは顕著で、孤独を苦にしない彼がハルカと過ごす時間に喜びを覚えていたのだ。
「降谷くん……」
「だから……んー、あー、なんて言えばいいのかな……とにかく、俺に対してはありのままの星宮でいてくれていいってことだ」
「ふふっ、相変わらず口下手だね~」
言葉に詰まったアオトのことを茶化す。
先ほどとは一転してどこか楽しそうだ。
「ご愛嬌ってやつだ」
「それに、やっぱり優しいね。小説を読んでイラストを描いてあげただけなのに、私のことをここまで信頼してくれるなんて、将来は詐欺に引っかっちゃうよ?」
ハルカはごく自然な笑みを浮かべる。
「まあ、そん時はそん時だよ。それより……やっと普通に笑ったな」
「あ……」
「何で隠すんだよ」
ハルカが気恥ずかしそうに両手で顔を隠したので、アオトは冗談めかした口調で彼女の顔を覗き込む。
すると、彼女はぷんすか怒っているのか、赤面した頬を膨らませて彼のことを睨みつけた。
たわいもないやりとりだったが、ここ数週間はこんなやり取りすらなかったので、彼は確かな幸福を感じていた。
何よりも、アオトは目の前で怒っているハルカの姿が全く怖くなくて、むしろ可愛らしく思えているくらいだった。
「もう……」
「悪い悪い。それより、俺からも1つだけ聞きたいことがあったんだ」
アオトは軽く謝辞を挟んでから姿勢を直すと、少し視線を下に向けた。
「なにかな?」
「答えたくないなら構わないが……星宮の右腕の傷について教えてほしい」
「えっ……ど、どうして……どうして、それを知ってるの……?」
アオトの問いに対し、ハルカは血の気が引いたような表情になる。途端に取り乱しており、疑問を問いかける言葉には色が失い。
「……実は映画館で上着を脱いだ時に少し見えたんだ」
アオトはハルカがここまで動揺するとは思っていなかったので、内心は彼女の変わり様に驚いていた。
「汚いもの……見せちゃったね。ごめんなさい」
「いや、そういう意味で言ったわけじゃない。俺は気になったことがあるだけだ」
「……なに?」
ハルカは見るからに気分が優れない面持ちになり、呼吸も少しばかり荒くなっていた。
自分の身を両腕で力強く抱きしめており、明らかに何かを恐れている様子がわかる。
——今は聞かないほうがいいかもな。星宮の過去に何があったのかは気になるが……おそらく、安易に深掘りしていい記憶ではないだろうな。
アオトはそんなハルカの様子を見て心持ちを変えると、ゆっくりとベンチから立ち上がり彼女に背を向けた
「いや、やっぱりなんでもない。それより、そろそろ旅館に戻ろうか。風邪を引いたら修学旅行が台無しだからな」
「そ、そうだね。でも、私はもう少し夜風を浴びてから戻るから、降谷くんは先に戻ってて?」
「……わかった。またな」
「うん、またね」
アオトはハルカに手を振り別れを告げると、静かな足取りで旅館へと戻る。
道中、茂みの中に隠れてこそこそついてきた佐山を発見したが、彼は突然電話が切れたことを心配して遠くの木陰から見守ってくれていたらしい。
アオトは佐山には深い事情は伝えず、問題はなかったとだけ言い残し、部屋へ戻り眠りについたのだった。