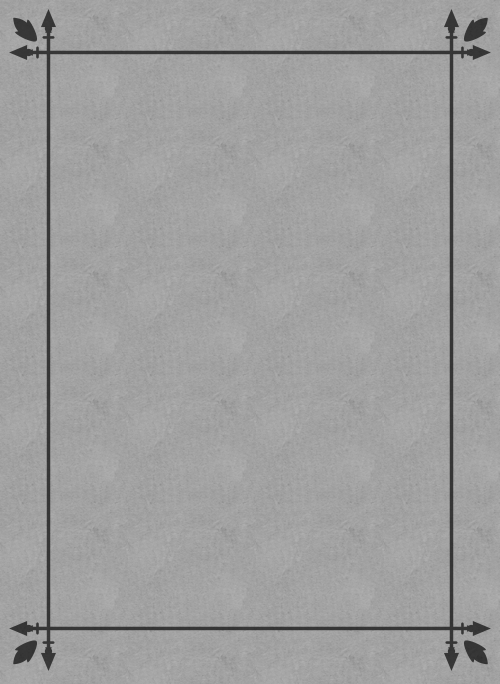「つまらない」
降谷碧都は退屈だった。
交友関係は狭く、恋人もいない。というより、恋愛経験はゼロだ。
そして、性格も暗く目立つタイプでもない。運動神経は並々で際立った能力もない。
特技も……これといって、ない。
強いて挙げるとすれば勉強が得意だったが、通っているのは、ごく普通の公立高校だった。
何かがしたかった。
何かを見つけたかった。
自分が全力で向き合える何かがほしかった。
だが、そう簡単に見つかるものではない。
一度没頭したり、気になったり、興味が湧けばとことん追求したがるアオトだったが、今日も彼は、ひと気がなく閑散とした高校の図書室にいた。
時刻は、まるで時の流れに取り残されたかのような静寂が漂う土曜日の昼下がり。
休日だというのに、アオトは独り勉強に没頭していた。
ただひたすらに問題集とノートを交互に見やってはその手を動かし、集中を途切らせることなく、その心は知識の海に浸かっていく。
電源の切られたスマホはリュックの奥底で眠り、代わりに机の上にはこだわりの配置で教科書や参考書、ノートや筆記用具を並べられている。
そんな真面目がちな彼は独りで机に向かって座り込み、汗ばむ全身に嫌気を感じながらも勉強に集中していた。
夏が終わりかけているというのに、北海道の気温はまだまだ下がる気配を見せない。
そんな図書室で聞こえるのは、紙を捲る心地良い音色と鳥の囀りだけ。
「疲れた」
しばらくすると、アオトは教科書とノートを閉じて机の上に体を預けて息を吐いた。
少し長めの黒髪が重力に従ってさらりと揺れると、その隙間からはやや切長な瞳をのぞかせる。
昼過ぎに図書室へ来てからもう3時間が経過していた。土曜日だから人が少ないのは最高だが、やはり何時間も勉強を続けるのは中々に大変だとアオトは思う。
先月の末に夏の休暇が終わり、皆が思い出の余韻に浸る中、彼だけは変わらず孤独な学び舎で日々を過ごしていた。
「……本でも読むか」
アオトは机を離れ、疲れた体を伸ばしながら流行りの小説が置かれているコーナーに向かった。
気分転換だ。
そこには、一度は見たことがある有名な小説が幾つも並んでいた。
中でもアオトの目を引いたのは、少し前にテレビドラマ化された恋愛小説だった。
ここだけの話、彼は自分の恋愛経験の無さに辟易している部分があった。それは別に恋人が欲しいというわけではないし、そこに劣等感を抱いているわけでもない。
むしろつまらない自分には彼女を作るだなんて夢のまた夢だと思っていた。
青春なんてクソ喰らえ……とまではいかないが、アオトからすれば青春を満喫する行為など宝くじで一等を当てるくらい難易度の高いものだった。
だが、一応、自分は思春期真っ只中の高校2年生だという自覚をしていたし、もちろん恋愛に対する興味を持っていた。
そう、高校生活という名の短い青春を満喫する周囲との温度差を感じていたのだ。
「……これにしよう」
アオトは周囲に誰もいないことを確認してから件の恋愛小説を手に取り、席に戻ってページをめくり始めた。
文字から漂う恋の甘さと物語の展開、初々しい主人公とヒロインの心情、そしてもどかしい熱を帯びた雰囲気が、彼の心を一時的に現実から離れさせることに成功した。
◇◇◇
「……あ……もうこんな時間か」
アオトは没頭していた小説のエピローグを読み終えたところで、ようやくその世界から抜け出した。
しかし、おもむろに時計を見ると驚いた。
まるで時間が飛んでしまったかのようだった。
初めての経験だな……アオトは心の中に口にする。
同時に、聞き慣れたチャイムの音が彼を現実に引き戻し、18時になっていることに気が付いた。
図書室は静寂に包まれたまま、夕暮れの光が窓から差し込んでいて幻想的だったが、図書室の当番を任されている男子生徒は気怠そうな様子でアオトを見つめている。
——どうやら退室しろってことらしいな。他に人はいないし、俺がいるせいで帰れなかったんだろう。申し訳ない。
アオトは心で侘びながら読み終えた1冊を丁寧に棚へ戻すと、リュックを背負って図書室を後にして帰路に就く。
そして、先ほどまで没頭していた本の内容を思い返す。
ストーリーは至ってシンプルだった。
主人公である大学生の青年と、余命宣告を受けた高校生のヒロインが、残された僅かな時間を共に過ごすというもの。
そこで出会うたくさんの人々との交友やまだ見ぬ世界の探究は2人の幸せを増幅させていく。
しかし、不治の病は楽しい時間を過ごしていくごとにヒロインの体を蝕んでいき、やがて最後は悲しみに暮れながら死を迎えて感動のラストに繋がるという話だ。
「……」
無言で帰路に就くアオトは、シンプルながらきちんとした起承転結のあるストーリーを思い出して心を震わせた。
先にも述べた通り、彼には恋愛経験がない。
故に、これまでの人生で触れてこなかった恋愛を題材にした小説を読むことで、彼の恋愛というジャンルに対する意識は大きく変容したのだ。
更に、彼の胸のうちには恋愛観の変容以外の別の感情が芽生えていた。
「……本って凄いな」
空を眺めて呟く。
アオトは恋愛小説がもたらす凝縮されたストーリーとその儚さに魅了されていた。
時に、連ねられた活字の間に差し込まれる美しいイラストも、その完成された物語の味を数段上へと引き上げていた。
かつて、たかが活字とイラストだけで構成された話の何が面白いんだと思っていた自分のことを殴ってやりたくなっていた。
それくらい彼は恋愛小説に魅了されていたのだ。
そして、自分もそんな人の心を揺さぶれるような恋愛小説を書いてみたいと強く思っていた。
感情表現の乏しくないアオトの胸が初めて高鳴った瞬間だった。
やるべきこと、やりたいこと、やってみたいこと……彼の心にはそれらが確かに芽生えていた。
「モノは試しだな」
それから足早に帰宅したアオトは自室でノートパソコンを開くと、思いのままに自分なりの恋愛小説を書いてみることにした。
今日は土曜日なので、当然ながら明日は日曜日。
彼には何も予定がないので時間はたくさんある。
アオトは燃えるような情熱で小説を書き進めた。
勉強する合間を縫って、彼は物語のキャラクターやプロットを素早く練り上げていった。孤独な図書室での経験や、小説の中で感じた恋の甘さや切なさが、彼の思考と筆を力強く進めさせた。
夜遅くまで机に向かい、夢中で執筆に没頭し、頭を悩ませながらもオリジナルのストーリーを練り上げていった。
そして、日曜日の深夜、彼の小説はついに完成した。
慣れない執筆作業は中々進まなかったが、それは彼自身の成長や感情を込めた作品であり、新たな一歩を踏み出す勇気と希望が詰まった物語だった。
◇◇◇
その日も、アオトは窓際の最後席に座り、教室の雰囲気の外にいた。
周りではクラスメイトが夏休みの思い出を語り合い、笑い声が響いている中、彼は一人静かに自らが手がけた作品を読み返していた。ノートパソコンからテキストデータをスマホに入れたので、周りからバレることなくこそこそと読み進めている。
心の中では、誰かに自分の小説を読んでほしいという思いが渦巻いていたが、読んでもらえるような交友関係を持っていないが故に諦めていた。
唯一の友人に読んでもらうという手もあったが、その友人は恋愛小説を読むタイプまでもないので遠慮していた。
しかし、アオトにとって短時間で書き上げたこのオリジナルの恋愛小説は、1つの宝物であり、誰かに共有したいという欲求は強かった。
アオトは辺りを見回した。
わがままなお願いかもしれないが、日頃から本を読んでいて温厚そうな人が良いと彼は考えていた。
「……」
無言で教室内に視線を這わせるアオトだったが、そう都合良く見つかるはずがなかった。
そもそも交友関係が極端に狭い彼は、進んで話しかけることすら憚られるくらいだった。
諦めかけたアオトだったが、ふとした拍子に隣の席に座る星宮晴香——ハルカを視界に捉えた。
彼女は一人でスマホをいじって柔和な笑みを浮かべていた。
「……」
彼女はダメだな。めちゃくちゃギャルだし、きっと俺の小説を見せたら気持ち悪がられるのが目に見える……そう考えたアオトは、すぐさまハルカのことを対象から除外した。
ハルカは明るく、好奇心旺盛な性格で知られており、とっつきやすくてアオトも何度か話したことがある。いわば単なるクラスメイトなのだが、金髪でよく目立つギャルに読んでもらうのはさすがに躊躇していた。
それなら趣味の合わない唯一の友人に読まれて酷評される方がずっとマシだとすら思っていた。
「困ったな……」
アオトは首を垂らして眉を顰めた。
そこで交友関係が極端に狭くて一人でいることが多い自分を初めて呪う。
だが、彼の自分の書いた小説を誰かに読んでほしいという気持ちには変化はなく、最悪の場合、担任にでも見てもらおうかと考えていた。
「……はぁ、どうしようかな」
「降谷くん? どしたの?」
アオトが弱々しく息を吐いた瞬間だった。
ハルカはスマホをいじる手を止めたかと思いきや、アオトの方に席を近づけて覗き込んできた。
「……え」
アオトは唐突に真正面に美少女が現れたことで、思わずたじろいでしまう。
自分のことを認識してくれているんだなという驚きと、なぜ話しかけてきたのかという疑念が心に宿る。
同時に普段は横目で見ていた彼女の姿を真正面から捉えることで、妙な緊張感を抱くことになる。
そりゃそうだ。ハルカが纏う人当たりの良さそうな雰囲気は、根暗で朴訥なアオトとは大違いだった。
整えられた明るい金髪のボブカットとくりくりとした丸い瞳と薄い唇、真白い肌、当然のように第一ボタンは外されており、首元の赤いリボンは緩んでいる。
ただ、そんなラフな着崩し方とは対照的に、彼女は袖捲りをせずに長袖のシャツを着用しており、なぜかこの時期に厚めのストッキングを履いていた。周りは気にしていない様子だったが、孤独を極めて周りをよく見ているアオトは少しだけ疑問に思った。
「……星宮さん、俺に何か用?」
アオトは平静を取り繕って言葉を返す。
気になりはしたが、特に服装については言及しないことにした。
「んー? 星宮でいいよ~。それで、なんで怖い顔してたの? 悩み事でもあるの?」
ハルカは優しげな声色でアオトに尋ねたが、彼は内心で”よりにもよって……相手は星宮さんかぁ”と失礼なことを考えていた。
正直、彼からすれば彼女は別世界の住人なので、関わり合いたくないとすら思っていた。
「まあ、そんな感じ」
ぶっきらぼうな相槌を打つ。
「ふーん……降谷くんの悩みかぁ。気になるねぇ。ちょうど退屈してたし、降谷くんさえ良ければ、その悩みってやつを私に聞かせてよ。解決できちゃうかもだし?」
ハルカはにへらと笑い、やや前のめりになる。
アオトの席は窓際の最後席になるので、彼女から距離を詰められたら逃げ場はない。背後の窓から外へとダイブすれば話は別だが、ここは3階なのでそれをしたら命は儚く散ることになる。
アオトは覚悟を決めた。どう転ぶかわからないが、見た目のギャル感に反して人の良さそうなハルカに相談してみることにする。
「星宮は、小説とか読むか?」
「うん、読む読む、めちゃくちゃ読むよ。一番好きなのは恋愛小説かな~……って、あれ? もしかして降谷くんの悩みは……恋の悩み!? 誰誰? 誰を狙ってるのさ! うちのクラス? それとも他クラス? まさかの先輩とか!?」
「断固として違うからな」
「なーんだ。じゃあ何に悩んでるのさ?」
ハルカは間髪入れずに否定されたことで不満げな様子を露わにしつつも、続け様に聞いてきた。
「実は……いや、いいや。やっぱり辞めた」
アオトはスマホに映し出されたテキストデータを彼女に見せようとしたが、直前で躊躇してしまう。
自信のない彼の言葉は教室に蔓延る些細な雑音にかき消された。
「えー! 気になるじゃーん! 教えてよー!」
「……笑わないか?」
「笑わない笑わない」
「本当に?」
「うん!」
「わかった。じゃあ、見せる」
わくわくした顔つきで食い下がるハルカに押し負けたアオトは、ついに意を決して自身のスマホを彼女に手渡した。
「……これ、小説? 降谷くんが書いたの?」
アオトのスマホを受け取ったハルカは僅かに目を見開いて驚きを露わにしていた。どこか感心したような声色でもある。
「まあ、恥ずかしい話なんだが……恋愛小説を書いてみたんだ」
「へー、じゃあ、悩みっていうのはそれ関連?」
「察してくれ」
「うんうん、誰かに読んでほしいからってことだね」
「ああ……俺みたいなやつが、おかしいだろ?」
「別にー、私も似たようなことしてるし気にしないよ。それより、私って恋愛小説は大好物だから、降谷くんさえ良ければ少し読んであげてもいいよ? 感想とかほしいでしょ?」
「ほんとか?」
アオトは願ってもみなかったハルカからの提案に対して食い気味に返事をした。まさかまさかの展開に心を躍らせる。
「うん。ゆっくり読みたいから、データちょうだい?」
「わ、わかった。どうやってあげればいい? LINEとかなら簡単に送れるんだけど……」
「……んー、じゃあ、LINEにしよっか。QR、追加して?」
「え? いいのか?」
ハルカが手に持つスマホにはLINEのQRコードが映し出されていたが、それを見たアオトは、本当に自分が友達登録していいのか遠慮気味になった。
「そっちが言ったんでしょ? そもそも、クラスメイトなのにLINE交換してないのなんて、降谷くんくらいだよ?」
「え? そうなの?」
「うん。だから早く追加してそのデータ送ってよ」
「……送った」
アオトはおずおずとハルカのQRコードを読み取り、そのままテキストデータを送りつけた。
とんとん拍子で母親以外の女性の連絡先をゲットしたのだった。
彼にとってのLINEとは、ニュースを見るくらいしか使い道がなかったので、こうして見知った人物がトーク履歴に残るのは不思議な気分だった。
「ありがと。こう見えても、ハルカちゃんは恋愛ものにはうるさいから覚悟しててね~?」
ハルカの言葉を聞いて、ほっと一安心したアオトは胸に手を当て息を吐く。
「……辛口評価は程々にお願いします」
文字数は一万文字程度の短編小説となっており、一日あれば読み終えることはできる文量である。
「感想は放課後でいい? あまり長い時間はつくれないけど」
「ああ。よろしく頼む」
「はーい」
ハルカはにこりと微笑んで体勢を直してスマホに視線を戻すと、器用に画面をスクロールさせながらアオト作の恋愛小説に目を通し始めた。
アオトはそんな彼女から目を逸らして窓の外を眺め、落ち着いた様子で嘆息する。
少し不安な気持ちを抱えながらも、喜びに満ちた気持ちで小説のデータを送り、その瞬間、自分の作品が他人の目に触れる喜びと緊張が入り混じった。
星宮晴香という予想だにしない《《読者》》の反応が気になりながらも、彼は自信を持って自分の作品を共有することに決意したのだった。
今日の放課後には読み終えて感想をくれるということなので、アオトは高揚感を胸に授業を受けて放課後が来るのをじっと待ったのだった。
◇◇◇
時刻は午後4時。
クラスメイトたちは各々が帰宅したり、所属する部活動へと顔を出しており、教室はアオトとハルカの2人きりになっていた。互いに自分の席に座り、そんな2人のことを窓から差し込む夕暮れの光が柔らかく照らしている。
そんな教室で2人きりになったアオトとハルカの間には、緊張と不安が交錯していた。
一方は初めてのオリジナル恋愛小説を読んでもらった高揚感と不安に押しつぶされそうになりつつも、渾身の一作を評価してもらえる胸の高鳴りを感じている。対して、もう一方は悩ましげな顔つきで首を傾げながらスマホをじっくり見つめていた。
「……星宮、どうだった?」
「んー、はっきり言っていい?」
躊躇いながら声をかけたアオトとは対照的に、ハルカはサバサバした様子だった。
「ああ」
アオトは期待を込めてごくりと息を呑んだ。
しかし、溜め息を吐きながら口を開くハルカの一言に絶句することになる。
「はぁぁぁぁ、全ッ然だめかなぁ……」
「え? ど、どこがダメだった……?」
「まず、リアリティがなさすぎ。高校を舞台にした恋愛は悪くないけど、主人公とヒロインの関係性が曖昧だし、キュンキュンするはずのセリフとかシーンも淡白すぎるかな。それに、恋愛小説特有のヒロインが余命宣告を受ける展開は悪くないけど、2人の関係がまとまらないままヒロインの子が死んじゃったから、読者は置いてけぼりって感じ? まあ、降谷くんは勉強できるタイプだろうし小説としてはかなり読めるよ。文章力もあるから読んでて疲れたりはしなかったしね。でも、恋愛小説に求めるようなキュンキュンは全く味わえなかったかな~~」
ハルカは、のびのびやんわりとした口調ではあったが、思いの丈を隠すことなく素直な意見を口にした。
言葉には、アオトに小説を書いた経験はもちろんのこと、おまけに恋愛経験まで全くないことを指摘する厳しさが暗ににじみ出ていた。
しかし、それはアオトもわかっていた。
期待していたような評価はされなかったが、確かにそう言われてみると不自然な点がいくつも散見された。
特に主人公の男から見たヒロインのポジションや境遇、1人1人の物語やラストまでの成長とエンディングの盛り上がりに関してはかなりイマイチだと、アオトは思っていた。
「……キュンキュンしないか」
「うん。恋愛小説に求める、主人公とヒロインのチグハグしてヤキモキするシーンが全くなかったね。もうちょっとドキドキ感と初々しい二人の空気感を味わいたいかな~。恋愛パート以外もあんまり良くないけど、特にそこの部分が台無しって感じ。これだと情景が思い浮かばないし、2人の表情とか感情がわかりにくいよ。これじゃネットでバズれないよ? 」
ハルカは肩をすくめて乾いた笑みを浮かべた。
「確かになぁ。うーん……そっか」
ハルカの感想を聞いたアオトはショックを受けると、落胆の色を隠すことなく俯いた。
そして、恋愛を経験したことがない自分が描いた作品には、確かに不足があったかもしれないと考えた。それでも、彼はハルカの率直な意見に感謝し、今後の成長に繋げることを決意していた。
同時に他人の小説を読んで具体性のある感想を述べてくれたハルカに対して少しだけ興味が湧いていた。
「ちなみに一つ気になったんだが、星宮は恋愛小説をよく読むって言ってたよな。結構な読書家だったりするのか?」
アオトは体勢を整えてハルカの方に向き直りながら尋ねた。
彼女はやけに小説に対する評価がしっかりしていたし、どことなく慣れた様子で捲し立てていた。
まるで評論家だ。
「……うん~、まあ、そんな感じかな。実は、私ってイラストを描くのが好きなんだけど、色んな発想を得るために恋愛小説はたくさん読んでるんだ」
「ふーん、どんなイラストを描いてるんだ?」
「んー、待ってね……ほら、こういうの。あまり見ないで、恥ずかしいから」
恥ずかしいからと言いつつも、ハルカは自身のスマホをアオトに隠すことなく見せてきた。
スマホには多彩な色合いで構成された美しいイラストが表示されていた。そういう方面に疎いアオトがパッと見る限り、正直プロかと思うくらいの出来栄えだった。制服を着た男女が手を取り合い、公園の遊具を背に夕焼けの道を歩くそのイラストは、幻想的なあまり思わず目を奪われてしまう。
とてもアマチュアとは思えないレベルだった。
「凄いな」
アオトは心の底から感動してしまい、それ以上の言葉が出てこなかった。
だが、嘘偽りない褒め言葉を耳にしたハルカは照れくさそうに笑みをこぼす。
「まあね~。まだ家族とか学校の友達には言ってないんだけど、みんなから注目されるようなイラストレーターになりたいんだ。売れてるトップレベルの人たちに比べるとまだまだだけどね」
ハルカは照れくさそうに微笑んでいたが、その言葉には確かな余裕と自信を感じさせた。それも妙なくらいに。だが、きっとそれこそ、彼女が1人で努力を積んできた結果なのだろうと、アオトは解釈する。
「……というか、誰にも言ってない将来の夢を俺なんかに伝えて大丈夫だったか?」
「うん。だって、降谷くんは勇気を振り絞って私にこの小説を読ませてくれたんでしょ? それならこっちも隠すことはないかなって思ったんだ。それに、降谷くんって友達いなさそうだし、バラしたりもしないでしょ?」
「最後の一言は余計だな」
「事実でしょ?」
「ふんっ……」
アオトはぶっきらぼうに鼻で笑ってみせた。イエスともノーとも答えてないが、無論、バラすつもりはない。
ただ単に、初めて他人から心のうちを明かされて信頼された感覚に嬉しさを感じていただけだった。
ハルカ自身がどう感じているかは別して、アオトはそうだった。
「……良いこと思いついた」
しばしの沈黙を挟んだのち、ハルカはパッと閃いたような顔つきになる。
どこか意味ありげな表情だ。
「良いこと?」
「うん、今度2人でお出掛けしよっか」
「へ? デートってことか?」
唐突なハルカからの提案を聞いたアオトは、素っ頓狂な声を漏らす。
すると、彼女はわたわたと取り乱しながら口を開く。
「あっ、た、ただお互いの小説とイラストのためにそういう経験を積む練習をしてみない? っていう提案だから、変な勘違いはしないでね。ほんとに、違うから」
——真っ向から否定されたら、それはそれで悲しいな。
アオトは心の中で涙を流したが、ハルカは続け様に口を開く。
「それに名前の相性もいい感じじゃない? 降谷くんの下の名前は……確か、アオトだったでしょ? それで、私の下の名前はハルカ。くっつけたらなんと、アオハルになるんだよね~」
「あおはる……って何だ?」
アオトは地方のご当地B級グルメを耳にした時のような反応を見せる。
無理もない。彼は青春とは無縁の学生なのだから。
「アオハルはアオハルだよ。青い春で青春。わかる?」
「あー……読み方を変えると青春ってことか。俺には縁のない世界だな」
「まあまあ」
「……それで、そのお出掛けってのは何が目的なんだ?」
アオトは互いの名前をもじったコンビ名などに興味なんてなかったので、特に深入りすることなく話題を戻した。
「私が単に降谷くんが書く恋愛小説を題材にしてイラストを描いてみたくなっただけかな? 降谷くんに恋愛経験がないのは当然のこととして、こう見えて私も恋人なんてできたことないし、誰かを好きになったこともないんだよね。そんな2人がタッグを組むのって王道じゃない?」
恋愛経験がないのは当然と言われたことで、アオトは少し反論したい気持ちに駆られたが、覆しようがない事実だったのでそっと胸にしまい込む。
そんなことより、アオト的にはハルカほどのルックスを持つ人が、自分と同じくそういった経験がないということに驚いていた。
「星宮も俺と一緒なんだな」
「……まあ、私はたくさん告白されたことがあるし、色んな男子と出かけたこともあるから、降谷くんとは違うよ?」
ハルカは同意を示したアオトの目を見て鼻で笑った。
確かに、2人を同類というには無理がある。それくらいクラスでもアオトは目立たない存在だったし、対してハルカは明るく活発でクラスでもよく目立つ方だった。
特定の誰かと仲が良いというわけでもなく、男女問わず満遍なく多くのクラスメイトと話している姿をアオトは見たことがある。
彼はそんな彼女に恋人や好きな人ができたことないなんて信じられなかった。だが、本人がそういうなら疑うわけにもいかない。
「……モテモテなんだな」
「うーん……モテモテかぁ。私のことを何も知らないで勘違いしてる人が多いだけだと思うけどね。外面がいくら良くても内面がダメだったら遠慮願いたいでしょ? 互いの立場とか性格、容姿、全部含めて恋愛なの。だから恋愛は簡単じゃないんだよ。だって、実際に降谷くんは私がどんな人なのか何も知らないでしょ?」
「まあ……そうだな。でも、俺に話しかけてくれる優しい人ってことくらいはわかるぞ」
アオトは思い悩んでいる他人に声をかけてやれるハルカのことをかなり評価していた。
ハルカの見た目は金髪のギャルでかなり癖があるが、そこはかとなく感じる人当たりの良さと優しさもあった。
アオトは少し会話を交わしただけで、ハルカのことを悪い人ではないと思っていたのだ。
「それだけで、私のことを優しい人だって思うんだね~」
「ああ、優しいと思うぞ。少なくとも、影でこそこそ俺の悪口を言う奴らとは違うと思う。でも、俺は星宮のことをほんの少ししか知らないから、きっと無鉄砲に告白してくる奴らと変わらないんだろうな」
ハルカはモテるタイプであるが故に当事者意識の高そうなことを言っていたが、アオトは他人から恋愛的な好意を向けられたことがないので、殆ど共感することができなかった。
しかし、彼女の優しさは身に沁みて実感していた。
「そういう意味では一緒かもね」
「だろ?」
アオトは特段反論するでもなく同意を示す。
彼は自分自身が彼女とは釣り合わないという事実を心のうちで理解していた。
そんな端的な返事をした彼に対して、ハルカは唐突に真剣な顔つきになり、
「……でも、あんまり、他人に期待しないほうがいいと思うよ。本当の私は優しくないかもしれないしね?」
と、何かに取り憑かれたかのように言った。
アオトはその現実味のある言い方がどこか気になったが、それでもハルカの事を信用した。
「俺は相手に過度な期待はしないけど、裏切られるその時までは相手を信じるよ。もちろん、星宮が優しいってことも信じてる。それに俺は相手を外見だけで判断はしないつもりだ」
「え~、なんか絵本の騎士様みたいだね。じゃあ、私がピンチになったら助けてくれるのかな?」
ハルカは口元に手を当てて、わざとらしくら 驚いた素振りを見せた。まるで、品定めをするかのように、瞳を細めてアオトのことをジッと見ている。
「まあ、時と場合にもよるけど、本当に困っている時はどうにかしてやらなくもないぞ」
「じゃあ、その時はお願いしちゃおうかな~」
「お互いに覚えていたらな」
アオトは茶化し口調のハルカの言葉に対して、呆れながらも乗ってあげた。
彼女とは深い関係になることはなさそうだと、彼は思っているので、あまり間に受けずに適当に返事をするに留める。
「はいはい。それで、お出掛けには行ってくれる?」
カスミはふとアオトから目を逸らして脱線しかけた話のレールを元に戻した。
「そうだな。俺も少し気になるし、一緒にそういうことをするのは別に構わないぞ。それより、本当にいいのか? 俺みたいな根暗と一緒にいたら変な噂が立つかもしれないぞ?」
「んー、大丈夫。私たちはお互いの目的のために協力するだけだから付き合ってるわけじゃないしね~」
アオトの気遣いに対して、ハルカは手をひらひらとはためかせながら軽くあしらって答えた。
まるで、照明に群がる羽虫を払うかのような仕草だ。無理に距離詰めたら手が飛んできそうだ。
「まあ、それもそうだな。わかった。じゃあ、今度の日曜日は空いてるか?」
「うん。どうせなら映画でも見よっか。お昼くらいに駅に集合でいい?」
「わかった」
アオトは特に表情を変えることなく首肯したが、心の中では初めて異性と遊ぶことに対して妙な気分に陥っていた。
「……ってかやば! もう4時半じゃん!」
アオトが夕焼けを見て目を細めていると、ハルカはハッとした表情で勢いよく席を立ち、そそくさと帰り支度を始めた。
「何か急ぎの用事でもあったのか?」
「うん、今日は5時からクラスのみんなでカラオケって話だったじゃん? 降谷くんも来る?」
「いや、大丈夫だ」
ハルカは特に何の気なしにアオトを誘っていたが、肝心のアオトは食い気味に断りを入れて彼女から視線を逸らした。
彼からすれば、彼女が言うような”みんな”の中に自分が入り込める自信も気概もなかったのだ。
「そっか。じゃあ、次の日曜日ね~」
「おう、またな」
ハルカがバタバタと駆け足で教室から出ていき、アオトは必然的に一人きりになった。
もちろん、アオトには用事なんて全くないので、ハルカが立ち去ってからすぐに自身も帰り支度を始めた。
彼は冷静なフリをしていたが、実は内心はバクバクだった。
あまりにも非現実的なハルカとのデートを日曜日に控えているという事実に困惑する。
「……夢か?」
相容れない存在だと思っていたのに、まさかこんなことが起きるなんて……。アオトは胸に手を当て早くなる鼓動をその身で感じた。
彼は自分に恋人ができるだなんて考えたこともなかったし、それは今も変わらなかった。
しかし、ハルカの様子を見る限り自分への嫌悪は感じられなかったので、勘違いしかけたウブな心が宿っているのも確かだった。
「ダメだ。切り替えよう」
アオトは空気を入れ替えるようにして大きく息を吐いた。
付き合うとか付き合わないとかそういうのじゃない。これは恋愛小説を書きたい自分と素晴らしいイラストを手がける彼女の協力関係に過ぎない……彼は、そう胸中で整理をつけて心を入れ替える。
「……帰ろ」
アオトは重たいリュックを背負って閑散とした校舎を後にすると、夕陽が空を染め、夏の終わりの風が心地よく吹き抜ける中、帰路に就いたのだった。
◇◇◇◇
札幌駅、通称札駅には様々なテナントが入っており、高校生から大人まで多くの人々が楽しめるようになっている。
構内の開けた空間には人々が行き交い、活気に満ちている。高い天井と広々としたスペースが、待ち合わせ場所にふさわしい穏やかな雰囲気を演出している。
大きく設けられた窓や出入り口の扉、吹き抜けになっていて高い天井の照明からは明るい光が差し込み、駅の喧騒と共に微かな風が流れていた。
その中で、待ち合わせ場所であるベンチに座るアオトの姿があった。
彼は周囲の様子を静かに眺めながら、時折腕時計に視線を移し、緊張と期待が入り混じった表情を浮かべて待ち合わせ相手であるハルカの到着を心待ちにしていた。
「……おまたせーーーー!」
待ち合わせの時刻を過ぎてから待つこと5分程。
ハルカは手を振りながら駆け足でやってきた。
彼は何の気なしに彼女の全身を下から上まで軽く眺めた。
上はチャコール色の厚手のカーディガンを羽織り、中には真白いトップスを身に纏っていた。
下にはブルーのジーンズを合わせており、シンプルであるが故に素材の良さが引き立っているのがわかる。
また、肩には小さなバッグを下げ、耳には煌びやかなイヤリングが光っている。とても高校二年生とは思えない大人びたコーデだ。
ほっそりしていて足も長い。中肉中背で取り柄のないアオトとは対照的だ。
「ふぅ、遅れてごめんね~」
「大丈夫だ」
「それで……どうかな?」
ハルカはアオトに自身のスタイルを見せつけるかのように、ぐるりと回ってモデルのようなポーズを決めている。
その美しい姿に通りすがりの人々も一瞬立ち止まり、その魅力に見惚れてしまうような雰囲気が漂っていた。
それはアオトも同様で、ハルカの姿を見てごくりと息を呑んでいた。
「え?」
「私の服装だよ。似合う?」
やっぱり容姿が整っていてよく目立つということはわかっていても、どんな言葉をかけてあげるが正解なのか……それがよくわからなかったアオトは言葉に詰まる。
「……まあ……ちょっと暑そうだな。今日は30度近くあるぞ?」
恋人っぽい感じをイメージするのならこの場面は間違いなく洋服を褒めるべきなのだが、照れ臭かったアオトはおかしな返事をしてしまった。
「はい。減点!」
ハルカはびしっとアオトに指を差す。
「え?」
「こういう時は気になる事があったとしても、素直に相手の服装を褒めるんだよ? 可愛いね、似合ってるねって言うのが正解かな。はっきりと思った事を言葉にするんだよ。可愛いと思ったら可愛い、似合ってるって思ったら似合ってるって……ね?」
ハルカは不満そうな表情を浮かべてアオトの隣に座る。
同時にふわりと甘めの香水の香りが漂い、慣れてないアオトは僅かに鼻を啜る。
「ふむふむ……参考になるな」
アオトは黒いスラックスのポケットから小さなメモ帳を取り出すと、一語一句丁寧に書き記していく。
その姿を見たハルカは頬を膨らませて更に不満気になるが、アオトは尚もメモを取り続ける。
「はぁぁぁぁ……降谷くん、メモはデートが終わってから取ってね。相手の女の子を置いてけぼりにしたらダメなんだよ!」
ハルカは大きな溜め息を吐いて呆れを露わにすると、少し強めの口調でアオトに注意した。彼女の期待とは裏腹に、アオトの言動は彼女の気持ちを満たすことができなかったのだ。
「ん、悪い。でも、本当に暑くないか? 下が半袖なら脱いだほうがいいと思うぞ?」
アオトはメモ帳をポケットに戻して謝辞を述べたが、今一度ハルカの姿を見るとやはり季節感があってないという感想が一番に出てきた。
「まあ……それはそれだよ」
ハルカは視線を動かしながら動揺していたが、アオトとしてもそれ以上は特に追求はしなかった。
単に彼女が天気予報を見てこなかったのだろう。それから、オシャレは我慢とも言うし……そういう事なのだろう、と結論付ける。
「行くか」
「うん」
アオトはハルカと少しの間を開けて隣を歩く。向かう先はエレベーターだ。7階に映画館があるのでそこを目指して進んでいく。
やがて、7階に到着すると、人々で賑わう通路を進んでいった。
ハルカは持ち前の綺麗な金髪が風になびく中、アオトの隣を楽しそうに歩いており、その姿はまるで夏の風をそのまま纏ったかように爽やかだった。
一方のアオトは、彼女の魅力に少し圧倒されながらも、彼女の隣を歩きながら気分を高めていた。
普段は比較的インドアなアオトからすれば、こうして映画館で映画を見るのは親に連れられて行った幼少期以来なので新鮮なことこの上なかった。
もちろん、ハルカと二人きりになるワクワク感も無くはなかったが、それ以上に映画館で見る映画への期待が高まっていた。
やがて、適当に会話を交わしながら歩くアオトと晴香は、気がついたら映画館のロビーに到着していた。
「降谷くん、何が見たいの?」
「そうだなぁ」
二人は映画館のロビーに立つと、小さな画面に映し出されている上映中の映画一覧に目を通した。
アオトは顎に手を当てじっくり悩み抜いた末に、唯一見覚えのある映画を指差した。
「あれはどうだ」
「……悪くないけど、どう見ても子供向け映画だよね、あれ」
「子供の頃なんかは毎週日曜日は早起きしてテレビで見てただろ? アニメに比べると映画は壮大だから結構面白いぞ?」
誰から見てもその映画は子供向けで対象年齢は3歳から5歳をターゲットにしていた。誰もが一度は見たことがある多種多様なパンが主人公の国民的キッズアニメである。決して高校生の男女がデートで見るような映画ではない。ただ、これは不器用なアオトなりの冗談だった。
「はい、減点。大して親しくもない女の子と2人で見る映画じゃないよね。子連れならわかるけどさ」
ハルカは呆れた様子で減点を言い渡すと、やれやれと首を横に振った。真顔で紡がれたアオトの冗談を本気と捉えてしまった結果である。
「うーん……」
2度目の減点を食らうアオトはムッと眉を顰めた。
彼からすればほんの冗談のつもりだったのだが、あまりにも無表情すぎたばかりにハルカには通じなかったらしい。
「ここは無難に恋愛映画はどうかな?」
ハルカは悩ましげなアオトの肩をつんつんと突く。
「そうだな。でも、恋愛映画は上映まで結構時間空いちゃうし、ホラー映画にしないか? 星宮がそういうの平気ならだけど、どうだ?」
「ふっふっふっ……何を隠そう、私ははホラー映画が大の苦手だよ! 降谷くんは平気?」
「俺はそういうのを見てもあんまり何も感じないな」
苦手だというのに乗り気で自信ありげなハルカに対して、アオトは元々感情表現が苦手だからかかなり淡白な返答だった。
「この映画、ネットで大バズりしてたんだけど、すっごい怖いらしいよ? 降谷くんでも声を上げてびっくりしちゃうかもねー」
「それはそれで楽しみだな。じゃあ、早速チケットを買うか」
「うん。そうだね」
どの映画を見るのか決めたアオトとハルカは二人並んで発券機へ向かうと、適当に座席を決めてチケットを購入した。
そして、次に二人はポップコーンとドリンクを買うために売店へと向かう。
「降谷くんはポップコーンは何味が好き?」
ハルカは頭ひとつ分背の高いアオトを見上げながら聞いてきた。
まるで彼のことを試すかのような目つきである。
「断然キャラメルだな。それ以外にありえない」
「いっしょー! やっぱポップコーンといえばキャラメルだよねー。でも、1人1つだと多そうだし、ポップコーンが1つとドリンクが2つ付いてくるセットにしよっか。飲み物はどうする?」
ハルカはアオトの答えに満足したのか力強く何度も頷いた。
互いに、無難な塩味や、変わり種だが確かに美味しい醤油バター味等ではなく、甘塩っぱいキャラメル味をチョイスしたのは、ほんの小さな初めての共通点であった。
「烏龍茶かな。星宮は?」
「私はオレンジジュースかな。昔から好きなんだよね~。覚えておいてね?」
「善処する」
アオトはハルカからメモを取っちゃダメと言われていたので、頭の片隅に記憶を残しておくことにした。
今後何かの役に立つことを願って。
「じゃあ、頼んでくるから待ってて? お金は後でまとめて計算しよ」
ハルカはちょうど空き始めた売店のカウンターへ一目散に向かうと、慣れた様子で注文を済ませて数分後にはトレーを手にアオトの元へ戻ってきた。
アオトはもしも自分だったら口下手だからもう少し時間がかかりそうだなと思い、慣れた様子で行動してくれたハルカへの感謝の言葉が自然と口から溢れる。
「星宮、俺の分までありがとう」
「そういうのは言えるんだね~」
ハルカは少し驚いた様子を見せる。
「当たり前だろ。わざわざ買ってきてもらったんだからな。それより、チケットを買うのが少し遅かったから上映開始までもうほとんど時間がなさそうだぞ。急ごうぜ」
「そうだね」
アオトはハルカと一緒に入場し、指定席に腰を下ろして息をつく。
日曜の昼間だからかそれなりに人が入ってる。
話題のホラー映画ということもあり、場内にはカップルが多い。
「ふぅ……いい席だな」
「そうだね。でも、ちょっと席の間隔が近くない?」
アオトは柔らかな座席のソファに背を預けて寛いでいたが、隣に座るハルカは何か気になるのかそわそわとしていた。
「そうか?」
「うん……というか……」
ハルカは薄暗い場内の中で手に持つチケットと、辺りの様子を交互に眺めていた。
映画館自体に来たのが久しすぎるアオトには何のことかわからない。
「どうした?」
アオトは少し距離を詰めてハルカに尋ねた。
すると、彼女は何かを理解したのか、ハッとした様子で口元を手で覆って目を見開いた。
「……ここカップルシートだった」
ハルカは頬を引くつかせながら口にしたが、アオトからすれば特に気にすることでもない。
「あー、別にいいんじゃないか?」
カップルシートは隣接し合う互いの間にあるはずの肘掛けがなく、席全体がやや広めに作られており、ゆっくりと映画を見ることができるからだ。足を伸ばせるフラットシートになっていてかなりリラックスできる。
だが、ハルカは何か言いだけな様子だった。
「私、ホラーとかすっごい苦手なの」
「言ってたな」
「いつもは女友達と一緒に見に行くんだけど、毎回怖がりすぎて泣きそうになってるんだー」
ハルカはCMが流れる巨大スクリーンを虚ろな瞳で見つめていたが、その焦点は全くと言っていいほど合っていなかった。
「それで?」
「今日はあんまり親しくない降谷くんが一緒でしょ? 肘掛けもないでしょ? カップルシートは座席が広くて自由が効くでしょ? どういうことかわかる?」
ハルカは乾いた笑みを浮かべていた。
そんな彼女の笑みを見て、アオトは考えた。
普段は女友達と一緒にホラー映画を見に行っていて、その度に泣きそうになっていて、今回は肘掛けがなくて広々として自由が効くカップルシート……二人を妨げるものは何もないということだ。
恋愛に疎い俺だって知ってるし、よくドラマかなんかで見たことがある。男女ペアで肝試しをしたら怖がった女性が男性と接近して、吊り橋効果とやらで距離が縮まるというアレだ。
アオトは怯えるハルカを見て先の展開を想像する。
「……ん? まさか……怖がった拍子に抱きついてきたり——」
「——ううん、手が出たらごめんね? 私、本当に怖い時はなりふり構わず暴れちゃうかも! 許してね? それに、暗いからってどさくさに紛れて変なことしたら……わかってるよね? 後、狭い場所はあまり得意じゃないから、少しだけ離れてみてくれると助かるかな~」
ハルカはアオトの言葉を遮り、胸の前で両の拳を力強く握り込むと、彼の想像した展開を大きく裏切ってきた。
「……はいよ」
溜め息混じりに返事をしたアオトはハルカと距離を取り端の方に移動する。
すると、ハルカはいよいよ暑くなったのか、カーディガンを脱いでマントのように肩にかけた。
「暑かったか?」
「うん。さすがにね。でも、降谷くんは半袖のTシャツしか着てないから、逆に寒くなりそうだけど」
「確かに……かなり空調が効いてるし、ホラーで怖くなったら寒くなっちゃうかもな」
アオトが冗談混じりに言うと同時に、場内は静けさを纏って暗くなっていく。
すっかり映画館のモードになった2人の間には沈黙が訪れる。
やがて、しばしのCMを挟んでから映画が始まったのだが、上映中、ハルカがびっくりして体を跳ねさせたり、広々とした座席の中で些か激しい挙動を見せることで、そこからふんわりと漂う女の子らしい良い香りと香水の甘い香りに気が散ってしまい、アオトはあまり映画に集中できていなかった。
まるでわざとアオトの気を引こうとしているのではないかと思うくらいに、ハルカは一挙手一投足激し目の動きをしていたのだ。
1度だけ、アオトがハルカに視線を向けたタイミングで、彼女が肩にかけていたカーディガンがはらりと落ちたのだが、その際に彼は彼女の右肘の辺りに深い火傷のような傷痕があるのを目にした。
デリカシーを保ち傷痕について尋ねる事はしなかったが、やはり激しい挙動と甘い香りも相まって、アオトは全く映画の世界に没入できなくなったのだった。
◇◇◇
やがて映画が終わると、札駅内の小綺麗なカフェに入った二人は映画の余韻に浸っていた。
「いやぁ、めちゃくちゃ怖かったねー。私ってばビビりなのにああいうのついつい見ちゃうんだよね。ネットでバズる理由もわかるよ」
ハルカは小刻みに震える自身の体を抱きしめながらも、その口調は飛び跳ねているかのように楽しそうだった。
「5分に1回くらいは悲鳴上げてたな。特に空から大量の生首が降ってくるシーンなんかはずっと叫んでたもんな」
対して、アオトは余裕そうな面持ちで口角を上げると、おもむろにアイスティーを啜ったが、その様子を見たハルカは頬を膨らませてすぐさま反論する。
「降谷くんだって暗い場所からオバケが出てきたシーンでビクってなってたじゃん! 『俺は何も感じないぜ☆彡』って言ってたのにねぇ~?」
「……まあな」
アオトは茶化してくるハルカから目を逸らした。
彼がオバケが出たシーンに反応したのは事実だが、それは別にホラー映画そのものに反応したわけじゃなかった。
本当は上映中に繰り出されるハルカの一挙手一投足が気になったせいだった。
肘掛けという名の防御壁が存在しないカップルシートだったからこそ、ハルカは無意識に動き回って時折アオトの体に触れてくることもあった。ホラーとは違ってそっち方面には全く耐性がないアオトは、その度に肩を振るわせて平静を取り繕うことに尽力していたのだ。
だが、そんなことを意識しているとバレたら嫌われる。そう思った彼は特に言い返さずに言葉を濁す。
「確かに、映画はまあまあだったな」
「ぷぷぷっ! やっぱりあの映画はホラー耐性のある降谷くんでもダメだったかぁ~。始まりから終わりまでずっと怖かったもんね」
「そうだな」
「……それで、どう?」
ハルカは冷たいオレンジジュースのストローに口をつけると、アオトに視線を向けて首を傾げた。
「何が?」
「小説だよ。2時間ちょっとだけだったけど女の子と一緒に過ごしたんだし、少しはアイディアが湧いてきたんじゃない?」
「あー、そうだな。色々とな」
正直言うと、アオトはハルカから漂う甘い香りとふとした無意識なボディタッチの応酬のせいで今の段階では頭の中に小説のアイディアは湧いていなかった。
記憶に新しいのは、彼女の右肘の辺りに見えた深い火傷のような傷痕だけだった。
「ふーん……じゃあ近いうちに今日のデートのことを小説にしてみてよ。私はそれを参考にしてイラストを描いてみるから、そうすればお互いに成長できる気がしない? 取り敢えず、来週の日曜日も予定入れとくね」
「次会うのは再来週かそれ以降にできないか? 定期テストが近いしな」
ぽちぽちと素早くスマホをいじっているハルカに対して、アオトは頭の中で近々の予定を確認した。
小説を書きつつもハルカとデートをして、尚且つ勉強もしたいので、明日からのテスト期間は遊ぶ時間には充てたくなかった。
「うーん……テストかぁ。うん、わかったよ」
「もしかしてテストがあることを忘れてたのか?」
「い、いや……別に、まあ、忘れてたかな?」
「少しは勉強した方がいいぞ」
「うっ……善処します」
ハルカは不服そうに唇を尖らせており、それ以上はテストに関する話題は出してほしくなさそうだったので、気を利かせたアオトは別の話題に切り替えることにする。
「ところで、話は変わるが星宮ぐらい絵が上手いなら、俺なんかとやるよりも良い相手がいるんじゃないか? わかっていると思うが俺なんてズブの素人だぞ?」
自虐ネタでもなんでもなく、アオトは何の実績もないズブの素人だった。素人に毛すら生えてないそこら辺に転がる路傍の石と何ら変わりない存在だ。
デートが始まってから言うことでもないと彼もわかっていたが、やはりなぜ自分なのかが気になっていた。
「前も言ったでしょ? 私のことは気にしないでって。これは単なる興味だから」
「でも……」
「いいの。付き合ってるわけじゃないんだし、お互いの為になるならそれでいいでしょ?」
食い下がるアオトに対してハルカは尚も言葉を続けた。お互いの為という部分が少し強調されたような気もしたが、恋人関係ではないという彼女からの隠れた主張だろう。
「まあ、そうなんだけど、やっぱり俺なんかの為にそこまでしてくれるのは申し訳ないというか……理由が気になるんだよな」
アオトはそれでもまだハルカが自分に声をかけてくれて、尚且つ小説まで読んでくれた本当の理由が知りたかった。
「ちゃんとした理由が知りたい?」
「ああ」
「降谷くんのことが好きだから」
真っ直ぐな瞳をアオトに向けながらハルカは言葉を紡いだ。
その瞬間。アオトの心臓の鼓動が急速に早くなる。
「え?」
アオトが素っ頓狂な声をあげで呆然としたのとほぼ同時。
ハルカはにやりと口角を上げて、したり顔になる。
「ぷっ! じょーだんだよ! 騙された? こういうのも恋人っぽいし、経験しておくのも悪くないでしょ? とにかく、私のことは気にしないでいいから、来週までに小説にしてみてよ。いい?」
ハルカは無邪気な子供のようにイタズラな笑みを浮かべていたが、向かいに座るアオトからすれば弄ばれた気分だった。
しかし、自己肯定感が低く、恋愛に疎いアオトは”女の子なんて皆そんなもんだ”と心の中で早々に納得し、先ほどまでの安直な自分の思考回路を恨んだ。
「はぁぁぁぁ……わかったよ。今日の経験を基に書いてみるよ」
アオトは大きく溜め息を吐いたが特に不満をこぼす事なく了承した。
彼からすればハルカほど絵が上手い人が自分に協力してくれるなら断る理由はなかった。
たとえそれが彼女の天邪鬼からくる突発的で曖昧な関係であっても、彼からすれば自分の描いた恋愛小説をもとにイラストを描いてくれるなんて夢みたいな話だった。
「うんうん。じゃあ、私はこの後用事があるから先に帰るけど、降谷くんは?」
「俺も、もうそろそろ帰るよ。色々とメモも取りたいし、今は結構良い案が出てきそうだから良い感じに書ける気がする」
「そう……それじゃあ、また明日!」
ハルカはストローに口をつけてオレンジジュースを一気に飲み干すと、すっきりとした顔つきで席を立った。
まだ時刻は午後3時を回ったばかりで解散するには早い時間だったが、まともな顔合わせは初めてだったので互いにやや遠慮がちなのがわかる。
「ああ、またな。それと、星宮、今日は俺に付き合ってくれてありがとう。その……遅くなったけど服も似合ってるし、今日は一緒に過ごせて楽しかった。また、よろしく頼む」
アオトはどこか照れくさそうに頬をかきながらも、真剣な瞳でハルカを見据えてお礼の言葉を告げる。
彼的には好意を向けられることが得意でなさそうなハルカにはあまりよろしくないかと思っていたが、やはり真面目な性格故か、これはしっかりと言葉にして伝えたい部分だった。
「……」
すると、アオトの言葉を聞いたハルカは少し驚いたようにして何度か瞬きをしてから、わざとらしく耳に髪をかける仕草を見せた。金髪がさらりと揺れて、彼女は一層色気を帯びた様相になる。
ごくごく自然な仕草だったが、まるでわざとアオトに見せつけているかのような艶やかさだった。
「……うん、こちらこそありがとう!」
ハルカはアオトに満面の笑みを浮かべて言葉を返すと、彼を残して一人で店を後にした。
そして、近くの雑貨屋に入って嘆息する。
「……んー、悪くないね~」
ハルカは雑貨屋の奥で一人佇みながら、アオトと過ごした時間を思い返すが、ショーケースに反射する彼女の顔は少々歪んでいた。
まるで、悪事を企む悪党のようだ。
「降谷くんって悪くないね……」
ハルカはごく自然な笑みを溢す。ただ、そこに先ほどまで見せていた人の良さは消えかけていた。
幸い、周囲には誰もいなかったが、何かおかしな思考をしているのは誰から見ても明白だろう。
「……あれ、これ……?」
そんなハルカはアオトのことを考えながらも何の気なしに視線を上に移すと、店内の壁に貼られた1枚のポスターが目に入った。
【恋愛小説コンテスト開催決定! 小説家を目指すキミへ! 応募締め切りは11/25——選考結果発表は12/25! 新時代の才能を発掘しよう!】
その文言を見てハッと何かを閃いた彼女は、すぐさまスマホでポスターの写真を撮り、迷う事なくアオトのLINEに送りつけた。
小説を書きたいと言っていた彼にはうってつけの機会だった。それに、自分の為にもなる。
「……これ……いいじゃん」
思い立ったハルカは小さな雑貨屋を抜け出すと、先ほどまでいたカフェへと早歩きで戻る。
別れてからまだ数分しか経っていないので、カフェの中にいるであろうアオトの姿を探す。
「すみません、前髪が少し長くて目つきの悪い人ってもう帰っちゃいましたか?」
カフェの中にアオトの姿が見当たらなかったので、ハルカはレジにいた店員の女性に声をかけた。
「あー、その方ならつい先程帰られましたよ。メモ帳を見ながらニヤニヤ笑ってましたね。確か、貴女はお連れの……」
「そうです。ちなみに、どっちに行きましたか?」
「左手側ですね。方向的に改札側だと思いますが……」
「ありがとうございます」
ハルカはすぐさまカフェを抜け出すと、店員の女性に教えてもらった通りに店を出て改札側へ歩みを進めた。
すると、人混みの向こうに見覚えのある後ろ姿を発見し、躊躇する事なくその背中を手のひらで叩く。
「降谷くーん!」
「んぁ……お、おお、星宮。予定があるんじゃなかったのか?」
ハルカに声をかけられたアオトは驚いた様子で振り向くと、伸びた前髪の隙間から彼女の姿をじっと見つめた。
先ほど別れたばかりの相手がなぜ目の前にいるんだという疑念が、その表情に如実に現れている。
だが、そんなアオトの動揺なんてハルカは考慮せずに、瞬く間に距離を詰める。
「LINE見た?」
「いや、見てない」
「何で!?」
「何でって言われても、俺って常に通知オフだし……」
「今すぐ確認してみて?」
「はいはい、わかったよ……」
ハルカに気圧されたアオトはポケットからスマホを取り出すと、不思議そうな面持ちでLINEを確認した。
「……えーっと、恋愛小説のコンテスト?」
アオトのスマホの画面には、つい先ほどハルカが送りつけたポスターが写っている。読み上げても彼は何が何だか理解していない。
「で、これがどうかしたのか?」
「挑戦してみたら?」
「え?」
ハルカからの唐突な提案を聞いたアオトは口をぽっかりと開けて固まった。
しかし、ハルカは全く構う事なく言葉を続けた。
「降谷くんは恋愛小説を上手く書けるようになりたいんでしょ? 期限は3ヶ月しかないけど、こういうのに挑戦してみる価値はあると思うんだ。小説投稿サイトに掲載して応募するみたいだし、ひょっとしたらバズって人気になれるかもよ?」
「バズる……? いや、俺は別にそういう目的のためにやってるわけじゃ……」
「カフェを出る時ニヤニヤしてたって店員さんが言ってたし、きっと何か思いついたんでしょ?」
「確かに、今日は星宮と過ごせたおかげで新鮮な経験はできたけど、俺なんかが書いた小説が賞を取れるわけないだろ」
アオトが自信なさげな表情で弱音をこぼしたが、ハルカはすぐさま首を横に振り顔に笑顔を貼り付ける。
「別に受賞なんてしなくてもいいじゃん。ただ、楽しむって理由だけじゃダメ?」
「……ダメじゃないけど、俺にできるかなぁ」
押せ押せのハルカの言葉を受けてアオトは腕を組む。
「降谷くんに足りないのは経験だけ! 文章力はあるから必ず上手くいく! 私も降谷くんが書き上げた小説を参考にしてイラストを描いてみるから、チャレンジしてみようよ!」
「……わかった。そこまで言うなら、やってみる」
不自然なくらい自分を評価してくれるハルカの言葉に励まされたアオトは、少しだけ自信を持ち始めた。
彼女の後押しによって、彼はコンテストへ挑戦する決意を固めたのだった。
「決まりだね。もしも小説を書き始めて3ヶ月の男子高校生が賞を取ったら話題になること間違いなしだよ! 頑張ろうね!」
「ああ」
アオトが快く返事をする事でハルカは満面の笑みを浮かべると、人目を気にせずぴょんぴょん飛び跳ねて喜びを露わにした。
その”喜びの真意”は彼女にしかわからない。
同時に、あまり目立ちたくない日陰を好む性格のアオトはそそくさと彼女と距離を取り他人のふりをする。
「ところで、用事はいいのか?」
「あっ忘れてた! 早く行かなきゃ! またねー!」
アオトの一言でハッとしたハルカは、ばたばたと走り去っていった。
「……頑張ってみようかな」
取り残されたアオトが呟いた言葉は人混みに流されて消えてしまったが、彼の心の中には確かなやる気が渦巻いていた。
同時に、星宮晴香という人物への強い興味と関心が心に宿り、また彼女と共に時間を過ごしたいと思うようになっていた。
人を感動させる恋愛小説を書いてみたい降谷碧都と、将来は有名なイラストレーターになりたい星宮晴香。
二人は大きな目的を叶えるために、3ヶ月後に締め切りが迫る恋愛小説コンテストへのチャレンジを決めたのだった。
◇◇◇
アオトとのデートの後の用事を済ませて自宅へと帰ってきたハルカは、自室のベッドに腰を下ろして一日の出来事を思い返していた。
今は着替えを終えて夕食を済ませ、お風呂にも入り終えたところだ。
時刻は午後7時を回ったところ。
ハルカは涼しげな生地の薄い寝巻きを身に纏いベッドに倒れ込むと、柔らかな枕に顔を埋めて不快感を孕んだ溜め息を吐く。
「あーあ……はぁぁぁぁぁぁ……」
その時、LINEの通知音が鳴る。
「降谷くんからだ……まっ、返信は後でいいや」
ハルカはスマホの通知音に気づき、アオトからのLINEが届いていることを確認した。
彼女はスマホを手に取って返信しようとしたが、今日は少しやるべきことがあるのを思い出すと、おもむろにTwitterを開いて眉間に皺を寄せる。
「……うーん……あんまりバズってないなぁ。もう、かなり上出来だったのに!」
ハルカはTwitterに映る自身のアカウントを確認すると、多大なフォロワー数の割にバズらない《《オリジナルイラスト》》を見て不満を溢す。
星宮晴香は飢えていた。
友人はもちろんのこと家族にすら明かしていないが、彼女はネット上では有名なイラストレーター【すたぁ☆】その人だったのだ。
フォロワーは50万人を超えており、現役女子高生イラストレーターとして名を馳せている。
しかし、最近は思うようにいかなかった。
50万人を超えるフォロワーは、どうして私のイラストを拡散してくれないんだと、彼女は心の中で愚痴る。
前までは新進気鋭のイラストレーターとして持ち上げてくれたくせに、最近はネット上での反応が薄くて満足できない。
心に植え付けられた承認欲求という名の魔物が、大きく口を開けて次の餌を待っているというのに……。
——こんなに承認欲求が芽生えて、内外で自分の性格が変わってしまったのはいつからかな。
ハルカは満たされない寂しい心の穴を直ちに埋めたかった。
「どうしよっかなぁ~」
ハルカはうつ伏せで寝転びながら、足をばたつかせて面白い話題はないかと模索した。
綺麗な一枚絵のイラストを描いても思うようにはバズってくれないし、何より仕上げるのにもそれなりの労力が必要だ。
自分が女子高生であるという利点を活かして、面白おかしい観点からどうにかして承認欲求を満たしたい……。
ハルカは高校の友達と遊んだ時の出来事や家族との何気ない会話を思い返すが、そんなありふれた日常には誰も見向きしない。
ネット上でバズるためには独特な着眼点だったり、奇抜なアイディア、現実とは乖離した非現実的な何かが必要なのだ。
「……あっ、降谷くんをネタにしよっかな」
ハルカはふと閃いた。
先日、彼女の興味を強く惹く出来事があった。
それは……降谷碧都が書く恋愛小説との出会いである。
いきなり恋愛小説を読んでほしいと言われた時はさすがに驚いたが、彼女にとってアオトは興味深い人物だった。
根暗で日陰ものなのに、なぜか唐突に恋愛小説に興味を持ち、挙句それを自分で書いてくるという特異な行動力。
観察対象としてはかなり面白い。
そもそもコンテストに彼を誘導したのも、あわよくばハルカ自身も目立ちたかったからという理由に他ならない。
もしも受賞しなかったり、そもそも途中で筆を折ってしまっても元の関係に戻るだけなので何ら問題はない。
「いいかも……今日からは新シリーズの投稿始めます……っと」
ハルカはすぐ行動に移す。
素早いフリックで文章を打ち込んでいき、今後バズる布石のために予め新シリーズを予期させるTweetを仕掛けておく。
「後は降谷くんと過ごした出来事をイラストにして、漫画ちっくな雰囲気に加工するだけだね」
ハルカは布石となるTweetを仕掛けてからすぐに机に向かい、さらさらとイラストを描き始めた。
まずは冒頭。描くのは今日の出来事だ。
クラスでも随一の陽気なギャルに対して、全く目立たない根暗男子が声をかけるシーン。
ポイントはその格差を強調すること。
ハルカにとってアオトは単なるクラスメイトに過ぎない。
そんな相手に対して、見た目に反して優しいギャルが甘い言葉をかけて茶化していく展開はよくウケる。
本来は関わり合いを持つはずのない2人が、ひょんな出来事をきっかけに関係を深めていく王道パターンである。
小馬鹿にした感じで題材にするのは少しばかり気が引けたが、自分の欲求には抗えなかった。
「まあ、2次元の中だから、ちょっとくらいは良い関係にしてあげてもいいかもね」
単なるクラスメイトであるアオトが恋愛対象に入ることは現状考えられなかったが、それはあくまでも現実の話。
絵の中の世界であればやりたい放題だった。
なので、このストーリーの大筋としては、金髪のギャルが根暗男子を茶化し、小馬鹿にし、その心を手懐けるような、SMないしは主従関係、校内カーストをうまく描いた明確な格差のある光景をイメージをしている。
きっとアオトはハルカとの経験を基にして純粋な恋愛模様を軸に小説を書くのだろうが、彼女が描くストーリーの主軸はそんな恋愛とは程遠かった。
時にはそんな恋愛ちっくなパートを織り交ぜていくつもりではあったが、やはり根暗男子を小馬鹿にする内容となっている。
まあ、アオトが何を思うかなんてハルカにとってはあまり関係なくて、彼女自身はネットの世界でバズって承認欲求を満たせればそれで良いのだ。
彼女の精神は、他人のことを考えるほどの余裕を持ち合わせてはいなかった。
「……降谷くんには内緒にした方がいいよね。私がプロのイラストレーターだって知っちゃったら、せっかく小説を書いてくれてるのに可哀想だし……」
ハルカはちょっとしたアオトへの気遣いを見せながらも筆を走らせる。
やがて、あっという間に2時間ほど経過すると、精巧な4枚のイラストが完成していた。
誰よりも筆が早いと自負しているハルカにとって、この程度の作業は造作もなかった。
「できた」
ハルカは完成したイラストを見て満面の笑みを浮かべた。
1枚目はアオトによく似た前髪の長い根暗男子が、金髪のギャルに話しかけられて挙動不審になるイラスト。
2枚目はそんな2人がデートに行き、根暗男子にちょっかいをかけて楽しむギャルのイラスト。
3枚目はデート終わりの会話を楽しむ平穏なイラスト。
4枚目は甘い言葉で誘惑して根暗男子の心を手玉にとるギャルのイラストだ。
どれも今日のハルカとアオトのデート内容に酷似したイラストだったが、冒頭の恋愛小説の下りを無くして互いの名前も変えているので違和感はない。
ただ、アオトがこれらを目にすればおそらく察しがつく。
しかし、今日見たホラー映画について何も知らなかったことから、きっとLINE以外にSNSはやっていないのだろうと彼女は推測する。
つまり、アオトにこのイラストとストーリーの存在バレることはない。
「あっ、タイトルどうしよ」
ハルカはTweetに添付した4枚のイラストを見て考える。
そしてすぐに思いつく。
「『根暗男子と金髪ギャル』でいっか。シンプルな方がわかりやすいし、ネット民にはこれくらいがウケるかな。はい、Tweetっと……」
ハルカは特に深く考えることなくTweetすると、次にLINEを開いてアオトから送られてきたメッセージ内容を確認することにした。
「んじゃ、返信するか~……どれどれ」
アオトからのメッセージには、今日のデートに対する感謝の言葉が端的に綴られていた。
『今日は俺なんかと出掛けてくれてありがとう。今、急いで小説を書いてるから後で送る。また感想を聞かせてくれると嬉しい』
「……」
ハルカはしばらくスマホを手にしたまま返信を考える。
当初は興味本位で声をかけただけなので、LINEも他の男子と同様に適当にあしらって終わらせるつもりだったが、今の彼女にとって彼はなくてはならない存在へと昇華していた。
今日のデートだって、彼女はたまたま日曜日に予定が何もなかったから誘いを受けたに過ぎない。
一緒に協力してみようと投げかけたのも、単なる興味本位だった。もしもアオトと合わないなと思ったら関係は白紙に戻っていた。
だが、ハルカはアオトのことを少しだけ気になっていた。
だからこそ、あまりぞんざいに扱いたくないし、むしろやり取りを重ねた方が自分のためになる……ハルカはそう考えた。
現に彼女は小説を読んで着想を得たり、実体験を基にイラストを描くのが得意だったからだ。
『こちらこそありがとう! 降谷くんは意外にも男らしいというか、ちゃんとお礼とか言えるタイプで良かったよ! また明日、学校で話そうねー』
ハルカは長考した末にごくごく無難な返信をした。
お礼を返しつつも相手を適度に持ち上げて、悪い印象は抱かせないようにする。
「……既読早っ」
メッセージを送って数秒だった。
すぐさまアオトは既読をつけると、瞬く間にメッセージを返してくる。
『学校ではあまり話したくない』
「え?」
何の気なしに告げられたその言葉にハルカは思わず動揺してしまった。
もしかして、私のこと嫌い? そう思うほどに、彼女は心に疑念を渦巻かせた。彼に嫌われたらネタが尽きてしまう。ハルカ的には先ほどの新シリーズが今後バズったら定期的にネタを収集したいので、今のうちはできるだけ関わりを持っておきたい。
今の段階で関係を断たれると計画が台無しになる。
そして何よりも、ハルカは誰かに嫌われるのを1番避けたかった。
しかし、数秒後にアオトから立て続けに送られてきたメッセージは、そんな迷いあぐねる彼女の思いを良い意味で裏切ってくれる。
『恋愛小説を書いてるとかあまり知られたくないし、俺なんかが星宮みたいなやつといたら変な目で見られるからな』
「あー、そういうことね」
嫌われてないと知りある意味ほっとしたハルカはすぐさまスマホをフリックする。
『わかったよ~。じゃあ、小説ができたらLINEで送ってね! それを見て私もイラストを描いてみるから!』
『”テキストデータ 映画館編 2万文字”が送付されました』
『え!? もうできたの!?』
『たった今完成した。一回書いて慣れたからかスラスラ書けたんだよ。星宮のアドバイス通り、今日の経験を基に書いてみたから時間があるときに目を通してみてくれ。俺はもう寝る。おやすみ』
「……まだ10時前だけど、やっぱ引きこもりっぽいし外に出ると疲れちゃうのかな」
ハルカはトーク画面を見ながら呆れたように口にした。そして、おもむろに送付されてきたテキストデータを開く。
「学校では話せないし、寝るまでにこれを読んでおこうかな~」
彼女はアオトが書き上げてくれた小説に目を通してみることにしたのだった。
◇◇◇
その日、アオトが通う高校は、午後の5限目と6限目が続けて体育の授業だったのが、生憎の雨天により自由時間になっていた。
不満を垂れ流したクラスメイト達だったが、たまたま体育館に空きがあったということで、彼らは檻から抜け出す囚人かのように教室からいなくなり、教室の中は閑散としていた。
「……」
そんな中、アオトは近々控える定期テストのために黙々と勉強に励んでいた。
静かな教室にはクラスメイト達の姿はなく、外から聞こえる雨音が静かな空間に静寂を添える。
彼の動かすペンが紙に触れる音や、ページをめくる音が教室を満たしていき、時間の流れと共に、彼の思考が紙に書き記され、知識が増えていく。
しかし、アオトは隣から感じる好奇の視線に邪魔をされて、あまり勉強に集中できずにいた。
「……星宮」
アオトは問題集に目を通しながらも視線の正体であるハルカを一瞥する。
「なぁに? ムスッとした降谷くん」
対するハルカは特に気にする様子もなくのんびりとした声で返事をする。
「学校では関わるなってこの前LINEで言ったばっかだろ。早く体育館に行って遊んできたらどうだ?」
「ケチくさいこと言わないでよね~。私って実は勉強があまり得意じゃないから、こういう機会に勉強しておくのも悪くないかなーって思っただけだし」
「いやいや、全く勉強してないだろ」
アオトの見た限り、ハルカの机の上には何も乗っていない。リュックも高校二年生とは思えないペラペラ加減で、勉強には無頓着な様子が窺える。
「あはははは……まあまあ、それはいいじゃん。私は単純に降谷くんと過ごしたかっただけだから、ここにいてもいいでしょ?」
「まあ、いいけど……人が来たら離れろよ?」
「もちろん。ところでさ。昨日送ってくれた小説、読んだよ!」
話を変えたハルカは少しだけ席を前にズラしてアオトとの距離を詰めると、スマホを片手にニコニコと笑った。
「……どうだった?」
恐る恐る尋ねるアオトはペンを手放した。
その内心は以前と同じような酷評をされないか不安が宿っていた。
「はっきり言っていい?」
「ああ」
前回と同じような流れにアオトは身構えるが、結果を発表する当のハルカはなぜか楽しそうな顔つきだったので、アオトは途端に複雑な心境に駆られて訳がわからなくなっていた。
だが、そんなアオトの予見は良い意味で大きく外れることになる。
「結構面白かった」
「……まじ?」
「うん。そもそもあれだけの時間で2万文字も書き上げたっていうことに驚いてるんだけど、降谷くんってもしかして天才なのかな?」
「んー、いや、ただ俺は感じた事を文章に起こしただけなんだけど……そっか、面白かったか。くくくく……なんか嬉しいな」
想像とは違うハルカからの好評価に対して、アオトは自分でも珍しいと思うくらい不敵な笑みをこぼしてしまった。
彼は素直に喜びを噛み締めていた。先日は酷評とは言わずとも長々と厳しい意見に晒されたので、こんな風に良い評価を受けるのは当然心が躍る。
「笑い方が不審者みたいだね」
「うるせぇ」
アオトはハルカから目を逸らすとぶっきらぼうに言葉を吐き捨てたが、その表情は柔和で怒りなどの感情は一切見受けられなかった。それくらい、今のアオトは心が満ち足りていた。
「まあまあ、それはそれとしてさ……降谷くん」
僅かに開かれた窓の隙間から湿っぽい風が流れてくると同時に、ハルカは一つ咳払いをしてアオトの名前を呼ぶ。
「何だ?」
「前見せてくれた小説はリアリティが無さすぎるって話をしたと思うんだけど、今回の小説は妙にリアリティがありすぎて、読んでる私の方が恥ずかしくなっちゃったんだよね。もしかしなくても、ヒロインの子って私がモデルだったりするのかな? すっごく魅力的に書いてくれてたから気になっちゃってさ~」
ハルカは真剣な顔つきでアオトの目を見て尋ねた。
そんな彼女の姿を初めて見て怒らせてしまったと勝手に勘違いしたアオトは、少し驚いた顔になったが、すぐに頭を下げて謝辞を述べる。
付き合いは短いが、最低限の礼儀を欠いてしまったと彼は感じていた。
「……悪い。モデルも何も、星宮をそのまま使わせてもらった。嫌なら全く別のヒロインに変えさせてもらうが……」
「ううん。それは別にいいんだ。ただ、私の容姿とか……その、香りとか? 一つ一つの行動とか表情とか、事細かに書かれていたから気になっちゃって。なんか恥ずかしいなぁ、って。別に怒ってるわけじゃないからね!?」
「そうなのか?」
「うん。それとはまた違うけど、デートの内容がそのままストーリーになってたから良いなぁって思っただけだよ! 見る人によっては私たちがデートしたってバレちゃうかもね?」
「……俺の小説なんて星宮以外に読んでくれないから大丈夫だよ」
ハルカが怒っていたわけではないと理解したアオトは瞳を閉じて胸を撫で下ろした。彼は彼女という最も身近な異性を等身大のままヒロインの席に据えていたので、小説を見せてしまえばこうなる展開は予測できていた。
しかし、彼は自身にまともな恋愛経験がなくて、異性とのデートは昨日が初めてだったので、こうする他なかったというのが正直なところなのである。
また、同じく恋愛経験がないと言っていたハルカなら許してくれるなんていう期待もしていた。
「後もう1つ!」
「あー、今度は何だ?」
「降谷くんって私のこと好きなの?」
ハルカは先の質問に続きまたも素っ頓狂なことを聞いてくる。
「はぁ? 急に何だよ?」
もちろんアオトは呆れた顔つきになり聞き返すが、ハルカは首を傾げて不思議そうな面持ちになるだけだ。
「だって、ヒロインが私ならその相手は降谷くんってことになるでしょ? 私のことを想うような描写もあったし、リアリティを求めるならそれってそういうことでしょ? でも、ごめんなさい。さすがに恋人にはなれないかなぁ~」
ハルカは両手を合わせて可愛らしく舌を出して笑みを見せた。冗談混じりのようにも聞こえるが、アオトからすればこんな振られ方をされて溜まったもんじゃなかった。
「……そうですか」
反論をする間も与えられることなく勝手に振られてしまったので、アオトは何も言葉を返すことなく一つ息を吐く。
彼女もまた完全な冗談で言っていたのか、呆れるアオトのことを見て口角を上げていた。
それから、二人の間にはしばしの沈黙が訪れた。
別に気まずいような様子はない。
ただ、やはりまだ親しい間柄ではないためか、えも言えぬ妙な空気感になってしまい、アオトは痺れを切らして口を開く。
「そういえば、星宮はイラストを描いてくれたのか?」
「まだまだだよ。小説を読み合えたのだって昨日の寝る前だし、もう少し時間が欲しいかな?」
筆の早いアオトとは違い、ハルカはそんなに作業効率が良い方ではなかったようだ。彼からすれば文字を書くのと絵を描くのとでは全く別物だということも理解していた。
そもそも美しいイラストを描くにはそれなりの時間が必要だということである。
「そうか。で、勉強の方は? 定期テスト、もう再来週だろ?」
「うっ……ま、まあ、何とかなるよ! 目指せ赤点回避!」
ハルカは苦虫を噛み潰したような表情を浮かべて、力のこもっていないガッツポーズを見せた。
「赤点回避って……随分と目標が低いんだな」
アオトとハルカが通う高校はごく普通の公立高校で、赤点のボーダーは30点となる。下回ると放課後は補習を命じられ、補習後の再テストに落ちたら再補習。さらにその後行われる再々テストに落ちたら……という形だ。
「仕方ないじゃん。勉強嫌いなんだもん」
「留年するぞ?」
「正直、かなり危ないかも」
アオトは冗談で留年の話をちらつかせたのだが、ハルカがマジな顔で危険を予期させるものだから驚いてしまった。
「は? じゃあ勉強しないとまずいだろ」
「うん。だから、こうして皆と遊ばないで教室に残ってるんだよ」
「雑談ばっかで何もしてないけどな」
かくいうアオトも、ハルカと雑談を始めてから一切勉強に手をつけていないので人のことは全く言えないのだが、彼からすれば赤点を取るなんて常識外の力技をしないと不可能な行為だった。それ故に、特に危機感を抱いてはいなかった。
むしろ、アオトは入学から今に至るまで全てのテストで学年トップ10入りを果たしているので、今回のテストだって別に問題はないレベルなのだ。
「まあね~、だから降谷くんにお願いがあるの」
「……嫌な予感がする」
多分、この流れはアレだな……と、アオトは確信めいた察しがついていた。
「勉強教えてくれない?」
「嫌だ」
案の定と言うべきか、ハルカが手のひらを擦り合わせて頼み込んできたので、アオトは両腕をクロスさせてバツを作り即答した。
「えー、なんで?」
「俺だって自分の勉強もしないといけないから忙しいんだよ」
「ふーん、私が赤点を取って補習することが決まったら放課後とか土日休みに遊びに行けなくなるけど、それでもいいんだ? そうしたらイラストも描けなくなるし、コンテストなんて夢のまた夢だよ?」
「……星宮、お前小賢しいな」
にたにたと笑っているハルカのしたり顔を見たアオトは背中を丸めて頭を抱えた。
「降谷くんってあまり乗り気じゃない感じ出してたけど、実は結構この関係を楽しんでるでしょ? 私といても苦じゃないでしょ? なら、私に勉強を教えたほうがお互いの為になると思うんだけどなぁ~……どうかな?」
ハルカは人の懐に入り込むのが上手くて愛嬌があるので、うるうるとした瞳で懇願されては真面目で意志の固いアオトも中々断りにくい。
「……わかった、わかったよ。今回だけだぞ」
「ありがとっ! 私も頑張るから! それに、放課後の勉強会って青春っぽいでしょ? そういうのも恋愛小説の醍醐味だと思わない?」
「確かに……そう言われてみると、なんかやる気出てきたわ」
アオトは顎に手を当てて考えた。彼女の言う通り、恋愛小説の舞台は別に校外だけに限った話ではない。むしろ、校内で起きる何らかのイベントを通して得られる経験も多数あるはずだ……アオトは口角を上げて首を縦に振る。
「でしょ? ってことで、今日の放課後は図書室に集合ね」
「はいよ」
アオトが端的に返事をするのとほぼ同時のことだった。
五限目の終了を告げるチャイムが鳴る。
「あ、終わった」
ハルカは時計を見ると、体を伸ばしてリラックスしながら席を立ち、教室の外へ向かって歩みを進める。
「じゃあ、私は体育館で遊んでくるから、放課後はよろしく~」
ハルカは小さく手を振りながら教室を後にした。
一人取り残されたアオトは、すっかり雨が止んで晴天となった空模様を眺めた。
「……やるか」
アオトは完全な静寂に包まれた教室の中で1人呟いた。
「星宮のために全教科のテスト範囲を改めて確認しておくか」
アオトはペンを手に取ると、分厚いリュックサックの中からいくつもの教科書と資料集を取り出し、付箋を貼ったページを捲りテスト範囲の確認作業を始めたのだった。
これまでの経験を基に、出題されそうな傾向を頭の中にインプットし、それらをノートに書き記していく。
今からハルカに全てを学習してもらうのは不可能なので、確実に30点以上取れる用に効率重視で勉強を進めることにした。
「頑張るぞ」
アオトはハルカと雑談を重ねたことで気が紛れて集中力が高まったのか、スラスラとペンを動かし続けて、気がつけば放課後を迎えていた。
どうやら、六限終了後のホームルームは無いらしく、各々が教室に荷物を取りに来て適当に解散していた。
アオトもその人混みに紛れて教室を後にすると、ハルカとの約束通り図書室へと向かったのだった。
◇◇◇
しんとした静寂に包まれる図書室内は、テストを間近に控える生徒たちが詰めかけているということもあり、普段よりも一層ピリッときた空気感が漂っていた。
そんな図書室の一角で、アオトとハルカは二人掛けの席で向かい合いながら勉強に励んでいた。
「……降谷くん」
ハルカは真剣な様子で問題を解き続けるアオトの指をペンで突いた。
「なんだ、星宮」
「ここ、わかんないから教えて?」
「理解しようとするな。丸ごと暗記しろって言っただろ?」
ハルカは可愛らしく両手を合わせてウインクまでしていたが、当のアオトは一瞥もせずに手を動かし続けていた。
「……本当にそのやり方で大丈夫なの?」
「ああ。本当は理解した方がいいんだが、正直言って今の星宮の頭じゃテストまで間に合わないのが目に見えてるからな。赤点回避の最短ルートは全教科を必死に暗記することだ」
アオトは尚も手を止めることなく、目の前の問題への集中力を切らさない。
二人が図書室にやってきてまだ30分ほどしか経過していなかったが、実はハルカの集中力は既に底をつきかけていた。
「……馬鹿にされてるけど、事実だよね。でも、数学はもちろん理解が必要だよね? 間に合うかな?」
「はぁぁぁ……数学は暗記だ」
不安そうに確認してきたハルカのことを尻目に、アオトは大きな溜め息と共に言葉を吐いた。
「じゃあ国語は?」
「それも、暗記だ」
「理科は?」
「無論、暗記だ」
「副教科の家庭科と保健は?」
「もちろん、暗記だ」
「じゃ、じゃあ、英語は?」
「暗記に決まってるだろ」
「もう! 暗記しかないじゃない!」
暗記暗記暗記暗記暗記。まるで、初めて言葉を覚えた赤ん坊のようにテンポ良く連呼するアオトに対して、ハルカはついに堪忍袋の尾を切らして声を大にした。
その瞬間に周囲で勉強に集中している生徒たちが驚いた表情で二人に視線を浴びせてくる。
まるで街中でバカップルを見かけた時のような冷ややかな視線だった。
「ご、ごめんなさぁ~い……」
ハルカはいたたまれない様子で肩をすくめると、小さな声で申し訳なさそうに口を開いた。
「……とにかく、最初は暗記だけでいいんだよ。ここが今の星宮の位置だとしたら、目指すのは赤点ボーダーよりも少し上の辺りになる。そこに到達するためには、星宮の得て不得手なんて関係なく、どの教科も高配点となるポイントを抑えて全て暗記するんだ。テスト範囲は事前に出てるし、中心となる部分も明確だから対策はしやすい。理解は別にその後でいい」
アオトは小さく咳払いをして空気を一変させると、いつの間にやらノートに書き記していた分布図をハルカに向けて見せる。
口頭で今のハルカの立ち位置と目指す位置を指し示しながら、簡潔かつ丁寧に説明した。
最後にシャーペンを手に持ち、先端をハルカに向けて最終確認をする。
「ここまでわかるか?」
「……」
ハルカは向けられたシャーペンの先端から目を逸らし身を震わせていた。呼吸が荒くなり、目の焦点は合っていない。
「星宮? どうした?」
アオトはシャーペンを下ろして尋ねた。
すると、ハルカはハッと我を取り戻し、胸に手を当てて呼吸を整える。
まるで夢の中にトリップしていたようだった。
「あ、ご、ごめん……ちょっと、あんまり尖った物とか向けられるの得意じゃなくて……」
「悪い。先端恐怖症だったんだな。配慮が足りなかった」
アオトは素直に頭を下げた。
映画館では確か狭い場所が苦手と言っていた記憶も残っており、更には先端恐怖症とのことで、ハルカの苦手なものを頭の中に刻んでおく。
「……そういうわけではないんだけど……とにかく、本当にさっきの方法だけで点なんて取れるの? ぶっちゃけ私って結構なお馬鹿さんだよ?」
先端恐怖症ではない……が、尖ったものが苦手という意味だろうか。
アオトには深く意味がわからなかったが、ハルカはすっかり平静を取り戻していた。
慣れているのか、既にケロッとしている。
「星宮がどのくらいの頭の良さなのかはよく知ってる。前回のテストのクラス順位は30人中28位でほぼ最下位だったか? しっかり補修組の真ん中の席に座ってたもんな」
ハルカが勉強を苦手にしていることなど、アオトからすれば当然のように知っていた。
というのも、彼はテスト終わりに発表される学年順位とクラス順位を入念にチェックしているからだ。
それもこれも、指定校推薦を使って大学に行くために、今の自分の立ち位置を把握しながら勉強しているからである。
「うぅっ……ちなみに、降谷くんは何位だったの?」
ハルカは半べそをかいて泣くふりをしながらアオトに聞いた。
「クラス順位は2位だったな。1位のヤツはうちの高校から東大を目指しているみたいだし、努力の差を考えれば当然の結果だな」
「ふーん……凄いねぇ」
アオトが堅物で結構真面目なタイプだということはハルカも知っていたが、まさか彼がクラスで2番目の秀才だとは思っていなかった。
「まあ、話は戻るが、うちはごくごく普通の公立高校だから、授業で使った教科書や問題集に載ってる問題をそのまま転記するなんてザラだ。暗記すれば30点くらい簡単に超えられるようにできてるんだよ。だから……まあ、テストまではちょっとだけ頑張ろうぜ?」
アオトは感嘆するハルカを一瞥してから再びノートに視線を移した。
全く慣れてないのがわかるぶっきらぼうなエールだったが、それは目の前のハルカの心に確実に浸透していた。
「……うん、わかった。赤点取っちゃったらコンテストに応募できなくなるし、頑張ってみるね!」
「静かに」
「あ、ごめん」
思わず大きな声出しながらガッツポーズをしてしまったハルカだったが、冷静沈着なアオトに咎められると、彼女はわざとらしくしゅんと縮こまって瞳を伏せている。
そんな彼女の姿をチラリと見たアオトは僅かに口角をあげると、一人で勉強していたこれまでよりも少しだけ気分が晴れやかなことに気がついた。
他人に勉強を教えながら自分の勉強も進めていく不安が多少なりともあったが、この分なら大丈夫そうだな。アオトは心の中で安心したのだった。
彼女なら一人でも勉強できるだろう。
「星宮」
「なぁに~?」
アオトに名前を呼ばれたハルカは、可愛らしく伸びのある声で返事をした。
「昨日もLINEで伝えたと思うが、校内で一緒に過ごすのは遠慮させてもらう。今日はこのまま付き合うが、明日からは一人で勉強してくれ。もしもわからない箇所があったら、都度LINEで聞いてほしい。それで大丈夫か?」
「うーん……私は別に降谷くんと過ごしてもそんなデメリットなんてないんだけど、まあ、降谷くんがそう言うなら仕方ないよね」
ハルカはそんな些細なことなんて特に気にしていないのだが、不器用ながら気遣いのできるアオトだからこそこういった提案をしたのだろうと理解を示した。
「悪いな」
「ううん。でも、やっぱり降谷くんと一緒に勉強したいなぁ~」
「……」
ハルカが懇願するような視線をぶつけてきたので、アオトはふっと目を逸らして口をつぐんだ。
すると、彼女は何か思いついたのか、おもむろに口を開く。
「ねぇ、降谷くんは学校だと目立っちゃうから嫌なんだもんね?」
「ん? まあ、そうだな」
アオトは周囲に視線を這わせながら相槌を打つ。閑散とした教室ならまだしも、できればテスト前の図書室のようなそこそこ人が多い場所は避けたいと思っていた。運良く、周りにはクラスメイトや見知った人物はいなさそうだが、星宮の容姿は秀でているので目立つのは免れない。
「ふーん」
「にやにやしてどうしたんだ」
「学校以外の場所で勉強しない? って提案だったんだけど……どうかな?」
ハルカはペンを転がして机に両肘をつき顎のあたりに手をやると、可愛らしく首を傾げてジッとアオトに視線を向けた。あざとさもあるが、鈍感なアオトはそれに気づかない。
「となると、市営の図書館辺りか? 学校からは少し遠いし、放課後になってから向かうにしても時間が勿体無いぞ」
アオトは何やら企んでいそうなハルカから目を逸らして考えた。カフェに行くにしても、学校の近くにはゆっくりできそうな感じの店はない。おまけに図書館以外の市の施設は体育館くらいしか思いつかないので、学校の外で勉強するのは中々至難だった。
「いい場所があるよ?」
「どこだ?」
「降谷くんの家」
「はぁ?」
「ご両親は共働き?」
アオトは口をあんぐりと開けていたが、彼の反応を見て微笑んだハルカは彼に質問をぶつけていく。
「……ああ、いつも八時くらいに帰ってくる」
「ぴったりだね。兄弟はいるの?」
「……1人っ子だ」
「ぴったりだね。私、犬と猫のアレルギー持ちなんだけどペットは飼ってる?」
「……飼ってない」
「ぴったりだね。じゃあ、明日からテストまでは放課後の時間を使って家にお邪魔するね。用事があったら行けないけど、そういう時はLINEするから安心してね」
ハルカはまるで魚の追い込み漁のような手口でアオトの選択肢を限定させていくと、最後はしたり顔で満面の笑みをこぼしていた。
「……え? もう決まったのか?」
アオトは呆然としたまま口を開く。
「うん。だって、1人で勉強しろーって言われても、私、自信ないし……単純な暗記はもちろんするけど、少しでも良い点取ってコンテストに備えたいから今回のテストは頑張ることにしたんだ。だから、降谷くんも協力してくれると嬉しいかな、ってね?」
「……仕方ないか」
アオトは留年間近のハルカのやる気を無碍にすることはできなかった。
彼の家は高校からは程近く、徒歩で数10分の距離だったので、距離を言い訳に断ることもできなかった。
「やったぁ! じゃあ、今日はここで頑張って、明日はそっちにお邪魔するね。一緒に帰ったら怪しまれるから、時間を置いてから家に行ったほうがいいよね?」
「んー、そうだな。住所は後で送っとくよ」
アオトは未だにクラスメイトの異性を易々と家にあげるのは……と心の中で葛藤していたが、すっかり乗り気なハルカに押されて気付けば快諾し話が進んでいた。
まあ、勉強するだけだし場所は学校以外であればどこでもいいか。アオトは自分にそう言い聞かせることにする。
「わぁぁ……楽しみ! やっぱり男の子ってベッドの下にえっちな本とか隠してたりするの? 変なことしたら即通報するけどおかしな妄想とかしてない? 大丈夫?」
「……エロ本は持ってないし、変なこともしないから安心してくれ。むしろ、俺は自由奔放な星宮に家を荒らされないか心配だ。ちゃんと勉強しなかったら追い出すからな?」
ワクワクと狂気を混同させたハルカの発言に戦慄しつつも、アオトはアオトで譲れない条件を課す。
「うん。降谷くんは私の想像以上に人想いというか、接しやすいから、私も期待に応えられるように勉強するね」
ハルカは意志のこもった澱みのない真っ直ぐな表情に変わると、自ら進んでペンを取って勉強を再開した。
それからは特に無駄なお喋りを挟むことなく、今日のところはアオトに言われた通りに暗記に集中し、気がつけば下校の時刻になっていた。
アオトは教室に忘れ物をしたということで、ハルカとは図書室の前で解散して1人で教室へ戻ることになったのだった。
◇◇◇◇
図書室にて開催されたハルカとの勉強会を終えたアオトは、忘れ物を回収するために1人で教室に足を運んでいた。
夕暮れの淡い光が差し込む教室には、当たり前だが誰の姿もない。
「えーっと……あったあった」
アオトは自分の机の中から保護者宛てのお知らせの紙が入ったクリアファイルを取り出すと、そそくさとリュックの中にしまい込んだ。
それと同時に教室の扉が勢いよく開かれた。
「——ん? おお、アオトじゃん。こんな時間まで勉強かよ?」
夕暮れを後光代わりに教室に入ってきたのは、アオトの数少ない友人である佐山だった。クラスは違うが、アオトとは幼馴染なのでそれなりに親しい間柄である。
そんな佐山は泥だらけのユニフォーム姿で、その表情は疲労に満ちている。
「佐山こそ、テスト前だってのに部活か? 相変わらず熱心だな」
「新しい外部コーチが鬼でよ、来週の月曜からテスト期間で休みだってのに今週末は練習試合もあるし……もう勉強なんて微塵もできてねぇから最悪だよ。俺が留年したらアオトも道連れだからな?」
佐山は呆れたような楽しいような、どこか複雑そうな表情で天を仰いでいた。
同性のアオトから見ても彼は爽やかなイケメンの部類に入るので、アンニュイな表情をしてもどこか様になる。
「道連れは遠慮願いたいが、お前も中々大変そうだな。留年したら洒落にならんからちゃんと勉強しろよ?」
「おう。それより、今日の放課後の図書室で星宮さんと黒髪の地味めな男が勉強してたって噂になってたぜ。それアオトのことだろ? なんだ、もしかして付き合ってんのか?」
「いや、別にそういうわけじゃない。たまたま一緒の席になっただけだよ。そもそも俺と彼女じゃ釣り合わないだろ?」
アオトは溜め息混じりに弁明する。
案の定というべきか、図書室の誰かが噂を広めたらしく、つい数十分前の話だというのになぜか部活中しだったはずの佐山の耳にまで情報が入っていた。
「俺は別にそんなことねぇと思うけどな。ちなみに、うちの西園寺先輩が星宮さんのことを狙ってるって噂もあるし、星宮さんはかなりの人気株だからなぁ。このまま取られたんじゃ絶対に後悔するぜ?」
「だから、俺と星宮はそんな関係じゃないって」
アオトは佐山からニヤつきながら茶化すような言い方をされているが、ハルカがなんでもない人から好意を向けられるのを嫌がっているのをよく知っているので、噂の真意についてはキッパリと否定した。
「そうか? 俺はサッカー部では生粋のベンチウォーマーだけど、その代わりに色んなゴシップを懐で温めてるんだぜ?」
「上手いことを言ったつもりかもしれないけど情けないぞ、それ。というか、お前が何と言おうと俺と星宮はそんな関係じゃないからな」
「んだよー、アオトは帰宅部で暇なんだからもっと恋愛しろよなー」
「はいはい、それよりお前はどうなんだ? 浮いた話はないのか?」
「よくぞ聞いてくれた! 俺は、ビッグでボインな大学生のお姉さんが好みなんだ。だから、大学に行ったら本気出すんだ! 高校生に興味はないッ! 俺は他の奴らとは違って星宮さんにはあまりそそられないぞ! なんか裏がありそうだし、たまに見せる真顔がちょっとだけ怖い!」
佐山は嬉しそうな面持ちで自分語りを始めると、メラメラと瞳の奥を燃やして拳を握り込んだ。
彼もハルカと同じく確実にモテる部類に入るのだが、好みが年上のお姉さんに限定されるので、同級生や一つ、二つ上の先輩、年下の後輩等の手が届く近い年齢からの告白は全て即答で断っている。
仲の良いアオトはもちろんそれを知っていて、そんな佐山に恋愛小説なんて見せても理解を示してくれないこともよくわかっていた。
だからこそ、彼にそれを打ち明けて共感を得られず終了する前に、ハルカと意気投合できたのは幸運だった。
「そこまで言うってことは、佐山からすれば星宮は完全な恋愛対象外なのか?」
「まあな。というか、周りはチヤホヤしてるけどよ、俺からすれば底が知れねぇっていうか……難しいんだけど、よくわからねぇんだよなぁ。言い方は悪いけど星宮さんって八方美人だろ? 変な噂は聞かないけど、クラスでは浮いてるお前に構うくらいには優しい感じだし、それも尚更怖いぜ。口下手で無口で俺以外と話さないアオトにわざわざ話しかけるなんて……おかしくね?」
佐山は普段とは違い、珍しく腑に落ちない曖昧な返答をした。
アオトから見ても、確かにハルカは八方美人だった。
だが、そこを疑いたくはなかった。
まだ関係をスタートさせたばかりだったが酷いことをされたわけではないし、むしろ前回のデートは悪くなかったとすら彼は思っていた。
無論、反省すべき点はあったのは事実だが。
「……そうだな」
アオトは心のうちでは反論したくなっていたが、息を呑んで言葉にするのは控えた。
「星宮さんの変な噂は全然聞かないけど……ちょびっとばかし掴みどころがない気がするってだけだ。ってことで、俺は遠慮願うぜ。お前も気をつけろよ?」
「お前は人付き合いが上手いから、そういうのを見極めるのも得意だもんな。俺的には星宮はそんなやつじゃないと思うけどな……」
アオトからした佐山は非常に明るくユーモアのある生粋の陽気者だった。だからこそ、たくさんの人と接して色んな人の内面を知っているし、アオトとは違う発想で星宮のことを評していたりする。
能天気な見た目と口調とは打って変わって、中々に食えない男なのだ。
「だといいけどよ。ちなみに、お前の好みは昔から変わらずか?」
「……昔からって?」
佐山は知ったような口ぶりでアオトに尋ねたが、当のアオトは昔と言われてもすぐにその記憶が出てこなかった。
「子供の頃に言ってただろ。背が低くて愛嬌のあるタイプが好きって。あれだろ、アオトの母ちゃんが高身長で強気な性格だから、その逆の小動物みたいな愛らしい女子が好きなんだよな?」
「確かに言ってたけど、今は分からないな。みてくれだけじゃ人の事はわからないからな」
そういえば子供の頃に女性のタイプの話をしていたなぁ……と、アオトは思い出す。
当時は子供の頃の直感的な発言だったが、そう言われてみると今も変わってないのかもしれないと思い始める。
ただ、まともな恋愛経験が1度として無いので判断しようがない。
「星宮さんはそれとは結構タイプが違うけど、愛嬌はバッチリだしチャンスがあればって感じか?」
「だから、俺と星宮はそんなんじゃねぇよ」
アオトは溜め息混じりに言葉を返すと、佐山の横を通り抜ける。
「帰るのかー?」
「帰って家事をしないといけないんだよ。お前も疲れてふらふらだろうし、気をつけて帰れよ」
「おうよ。またな~」
アオトは佐山に別れを告げて教室を後にした。
廊下を早歩きで駆け抜け、階段を小気味良いステップで駆け下りる。下駄箱では一瞬にして靴を履き替えて、真っ赤に染まりきった空を眺めながら外を歩く。
本当は勉強で頭を使って疲れたので早く家に帰りたかったのだ。
だが、まさかまさかの数少ない友人に会ってしまい、その心身は更に疲弊していた。
佐山は悪いやつじゃないのだが、基本テンションが高い根っからのスポーツマンなので、インドア気質なアオトからすれば真逆の存在だった。
とにかく、アオトは疲れていた。
——西園寺先輩だとかはどうでもいいし、星宮と俺の間には何も起こりようがない。コンテストが終わるその時までは、今の奇妙な関係を継続するつもりだが、それ以降はまだどうなるかわからない。
でも……星宮は悪いやつじゃない。むしろ、俺なんかに構ってくれる良いやつだ。だから、できることなら仲良くしたい。
アオトは一人心の中で気持ちを整理する。
「……帰ろう」
彼は疲れ切った頭を休めるために足早に帰路に就いたのだった。
◇◇◇◇
翌日の放課後。
アオトは学校からダッシュで家まで帰ると、丁寧かつ迅速に部屋の隅々まで掃除していた。
かっちりとした制服から着替えて、今は半袖短パンになっており、その上からエプロンをつけている。
これこそアオトが普段家で過ごす時の格好だった。
というのも、両親は家を出るのが早く、尚且つ帰宅も遅くて毎日忙しい日々を送っているので、こうして帰宅後の掃除や家事、炊事を担うのはアオトの役目となっていたからだ。
2階建てのごくごく普通の1軒家なので、アオト的には特に苦痛ではない。むしろ、毎日のルーティンになっており日常の一部にすっかり溶けんでいるくらいだった。
しかし、今日に限ってはハルカが来るので、いつも以上に念入りに掃除をしておく必要がある。
ある程度フランクに接することのできる相手とはいえ、アオトからしたらハルカは異性のクラスメイトだ。気分的に良い印象を持たれたいのは確かだったし、何よりも勉強のための土台作りという意味でも清潔さは大切である。
空気を循環させるために窓を開放させて換気を行い、床の乾拭きして髪の毛や埃を全て取り、リビング全体のインテリアの位置を調整する。
「……よし」
やがて、ある程度の準備を終えたアオトは息をついてソファに座る。既に帰宅してから30分ほど経過していた。
そろそろハルカが現れる頃だな……アオトがテーブルを拭きながら置き時計を見たのとほぼ同時、インターホンが鳴った。
「開いてるから勝手に入っていいぞー」
アオトは玄関先に向かいながら声をかける。
すると、ゆっくりと玄関扉が開かれて、さらりとゆらめく金髪が扉の隙間からひょこっと覗かせた。
「お邪魔しまーす」
ハルカは楽しげな様子で扉をくぐると、玄関先に立ち止まって軽く会釈をした。
そして流れのままにアオトの姿を捉えて感嘆の声を上げる。
「おー……降谷くん、いつもとイメージが違うねぇ~」
「ん? まあ、家ではこんなもんだろ」
「ギャップ萌えってやつかな? 好きになっちゃったりして?」
「バカな冗談言ってないで早く入ったらどうだ?」
「はいはぁ~い」
ハルカは言われるがままにスニーカーを脱ぐと、丁寧に揃えてからアオトの後を追った。
ラフな格好だが内面は真面目がちなアオトと、制服こそ着ているがフランクな性格のハルカ。
二人は出会って間もないのにテンポ感の良いやり取りを重ねていた。
「飲み物とお菓子を用意するから適当に座って待っててくれ」
「うん。ありがとっ」
リビングのソファに腰を下ろしたハルカは疲れを癒すようにリラックスモードになり、タックインしていたシャツを外に出していた。
キッチンに立ちながらそれを見ていたアオトは、事前に用意していたジュースをコップに注ぎ、お菓子が乗せられたトレーの上に乗せる。
「お待たせ。オレンジジュースでよかったか?」
「うーん、よくわかってるじゃん! ピカピカなリビングとふかふかのソファで味わうキンキンに冷えたオレンジジュースは最高だぁ~」
ハルカは満足そうに頷き、冷えたコップに口をつけてた。
まるで幼子のような純真無垢で柔らかい顔つきになっている。
「好きって言ってたからな。それと、チョコと適当なしょっぱい系のお菓子だ。自由につまんでくれ」
「やるね、降谷くん。相手の好みを覚えるのは恋愛において最重要ポイントなんだよ。これは大幅加点かな?」
「そりゃ良かった」
アオトは他人事のような淡白な反応だったが、内心はハルカが喜んでくれて少しだけホッとしている気持ちだった。
実は、彼は恋愛小説を書くために恋愛そのものを学ぶにあたって、ハルカとの些細な会話内容はもちろんのこと、彼女のみならず大衆女子の好みの把握など、色々とメモに残して勉強と同じくらいの学習をしていたのだ。
故に、こうして小さいながらに努力が報われたのは、彼にとっては大きな出来事だと言えよう。
「んじゃ、始めるか。わからないところがあったら都度聞いてくれ」
「うん。でも、その前に窓を開けてもらっていい?」
「別にいいけど……エアコンも効いてるし、換気ならさっきしたばかりだから大丈夫だと思うぞ? それに、隣の家とは結構近いから声が響くんだが……」
「ごめんね、どうしても窓は開けてほしいの」
「わかった」
理由はわからないが食い下がるハルカのお願いを聞き入れた。
彼は事前に喚起を済ませてエアコンの温度設定も調整していたのだが、どういうわけか彼女は窓を開けることにこだわっているらしかった。
一軒家とは言え、辺りは閑散な住宅街なので騒音の苦情が来ないことを祈る。
何らかの要因があってハルカが悲鳴でもあげたら、通報されること間違いなしだ。
「じゃあ、始めようか」
アオトは現在の時刻を確認してからスタートの合図を出した。
今は午後4時を回る少し前なので、2時間近くは勉強できるだろう。あまり外が暗くなると彼女に迷惑がかかるので、良いところで切り上げて終わらせるか……アオトは頭の中でおおよそのプランを立ててからペンを握ったのだった。
それから時間が流れていき、勉強会はつつがなく進んでいった。
しかし、勉強中、ハルカは急にアオトとの距離を詰めてノートを覗き込んできたり、なぜか姿勢を低くして上目遣いで彼を見つめたり……他にも色々と謎めいた活発さを見せていた。
そこでアオトは考えた。
——もしかして……星宮が色んな男から言い寄られてモテモテなのは、こういうあざとくて勘違いさせる仕草が原因なのでは?
だとすれば俺も危ない。ここで星宮サイドに転げ落ちてしまったら、満を持して想いを伝えた挙句に振られてしまうのは明白だ。
二人きりの勉強会を通して、勉強をしつつも恋愛小説のアイディアを得たいアオトだったが、一旦は恋愛小説のことなど考えずに勉強に集中することにした。
やがて、約2時間が経過した。
「あーーーーーーー、疲れた!」
午後6時前。ハルカはさながら自分の家にいるかのような体勢で、ソファの上にだらしなく寝転がっていた。
姿勢良くソファに座るアオトの太ももの手前辺りまで頭が来ており、未だ勉強を続けている彼のことを下から見上げているような格好だ。
「……終わるか」
アオトは置き時計を一瞥して時刻を確認すると、一つ息を吐いて全身の力を抜いた。本当は視界の端に映るハルカの姿が気になっていたが、あまり注視しすぎても怪しまれそうだったのであえて触れないでいた。
これまでにも彼女は怪しげな行動をしていたので、彼はそのどれもを見て見ぬふりをしてきていた。
「いやー、勉強って大変だね~」
「結構頑張ってたじゃないか。序盤はチョコばかり食べてたから心配だったけどな」
「へへへ、美味しくてついつい……」
ハルカは向きを変えて仰向けからうつ伏せになると、舌を出して茶目っ気のある笑みを浮かべた。
アオトの目からわかるくらいに気分は良さげなのか足をパタパタさせている。
「……まあ、休み休みでも続けることが大切だし、この分なら問題なさそうだな」
「うん。暗記しながら、わからないところは降谷くんに教えてもらって、それを理解に繋げる感じだったら続けられそうな気がする! それに、降谷くんも女の子と二人でお家デートなんてしちゃったんだし、良い案が浮かんだりしたんじゃない?」
「あー……そっち方面は何も考えてなかったな」
「えー、もったいないなぁ~。せっかく私が彼女っぽいアピールしてたのに! 近づいてノートを覗き込んだり、今だって恥ずかしいけど寝転がって上目遣いにしてるんだよ?」
ハルカは上体を起こしてソファの上で足を崩して女の子座りになると、不満そうな顔つきでアオトにクレームを入れた。
「……全部わざとだったのか」
アオトは勉強の合間合間で繰り出されるハルカのさりげない仕草の真意をここで理解した。
アオトからすれば、ハルカは元々ラフでそういう人だろうという認識があったので特に触れていなかったし、何ならモテモテだという話に関連して男を勘違いさせるタイプなんだと解釈していた。
「当たり前じゃん。私は誰にでもそんなことはしないし、今回のはあくまでも降谷くんの経験を培うための作戦だったんだからね? もしかして全然気づいてなかったの?」
ハルカは些か鈍感過ぎるアオトを見て驚いていたが、驚きたいのはアオトの方だった。
わざとらしく胸を張りながら体を伸ばしたり、急に距離を詰めてきたり、消しゴムを取るときに不自然に手が触れたり……アオトは策士な彼女にしてやられたと感じていた。
「全然気づかなかったし、むしろ誰にでもやってるもんだと思ってた。星宮はモテモテだって話をしてたしな。そのせいで数多の男が勘違いしたんだって考えてたな。違ったんだな」
「私は私のことを分かってくれる人しか選ばないからね?」
「悪女じゃないなら良かった。美人局的な腹黒い人だったらどうしようかと思ったぞ」
アオトは冗談混じり言ったのだが、目の前のハルカは少しばかり眉を上げてその言葉に反応していた。
「……全く、せっかくこっちが恥ずかしい思いをしながら頑張ったっていうのにさぁ」
唇を尖らせてぶーぶー口にするハルカは見て、アオトは大人びた見た目に反して子供らしいなと思い空笑いを浮かべる。
「悪かったな。無駄にしないように頑張って小説にするから許してくれ」
「なら許す」
「どーも」
一通りのやり取りがひと段落したその時だった。
テーブルの上に置かれた置き時計が音を鳴らし、午後6時を告げた。
「もう6時じゃん。勉強をしてるのにこんなにあっという間って思ったの初めてかも」
「それくらい必死に頑張ったってことだ」
「よく褒め上手って言われない?」
自分の努力が認められて嬉しかったのか、ハルカはニヤリと笑っていた。
「言われたことないな」
「そう?」
「ああ」
端的な返事をするアオトは校内に友達は佐山くらいしかいないので、こんなやりとりをすることすら稀有であった。
「ふーん。ちなみに、ハルカちゃんは褒めると伸びるタイプだからね? メモメモ」
「はいはい。メモメモ」
アオトはハルカが褒めて伸びるタイプだという新情報を頭の中に植え付けた。
「よろしい、じゃあ、時間も時間だし帰るね」
満足げなハルカはテーブルの上に散らかった教材をリュックの中な収納していく。
その際に一緒に自分が食べ散らかしたお菓子のゴミを片付けようとしたが、それは既にアオトの手によってまとめられていた。
「後は俺が片付けておくから大丈夫だ。まだ明るいが、気をつけるんだぞ?」
「うん、電車だけどそんなに遠くないから大丈夫だよ~」
ハルカは静かに靴を履いて玄関扉に手をかけた。
「そうか。じゃ、またな」
アオトが小さく手を振ると、ハルカも手を振り返す。玄関扉が閉まり切るその時まで。
「……楽しかったな」
アオトはリビングへ向かうと、先ほどの騒々しさとは一転して静けさの漂う空間を見て物悲しい気持ちに陥った。
彼にとっては彼女と過ごした時間は新鮮で楽しいことこの上なかった。
また明日も、明後日も……過ごせたらな、と思う。
「……よし、片付けをして夜飯の準備を始めるか」
アオトは先ほどまでの楽しい気分に浸りつつも、エプロンを締め直し、そそくさと行動を開始した。
散らかったお菓子のゴミと飲みかけのコッピを片付け、半分ほど開けられた窓を閉める。
そんなことを適当にこなしながらも、ハルカとは恋人にはなれずとも、より仲を深めていきたいと率直に感じていたのだった。
最近は毎日のように彼女とLINEでやり取りを重ねているので尚更だった。
◇◇◇◇
翌週の月曜日。
帰りのホームルームを終えたばかりの教室はいつも騒がしいが、今日に限っては普段よりも一段と騒々しかった。
というのも、今日から定期テストの1週間前になるので、全ての部活がテスト終了までは強制的に休み期間になるからだ。
だから普段は放課後の時間を部活で奪われているクラスメイトたちは、皆一様に浮き足立っておりテンションが高いのも頷ける。
しかし、落ち着いた空間を好むアオトは、そんな彼らを一瞥してからおもむろに耳にイヤホンを差し込むと、適当な流行り曲を流して自身と周りの音を完全に断絶した。
「……」
アオトはリュックを背負って席を立ち、横目でちらりとハルカの姿を確認した。
ハルカは机の周りに集まった友人たちと談笑していた。
ホームルームが終わってすぐに友人が集まってくるなんて、アオトからすれば考えられない世界だ。
曲の静かな間奏の部分を突き抜けてアオトの耳に聞こえてきたが、どうやら彼女たちは艶やかな恋バナに夢中になっていたようだった。
ハルカを中心に皆のルックスが整っているためか、クラスメイトの男子たちは彼女たちの恋バナにひそひそと聞き耳を立てている。
その中で西園寺先輩という聞き覚えのある名前も耳に入ってきたが、アオトからすれば何の関係もないので特に興味はなかった。
西園寺先輩というサッカー部のイケメンはさぞモテるのだろう……それくらいの認識だ。
1つ気になるのは、ハルカの表情があまり乗り気じゃなさそうに見えたことくらいだったが、アオトは特に深く考えることなく教室を後にした。
向かう先は下駄箱。目的は早期の帰宅。
彼は足早に外へ出ると、スマホを確認しながら歩みを進める。
「……今日も来るのかな」
アオトは歩きスマホをしながらハルカからの連絡を待つ。
先週、彼女は火曜日から始まり金曜日まで、毎日欠かさずアオトの家に入り浸っていた。土日は自分の家で勉強すると言って来なかったのだが、それを抜きにしても2人はほとんどの時間を一緒に過ごしていることになる。
だからこそ、アオトはどうせ今日もひょっこり現れて、一緒に夕暮れまで勉強するのだろうと考えていた。
しかし、いつもなら来るはずの連絡が一向に来ない。
「……どうしたんだろう」
不思議に思ったアオトは、頭を整理させるために近くの公園に立ち寄りベンチに腰を下ろす。
一度はこちらからメッセージを送ってみようかとも考えていたが、どこか気恥ずかしくなりトーク画面を開いたまま何もできずにいた。
「んー……困ったなぁ」
そそくさと帰宅しても良かったのだが、やはりどこか気がかりだった。というより、アオトは嫌な予感がしていた。
ただ、こちらからアクションを起こすのは……と、胸中では葛藤を繰り広げるしかない。
やむなく、アオトは画面をそのままにスマホを隣に置くと、気を紛らわせるために公園に目をやった。
公園では子供達が遊んでいた。
男の子3人が、キャッキャッと純真な笑顔を浮かべてはしゃいでおり、彼は懐かしさに胸を満たされる。
なぜなら、ここはアオトも子供の頃に遊びにきたことがあったからだ。
当時は5歳にも満たない子供だったが、楽しい記憶というのはいつでも覚えていた。
特に、今座っているベンチもそうだし、反対側の滑り台と隣のブランコの辺りでよく集まっていた。
「……懐かしいなぁ」
アオトは気を紛らわせることに成功し、リラックスした体勢で天を仰ぐ。
しかし、やはり視線はスマホへと向いてしまう。
改めてハルカとのトーク画面を見て不思議に思うと同時に、彼女の身に何かあったのだろうかと少し心配になる。
「あ、来た」
その最中、少しの不安を胸にじっくりとトーク画面を眺めていると、ようやくハルカからメッセージが送られてきた。
『今日は行けない! 急に先輩と遊ぶことになっちゃった! ごめんね~』
ハルカは可愛らしい猫のスタンプと共にメッセージを送信してきた。
ちょうどトーク画面を開いていたアオトはすぐに返信すふ。
『了解』
アオトは端的に返信してからスマホをポケットにしまう。
彼はからすれば、家に来ないなら来ないでそれは別に構わなかった。ただ、約束をしていたからこそ一言くらい連絡が欲しかっただけだった。
ここ最近はハルカが入り浸っていたから尚更だ。
ルーティンとまではいかないが、毎日のように2人で勉強をしていたし、彼自身もそろそろ一人で息抜きをしたいと考えていたので都合が良い。
なので、今日くらいは小説を執筆することに決めた。
勉強会を通して映画の時とはまた違う知見を得ることもできたので、アオトはそれなりに気合が入っているのだ。
「帰ろう」
アオトはおもむろに立ち上がると、目一杯体を伸ばしてから公園を後にしたのだが、前方に見知った後ろ姿を発見したことで溜め息が溢れる。
重力に逆らってツンツンした黒髪で中肉中背の男子は、アオトと同じ高校の制服を着用しており、大きく捲られた腕はこんがりと日焼けしている。
「佐山、お前電柱に隠れて何してんだ?」
「し、しーーーっ! 静かに!」
アオトに声をかけられた佐山はあからさまに取り乱していた。ストーカーに見間違われそうなほど、かなり怪しい挙動である。
「何してんだよ」
「ほら、あれを見ろ」
佐山は不思議そうにしているアオトの肩を右手で力強く抱き寄せると、コソコソと小さな声で前方の人混みを指差した。
「ん? あれは……」
アオトは目を細めて佐山が指差す方向を凝視すると、そこには見知った金髪のボブカットの女子生徒と、その隣には高身長で茶髪の男子生徒が並んで歩いていた。
アオトは金髪のボブカットの女子生徒がハルカであることにすぐに気づいていた。
「俺の言ってた通りだったろ? 西園寺先輩は部活の休み期間を使って星宮さんを落とす気なんだよ。たった1週間しかないのにだぜ。考えられるか?」
佐山は子供のようなイタズラな笑みを浮かべて楽しそうにしていた。陽気でひょうきんな彼は昔のまま性格が変わっていないのだなと、アオトは変なところで安心した。
「だから今日は来れなかったのか」
「何の話だ?」
「いやなんでもない。それより、あれが西園寺先輩か?」
アオトはハルカが今日の勉強会に来なかった理由を察したが、佐山には適当に誤魔化して話を逸らした。
「おうよ。我がサッカー部の不動のエースにして、バリバリのイケメンだぜ。どっかの国のハーフだからか、顔は整ってるし身長も高くて運動神経抜群だ。おまけに頭も良いときた! 家柄も良くて大企業の御曹司って言ってたぞ。めちゃくちゃキザでナルシストな部分もあるけど、それでも凄いだろ?」
「何でお前が自慢げに語ってんだ。凄いのは西園寺先輩だろ」
「まあまあ、俺もある意味あの人に一目置いてんだからいいだろ? それより、どう思う?」
「何が?」
「星宮さんと西園寺先輩だよ。付き合うと思うか?」
佐山はニヤニヤしながらアオトに問いかけた。
正直、アオトとしてはハルカの性格からしてああいったタイプには靡かなさそうだと思っていたが、ここから見る限り西園寺は確かに優れた容姿だとわかる。故に、ハルカがそちらに転んでもおかしくはないのではと考え始めた。
「……どうだろうな」
アオトは適当に答えを濁して、ハルカと西園寺の行方を目で追った。
ハルカは肩を縮こまらせて遠慮がちに歩いているが、隣の西園寺は少々強引に彼女との距離を詰めているように見えた。
ハルカのことを少しは知っているアオト視点だと、あれはハルカが嫌がっているようにしか見えないが、見る人によっては照れくさそうにしている彼女とグイグイ攻める彼氏のような感じもする。
アオトはそんな二人の後ろ姿を眺めながら心の中で分析していると、突如として西園寺がハルカの手首を握ってズカズカと歩いて行った。
「おっ、カラオケに入ったぞ! 俺たちも行くぞ!」
「ちょ、おい!」
行動の早い佐山はさながら西園寺のようにアオトの手首を握ると、サッカー部で鍛えたステップワークを生かして即座に駆け出した。ベンチウォーマーのくせに足だけは速い。
アオトは強引な力の差に抗う術がなく、のこのこのカラオケ店に引きずりこまれていき、気がつけば佐山と2人きりで個室の中にいた。
「……で、何で2人についてきたんだよ。しかも運良く隣の部屋だし」
少々タバコ臭いカラオケの個室で、アオトが溜め息混じりに口を開く。
「へへへへへ、良いじゃねぇか。他人の色恋沙汰に俺が目がないのはよく知ってんだろ?」
「まあな。よく知ってるよ。幼稚園の頃からゴシップ好きだったもんな。で、色恋沙汰ってことは、やっぱりお前の言っていた噂通り、西園寺先輩は星宮を狙ってたのか?」
アオトは悪どい笑みを浮かべる佐山に尋ねた。
少なからずハルカとは交友を深めたつもりだったので、興味がないふりをしつつもやはり少しは気になるのだ。
「おうよ。こうして俺が2人をつけていたのもそれが理由さ。帰ってゲームでもしようとしたら、校門で星宮さんが1人でいるところを見かけてよ。星宮さんは人気者だから普段は誰かと一緒にいるのにおかしいなぁって思ってたら、そこに西園寺先輩が現れたんだよ。なんでも、星宮さんの友達がけしかかて、無理やりデートの予定を作ったらしいぜ? 美男美女だからお似合いだよなぁ~」
佐山はなぜかマイクを片手にエコーのかかった声を響かせながら教えてくれた。
長々としながらもここに至るまでの経緯が簡潔にまとめられており、それを聞いたアオトはすぐに話の大まかな流れを理解した。
「ふーん……だから星宮は教室で恋バナをしてたのか」
「そうなのか?」
「ああ。友達と楽しそうに話してたな。星宮はちょっと嫌そうな顔だった気がするけど」
アオトは帰り際に横目で見たハルカの苦々しい表情を思い出した。
普段はハキハキしている彼女にしては珍しく戸惑っていたような感じだった。
「へー、そりゃぁ意外だな。もしかしてあんまり西園寺先輩がタイプじゃないとか?」
「わからん。でも、最初は興味がなくても後から好きになるパターンかもな」
「そうだなー……ってか、隣の部屋なのに全く音が聞こえなくないか?」
佐山はマイクを置いてハルカと西園寺が入室した部屋の方向の壁に耳を当てると、目を閉じて不思議そうな表情を浮かべた。
「いや……何か聞こえるぞ」
アオトは佐山に続いて壁に耳を当ててみると、薄らと何かが聞こえてきた。だがそれは音楽や歌声ではない。
「……これ、西園寺先輩の声だな。なんか激しく叫んでないか?」
「まさか……」
アオトと佐山は互いに目を合わせると、最悪の展開を想定して息を呑む。
「なんか、嫌な予感がするぜ。西園寺先輩はそんな人じゃねぇって信じたいけど、相手は非力な女の子だからな……一緒に来てくれるか?」
「ああ。もとよりそのつもりだ」
「行くぞ!」
「おう!」
2人は勢いよく部屋を飛び出すと、左手側のハルカと西園寺がいる部屋へ向かい扉の前に密着して耳を澄ませた。
すると、妙な声が聞こえてくる。
「——フッ! ハッ! ハハァッ! どうだい? 子猫ちゃん、僕の美しい裸体は!」
「も、もうやめてください……」
アオトの耳に聞こえてくるのは、西園寺であろう気合の入った元気な声と、力の抜けたハルカの声。
途端にアオトは身の毛がよだち、更に嫌な想像をしてしまった。
しかし、横に立つ佐山は先んじてドアのガラス窓から部屋の中の様子を覗き見ており、呆れたように頬を掻いてニヤけていた。
「アオト、どうやら俺たちはおかしな勘違いをしちまったらしい。ほら、ガラス窓から覗いてみろ」
「……あー……なーんか、気持ち悪いポーズを取ってるな。西園寺先輩ってキザなナルシストなんだっけ?」
アオトは佐山に言われるがままにガラス窓から部屋の中を覗いたが、すぐに後悔することになった。
なんと、部屋の中では靴を脱いで席に立つボクサーパンツの大男が数多のポーズを決めていたのだから。
何を隠そう、大男の正体は西園寺である。彼は一室の照明をパーティー仕様にすることで、サッカー部で鍛えた肉体美をこれでもかと言わんばかりに魅せていた。
「言葉は悪いが、言い換えるなら変態だ。それも極度のな。部活終わりはたまにこういうトチ狂った事をやることはあるんだけど、まさか星宮さん相手にやるとはなぁ……アオトは信じてくれないかもしれないけどよ、あの人、普段の性格は温厚で良い人なんだぜ? ただちょっとタガが外れるとああなっちまうんだ。不思議だろ?」
「良い人かどうかは置いておいて、間違いなくあれは変態だ。表の顔はよく知らないけど、裏の顔があれじゃあ星宮もドン引きだろうな」
情報を持ってて見慣れているはずの佐山でさえ引くくらいだ。一対一でその姿を目に焼き付けさせられる星宮にとっては厳しい試練だろう。むしろ、拷問というべきか。
「はぁぁぁぁ……俺が突撃して西園寺先輩の気を引いておくから、アオトは星宮さんを連れて早く店の外に出ろ。さすがにかわいそーだ」
「いいのか?」
アオトからすれば西園寺には絡まれたくなかったし、できればハルカの事を助けたかったので願ってもない提案だったが、この作戦だと佐山が変態の犠牲になってしまう。
「俺は慣れてる。合宿の時はゼロ距離であの人の全裸を拝んだこともあるし、全裸で尻相撲もした。全裸で手押し相撲もした。全裸で己の武器を……おえぇぇ……っ吐き気が……んじゃ、後は頼んだぜっ——西園寺せんぱーーーーーいっ!!」
佐山は苦しげな顔つきでアオトにサムズアップを見せた次の瞬間。勢いよく扉を開いて部屋の中に転がり込んでいくと、意味不明な奇声をあげながら西園寺の名前を叫び始めた。
「佐山! 佐山ではないか! お前も僕のショーを見にきたのかね!?」
「はいっ! 西園寺先輩! 今日は踊り明かしましょう!」
「ふははっ! やはりお前は良い後輩だ! さあ、楽しいビートをかけろ! 星宮は僕の肉体を見てもノリノリにならないし、むしろ怖がっているように見えたのでな! 予定変更だ! 佐山、いくぞ!」
「お任せあれ!」
アオトは扉を僅かに開けて隙間から2人の意味不明なやりとりを見届けると、ふらふらの足取りでこちらにやってくるハルカに目配せを送る。
「……ふ、ふるやくんっ!」
ハルカは今にも倒れそうなくらい覚束ない足取りでなんとか扉を潜ると、勢いそのままにアオトの胸元へ飛び込んだ。
アオトは一瞬心臓が跳ねたが、動揺を誤魔化すように咳払いをしてやり過ごす。
「とにかく、外へ出よう」
「……うん」
アオトは元気のないハルカの体を支えながら店の外へ出た。
そして、店の近くのベンチに彼女のことを座らせると、彼は優しい声色で言葉をかける。
「星宮、大丈夫か?」
アオトは自分ができる目一杯の気遣いをした。すると、酷い目にあったであろうハルカは涙で潤んだ瞳で彼のことを見つめた。
「だいじょーぶなわけないじゃん! 私が絵が得意なこと話したら急にカラオケに連れ込まれて、一度も歌わずにずぅぅぅーーーーーーっと変なポーズを取って筋肉を見せてくるの! 最初はふざけてるのかと思って、なんですかそれ? って笑いながら聞いたら、真面目な顔つきで、僕の裸体をデッサンしろ! ですって! あれは変態! 変態! ヘ・ン・タ・イ! わかる!? もう……何をされるかわからなくてほんとに怖かったんだから……」
「……大変だったな」
アオトは相槌を打ちながら彼女の隣に腰を下ろす。
金髪を揺らしながら、語気を荒げて早口で勢いよく捲し立てるハルカの姿はかなり新鮮で、普段の彼女からは想像もつかない形相だった。
まるで、その姿が本物かのような出立ちで、吐き出される言葉には違和感はなかった。
とにかく、その吐き捨てるような強い言葉の数々にアオトは内心驚いていた。
だが、それもこれも仕方がないと言えるくらいには酷い目に遭ったのだろうと解釈する。
なぜなら、アオトは気づいていたからだ。
今の彼女の顔は明確に青ざめており、全身が小刻みに震えていることに。
「ほんっとに、毎日西園寺先輩の裸体が夢に出てきちゃうところだったよ。ああいう高圧的で強引な人は……昔からほんとにダメなの」
ハルカは頭を抱えて俯いていたが、思いの丈を吐き出したことで少しだけ落ち着きを取り戻していた。
しかし、まだ正常ではないらしく、憔悴しきったような顔つきだった。
アオトは同情する。あんな変態からダンスを見せられて、それをデッサンしろだなんて言われたら怯えるのも無理はない。
「まあ、真の救世主は佐山だから、今度会った時にでもお礼言っておけよ? 今ごろ、あいつが星宮の代わりに犠牲になってるだろうからな」
アオトは頭の中でサムズアップしている盟友を想起した。彼の犠牲があってこそ、アオトとハルカはこうして無事でいられたのだ。
「佐山くんが?」
「ああ」
「そうなんだ。知り合いなの?」
「端的に言うと俺と佐山は幼馴染だ。意外か?」
「うん。佐山くんって結構明るいタイプでしょ? 降谷くんとは割と正反対な感じだよね」
「確かにな。俺は人付き合いが苦手で見た目通り暗いタイプだから、打算なしに俺と向き合ってくれているあいつのことが好きなんだよ」
アオトからすれば今隣にいるハルカも自身と向き合ってくれる存在だと勝手に思っていたが、真っ向からそれを伝えるのは恥ずかしいので控えた。
「ふーん……一つ気になったんだけど、降谷くんって佐山くん以外に友達っていないの?」
ハルカは口元に手を当てながらアオトに尋ねる。
それは特に嫌味ったらしい言い方ではなく、単純な疑問をぶつけただけだったように彼は思えた。
「いない。昔からずっとな」
アオトは即答した。
佐山の他にも1人だけ幼馴染がいたが、その男の子はある日忽然と姿を消してしまったので行く末知らずである。
その男の子遊んだ記憶は、アオトの頭の中にたくさん眠っていた。
アオトはその男の子名前だって覚えていた。金城、人呼んで金ちゃんだ。
「今は私がいるし、いいじゃん? ね?」
「まあな……で、この後はどうする?」
アオトはハルカから恥ずかしげもなくそんなことを言われたので、ぶっきらぼうに言葉を返して話題を変えた。
ベンチから立ち上がりハルカの事を優しく見下ろす。
「この後?」
「もう精神的に参ってるんだろ? 1人で帰れるのか?」
アオトはハルカを元気つけるために普段は絶対やらないような、かなり得意げな笑みを浮かべた。
そんな彼が繰り出す予想外のユーモアに対して、彼女は意味ありげな様子で俯いて首を横に振る。
その表情はアオトには見えなかったが、きっと微笑んでいるのか頬を緩めているのだろうと勝手に推測する。
「全然ダメ……でも、今日は送ってほしいかな。なんか疲れちゃったしね。いい?」
「ああ。じゃあ、帰ろうか」
アオトはごく自然に右手を差し出した。
「……うん」
ハルカは顔を上げると、体調が悪そうな表情を浮かべながらもその手を取った。
きっと西園寺先輩のせいで疲れているのだろう……そう思ったアオトは優しく微笑みかけて彼女をエスコートした。
そんな二人の繋がれた手は、歩き出すと同時に自然と解けたが、確かに”何か”が芽生え始めていた。
◇◇◇◇
帰宅したハルカは自室のベッドで頭を抱えていた。
「はぁぁぁ……なんなのあのチャラい茶髪は。マジで無理なんだけど! こっちが話題作りのためにちょっと下手に出たら良い気になってさ!」
愚痴るハルカの表情は酷く歪んでいたが、彼女自身は気にも留めず尚も溜まっていた鬱憤を吐き出し続ける。
「まあ、今回は降谷くんが助けてくれたからよかったけどさぁ~……」
ハルカはアオトと西園寺の姿を想起するのとほぼ同時に全身に悪寒を走らせる。
彼女からすれば、西園寺と2人でデートまがいの事をしたのは、完全な話題作りの為だった。
結果的に、以前Twitterでシリーズ化して絶賛大バズり中の『根暗男子と金髪ギャル』に上手く登場させて、西園寺は引き立て役になってもらうからそれはそれで無問題だ。
しかし、思いの外キャラクター性が強いせいで心身ともに疲弊してしまい、挙げ句の果てには打算のみで付き合いを継続しているアオトが現れてしまった。
圧倒的に西園寺のことが苦手になったハルカからすれば、困り果てていた自分のことを助けてくれた彼には少なからず感謝していた。
ただ、それでも割に合わないほど、望まぬ展開の連続だったという事実に変わりはない。
ハルカは西園寺のように興味のない男と付き合うなんて死んでも嫌だった。
おまけに、西園寺は彼女が特に苦手としている高圧的で強引な俺様系の男だった。
「……やっぱり西園寺先輩はちょっと無理かも」
ハルカは助けてもらえて嬉しかったという事実と、西園寺は抱く嫌悪感という奇妙なジレンマに悩まされつつも、頭の中では新たなネタができたと少し喜んでいるのも事実だった。
「まあ、いいか。今日も投稿するネタができたし、映画デート編、勉強会編に続いて、今回が3話目のライバル出現編。今回もバズんのは既定路線かな」
ハルカは一転して楽しげな様子で自室へ戻ると、慣れたように机に向かいペンを手に取る。
初めの映画デート編はたった一晩で数百万人の目に留まることになり、いいねと新規フォロー通知が鳴り止まないほどだった。
続けて、勉強会編も同様で、更なる続編を期待する声も多数上がっていた。
特に勉強会編では頑張った甲斐があったなぁ、と彼女は自分を褒めていた。
特にあまり親しくない異性の家に行ったのも凄いことだが、更にはソファの上に寝転がって上目遣いで見つめてみたり、わざと距離を詰めてノートを覗き込んでみたり……アオトの反応を引き出すためとはいえ、ハルカはかなり身を削った自覚があった。
故に、今回のライバル出現編には期待がかかっている。
「……楽しい」
彼女はつい先日まで承認欲求に飢えていた自分が、今では嘘のように充実していることに気がついた。
でも、同時に、もっと、もっと、もっと……もっと自分の描いたイラストでバズりたい。流行りたい。そんな思いが彼女の胸中に宿り続けていたのも事実だった。
それから数時間。ハルカは手を動かし続けて、今日の出来事を参考にしてイラストを描いていく。
アオトとの勉強会では発揮できなかったほどの高い集中力を維持する。
しかし、唐突にスマホが振動と共に高い音を鳴らし、集中力はハサミで切ったかのようにプツッと解けてしまう。
「……降谷くんからか」
ハルカはおもむろにスマホを見ると、案の定と言うべきかアオトからのLINEが届いていた。
LINEの友達になったあの日から、気がつけば今では毎日のようにたわいもないやり取りを続けていた。
だが、あまりLINEでのやり取りが得意ではなく、自分1人の時間を削られたくないハルカは、こんなことになるなら最初からテキストデータをLINEで送ってもらうんじゃなかったと少しだけ思っていた。
まあ、クラスメイトのみんなと交換しているのに、あの場面でLINE交換しないのは不自然だと彼女は考えたので致し方ない。
「気分転換に返そーかな」
もしもここで彼を蔑ろにして今の関係が切れたら、次の話が浮かばなくなる。
ハルカはイラストを描く際に、恋愛小説や実体験を参考にしているというのは紛れもない事実なので、彼にはもっと頑張ってもらわないといけないのだ。
『体調は平気か? 先週の勉強会で少し詰め込み過ぎたから無理しないで休んでくれ』
「……気遣いができて優しいよね~」
アオトのおかげで勉強が捗っているのは事実だと思っていたし、渋々ながらも色々と協力してくれる彼の評価は他の男子よりも幾分か高かった。
「んー……」
ハルカは迷った末に上手く言葉を選んでメッセージを返す。
『ありがと~! 降谷くんも無理しないでねっ! あとは1人で頑張るから!』
『わからないことがあったら聞いてくれ。ほれと、不躾なことを聞くようで悪いが、星宮は男が苦手なのか?』
『ううん、どうして?』
『なんとなくだ。西園寺先輩のことあんまり好きそうじゃなかったし』
『男の人は別に苦手じゃないよ! ちょっと怖い時もあるけどね。でも、西園寺先輩みたいに高圧的で強引で、力任せに何でもしようとするタイプは苦手かも?』
『そうか。それだけ聞きたかった』
「……何の確認かな? もしかして、私のことを知ろうとしてる?」
ハルカはテンポよく会話を続けてキリのいいところでスマホを裏返した。
何を思ったのか、アオトがよくわからない質問をぶつけてきたことだけが気になっていたが、今はイラストを優先にしたいので再びペンを取って作業を開始した。
やがて、10枚前後のイラストが完成すると、彼女はピックアップした4枚のイラストを慣れた手つきでTweetし、一息つく。
【根暗男子と金髪ギャル】の3話目の更新をつつがなく終えたのだった。
「んーーーー、終わったぁ。余ったイラストは、とりま分かりやすいようにスマホにまとめて移しとこっかなぁ~」
やりきったハルカは疲れた体を伸ばすと、パソコンとスマホを同期させて最後の作業を終わらせにかかる。
今し方書き終えたばかりの数枚のイラストデータをスマホに移していく。
これらは全てストーリーとは関係のないおまけの一幕として仕上げた一枚絵となり、ハルカ自身がバズった反応をリアルタイムで観察しながら都度投稿していく予定である。
燃え滾る炎を消さぬように薪を焚べ続けるイメージだ。
「よし、終わり」
一通りの作業を終えたハルカは椅子から立ち上がり体を伸ばした。
「……ってか、私のどこがいいんだろ。降谷くんってそういうところ見る目ないよね」
ハルカは思い出す。
会った当初から自分のことを優しい人だと話していた彼の言葉を。
——本当に見る目がない。
私はきみのことをネタにして、承認欲求を満たすことしかできないダメな人間なのに。
周りからは優しくて、ノリが良くて、明るくて、人当たりが良くて、誰とでも仲良くなれて、容姿も優れていて、殆ど完璧な人間だって思われてるけど、実際の私はそうじゃない……私は、そんなんじゃない。
でも、そうしないと私は自分を保てないから。
自分を表現できないから、嫌われるのが怖いから。
「……私は悪くない」
ハルカは自身に対する周囲からの評価と、その本性との乖離を問題視していたが、それは過去の出来事の蓄積が産んだ致し方ない産物として処理し、すぐに思考を放棄した。
本当は、逃げてはいけないとわかっていた。
自分自身を取り繕って、周りに笑顔を振りまいて、本当の自分を心の中に隠し込んで、裏では愚痴を吐き散らしているなんて、他の人に知られたらまず間違いなく嫌われる。
だが、そう簡単に自分の本性を曝け出すなんて出来なかった。
「……お風呂に入ろ」
ハルカは脱衣所に向かうと服を脱いで鏡に映る自分の体を眺めた。
「汚い」
ハルカは自分が嫌いだった。
昔、父親に傷つけられたこの体が嫌だった。
首の下から足の先まで、無数の傷が消えることなく生々しく残り、同級生の女子とはまるで比較にならないほど醜かった。
ハルカは怯えていた。
こんな自分が周りに溶け込めるはずがない。過去のトラウマを克服できない自分が心底憎かった。
だから、ハルカはこれからも自分を偽って生きていく。
父親がそうしたように。家庭内では酒に溺れて暴力を振るい、一度外へ出ると近所の人たちに笑顔を振り撒き、そんな表裏一体な生き方を選ぶ。
——だって、私もそうやって躾けられてきたから。降谷くんには、裏でこっそり小馬鹿にしてイラストを描いているだなんてバレるわけにはいかない。
ハルカの頭の中には、今は檻の中にいるはずの憎い父親の姿が想起していた。忘れたくても忘れられなかった。
本当はもっとはっちゃけたいし、クラスメイトとお淑やかに馴れ合うのはむず痒かった。できれば、恋人だって欲しかったし、でも、それを選ぶのが怖かった。もしも父親と同じようなDV男だったらと考えると、碌に異性と付き合うことができなくなっていたのだ。
それこそが星宮晴香だった。
彼女は臆病だった。故に自分を偽る。故に他人の顔色を窺う。
「……おやすみ」
体を清潔して布団に入ったハルカは、今日も翌朝の世間からの反応を期待して眠りに就いた。
そして、翌日、またも50万人のフォロワーを抱えるイラストレーター『すたぁ☆』は大バズりを記録したのだった。
しかし、彼女の承認欲求はこれまでと同じように充分に満たされることはなかったのだった。
◇◇◇◇
1週間後。
「……」
教室の一角、窓際の最後席に座るアオトは、すらすらと問題を解き進めていた。
日々の知識の蓄積があるからこそ、全く詰めることはない。暗記も理解も何もかも、彼にとっては問題ではなかった。
どの教科においても9割以上の点数を確実に取れるよう勉強しているからだ。
しかし、今回は自分だけのテストではない。
アオトにとって最も懸念すべき点は、悩ましげな様子で頭を捻っている右隣のハルカの事だ。
一緒に勉強した4日間は何も問題がなかった。むしろ、ジュースとお菓子を貪りながらも熱心に勉強する彼女の姿は素晴らしかった。だが、変態先輩こと西園寺に会って以降は、彼女の動向をアオトは知り得なかった。LINEで些細なやり取りは続けていたが、授業中の様子を見ても、机の下でスマホを確認するばかりであまり勉強に集中できていないように見えていた。
ハルカはずっと何かが気になって仕方がないような様子だったので、アオトは心配だった。
もしも、星宮が赤点を取って、その後の補習テストに落ちて、再補習テストにも落ちたら……そう思うと、勉強を教えた俺はなんで愚かだったんだと……。
だが、いくらアオトが自責の念に駆られようとも、ハルカは今現在の段階で蓄積した努力を武器に戦うしかないのが現状だ。
だからアオトは祈るしかない。全教科において解答と見直しを最速の15分程度で終わらせてからは、カンニングを疑われない程度に横目でハルカの様子を確認しつつ、机の下で両手を合わせて心の中で神頼みをするのがルーティンだった。
「……頑張れ」
時には机に伏せて誰にも聞こえない声でエールを送り、アオトは根暗で人付き合いが苦手な自分らしくないなと思いつつも、ハルカを気にかけるその想いは真っ直ぐだった。
やがて、5日間に及ぶ定期テストが終了すると、皆がぐったり疲れた様子でテストの感触を語り合っていた。
そんな中で、アオトは普段ならば早々に教室を出て帰路に就くのだが、右隣で顔を伏せて固まるハルカのことが気になってそれどころではなかった。
「……星宮」
アオトは顔を近づけて小さな声でハルカの名前を呼ぶ。
すると、彼女は顔を僅かに上げて苦々しい表情を浮かべたが、ゆっくりと首を縦に振り口を開く。
「大丈夫。赤点は回避できたと思う」
ハルカが口にしたのは今のアオトのことを安心させられる最高の一言だった。
「……良かった」
「ふふ」
青とは柔らかい笑みを浮かべるハルカを見てほっと一安心した。
そんな二人のやり取りに周囲は全く気が付かない。
しかし、長くは続かない。
気がつけば、ハルカの机の周りには何人もの女子が来ていたからだ。
「終わったーーー! マックで自己採点しよーよ!」
「えー、せっかくテストから解放されたんだし、今日くらいはいいじゃーん」
「んー、じゃぁ、記念にプリでも撮る?」
「いいねぇー!」
4、5人の女子生徒たちはハルカを取り囲うようにして楽しげな声色で会話を繰り広げている。
アオトはそんな彼女らの会話を聞き流しつつも席を立つ。
今日は帰ったらゆっくり休もう……アオトは一人でに嘆息してこの後のプランを決めたのだった。
それから彼の行動は早かった。
誰にもバレることなく人の合間を縫って教室を出てから廊下を駆けていくと、テストが終わったばかりで空いている玄関口から堂々と1人で太陽の下に降り立った。
「……絶好の執筆日和だ」
アオトは珍しく晴れやかな顔つきだった。
本来は小説の執筆なんて自室に引きこもって画面と睨めっこするだけなのだが、アオトにとっては実に2週間ぶりの執筆になるので書きたいことは山ほどあったのだ。
ハルカと共に過ごした時間は余すことなく記憶とメモに残してあるので、後はそれを想いに変えて文字にするだけだ。
それから、アオトは家の中へ転がり込むようにして帰宅すると、手洗いうがいだけはきっちり済ませてすぐさま自室へ篭り始めた。
彼はパソコンの画面を見ながら記憶とメモを頼りにエピソードを練り上げていく。やがて、1時間、2時間……と、悠久の時を超えてその日の夜を明かしたのだった。
◇◇◇◇
翌週。
アオトは憂鬱な月曜日の始まりだというのに、美容男子顔負けの艶やかな表情だった。
彼はニヤケが出るのを抑えながら自分の席に座り、真剣な眼差しで手に持つスマホを眺めている。
いつも通り周囲の関心がアオトに向くことはないのだが、隣の席のハルカだけは例外だった。
『良いことでもあったの?』
『金土日で書き続けて五万文字に到達した』
アオトのLINEの通知は相変わらずオフだったが、たまたまLINEニュースを見ていたためにすぐさまハルカに返信した。
『すご』
『星宮は進展あったか?』
『実は私も一枚だけ描けたよ!』
『おー、見せてくれ』
『うん。描くのが遅くて本当にごめんね』
詫びを入れるハルカだったが、アオトからすれば協力してくれているのだから全く気にしなくていいのに、と思っていた。
「……すげぇ」
すぐに送られてきたハルカからのイラストをクリックしたアオトは、そのイラストを見るや否や、無意識のうちに感嘆の言葉を溢していた。
彼はイラストに魅了されてしまい、画像の中の世界に吸い込まれてしまいそうになっていた。
彼女から送られてきたイラストは、私服を着た男女の後ろ姿が描かれていた。
男の方は真面目そうな印象で、腕には時計をつけて、地味な格好で真っ直ぐな姿勢で歩いている。
一方、女の方は元気そうで活発な印象で、肩から下げた小さなバッグと、足を曝け出した爽やかな格好はその明るい性格を窺わせる。
そんな二人が歩いているのは、どこかの建物の中だったが、その場所をアオトは知っていた。故に思わず感傷的な気持ちになる。
また、イラスト全体には夏から秋への変わりゆく様を感じさせるスカイブルーを中心とした夏っぽいような色合いが使われており、その情景と季節感がよりリアルに感じられる。
このイラストは、アオトにとってただの絵画以上の意味を持っているようで、彼の心を奪うだけでなく、思い出を呼び覚ますものでもあった。
「……」
アオトはその感動を言葉にして伝えようと、はやる気持ちを抑えながらも指で文字盤をフリックする。
『ありがとう。星宮は必ずプロになれるよ』
嘘偽りない言葉だった。
『そう?』
『なれる。何の保証もないが俺はそう思う。感動した。星宮は凄いよ。俺はそれくらいこの絵が好きだ』
アオトは行き当たりばったりで突発的な言動はあまり好まないのだが、それでもハルカのイラストは一目見ただけでイラストレーターとして成功しないわけがないと確信していた。
『後で俺が書いたテキストも送るから読んでくれ』
『うん』
こうして一連のやり取りを終えると、アオトはスマホを机に伏せて天を仰いだ。
ハルカが描いたイラストを見たことで、その気持ちはより一層の充足感を抱いていた。
きっと、描き終えた彼女もそうに違いない。
そう思ったアオトは右隣にいるハルカの姿を横目で一瞥したのだが、それとほぼ同時に担任が教室に入ってくる。
授業開始前のショートホームルームが始まった。
「おはようございます。いつもはこの時間を読書や自習のために充ててましたが、本日は転校生の紹介をしたいと思います」
アオトのクラスをまとめあげる中年の女性教諭は、特にサプライズ感を持たせずに割と重大な発表をした。
皆が呆気に取られた顔つきになっていたが、ほんの数秒の静寂をおいてからすぐさまクラス全体が湧き立った。
早朝だというのに騒がしい。でも、転校生は珍しいなと、アオトは窓の外を見て考える。
彼はどうせ自分と接点を持つことなどないと思っているので最初から興味がないのだ。
「せんせー、男? 女?」
「女の子です。白銀さん、どうぞ」
中年の女性教諭はチャラついた生徒をあしらうように答えると、教室の外へ向かって手招きをして件の転校生の名前を呼んだ。
アオトは尚も窓の外に視線を向けて、秋を実感させる一匹のトンボと見つめあっていた。
「初めまして。白銀香澄です。東京の女子校から来ました。共学に通うのは初めてなのでみなさん仲良くしてください。お願いしますっ!」
「はい、白銀さん。ありがとうございます。席は廊下側の一番後ろの席が空いてるのでそちらにお願いします」
アオトがトンボと見つめあっている間に自己紹介は終わったらしく、教室の中は白銀香澄——カスミへの拍手と声高らかな男子の叫びで満たされていた。
彼はここでようやく転校生の女子に目を向ける。関わり合いを持つことはないと思うが、一応クラスメイトになったので、見た目と名前くらいは頭に入れておくことにした。
ダークブルーっぽい髪色は尻尾のように結われており、言わばポニーテールだった。
容姿は低身長で150センチないくらい、それと胸がメロンのように大きい。
アオトが何の気なしにボーッと観察をしていると、なんとなく、一瞬、彼はカスミと目が合ったような感覚を覚えた。
しかし、すぐにそれは勘違いだろうと片付ける。
「……白銀……珍しい苗字だな」
そんなアオトの呟きは、未だ続く喧騒に押しつぶされて消えていったのだった。
◇◇◇◇
転校生がやってくるという一大イベントはあったが、つつがなくその日の授業は終わっていた。
アオトはいつものように手際良く帰りの支度を済ませると、ちらりと星宮に目配せを送ってから席を立つが、肝心の彼女は友達との会話に夢中になっていてからに気がついていないようだった。
いつの間にやら復活していて、今朝の照れはなんだったのか、既にいつもの調子を取り戻していた。
アオトは少しくらいハルカと会話を交わしたいと思っていたが、今はその時ではなさそうなので大人しく帰ることにした。
今なら例の転校生がクラス中の関心を集めているので、堂々と歩いて抜け出すことができる。
「……」
こうして、アオトはさながら忍びのように、誰にもバレることなく廊下へ出た。
同時に他クラスの生徒たちが転校生の姿を一目見ようと、二つある教室の出入り口に詰めかけてくる。
危ない危ない……アオトは内心冷や汗かきながらも胸を撫で下ろす。
だが、彼らがごった返しているせいで、いつも使っている正面の階段までは辿り着けそうもなかった。
「遠回りになるが裏から行くか」
アオトは野次馬たちを一瞥してから踵を返すと、長い廊下を歩いてひと気の少ない裏手へ向かい、先ほどとは打って変わって閑散としている階段を駆け下りた。
しかし、そんなアオトが階段の踊り場に到達した瞬間、彼の目の前に一人の女子生徒が立ち塞がるようにして躍り出てきた。
「——ねぇ、ボクのこと覚えてる?」
「……え? 俺?」
突如として眼前に現れた女子生徒の目は間違いなくアオトの姿を捉えていた。
彼はまさか話しかけられたのが自分だと思わずに動揺を露わにする。
というのも、その女子生徒は、今朝方転校してきたばかりの白銀香澄だったからだ。
彼女はまんまるの愛らしい瞳をキラキラと輝かせながら、アオトのことを見上げている。
「わぁ……その顔、やっぱりそーだ! 久しぶり!」
カスミは力の抜けたアオトの両手を自身の両手で握り込むと、ぴょんぴょんと跳ねながら喜びを露わにしていた。
「……えーっと、どこかで会ったっけ?」
「え、ボクのこと、忘れちゃったの?」
悲しげな顔つきで小動物のようにしゅんと俯いているが、本当にアオトは彼女のことを知らなかった。
忘れちゃったの? と、間近で言われても、何一つとして思い出せない。
そもそも、彼には星宮を除けば女性の知り合いなど存在しないのだ。
「……うーん」
アオトはカスミの顔をじっくりと見てみた。
ダメだ。彼は心の中で諦めの言葉を口にする。
どう足掻いても記憶の中に彼女の姿を見つけ出せなかった。
「悪い。やっぱり人違いだと思うぞ?」
「えー! もしかして記憶喪失? あんなにたくさん遊んだのに、ボクのことを忘れちゃったってこと!?」
「いやいやいやいや。俺は生まれてこの方、女の子の友達なんてできたことないんだよ。だから、白銀さんは赤の他人。OK?」
食い下がってくるカスミのことを少し鬱陶しく思ったアオトは、きっぱりと言葉で拒絶の色を示した。
彼も昔から付き合いのある佐山が相手なら別だが、赤の他人、ましてやクラスメイト、しかも転校生にこんなことは言いたくなかった。だが、こうしないと変な幻想を抱かせて付き纏われそうな予感がしていたのだ。
「うぅぅ……もう知らないっ! アオくんのばかぁぁぁぁーーーー!」
アオトから拒絶の意を突きつけられたカスミは、まるで幼子のような純真な瞳から涙を溢すと、とてとてと小さな体で階段を駆け上がっていってしまった。
彼は少し言いすぎたかなと思いつつも、自己防衛のためには仕方のない判断だと解釈して今の出来事は忘れることにした。
「……帰るか」
「降谷くぅーん? 女の子を泣かせたらダメなんだぞ~?」
「はぁぁぁ……星宮、見てたのか?」
気を取り直して帰ろうとしたアオトだったが、予想外の相手に呼び止められて溜め息を吐いた
「まあね~。ってか、向こうは降谷くんのこと知ってる感じだったけど、本当に赤の他人なの?」
ハルカはカスミが走り去って行った方向を見ながら、ゆっくりと階段を下りてくる。
この口ぶり的にどうやら一連の流れを見ていたようだ。
「当たり前だろ。俺の知り合いといえば、佐山と星宮……超ギリギリ西園寺先輩くらいじゃないか?」
「え、それって怖くない? 向こうは跳ねて飛んで手を握っちゃうくらいの相手を勘違いしてるってことでしょ?」
「まあ……よっぽどその相手が好きだったんだろうよ」
「……うんうん、こっちのライバルも登場か。面白くなってきた」
「何か言ったか?」
小声で何かを口にしていたハルカだったが、アオトの耳には届いていなかった。
「ううん」
「そうか? んで、ここには何しにきたんだ。たまたま通りがかったわけじゃないんだろ?」
アオトはおもむろに用を尋ねた。
こんな正面玄関から離れた裏の階段を使う生徒はあまりいない。
「たまたまだよ」
「そうか」
ハルカは即答したが特に深く言及することでもないので、アオトは軽く流すに留めた。
同時に、一連の会話が終わったことで、2人きりしかいない狭い踊り場には沈黙が訪れた。
途端にしんとした静けさが辺りを支配したかに思えたが、それを破ったのは、ハルカのスマホから聞こえる通知音だった。
彼女はおもむろにポケットの中からスマホを取り出すと、指でスワイプしながら何かを確認していた。
表情が今まで見たどの瞬間よりも生き生きとしており、それはむしろ恍惚と表現するのが相応しいくらいだった。
「何してるんだ?」
気になったアオトは何の気なしに尋ねる。
「んー? えーっとね……まあ、色々かなぁ」
誤魔化したハルカだったが、一目見てわかるほどには口角が上がっていた。
幸せを噛み締めているようにも見える。
しかし、そんな時。
彼女はふとした拍子に手のひらの中からスマホが滑り落とすと、それはアオトの足元にやってきた。
「……あ」
先に声を漏らしたのはハルカだった。単にスマホを落としただけだというのに、彼女は取り返しのつかない失態を犯してしまった時のようにその顔を青褪めさせていた。
しかし、アオトからすれば何のことかわからない。
「ん?」
アオトはハルカのスマホを拾い上げる。単なる親切心だった。
スマホの液晶は上を向いており、そこにはアオトの知らないアニメ調のイラストが表示されていた。
イラストには艶やかなボブカットの金髪を揺らして陽気に笑う女子生徒と、一転して暗そうな雰囲気を醸し出してはいるが楽しげに微笑む黒髪の男子生徒の姿が映っている。
一見すると、仲睦まじい男女のイラストのようだっったが、彼は妙な既視感を覚えた。
アオトは見覚えのないはずのイラストなのに、どこか記憶の微かで知っているような光景だと感じていた。
「これは何だ?」
アオトからすれば単純な疑問だった。
このイラストは俺のために描いてくれたのか、そういう意味を込めて尋ねたのだが、目の前にいるハルカはどういうわけか心底焦った顔つきになっていた。
彼女はごくりと息を呑むと、そこから間髪入れずに飛びついてくる。
「……返して!」
「ど、どうした? これは俺と星宮じゃないか? それに……同じようなイラストが何枚もあるけど、どれも俺が見たことのないイラストだな」
ハルカがスマホを奪い取ろうとしてきたが、胸に残る疑念を晴らしたいアオトはバックステップを踏んで距離を取った。
普段の彼ならこんなことはしない。
ただ、今は自然と反射的に体が動いていたようだ。
「これは俺のために描いてくれたイラストじゃないのか?」
アオトはどうしてそれほどまでにハルカが焦っているのか、全く理解できなかった。
彼から見たこれまでの彼女は、活発で明るい性格ながらもどこか達観した部分もあり、同い年の割に経験値が高くて余裕を持った存在だった。なのに、今はおかしなくらい動揺を明らかにしている。
しかし、そんなアオトの妙な疑念はすぐさま振り払われることになる。
「……そう、そうだよ。これはね、降谷くんのためを思っていっっっぱい描き溜めたイラストだよ! びっくりした?」
突如として、ハルカは満面の笑みを浮かべて、明るく朗らかな雰囲気を作り出すと、まるでドッキリのネタバラシでもしているかのような軽い口調で言い放った。
「え? まじ?」
ハルカの真意を知ったアオトは胸を跳ねさせて喜びを露わにして聞き返す。
「うん! いや~、このイラストは降谷くんが書いてくれた小説とは関係ないオリジナルだったから、本当は後で見せて驚かせようと思ってたんだぁ~。まさかスマホを落としちゃうなんて、私ってばおっちょこちょいだよね~」
「……そういうことか。良かった。なんか良からぬ事情でもあるのかと思ったぞ」
アオトは何がない様子で距離を詰めてきたハルカにスマホを返してあげた。
さすがのアオトもまさか彼女がオリジナルのイラストを描いてくれるとは思っていなかったので、驚きと同時に安心の念が胸中を支配していた。
彼はてっきり彼女が自分にとてつもない隠し事をしているものだと考えていたが、その疑念は今の今で振り払われることになったのだ。
「そんなわけないでしょ? 私たちはアオハルコンビだよ? コンテストまでは後2ヶ月ちょっと! 2人で頑張るよ」
「……そうだな。うん、頑張ろう。確か文字の規定は10万字だったはずだし、もっと気合いを入れないとな」
現状は5万字に加えて、ハルカのイラストが1枚。
コンテストの応募にあたってイラストの提出は特に不要なのだが、やはりアオト的には自分の書いた小説にイラストが添付されると気合が入るのだ。
「うんうん、その意気だよ。私も筆が遅いなりに頑張ってみるから、悔いのないようにしよ?」
「ああ、星宮がそう言ってくれると俺もすごいやる気が出てきたよ」
「いいね~!」
ハルカは肘でアオトのことを小突くと、いたずらっ子のような笑みを浮かべた。
「……あんなにたくさん描いてくれてありがとな。本当に、嬉しいよ」
アオトはすぐ側にいるハルカを横目で見ながら、照れ臭さを感じつつも言葉にして感謝を伝えた。
「お互い様でしょ?」
「そう言ってくれると助かるよ」
優しく微笑んでくれるハルカを見て、アオトは穏やかな心に満ちていた。
窓から差し込む淡い陽の光もそんな彼の安らかな思いを増長させる。
「あっ、それと話は変わるけど、再来週は修学旅行でしょ? 誰と回るのか決めた?」
「……もう、みんなそういう話をしてるのか?」
「え? もしかして1人?」
「まあ、そうだな」
アオトは特に誤魔化すことなく答える。
単に友達が少ないだけで別に恥ずかしいことではない……と、彼女との交友関係の格差を肯定する。
「いいなぁ……」
「え?」
ハルカが羨望の眼差しをアオトに向けながら何かを口にしたが、彼の耳には届いていなかった。
「な、なんでもないよ!」
「ん、星宮は誰と回るんだ?」
「私は友達とだね~。たくさん誘われちゃったから大所帯で大変だよ」
ハルカはあんまり乗り気ではないのか、傍目でもわかるくらい明らかに肩を落としていた。
「楽しそうじゃないか」
「1人の方が気が楽じゃない? 周りに気を遣わなくていいし、やりたいことが好きにできるよ?」
「それもそうだな」
ないものねだりとはよく言ったもので、アオトは交友関係が広いハルカのことが少しだけ羨ましく思えていた。
「うん……それじゃあ、私はそろそろ行くね」
「ああ」
「うん……あ、それと、明日の放課後に白銀さんの歓迎会をやることになったんだけど、来る?」
「いや、大丈夫だ」
「そ、またね」
アオトは階段を上っていくハルカに手を振り今日のところは別れを告げた。
そして、1人になって胸を撫で下ろす。
「よかった」
思わず口にする安堵の言葉。
アオトは数多くのイラストを描いてくれたハルカへの感謝の念が絶えなかった。
そして、沸る情熱を無駄にしないためにも一つ心に誓う。
——今日は帰ったらすぐに執筆に取り掛かろう。
俺と星宮をモデルにした恋愛小説も既に5万字になり山場を迎え始めている。そろそろ恋のライバルなんかも登場させてつつも、最後は2人がハッピーエンドで終われる未来を目指す……。
彼が思い描く恋愛小説は、平和な世界観で感動的な描写を織り交ぜつつも最後は誰もが不幸にならないハッピーエンドだった。
だからこそ、アオトはハルカと過ごす時間をより大切にする必要がある。
そんな物語の最後を想起するにつれて、彼はこれまで抱いたことのない気持ちを胸に秘め始めていた。
「……星宮」
1人でに、アオトは彼女の名前を呼ぶ。
同時に心臓がとくんっと大きく鼓動した。
この想いの真実にアオトはまだ気づかない。
◇◇◇◇
その日、部活を終えた佐山は、先輩たちに挨拶を済ませて部室を後にしていた。
「では、佐山よ! 部活終わり恒例の僕のショータイムに立ち会えないのは残念だが、教室に忘れ物をしたということであれば仕方があるまい! 明日は必ずや参加するようにっ! ではな!」
「西園寺先輩、別れの挨拶はいいですから先に服を着てください」
「うむ!」
「んじゃ、おつかれっした!」
佐山はいつも通り全裸な西園寺に挨拶を返すと、そそくさとグラウンド近くの部室を離れて校舎へと戻る。
「ふぃーーーーー、今日も疲れたぜ、マジで鬼コーチやべぇって」
佐山は疲労を感じて震える足を懸命に動かしながらボヤいた。
向かう先は教室だ。今日の体育でジャージが汚れたので回収しなければならなかった。
佐山としては疲れたので早く帰りたかったのが本音だが、汗が染みたジャージを放置したくはなかったのでやむなく教室へ向かう。
時刻は既に午後の7時を回っており、この時間はサッカー部と一部の教員しか校舎にはおらず、一般の生徒が下校済みなこともあってか教室は閑散としている。
「あったあった」
佐山はジャージが入った袋を回収してそそくさと教室を後にする。
「……あー……かーえろ。俺も彼女がいたらサイコーだったのになぁ。西園寺先輩みたいな容姿が欲しいぜ。唯我独尊で破天荒な性格と特殊な変態性はいらねぇけどな」
退屈凌ぎに独り言をぶつくさ口にする。
ぶんぶんと布袋の持ち手を振り回しながら歩みを進める。
周囲には誰もいないので言いたい放題だ。しかし、廊下へと出て一階へ続く階段へ向かう最中、明かりのついた教室が目に入った。
「あそこはアオトのクラスだな。誰かいんのか?」
佐山はじっと瞳を細めると、暗い廊下に明かりが漏れる教室を見やった。
まだ午後の7時とはいえ、秋口になっているため既に外は暗い。
こんな時間まで残っている生徒は、巡回している教員に帰宅を促されそうなものだ。
不思議に思った彼は、まるで夏の虫のように明かりに引き寄せられていく。忍び足で距離を詰めると、恐る恐る薄ら開かれた戸の隙間から、教室の中を覗き込んだ。
すると、そこには予想だにしない人物がいた。
「ありゃあ、星宮さんか? 一人で何してんだ」
佐山の視線の先には、席について忙しなくスマホを弄るハルカの姿があった。金髪のボブカットだからよく目立つ。
彼からすればあまり関わりのない相手であったが、最近は友人のアオトが親しくしているという噂もあるため少しばかり気になっていた。
「……」
佐山は息を顰めてハルカのことを凝視する。
特に何をするでもない。
彼女は激しく貧乏ゆすりをしていて、あまり機嫌が良くなさそうだったのは能天気な佐山でもわかった。
——星宮さんってこんな感じなのかよ。
心の中で佐山が動揺したのとほぼ同時のこと。
「あー……ほんとに最悪」
ハルカは佐山が見ていることなどつゆ知らず、ドスの効いた低い声を出す。
普段の高くてよく通る耳障りの良い声とは大違いだった。
「え?」
佐山は思わず素っ頓狂な声をあげたが、咄嗟に自身の口を真一文字に塞ぎ難を逃れる。
そして、続け様に吐かれたハルカの言葉に耳を澄ます。
「みんな私に期待しすぎだっての。笑顔を振りまいていい子ちゃん振んのがどんだけ疲れると思ってんのよ。ってか、この髪は地毛だし真似したいとか知らないから。私の気持ちも理解できないくせに擦り寄ってこないでほしいんだけど。どうせ私のこんな姿を知ったら幻滅するくせに」
ハルカは決して怒鳴ることはせず、極めて静かな口ぶりだったが、鈍感な佐山でもわかるほど物悲しい雰囲気を身に纏っていた。
「……どういうことだ」
佐山はごくりと息を呑む。
おそらく見てはいけない光景なのだろうと理解していたので、罪悪感に苛まれてしまう。
しかし、ゴシップ好きな彼はこの機会を逃すまいと、目の前の光景と彼女の発言を目と耳に焼き付けていく。
それもそうだ。
皆から人気者で、色んな場所で多くの話題が絶えない星宮晴香という女子生徒が、まさかこんな裏の一面を持っていたなんて誰も想像していなかったから。
「ねぇ……きみは優しいから、本当の私の姿を見ても幻滅しない? 心も体も醜いし、必死に自分を作らないと生きていけない。きみの小説に出てくるお姫様みたいな女の子じゃないんだよ? イラストで見たような綺麗な笑顔は作り物なんだよ?」
ハルカは静かに席を立つと、左隣の席の机と椅子を見下ろしながら囁くような声で言葉を紡ぐ。
佐山からすれば意味がわからなかったが、確かにハルカの声は泣いていた。
「……なんで、泣いてるんだ。しかもその席って……」
佐山は数多くの疑問が頭を満たし眉を顰める。
ハルカが日頃から我慢しながら、誰かと付き合いを継続しているのはわかった。
表向きはあんな人当たりの良い性格なのに、裏では過度な鬱憤が溜まっていて、周囲との温度差がありすぎるという事実は佐山の想定外だった。
ゴシップ好きである彼でも全く知り得ない情報ということは、これまで上手く隠して生活してきたのだろうとわかる。
佐山としてはもっと観察を続けていたかったが、小心者な彼はもう見ていられなくなっていた。
もしも接触なんかしてしまった時には、何をされるかたまったもんじゃない……彼は一つ息を吐いて一歩後退した。
しかし、確かな焦りが行動に現れてしまい、ジャージの入った布袋が扉に接触する。
——ガタッ……静寂に包まれる薄暗い廊下に、違和感のある小さな音が響く。
「誰!?」
ハルカは即座に反応すると、焦燥感に駆られた目つきを扉の隙間に向ける。その反応の早さから、余程人に見られたくない光景だったのだとわかる。
刹那。
佐山は彼女と目が合ったような気がしたが、そんなことを考える余裕などなくわ物音など気にせず、気がついたらドタバタと必死に駆け出していた。
ドッと全身から冷や汗があふれ出てくる。
背後は振り返らずに、暗闇に塗れて階段を駆け下りる。下駄箱で靴を履き替えたら、教室の窓から見られないように校門を出てすぐに裏手へ回り、わざと遠回りをして帰路へ就く。
「はぁはぁはぁはぁ……っっ……や、やべぇよ、マジで……」
佐山はサッカー部で蓄積した疲労など感じさせない猛ダッシュで学校から離れると、周囲に誰もいないことを確認してから息を落ち着かせた。
「——あ、あの席って確かアオトんとこだよな? まさか、いや……でも、わかんねぇけど、どっちにしろ星宮さんってかなりイメージと違ったな……」
佐山は混乱の中でうろ覚えであったが、ハルカが見下ろして語りかけていた席の位置を思い出した。
あそこはアオトの席だった。
でも、わからないことの方が多い。
小説とイラストというワード……佐山には全くピンとこなかった。
今はいくら考えても何も思いつかない。
佐山は、自分自身も含めて、皆がハルカに抱いていたイメージとの乖離が深すぎるあまり、すっかり思考回路が麻痺していたからだ。
「……変な夢、だよな。うん、夢だな!」
考え込んだ末に、佐山はいったん都合の良い方向に話を片付けると、ふらふらとした足取りで家路を辿ったのだった。
その後、家に帰って落ち着いた頃に再度思考した結果、先程の出来事が現実だと知り頭を抱えることになるのだが。
◇◇◇◇
翌日の放課後。
アオトは珍しく佐山に呼び出されていた。
場所はグラウンドの側にあるひと気のない石階段の中腹部。二人は拳ひとつ分空けて並んで座っている。
「佐山、俺はやる事があるから忙しいんだぞ」
アオトは恨めしそうな目つきで左隣に座る佐山を睨みつける。
今日の放課後は、近日控える修学旅行に向けた日用品と衣服を買う予定があったのだ。
「馬鹿、俺だってもう部活の時間だからうかうかしてらんねぇんだよ」
「じゃあ、早く本題に入ってくれよ」
「わかったよ。んじゃ、1つ聞くぜ。お前、小説とか書いてるか?」
「へ?」
いきなり突拍子もない質問をぶつけられてアオトは、反射的に肩を大きく震わせた。
「その反応、ビンゴだな」
佐山はしてやったりといった様子で口角を上げる。
「な、なんで俺が小説を書いてるって知ってんだよ!」
「聞いたんだよ」
「誰から?」
アオトは間髪入れずに尋ねる。
「……驚くなよ?」
「お、おう……」
もったいぶった佐山に対して、アオトはごくりと息を呑む。
「星宮さんだ」
「は? 星宮が? お前と星宮は殆ど繋がりがないはずだろ? いつどこで聞いたんだよ」
「まあまあ、落ち着けよ。まずは昨日の部活終わりのことだ。俺はたまたまお前のクラスの教室の明かりが点いていることに気が付いてよ、なんだなんだと思って覗いてみたら、何とそこには星宮さんがいたんだよ。時刻は夜の7時過ぎだ」
「それで?」
気になる点も散見されたものの、ここまでは特に変哲のない話だったので、アオトは適当に相槌を挟むに留める。本当は心臓の鼓動が早くなっていたが、友人である佐山のことを信頼して冷静になる。
「んで、そしたら急にだぜ? 星宮さんがお前の机を見下ろして、小説やイラストはどうこうとか……作り物の笑顔とか、正直俺もビビってはっきりは覚えてねぇんだけどよ、いつもの星宮さんとは別人みたいにぶつぶつ何か言ってたんだよ」
「……悪い、その説明じゃよくわからないんだけど、星宮が夜の教室に1人でいたってことか?」
「おう、その通りだ。めちゃくちゃ低いテンションでな」
佐山は力強く頷いた。
長年の付き合いがあるアオトは、彼が嘘をついているようには見えない。
しかし、話を聞いて状況を整理してみても、全く想像もつかずあり得ないとしか思えなかった。
「そもそもそれは本当に星宮なのか? 本当に別人だったってことはあり得ないか?」
「おいおい、星宮さんなんて地毛が金髪なせいで、どこにいても1番目立つんだから見間違えねぇよ」
「ふーん……何で俺に教えてくれたんだ?」
「お前は星宮さんと仲良くしてんだろ? 昨日なんてよ、『きみは優しいから、本当の私の姿を見ても幻滅しない』って、お前の机を見下ろしながら言ってたんだぜ? 意味深すぎて理解不能だけど、何か裏があると思わねぇか?」
佐山は珍しく顎に手を当ててじっくりと考え込むような仕草を見せた。
しかし、そんな彼の言葉など間に受けていないアオトは、大きく溜め息を吐いた後に口を開く。
「……ちなみに、全く話は変わるが、昨日の部活はどんな感じだった?」
「クッッッソ疲れたな。鬼コーチに走らされまくって、もう帰りはフラッフラだったよ。帰ったらすぐに爆睡して、朝起きたのもギリギリの時間だったな」
「わかったぞ。佐山、お前は疲れてるんだよ。夢でも見たんじゃないか? そもそも星宮がそんな人じゃないのはよく知ってるだろ? いくらゴシップが好きだからとはいえ、そんな話をしても誰も信じないぞ?」
アオトは佐山の話を全て一蹴した。
ゴシップ好きでありもしない噂ばかりを懐で温めている彼の話など、最初から信憑性は薄いとすら思っているくらいだ。
「はぁ!? 違ぇよ、俺は確かにこの目で見てこの耳で聞いたんだよ! もしも俺の話が嘘なんだとしたら、どうして俺はお前が小説を書いてるって知ってんだよ!」
「うーん……俺の唯一の友達だし信じたいのは山々なんだけどさ、どうしても星宮がそんな事をするとは思えないんだよな。お前が俺の小説のことを知ってるのだって、たまたまスマホを見たからとかじゃないか? 俺ってパスワードとかかけてないし、な?」
佐山はオーバーすぎるリアクションで仰天して見せたが、アオトの心には全くと言っていいほど響いていなかった。
むしろ、尚もハルカを疑い続けている佐山に辟易しているくらいだった。
「……お前、毒されてるんじゃないか? 大丈夫か? 利用されるような心当たりがあったり、変な頼み事とかされてないか? 美人局とか金銭目的の詐欺とか……ねぇか? イラストがどうこう言ってたし……ちょっと怪しいぜ?」
「大丈夫だよ」
アオトは即答する。
小説を読んでもらい、イラストを描いてもらう。
そして、ゆくゆくはクリスマスの日に控えるコンテストへの応募を目指す。アオトとハルカの間には他人に言えないそんな秘密があったが、彼からすればそれは佐山に心配されるような問題事なんかじゃない。
「……ならいいけどよ。とにかく、ちょっとは気をつけたほうがいいぜ。忠告はしたからな。多分だけど星宮さんはお前が思ってるような人じゃないぞ。それと、俺の話はゼッテー夢じゃねぇから、それだけは覚えとけ!」
佐山はアオトにビシッと指を刺して力強く言い放つと、重たそうなリュックを背負って駆け足で立ち去った。
「相変わらず心配性だな、あいつは」
アオトは嘆息すると、佐山から聞いた話を頭の片隅に入れて昔のことを思い出した。
彼と佐山の付き合いは五歳になる少し前からになるが、当時から陽気で人に優しいやつだった。
いわゆるお人好しで心配性気味な性格は今も変わっておらず、時折りアオトのことを気にかけている。
また、互いの両親も親しい関係を築いており、俗に言う幼馴染というやつだった。
そんな幼少期には、別の人物もいた。
それは、金城こと金ちゃんである。
同い年の少年、金ちゃんは、男気のある性格で2人ともすぐに仲良くなった。
しかし、アオトと佐山、そして金ちゃんが仲を深めてから半年後のある日、金ちゃんは忽然と姿を消した。
アオトは幼いあまりその理由をよく覚えていないが、金ちゃんがいなくなってショックを覚えた記憶はある。
だから、その時から、一度築いた関係は大切にしたいとも思うようになっていた。
それは、幼馴染である佐山はもちろんのこと、直近で知り合った星宮もそうだ。
アオトは佐山の話を完全に否定するつもりはなかったが、やはり彼の話を聞いたせいで彼女のことを信じきれない気持ちも大いにあった。
「……佐山の話が本当なら、星宮はどうしてそんなことをしてるんだ?」
アオトは一つ呟き立ち上がると、一人で校舎を後にする。
道中、俯いたハルカとたまたますれ違った彼は、小さな声で挨拶をしたが、彼女は一瞥くれるだけで何を言わなかった。まるで、思いに耽ったような悩ましげな顔つきをしていて、とても世間話を持ちかけられるような雰囲気ではなかった。
帰宅したアオトは佐山の言葉を思い出す。
彼はハルカが何を考えているのか、その真意は詳しくわからなかったが、”具合が悪いなら、お大事に”と、労いのメッセージを送ったのだった。
降谷碧都は退屈だった。
交友関係は狭く、恋人もいない。というより、恋愛経験はゼロだ。
そして、性格も暗く目立つタイプでもない。運動神経は並々で際立った能力もない。
特技も……これといって、ない。
強いて挙げるとすれば勉強が得意だったが、通っているのは、ごく普通の公立高校だった。
何かがしたかった。
何かを見つけたかった。
自分が全力で向き合える何かがほしかった。
だが、そう簡単に見つかるものではない。
一度没頭したり、気になったり、興味が湧けばとことん追求したがるアオトだったが、今日も彼は、ひと気がなく閑散とした高校の図書室にいた。
時刻は、まるで時の流れに取り残されたかのような静寂が漂う土曜日の昼下がり。
休日だというのに、アオトは独り勉強に没頭していた。
ただひたすらに問題集とノートを交互に見やってはその手を動かし、集中を途切らせることなく、その心は知識の海に浸かっていく。
電源の切られたスマホはリュックの奥底で眠り、代わりに机の上にはこだわりの配置で教科書や参考書、ノートや筆記用具を並べられている。
そんな真面目がちな彼は独りで机に向かって座り込み、汗ばむ全身に嫌気を感じながらも勉強に集中していた。
夏が終わりかけているというのに、北海道の気温はまだまだ下がる気配を見せない。
そんな図書室で聞こえるのは、紙を捲る心地良い音色と鳥の囀りだけ。
「疲れた」
しばらくすると、アオトは教科書とノートを閉じて机の上に体を預けて息を吐いた。
少し長めの黒髪が重力に従ってさらりと揺れると、その隙間からはやや切長な瞳をのぞかせる。
昼過ぎに図書室へ来てからもう3時間が経過していた。土曜日だから人が少ないのは最高だが、やはり何時間も勉強を続けるのは中々に大変だとアオトは思う。
先月の末に夏の休暇が終わり、皆が思い出の余韻に浸る中、彼だけは変わらず孤独な学び舎で日々を過ごしていた。
「……本でも読むか」
アオトは机を離れ、疲れた体を伸ばしながら流行りの小説が置かれているコーナーに向かった。
気分転換だ。
そこには、一度は見たことがある有名な小説が幾つも並んでいた。
中でもアオトの目を引いたのは、少し前にテレビドラマ化された恋愛小説だった。
ここだけの話、彼は自分の恋愛経験の無さに辟易している部分があった。それは別に恋人が欲しいというわけではないし、そこに劣等感を抱いているわけでもない。
むしろつまらない自分には彼女を作るだなんて夢のまた夢だと思っていた。
青春なんてクソ喰らえ……とまではいかないが、アオトからすれば青春を満喫する行為など宝くじで一等を当てるくらい難易度の高いものだった。
だが、一応、自分は思春期真っ只中の高校2年生だという自覚をしていたし、もちろん恋愛に対する興味を持っていた。
そう、高校生活という名の短い青春を満喫する周囲との温度差を感じていたのだ。
「……これにしよう」
アオトは周囲に誰もいないことを確認してから件の恋愛小説を手に取り、席に戻ってページをめくり始めた。
文字から漂う恋の甘さと物語の展開、初々しい主人公とヒロインの心情、そしてもどかしい熱を帯びた雰囲気が、彼の心を一時的に現実から離れさせることに成功した。
◇◇◇
「……あ……もうこんな時間か」
アオトは没頭していた小説のエピローグを読み終えたところで、ようやくその世界から抜け出した。
しかし、おもむろに時計を見ると驚いた。
まるで時間が飛んでしまったかのようだった。
初めての経験だな……アオトは心の中に口にする。
同時に、聞き慣れたチャイムの音が彼を現実に引き戻し、18時になっていることに気が付いた。
図書室は静寂に包まれたまま、夕暮れの光が窓から差し込んでいて幻想的だったが、図書室の当番を任されている男子生徒は気怠そうな様子でアオトを見つめている。
——どうやら退室しろってことらしいな。他に人はいないし、俺がいるせいで帰れなかったんだろう。申し訳ない。
アオトは心で侘びながら読み終えた1冊を丁寧に棚へ戻すと、リュックを背負って図書室を後にして帰路に就く。
そして、先ほどまで没頭していた本の内容を思い返す。
ストーリーは至ってシンプルだった。
主人公である大学生の青年と、余命宣告を受けた高校生のヒロインが、残された僅かな時間を共に過ごすというもの。
そこで出会うたくさんの人々との交友やまだ見ぬ世界の探究は2人の幸せを増幅させていく。
しかし、不治の病は楽しい時間を過ごしていくごとにヒロインの体を蝕んでいき、やがて最後は悲しみに暮れながら死を迎えて感動のラストに繋がるという話だ。
「……」
無言で帰路に就くアオトは、シンプルながらきちんとした起承転結のあるストーリーを思い出して心を震わせた。
先にも述べた通り、彼には恋愛経験がない。
故に、これまでの人生で触れてこなかった恋愛を題材にした小説を読むことで、彼の恋愛というジャンルに対する意識は大きく変容したのだ。
更に、彼の胸のうちには恋愛観の変容以外の別の感情が芽生えていた。
「……本って凄いな」
空を眺めて呟く。
アオトは恋愛小説がもたらす凝縮されたストーリーとその儚さに魅了されていた。
時に、連ねられた活字の間に差し込まれる美しいイラストも、その完成された物語の味を数段上へと引き上げていた。
かつて、たかが活字とイラストだけで構成された話の何が面白いんだと思っていた自分のことを殴ってやりたくなっていた。
それくらい彼は恋愛小説に魅了されていたのだ。
そして、自分もそんな人の心を揺さぶれるような恋愛小説を書いてみたいと強く思っていた。
感情表現の乏しくないアオトの胸が初めて高鳴った瞬間だった。
やるべきこと、やりたいこと、やってみたいこと……彼の心にはそれらが確かに芽生えていた。
「モノは試しだな」
それから足早に帰宅したアオトは自室でノートパソコンを開くと、思いのままに自分なりの恋愛小説を書いてみることにした。
今日は土曜日なので、当然ながら明日は日曜日。
彼には何も予定がないので時間はたくさんある。
アオトは燃えるような情熱で小説を書き進めた。
勉強する合間を縫って、彼は物語のキャラクターやプロットを素早く練り上げていった。孤独な図書室での経験や、小説の中で感じた恋の甘さや切なさが、彼の思考と筆を力強く進めさせた。
夜遅くまで机に向かい、夢中で執筆に没頭し、頭を悩ませながらもオリジナルのストーリーを練り上げていった。
そして、日曜日の深夜、彼の小説はついに完成した。
慣れない執筆作業は中々進まなかったが、それは彼自身の成長や感情を込めた作品であり、新たな一歩を踏み出す勇気と希望が詰まった物語だった。
◇◇◇
その日も、アオトは窓際の最後席に座り、教室の雰囲気の外にいた。
周りではクラスメイトが夏休みの思い出を語り合い、笑い声が響いている中、彼は一人静かに自らが手がけた作品を読み返していた。ノートパソコンからテキストデータをスマホに入れたので、周りからバレることなくこそこそと読み進めている。
心の中では、誰かに自分の小説を読んでほしいという思いが渦巻いていたが、読んでもらえるような交友関係を持っていないが故に諦めていた。
唯一の友人に読んでもらうという手もあったが、その友人は恋愛小説を読むタイプまでもないので遠慮していた。
しかし、アオトにとって短時間で書き上げたこのオリジナルの恋愛小説は、1つの宝物であり、誰かに共有したいという欲求は強かった。
アオトは辺りを見回した。
わがままなお願いかもしれないが、日頃から本を読んでいて温厚そうな人が良いと彼は考えていた。
「……」
無言で教室内に視線を這わせるアオトだったが、そう都合良く見つかるはずがなかった。
そもそも交友関係が極端に狭い彼は、進んで話しかけることすら憚られるくらいだった。
諦めかけたアオトだったが、ふとした拍子に隣の席に座る星宮晴香——ハルカを視界に捉えた。
彼女は一人でスマホをいじって柔和な笑みを浮かべていた。
「……」
彼女はダメだな。めちゃくちゃギャルだし、きっと俺の小説を見せたら気持ち悪がられるのが目に見える……そう考えたアオトは、すぐさまハルカのことを対象から除外した。
ハルカは明るく、好奇心旺盛な性格で知られており、とっつきやすくてアオトも何度か話したことがある。いわば単なるクラスメイトなのだが、金髪でよく目立つギャルに読んでもらうのはさすがに躊躇していた。
それなら趣味の合わない唯一の友人に読まれて酷評される方がずっとマシだとすら思っていた。
「困ったな……」
アオトは首を垂らして眉を顰めた。
そこで交友関係が極端に狭くて一人でいることが多い自分を初めて呪う。
だが、彼の自分の書いた小説を誰かに読んでほしいという気持ちには変化はなく、最悪の場合、担任にでも見てもらおうかと考えていた。
「……はぁ、どうしようかな」
「降谷くん? どしたの?」
アオトが弱々しく息を吐いた瞬間だった。
ハルカはスマホをいじる手を止めたかと思いきや、アオトの方に席を近づけて覗き込んできた。
「……え」
アオトは唐突に真正面に美少女が現れたことで、思わずたじろいでしまう。
自分のことを認識してくれているんだなという驚きと、なぜ話しかけてきたのかという疑念が心に宿る。
同時に普段は横目で見ていた彼女の姿を真正面から捉えることで、妙な緊張感を抱くことになる。
そりゃそうだ。ハルカが纏う人当たりの良さそうな雰囲気は、根暗で朴訥なアオトとは大違いだった。
整えられた明るい金髪のボブカットとくりくりとした丸い瞳と薄い唇、真白い肌、当然のように第一ボタンは外されており、首元の赤いリボンは緩んでいる。
ただ、そんなラフな着崩し方とは対照的に、彼女は袖捲りをせずに長袖のシャツを着用しており、なぜかこの時期に厚めのストッキングを履いていた。周りは気にしていない様子だったが、孤独を極めて周りをよく見ているアオトは少しだけ疑問に思った。
「……星宮さん、俺に何か用?」
アオトは平静を取り繕って言葉を返す。
気になりはしたが、特に服装については言及しないことにした。
「んー? 星宮でいいよ~。それで、なんで怖い顔してたの? 悩み事でもあるの?」
ハルカは優しげな声色でアオトに尋ねたが、彼は内心で”よりにもよって……相手は星宮さんかぁ”と失礼なことを考えていた。
正直、彼からすれば彼女は別世界の住人なので、関わり合いたくないとすら思っていた。
「まあ、そんな感じ」
ぶっきらぼうな相槌を打つ。
「ふーん……降谷くんの悩みかぁ。気になるねぇ。ちょうど退屈してたし、降谷くんさえ良ければ、その悩みってやつを私に聞かせてよ。解決できちゃうかもだし?」
ハルカはにへらと笑い、やや前のめりになる。
アオトの席は窓際の最後席になるので、彼女から距離を詰められたら逃げ場はない。背後の窓から外へとダイブすれば話は別だが、ここは3階なのでそれをしたら命は儚く散ることになる。
アオトは覚悟を決めた。どう転ぶかわからないが、見た目のギャル感に反して人の良さそうなハルカに相談してみることにする。
「星宮は、小説とか読むか?」
「うん、読む読む、めちゃくちゃ読むよ。一番好きなのは恋愛小説かな~……って、あれ? もしかして降谷くんの悩みは……恋の悩み!? 誰誰? 誰を狙ってるのさ! うちのクラス? それとも他クラス? まさかの先輩とか!?」
「断固として違うからな」
「なーんだ。じゃあ何に悩んでるのさ?」
ハルカは間髪入れずに否定されたことで不満げな様子を露わにしつつも、続け様に聞いてきた。
「実は……いや、いいや。やっぱり辞めた」
アオトはスマホに映し出されたテキストデータを彼女に見せようとしたが、直前で躊躇してしまう。
自信のない彼の言葉は教室に蔓延る些細な雑音にかき消された。
「えー! 気になるじゃーん! 教えてよー!」
「……笑わないか?」
「笑わない笑わない」
「本当に?」
「うん!」
「わかった。じゃあ、見せる」
わくわくした顔つきで食い下がるハルカに押し負けたアオトは、ついに意を決して自身のスマホを彼女に手渡した。
「……これ、小説? 降谷くんが書いたの?」
アオトのスマホを受け取ったハルカは僅かに目を見開いて驚きを露わにしていた。どこか感心したような声色でもある。
「まあ、恥ずかしい話なんだが……恋愛小説を書いてみたんだ」
「へー、じゃあ、悩みっていうのはそれ関連?」
「察してくれ」
「うんうん、誰かに読んでほしいからってことだね」
「ああ……俺みたいなやつが、おかしいだろ?」
「別にー、私も似たようなことしてるし気にしないよ。それより、私って恋愛小説は大好物だから、降谷くんさえ良ければ少し読んであげてもいいよ? 感想とかほしいでしょ?」
「ほんとか?」
アオトは願ってもみなかったハルカからの提案に対して食い気味に返事をした。まさかまさかの展開に心を躍らせる。
「うん。ゆっくり読みたいから、データちょうだい?」
「わ、わかった。どうやってあげればいい? LINEとかなら簡単に送れるんだけど……」
「……んー、じゃあ、LINEにしよっか。QR、追加して?」
「え? いいのか?」
ハルカが手に持つスマホにはLINEのQRコードが映し出されていたが、それを見たアオトは、本当に自分が友達登録していいのか遠慮気味になった。
「そっちが言ったんでしょ? そもそも、クラスメイトなのにLINE交換してないのなんて、降谷くんくらいだよ?」
「え? そうなの?」
「うん。だから早く追加してそのデータ送ってよ」
「……送った」
アオトはおずおずとハルカのQRコードを読み取り、そのままテキストデータを送りつけた。
とんとん拍子で母親以外の女性の連絡先をゲットしたのだった。
彼にとってのLINEとは、ニュースを見るくらいしか使い道がなかったので、こうして見知った人物がトーク履歴に残るのは不思議な気分だった。
「ありがと。こう見えても、ハルカちゃんは恋愛ものにはうるさいから覚悟しててね~?」
ハルカの言葉を聞いて、ほっと一安心したアオトは胸に手を当て息を吐く。
「……辛口評価は程々にお願いします」
文字数は一万文字程度の短編小説となっており、一日あれば読み終えることはできる文量である。
「感想は放課後でいい? あまり長い時間はつくれないけど」
「ああ。よろしく頼む」
「はーい」
ハルカはにこりと微笑んで体勢を直してスマホに視線を戻すと、器用に画面をスクロールさせながらアオト作の恋愛小説に目を通し始めた。
アオトはそんな彼女から目を逸らして窓の外を眺め、落ち着いた様子で嘆息する。
少し不安な気持ちを抱えながらも、喜びに満ちた気持ちで小説のデータを送り、その瞬間、自分の作品が他人の目に触れる喜びと緊張が入り混じった。
星宮晴香という予想だにしない《《読者》》の反応が気になりながらも、彼は自信を持って自分の作品を共有することに決意したのだった。
今日の放課後には読み終えて感想をくれるということなので、アオトは高揚感を胸に授業を受けて放課後が来るのをじっと待ったのだった。
◇◇◇
時刻は午後4時。
クラスメイトたちは各々が帰宅したり、所属する部活動へと顔を出しており、教室はアオトとハルカの2人きりになっていた。互いに自分の席に座り、そんな2人のことを窓から差し込む夕暮れの光が柔らかく照らしている。
そんな教室で2人きりになったアオトとハルカの間には、緊張と不安が交錯していた。
一方は初めてのオリジナル恋愛小説を読んでもらった高揚感と不安に押しつぶされそうになりつつも、渾身の一作を評価してもらえる胸の高鳴りを感じている。対して、もう一方は悩ましげな顔つきで首を傾げながらスマホをじっくり見つめていた。
「……星宮、どうだった?」
「んー、はっきり言っていい?」
躊躇いながら声をかけたアオトとは対照的に、ハルカはサバサバした様子だった。
「ああ」
アオトは期待を込めてごくりと息を呑んだ。
しかし、溜め息を吐きながら口を開くハルカの一言に絶句することになる。
「はぁぁぁぁ、全ッ然だめかなぁ……」
「え? ど、どこがダメだった……?」
「まず、リアリティがなさすぎ。高校を舞台にした恋愛は悪くないけど、主人公とヒロインの関係性が曖昧だし、キュンキュンするはずのセリフとかシーンも淡白すぎるかな。それに、恋愛小説特有のヒロインが余命宣告を受ける展開は悪くないけど、2人の関係がまとまらないままヒロインの子が死んじゃったから、読者は置いてけぼりって感じ? まあ、降谷くんは勉強できるタイプだろうし小説としてはかなり読めるよ。文章力もあるから読んでて疲れたりはしなかったしね。でも、恋愛小説に求めるようなキュンキュンは全く味わえなかったかな~~」
ハルカは、のびのびやんわりとした口調ではあったが、思いの丈を隠すことなく素直な意見を口にした。
言葉には、アオトに小説を書いた経験はもちろんのこと、おまけに恋愛経験まで全くないことを指摘する厳しさが暗ににじみ出ていた。
しかし、それはアオトもわかっていた。
期待していたような評価はされなかったが、確かにそう言われてみると不自然な点がいくつも散見された。
特に主人公の男から見たヒロインのポジションや境遇、1人1人の物語やラストまでの成長とエンディングの盛り上がりに関してはかなりイマイチだと、アオトは思っていた。
「……キュンキュンしないか」
「うん。恋愛小説に求める、主人公とヒロインのチグハグしてヤキモキするシーンが全くなかったね。もうちょっとドキドキ感と初々しい二人の空気感を味わいたいかな~。恋愛パート以外もあんまり良くないけど、特にそこの部分が台無しって感じ。これだと情景が思い浮かばないし、2人の表情とか感情がわかりにくいよ。これじゃネットでバズれないよ? 」
ハルカは肩をすくめて乾いた笑みを浮かべた。
「確かになぁ。うーん……そっか」
ハルカの感想を聞いたアオトはショックを受けると、落胆の色を隠すことなく俯いた。
そして、恋愛を経験したことがない自分が描いた作品には、確かに不足があったかもしれないと考えた。それでも、彼はハルカの率直な意見に感謝し、今後の成長に繋げることを決意していた。
同時に他人の小説を読んで具体性のある感想を述べてくれたハルカに対して少しだけ興味が湧いていた。
「ちなみに一つ気になったんだが、星宮は恋愛小説をよく読むって言ってたよな。結構な読書家だったりするのか?」
アオトは体勢を整えてハルカの方に向き直りながら尋ねた。
彼女はやけに小説に対する評価がしっかりしていたし、どことなく慣れた様子で捲し立てていた。
まるで評論家だ。
「……うん~、まあ、そんな感じかな。実は、私ってイラストを描くのが好きなんだけど、色んな発想を得るために恋愛小説はたくさん読んでるんだ」
「ふーん、どんなイラストを描いてるんだ?」
「んー、待ってね……ほら、こういうの。あまり見ないで、恥ずかしいから」
恥ずかしいからと言いつつも、ハルカは自身のスマホをアオトに隠すことなく見せてきた。
スマホには多彩な色合いで構成された美しいイラストが表示されていた。そういう方面に疎いアオトがパッと見る限り、正直プロかと思うくらいの出来栄えだった。制服を着た男女が手を取り合い、公園の遊具を背に夕焼けの道を歩くそのイラストは、幻想的なあまり思わず目を奪われてしまう。
とてもアマチュアとは思えないレベルだった。
「凄いな」
アオトは心の底から感動してしまい、それ以上の言葉が出てこなかった。
だが、嘘偽りない褒め言葉を耳にしたハルカは照れくさそうに笑みをこぼす。
「まあね~。まだ家族とか学校の友達には言ってないんだけど、みんなから注目されるようなイラストレーターになりたいんだ。売れてるトップレベルの人たちに比べるとまだまだだけどね」
ハルカは照れくさそうに微笑んでいたが、その言葉には確かな余裕と自信を感じさせた。それも妙なくらいに。だが、きっとそれこそ、彼女が1人で努力を積んできた結果なのだろうと、アオトは解釈する。
「……というか、誰にも言ってない将来の夢を俺なんかに伝えて大丈夫だったか?」
「うん。だって、降谷くんは勇気を振り絞って私にこの小説を読ませてくれたんでしょ? それならこっちも隠すことはないかなって思ったんだ。それに、降谷くんって友達いなさそうだし、バラしたりもしないでしょ?」
「最後の一言は余計だな」
「事実でしょ?」
「ふんっ……」
アオトはぶっきらぼうに鼻で笑ってみせた。イエスともノーとも答えてないが、無論、バラすつもりはない。
ただ単に、初めて他人から心のうちを明かされて信頼された感覚に嬉しさを感じていただけだった。
ハルカ自身がどう感じているかは別して、アオトはそうだった。
「……良いこと思いついた」
しばしの沈黙を挟んだのち、ハルカはパッと閃いたような顔つきになる。
どこか意味ありげな表情だ。
「良いこと?」
「うん、今度2人でお出掛けしよっか」
「へ? デートってことか?」
唐突なハルカからの提案を聞いたアオトは、素っ頓狂な声を漏らす。
すると、彼女はわたわたと取り乱しながら口を開く。
「あっ、た、ただお互いの小説とイラストのためにそういう経験を積む練習をしてみない? っていう提案だから、変な勘違いはしないでね。ほんとに、違うから」
——真っ向から否定されたら、それはそれで悲しいな。
アオトは心の中で涙を流したが、ハルカは続け様に口を開く。
「それに名前の相性もいい感じじゃない? 降谷くんの下の名前は……確か、アオトだったでしょ? それで、私の下の名前はハルカ。くっつけたらなんと、アオハルになるんだよね~」
「あおはる……って何だ?」
アオトは地方のご当地B級グルメを耳にした時のような反応を見せる。
無理もない。彼は青春とは無縁の学生なのだから。
「アオハルはアオハルだよ。青い春で青春。わかる?」
「あー……読み方を変えると青春ってことか。俺には縁のない世界だな」
「まあまあ」
「……それで、そのお出掛けってのは何が目的なんだ?」
アオトは互いの名前をもじったコンビ名などに興味なんてなかったので、特に深入りすることなく話題を戻した。
「私が単に降谷くんが書く恋愛小説を題材にしてイラストを描いてみたくなっただけかな? 降谷くんに恋愛経験がないのは当然のこととして、こう見えて私も恋人なんてできたことないし、誰かを好きになったこともないんだよね。そんな2人がタッグを組むのって王道じゃない?」
恋愛経験がないのは当然と言われたことで、アオトは少し反論したい気持ちに駆られたが、覆しようがない事実だったのでそっと胸にしまい込む。
そんなことより、アオト的にはハルカほどのルックスを持つ人が、自分と同じくそういった経験がないということに驚いていた。
「星宮も俺と一緒なんだな」
「……まあ、私はたくさん告白されたことがあるし、色んな男子と出かけたこともあるから、降谷くんとは違うよ?」
ハルカは同意を示したアオトの目を見て鼻で笑った。
確かに、2人を同類というには無理がある。それくらいクラスでもアオトは目立たない存在だったし、対してハルカは明るく活発でクラスでもよく目立つ方だった。
特定の誰かと仲が良いというわけでもなく、男女問わず満遍なく多くのクラスメイトと話している姿をアオトは見たことがある。
彼はそんな彼女に恋人や好きな人ができたことないなんて信じられなかった。だが、本人がそういうなら疑うわけにもいかない。
「……モテモテなんだな」
「うーん……モテモテかぁ。私のことを何も知らないで勘違いしてる人が多いだけだと思うけどね。外面がいくら良くても内面がダメだったら遠慮願いたいでしょ? 互いの立場とか性格、容姿、全部含めて恋愛なの。だから恋愛は簡単じゃないんだよ。だって、実際に降谷くんは私がどんな人なのか何も知らないでしょ?」
「まあ……そうだな。でも、俺に話しかけてくれる優しい人ってことくらいはわかるぞ」
アオトは思い悩んでいる他人に声をかけてやれるハルカのことをかなり評価していた。
ハルカの見た目は金髪のギャルでかなり癖があるが、そこはかとなく感じる人当たりの良さと優しさもあった。
アオトは少し会話を交わしただけで、ハルカのことを悪い人ではないと思っていたのだ。
「それだけで、私のことを優しい人だって思うんだね~」
「ああ、優しいと思うぞ。少なくとも、影でこそこそ俺の悪口を言う奴らとは違うと思う。でも、俺は星宮のことをほんの少ししか知らないから、きっと無鉄砲に告白してくる奴らと変わらないんだろうな」
ハルカはモテるタイプであるが故に当事者意識の高そうなことを言っていたが、アオトは他人から恋愛的な好意を向けられたことがないので、殆ど共感することができなかった。
しかし、彼女の優しさは身に沁みて実感していた。
「そういう意味では一緒かもね」
「だろ?」
アオトは特段反論するでもなく同意を示す。
彼は自分自身が彼女とは釣り合わないという事実を心のうちで理解していた。
そんな端的な返事をした彼に対して、ハルカは唐突に真剣な顔つきになり、
「……でも、あんまり、他人に期待しないほうがいいと思うよ。本当の私は優しくないかもしれないしね?」
と、何かに取り憑かれたかのように言った。
アオトはその現実味のある言い方がどこか気になったが、それでもハルカの事を信用した。
「俺は相手に過度な期待はしないけど、裏切られるその時までは相手を信じるよ。もちろん、星宮が優しいってことも信じてる。それに俺は相手を外見だけで判断はしないつもりだ」
「え~、なんか絵本の騎士様みたいだね。じゃあ、私がピンチになったら助けてくれるのかな?」
ハルカは口元に手を当てて、わざとらしくら 驚いた素振りを見せた。まるで、品定めをするかのように、瞳を細めてアオトのことをジッと見ている。
「まあ、時と場合にもよるけど、本当に困っている時はどうにかしてやらなくもないぞ」
「じゃあ、その時はお願いしちゃおうかな~」
「お互いに覚えていたらな」
アオトは茶化し口調のハルカの言葉に対して、呆れながらも乗ってあげた。
彼女とは深い関係になることはなさそうだと、彼は思っているので、あまり間に受けずに適当に返事をするに留める。
「はいはい。それで、お出掛けには行ってくれる?」
カスミはふとアオトから目を逸らして脱線しかけた話のレールを元に戻した。
「そうだな。俺も少し気になるし、一緒にそういうことをするのは別に構わないぞ。それより、本当にいいのか? 俺みたいな根暗と一緒にいたら変な噂が立つかもしれないぞ?」
「んー、大丈夫。私たちはお互いの目的のために協力するだけだから付き合ってるわけじゃないしね~」
アオトの気遣いに対して、ハルカは手をひらひらとはためかせながら軽くあしらって答えた。
まるで、照明に群がる羽虫を払うかのような仕草だ。無理に距離詰めたら手が飛んできそうだ。
「まあ、それもそうだな。わかった。じゃあ、今度の日曜日は空いてるか?」
「うん。どうせなら映画でも見よっか。お昼くらいに駅に集合でいい?」
「わかった」
アオトは特に表情を変えることなく首肯したが、心の中では初めて異性と遊ぶことに対して妙な気分に陥っていた。
「……ってかやば! もう4時半じゃん!」
アオトが夕焼けを見て目を細めていると、ハルカはハッとした表情で勢いよく席を立ち、そそくさと帰り支度を始めた。
「何か急ぎの用事でもあったのか?」
「うん、今日は5時からクラスのみんなでカラオケって話だったじゃん? 降谷くんも来る?」
「いや、大丈夫だ」
ハルカは特に何の気なしにアオトを誘っていたが、肝心のアオトは食い気味に断りを入れて彼女から視線を逸らした。
彼からすれば、彼女が言うような”みんな”の中に自分が入り込める自信も気概もなかったのだ。
「そっか。じゃあ、次の日曜日ね~」
「おう、またな」
ハルカがバタバタと駆け足で教室から出ていき、アオトは必然的に一人きりになった。
もちろん、アオトには用事なんて全くないので、ハルカが立ち去ってからすぐに自身も帰り支度を始めた。
彼は冷静なフリをしていたが、実は内心はバクバクだった。
あまりにも非現実的なハルカとのデートを日曜日に控えているという事実に困惑する。
「……夢か?」
相容れない存在だと思っていたのに、まさかこんなことが起きるなんて……。アオトは胸に手を当て早くなる鼓動をその身で感じた。
彼は自分に恋人ができるだなんて考えたこともなかったし、それは今も変わらなかった。
しかし、ハルカの様子を見る限り自分への嫌悪は感じられなかったので、勘違いしかけたウブな心が宿っているのも確かだった。
「ダメだ。切り替えよう」
アオトは空気を入れ替えるようにして大きく息を吐いた。
付き合うとか付き合わないとかそういうのじゃない。これは恋愛小説を書きたい自分と素晴らしいイラストを手がける彼女の協力関係に過ぎない……彼は、そう胸中で整理をつけて心を入れ替える。
「……帰ろ」
アオトは重たいリュックを背負って閑散とした校舎を後にすると、夕陽が空を染め、夏の終わりの風が心地よく吹き抜ける中、帰路に就いたのだった。
◇◇◇◇
札幌駅、通称札駅には様々なテナントが入っており、高校生から大人まで多くの人々が楽しめるようになっている。
構内の開けた空間には人々が行き交い、活気に満ちている。高い天井と広々としたスペースが、待ち合わせ場所にふさわしい穏やかな雰囲気を演出している。
大きく設けられた窓や出入り口の扉、吹き抜けになっていて高い天井の照明からは明るい光が差し込み、駅の喧騒と共に微かな風が流れていた。
その中で、待ち合わせ場所であるベンチに座るアオトの姿があった。
彼は周囲の様子を静かに眺めながら、時折腕時計に視線を移し、緊張と期待が入り混じった表情を浮かべて待ち合わせ相手であるハルカの到着を心待ちにしていた。
「……おまたせーーーー!」
待ち合わせの時刻を過ぎてから待つこと5分程。
ハルカは手を振りながら駆け足でやってきた。
彼は何の気なしに彼女の全身を下から上まで軽く眺めた。
上はチャコール色の厚手のカーディガンを羽織り、中には真白いトップスを身に纏っていた。
下にはブルーのジーンズを合わせており、シンプルであるが故に素材の良さが引き立っているのがわかる。
また、肩には小さなバッグを下げ、耳には煌びやかなイヤリングが光っている。とても高校二年生とは思えない大人びたコーデだ。
ほっそりしていて足も長い。中肉中背で取り柄のないアオトとは対照的だ。
「ふぅ、遅れてごめんね~」
「大丈夫だ」
「それで……どうかな?」
ハルカはアオトに自身のスタイルを見せつけるかのように、ぐるりと回ってモデルのようなポーズを決めている。
その美しい姿に通りすがりの人々も一瞬立ち止まり、その魅力に見惚れてしまうような雰囲気が漂っていた。
それはアオトも同様で、ハルカの姿を見てごくりと息を呑んでいた。
「え?」
「私の服装だよ。似合う?」
やっぱり容姿が整っていてよく目立つということはわかっていても、どんな言葉をかけてあげるが正解なのか……それがよくわからなかったアオトは言葉に詰まる。
「……まあ……ちょっと暑そうだな。今日は30度近くあるぞ?」
恋人っぽい感じをイメージするのならこの場面は間違いなく洋服を褒めるべきなのだが、照れ臭かったアオトはおかしな返事をしてしまった。
「はい。減点!」
ハルカはびしっとアオトに指を差す。
「え?」
「こういう時は気になる事があったとしても、素直に相手の服装を褒めるんだよ? 可愛いね、似合ってるねって言うのが正解かな。はっきりと思った事を言葉にするんだよ。可愛いと思ったら可愛い、似合ってるって思ったら似合ってるって……ね?」
ハルカは不満そうな表情を浮かべてアオトの隣に座る。
同時にふわりと甘めの香水の香りが漂い、慣れてないアオトは僅かに鼻を啜る。
「ふむふむ……参考になるな」
アオトは黒いスラックスのポケットから小さなメモ帳を取り出すと、一語一句丁寧に書き記していく。
その姿を見たハルカは頬を膨らませて更に不満気になるが、アオトは尚もメモを取り続ける。
「はぁぁぁぁ……降谷くん、メモはデートが終わってから取ってね。相手の女の子を置いてけぼりにしたらダメなんだよ!」
ハルカは大きな溜め息を吐いて呆れを露わにすると、少し強めの口調でアオトに注意した。彼女の期待とは裏腹に、アオトの言動は彼女の気持ちを満たすことができなかったのだ。
「ん、悪い。でも、本当に暑くないか? 下が半袖なら脱いだほうがいいと思うぞ?」
アオトはメモ帳をポケットに戻して謝辞を述べたが、今一度ハルカの姿を見るとやはり季節感があってないという感想が一番に出てきた。
「まあ……それはそれだよ」
ハルカは視線を動かしながら動揺していたが、アオトとしてもそれ以上は特に追求はしなかった。
単に彼女が天気予報を見てこなかったのだろう。それから、オシャレは我慢とも言うし……そういう事なのだろう、と結論付ける。
「行くか」
「うん」
アオトはハルカと少しの間を開けて隣を歩く。向かう先はエレベーターだ。7階に映画館があるのでそこを目指して進んでいく。
やがて、7階に到着すると、人々で賑わう通路を進んでいった。
ハルカは持ち前の綺麗な金髪が風になびく中、アオトの隣を楽しそうに歩いており、その姿はまるで夏の風をそのまま纏ったかように爽やかだった。
一方のアオトは、彼女の魅力に少し圧倒されながらも、彼女の隣を歩きながら気分を高めていた。
普段は比較的インドアなアオトからすれば、こうして映画館で映画を見るのは親に連れられて行った幼少期以来なので新鮮なことこの上なかった。
もちろん、ハルカと二人きりになるワクワク感も無くはなかったが、それ以上に映画館で見る映画への期待が高まっていた。
やがて、適当に会話を交わしながら歩くアオトと晴香は、気がついたら映画館のロビーに到着していた。
「降谷くん、何が見たいの?」
「そうだなぁ」
二人は映画館のロビーに立つと、小さな画面に映し出されている上映中の映画一覧に目を通した。
アオトは顎に手を当てじっくり悩み抜いた末に、唯一見覚えのある映画を指差した。
「あれはどうだ」
「……悪くないけど、どう見ても子供向け映画だよね、あれ」
「子供の頃なんかは毎週日曜日は早起きしてテレビで見てただろ? アニメに比べると映画は壮大だから結構面白いぞ?」
誰から見てもその映画は子供向けで対象年齢は3歳から5歳をターゲットにしていた。誰もが一度は見たことがある多種多様なパンが主人公の国民的キッズアニメである。決して高校生の男女がデートで見るような映画ではない。ただ、これは不器用なアオトなりの冗談だった。
「はい、減点。大して親しくもない女の子と2人で見る映画じゃないよね。子連れならわかるけどさ」
ハルカは呆れた様子で減点を言い渡すと、やれやれと首を横に振った。真顔で紡がれたアオトの冗談を本気と捉えてしまった結果である。
「うーん……」
2度目の減点を食らうアオトはムッと眉を顰めた。
彼からすればほんの冗談のつもりだったのだが、あまりにも無表情すぎたばかりにハルカには通じなかったらしい。
「ここは無難に恋愛映画はどうかな?」
ハルカは悩ましげなアオトの肩をつんつんと突く。
「そうだな。でも、恋愛映画は上映まで結構時間空いちゃうし、ホラー映画にしないか? 星宮がそういうの平気ならだけど、どうだ?」
「ふっふっふっ……何を隠そう、私ははホラー映画が大の苦手だよ! 降谷くんは平気?」
「俺はそういうのを見てもあんまり何も感じないな」
苦手だというのに乗り気で自信ありげなハルカに対して、アオトは元々感情表現が苦手だからかかなり淡白な返答だった。
「この映画、ネットで大バズりしてたんだけど、すっごい怖いらしいよ? 降谷くんでも声を上げてびっくりしちゃうかもねー」
「それはそれで楽しみだな。じゃあ、早速チケットを買うか」
「うん。そうだね」
どの映画を見るのか決めたアオトとハルカは二人並んで発券機へ向かうと、適当に座席を決めてチケットを購入した。
そして、次に二人はポップコーンとドリンクを買うために売店へと向かう。
「降谷くんはポップコーンは何味が好き?」
ハルカは頭ひとつ分背の高いアオトを見上げながら聞いてきた。
まるで彼のことを試すかのような目つきである。
「断然キャラメルだな。それ以外にありえない」
「いっしょー! やっぱポップコーンといえばキャラメルだよねー。でも、1人1つだと多そうだし、ポップコーンが1つとドリンクが2つ付いてくるセットにしよっか。飲み物はどうする?」
ハルカはアオトの答えに満足したのか力強く何度も頷いた。
互いに、無難な塩味や、変わり種だが確かに美味しい醤油バター味等ではなく、甘塩っぱいキャラメル味をチョイスしたのは、ほんの小さな初めての共通点であった。
「烏龍茶かな。星宮は?」
「私はオレンジジュースかな。昔から好きなんだよね~。覚えておいてね?」
「善処する」
アオトはハルカからメモを取っちゃダメと言われていたので、頭の片隅に記憶を残しておくことにした。
今後何かの役に立つことを願って。
「じゃあ、頼んでくるから待ってて? お金は後でまとめて計算しよ」
ハルカはちょうど空き始めた売店のカウンターへ一目散に向かうと、慣れた様子で注文を済ませて数分後にはトレーを手にアオトの元へ戻ってきた。
アオトはもしも自分だったら口下手だからもう少し時間がかかりそうだなと思い、慣れた様子で行動してくれたハルカへの感謝の言葉が自然と口から溢れる。
「星宮、俺の分までありがとう」
「そういうのは言えるんだね~」
ハルカは少し驚いた様子を見せる。
「当たり前だろ。わざわざ買ってきてもらったんだからな。それより、チケットを買うのが少し遅かったから上映開始までもうほとんど時間がなさそうだぞ。急ごうぜ」
「そうだね」
アオトはハルカと一緒に入場し、指定席に腰を下ろして息をつく。
日曜の昼間だからかそれなりに人が入ってる。
話題のホラー映画ということもあり、場内にはカップルが多い。
「ふぅ……いい席だな」
「そうだね。でも、ちょっと席の間隔が近くない?」
アオトは柔らかな座席のソファに背を預けて寛いでいたが、隣に座るハルカは何か気になるのかそわそわとしていた。
「そうか?」
「うん……というか……」
ハルカは薄暗い場内の中で手に持つチケットと、辺りの様子を交互に眺めていた。
映画館自体に来たのが久しすぎるアオトには何のことかわからない。
「どうした?」
アオトは少し距離を詰めてハルカに尋ねた。
すると、彼女は何かを理解したのか、ハッとした様子で口元を手で覆って目を見開いた。
「……ここカップルシートだった」
ハルカは頬を引くつかせながら口にしたが、アオトからすれば特に気にすることでもない。
「あー、別にいいんじゃないか?」
カップルシートは隣接し合う互いの間にあるはずの肘掛けがなく、席全体がやや広めに作られており、ゆっくりと映画を見ることができるからだ。足を伸ばせるフラットシートになっていてかなりリラックスできる。
だが、ハルカは何か言いだけな様子だった。
「私、ホラーとかすっごい苦手なの」
「言ってたな」
「いつもは女友達と一緒に見に行くんだけど、毎回怖がりすぎて泣きそうになってるんだー」
ハルカはCMが流れる巨大スクリーンを虚ろな瞳で見つめていたが、その焦点は全くと言っていいほど合っていなかった。
「それで?」
「今日はあんまり親しくない降谷くんが一緒でしょ? 肘掛けもないでしょ? カップルシートは座席が広くて自由が効くでしょ? どういうことかわかる?」
ハルカは乾いた笑みを浮かべていた。
そんな彼女の笑みを見て、アオトは考えた。
普段は女友達と一緒にホラー映画を見に行っていて、その度に泣きそうになっていて、今回は肘掛けがなくて広々として自由が効くカップルシート……二人を妨げるものは何もないということだ。
恋愛に疎い俺だって知ってるし、よくドラマかなんかで見たことがある。男女ペアで肝試しをしたら怖がった女性が男性と接近して、吊り橋効果とやらで距離が縮まるというアレだ。
アオトは怯えるハルカを見て先の展開を想像する。
「……ん? まさか……怖がった拍子に抱きついてきたり——」
「——ううん、手が出たらごめんね? 私、本当に怖い時はなりふり構わず暴れちゃうかも! 許してね? それに、暗いからってどさくさに紛れて変なことしたら……わかってるよね? 後、狭い場所はあまり得意じゃないから、少しだけ離れてみてくれると助かるかな~」
ハルカはアオトの言葉を遮り、胸の前で両の拳を力強く握り込むと、彼の想像した展開を大きく裏切ってきた。
「……はいよ」
溜め息混じりに返事をしたアオトはハルカと距離を取り端の方に移動する。
すると、ハルカはいよいよ暑くなったのか、カーディガンを脱いでマントのように肩にかけた。
「暑かったか?」
「うん。さすがにね。でも、降谷くんは半袖のTシャツしか着てないから、逆に寒くなりそうだけど」
「確かに……かなり空調が効いてるし、ホラーで怖くなったら寒くなっちゃうかもな」
アオトが冗談混じりに言うと同時に、場内は静けさを纏って暗くなっていく。
すっかり映画館のモードになった2人の間には沈黙が訪れる。
やがて、しばしのCMを挟んでから映画が始まったのだが、上映中、ハルカがびっくりして体を跳ねさせたり、広々とした座席の中で些か激しい挙動を見せることで、そこからふんわりと漂う女の子らしい良い香りと香水の甘い香りに気が散ってしまい、アオトはあまり映画に集中できていなかった。
まるでわざとアオトの気を引こうとしているのではないかと思うくらいに、ハルカは一挙手一投足激し目の動きをしていたのだ。
1度だけ、アオトがハルカに視線を向けたタイミングで、彼女が肩にかけていたカーディガンがはらりと落ちたのだが、その際に彼は彼女の右肘の辺りに深い火傷のような傷痕があるのを目にした。
デリカシーを保ち傷痕について尋ねる事はしなかったが、やはり激しい挙動と甘い香りも相まって、アオトは全く映画の世界に没入できなくなったのだった。
◇◇◇
やがて映画が終わると、札駅内の小綺麗なカフェに入った二人は映画の余韻に浸っていた。
「いやぁ、めちゃくちゃ怖かったねー。私ってばビビりなのにああいうのついつい見ちゃうんだよね。ネットでバズる理由もわかるよ」
ハルカは小刻みに震える自身の体を抱きしめながらも、その口調は飛び跳ねているかのように楽しそうだった。
「5分に1回くらいは悲鳴上げてたな。特に空から大量の生首が降ってくるシーンなんかはずっと叫んでたもんな」
対して、アオトは余裕そうな面持ちで口角を上げると、おもむろにアイスティーを啜ったが、その様子を見たハルカは頬を膨らませてすぐさま反論する。
「降谷くんだって暗い場所からオバケが出てきたシーンでビクってなってたじゃん! 『俺は何も感じないぜ☆彡』って言ってたのにねぇ~?」
「……まあな」
アオトは茶化してくるハルカから目を逸らした。
彼がオバケが出たシーンに反応したのは事実だが、それは別にホラー映画そのものに反応したわけじゃなかった。
本当は上映中に繰り出されるハルカの一挙手一投足が気になったせいだった。
肘掛けという名の防御壁が存在しないカップルシートだったからこそ、ハルカは無意識に動き回って時折アオトの体に触れてくることもあった。ホラーとは違ってそっち方面には全く耐性がないアオトは、その度に肩を振るわせて平静を取り繕うことに尽力していたのだ。
だが、そんなことを意識しているとバレたら嫌われる。そう思った彼は特に言い返さずに言葉を濁す。
「確かに、映画はまあまあだったな」
「ぷぷぷっ! やっぱりあの映画はホラー耐性のある降谷くんでもダメだったかぁ~。始まりから終わりまでずっと怖かったもんね」
「そうだな」
「……それで、どう?」
ハルカは冷たいオレンジジュースのストローに口をつけると、アオトに視線を向けて首を傾げた。
「何が?」
「小説だよ。2時間ちょっとだけだったけど女の子と一緒に過ごしたんだし、少しはアイディアが湧いてきたんじゃない?」
「あー、そうだな。色々とな」
正直言うと、アオトはハルカから漂う甘い香りとふとした無意識なボディタッチの応酬のせいで今の段階では頭の中に小説のアイディアは湧いていなかった。
記憶に新しいのは、彼女の右肘の辺りに見えた深い火傷のような傷痕だけだった。
「ふーん……じゃあ近いうちに今日のデートのことを小説にしてみてよ。私はそれを参考にしてイラストを描いてみるから、そうすればお互いに成長できる気がしない? 取り敢えず、来週の日曜日も予定入れとくね」
「次会うのは再来週かそれ以降にできないか? 定期テストが近いしな」
ぽちぽちと素早くスマホをいじっているハルカに対して、アオトは頭の中で近々の予定を確認した。
小説を書きつつもハルカとデートをして、尚且つ勉強もしたいので、明日からのテスト期間は遊ぶ時間には充てたくなかった。
「うーん……テストかぁ。うん、わかったよ」
「もしかしてテストがあることを忘れてたのか?」
「い、いや……別に、まあ、忘れてたかな?」
「少しは勉強した方がいいぞ」
「うっ……善処します」
ハルカは不服そうに唇を尖らせており、それ以上はテストに関する話題は出してほしくなさそうだったので、気を利かせたアオトは別の話題に切り替えることにする。
「ところで、話は変わるが星宮ぐらい絵が上手いなら、俺なんかとやるよりも良い相手がいるんじゃないか? わかっていると思うが俺なんてズブの素人だぞ?」
自虐ネタでもなんでもなく、アオトは何の実績もないズブの素人だった。素人に毛すら生えてないそこら辺に転がる路傍の石と何ら変わりない存在だ。
デートが始まってから言うことでもないと彼もわかっていたが、やはりなぜ自分なのかが気になっていた。
「前も言ったでしょ? 私のことは気にしないでって。これは単なる興味だから」
「でも……」
「いいの。付き合ってるわけじゃないんだし、お互いの為になるならそれでいいでしょ?」
食い下がるアオトに対してハルカは尚も言葉を続けた。お互いの為という部分が少し強調されたような気もしたが、恋人関係ではないという彼女からの隠れた主張だろう。
「まあ、そうなんだけど、やっぱり俺なんかの為にそこまでしてくれるのは申し訳ないというか……理由が気になるんだよな」
アオトはそれでもまだハルカが自分に声をかけてくれて、尚且つ小説まで読んでくれた本当の理由が知りたかった。
「ちゃんとした理由が知りたい?」
「ああ」
「降谷くんのことが好きだから」
真っ直ぐな瞳をアオトに向けながらハルカは言葉を紡いだ。
その瞬間。アオトの心臓の鼓動が急速に早くなる。
「え?」
アオトが素っ頓狂な声をあげで呆然としたのとほぼ同時。
ハルカはにやりと口角を上げて、したり顔になる。
「ぷっ! じょーだんだよ! 騙された? こういうのも恋人っぽいし、経験しておくのも悪くないでしょ? とにかく、私のことは気にしないでいいから、来週までに小説にしてみてよ。いい?」
ハルカは無邪気な子供のようにイタズラな笑みを浮かべていたが、向かいに座るアオトからすれば弄ばれた気分だった。
しかし、自己肯定感が低く、恋愛に疎いアオトは”女の子なんて皆そんなもんだ”と心の中で早々に納得し、先ほどまでの安直な自分の思考回路を恨んだ。
「はぁぁぁぁ……わかったよ。今日の経験を基に書いてみるよ」
アオトは大きく溜め息を吐いたが特に不満をこぼす事なく了承した。
彼からすればハルカほど絵が上手い人が自分に協力してくれるなら断る理由はなかった。
たとえそれが彼女の天邪鬼からくる突発的で曖昧な関係であっても、彼からすれば自分の描いた恋愛小説をもとにイラストを描いてくれるなんて夢みたいな話だった。
「うんうん。じゃあ、私はこの後用事があるから先に帰るけど、降谷くんは?」
「俺も、もうそろそろ帰るよ。色々とメモも取りたいし、今は結構良い案が出てきそうだから良い感じに書ける気がする」
「そう……それじゃあ、また明日!」
ハルカはストローに口をつけてオレンジジュースを一気に飲み干すと、すっきりとした顔つきで席を立った。
まだ時刻は午後3時を回ったばかりで解散するには早い時間だったが、まともな顔合わせは初めてだったので互いにやや遠慮がちなのがわかる。
「ああ、またな。それと、星宮、今日は俺に付き合ってくれてありがとう。その……遅くなったけど服も似合ってるし、今日は一緒に過ごせて楽しかった。また、よろしく頼む」
アオトはどこか照れくさそうに頬をかきながらも、真剣な瞳でハルカを見据えてお礼の言葉を告げる。
彼的には好意を向けられることが得意でなさそうなハルカにはあまりよろしくないかと思っていたが、やはり真面目な性格故か、これはしっかりと言葉にして伝えたい部分だった。
「……」
すると、アオトの言葉を聞いたハルカは少し驚いたようにして何度か瞬きをしてから、わざとらしく耳に髪をかける仕草を見せた。金髪がさらりと揺れて、彼女は一層色気を帯びた様相になる。
ごくごく自然な仕草だったが、まるでわざとアオトに見せつけているかのような艶やかさだった。
「……うん、こちらこそありがとう!」
ハルカはアオトに満面の笑みを浮かべて言葉を返すと、彼を残して一人で店を後にした。
そして、近くの雑貨屋に入って嘆息する。
「……んー、悪くないね~」
ハルカは雑貨屋の奥で一人佇みながら、アオトと過ごした時間を思い返すが、ショーケースに反射する彼女の顔は少々歪んでいた。
まるで、悪事を企む悪党のようだ。
「降谷くんって悪くないね……」
ハルカはごく自然な笑みを溢す。ただ、そこに先ほどまで見せていた人の良さは消えかけていた。
幸い、周囲には誰もいなかったが、何かおかしな思考をしているのは誰から見ても明白だろう。
「……あれ、これ……?」
そんなハルカはアオトのことを考えながらも何の気なしに視線を上に移すと、店内の壁に貼られた1枚のポスターが目に入った。
【恋愛小説コンテスト開催決定! 小説家を目指すキミへ! 応募締め切りは11/25——選考結果発表は12/25! 新時代の才能を発掘しよう!】
その文言を見てハッと何かを閃いた彼女は、すぐさまスマホでポスターの写真を撮り、迷う事なくアオトのLINEに送りつけた。
小説を書きたいと言っていた彼にはうってつけの機会だった。それに、自分の為にもなる。
「……これ……いいじゃん」
思い立ったハルカは小さな雑貨屋を抜け出すと、先ほどまでいたカフェへと早歩きで戻る。
別れてからまだ数分しか経っていないので、カフェの中にいるであろうアオトの姿を探す。
「すみません、前髪が少し長くて目つきの悪い人ってもう帰っちゃいましたか?」
カフェの中にアオトの姿が見当たらなかったので、ハルカはレジにいた店員の女性に声をかけた。
「あー、その方ならつい先程帰られましたよ。メモ帳を見ながらニヤニヤ笑ってましたね。確か、貴女はお連れの……」
「そうです。ちなみに、どっちに行きましたか?」
「左手側ですね。方向的に改札側だと思いますが……」
「ありがとうございます」
ハルカはすぐさまカフェを抜け出すと、店員の女性に教えてもらった通りに店を出て改札側へ歩みを進めた。
すると、人混みの向こうに見覚えのある後ろ姿を発見し、躊躇する事なくその背中を手のひらで叩く。
「降谷くーん!」
「んぁ……お、おお、星宮。予定があるんじゃなかったのか?」
ハルカに声をかけられたアオトは驚いた様子で振り向くと、伸びた前髪の隙間から彼女の姿をじっと見つめた。
先ほど別れたばかりの相手がなぜ目の前にいるんだという疑念が、その表情に如実に現れている。
だが、そんなアオトの動揺なんてハルカは考慮せずに、瞬く間に距離を詰める。
「LINE見た?」
「いや、見てない」
「何で!?」
「何でって言われても、俺って常に通知オフだし……」
「今すぐ確認してみて?」
「はいはい、わかったよ……」
ハルカに気圧されたアオトはポケットからスマホを取り出すと、不思議そうな面持ちでLINEを確認した。
「……えーっと、恋愛小説のコンテスト?」
アオトのスマホの画面には、つい先ほどハルカが送りつけたポスターが写っている。読み上げても彼は何が何だか理解していない。
「で、これがどうかしたのか?」
「挑戦してみたら?」
「え?」
ハルカからの唐突な提案を聞いたアオトは口をぽっかりと開けて固まった。
しかし、ハルカは全く構う事なく言葉を続けた。
「降谷くんは恋愛小説を上手く書けるようになりたいんでしょ? 期限は3ヶ月しかないけど、こういうのに挑戦してみる価値はあると思うんだ。小説投稿サイトに掲載して応募するみたいだし、ひょっとしたらバズって人気になれるかもよ?」
「バズる……? いや、俺は別にそういう目的のためにやってるわけじゃ……」
「カフェを出る時ニヤニヤしてたって店員さんが言ってたし、きっと何か思いついたんでしょ?」
「確かに、今日は星宮と過ごせたおかげで新鮮な経験はできたけど、俺なんかが書いた小説が賞を取れるわけないだろ」
アオトが自信なさげな表情で弱音をこぼしたが、ハルカはすぐさま首を横に振り顔に笑顔を貼り付ける。
「別に受賞なんてしなくてもいいじゃん。ただ、楽しむって理由だけじゃダメ?」
「……ダメじゃないけど、俺にできるかなぁ」
押せ押せのハルカの言葉を受けてアオトは腕を組む。
「降谷くんに足りないのは経験だけ! 文章力はあるから必ず上手くいく! 私も降谷くんが書き上げた小説を参考にしてイラストを描いてみるから、チャレンジしてみようよ!」
「……わかった。そこまで言うなら、やってみる」
不自然なくらい自分を評価してくれるハルカの言葉に励まされたアオトは、少しだけ自信を持ち始めた。
彼女の後押しによって、彼はコンテストへ挑戦する決意を固めたのだった。
「決まりだね。もしも小説を書き始めて3ヶ月の男子高校生が賞を取ったら話題になること間違いなしだよ! 頑張ろうね!」
「ああ」
アオトが快く返事をする事でハルカは満面の笑みを浮かべると、人目を気にせずぴょんぴょん飛び跳ねて喜びを露わにした。
その”喜びの真意”は彼女にしかわからない。
同時に、あまり目立ちたくない日陰を好む性格のアオトはそそくさと彼女と距離を取り他人のふりをする。
「ところで、用事はいいのか?」
「あっ忘れてた! 早く行かなきゃ! またねー!」
アオトの一言でハッとしたハルカは、ばたばたと走り去っていった。
「……頑張ってみようかな」
取り残されたアオトが呟いた言葉は人混みに流されて消えてしまったが、彼の心の中には確かなやる気が渦巻いていた。
同時に、星宮晴香という人物への強い興味と関心が心に宿り、また彼女と共に時間を過ごしたいと思うようになっていた。
人を感動させる恋愛小説を書いてみたい降谷碧都と、将来は有名なイラストレーターになりたい星宮晴香。
二人は大きな目的を叶えるために、3ヶ月後に締め切りが迫る恋愛小説コンテストへのチャレンジを決めたのだった。
◇◇◇
アオトとのデートの後の用事を済ませて自宅へと帰ってきたハルカは、自室のベッドに腰を下ろして一日の出来事を思い返していた。
今は着替えを終えて夕食を済ませ、お風呂にも入り終えたところだ。
時刻は午後7時を回ったところ。
ハルカは涼しげな生地の薄い寝巻きを身に纏いベッドに倒れ込むと、柔らかな枕に顔を埋めて不快感を孕んだ溜め息を吐く。
「あーあ……はぁぁぁぁぁぁ……」
その時、LINEの通知音が鳴る。
「降谷くんからだ……まっ、返信は後でいいや」
ハルカはスマホの通知音に気づき、アオトからのLINEが届いていることを確認した。
彼女はスマホを手に取って返信しようとしたが、今日は少しやるべきことがあるのを思い出すと、おもむろにTwitterを開いて眉間に皺を寄せる。
「……うーん……あんまりバズってないなぁ。もう、かなり上出来だったのに!」
ハルカはTwitterに映る自身のアカウントを確認すると、多大なフォロワー数の割にバズらない《《オリジナルイラスト》》を見て不満を溢す。
星宮晴香は飢えていた。
友人はもちろんのこと家族にすら明かしていないが、彼女はネット上では有名なイラストレーター【すたぁ☆】その人だったのだ。
フォロワーは50万人を超えており、現役女子高生イラストレーターとして名を馳せている。
しかし、最近は思うようにいかなかった。
50万人を超えるフォロワーは、どうして私のイラストを拡散してくれないんだと、彼女は心の中で愚痴る。
前までは新進気鋭のイラストレーターとして持ち上げてくれたくせに、最近はネット上での反応が薄くて満足できない。
心に植え付けられた承認欲求という名の魔物が、大きく口を開けて次の餌を待っているというのに……。
——こんなに承認欲求が芽生えて、内外で自分の性格が変わってしまったのはいつからかな。
ハルカは満たされない寂しい心の穴を直ちに埋めたかった。
「どうしよっかなぁ~」
ハルカはうつ伏せで寝転びながら、足をばたつかせて面白い話題はないかと模索した。
綺麗な一枚絵のイラストを描いても思うようにはバズってくれないし、何より仕上げるのにもそれなりの労力が必要だ。
自分が女子高生であるという利点を活かして、面白おかしい観点からどうにかして承認欲求を満たしたい……。
ハルカは高校の友達と遊んだ時の出来事や家族との何気ない会話を思い返すが、そんなありふれた日常には誰も見向きしない。
ネット上でバズるためには独特な着眼点だったり、奇抜なアイディア、現実とは乖離した非現実的な何かが必要なのだ。
「……あっ、降谷くんをネタにしよっかな」
ハルカはふと閃いた。
先日、彼女の興味を強く惹く出来事があった。
それは……降谷碧都が書く恋愛小説との出会いである。
いきなり恋愛小説を読んでほしいと言われた時はさすがに驚いたが、彼女にとってアオトは興味深い人物だった。
根暗で日陰ものなのに、なぜか唐突に恋愛小説に興味を持ち、挙句それを自分で書いてくるという特異な行動力。
観察対象としてはかなり面白い。
そもそもコンテストに彼を誘導したのも、あわよくばハルカ自身も目立ちたかったからという理由に他ならない。
もしも受賞しなかったり、そもそも途中で筆を折ってしまっても元の関係に戻るだけなので何ら問題はない。
「いいかも……今日からは新シリーズの投稿始めます……っと」
ハルカはすぐ行動に移す。
素早いフリックで文章を打ち込んでいき、今後バズる布石のために予め新シリーズを予期させるTweetを仕掛けておく。
「後は降谷くんと過ごした出来事をイラストにして、漫画ちっくな雰囲気に加工するだけだね」
ハルカは布石となるTweetを仕掛けてからすぐに机に向かい、さらさらとイラストを描き始めた。
まずは冒頭。描くのは今日の出来事だ。
クラスでも随一の陽気なギャルに対して、全く目立たない根暗男子が声をかけるシーン。
ポイントはその格差を強調すること。
ハルカにとってアオトは単なるクラスメイトに過ぎない。
そんな相手に対して、見た目に反して優しいギャルが甘い言葉をかけて茶化していく展開はよくウケる。
本来は関わり合いを持つはずのない2人が、ひょんな出来事をきっかけに関係を深めていく王道パターンである。
小馬鹿にした感じで題材にするのは少しばかり気が引けたが、自分の欲求には抗えなかった。
「まあ、2次元の中だから、ちょっとくらいは良い関係にしてあげてもいいかもね」
単なるクラスメイトであるアオトが恋愛対象に入ることは現状考えられなかったが、それはあくまでも現実の話。
絵の中の世界であればやりたい放題だった。
なので、このストーリーの大筋としては、金髪のギャルが根暗男子を茶化し、小馬鹿にし、その心を手懐けるような、SMないしは主従関係、校内カーストをうまく描いた明確な格差のある光景をイメージをしている。
きっとアオトはハルカとの経験を基にして純粋な恋愛模様を軸に小説を書くのだろうが、彼女が描くストーリーの主軸はそんな恋愛とは程遠かった。
時にはそんな恋愛ちっくなパートを織り交ぜていくつもりではあったが、やはり根暗男子を小馬鹿にする内容となっている。
まあ、アオトが何を思うかなんてハルカにとってはあまり関係なくて、彼女自身はネットの世界でバズって承認欲求を満たせればそれで良いのだ。
彼女の精神は、他人のことを考えるほどの余裕を持ち合わせてはいなかった。
「……降谷くんには内緒にした方がいいよね。私がプロのイラストレーターだって知っちゃったら、せっかく小説を書いてくれてるのに可哀想だし……」
ハルカはちょっとしたアオトへの気遣いを見せながらも筆を走らせる。
やがて、あっという間に2時間ほど経過すると、精巧な4枚のイラストが完成していた。
誰よりも筆が早いと自負しているハルカにとって、この程度の作業は造作もなかった。
「できた」
ハルカは完成したイラストを見て満面の笑みを浮かべた。
1枚目はアオトによく似た前髪の長い根暗男子が、金髪のギャルに話しかけられて挙動不審になるイラスト。
2枚目はそんな2人がデートに行き、根暗男子にちょっかいをかけて楽しむギャルのイラスト。
3枚目はデート終わりの会話を楽しむ平穏なイラスト。
4枚目は甘い言葉で誘惑して根暗男子の心を手玉にとるギャルのイラストだ。
どれも今日のハルカとアオトのデート内容に酷似したイラストだったが、冒頭の恋愛小説の下りを無くして互いの名前も変えているので違和感はない。
ただ、アオトがこれらを目にすればおそらく察しがつく。
しかし、今日見たホラー映画について何も知らなかったことから、きっとLINE以外にSNSはやっていないのだろうと彼女は推測する。
つまり、アオトにこのイラストとストーリーの存在バレることはない。
「あっ、タイトルどうしよ」
ハルカはTweetに添付した4枚のイラストを見て考える。
そしてすぐに思いつく。
「『根暗男子と金髪ギャル』でいっか。シンプルな方がわかりやすいし、ネット民にはこれくらいがウケるかな。はい、Tweetっと……」
ハルカは特に深く考えることなくTweetすると、次にLINEを開いてアオトから送られてきたメッセージ内容を確認することにした。
「んじゃ、返信するか~……どれどれ」
アオトからのメッセージには、今日のデートに対する感謝の言葉が端的に綴られていた。
『今日は俺なんかと出掛けてくれてありがとう。今、急いで小説を書いてるから後で送る。また感想を聞かせてくれると嬉しい』
「……」
ハルカはしばらくスマホを手にしたまま返信を考える。
当初は興味本位で声をかけただけなので、LINEも他の男子と同様に適当にあしらって終わらせるつもりだったが、今の彼女にとって彼はなくてはならない存在へと昇華していた。
今日のデートだって、彼女はたまたま日曜日に予定が何もなかったから誘いを受けたに過ぎない。
一緒に協力してみようと投げかけたのも、単なる興味本位だった。もしもアオトと合わないなと思ったら関係は白紙に戻っていた。
だが、ハルカはアオトのことを少しだけ気になっていた。
だからこそ、あまりぞんざいに扱いたくないし、むしろやり取りを重ねた方が自分のためになる……ハルカはそう考えた。
現に彼女は小説を読んで着想を得たり、実体験を基にイラストを描くのが得意だったからだ。
『こちらこそありがとう! 降谷くんは意外にも男らしいというか、ちゃんとお礼とか言えるタイプで良かったよ! また明日、学校で話そうねー』
ハルカは長考した末にごくごく無難な返信をした。
お礼を返しつつも相手を適度に持ち上げて、悪い印象は抱かせないようにする。
「……既読早っ」
メッセージを送って数秒だった。
すぐさまアオトは既読をつけると、瞬く間にメッセージを返してくる。
『学校ではあまり話したくない』
「え?」
何の気なしに告げられたその言葉にハルカは思わず動揺してしまった。
もしかして、私のこと嫌い? そう思うほどに、彼女は心に疑念を渦巻かせた。彼に嫌われたらネタが尽きてしまう。ハルカ的には先ほどの新シリーズが今後バズったら定期的にネタを収集したいので、今のうちはできるだけ関わりを持っておきたい。
今の段階で関係を断たれると計画が台無しになる。
そして何よりも、ハルカは誰かに嫌われるのを1番避けたかった。
しかし、数秒後にアオトから立て続けに送られてきたメッセージは、そんな迷いあぐねる彼女の思いを良い意味で裏切ってくれる。
『恋愛小説を書いてるとかあまり知られたくないし、俺なんかが星宮みたいなやつといたら変な目で見られるからな』
「あー、そういうことね」
嫌われてないと知りある意味ほっとしたハルカはすぐさまスマホをフリックする。
『わかったよ~。じゃあ、小説ができたらLINEで送ってね! それを見て私もイラストを描いてみるから!』
『”テキストデータ 映画館編 2万文字”が送付されました』
『え!? もうできたの!?』
『たった今完成した。一回書いて慣れたからかスラスラ書けたんだよ。星宮のアドバイス通り、今日の経験を基に書いてみたから時間があるときに目を通してみてくれ。俺はもう寝る。おやすみ』
「……まだ10時前だけど、やっぱ引きこもりっぽいし外に出ると疲れちゃうのかな」
ハルカはトーク画面を見ながら呆れたように口にした。そして、おもむろに送付されてきたテキストデータを開く。
「学校では話せないし、寝るまでにこれを読んでおこうかな~」
彼女はアオトが書き上げてくれた小説に目を通してみることにしたのだった。
◇◇◇
その日、アオトが通う高校は、午後の5限目と6限目が続けて体育の授業だったのが、生憎の雨天により自由時間になっていた。
不満を垂れ流したクラスメイト達だったが、たまたま体育館に空きがあったということで、彼らは檻から抜け出す囚人かのように教室からいなくなり、教室の中は閑散としていた。
「……」
そんな中、アオトは近々控える定期テストのために黙々と勉強に励んでいた。
静かな教室にはクラスメイト達の姿はなく、外から聞こえる雨音が静かな空間に静寂を添える。
彼の動かすペンが紙に触れる音や、ページをめくる音が教室を満たしていき、時間の流れと共に、彼の思考が紙に書き記され、知識が増えていく。
しかし、アオトは隣から感じる好奇の視線に邪魔をされて、あまり勉強に集中できずにいた。
「……星宮」
アオトは問題集に目を通しながらも視線の正体であるハルカを一瞥する。
「なぁに? ムスッとした降谷くん」
対するハルカは特に気にする様子もなくのんびりとした声で返事をする。
「学校では関わるなってこの前LINEで言ったばっかだろ。早く体育館に行って遊んできたらどうだ?」
「ケチくさいこと言わないでよね~。私って実は勉強があまり得意じゃないから、こういう機会に勉強しておくのも悪くないかなーって思っただけだし」
「いやいや、全く勉強してないだろ」
アオトの見た限り、ハルカの机の上には何も乗っていない。リュックも高校二年生とは思えないペラペラ加減で、勉強には無頓着な様子が窺える。
「あはははは……まあまあ、それはいいじゃん。私は単純に降谷くんと過ごしたかっただけだから、ここにいてもいいでしょ?」
「まあ、いいけど……人が来たら離れろよ?」
「もちろん。ところでさ。昨日送ってくれた小説、読んだよ!」
話を変えたハルカは少しだけ席を前にズラしてアオトとの距離を詰めると、スマホを片手にニコニコと笑った。
「……どうだった?」
恐る恐る尋ねるアオトはペンを手放した。
その内心は以前と同じような酷評をされないか不安が宿っていた。
「はっきり言っていい?」
「ああ」
前回と同じような流れにアオトは身構えるが、結果を発表する当のハルカはなぜか楽しそうな顔つきだったので、アオトは途端に複雑な心境に駆られて訳がわからなくなっていた。
だが、そんなアオトの予見は良い意味で大きく外れることになる。
「結構面白かった」
「……まじ?」
「うん。そもそもあれだけの時間で2万文字も書き上げたっていうことに驚いてるんだけど、降谷くんってもしかして天才なのかな?」
「んー、いや、ただ俺は感じた事を文章に起こしただけなんだけど……そっか、面白かったか。くくくく……なんか嬉しいな」
想像とは違うハルカからの好評価に対して、アオトは自分でも珍しいと思うくらい不敵な笑みをこぼしてしまった。
彼は素直に喜びを噛み締めていた。先日は酷評とは言わずとも長々と厳しい意見に晒されたので、こんな風に良い評価を受けるのは当然心が躍る。
「笑い方が不審者みたいだね」
「うるせぇ」
アオトはハルカから目を逸らすとぶっきらぼうに言葉を吐き捨てたが、その表情は柔和で怒りなどの感情は一切見受けられなかった。それくらい、今のアオトは心が満ち足りていた。
「まあまあ、それはそれとしてさ……降谷くん」
僅かに開かれた窓の隙間から湿っぽい風が流れてくると同時に、ハルカは一つ咳払いをしてアオトの名前を呼ぶ。
「何だ?」
「前見せてくれた小説はリアリティが無さすぎるって話をしたと思うんだけど、今回の小説は妙にリアリティがありすぎて、読んでる私の方が恥ずかしくなっちゃったんだよね。もしかしなくても、ヒロインの子って私がモデルだったりするのかな? すっごく魅力的に書いてくれてたから気になっちゃってさ~」
ハルカは真剣な顔つきでアオトの目を見て尋ねた。
そんな彼女の姿を初めて見て怒らせてしまったと勝手に勘違いしたアオトは、少し驚いた顔になったが、すぐに頭を下げて謝辞を述べる。
付き合いは短いが、最低限の礼儀を欠いてしまったと彼は感じていた。
「……悪い。モデルも何も、星宮をそのまま使わせてもらった。嫌なら全く別のヒロインに変えさせてもらうが……」
「ううん。それは別にいいんだ。ただ、私の容姿とか……その、香りとか? 一つ一つの行動とか表情とか、事細かに書かれていたから気になっちゃって。なんか恥ずかしいなぁ、って。別に怒ってるわけじゃないからね!?」
「そうなのか?」
「うん。それとはまた違うけど、デートの内容がそのままストーリーになってたから良いなぁって思っただけだよ! 見る人によっては私たちがデートしたってバレちゃうかもね?」
「……俺の小説なんて星宮以外に読んでくれないから大丈夫だよ」
ハルカが怒っていたわけではないと理解したアオトは瞳を閉じて胸を撫で下ろした。彼は彼女という最も身近な異性を等身大のままヒロインの席に据えていたので、小説を見せてしまえばこうなる展開は予測できていた。
しかし、彼は自身にまともな恋愛経験がなくて、異性とのデートは昨日が初めてだったので、こうする他なかったというのが正直なところなのである。
また、同じく恋愛経験がないと言っていたハルカなら許してくれるなんていう期待もしていた。
「後もう1つ!」
「あー、今度は何だ?」
「降谷くんって私のこと好きなの?」
ハルカは先の質問に続きまたも素っ頓狂なことを聞いてくる。
「はぁ? 急に何だよ?」
もちろんアオトは呆れた顔つきになり聞き返すが、ハルカは首を傾げて不思議そうな面持ちになるだけだ。
「だって、ヒロインが私ならその相手は降谷くんってことになるでしょ? 私のことを想うような描写もあったし、リアリティを求めるならそれってそういうことでしょ? でも、ごめんなさい。さすがに恋人にはなれないかなぁ~」
ハルカは両手を合わせて可愛らしく舌を出して笑みを見せた。冗談混じりのようにも聞こえるが、アオトからすればこんな振られ方をされて溜まったもんじゃなかった。
「……そうですか」
反論をする間も与えられることなく勝手に振られてしまったので、アオトは何も言葉を返すことなく一つ息を吐く。
彼女もまた完全な冗談で言っていたのか、呆れるアオトのことを見て口角を上げていた。
それから、二人の間にはしばしの沈黙が訪れた。
別に気まずいような様子はない。
ただ、やはりまだ親しい間柄ではないためか、えも言えぬ妙な空気感になってしまい、アオトは痺れを切らして口を開く。
「そういえば、星宮はイラストを描いてくれたのか?」
「まだまだだよ。小説を読み合えたのだって昨日の寝る前だし、もう少し時間が欲しいかな?」
筆の早いアオトとは違い、ハルカはそんなに作業効率が良い方ではなかったようだ。彼からすれば文字を書くのと絵を描くのとでは全く別物だということも理解していた。
そもそも美しいイラストを描くにはそれなりの時間が必要だということである。
「そうか。で、勉強の方は? 定期テスト、もう再来週だろ?」
「うっ……ま、まあ、何とかなるよ! 目指せ赤点回避!」
ハルカは苦虫を噛み潰したような表情を浮かべて、力のこもっていないガッツポーズを見せた。
「赤点回避って……随分と目標が低いんだな」
アオトとハルカが通う高校はごく普通の公立高校で、赤点のボーダーは30点となる。下回ると放課後は補習を命じられ、補習後の再テストに落ちたら再補習。さらにその後行われる再々テストに落ちたら……という形だ。
「仕方ないじゃん。勉強嫌いなんだもん」
「留年するぞ?」
「正直、かなり危ないかも」
アオトは冗談で留年の話をちらつかせたのだが、ハルカがマジな顔で危険を予期させるものだから驚いてしまった。
「は? じゃあ勉強しないとまずいだろ」
「うん。だから、こうして皆と遊ばないで教室に残ってるんだよ」
「雑談ばっかで何もしてないけどな」
かくいうアオトも、ハルカと雑談を始めてから一切勉強に手をつけていないので人のことは全く言えないのだが、彼からすれば赤点を取るなんて常識外の力技をしないと不可能な行為だった。それ故に、特に危機感を抱いてはいなかった。
むしろ、アオトは入学から今に至るまで全てのテストで学年トップ10入りを果たしているので、今回のテストだって別に問題はないレベルなのだ。
「まあね~、だから降谷くんにお願いがあるの」
「……嫌な予感がする」
多分、この流れはアレだな……と、アオトは確信めいた察しがついていた。
「勉強教えてくれない?」
「嫌だ」
案の定と言うべきか、ハルカが手のひらを擦り合わせて頼み込んできたので、アオトは両腕をクロスさせてバツを作り即答した。
「えー、なんで?」
「俺だって自分の勉強もしないといけないから忙しいんだよ」
「ふーん、私が赤点を取って補習することが決まったら放課後とか土日休みに遊びに行けなくなるけど、それでもいいんだ? そうしたらイラストも描けなくなるし、コンテストなんて夢のまた夢だよ?」
「……星宮、お前小賢しいな」
にたにたと笑っているハルカのしたり顔を見たアオトは背中を丸めて頭を抱えた。
「降谷くんってあまり乗り気じゃない感じ出してたけど、実は結構この関係を楽しんでるでしょ? 私といても苦じゃないでしょ? なら、私に勉強を教えたほうがお互いの為になると思うんだけどなぁ~……どうかな?」
ハルカは人の懐に入り込むのが上手くて愛嬌があるので、うるうるとした瞳で懇願されては真面目で意志の固いアオトも中々断りにくい。
「……わかった、わかったよ。今回だけだぞ」
「ありがとっ! 私も頑張るから! それに、放課後の勉強会って青春っぽいでしょ? そういうのも恋愛小説の醍醐味だと思わない?」
「確かに……そう言われてみると、なんかやる気出てきたわ」
アオトは顎に手を当てて考えた。彼女の言う通り、恋愛小説の舞台は別に校外だけに限った話ではない。むしろ、校内で起きる何らかのイベントを通して得られる経験も多数あるはずだ……アオトは口角を上げて首を縦に振る。
「でしょ? ってことで、今日の放課後は図書室に集合ね」
「はいよ」
アオトが端的に返事をするのとほぼ同時のことだった。
五限目の終了を告げるチャイムが鳴る。
「あ、終わった」
ハルカは時計を見ると、体を伸ばしてリラックスしながら席を立ち、教室の外へ向かって歩みを進める。
「じゃあ、私は体育館で遊んでくるから、放課後はよろしく~」
ハルカは小さく手を振りながら教室を後にした。
一人取り残されたアオトは、すっかり雨が止んで晴天となった空模様を眺めた。
「……やるか」
アオトは完全な静寂に包まれた教室の中で1人呟いた。
「星宮のために全教科のテスト範囲を改めて確認しておくか」
アオトはペンを手に取ると、分厚いリュックサックの中からいくつもの教科書と資料集を取り出し、付箋を貼ったページを捲りテスト範囲の確認作業を始めたのだった。
これまでの経験を基に、出題されそうな傾向を頭の中にインプットし、それらをノートに書き記していく。
今からハルカに全てを学習してもらうのは不可能なので、確実に30点以上取れる用に効率重視で勉強を進めることにした。
「頑張るぞ」
アオトはハルカと雑談を重ねたことで気が紛れて集中力が高まったのか、スラスラとペンを動かし続けて、気がつけば放課後を迎えていた。
どうやら、六限終了後のホームルームは無いらしく、各々が教室に荷物を取りに来て適当に解散していた。
アオトもその人混みに紛れて教室を後にすると、ハルカとの約束通り図書室へと向かったのだった。
◇◇◇
しんとした静寂に包まれる図書室内は、テストを間近に控える生徒たちが詰めかけているということもあり、普段よりも一層ピリッときた空気感が漂っていた。
そんな図書室の一角で、アオトとハルカは二人掛けの席で向かい合いながら勉強に励んでいた。
「……降谷くん」
ハルカは真剣な様子で問題を解き続けるアオトの指をペンで突いた。
「なんだ、星宮」
「ここ、わかんないから教えて?」
「理解しようとするな。丸ごと暗記しろって言っただろ?」
ハルカは可愛らしく両手を合わせてウインクまでしていたが、当のアオトは一瞥もせずに手を動かし続けていた。
「……本当にそのやり方で大丈夫なの?」
「ああ。本当は理解した方がいいんだが、正直言って今の星宮の頭じゃテストまで間に合わないのが目に見えてるからな。赤点回避の最短ルートは全教科を必死に暗記することだ」
アオトは尚も手を止めることなく、目の前の問題への集中力を切らさない。
二人が図書室にやってきてまだ30分ほどしか経過していなかったが、実はハルカの集中力は既に底をつきかけていた。
「……馬鹿にされてるけど、事実だよね。でも、数学はもちろん理解が必要だよね? 間に合うかな?」
「はぁぁぁ……数学は暗記だ」
不安そうに確認してきたハルカのことを尻目に、アオトは大きな溜め息と共に言葉を吐いた。
「じゃあ国語は?」
「それも、暗記だ」
「理科は?」
「無論、暗記だ」
「副教科の家庭科と保健は?」
「もちろん、暗記だ」
「じゃ、じゃあ、英語は?」
「暗記に決まってるだろ」
「もう! 暗記しかないじゃない!」
暗記暗記暗記暗記暗記。まるで、初めて言葉を覚えた赤ん坊のようにテンポ良く連呼するアオトに対して、ハルカはついに堪忍袋の尾を切らして声を大にした。
その瞬間に周囲で勉強に集中している生徒たちが驚いた表情で二人に視線を浴びせてくる。
まるで街中でバカップルを見かけた時のような冷ややかな視線だった。
「ご、ごめんなさぁ~い……」
ハルカはいたたまれない様子で肩をすくめると、小さな声で申し訳なさそうに口を開いた。
「……とにかく、最初は暗記だけでいいんだよ。ここが今の星宮の位置だとしたら、目指すのは赤点ボーダーよりも少し上の辺りになる。そこに到達するためには、星宮の得て不得手なんて関係なく、どの教科も高配点となるポイントを抑えて全て暗記するんだ。テスト範囲は事前に出てるし、中心となる部分も明確だから対策はしやすい。理解は別にその後でいい」
アオトは小さく咳払いをして空気を一変させると、いつの間にやらノートに書き記していた分布図をハルカに向けて見せる。
口頭で今のハルカの立ち位置と目指す位置を指し示しながら、簡潔かつ丁寧に説明した。
最後にシャーペンを手に持ち、先端をハルカに向けて最終確認をする。
「ここまでわかるか?」
「……」
ハルカは向けられたシャーペンの先端から目を逸らし身を震わせていた。呼吸が荒くなり、目の焦点は合っていない。
「星宮? どうした?」
アオトはシャーペンを下ろして尋ねた。
すると、ハルカはハッと我を取り戻し、胸に手を当てて呼吸を整える。
まるで夢の中にトリップしていたようだった。
「あ、ご、ごめん……ちょっと、あんまり尖った物とか向けられるの得意じゃなくて……」
「悪い。先端恐怖症だったんだな。配慮が足りなかった」
アオトは素直に頭を下げた。
映画館では確か狭い場所が苦手と言っていた記憶も残っており、更には先端恐怖症とのことで、ハルカの苦手なものを頭の中に刻んでおく。
「……そういうわけではないんだけど……とにかく、本当にさっきの方法だけで点なんて取れるの? ぶっちゃけ私って結構なお馬鹿さんだよ?」
先端恐怖症ではない……が、尖ったものが苦手という意味だろうか。
アオトには深く意味がわからなかったが、ハルカはすっかり平静を取り戻していた。
慣れているのか、既にケロッとしている。
「星宮がどのくらいの頭の良さなのかはよく知ってる。前回のテストのクラス順位は30人中28位でほぼ最下位だったか? しっかり補修組の真ん中の席に座ってたもんな」
ハルカが勉強を苦手にしていることなど、アオトからすれば当然のように知っていた。
というのも、彼はテスト終わりに発表される学年順位とクラス順位を入念にチェックしているからだ。
それもこれも、指定校推薦を使って大学に行くために、今の自分の立ち位置を把握しながら勉強しているからである。
「うぅっ……ちなみに、降谷くんは何位だったの?」
ハルカは半べそをかいて泣くふりをしながらアオトに聞いた。
「クラス順位は2位だったな。1位のヤツはうちの高校から東大を目指しているみたいだし、努力の差を考えれば当然の結果だな」
「ふーん……凄いねぇ」
アオトが堅物で結構真面目なタイプだということはハルカも知っていたが、まさか彼がクラスで2番目の秀才だとは思っていなかった。
「まあ、話は戻るが、うちはごくごく普通の公立高校だから、授業で使った教科書や問題集に載ってる問題をそのまま転記するなんてザラだ。暗記すれば30点くらい簡単に超えられるようにできてるんだよ。だから……まあ、テストまではちょっとだけ頑張ろうぜ?」
アオトは感嘆するハルカを一瞥してから再びノートに視線を移した。
全く慣れてないのがわかるぶっきらぼうなエールだったが、それは目の前のハルカの心に確実に浸透していた。
「……うん、わかった。赤点取っちゃったらコンテストに応募できなくなるし、頑張ってみるね!」
「静かに」
「あ、ごめん」
思わず大きな声出しながらガッツポーズをしてしまったハルカだったが、冷静沈着なアオトに咎められると、彼女はわざとらしくしゅんと縮こまって瞳を伏せている。
そんな彼女の姿をチラリと見たアオトは僅かに口角をあげると、一人で勉強していたこれまでよりも少しだけ気分が晴れやかなことに気がついた。
他人に勉強を教えながら自分の勉強も進めていく不安が多少なりともあったが、この分なら大丈夫そうだな。アオトは心の中で安心したのだった。
彼女なら一人でも勉強できるだろう。
「星宮」
「なぁに~?」
アオトに名前を呼ばれたハルカは、可愛らしく伸びのある声で返事をした。
「昨日もLINEで伝えたと思うが、校内で一緒に過ごすのは遠慮させてもらう。今日はこのまま付き合うが、明日からは一人で勉強してくれ。もしもわからない箇所があったら、都度LINEで聞いてほしい。それで大丈夫か?」
「うーん……私は別に降谷くんと過ごしてもそんなデメリットなんてないんだけど、まあ、降谷くんがそう言うなら仕方ないよね」
ハルカはそんな些細なことなんて特に気にしていないのだが、不器用ながら気遣いのできるアオトだからこそこういった提案をしたのだろうと理解を示した。
「悪いな」
「ううん。でも、やっぱり降谷くんと一緒に勉強したいなぁ~」
「……」
ハルカが懇願するような視線をぶつけてきたので、アオトはふっと目を逸らして口をつぐんだ。
すると、彼女は何か思いついたのか、おもむろに口を開く。
「ねぇ、降谷くんは学校だと目立っちゃうから嫌なんだもんね?」
「ん? まあ、そうだな」
アオトは周囲に視線を這わせながら相槌を打つ。閑散とした教室ならまだしも、できればテスト前の図書室のようなそこそこ人が多い場所は避けたいと思っていた。運良く、周りにはクラスメイトや見知った人物はいなさそうだが、星宮の容姿は秀でているので目立つのは免れない。
「ふーん」
「にやにやしてどうしたんだ」
「学校以外の場所で勉強しない? って提案だったんだけど……どうかな?」
ハルカはペンを転がして机に両肘をつき顎のあたりに手をやると、可愛らしく首を傾げてジッとアオトに視線を向けた。あざとさもあるが、鈍感なアオトはそれに気づかない。
「となると、市営の図書館辺りか? 学校からは少し遠いし、放課後になってから向かうにしても時間が勿体無いぞ」
アオトは何やら企んでいそうなハルカから目を逸らして考えた。カフェに行くにしても、学校の近くにはゆっくりできそうな感じの店はない。おまけに図書館以外の市の施設は体育館くらいしか思いつかないので、学校の外で勉強するのは中々至難だった。
「いい場所があるよ?」
「どこだ?」
「降谷くんの家」
「はぁ?」
「ご両親は共働き?」
アオトは口をあんぐりと開けていたが、彼の反応を見て微笑んだハルカは彼に質問をぶつけていく。
「……ああ、いつも八時くらいに帰ってくる」
「ぴったりだね。兄弟はいるの?」
「……1人っ子だ」
「ぴったりだね。私、犬と猫のアレルギー持ちなんだけどペットは飼ってる?」
「……飼ってない」
「ぴったりだね。じゃあ、明日からテストまでは放課後の時間を使って家にお邪魔するね。用事があったら行けないけど、そういう時はLINEするから安心してね」
ハルカはまるで魚の追い込み漁のような手口でアオトの選択肢を限定させていくと、最後はしたり顔で満面の笑みをこぼしていた。
「……え? もう決まったのか?」
アオトは呆然としたまま口を開く。
「うん。だって、1人で勉強しろーって言われても、私、自信ないし……単純な暗記はもちろんするけど、少しでも良い点取ってコンテストに備えたいから今回のテストは頑張ることにしたんだ。だから、降谷くんも協力してくれると嬉しいかな、ってね?」
「……仕方ないか」
アオトは留年間近のハルカのやる気を無碍にすることはできなかった。
彼の家は高校からは程近く、徒歩で数10分の距離だったので、距離を言い訳に断ることもできなかった。
「やったぁ! じゃあ、今日はここで頑張って、明日はそっちにお邪魔するね。一緒に帰ったら怪しまれるから、時間を置いてから家に行ったほうがいいよね?」
「んー、そうだな。住所は後で送っとくよ」
アオトは未だにクラスメイトの異性を易々と家にあげるのは……と心の中で葛藤していたが、すっかり乗り気なハルカに押されて気付けば快諾し話が進んでいた。
まあ、勉強するだけだし場所は学校以外であればどこでもいいか。アオトは自分にそう言い聞かせることにする。
「わぁぁ……楽しみ! やっぱり男の子ってベッドの下にえっちな本とか隠してたりするの? 変なことしたら即通報するけどおかしな妄想とかしてない? 大丈夫?」
「……エロ本は持ってないし、変なこともしないから安心してくれ。むしろ、俺は自由奔放な星宮に家を荒らされないか心配だ。ちゃんと勉強しなかったら追い出すからな?」
ワクワクと狂気を混同させたハルカの発言に戦慄しつつも、アオトはアオトで譲れない条件を課す。
「うん。降谷くんは私の想像以上に人想いというか、接しやすいから、私も期待に応えられるように勉強するね」
ハルカは意志のこもった澱みのない真っ直ぐな表情に変わると、自ら進んでペンを取って勉強を再開した。
それからは特に無駄なお喋りを挟むことなく、今日のところはアオトに言われた通りに暗記に集中し、気がつけば下校の時刻になっていた。
アオトは教室に忘れ物をしたということで、ハルカとは図書室の前で解散して1人で教室へ戻ることになったのだった。
◇◇◇◇
図書室にて開催されたハルカとの勉強会を終えたアオトは、忘れ物を回収するために1人で教室に足を運んでいた。
夕暮れの淡い光が差し込む教室には、当たり前だが誰の姿もない。
「えーっと……あったあった」
アオトは自分の机の中から保護者宛てのお知らせの紙が入ったクリアファイルを取り出すと、そそくさとリュックの中にしまい込んだ。
それと同時に教室の扉が勢いよく開かれた。
「——ん? おお、アオトじゃん。こんな時間まで勉強かよ?」
夕暮れを後光代わりに教室に入ってきたのは、アオトの数少ない友人である佐山だった。クラスは違うが、アオトとは幼馴染なのでそれなりに親しい間柄である。
そんな佐山は泥だらけのユニフォーム姿で、その表情は疲労に満ちている。
「佐山こそ、テスト前だってのに部活か? 相変わらず熱心だな」
「新しい外部コーチが鬼でよ、来週の月曜からテスト期間で休みだってのに今週末は練習試合もあるし……もう勉強なんて微塵もできてねぇから最悪だよ。俺が留年したらアオトも道連れだからな?」
佐山は呆れたような楽しいような、どこか複雑そうな表情で天を仰いでいた。
同性のアオトから見ても彼は爽やかなイケメンの部類に入るので、アンニュイな表情をしてもどこか様になる。
「道連れは遠慮願いたいが、お前も中々大変そうだな。留年したら洒落にならんからちゃんと勉強しろよ?」
「おう。それより、今日の放課後の図書室で星宮さんと黒髪の地味めな男が勉強してたって噂になってたぜ。それアオトのことだろ? なんだ、もしかして付き合ってんのか?」
「いや、別にそういうわけじゃない。たまたま一緒の席になっただけだよ。そもそも俺と彼女じゃ釣り合わないだろ?」
アオトは溜め息混じりに弁明する。
案の定というべきか、図書室の誰かが噂を広めたらしく、つい数十分前の話だというのになぜか部活中しだったはずの佐山の耳にまで情報が入っていた。
「俺は別にそんなことねぇと思うけどな。ちなみに、うちの西園寺先輩が星宮さんのことを狙ってるって噂もあるし、星宮さんはかなりの人気株だからなぁ。このまま取られたんじゃ絶対に後悔するぜ?」
「だから、俺と星宮はそんな関係じゃないって」
アオトは佐山からニヤつきながら茶化すような言い方をされているが、ハルカがなんでもない人から好意を向けられるのを嫌がっているのをよく知っているので、噂の真意についてはキッパリと否定した。
「そうか? 俺はサッカー部では生粋のベンチウォーマーだけど、その代わりに色んなゴシップを懐で温めてるんだぜ?」
「上手いことを言ったつもりかもしれないけど情けないぞ、それ。というか、お前が何と言おうと俺と星宮はそんな関係じゃないからな」
「んだよー、アオトは帰宅部で暇なんだからもっと恋愛しろよなー」
「はいはい、それよりお前はどうなんだ? 浮いた話はないのか?」
「よくぞ聞いてくれた! 俺は、ビッグでボインな大学生のお姉さんが好みなんだ。だから、大学に行ったら本気出すんだ! 高校生に興味はないッ! 俺は他の奴らとは違って星宮さんにはあまりそそられないぞ! なんか裏がありそうだし、たまに見せる真顔がちょっとだけ怖い!」
佐山は嬉しそうな面持ちで自分語りを始めると、メラメラと瞳の奥を燃やして拳を握り込んだ。
彼もハルカと同じく確実にモテる部類に入るのだが、好みが年上のお姉さんに限定されるので、同級生や一つ、二つ上の先輩、年下の後輩等の手が届く近い年齢からの告白は全て即答で断っている。
仲の良いアオトはもちろんそれを知っていて、そんな佐山に恋愛小説なんて見せても理解を示してくれないこともよくわかっていた。
だからこそ、彼にそれを打ち明けて共感を得られず終了する前に、ハルカと意気投合できたのは幸運だった。
「そこまで言うってことは、佐山からすれば星宮は完全な恋愛対象外なのか?」
「まあな。というか、周りはチヤホヤしてるけどよ、俺からすれば底が知れねぇっていうか……難しいんだけど、よくわからねぇんだよなぁ。言い方は悪いけど星宮さんって八方美人だろ? 変な噂は聞かないけど、クラスでは浮いてるお前に構うくらいには優しい感じだし、それも尚更怖いぜ。口下手で無口で俺以外と話さないアオトにわざわざ話しかけるなんて……おかしくね?」
佐山は普段とは違い、珍しく腑に落ちない曖昧な返答をした。
アオトから見ても、確かにハルカは八方美人だった。
だが、そこを疑いたくはなかった。
まだ関係をスタートさせたばかりだったが酷いことをされたわけではないし、むしろ前回のデートは悪くなかったとすら彼は思っていた。
無論、反省すべき点はあったのは事実だが。
「……そうだな」
アオトは心のうちでは反論したくなっていたが、息を呑んで言葉にするのは控えた。
「星宮さんの変な噂は全然聞かないけど……ちょびっとばかし掴みどころがない気がするってだけだ。ってことで、俺は遠慮願うぜ。お前も気をつけろよ?」
「お前は人付き合いが上手いから、そういうのを見極めるのも得意だもんな。俺的には星宮はそんなやつじゃないと思うけどな……」
アオトからした佐山は非常に明るくユーモアのある生粋の陽気者だった。だからこそ、たくさんの人と接して色んな人の内面を知っているし、アオトとは違う発想で星宮のことを評していたりする。
能天気な見た目と口調とは打って変わって、中々に食えない男なのだ。
「だといいけどよ。ちなみに、お前の好みは昔から変わらずか?」
「……昔からって?」
佐山は知ったような口ぶりでアオトに尋ねたが、当のアオトは昔と言われてもすぐにその記憶が出てこなかった。
「子供の頃に言ってただろ。背が低くて愛嬌のあるタイプが好きって。あれだろ、アオトの母ちゃんが高身長で強気な性格だから、その逆の小動物みたいな愛らしい女子が好きなんだよな?」
「確かに言ってたけど、今は分からないな。みてくれだけじゃ人の事はわからないからな」
そういえば子供の頃に女性のタイプの話をしていたなぁ……と、アオトは思い出す。
当時は子供の頃の直感的な発言だったが、そう言われてみると今も変わってないのかもしれないと思い始める。
ただ、まともな恋愛経験が1度として無いので判断しようがない。
「星宮さんはそれとは結構タイプが違うけど、愛嬌はバッチリだしチャンスがあればって感じか?」
「だから、俺と星宮はそんなんじゃねぇよ」
アオトは溜め息混じりに言葉を返すと、佐山の横を通り抜ける。
「帰るのかー?」
「帰って家事をしないといけないんだよ。お前も疲れてふらふらだろうし、気をつけて帰れよ」
「おうよ。またな~」
アオトは佐山に別れを告げて教室を後にした。
廊下を早歩きで駆け抜け、階段を小気味良いステップで駆け下りる。下駄箱では一瞬にして靴を履き替えて、真っ赤に染まりきった空を眺めながら外を歩く。
本当は勉強で頭を使って疲れたので早く家に帰りたかったのだ。
だが、まさかまさかの数少ない友人に会ってしまい、その心身は更に疲弊していた。
佐山は悪いやつじゃないのだが、基本テンションが高い根っからのスポーツマンなので、インドア気質なアオトからすれば真逆の存在だった。
とにかく、アオトは疲れていた。
——西園寺先輩だとかはどうでもいいし、星宮と俺の間には何も起こりようがない。コンテストが終わるその時までは、今の奇妙な関係を継続するつもりだが、それ以降はまだどうなるかわからない。
でも……星宮は悪いやつじゃない。むしろ、俺なんかに構ってくれる良いやつだ。だから、できることなら仲良くしたい。
アオトは一人心の中で気持ちを整理する。
「……帰ろう」
彼は疲れ切った頭を休めるために足早に帰路に就いたのだった。
◇◇◇◇
翌日の放課後。
アオトは学校からダッシュで家まで帰ると、丁寧かつ迅速に部屋の隅々まで掃除していた。
かっちりとした制服から着替えて、今は半袖短パンになっており、その上からエプロンをつけている。
これこそアオトが普段家で過ごす時の格好だった。
というのも、両親は家を出るのが早く、尚且つ帰宅も遅くて毎日忙しい日々を送っているので、こうして帰宅後の掃除や家事、炊事を担うのはアオトの役目となっていたからだ。
2階建てのごくごく普通の1軒家なので、アオト的には特に苦痛ではない。むしろ、毎日のルーティンになっており日常の一部にすっかり溶けんでいるくらいだった。
しかし、今日に限ってはハルカが来るので、いつも以上に念入りに掃除をしておく必要がある。
ある程度フランクに接することのできる相手とはいえ、アオトからしたらハルカは異性のクラスメイトだ。気分的に良い印象を持たれたいのは確かだったし、何よりも勉強のための土台作りという意味でも清潔さは大切である。
空気を循環させるために窓を開放させて換気を行い、床の乾拭きして髪の毛や埃を全て取り、リビング全体のインテリアの位置を調整する。
「……よし」
やがて、ある程度の準備を終えたアオトは息をついてソファに座る。既に帰宅してから30分ほど経過していた。
そろそろハルカが現れる頃だな……アオトがテーブルを拭きながら置き時計を見たのとほぼ同時、インターホンが鳴った。
「開いてるから勝手に入っていいぞー」
アオトは玄関先に向かいながら声をかける。
すると、ゆっくりと玄関扉が開かれて、さらりとゆらめく金髪が扉の隙間からひょこっと覗かせた。
「お邪魔しまーす」
ハルカは楽しげな様子で扉をくぐると、玄関先に立ち止まって軽く会釈をした。
そして流れのままにアオトの姿を捉えて感嘆の声を上げる。
「おー……降谷くん、いつもとイメージが違うねぇ~」
「ん? まあ、家ではこんなもんだろ」
「ギャップ萌えってやつかな? 好きになっちゃったりして?」
「バカな冗談言ってないで早く入ったらどうだ?」
「はいはぁ~い」
ハルカは言われるがままにスニーカーを脱ぐと、丁寧に揃えてからアオトの後を追った。
ラフな格好だが内面は真面目がちなアオトと、制服こそ着ているがフランクな性格のハルカ。
二人は出会って間もないのにテンポ感の良いやり取りを重ねていた。
「飲み物とお菓子を用意するから適当に座って待っててくれ」
「うん。ありがとっ」
リビングのソファに腰を下ろしたハルカは疲れを癒すようにリラックスモードになり、タックインしていたシャツを外に出していた。
キッチンに立ちながらそれを見ていたアオトは、事前に用意していたジュースをコップに注ぎ、お菓子が乗せられたトレーの上に乗せる。
「お待たせ。オレンジジュースでよかったか?」
「うーん、よくわかってるじゃん! ピカピカなリビングとふかふかのソファで味わうキンキンに冷えたオレンジジュースは最高だぁ~」
ハルカは満足そうに頷き、冷えたコップに口をつけてた。
まるで幼子のような純真無垢で柔らかい顔つきになっている。
「好きって言ってたからな。それと、チョコと適当なしょっぱい系のお菓子だ。自由につまんでくれ」
「やるね、降谷くん。相手の好みを覚えるのは恋愛において最重要ポイントなんだよ。これは大幅加点かな?」
「そりゃ良かった」
アオトは他人事のような淡白な反応だったが、内心はハルカが喜んでくれて少しだけホッとしている気持ちだった。
実は、彼は恋愛小説を書くために恋愛そのものを学ぶにあたって、ハルカとの些細な会話内容はもちろんのこと、彼女のみならず大衆女子の好みの把握など、色々とメモに残して勉強と同じくらいの学習をしていたのだ。
故に、こうして小さいながらに努力が報われたのは、彼にとっては大きな出来事だと言えよう。
「んじゃ、始めるか。わからないところがあったら都度聞いてくれ」
「うん。でも、その前に窓を開けてもらっていい?」
「別にいいけど……エアコンも効いてるし、換気ならさっきしたばかりだから大丈夫だと思うぞ? それに、隣の家とは結構近いから声が響くんだが……」
「ごめんね、どうしても窓は開けてほしいの」
「わかった」
理由はわからないが食い下がるハルカのお願いを聞き入れた。
彼は事前に喚起を済ませてエアコンの温度設定も調整していたのだが、どういうわけか彼女は窓を開けることにこだわっているらしかった。
一軒家とは言え、辺りは閑散な住宅街なので騒音の苦情が来ないことを祈る。
何らかの要因があってハルカが悲鳴でもあげたら、通報されること間違いなしだ。
「じゃあ、始めようか」
アオトは現在の時刻を確認してからスタートの合図を出した。
今は午後4時を回る少し前なので、2時間近くは勉強できるだろう。あまり外が暗くなると彼女に迷惑がかかるので、良いところで切り上げて終わらせるか……アオトは頭の中でおおよそのプランを立ててからペンを握ったのだった。
それから時間が流れていき、勉強会はつつがなく進んでいった。
しかし、勉強中、ハルカは急にアオトとの距離を詰めてノートを覗き込んできたり、なぜか姿勢を低くして上目遣いで彼を見つめたり……他にも色々と謎めいた活発さを見せていた。
そこでアオトは考えた。
——もしかして……星宮が色んな男から言い寄られてモテモテなのは、こういうあざとくて勘違いさせる仕草が原因なのでは?
だとすれば俺も危ない。ここで星宮サイドに転げ落ちてしまったら、満を持して想いを伝えた挙句に振られてしまうのは明白だ。
二人きりの勉強会を通して、勉強をしつつも恋愛小説のアイディアを得たいアオトだったが、一旦は恋愛小説のことなど考えずに勉強に集中することにした。
やがて、約2時間が経過した。
「あーーーーーーー、疲れた!」
午後6時前。ハルカはさながら自分の家にいるかのような体勢で、ソファの上にだらしなく寝転がっていた。
姿勢良くソファに座るアオトの太ももの手前辺りまで頭が来ており、未だ勉強を続けている彼のことを下から見上げているような格好だ。
「……終わるか」
アオトは置き時計を一瞥して時刻を確認すると、一つ息を吐いて全身の力を抜いた。本当は視界の端に映るハルカの姿が気になっていたが、あまり注視しすぎても怪しまれそうだったのであえて触れないでいた。
これまでにも彼女は怪しげな行動をしていたので、彼はそのどれもを見て見ぬふりをしてきていた。
「いやー、勉強って大変だね~」
「結構頑張ってたじゃないか。序盤はチョコばかり食べてたから心配だったけどな」
「へへへ、美味しくてついつい……」
ハルカは向きを変えて仰向けからうつ伏せになると、舌を出して茶目っ気のある笑みを浮かべた。
アオトの目からわかるくらいに気分は良さげなのか足をパタパタさせている。
「……まあ、休み休みでも続けることが大切だし、この分なら問題なさそうだな」
「うん。暗記しながら、わからないところは降谷くんに教えてもらって、それを理解に繋げる感じだったら続けられそうな気がする! それに、降谷くんも女の子と二人でお家デートなんてしちゃったんだし、良い案が浮かんだりしたんじゃない?」
「あー……そっち方面は何も考えてなかったな」
「えー、もったいないなぁ~。せっかく私が彼女っぽいアピールしてたのに! 近づいてノートを覗き込んだり、今だって恥ずかしいけど寝転がって上目遣いにしてるんだよ?」
ハルカは上体を起こしてソファの上で足を崩して女の子座りになると、不満そうな顔つきでアオトにクレームを入れた。
「……全部わざとだったのか」
アオトは勉強の合間合間で繰り出されるハルカのさりげない仕草の真意をここで理解した。
アオトからすれば、ハルカは元々ラフでそういう人だろうという認識があったので特に触れていなかったし、何ならモテモテだという話に関連して男を勘違いさせるタイプなんだと解釈していた。
「当たり前じゃん。私は誰にでもそんなことはしないし、今回のはあくまでも降谷くんの経験を培うための作戦だったんだからね? もしかして全然気づいてなかったの?」
ハルカは些か鈍感過ぎるアオトを見て驚いていたが、驚きたいのはアオトの方だった。
わざとらしく胸を張りながら体を伸ばしたり、急に距離を詰めてきたり、消しゴムを取るときに不自然に手が触れたり……アオトは策士な彼女にしてやられたと感じていた。
「全然気づかなかったし、むしろ誰にでもやってるもんだと思ってた。星宮はモテモテだって話をしてたしな。そのせいで数多の男が勘違いしたんだって考えてたな。違ったんだな」
「私は私のことを分かってくれる人しか選ばないからね?」
「悪女じゃないなら良かった。美人局的な腹黒い人だったらどうしようかと思ったぞ」
アオトは冗談混じり言ったのだが、目の前のハルカは少しばかり眉を上げてその言葉に反応していた。
「……全く、せっかくこっちが恥ずかしい思いをしながら頑張ったっていうのにさぁ」
唇を尖らせてぶーぶー口にするハルカは見て、アオトは大人びた見た目に反して子供らしいなと思い空笑いを浮かべる。
「悪かったな。無駄にしないように頑張って小説にするから許してくれ」
「なら許す」
「どーも」
一通りのやり取りがひと段落したその時だった。
テーブルの上に置かれた置き時計が音を鳴らし、午後6時を告げた。
「もう6時じゃん。勉強をしてるのにこんなにあっという間って思ったの初めてかも」
「それくらい必死に頑張ったってことだ」
「よく褒め上手って言われない?」
自分の努力が認められて嬉しかったのか、ハルカはニヤリと笑っていた。
「言われたことないな」
「そう?」
「ああ」
端的な返事をするアオトは校内に友達は佐山くらいしかいないので、こんなやりとりをすることすら稀有であった。
「ふーん。ちなみに、ハルカちゃんは褒めると伸びるタイプだからね? メモメモ」
「はいはい。メモメモ」
アオトはハルカが褒めて伸びるタイプだという新情報を頭の中に植え付けた。
「よろしい、じゃあ、時間も時間だし帰るね」
満足げなハルカはテーブルの上に散らかった教材をリュックの中な収納していく。
その際に一緒に自分が食べ散らかしたお菓子のゴミを片付けようとしたが、それは既にアオトの手によってまとめられていた。
「後は俺が片付けておくから大丈夫だ。まだ明るいが、気をつけるんだぞ?」
「うん、電車だけどそんなに遠くないから大丈夫だよ~」
ハルカは静かに靴を履いて玄関扉に手をかけた。
「そうか。じゃ、またな」
アオトが小さく手を振ると、ハルカも手を振り返す。玄関扉が閉まり切るその時まで。
「……楽しかったな」
アオトはリビングへ向かうと、先ほどの騒々しさとは一転して静けさの漂う空間を見て物悲しい気持ちに陥った。
彼にとっては彼女と過ごした時間は新鮮で楽しいことこの上なかった。
また明日も、明後日も……過ごせたらな、と思う。
「……よし、片付けをして夜飯の準備を始めるか」
アオトは先ほどまでの楽しい気分に浸りつつも、エプロンを締め直し、そそくさと行動を開始した。
散らかったお菓子のゴミと飲みかけのコッピを片付け、半分ほど開けられた窓を閉める。
そんなことを適当にこなしながらも、ハルカとは恋人にはなれずとも、より仲を深めていきたいと率直に感じていたのだった。
最近は毎日のように彼女とLINEでやり取りを重ねているので尚更だった。
◇◇◇◇
翌週の月曜日。
帰りのホームルームを終えたばかりの教室はいつも騒がしいが、今日に限っては普段よりも一段と騒々しかった。
というのも、今日から定期テストの1週間前になるので、全ての部活がテスト終了までは強制的に休み期間になるからだ。
だから普段は放課後の時間を部活で奪われているクラスメイトたちは、皆一様に浮き足立っておりテンションが高いのも頷ける。
しかし、落ち着いた空間を好むアオトは、そんな彼らを一瞥してからおもむろに耳にイヤホンを差し込むと、適当な流行り曲を流して自身と周りの音を完全に断絶した。
「……」
アオトはリュックを背負って席を立ち、横目でちらりとハルカの姿を確認した。
ハルカは机の周りに集まった友人たちと談笑していた。
ホームルームが終わってすぐに友人が集まってくるなんて、アオトからすれば考えられない世界だ。
曲の静かな間奏の部分を突き抜けてアオトの耳に聞こえてきたが、どうやら彼女たちは艶やかな恋バナに夢中になっていたようだった。
ハルカを中心に皆のルックスが整っているためか、クラスメイトの男子たちは彼女たちの恋バナにひそひそと聞き耳を立てている。
その中で西園寺先輩という聞き覚えのある名前も耳に入ってきたが、アオトからすれば何の関係もないので特に興味はなかった。
西園寺先輩というサッカー部のイケメンはさぞモテるのだろう……それくらいの認識だ。
1つ気になるのは、ハルカの表情があまり乗り気じゃなさそうに見えたことくらいだったが、アオトは特に深く考えることなく教室を後にした。
向かう先は下駄箱。目的は早期の帰宅。
彼は足早に外へ出ると、スマホを確認しながら歩みを進める。
「……今日も来るのかな」
アオトは歩きスマホをしながらハルカからの連絡を待つ。
先週、彼女は火曜日から始まり金曜日まで、毎日欠かさずアオトの家に入り浸っていた。土日は自分の家で勉強すると言って来なかったのだが、それを抜きにしても2人はほとんどの時間を一緒に過ごしていることになる。
だからこそ、アオトはどうせ今日もひょっこり現れて、一緒に夕暮れまで勉強するのだろうと考えていた。
しかし、いつもなら来るはずの連絡が一向に来ない。
「……どうしたんだろう」
不思議に思ったアオトは、頭を整理させるために近くの公園に立ち寄りベンチに腰を下ろす。
一度はこちらからメッセージを送ってみようかとも考えていたが、どこか気恥ずかしくなりトーク画面を開いたまま何もできずにいた。
「んー……困ったなぁ」
そそくさと帰宅しても良かったのだが、やはりどこか気がかりだった。というより、アオトは嫌な予感がしていた。
ただ、こちらからアクションを起こすのは……と、胸中では葛藤を繰り広げるしかない。
やむなく、アオトは画面をそのままにスマホを隣に置くと、気を紛らわせるために公園に目をやった。
公園では子供達が遊んでいた。
男の子3人が、キャッキャッと純真な笑顔を浮かべてはしゃいでおり、彼は懐かしさに胸を満たされる。
なぜなら、ここはアオトも子供の頃に遊びにきたことがあったからだ。
当時は5歳にも満たない子供だったが、楽しい記憶というのはいつでも覚えていた。
特に、今座っているベンチもそうだし、反対側の滑り台と隣のブランコの辺りでよく集まっていた。
「……懐かしいなぁ」
アオトは気を紛らわせることに成功し、リラックスした体勢で天を仰ぐ。
しかし、やはり視線はスマホへと向いてしまう。
改めてハルカとのトーク画面を見て不思議に思うと同時に、彼女の身に何かあったのだろうかと少し心配になる。
「あ、来た」
その最中、少しの不安を胸にじっくりとトーク画面を眺めていると、ようやくハルカからメッセージが送られてきた。
『今日は行けない! 急に先輩と遊ぶことになっちゃった! ごめんね~』
ハルカは可愛らしい猫のスタンプと共にメッセージを送信してきた。
ちょうどトーク画面を開いていたアオトはすぐに返信すふ。
『了解』
アオトは端的に返信してからスマホをポケットにしまう。
彼はからすれば、家に来ないなら来ないでそれは別に構わなかった。ただ、約束をしていたからこそ一言くらい連絡が欲しかっただけだった。
ここ最近はハルカが入り浸っていたから尚更だ。
ルーティンとまではいかないが、毎日のように2人で勉強をしていたし、彼自身もそろそろ一人で息抜きをしたいと考えていたので都合が良い。
なので、今日くらいは小説を執筆することに決めた。
勉強会を通して映画の時とはまた違う知見を得ることもできたので、アオトはそれなりに気合が入っているのだ。
「帰ろう」
アオトはおもむろに立ち上がると、目一杯体を伸ばしてから公園を後にしたのだが、前方に見知った後ろ姿を発見したことで溜め息が溢れる。
重力に逆らってツンツンした黒髪で中肉中背の男子は、アオトと同じ高校の制服を着用しており、大きく捲られた腕はこんがりと日焼けしている。
「佐山、お前電柱に隠れて何してんだ?」
「し、しーーーっ! 静かに!」
アオトに声をかけられた佐山はあからさまに取り乱していた。ストーカーに見間違われそうなほど、かなり怪しい挙動である。
「何してんだよ」
「ほら、あれを見ろ」
佐山は不思議そうにしているアオトの肩を右手で力強く抱き寄せると、コソコソと小さな声で前方の人混みを指差した。
「ん? あれは……」
アオトは目を細めて佐山が指差す方向を凝視すると、そこには見知った金髪のボブカットの女子生徒と、その隣には高身長で茶髪の男子生徒が並んで歩いていた。
アオトは金髪のボブカットの女子生徒がハルカであることにすぐに気づいていた。
「俺の言ってた通りだったろ? 西園寺先輩は部活の休み期間を使って星宮さんを落とす気なんだよ。たった1週間しかないのにだぜ。考えられるか?」
佐山は子供のようなイタズラな笑みを浮かべて楽しそうにしていた。陽気でひょうきんな彼は昔のまま性格が変わっていないのだなと、アオトは変なところで安心した。
「だから今日は来れなかったのか」
「何の話だ?」
「いやなんでもない。それより、あれが西園寺先輩か?」
アオトはハルカが今日の勉強会に来なかった理由を察したが、佐山には適当に誤魔化して話を逸らした。
「おうよ。我がサッカー部の不動のエースにして、バリバリのイケメンだぜ。どっかの国のハーフだからか、顔は整ってるし身長も高くて運動神経抜群だ。おまけに頭も良いときた! 家柄も良くて大企業の御曹司って言ってたぞ。めちゃくちゃキザでナルシストな部分もあるけど、それでも凄いだろ?」
「何でお前が自慢げに語ってんだ。凄いのは西園寺先輩だろ」
「まあまあ、俺もある意味あの人に一目置いてんだからいいだろ? それより、どう思う?」
「何が?」
「星宮さんと西園寺先輩だよ。付き合うと思うか?」
佐山はニヤニヤしながらアオトに問いかけた。
正直、アオトとしてはハルカの性格からしてああいったタイプには靡かなさそうだと思っていたが、ここから見る限り西園寺は確かに優れた容姿だとわかる。故に、ハルカがそちらに転んでもおかしくはないのではと考え始めた。
「……どうだろうな」
アオトは適当に答えを濁して、ハルカと西園寺の行方を目で追った。
ハルカは肩を縮こまらせて遠慮がちに歩いているが、隣の西園寺は少々強引に彼女との距離を詰めているように見えた。
ハルカのことを少しは知っているアオト視点だと、あれはハルカが嫌がっているようにしか見えないが、見る人によっては照れくさそうにしている彼女とグイグイ攻める彼氏のような感じもする。
アオトはそんな二人の後ろ姿を眺めながら心の中で分析していると、突如として西園寺がハルカの手首を握ってズカズカと歩いて行った。
「おっ、カラオケに入ったぞ! 俺たちも行くぞ!」
「ちょ、おい!」
行動の早い佐山はさながら西園寺のようにアオトの手首を握ると、サッカー部で鍛えたステップワークを生かして即座に駆け出した。ベンチウォーマーのくせに足だけは速い。
アオトは強引な力の差に抗う術がなく、のこのこのカラオケ店に引きずりこまれていき、気がつけば佐山と2人きりで個室の中にいた。
「……で、何で2人についてきたんだよ。しかも運良く隣の部屋だし」
少々タバコ臭いカラオケの個室で、アオトが溜め息混じりに口を開く。
「へへへへへ、良いじゃねぇか。他人の色恋沙汰に俺が目がないのはよく知ってんだろ?」
「まあな。よく知ってるよ。幼稚園の頃からゴシップ好きだったもんな。で、色恋沙汰ってことは、やっぱりお前の言っていた噂通り、西園寺先輩は星宮を狙ってたのか?」
アオトは悪どい笑みを浮かべる佐山に尋ねた。
少なからずハルカとは交友を深めたつもりだったので、興味がないふりをしつつもやはり少しは気になるのだ。
「おうよ。こうして俺が2人をつけていたのもそれが理由さ。帰ってゲームでもしようとしたら、校門で星宮さんが1人でいるところを見かけてよ。星宮さんは人気者だから普段は誰かと一緒にいるのにおかしいなぁって思ってたら、そこに西園寺先輩が現れたんだよ。なんでも、星宮さんの友達がけしかかて、無理やりデートの予定を作ったらしいぜ? 美男美女だからお似合いだよなぁ~」
佐山はなぜかマイクを片手にエコーのかかった声を響かせながら教えてくれた。
長々としながらもここに至るまでの経緯が簡潔にまとめられており、それを聞いたアオトはすぐに話の大まかな流れを理解した。
「ふーん……だから星宮は教室で恋バナをしてたのか」
「そうなのか?」
「ああ。友達と楽しそうに話してたな。星宮はちょっと嫌そうな顔だった気がするけど」
アオトは帰り際に横目で見たハルカの苦々しい表情を思い出した。
普段はハキハキしている彼女にしては珍しく戸惑っていたような感じだった。
「へー、そりゃぁ意外だな。もしかしてあんまり西園寺先輩がタイプじゃないとか?」
「わからん。でも、最初は興味がなくても後から好きになるパターンかもな」
「そうだなー……ってか、隣の部屋なのに全く音が聞こえなくないか?」
佐山はマイクを置いてハルカと西園寺が入室した部屋の方向の壁に耳を当てると、目を閉じて不思議そうな表情を浮かべた。
「いや……何か聞こえるぞ」
アオトは佐山に続いて壁に耳を当ててみると、薄らと何かが聞こえてきた。だがそれは音楽や歌声ではない。
「……これ、西園寺先輩の声だな。なんか激しく叫んでないか?」
「まさか……」
アオトと佐山は互いに目を合わせると、最悪の展開を想定して息を呑む。
「なんか、嫌な予感がするぜ。西園寺先輩はそんな人じゃねぇって信じたいけど、相手は非力な女の子だからな……一緒に来てくれるか?」
「ああ。もとよりそのつもりだ」
「行くぞ!」
「おう!」
2人は勢いよく部屋を飛び出すと、左手側のハルカと西園寺がいる部屋へ向かい扉の前に密着して耳を澄ませた。
すると、妙な声が聞こえてくる。
「——フッ! ハッ! ハハァッ! どうだい? 子猫ちゃん、僕の美しい裸体は!」
「も、もうやめてください……」
アオトの耳に聞こえてくるのは、西園寺であろう気合の入った元気な声と、力の抜けたハルカの声。
途端にアオトは身の毛がよだち、更に嫌な想像をしてしまった。
しかし、横に立つ佐山は先んじてドアのガラス窓から部屋の中の様子を覗き見ており、呆れたように頬を掻いてニヤけていた。
「アオト、どうやら俺たちはおかしな勘違いをしちまったらしい。ほら、ガラス窓から覗いてみろ」
「……あー……なーんか、気持ち悪いポーズを取ってるな。西園寺先輩ってキザなナルシストなんだっけ?」
アオトは佐山に言われるがままにガラス窓から部屋の中を覗いたが、すぐに後悔することになった。
なんと、部屋の中では靴を脱いで席に立つボクサーパンツの大男が数多のポーズを決めていたのだから。
何を隠そう、大男の正体は西園寺である。彼は一室の照明をパーティー仕様にすることで、サッカー部で鍛えた肉体美をこれでもかと言わんばかりに魅せていた。
「言葉は悪いが、言い換えるなら変態だ。それも極度のな。部活終わりはたまにこういうトチ狂った事をやることはあるんだけど、まさか星宮さん相手にやるとはなぁ……アオトは信じてくれないかもしれないけどよ、あの人、普段の性格は温厚で良い人なんだぜ? ただちょっとタガが外れるとああなっちまうんだ。不思議だろ?」
「良い人かどうかは置いておいて、間違いなくあれは変態だ。表の顔はよく知らないけど、裏の顔があれじゃあ星宮もドン引きだろうな」
情報を持ってて見慣れているはずの佐山でさえ引くくらいだ。一対一でその姿を目に焼き付けさせられる星宮にとっては厳しい試練だろう。むしろ、拷問というべきか。
「はぁぁぁぁ……俺が突撃して西園寺先輩の気を引いておくから、アオトは星宮さんを連れて早く店の外に出ろ。さすがにかわいそーだ」
「いいのか?」
アオトからすれば西園寺には絡まれたくなかったし、できればハルカの事を助けたかったので願ってもない提案だったが、この作戦だと佐山が変態の犠牲になってしまう。
「俺は慣れてる。合宿の時はゼロ距離であの人の全裸を拝んだこともあるし、全裸で尻相撲もした。全裸で手押し相撲もした。全裸で己の武器を……おえぇぇ……っ吐き気が……んじゃ、後は頼んだぜっ——西園寺せんぱーーーーーいっ!!」
佐山は苦しげな顔つきでアオトにサムズアップを見せた次の瞬間。勢いよく扉を開いて部屋の中に転がり込んでいくと、意味不明な奇声をあげながら西園寺の名前を叫び始めた。
「佐山! 佐山ではないか! お前も僕のショーを見にきたのかね!?」
「はいっ! 西園寺先輩! 今日は踊り明かしましょう!」
「ふははっ! やはりお前は良い後輩だ! さあ、楽しいビートをかけろ! 星宮は僕の肉体を見てもノリノリにならないし、むしろ怖がっているように見えたのでな! 予定変更だ! 佐山、いくぞ!」
「お任せあれ!」
アオトは扉を僅かに開けて隙間から2人の意味不明なやりとりを見届けると、ふらふらの足取りでこちらにやってくるハルカに目配せを送る。
「……ふ、ふるやくんっ!」
ハルカは今にも倒れそうなくらい覚束ない足取りでなんとか扉を潜ると、勢いそのままにアオトの胸元へ飛び込んだ。
アオトは一瞬心臓が跳ねたが、動揺を誤魔化すように咳払いをしてやり過ごす。
「とにかく、外へ出よう」
「……うん」
アオトは元気のないハルカの体を支えながら店の外へ出た。
そして、店の近くのベンチに彼女のことを座らせると、彼は優しい声色で言葉をかける。
「星宮、大丈夫か?」
アオトは自分ができる目一杯の気遣いをした。すると、酷い目にあったであろうハルカは涙で潤んだ瞳で彼のことを見つめた。
「だいじょーぶなわけないじゃん! 私が絵が得意なこと話したら急にカラオケに連れ込まれて、一度も歌わずにずぅぅぅーーーーーーっと変なポーズを取って筋肉を見せてくるの! 最初はふざけてるのかと思って、なんですかそれ? って笑いながら聞いたら、真面目な顔つきで、僕の裸体をデッサンしろ! ですって! あれは変態! 変態! ヘ・ン・タ・イ! わかる!? もう……何をされるかわからなくてほんとに怖かったんだから……」
「……大変だったな」
アオトは相槌を打ちながら彼女の隣に腰を下ろす。
金髪を揺らしながら、語気を荒げて早口で勢いよく捲し立てるハルカの姿はかなり新鮮で、普段の彼女からは想像もつかない形相だった。
まるで、その姿が本物かのような出立ちで、吐き出される言葉には違和感はなかった。
とにかく、その吐き捨てるような強い言葉の数々にアオトは内心驚いていた。
だが、それもこれも仕方がないと言えるくらいには酷い目に遭ったのだろうと解釈する。
なぜなら、アオトは気づいていたからだ。
今の彼女の顔は明確に青ざめており、全身が小刻みに震えていることに。
「ほんっとに、毎日西園寺先輩の裸体が夢に出てきちゃうところだったよ。ああいう高圧的で強引な人は……昔からほんとにダメなの」
ハルカは頭を抱えて俯いていたが、思いの丈を吐き出したことで少しだけ落ち着きを取り戻していた。
しかし、まだ正常ではないらしく、憔悴しきったような顔つきだった。
アオトは同情する。あんな変態からダンスを見せられて、それをデッサンしろだなんて言われたら怯えるのも無理はない。
「まあ、真の救世主は佐山だから、今度会った時にでもお礼言っておけよ? 今ごろ、あいつが星宮の代わりに犠牲になってるだろうからな」
アオトは頭の中でサムズアップしている盟友を想起した。彼の犠牲があってこそ、アオトとハルカはこうして無事でいられたのだ。
「佐山くんが?」
「ああ」
「そうなんだ。知り合いなの?」
「端的に言うと俺と佐山は幼馴染だ。意外か?」
「うん。佐山くんって結構明るいタイプでしょ? 降谷くんとは割と正反対な感じだよね」
「確かにな。俺は人付き合いが苦手で見た目通り暗いタイプだから、打算なしに俺と向き合ってくれているあいつのことが好きなんだよ」
アオトからすれば今隣にいるハルカも自身と向き合ってくれる存在だと勝手に思っていたが、真っ向からそれを伝えるのは恥ずかしいので控えた。
「ふーん……一つ気になったんだけど、降谷くんって佐山くん以外に友達っていないの?」
ハルカは口元に手を当てながらアオトに尋ねる。
それは特に嫌味ったらしい言い方ではなく、単純な疑問をぶつけただけだったように彼は思えた。
「いない。昔からずっとな」
アオトは即答した。
佐山の他にも1人だけ幼馴染がいたが、その男の子はある日忽然と姿を消してしまったので行く末知らずである。
その男の子遊んだ記憶は、アオトの頭の中にたくさん眠っていた。
アオトはその男の子名前だって覚えていた。金城、人呼んで金ちゃんだ。
「今は私がいるし、いいじゃん? ね?」
「まあな……で、この後はどうする?」
アオトはハルカから恥ずかしげもなくそんなことを言われたので、ぶっきらぼうに言葉を返して話題を変えた。
ベンチから立ち上がりハルカの事を優しく見下ろす。
「この後?」
「もう精神的に参ってるんだろ? 1人で帰れるのか?」
アオトはハルカを元気つけるために普段は絶対やらないような、かなり得意げな笑みを浮かべた。
そんな彼が繰り出す予想外のユーモアに対して、彼女は意味ありげな様子で俯いて首を横に振る。
その表情はアオトには見えなかったが、きっと微笑んでいるのか頬を緩めているのだろうと勝手に推測する。
「全然ダメ……でも、今日は送ってほしいかな。なんか疲れちゃったしね。いい?」
「ああ。じゃあ、帰ろうか」
アオトはごく自然に右手を差し出した。
「……うん」
ハルカは顔を上げると、体調が悪そうな表情を浮かべながらもその手を取った。
きっと西園寺先輩のせいで疲れているのだろう……そう思ったアオトは優しく微笑みかけて彼女をエスコートした。
そんな二人の繋がれた手は、歩き出すと同時に自然と解けたが、確かに”何か”が芽生え始めていた。
◇◇◇◇
帰宅したハルカは自室のベッドで頭を抱えていた。
「はぁぁぁ……なんなのあのチャラい茶髪は。マジで無理なんだけど! こっちが話題作りのためにちょっと下手に出たら良い気になってさ!」
愚痴るハルカの表情は酷く歪んでいたが、彼女自身は気にも留めず尚も溜まっていた鬱憤を吐き出し続ける。
「まあ、今回は降谷くんが助けてくれたからよかったけどさぁ~……」
ハルカはアオトと西園寺の姿を想起するのとほぼ同時に全身に悪寒を走らせる。
彼女からすれば、西園寺と2人でデートまがいの事をしたのは、完全な話題作りの為だった。
結果的に、以前Twitterでシリーズ化して絶賛大バズり中の『根暗男子と金髪ギャル』に上手く登場させて、西園寺は引き立て役になってもらうからそれはそれで無問題だ。
しかし、思いの外キャラクター性が強いせいで心身ともに疲弊してしまい、挙げ句の果てには打算のみで付き合いを継続しているアオトが現れてしまった。
圧倒的に西園寺のことが苦手になったハルカからすれば、困り果てていた自分のことを助けてくれた彼には少なからず感謝していた。
ただ、それでも割に合わないほど、望まぬ展開の連続だったという事実に変わりはない。
ハルカは西園寺のように興味のない男と付き合うなんて死んでも嫌だった。
おまけに、西園寺は彼女が特に苦手としている高圧的で強引な俺様系の男だった。
「……やっぱり西園寺先輩はちょっと無理かも」
ハルカは助けてもらえて嬉しかったという事実と、西園寺は抱く嫌悪感という奇妙なジレンマに悩まされつつも、頭の中では新たなネタができたと少し喜んでいるのも事実だった。
「まあ、いいか。今日も投稿するネタができたし、映画デート編、勉強会編に続いて、今回が3話目のライバル出現編。今回もバズんのは既定路線かな」
ハルカは一転して楽しげな様子で自室へ戻ると、慣れたように机に向かいペンを手に取る。
初めの映画デート編はたった一晩で数百万人の目に留まることになり、いいねと新規フォロー通知が鳴り止まないほどだった。
続けて、勉強会編も同様で、更なる続編を期待する声も多数上がっていた。
特に勉強会編では頑張った甲斐があったなぁ、と彼女は自分を褒めていた。
特にあまり親しくない異性の家に行ったのも凄いことだが、更にはソファの上に寝転がって上目遣いで見つめてみたり、わざと距離を詰めてノートを覗き込んでみたり……アオトの反応を引き出すためとはいえ、ハルカはかなり身を削った自覚があった。
故に、今回のライバル出現編には期待がかかっている。
「……楽しい」
彼女はつい先日まで承認欲求に飢えていた自分が、今では嘘のように充実していることに気がついた。
でも、同時に、もっと、もっと、もっと……もっと自分の描いたイラストでバズりたい。流行りたい。そんな思いが彼女の胸中に宿り続けていたのも事実だった。
それから数時間。ハルカは手を動かし続けて、今日の出来事を参考にしてイラストを描いていく。
アオトとの勉強会では発揮できなかったほどの高い集中力を維持する。
しかし、唐突にスマホが振動と共に高い音を鳴らし、集中力はハサミで切ったかのようにプツッと解けてしまう。
「……降谷くんからか」
ハルカはおもむろにスマホを見ると、案の定と言うべきかアオトからのLINEが届いていた。
LINEの友達になったあの日から、気がつけば今では毎日のようにたわいもないやり取りを続けていた。
だが、あまりLINEでのやり取りが得意ではなく、自分1人の時間を削られたくないハルカは、こんなことになるなら最初からテキストデータをLINEで送ってもらうんじゃなかったと少しだけ思っていた。
まあ、クラスメイトのみんなと交換しているのに、あの場面でLINE交換しないのは不自然だと彼女は考えたので致し方ない。
「気分転換に返そーかな」
もしもここで彼を蔑ろにして今の関係が切れたら、次の話が浮かばなくなる。
ハルカはイラストを描く際に、恋愛小説や実体験を参考にしているというのは紛れもない事実なので、彼にはもっと頑張ってもらわないといけないのだ。
『体調は平気か? 先週の勉強会で少し詰め込み過ぎたから無理しないで休んでくれ』
「……気遣いができて優しいよね~」
アオトのおかげで勉強が捗っているのは事実だと思っていたし、渋々ながらも色々と協力してくれる彼の評価は他の男子よりも幾分か高かった。
「んー……」
ハルカは迷った末に上手く言葉を選んでメッセージを返す。
『ありがと~! 降谷くんも無理しないでねっ! あとは1人で頑張るから!』
『わからないことがあったら聞いてくれ。ほれと、不躾なことを聞くようで悪いが、星宮は男が苦手なのか?』
『ううん、どうして?』
『なんとなくだ。西園寺先輩のことあんまり好きそうじゃなかったし』
『男の人は別に苦手じゃないよ! ちょっと怖い時もあるけどね。でも、西園寺先輩みたいに高圧的で強引で、力任せに何でもしようとするタイプは苦手かも?』
『そうか。それだけ聞きたかった』
「……何の確認かな? もしかして、私のことを知ろうとしてる?」
ハルカはテンポよく会話を続けてキリのいいところでスマホを裏返した。
何を思ったのか、アオトがよくわからない質問をぶつけてきたことだけが気になっていたが、今はイラストを優先にしたいので再びペンを取って作業を開始した。
やがて、10枚前後のイラストが完成すると、彼女はピックアップした4枚のイラストを慣れた手つきでTweetし、一息つく。
【根暗男子と金髪ギャル】の3話目の更新をつつがなく終えたのだった。
「んーーーー、終わったぁ。余ったイラストは、とりま分かりやすいようにスマホにまとめて移しとこっかなぁ~」
やりきったハルカは疲れた体を伸ばすと、パソコンとスマホを同期させて最後の作業を終わらせにかかる。
今し方書き終えたばかりの数枚のイラストデータをスマホに移していく。
これらは全てストーリーとは関係のないおまけの一幕として仕上げた一枚絵となり、ハルカ自身がバズった反応をリアルタイムで観察しながら都度投稿していく予定である。
燃え滾る炎を消さぬように薪を焚べ続けるイメージだ。
「よし、終わり」
一通りの作業を終えたハルカは椅子から立ち上がり体を伸ばした。
「……ってか、私のどこがいいんだろ。降谷くんってそういうところ見る目ないよね」
ハルカは思い出す。
会った当初から自分のことを優しい人だと話していた彼の言葉を。
——本当に見る目がない。
私はきみのことをネタにして、承認欲求を満たすことしかできないダメな人間なのに。
周りからは優しくて、ノリが良くて、明るくて、人当たりが良くて、誰とでも仲良くなれて、容姿も優れていて、殆ど完璧な人間だって思われてるけど、実際の私はそうじゃない……私は、そんなんじゃない。
でも、そうしないと私は自分を保てないから。
自分を表現できないから、嫌われるのが怖いから。
「……私は悪くない」
ハルカは自身に対する周囲からの評価と、その本性との乖離を問題視していたが、それは過去の出来事の蓄積が産んだ致し方ない産物として処理し、すぐに思考を放棄した。
本当は、逃げてはいけないとわかっていた。
自分自身を取り繕って、周りに笑顔を振りまいて、本当の自分を心の中に隠し込んで、裏では愚痴を吐き散らしているなんて、他の人に知られたらまず間違いなく嫌われる。
だが、そう簡単に自分の本性を曝け出すなんて出来なかった。
「……お風呂に入ろ」
ハルカは脱衣所に向かうと服を脱いで鏡に映る自分の体を眺めた。
「汚い」
ハルカは自分が嫌いだった。
昔、父親に傷つけられたこの体が嫌だった。
首の下から足の先まで、無数の傷が消えることなく生々しく残り、同級生の女子とはまるで比較にならないほど醜かった。
ハルカは怯えていた。
こんな自分が周りに溶け込めるはずがない。過去のトラウマを克服できない自分が心底憎かった。
だから、ハルカはこれからも自分を偽って生きていく。
父親がそうしたように。家庭内では酒に溺れて暴力を振るい、一度外へ出ると近所の人たちに笑顔を振り撒き、そんな表裏一体な生き方を選ぶ。
——だって、私もそうやって躾けられてきたから。降谷くんには、裏でこっそり小馬鹿にしてイラストを描いているだなんてバレるわけにはいかない。
ハルカの頭の中には、今は檻の中にいるはずの憎い父親の姿が想起していた。忘れたくても忘れられなかった。
本当はもっとはっちゃけたいし、クラスメイトとお淑やかに馴れ合うのはむず痒かった。できれば、恋人だって欲しかったし、でも、それを選ぶのが怖かった。もしも父親と同じようなDV男だったらと考えると、碌に異性と付き合うことができなくなっていたのだ。
それこそが星宮晴香だった。
彼女は臆病だった。故に自分を偽る。故に他人の顔色を窺う。
「……おやすみ」
体を清潔して布団に入ったハルカは、今日も翌朝の世間からの反応を期待して眠りに就いた。
そして、翌日、またも50万人のフォロワーを抱えるイラストレーター『すたぁ☆』は大バズりを記録したのだった。
しかし、彼女の承認欲求はこれまでと同じように充分に満たされることはなかったのだった。
◇◇◇◇
1週間後。
「……」
教室の一角、窓際の最後席に座るアオトは、すらすらと問題を解き進めていた。
日々の知識の蓄積があるからこそ、全く詰めることはない。暗記も理解も何もかも、彼にとっては問題ではなかった。
どの教科においても9割以上の点数を確実に取れるよう勉強しているからだ。
しかし、今回は自分だけのテストではない。
アオトにとって最も懸念すべき点は、悩ましげな様子で頭を捻っている右隣のハルカの事だ。
一緒に勉強した4日間は何も問題がなかった。むしろ、ジュースとお菓子を貪りながらも熱心に勉強する彼女の姿は素晴らしかった。だが、変態先輩こと西園寺に会って以降は、彼女の動向をアオトは知り得なかった。LINEで些細なやり取りは続けていたが、授業中の様子を見ても、机の下でスマホを確認するばかりであまり勉強に集中できていないように見えていた。
ハルカはずっと何かが気になって仕方がないような様子だったので、アオトは心配だった。
もしも、星宮が赤点を取って、その後の補習テストに落ちて、再補習テストにも落ちたら……そう思うと、勉強を教えた俺はなんで愚かだったんだと……。
だが、いくらアオトが自責の念に駆られようとも、ハルカは今現在の段階で蓄積した努力を武器に戦うしかないのが現状だ。
だからアオトは祈るしかない。全教科において解答と見直しを最速の15分程度で終わらせてからは、カンニングを疑われない程度に横目でハルカの様子を確認しつつ、机の下で両手を合わせて心の中で神頼みをするのがルーティンだった。
「……頑張れ」
時には机に伏せて誰にも聞こえない声でエールを送り、アオトは根暗で人付き合いが苦手な自分らしくないなと思いつつも、ハルカを気にかけるその想いは真っ直ぐだった。
やがて、5日間に及ぶ定期テストが終了すると、皆がぐったり疲れた様子でテストの感触を語り合っていた。
そんな中で、アオトは普段ならば早々に教室を出て帰路に就くのだが、右隣で顔を伏せて固まるハルカのことが気になってそれどころではなかった。
「……星宮」
アオトは顔を近づけて小さな声でハルカの名前を呼ぶ。
すると、彼女は顔を僅かに上げて苦々しい表情を浮かべたが、ゆっくりと首を縦に振り口を開く。
「大丈夫。赤点は回避できたと思う」
ハルカが口にしたのは今のアオトのことを安心させられる最高の一言だった。
「……良かった」
「ふふ」
青とは柔らかい笑みを浮かべるハルカを見てほっと一安心した。
そんな二人のやり取りに周囲は全く気が付かない。
しかし、長くは続かない。
気がつけば、ハルカの机の周りには何人もの女子が来ていたからだ。
「終わったーーー! マックで自己採点しよーよ!」
「えー、せっかくテストから解放されたんだし、今日くらいはいいじゃーん」
「んー、じゃぁ、記念にプリでも撮る?」
「いいねぇー!」
4、5人の女子生徒たちはハルカを取り囲うようにして楽しげな声色で会話を繰り広げている。
アオトはそんな彼女らの会話を聞き流しつつも席を立つ。
今日は帰ったらゆっくり休もう……アオトは一人でに嘆息してこの後のプランを決めたのだった。
それから彼の行動は早かった。
誰にもバレることなく人の合間を縫って教室を出てから廊下を駆けていくと、テストが終わったばかりで空いている玄関口から堂々と1人で太陽の下に降り立った。
「……絶好の執筆日和だ」
アオトは珍しく晴れやかな顔つきだった。
本来は小説の執筆なんて自室に引きこもって画面と睨めっこするだけなのだが、アオトにとっては実に2週間ぶりの執筆になるので書きたいことは山ほどあったのだ。
ハルカと共に過ごした時間は余すことなく記憶とメモに残してあるので、後はそれを想いに変えて文字にするだけだ。
それから、アオトは家の中へ転がり込むようにして帰宅すると、手洗いうがいだけはきっちり済ませてすぐさま自室へ篭り始めた。
彼はパソコンの画面を見ながら記憶とメモを頼りにエピソードを練り上げていく。やがて、1時間、2時間……と、悠久の時を超えてその日の夜を明かしたのだった。
◇◇◇◇
翌週。
アオトは憂鬱な月曜日の始まりだというのに、美容男子顔負けの艶やかな表情だった。
彼はニヤケが出るのを抑えながら自分の席に座り、真剣な眼差しで手に持つスマホを眺めている。
いつも通り周囲の関心がアオトに向くことはないのだが、隣の席のハルカだけは例外だった。
『良いことでもあったの?』
『金土日で書き続けて五万文字に到達した』
アオトのLINEの通知は相変わらずオフだったが、たまたまLINEニュースを見ていたためにすぐさまハルカに返信した。
『すご』
『星宮は進展あったか?』
『実は私も一枚だけ描けたよ!』
『おー、見せてくれ』
『うん。描くのが遅くて本当にごめんね』
詫びを入れるハルカだったが、アオトからすれば協力してくれているのだから全く気にしなくていいのに、と思っていた。
「……すげぇ」
すぐに送られてきたハルカからのイラストをクリックしたアオトは、そのイラストを見るや否や、無意識のうちに感嘆の言葉を溢していた。
彼はイラストに魅了されてしまい、画像の中の世界に吸い込まれてしまいそうになっていた。
彼女から送られてきたイラストは、私服を着た男女の後ろ姿が描かれていた。
男の方は真面目そうな印象で、腕には時計をつけて、地味な格好で真っ直ぐな姿勢で歩いている。
一方、女の方は元気そうで活発な印象で、肩から下げた小さなバッグと、足を曝け出した爽やかな格好はその明るい性格を窺わせる。
そんな二人が歩いているのは、どこかの建物の中だったが、その場所をアオトは知っていた。故に思わず感傷的な気持ちになる。
また、イラスト全体には夏から秋への変わりゆく様を感じさせるスカイブルーを中心とした夏っぽいような色合いが使われており、その情景と季節感がよりリアルに感じられる。
このイラストは、アオトにとってただの絵画以上の意味を持っているようで、彼の心を奪うだけでなく、思い出を呼び覚ますものでもあった。
「……」
アオトはその感動を言葉にして伝えようと、はやる気持ちを抑えながらも指で文字盤をフリックする。
『ありがとう。星宮は必ずプロになれるよ』
嘘偽りない言葉だった。
『そう?』
『なれる。何の保証もないが俺はそう思う。感動した。星宮は凄いよ。俺はそれくらいこの絵が好きだ』
アオトは行き当たりばったりで突発的な言動はあまり好まないのだが、それでもハルカのイラストは一目見ただけでイラストレーターとして成功しないわけがないと確信していた。
『後で俺が書いたテキストも送るから読んでくれ』
『うん』
こうして一連のやり取りを終えると、アオトはスマホを机に伏せて天を仰いだ。
ハルカが描いたイラストを見たことで、その気持ちはより一層の充足感を抱いていた。
きっと、描き終えた彼女もそうに違いない。
そう思ったアオトは右隣にいるハルカの姿を横目で一瞥したのだが、それとほぼ同時に担任が教室に入ってくる。
授業開始前のショートホームルームが始まった。
「おはようございます。いつもはこの時間を読書や自習のために充ててましたが、本日は転校生の紹介をしたいと思います」
アオトのクラスをまとめあげる中年の女性教諭は、特にサプライズ感を持たせずに割と重大な発表をした。
皆が呆気に取られた顔つきになっていたが、ほんの数秒の静寂をおいてからすぐさまクラス全体が湧き立った。
早朝だというのに騒がしい。でも、転校生は珍しいなと、アオトは窓の外を見て考える。
彼はどうせ自分と接点を持つことなどないと思っているので最初から興味がないのだ。
「せんせー、男? 女?」
「女の子です。白銀さん、どうぞ」
中年の女性教諭はチャラついた生徒をあしらうように答えると、教室の外へ向かって手招きをして件の転校生の名前を呼んだ。
アオトは尚も窓の外に視線を向けて、秋を実感させる一匹のトンボと見つめあっていた。
「初めまして。白銀香澄です。東京の女子校から来ました。共学に通うのは初めてなのでみなさん仲良くしてください。お願いしますっ!」
「はい、白銀さん。ありがとうございます。席は廊下側の一番後ろの席が空いてるのでそちらにお願いします」
アオトがトンボと見つめあっている間に自己紹介は終わったらしく、教室の中は白銀香澄——カスミへの拍手と声高らかな男子の叫びで満たされていた。
彼はここでようやく転校生の女子に目を向ける。関わり合いを持つことはないと思うが、一応クラスメイトになったので、見た目と名前くらいは頭に入れておくことにした。
ダークブルーっぽい髪色は尻尾のように結われており、言わばポニーテールだった。
容姿は低身長で150センチないくらい、それと胸がメロンのように大きい。
アオトが何の気なしにボーッと観察をしていると、なんとなく、一瞬、彼はカスミと目が合ったような感覚を覚えた。
しかし、すぐにそれは勘違いだろうと片付ける。
「……白銀……珍しい苗字だな」
そんなアオトの呟きは、未だ続く喧騒に押しつぶされて消えていったのだった。
◇◇◇◇
転校生がやってくるという一大イベントはあったが、つつがなくその日の授業は終わっていた。
アオトはいつものように手際良く帰りの支度を済ませると、ちらりと星宮に目配せを送ってから席を立つが、肝心の彼女は友達との会話に夢中になっていてからに気がついていないようだった。
いつの間にやら復活していて、今朝の照れはなんだったのか、既にいつもの調子を取り戻していた。
アオトは少しくらいハルカと会話を交わしたいと思っていたが、今はその時ではなさそうなので大人しく帰ることにした。
今なら例の転校生がクラス中の関心を集めているので、堂々と歩いて抜け出すことができる。
「……」
こうして、アオトはさながら忍びのように、誰にもバレることなく廊下へ出た。
同時に他クラスの生徒たちが転校生の姿を一目見ようと、二つある教室の出入り口に詰めかけてくる。
危ない危ない……アオトは内心冷や汗かきながらも胸を撫で下ろす。
だが、彼らがごった返しているせいで、いつも使っている正面の階段までは辿り着けそうもなかった。
「遠回りになるが裏から行くか」
アオトは野次馬たちを一瞥してから踵を返すと、長い廊下を歩いてひと気の少ない裏手へ向かい、先ほどとは打って変わって閑散としている階段を駆け下りた。
しかし、そんなアオトが階段の踊り場に到達した瞬間、彼の目の前に一人の女子生徒が立ち塞がるようにして躍り出てきた。
「——ねぇ、ボクのこと覚えてる?」
「……え? 俺?」
突如として眼前に現れた女子生徒の目は間違いなくアオトの姿を捉えていた。
彼はまさか話しかけられたのが自分だと思わずに動揺を露わにする。
というのも、その女子生徒は、今朝方転校してきたばかりの白銀香澄だったからだ。
彼女はまんまるの愛らしい瞳をキラキラと輝かせながら、アオトのことを見上げている。
「わぁ……その顔、やっぱりそーだ! 久しぶり!」
カスミは力の抜けたアオトの両手を自身の両手で握り込むと、ぴょんぴょんと跳ねながら喜びを露わにしていた。
「……えーっと、どこかで会ったっけ?」
「え、ボクのこと、忘れちゃったの?」
悲しげな顔つきで小動物のようにしゅんと俯いているが、本当にアオトは彼女のことを知らなかった。
忘れちゃったの? と、間近で言われても、何一つとして思い出せない。
そもそも、彼には星宮を除けば女性の知り合いなど存在しないのだ。
「……うーん」
アオトはカスミの顔をじっくりと見てみた。
ダメだ。彼は心の中で諦めの言葉を口にする。
どう足掻いても記憶の中に彼女の姿を見つけ出せなかった。
「悪い。やっぱり人違いだと思うぞ?」
「えー! もしかして記憶喪失? あんなにたくさん遊んだのに、ボクのことを忘れちゃったってこと!?」
「いやいやいやいや。俺は生まれてこの方、女の子の友達なんてできたことないんだよ。だから、白銀さんは赤の他人。OK?」
食い下がってくるカスミのことを少し鬱陶しく思ったアオトは、きっぱりと言葉で拒絶の色を示した。
彼も昔から付き合いのある佐山が相手なら別だが、赤の他人、ましてやクラスメイト、しかも転校生にこんなことは言いたくなかった。だが、こうしないと変な幻想を抱かせて付き纏われそうな予感がしていたのだ。
「うぅぅ……もう知らないっ! アオくんのばかぁぁぁぁーーーー!」
アオトから拒絶の意を突きつけられたカスミは、まるで幼子のような純真な瞳から涙を溢すと、とてとてと小さな体で階段を駆け上がっていってしまった。
彼は少し言いすぎたかなと思いつつも、自己防衛のためには仕方のない判断だと解釈して今の出来事は忘れることにした。
「……帰るか」
「降谷くぅーん? 女の子を泣かせたらダメなんだぞ~?」
「はぁぁぁ……星宮、見てたのか?」
気を取り直して帰ろうとしたアオトだったが、予想外の相手に呼び止められて溜め息を吐いた
「まあね~。ってか、向こうは降谷くんのこと知ってる感じだったけど、本当に赤の他人なの?」
ハルカはカスミが走り去って行った方向を見ながら、ゆっくりと階段を下りてくる。
この口ぶり的にどうやら一連の流れを見ていたようだ。
「当たり前だろ。俺の知り合いといえば、佐山と星宮……超ギリギリ西園寺先輩くらいじゃないか?」
「え、それって怖くない? 向こうは跳ねて飛んで手を握っちゃうくらいの相手を勘違いしてるってことでしょ?」
「まあ……よっぽどその相手が好きだったんだろうよ」
「……うんうん、こっちのライバルも登場か。面白くなってきた」
「何か言ったか?」
小声で何かを口にしていたハルカだったが、アオトの耳には届いていなかった。
「ううん」
「そうか? んで、ここには何しにきたんだ。たまたま通りがかったわけじゃないんだろ?」
アオトはおもむろに用を尋ねた。
こんな正面玄関から離れた裏の階段を使う生徒はあまりいない。
「たまたまだよ」
「そうか」
ハルカは即答したが特に深く言及することでもないので、アオトは軽く流すに留めた。
同時に、一連の会話が終わったことで、2人きりしかいない狭い踊り場には沈黙が訪れた。
途端にしんとした静けさが辺りを支配したかに思えたが、それを破ったのは、ハルカのスマホから聞こえる通知音だった。
彼女はおもむろにポケットの中からスマホを取り出すと、指でスワイプしながら何かを確認していた。
表情が今まで見たどの瞬間よりも生き生きとしており、それはむしろ恍惚と表現するのが相応しいくらいだった。
「何してるんだ?」
気になったアオトは何の気なしに尋ねる。
「んー? えーっとね……まあ、色々かなぁ」
誤魔化したハルカだったが、一目見てわかるほどには口角が上がっていた。
幸せを噛み締めているようにも見える。
しかし、そんな時。
彼女はふとした拍子に手のひらの中からスマホが滑り落とすと、それはアオトの足元にやってきた。
「……あ」
先に声を漏らしたのはハルカだった。単にスマホを落としただけだというのに、彼女は取り返しのつかない失態を犯してしまった時のようにその顔を青褪めさせていた。
しかし、アオトからすれば何のことかわからない。
「ん?」
アオトはハルカのスマホを拾い上げる。単なる親切心だった。
スマホの液晶は上を向いており、そこにはアオトの知らないアニメ調のイラストが表示されていた。
イラストには艶やかなボブカットの金髪を揺らして陽気に笑う女子生徒と、一転して暗そうな雰囲気を醸し出してはいるが楽しげに微笑む黒髪の男子生徒の姿が映っている。
一見すると、仲睦まじい男女のイラストのようだっったが、彼は妙な既視感を覚えた。
アオトは見覚えのないはずのイラストなのに、どこか記憶の微かで知っているような光景だと感じていた。
「これは何だ?」
アオトからすれば単純な疑問だった。
このイラストは俺のために描いてくれたのか、そういう意味を込めて尋ねたのだが、目の前にいるハルカはどういうわけか心底焦った顔つきになっていた。
彼女はごくりと息を呑むと、そこから間髪入れずに飛びついてくる。
「……返して!」
「ど、どうした? これは俺と星宮じゃないか? それに……同じようなイラストが何枚もあるけど、どれも俺が見たことのないイラストだな」
ハルカがスマホを奪い取ろうとしてきたが、胸に残る疑念を晴らしたいアオトはバックステップを踏んで距離を取った。
普段の彼ならこんなことはしない。
ただ、今は自然と反射的に体が動いていたようだ。
「これは俺のために描いてくれたイラストじゃないのか?」
アオトはどうしてそれほどまでにハルカが焦っているのか、全く理解できなかった。
彼から見たこれまでの彼女は、活発で明るい性格ながらもどこか達観した部分もあり、同い年の割に経験値が高くて余裕を持った存在だった。なのに、今はおかしなくらい動揺を明らかにしている。
しかし、そんなアオトの妙な疑念はすぐさま振り払われることになる。
「……そう、そうだよ。これはね、降谷くんのためを思っていっっっぱい描き溜めたイラストだよ! びっくりした?」
突如として、ハルカは満面の笑みを浮かべて、明るく朗らかな雰囲気を作り出すと、まるでドッキリのネタバラシでもしているかのような軽い口調で言い放った。
「え? まじ?」
ハルカの真意を知ったアオトは胸を跳ねさせて喜びを露わにして聞き返す。
「うん! いや~、このイラストは降谷くんが書いてくれた小説とは関係ないオリジナルだったから、本当は後で見せて驚かせようと思ってたんだぁ~。まさかスマホを落としちゃうなんて、私ってばおっちょこちょいだよね~」
「……そういうことか。良かった。なんか良からぬ事情でもあるのかと思ったぞ」
アオトは何がない様子で距離を詰めてきたハルカにスマホを返してあげた。
さすがのアオトもまさか彼女がオリジナルのイラストを描いてくれるとは思っていなかったので、驚きと同時に安心の念が胸中を支配していた。
彼はてっきり彼女が自分にとてつもない隠し事をしているものだと考えていたが、その疑念は今の今で振り払われることになったのだ。
「そんなわけないでしょ? 私たちはアオハルコンビだよ? コンテストまでは後2ヶ月ちょっと! 2人で頑張るよ」
「……そうだな。うん、頑張ろう。確か文字の規定は10万字だったはずだし、もっと気合いを入れないとな」
現状は5万字に加えて、ハルカのイラストが1枚。
コンテストの応募にあたってイラストの提出は特に不要なのだが、やはりアオト的には自分の書いた小説にイラストが添付されると気合が入るのだ。
「うんうん、その意気だよ。私も筆が遅いなりに頑張ってみるから、悔いのないようにしよ?」
「ああ、星宮がそう言ってくれると俺もすごいやる気が出てきたよ」
「いいね~!」
ハルカは肘でアオトのことを小突くと、いたずらっ子のような笑みを浮かべた。
「……あんなにたくさん描いてくれてありがとな。本当に、嬉しいよ」
アオトはすぐ側にいるハルカを横目で見ながら、照れ臭さを感じつつも言葉にして感謝を伝えた。
「お互い様でしょ?」
「そう言ってくれると助かるよ」
優しく微笑んでくれるハルカを見て、アオトは穏やかな心に満ちていた。
窓から差し込む淡い陽の光もそんな彼の安らかな思いを増長させる。
「あっ、それと話は変わるけど、再来週は修学旅行でしょ? 誰と回るのか決めた?」
「……もう、みんなそういう話をしてるのか?」
「え? もしかして1人?」
「まあ、そうだな」
アオトは特に誤魔化すことなく答える。
単に友達が少ないだけで別に恥ずかしいことではない……と、彼女との交友関係の格差を肯定する。
「いいなぁ……」
「え?」
ハルカが羨望の眼差しをアオトに向けながら何かを口にしたが、彼の耳には届いていなかった。
「な、なんでもないよ!」
「ん、星宮は誰と回るんだ?」
「私は友達とだね~。たくさん誘われちゃったから大所帯で大変だよ」
ハルカはあんまり乗り気ではないのか、傍目でもわかるくらい明らかに肩を落としていた。
「楽しそうじゃないか」
「1人の方が気が楽じゃない? 周りに気を遣わなくていいし、やりたいことが好きにできるよ?」
「それもそうだな」
ないものねだりとはよく言ったもので、アオトは交友関係が広いハルカのことが少しだけ羨ましく思えていた。
「うん……それじゃあ、私はそろそろ行くね」
「ああ」
「うん……あ、それと、明日の放課後に白銀さんの歓迎会をやることになったんだけど、来る?」
「いや、大丈夫だ」
「そ、またね」
アオトは階段を上っていくハルカに手を振り今日のところは別れを告げた。
そして、1人になって胸を撫で下ろす。
「よかった」
思わず口にする安堵の言葉。
アオトは数多くのイラストを描いてくれたハルカへの感謝の念が絶えなかった。
そして、沸る情熱を無駄にしないためにも一つ心に誓う。
——今日は帰ったらすぐに執筆に取り掛かろう。
俺と星宮をモデルにした恋愛小説も既に5万字になり山場を迎え始めている。そろそろ恋のライバルなんかも登場させてつつも、最後は2人がハッピーエンドで終われる未来を目指す……。
彼が思い描く恋愛小説は、平和な世界観で感動的な描写を織り交ぜつつも最後は誰もが不幸にならないハッピーエンドだった。
だからこそ、アオトはハルカと過ごす時間をより大切にする必要がある。
そんな物語の最後を想起するにつれて、彼はこれまで抱いたことのない気持ちを胸に秘め始めていた。
「……星宮」
1人でに、アオトは彼女の名前を呼ぶ。
同時に心臓がとくんっと大きく鼓動した。
この想いの真実にアオトはまだ気づかない。
◇◇◇◇
その日、部活を終えた佐山は、先輩たちに挨拶を済ませて部室を後にしていた。
「では、佐山よ! 部活終わり恒例の僕のショータイムに立ち会えないのは残念だが、教室に忘れ物をしたということであれば仕方があるまい! 明日は必ずや参加するようにっ! ではな!」
「西園寺先輩、別れの挨拶はいいですから先に服を着てください」
「うむ!」
「んじゃ、おつかれっした!」
佐山はいつも通り全裸な西園寺に挨拶を返すと、そそくさとグラウンド近くの部室を離れて校舎へと戻る。
「ふぃーーーーー、今日も疲れたぜ、マジで鬼コーチやべぇって」
佐山は疲労を感じて震える足を懸命に動かしながらボヤいた。
向かう先は教室だ。今日の体育でジャージが汚れたので回収しなければならなかった。
佐山としては疲れたので早く帰りたかったのが本音だが、汗が染みたジャージを放置したくはなかったのでやむなく教室へ向かう。
時刻は既に午後の7時を回っており、この時間はサッカー部と一部の教員しか校舎にはおらず、一般の生徒が下校済みなこともあってか教室は閑散としている。
「あったあった」
佐山はジャージが入った袋を回収してそそくさと教室を後にする。
「……あー……かーえろ。俺も彼女がいたらサイコーだったのになぁ。西園寺先輩みたいな容姿が欲しいぜ。唯我独尊で破天荒な性格と特殊な変態性はいらねぇけどな」
退屈凌ぎに独り言をぶつくさ口にする。
ぶんぶんと布袋の持ち手を振り回しながら歩みを進める。
周囲には誰もいないので言いたい放題だ。しかし、廊下へと出て一階へ続く階段へ向かう最中、明かりのついた教室が目に入った。
「あそこはアオトのクラスだな。誰かいんのか?」
佐山はじっと瞳を細めると、暗い廊下に明かりが漏れる教室を見やった。
まだ午後の7時とはいえ、秋口になっているため既に外は暗い。
こんな時間まで残っている生徒は、巡回している教員に帰宅を促されそうなものだ。
不思議に思った彼は、まるで夏の虫のように明かりに引き寄せられていく。忍び足で距離を詰めると、恐る恐る薄ら開かれた戸の隙間から、教室の中を覗き込んだ。
すると、そこには予想だにしない人物がいた。
「ありゃあ、星宮さんか? 一人で何してんだ」
佐山の視線の先には、席について忙しなくスマホを弄るハルカの姿があった。金髪のボブカットだからよく目立つ。
彼からすればあまり関わりのない相手であったが、最近は友人のアオトが親しくしているという噂もあるため少しばかり気になっていた。
「……」
佐山は息を顰めてハルカのことを凝視する。
特に何をするでもない。
彼女は激しく貧乏ゆすりをしていて、あまり機嫌が良くなさそうだったのは能天気な佐山でもわかった。
——星宮さんってこんな感じなのかよ。
心の中で佐山が動揺したのとほぼ同時のこと。
「あー……ほんとに最悪」
ハルカは佐山が見ていることなどつゆ知らず、ドスの効いた低い声を出す。
普段の高くてよく通る耳障りの良い声とは大違いだった。
「え?」
佐山は思わず素っ頓狂な声をあげたが、咄嗟に自身の口を真一文字に塞ぎ難を逃れる。
そして、続け様に吐かれたハルカの言葉に耳を澄ます。
「みんな私に期待しすぎだっての。笑顔を振りまいていい子ちゃん振んのがどんだけ疲れると思ってんのよ。ってか、この髪は地毛だし真似したいとか知らないから。私の気持ちも理解できないくせに擦り寄ってこないでほしいんだけど。どうせ私のこんな姿を知ったら幻滅するくせに」
ハルカは決して怒鳴ることはせず、極めて静かな口ぶりだったが、鈍感な佐山でもわかるほど物悲しい雰囲気を身に纏っていた。
「……どういうことだ」
佐山はごくりと息を呑む。
おそらく見てはいけない光景なのだろうと理解していたので、罪悪感に苛まれてしまう。
しかし、ゴシップ好きな彼はこの機会を逃すまいと、目の前の光景と彼女の発言を目と耳に焼き付けていく。
それもそうだ。
皆から人気者で、色んな場所で多くの話題が絶えない星宮晴香という女子生徒が、まさかこんな裏の一面を持っていたなんて誰も想像していなかったから。
「ねぇ……きみは優しいから、本当の私の姿を見ても幻滅しない? 心も体も醜いし、必死に自分を作らないと生きていけない。きみの小説に出てくるお姫様みたいな女の子じゃないんだよ? イラストで見たような綺麗な笑顔は作り物なんだよ?」
ハルカは静かに席を立つと、左隣の席の机と椅子を見下ろしながら囁くような声で言葉を紡ぐ。
佐山からすれば意味がわからなかったが、確かにハルカの声は泣いていた。
「……なんで、泣いてるんだ。しかもその席って……」
佐山は数多くの疑問が頭を満たし眉を顰める。
ハルカが日頃から我慢しながら、誰かと付き合いを継続しているのはわかった。
表向きはあんな人当たりの良い性格なのに、裏では過度な鬱憤が溜まっていて、周囲との温度差がありすぎるという事実は佐山の想定外だった。
ゴシップ好きである彼でも全く知り得ない情報ということは、これまで上手く隠して生活してきたのだろうとわかる。
佐山としてはもっと観察を続けていたかったが、小心者な彼はもう見ていられなくなっていた。
もしも接触なんかしてしまった時には、何をされるかたまったもんじゃない……彼は一つ息を吐いて一歩後退した。
しかし、確かな焦りが行動に現れてしまい、ジャージの入った布袋が扉に接触する。
——ガタッ……静寂に包まれる薄暗い廊下に、違和感のある小さな音が響く。
「誰!?」
ハルカは即座に反応すると、焦燥感に駆られた目つきを扉の隙間に向ける。その反応の早さから、余程人に見られたくない光景だったのだとわかる。
刹那。
佐山は彼女と目が合ったような気がしたが、そんなことを考える余裕などなくわ物音など気にせず、気がついたらドタバタと必死に駆け出していた。
ドッと全身から冷や汗があふれ出てくる。
背後は振り返らずに、暗闇に塗れて階段を駆け下りる。下駄箱で靴を履き替えたら、教室の窓から見られないように校門を出てすぐに裏手へ回り、わざと遠回りをして帰路へ就く。
「はぁはぁはぁはぁ……っっ……や、やべぇよ、マジで……」
佐山はサッカー部で蓄積した疲労など感じさせない猛ダッシュで学校から離れると、周囲に誰もいないことを確認してから息を落ち着かせた。
「——あ、あの席って確かアオトんとこだよな? まさか、いや……でも、わかんねぇけど、どっちにしろ星宮さんってかなりイメージと違ったな……」
佐山は混乱の中でうろ覚えであったが、ハルカが見下ろして語りかけていた席の位置を思い出した。
あそこはアオトの席だった。
でも、わからないことの方が多い。
小説とイラストというワード……佐山には全くピンとこなかった。
今はいくら考えても何も思いつかない。
佐山は、自分自身も含めて、皆がハルカに抱いていたイメージとの乖離が深すぎるあまり、すっかり思考回路が麻痺していたからだ。
「……変な夢、だよな。うん、夢だな!」
考え込んだ末に、佐山はいったん都合の良い方向に話を片付けると、ふらふらとした足取りで家路を辿ったのだった。
その後、家に帰って落ち着いた頃に再度思考した結果、先程の出来事が現実だと知り頭を抱えることになるのだが。
◇◇◇◇
翌日の放課後。
アオトは珍しく佐山に呼び出されていた。
場所はグラウンドの側にあるひと気のない石階段の中腹部。二人は拳ひとつ分空けて並んで座っている。
「佐山、俺はやる事があるから忙しいんだぞ」
アオトは恨めしそうな目つきで左隣に座る佐山を睨みつける。
今日の放課後は、近日控える修学旅行に向けた日用品と衣服を買う予定があったのだ。
「馬鹿、俺だってもう部活の時間だからうかうかしてらんねぇんだよ」
「じゃあ、早く本題に入ってくれよ」
「わかったよ。んじゃ、1つ聞くぜ。お前、小説とか書いてるか?」
「へ?」
いきなり突拍子もない質問をぶつけられてアオトは、反射的に肩を大きく震わせた。
「その反応、ビンゴだな」
佐山はしてやったりといった様子で口角を上げる。
「な、なんで俺が小説を書いてるって知ってんだよ!」
「聞いたんだよ」
「誰から?」
アオトは間髪入れずに尋ねる。
「……驚くなよ?」
「お、おう……」
もったいぶった佐山に対して、アオトはごくりと息を呑む。
「星宮さんだ」
「は? 星宮が? お前と星宮は殆ど繋がりがないはずだろ? いつどこで聞いたんだよ」
「まあまあ、落ち着けよ。まずは昨日の部活終わりのことだ。俺はたまたまお前のクラスの教室の明かりが点いていることに気が付いてよ、なんだなんだと思って覗いてみたら、何とそこには星宮さんがいたんだよ。時刻は夜の7時過ぎだ」
「それで?」
気になる点も散見されたものの、ここまでは特に変哲のない話だったので、アオトは適当に相槌を挟むに留める。本当は心臓の鼓動が早くなっていたが、友人である佐山のことを信頼して冷静になる。
「んで、そしたら急にだぜ? 星宮さんがお前の机を見下ろして、小説やイラストはどうこうとか……作り物の笑顔とか、正直俺もビビってはっきりは覚えてねぇんだけどよ、いつもの星宮さんとは別人みたいにぶつぶつ何か言ってたんだよ」
「……悪い、その説明じゃよくわからないんだけど、星宮が夜の教室に1人でいたってことか?」
「おう、その通りだ。めちゃくちゃ低いテンションでな」
佐山は力強く頷いた。
長年の付き合いがあるアオトは、彼が嘘をついているようには見えない。
しかし、話を聞いて状況を整理してみても、全く想像もつかずあり得ないとしか思えなかった。
「そもそもそれは本当に星宮なのか? 本当に別人だったってことはあり得ないか?」
「おいおい、星宮さんなんて地毛が金髪なせいで、どこにいても1番目立つんだから見間違えねぇよ」
「ふーん……何で俺に教えてくれたんだ?」
「お前は星宮さんと仲良くしてんだろ? 昨日なんてよ、『きみは優しいから、本当の私の姿を見ても幻滅しない』って、お前の机を見下ろしながら言ってたんだぜ? 意味深すぎて理解不能だけど、何か裏があると思わねぇか?」
佐山は珍しく顎に手を当ててじっくりと考え込むような仕草を見せた。
しかし、そんな彼の言葉など間に受けていないアオトは、大きく溜め息を吐いた後に口を開く。
「……ちなみに、全く話は変わるが、昨日の部活はどんな感じだった?」
「クッッッソ疲れたな。鬼コーチに走らされまくって、もう帰りはフラッフラだったよ。帰ったらすぐに爆睡して、朝起きたのもギリギリの時間だったな」
「わかったぞ。佐山、お前は疲れてるんだよ。夢でも見たんじゃないか? そもそも星宮がそんな人じゃないのはよく知ってるだろ? いくらゴシップが好きだからとはいえ、そんな話をしても誰も信じないぞ?」
アオトは佐山の話を全て一蹴した。
ゴシップ好きでありもしない噂ばかりを懐で温めている彼の話など、最初から信憑性は薄いとすら思っているくらいだ。
「はぁ!? 違ぇよ、俺は確かにこの目で見てこの耳で聞いたんだよ! もしも俺の話が嘘なんだとしたら、どうして俺はお前が小説を書いてるって知ってんだよ!」
「うーん……俺の唯一の友達だし信じたいのは山々なんだけどさ、どうしても星宮がそんな事をするとは思えないんだよな。お前が俺の小説のことを知ってるのだって、たまたまスマホを見たからとかじゃないか? 俺ってパスワードとかかけてないし、な?」
佐山はオーバーすぎるリアクションで仰天して見せたが、アオトの心には全くと言っていいほど響いていなかった。
むしろ、尚もハルカを疑い続けている佐山に辟易しているくらいだった。
「……お前、毒されてるんじゃないか? 大丈夫か? 利用されるような心当たりがあったり、変な頼み事とかされてないか? 美人局とか金銭目的の詐欺とか……ねぇか? イラストがどうこう言ってたし……ちょっと怪しいぜ?」
「大丈夫だよ」
アオトは即答する。
小説を読んでもらい、イラストを描いてもらう。
そして、ゆくゆくはクリスマスの日に控えるコンテストへの応募を目指す。アオトとハルカの間には他人に言えないそんな秘密があったが、彼からすればそれは佐山に心配されるような問題事なんかじゃない。
「……ならいいけどよ。とにかく、ちょっとは気をつけたほうがいいぜ。忠告はしたからな。多分だけど星宮さんはお前が思ってるような人じゃないぞ。それと、俺の話はゼッテー夢じゃねぇから、それだけは覚えとけ!」
佐山はアオトにビシッと指を刺して力強く言い放つと、重たそうなリュックを背負って駆け足で立ち去った。
「相変わらず心配性だな、あいつは」
アオトは嘆息すると、佐山から聞いた話を頭の片隅に入れて昔のことを思い出した。
彼と佐山の付き合いは五歳になる少し前からになるが、当時から陽気で人に優しいやつだった。
いわゆるお人好しで心配性気味な性格は今も変わっておらず、時折りアオトのことを気にかけている。
また、互いの両親も親しい関係を築いており、俗に言う幼馴染というやつだった。
そんな幼少期には、別の人物もいた。
それは、金城こと金ちゃんである。
同い年の少年、金ちゃんは、男気のある性格で2人ともすぐに仲良くなった。
しかし、アオトと佐山、そして金ちゃんが仲を深めてから半年後のある日、金ちゃんは忽然と姿を消した。
アオトは幼いあまりその理由をよく覚えていないが、金ちゃんがいなくなってショックを覚えた記憶はある。
だから、その時から、一度築いた関係は大切にしたいとも思うようになっていた。
それは、幼馴染である佐山はもちろんのこと、直近で知り合った星宮もそうだ。
アオトは佐山の話を完全に否定するつもりはなかったが、やはり彼の話を聞いたせいで彼女のことを信じきれない気持ちも大いにあった。
「……佐山の話が本当なら、星宮はどうしてそんなことをしてるんだ?」
アオトは一つ呟き立ち上がると、一人で校舎を後にする。
道中、俯いたハルカとたまたますれ違った彼は、小さな声で挨拶をしたが、彼女は一瞥くれるだけで何を言わなかった。まるで、思いに耽ったような悩ましげな顔つきをしていて、とても世間話を持ちかけられるような雰囲気ではなかった。
帰宅したアオトは佐山の言葉を思い出す。
彼はハルカが何を考えているのか、その真意は詳しくわからなかったが、”具合が悪いなら、お大事に”と、労いのメッセージを送ったのだった。