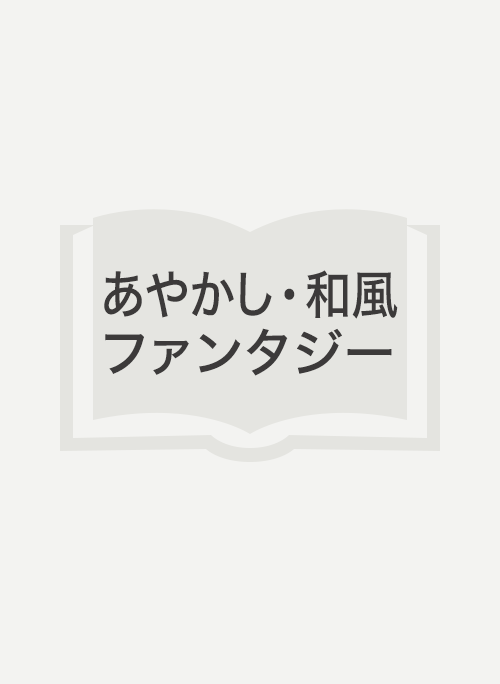帰りが遅くなった――といっても、まだ夜の八時にはなっていないのだけれど、わたしにとっては十分に遅い時間で、しかも、初めての遅い時間だったのでお父さんやお母さんからは怒られてしまった。
でも、その中でお兄ちゃんだけは庇ってくれて――それは、わたしが出て行った理由を知っているからだろうけど――繕うように笑いかけてくる笑顔が、なんだかすごく悲しかった。
――ううん、胸の奥が締め付けられて、『痛かった』。
お風呂に入って、ご飯を食べて――一人で食べたかったのに、お父さんもお母さんも、そして、お兄ちゃんも待っていてくれたので、一緒にご飯を食べて。
何も聞いてくれないことに安心もして、お兄ちゃんが『心配』――わたしの心配ではなく、『あのこと』を話さないか、という心配――をしていることもわかったから、わたしも何も話さなかった。
部屋に戻って、ベッドに倒れこむ。
「…………」
明日は学校だ――普通の生活、普通の日常が戻ってくる。
お兄ちゃんと彼女さんは別れたりしないだろう。少しの間は気まずくなっちゃうかもしれないけれど、それもいつか元通りになるはずだ。
そして……『あれ』をまたしちゃうんだろうな……
ずっと隠したままでよかった。わたしの気持ちはずっと隠すつもりでいた。
ただ、想っていればそれでよかった。それだけで――幸せのはずだった。
――こんなにショックを受けるなんて、自分でも思っていなかった。
忘れられないよ……好きな気持ちを。
知らないうちに泣いていたことを気付いた時――気付いたことによってもっと泣きそうだったから、わたしは布団に顔を埋めた。
胸の奥が苦しい――苦しい――苦しい――
『あなたは一体どうしたいの?』
『……いいわ、もう好きにしなさい。自己満足で壊れればいいじゃない』
『――それで、誰が一番悲しむのよ』
壊してほしい。忘れられるなら――わたしを求めてくれるなら、滅茶苦茶にされてもいい。
だけど、
――だけど。
(――壊れたら、お兄ちゃん悲しむかな)
きっと、彼女さんと幸せになれない。普通の幸せを送れなくなってしまう。
わたしが、お兄ちゃんの幸せの足を引っ張るのは……それはしたくない。
わたしのせいで、何かが悪くなるのは嫌。
だから、秘密にするの。なにもかも。
わたしの気持ちも、今日のことも――『妹』のことも――
――目を開けると、外が明るくなっていた。
いつの間にか眠っていたみたい――頬に残っている涙の後をこしこしと拭って、わたしは身体を起き上がらせた。
いつもの日常――いつもの朝。
これが現実なのに、なんだか非現実みたいに感じる。嘘の世界に思えて――昨日のことがなにもなくなってしまったような、全部消えてしまうような――
「――――っ」
わたしは、胸に当てた手をきゅっと握る。
このまま普通に生きていけば、昨日のことは消えてしまう。なかったことになってしまう。
それが一番良くて、誰もが幸せになる方法――でも。
わたしの気持ちまで……消さないで!
わたしは立ち上がった。
昨日のことを無くしたくない。昨日の現実をそのまま続けていきたい。
だから、わたしは――