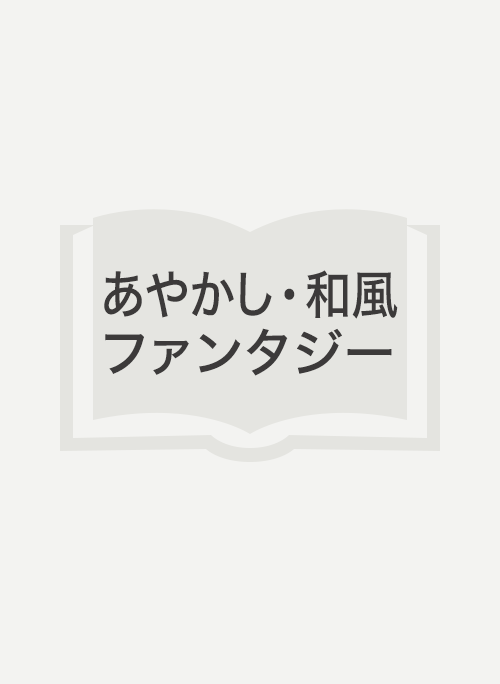聞いた住所は事務所があるマンションから二駅ほど離れた場所だった。もちろん家までは送らない。家など知りたくもない。近くまでだ。
聞けば財布も持たないまま家を飛び出したらしい。知らずに事務所のあるあそこまで歩いてきたのは――それだけショックだったということだろう。こんな小さな少女が、無意味に歩くには遠すぎる距離だった。
(……ショック、ね)
少女は俯いたまま、こちらが問いかけた時しか話さなかった。
無駄な話はしない、お互いに。
「…………はぁ」
だけれど、少女の家に近づくにつれてとうとう我慢ができなくなり、シオリは車を止めてハンドルに頭を乗せた。
「――ねえ、一つ聞いていいかしら?」
少女はゆっくりと顔を上げてシオリを見つめる。その真っ直ぐな視線に居心地が悪くなりながらも、ついでに余計なことをしている自分のお人よしさに苛立ちながらもシオリは止めるわけにもいかず、続けた。
「あなたは、一体どうしたいの?」
「…………」
少しだけ、少女の頭が揺れた。
考え、そして、俯く。
(――分からないでしょうね)
心で呟きながらも、だからといって、シオリもどうしたらいいかなんて分かっていなかった。
「忘れろ」なんて簡単に言えない。言ったところで、忘れるわけがない。
――『同じ気持ち』を分かった人間でなければ、言葉は伝わらないだろう。
「…………」
シオリは溜息をついた。ほんとに嫌いだ。嫌いすぎて、吐き気がする。
「昔ね」
絞り出すように呟いた声は、思った以上に低くなっていた。これじゃあ脅すみたいじゃない、とも思うが、もうどうなってもいい、とも思い直してシオリは続ける。
「昔ね、あなたと同じように兄を好きな子がいたの」
伝えられた言葉にサクラは視線を上げてシオリを見つめた。
「……その子は、どうしたんですか」
「死んだわ。結ばれないことを思い悩んで、泣いて泣いて……そのまま自分で」
はっきりと伝え、冷たい視線でサクラを見返す。