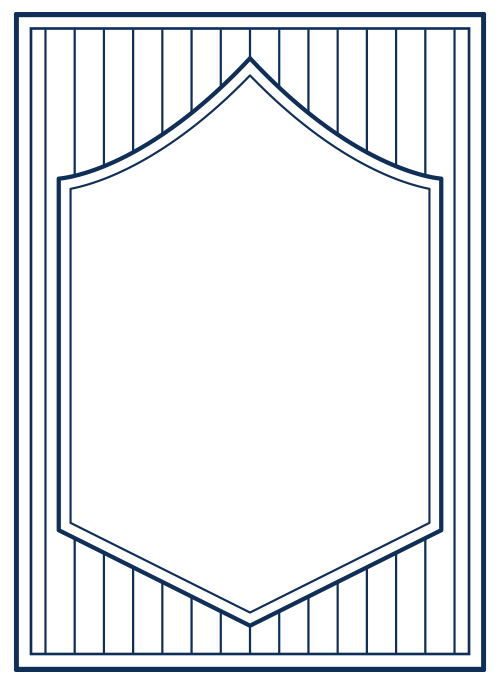見渡す限りどこまでも続く草一本生えてない荒野。
青い空には大きな白い天体が浮かんでいる。
そんな景色の絵を描いている裕也に、
「もうやめなよ」
幼馴染みの理沙が言った。
「ホントにそれが描きたい絵なの?」
詰問調で訊ねてくる理沙を裕也は睨み付けた。
裕也は子供の頃から絵ばかり描いていた。
「ゆう君、一緒に遊ぼ」
理沙がそう声を掛けてくる度に、
「これ、描いたらね」
裕也はスケッチブックから顔を上げずに答えていた。
理沙は他の友達がいる時は遊びに行ってしまったが、一人の時はその場に残って裕也が描いてるところを眺めていた。
黙って絵を描いているところなど見ていて何が楽しいのか分からなかったが理沙が一緒にいるのは嫌ではなかった。
小学校の時の休み時間、
「お前、絵ばっか描いてて楽しいのかよ」
クラスメイトが茶化すように言った。
「うん」
顔も上げずに答えた裕也に鼻白んだクラスメイトはどこかへ行ってしまった。
「せっかく仙台に来たのにスケッチ? 観光すればいいのに」
母が呆れたように言った。
「わざわざ来たからだよ。滅多に来られないんだから」
「滅多に来ないのは家で絵ばかり描いてるからでしょ」
母はそう言うと諦め顔で父と松島へ出掛けていった。
松島も綺麗だと聞くが、今はこの景色を描き止めたかった。
時間があったら松島にも行って描こうと思っていたが結局その絵だけで時間切れになってしまった。
荒涼とした大地と空に浮かぶ月より大きな白い天体。
それは物心ついた時からよく見る夢の中の光景だった。
白い星を見る度によく分からない衝動に突き動かされて描き続けてきた。
焦げ茶色の大地と白い星、たまに白い星の側に、月と同じか少し小さいくらいの天体が見えることがある。
絵を見た人達からは「中二病」と笑われた。
しかし夢を見る度に「描かなければ」という使命感に駆られて止められないのだ。
理沙は裕也の夢の絵を嫌っているようでいつも眉を顰めていた。
「何を描こうと僕の勝手だろ」
裕也が素っ気なくそう言うと、
「普通の絵はこんなに綺麗なのに……」
理沙が裕也の描いた冬の仙台の風景画を見てぽつりと呟いた。
「綺麗じゃなくて悪かったな!」
かっとなって怒鳴り付けた。
絵を否定することは裕也を否定することだ。
裏切られた。
それが正直な気持ちだった。
確かに夢の世界はどこまで行っても草一本生えていない荒れた大地だ。
そんな光景のどこがいいのかと聞かれても答えられない。
ただ伝えたい。
誰に?
と訊ねられても分からない。
ただ白い星を見上げる度に感情が溢れ出してきて、それを伝えたくなるのだ。
正体不明の誰かに。
理沙は裕也の剣幕に怯んだ表情を見せると踵を返して去っていった。
それが高校二年のクリスマスイブの日だった。
中学の時の同級生達とクリスマスパーティをしようと誘いに来て裕也が絵を理由に断って口論になったのだ。
理沙とは高校が違ったからそれきり会わなくなった。
裕也は美大の三年生になっていた。
大学の文化祭の日、自分の絵の前で立ち止まっているカップルがいた。
あの星の絵を眺めるのは中二を患っている者か、バカにしてせせら笑う者のどちらかだ。
さり気なくカップルの表情を見える位置に移動してみた。
中二っぽい感じはしないがバカにしている表情でもない。
やけに真面目な顔で見ている。
清美と共に美大の文化祭に来た楸矢は一枚の絵の前で足を止めた。
荒涼とした大地の上に白い大きな天体が浮かんでいる絵だ。
「珍しいですね、こんなに大きな月を書くなんて」
清美がそう言うと、
「……これ、月じゃないよ」
楸矢が絵を見詰めたまま答えた。
「え?」
絵画で実物より大きく描くのは珍しくない。
誇張しているわけではなくても注目しているものは脳内補正で大きく感じるからだ。
だから写真に撮ると予想外に小さくて驚く事も珍しくない。
だが、これは月ではない。
「これ、ムーシケーだよ」
楸矢が白い月を指して言った。
ムーシケーって確か楸矢さん達の祖先――ムーシコス――が住んでいた惑星だっけ……。
四千年前、ムーシコスが住んでいた惑星ムーシケーに隕石が降り注ぐようになった為、地球へ避難してきたと言っていた。
それ以来、地球人に交じって暮らしてきたから地球人との違いはないらしい。
ただ一つ、ムーシコスが奏でる旋律はどこにいても聴こえるという点を除いて。
清美の親友の小夜と楸矢の兄の柊矢もムーシコスで二人も恋人同士なのだが、しょっちゅう一緒に歌っているらしい。
清美には歌声は聴こえないが楸矢には聴こえる為げんなりした様子をしている時は大体二人で歌っている時のようだ。
恋人同士でラブソングのデュエットは確かに痛い。
想像しただけでも痛々しいから歌う度に聴こえるのは辛いだろうといつも同情していた。
それはともかく――。
「ここ」
楸矢は絵の地平線の左端の白い半円形の小さな山を指した。
「これ、ドラマだよ」
「ドラマ?」
清美は首を傾げた。
テレビの話ではないのは明らかだがよく分からない。
ムーシケーやムーシコスの説明は聞いたものの全く知らない言語の単語の上に長い。
しかも似ている。
同じ語源からの派生だかららしいが馴染みがない上に長くて似てるとなると混乱する。
ただ『ドラマ』という言葉は聞いた事が無い。
あれば今と同じ疑問を抱いただろうから覚えてるはずだ。
「ドラマって言うのはムーシケーとグラフェーの衛星」
グラフェーとムーシケーは二重惑星らしい。
そしてグラフェーは巨大隕石の衝突で壊滅したと聞いた。
だからムーシケーはムーシコスを地球に送ったのだと。
ムーシケーには意志があって楸矢や小夜にはそれが分かるらしい。
意志が分かるのはクレーイス・エコーというムーシケーに選ばれたムーシコスだけで、普通のムーシコスには分からないそうだ。
グラフェーを描いた絵なら荒廃していてもおかしくない。
「えいせい……月って事ですか? これは山じゃないって事ですか?」
「そう、月。地平線から上り始めてるか沈み始めてるから山みたいに見えてるだけ」
楸矢はそう説明しながら絵を見ていた。
絵からとても強い想いが伝わってくる。
だけど……。
楸矢は考え込んだ。
どう解釈すれば良いのか良く分からない。
ムーシコスはグラフェーには行けないはずだからグラフェーからムーシケーを見る事は出来ない。
どちらにしろムーシコスが想いを伝える手段は歌だから絵では伝わらない。
となると描いたのはグラフェーから来た人間と言う事になるが、ムーシコスにグラフェーの人間の想いは感知出来ないはずだ。
と言うか、そう言う話は聞いたことがない。
だとしたらこれはグラフェーから来た人間の想いを感じ取っているのではなく、ムーシケーが何かを伝えてきているのだ。
「文化祭、今日までだよね?」
「はい」
清美の返事を聞くと楸矢は辺りを見回した。
楸矢は入口に立っているスタッフらしき女性に歩み寄った。
「すみません、あの絵描いた人、いますか?」
楸矢は絵のタイトルを告げて訊ねた。
「裕也君」
女性が青年に声を掛けた。
「何?」
様子を見ていた裕也はすぐにカップルの側に向かった。
楸矢は女性に礼を言うと、
「あそこに展示してある絵なんだけど……」
裕也に向き直って訊ねた。
「何か?」
「あの絵、見せたい人がいるんだけど今からじゃ文化祭が終わるまでには来られそうにないから、他の日に見せてもらえないかと思って」
「写真、撮って送っていいよ」
真似をされて困るような絵ではない。
「写真で分かるかどうか……」
「何が?」
「あの絵に込められた想い」
裕也は驚いて楸矢を見た。
分かった人は初めてだ。
「それに、他にもあるでしょ」
楸矢が言った。
「え……?」
「あの惑星の絵、見て描いたんでしょ。だとしたら見たのは一度だけじゃないよね」
「まさか……君も見た事あるのか!?」
「向こうからは無い」
「向こうってどういう……」
「多分、見せたいって言った人の方が上手く説明出来ると思う」
「分かった」
楸矢と裕也は連絡先を交換した。
翌日、楸矢は椿矢を家に呼んだ。
小夜と柊矢もいる。
楸矢は美大で見た絵の話をした。
「グラフェー!?」
椿矢が声を上げた。
小夜も目を丸くしている。
柊矢はどうでも良さそうな表情をしていた。
「ムーシケーを地上から見上げてる絵だし、ドラマも見えてるって事はグラフェーから見たって事でしょ。地面に草一本も生えてないし」
「それで? グラフェーからも来てるのは知ってるだろ」
柊矢が無愛想に言った。
小夜と音楽にしか興味のない柊矢は、小夜と歌っているところを邪魔されたので不機嫌なのだ。
小夜ちゃんと歌……。
柊兄、ブレないな……。
「よく分からないけど、ただムーシケーを描いただけじゃないみたいなんだ。俺達はグラフェーの人間じゃないから普通ならただの絵に見えるはずでしょ」
「ムーシケーに関係あるかもしれないって事?」
椿矢が訊ねた。
「うん」
「そうなるとクレーイス・エコーの役割になるから僕は関係ないと思うけど」
クレーイス・エコーとはムーシケーの巫女のようなものでムーシケーの意志を実行する――ムーシケーの伝えてきた歌を歌う――者を指す。
ただ、ここは地球だ。
ムーシケーは地球や地球人には干渉しない。
だからムーシケーが意志を伝えてくることは滅多にない。
ムーシケーやムーシコスに絡むことが起きた時だけムーシカを伝えてくるだけだ。
「自分を地球人だと思ってる人にグラフェーの説明、俺達に出来ると思う?」
確かに……。
柊矢は賢いが小夜以外の人間には素っ気ない。
小夜も頭は良いが内気な上に男性が苦手だから初対面の相手とは上手く話せない。
楸矢は賢明ではあるが説明の類は苦手だ。
何よりこの四人の中で一番ムーシケーに関する知識があるのは一族の言い伝えを訊いていてムーシケーやムーシカの研究もしている椿矢だ。
「分かった、一緒に行くよ」
椿矢は頷いた。
翌週の日曜日、裕也の家に楸矢、柊矢、小夜、椿矢の四人が来ていた。
楸矢は裕也に四人を紹介した。
裕也は今まで描いた絵を見せた。
絵を見た瞬間、小夜と柊矢が目を見開いた。
「どう思う?」
楸矢が三人に訊ねた。
「ごめん、僕には普通の絵に見える」
椿矢が謝った。
「てことは、ムーシケーだって分かるのはクレーイス・エコーだけなんだな」
柊矢が言った。
「どういう事だ? ムーシケー? クレー……何?」
裕也が訊ねると椿矢が白い星を指した。
「これはムーシケーって惑星。この絵はグラフェーって惑星の地上からムーシケーを見上げたもの。こっちの小さいのはムーシケーとグラフェーの衛星のドラマ」
「なんでそんな事が分かるんだ!? アニメか何かに出てきたものなのか?」
裕也の問いに、
「四千年前、君の先祖はグラフェーから、僕達四人の先祖はムーシケーから来たから」
椿矢が答えた。
「ここに居る全員が宇宙人だって言うのか!?」
裕也は正気かというように椿矢を見た。
「大昔の先祖がね」
「ここに人が住めるのか?」
椿矢は数千年前、ムーシケーとグラフェーの外側を回ってる惑星が別の天体とぶつかって砕け、その破片の中でも大きなものがグラフェーに落ちて壊滅したと説明した。
破片が落ちてくるのに気付いたグラフェーとムーシケーは自分達の惑星の人間達を救うために地球に送った。
「送ったってどうやって」
「空間が偶に地球と繋がるんだよね。それでムーシコス――あ、ムーシケーの人間の事ね――は地球との間を往き来出来るんだ」
「今も往き来してるのか?」
「基本的には無理。ムーシケーが拒んでるから。例外的に許された人が短時間だけなら行けるだけ」
椿矢が答える。
「さっきから気付いたとか、拒んでるとか意志があるみたいな言い方してるが……」
「ムーシケーは意識があるから」
「ムーシケーは?」
「グラフェーは衝突の時の衝撃で意識を失ったみたい」
「みたいってはっきりとは分からないのか?」
「惑星の意志とか普通は分からないでしょ」
それはそうだ。
「そもそも意志があるなんて最近まで誰も知らなかったくらいだよ」
「なんで分かったんだ?」
「クレーイス・エコーって巫子みたいな役割を与えられた人の中に稀に分かる人がいるの。彼女がそう」
椿矢が小夜に視線を向けた。
「彼女ほどじゃないけど彼らも分かる。だから君の絵に込められてる想いに気付いた」
椿矢が柊矢と楸矢に目を向けた。
「あんたは分からないのか?」
「うん。ムーシケーの意志も分からないし、君の絵も普通の絵に見える」
裕也は文化祭で楸矢が「絵に想いが込められている」と言っていたのを思い出した。
つまりクレーイス・エコーと呼ばれる人達にだけ感じ取れる何かがあるのだ。
「その話をする為にわざわざ見に来たんじゃないんだろ」
「この絵、想いを伝えたくて描いてるんだろ」
柊矢が言った。
裕也は黙って頷く。
「僕達はグラフェーの人間じゃないから断言は出来ないけど、君はグラフェーのクレーイス・エコー的な人なんじゃないかな」
椿矢が説明した。
「巫子って事か?」
裕也の問いに椿矢が頷いた。
「グラフェーは意識が無いのに選べるの?」
楸矢が訊ねた。
「この絵、グラフェーの想いをムーシケーに伝えたいんだよね?」
椿矢が再度確認するように訊ねた。
小夜が首肯する。
「でもグラフェーは今、意識が無いし、そもそも両想いなんだからわざわざ描く必要ないよね」
椿矢の言葉に小夜が再度頷いた。
「多分だけど、グラフェーの意識が無いから中途半端な受け取り方しちゃってるんだと思う」
「それで? どうしろって言うんだ」
「別に」
柊矢が答えた。
「え?」
裕也は意味が分からず柊矢の顔を見た。
「ムーシケーと関係ないなら俺達にも関係ない」
「いや、関係あるでしょ。君達は絵から想いを感じ取ったんだから」
椿矢が言った。
「グラフェーの想いならムーシケーはとっくに知ってるし、この絵の事も楸矢が見た時点で知っただろ。用は済んだから後は好きなようにすれば良い」
柊矢がそう言った時、柊矢、楸矢、椿矢の視線が小夜に集まった。
小夜がネックレスを服の下から取り出す。
小夜が着けていたネックレス――クレーイスが光ったのだ。
裕也にはただのネックレスにしか見えなかったが。
椿矢も光っているのが見えただけだがムーシカを伝えてきているらしいと言う事は分かった。
「帰るぞ」
柊矢が踵を返した。
小夜が裕也に礼を言って頭を下げると後に続いた。
楸矢は、
「聞きたいことが合ったら連絡して」
と言い残して椿矢と共に出ていった。
「なんだったんだ」
裕也はよく分からないまま首を捻った。
「なんであそこで歌わなかったの?」
椿矢が訊ねた。
クレーイスが光ったのならムーシケーがムーシカを伝えてきたと言う事だし、あそこで伝えてきたなら裕也に聞かせろという事だろう。
ムーシコスならムーシカはどこにいても聴こえるが、裕也はムーシコスでは無いからムーシカは肉声でなければ聴こえない。
「演奏も必要らしい」
柊矢が答えた。
ムーシコスには歌手と演奏家がいる。
〝歌〟はムーソポイオスが歌った時だけ、〝演奏〟はキタリステースが専用の楽器で演奏した時だけ、その場に居ないムーシコス全員に聴こえる。
裕也はムーシコスではないから普通の楽器でも良いのかもしれないが、どちらにしろ今は手元に楽器がない。
一旦家に戻る必要があるのだ。
数日後の夕方、裕也が大学の門を出ると人だかりが出来ていた。
歌声が聴こえてくる。
大学の前で路上ライブなんて珍し……。
声の方に視線を向けて目を剥いた。
この前の四人がいた。
楸矢、柊矢、椿矢が見慣れない楽器を弾いている。
そして小夜が歌っていた。
知らない言語の不思議な旋律だったが何故か惹き付けられて思わず足を止めて聴き入ってしまった。
その夜、裕也が眠りにつくといつものようにあの星の夢を見た。
だが今日はいつもと違った。
荒れ果てた大地にどこからか歌声が聴こえてくる。
大学の前で聴いたあの歌だ。
澄んだソプラノの歌声が風のように流れていく。
荒涼とした惑星に空から銀色のものが無数に降ってきている。
まるで雪のようだ。
それは本来なら人間の目には見えないほど微細な有機物。
それがゆっくりと落ちて地上に降り積もっていく。
大地も降り注ぐ有機物――生命の源――で覆われて淡く光っていた。
突如、轟音がして空の片隅が明るく光った。
火球だ。
地響きと共に地面が揺れた。
その間にも空を次々と流星が流れていく。
この星の大地はどこも乾いて草一本生えていない。
水がほとんど無いからだ。
今ある水だけでは生命を育む事は出来ない。
この惑星は隕石によって壊滅した。
だが隕石は破滅だけではなく生命に必要な水ももたらす。
隕石の表面の酸素原子と恒星から吹き付けられる高エネルギーの水素イオンが反応して水になるのだ。
それが隕石として落ちてくる事で惑星上に水が溜まっていく。
隕石によってもたらされた水が海になった時、これらの有機物は生命となり、雨が降り注いで大地を潤し、やがてこの惑星も地球と同じように緑豊かな惑星になる――以前のような生命の溢れる大地に。
裕也は白い惑星を見上げた。
そうだ、自分が想いを伝えたかった相手はあの白い惑星だ。
あの惑星へ、この惑星の想いを伝えなければいけない。
その使命感だけでこの風景を描き続けてきた。
けれど……。
あの惑星はとっくの昔にこの惑星の想いを知っている。
歌が教えてくれた。
知らない言葉なのに何故かそれが分かった。
もう、この景色を描く必要はない。
好きに描いていい、と。
絵で想いを伝えるべき相手はあの惑星ではない。
裕也は目を覚ました。
窓の外を見ると東の地平線が淡く輝いていた。
夜明けだ。
天頂付近はまだ青墨の夜空だが、徐々にその範囲が狭くなって薄い青になっていく。
この星にはこんなに綺麗な色が溢れてたんだな……。
『普通の絵はこんなに綺麗なのに……』
あの時の言葉はそう言う事だったのだ。
あの惑星の呪縛に捕らわれて何も見えてなかった。
謝ろう。
裕也は仕舞ってあった理沙の肖像画を取り出した。
唯一裕也が描いた人物画だ。
理沙と会わなくなってしばらく経ってから描いたものである。
受け取ってくれるだろうか。
それ以前に口を利いてもらえるだろうか。
裕也は首を振った。
許してくれなくても仕方ない。
まずは謝らなければ許してもらうことも出来ないのだ。
絵を抱えると理沙の家に向かって歩き出した。
* * *
いくつかの点についてサイエンスライターの彩恵りりさんに相談しました。ただし全てについて確認をしたわけではないため、考証に間違いがあればそれは私の責任です。
青い空には大きな白い天体が浮かんでいる。
そんな景色の絵を描いている裕也に、
「もうやめなよ」
幼馴染みの理沙が言った。
「ホントにそれが描きたい絵なの?」
詰問調で訊ねてくる理沙を裕也は睨み付けた。
裕也は子供の頃から絵ばかり描いていた。
「ゆう君、一緒に遊ぼ」
理沙がそう声を掛けてくる度に、
「これ、描いたらね」
裕也はスケッチブックから顔を上げずに答えていた。
理沙は他の友達がいる時は遊びに行ってしまったが、一人の時はその場に残って裕也が描いてるところを眺めていた。
黙って絵を描いているところなど見ていて何が楽しいのか分からなかったが理沙が一緒にいるのは嫌ではなかった。
小学校の時の休み時間、
「お前、絵ばっか描いてて楽しいのかよ」
クラスメイトが茶化すように言った。
「うん」
顔も上げずに答えた裕也に鼻白んだクラスメイトはどこかへ行ってしまった。
「せっかく仙台に来たのにスケッチ? 観光すればいいのに」
母が呆れたように言った。
「わざわざ来たからだよ。滅多に来られないんだから」
「滅多に来ないのは家で絵ばかり描いてるからでしょ」
母はそう言うと諦め顔で父と松島へ出掛けていった。
松島も綺麗だと聞くが、今はこの景色を描き止めたかった。
時間があったら松島にも行って描こうと思っていたが結局その絵だけで時間切れになってしまった。
荒涼とした大地と空に浮かぶ月より大きな白い天体。
それは物心ついた時からよく見る夢の中の光景だった。
白い星を見る度によく分からない衝動に突き動かされて描き続けてきた。
焦げ茶色の大地と白い星、たまに白い星の側に、月と同じか少し小さいくらいの天体が見えることがある。
絵を見た人達からは「中二病」と笑われた。
しかし夢を見る度に「描かなければ」という使命感に駆られて止められないのだ。
理沙は裕也の夢の絵を嫌っているようでいつも眉を顰めていた。
「何を描こうと僕の勝手だろ」
裕也が素っ気なくそう言うと、
「普通の絵はこんなに綺麗なのに……」
理沙が裕也の描いた冬の仙台の風景画を見てぽつりと呟いた。
「綺麗じゃなくて悪かったな!」
かっとなって怒鳴り付けた。
絵を否定することは裕也を否定することだ。
裏切られた。
それが正直な気持ちだった。
確かに夢の世界はどこまで行っても草一本生えていない荒れた大地だ。
そんな光景のどこがいいのかと聞かれても答えられない。
ただ伝えたい。
誰に?
と訊ねられても分からない。
ただ白い星を見上げる度に感情が溢れ出してきて、それを伝えたくなるのだ。
正体不明の誰かに。
理沙は裕也の剣幕に怯んだ表情を見せると踵を返して去っていった。
それが高校二年のクリスマスイブの日だった。
中学の時の同級生達とクリスマスパーティをしようと誘いに来て裕也が絵を理由に断って口論になったのだ。
理沙とは高校が違ったからそれきり会わなくなった。
裕也は美大の三年生になっていた。
大学の文化祭の日、自分の絵の前で立ち止まっているカップルがいた。
あの星の絵を眺めるのは中二を患っている者か、バカにしてせせら笑う者のどちらかだ。
さり気なくカップルの表情を見える位置に移動してみた。
中二っぽい感じはしないがバカにしている表情でもない。
やけに真面目な顔で見ている。
清美と共に美大の文化祭に来た楸矢は一枚の絵の前で足を止めた。
荒涼とした大地の上に白い大きな天体が浮かんでいる絵だ。
「珍しいですね、こんなに大きな月を書くなんて」
清美がそう言うと、
「……これ、月じゃないよ」
楸矢が絵を見詰めたまま答えた。
「え?」
絵画で実物より大きく描くのは珍しくない。
誇張しているわけではなくても注目しているものは脳内補正で大きく感じるからだ。
だから写真に撮ると予想外に小さくて驚く事も珍しくない。
だが、これは月ではない。
「これ、ムーシケーだよ」
楸矢が白い月を指して言った。
ムーシケーって確か楸矢さん達の祖先――ムーシコス――が住んでいた惑星だっけ……。
四千年前、ムーシコスが住んでいた惑星ムーシケーに隕石が降り注ぐようになった為、地球へ避難してきたと言っていた。
それ以来、地球人に交じって暮らしてきたから地球人との違いはないらしい。
ただ一つ、ムーシコスが奏でる旋律はどこにいても聴こえるという点を除いて。
清美の親友の小夜と楸矢の兄の柊矢もムーシコスで二人も恋人同士なのだが、しょっちゅう一緒に歌っているらしい。
清美には歌声は聴こえないが楸矢には聴こえる為げんなりした様子をしている時は大体二人で歌っている時のようだ。
恋人同士でラブソングのデュエットは確かに痛い。
想像しただけでも痛々しいから歌う度に聴こえるのは辛いだろうといつも同情していた。
それはともかく――。
「ここ」
楸矢は絵の地平線の左端の白い半円形の小さな山を指した。
「これ、ドラマだよ」
「ドラマ?」
清美は首を傾げた。
テレビの話ではないのは明らかだがよく分からない。
ムーシケーやムーシコスの説明は聞いたものの全く知らない言語の単語の上に長い。
しかも似ている。
同じ語源からの派生だかららしいが馴染みがない上に長くて似てるとなると混乱する。
ただ『ドラマ』という言葉は聞いた事が無い。
あれば今と同じ疑問を抱いただろうから覚えてるはずだ。
「ドラマって言うのはムーシケーとグラフェーの衛星」
グラフェーとムーシケーは二重惑星らしい。
そしてグラフェーは巨大隕石の衝突で壊滅したと聞いた。
だからムーシケーはムーシコスを地球に送ったのだと。
ムーシケーには意志があって楸矢や小夜にはそれが分かるらしい。
意志が分かるのはクレーイス・エコーというムーシケーに選ばれたムーシコスだけで、普通のムーシコスには分からないそうだ。
グラフェーを描いた絵なら荒廃していてもおかしくない。
「えいせい……月って事ですか? これは山じゃないって事ですか?」
「そう、月。地平線から上り始めてるか沈み始めてるから山みたいに見えてるだけ」
楸矢はそう説明しながら絵を見ていた。
絵からとても強い想いが伝わってくる。
だけど……。
楸矢は考え込んだ。
どう解釈すれば良いのか良く分からない。
ムーシコスはグラフェーには行けないはずだからグラフェーからムーシケーを見る事は出来ない。
どちらにしろムーシコスが想いを伝える手段は歌だから絵では伝わらない。
となると描いたのはグラフェーから来た人間と言う事になるが、ムーシコスにグラフェーの人間の想いは感知出来ないはずだ。
と言うか、そう言う話は聞いたことがない。
だとしたらこれはグラフェーから来た人間の想いを感じ取っているのではなく、ムーシケーが何かを伝えてきているのだ。
「文化祭、今日までだよね?」
「はい」
清美の返事を聞くと楸矢は辺りを見回した。
楸矢は入口に立っているスタッフらしき女性に歩み寄った。
「すみません、あの絵描いた人、いますか?」
楸矢は絵のタイトルを告げて訊ねた。
「裕也君」
女性が青年に声を掛けた。
「何?」
様子を見ていた裕也はすぐにカップルの側に向かった。
楸矢は女性に礼を言うと、
「あそこに展示してある絵なんだけど……」
裕也に向き直って訊ねた。
「何か?」
「あの絵、見せたい人がいるんだけど今からじゃ文化祭が終わるまでには来られそうにないから、他の日に見せてもらえないかと思って」
「写真、撮って送っていいよ」
真似をされて困るような絵ではない。
「写真で分かるかどうか……」
「何が?」
「あの絵に込められた想い」
裕也は驚いて楸矢を見た。
分かった人は初めてだ。
「それに、他にもあるでしょ」
楸矢が言った。
「え……?」
「あの惑星の絵、見て描いたんでしょ。だとしたら見たのは一度だけじゃないよね」
「まさか……君も見た事あるのか!?」
「向こうからは無い」
「向こうってどういう……」
「多分、見せたいって言った人の方が上手く説明出来ると思う」
「分かった」
楸矢と裕也は連絡先を交換した。
翌日、楸矢は椿矢を家に呼んだ。
小夜と柊矢もいる。
楸矢は美大で見た絵の話をした。
「グラフェー!?」
椿矢が声を上げた。
小夜も目を丸くしている。
柊矢はどうでも良さそうな表情をしていた。
「ムーシケーを地上から見上げてる絵だし、ドラマも見えてるって事はグラフェーから見たって事でしょ。地面に草一本も生えてないし」
「それで? グラフェーからも来てるのは知ってるだろ」
柊矢が無愛想に言った。
小夜と音楽にしか興味のない柊矢は、小夜と歌っているところを邪魔されたので不機嫌なのだ。
小夜ちゃんと歌……。
柊兄、ブレないな……。
「よく分からないけど、ただムーシケーを描いただけじゃないみたいなんだ。俺達はグラフェーの人間じゃないから普通ならただの絵に見えるはずでしょ」
「ムーシケーに関係あるかもしれないって事?」
椿矢が訊ねた。
「うん」
「そうなるとクレーイス・エコーの役割になるから僕は関係ないと思うけど」
クレーイス・エコーとはムーシケーの巫女のようなものでムーシケーの意志を実行する――ムーシケーの伝えてきた歌を歌う――者を指す。
ただ、ここは地球だ。
ムーシケーは地球や地球人には干渉しない。
だからムーシケーが意志を伝えてくることは滅多にない。
ムーシケーやムーシコスに絡むことが起きた時だけムーシカを伝えてくるだけだ。
「自分を地球人だと思ってる人にグラフェーの説明、俺達に出来ると思う?」
確かに……。
柊矢は賢いが小夜以外の人間には素っ気ない。
小夜も頭は良いが内気な上に男性が苦手だから初対面の相手とは上手く話せない。
楸矢は賢明ではあるが説明の類は苦手だ。
何よりこの四人の中で一番ムーシケーに関する知識があるのは一族の言い伝えを訊いていてムーシケーやムーシカの研究もしている椿矢だ。
「分かった、一緒に行くよ」
椿矢は頷いた。
翌週の日曜日、裕也の家に楸矢、柊矢、小夜、椿矢の四人が来ていた。
楸矢は裕也に四人を紹介した。
裕也は今まで描いた絵を見せた。
絵を見た瞬間、小夜と柊矢が目を見開いた。
「どう思う?」
楸矢が三人に訊ねた。
「ごめん、僕には普通の絵に見える」
椿矢が謝った。
「てことは、ムーシケーだって分かるのはクレーイス・エコーだけなんだな」
柊矢が言った。
「どういう事だ? ムーシケー? クレー……何?」
裕也が訊ねると椿矢が白い星を指した。
「これはムーシケーって惑星。この絵はグラフェーって惑星の地上からムーシケーを見上げたもの。こっちの小さいのはムーシケーとグラフェーの衛星のドラマ」
「なんでそんな事が分かるんだ!? アニメか何かに出てきたものなのか?」
裕也の問いに、
「四千年前、君の先祖はグラフェーから、僕達四人の先祖はムーシケーから来たから」
椿矢が答えた。
「ここに居る全員が宇宙人だって言うのか!?」
裕也は正気かというように椿矢を見た。
「大昔の先祖がね」
「ここに人が住めるのか?」
椿矢は数千年前、ムーシケーとグラフェーの外側を回ってる惑星が別の天体とぶつかって砕け、その破片の中でも大きなものがグラフェーに落ちて壊滅したと説明した。
破片が落ちてくるのに気付いたグラフェーとムーシケーは自分達の惑星の人間達を救うために地球に送った。
「送ったってどうやって」
「空間が偶に地球と繋がるんだよね。それでムーシコス――あ、ムーシケーの人間の事ね――は地球との間を往き来出来るんだ」
「今も往き来してるのか?」
「基本的には無理。ムーシケーが拒んでるから。例外的に許された人が短時間だけなら行けるだけ」
椿矢が答える。
「さっきから気付いたとか、拒んでるとか意志があるみたいな言い方してるが……」
「ムーシケーは意識があるから」
「ムーシケーは?」
「グラフェーは衝突の時の衝撃で意識を失ったみたい」
「みたいってはっきりとは分からないのか?」
「惑星の意志とか普通は分からないでしょ」
それはそうだ。
「そもそも意志があるなんて最近まで誰も知らなかったくらいだよ」
「なんで分かったんだ?」
「クレーイス・エコーって巫子みたいな役割を与えられた人の中に稀に分かる人がいるの。彼女がそう」
椿矢が小夜に視線を向けた。
「彼女ほどじゃないけど彼らも分かる。だから君の絵に込められてる想いに気付いた」
椿矢が柊矢と楸矢に目を向けた。
「あんたは分からないのか?」
「うん。ムーシケーの意志も分からないし、君の絵も普通の絵に見える」
裕也は文化祭で楸矢が「絵に想いが込められている」と言っていたのを思い出した。
つまりクレーイス・エコーと呼ばれる人達にだけ感じ取れる何かがあるのだ。
「その話をする為にわざわざ見に来たんじゃないんだろ」
「この絵、想いを伝えたくて描いてるんだろ」
柊矢が言った。
裕也は黙って頷く。
「僕達はグラフェーの人間じゃないから断言は出来ないけど、君はグラフェーのクレーイス・エコー的な人なんじゃないかな」
椿矢が説明した。
「巫子って事か?」
裕也の問いに椿矢が頷いた。
「グラフェーは意識が無いのに選べるの?」
楸矢が訊ねた。
「この絵、グラフェーの想いをムーシケーに伝えたいんだよね?」
椿矢が再度確認するように訊ねた。
小夜が首肯する。
「でもグラフェーは今、意識が無いし、そもそも両想いなんだからわざわざ描く必要ないよね」
椿矢の言葉に小夜が再度頷いた。
「多分だけど、グラフェーの意識が無いから中途半端な受け取り方しちゃってるんだと思う」
「それで? どうしろって言うんだ」
「別に」
柊矢が答えた。
「え?」
裕也は意味が分からず柊矢の顔を見た。
「ムーシケーと関係ないなら俺達にも関係ない」
「いや、関係あるでしょ。君達は絵から想いを感じ取ったんだから」
椿矢が言った。
「グラフェーの想いならムーシケーはとっくに知ってるし、この絵の事も楸矢が見た時点で知っただろ。用は済んだから後は好きなようにすれば良い」
柊矢がそう言った時、柊矢、楸矢、椿矢の視線が小夜に集まった。
小夜がネックレスを服の下から取り出す。
小夜が着けていたネックレス――クレーイスが光ったのだ。
裕也にはただのネックレスにしか見えなかったが。
椿矢も光っているのが見えただけだがムーシカを伝えてきているらしいと言う事は分かった。
「帰るぞ」
柊矢が踵を返した。
小夜が裕也に礼を言って頭を下げると後に続いた。
楸矢は、
「聞きたいことが合ったら連絡して」
と言い残して椿矢と共に出ていった。
「なんだったんだ」
裕也はよく分からないまま首を捻った。
「なんであそこで歌わなかったの?」
椿矢が訊ねた。
クレーイスが光ったのならムーシケーがムーシカを伝えてきたと言う事だし、あそこで伝えてきたなら裕也に聞かせろという事だろう。
ムーシコスならムーシカはどこにいても聴こえるが、裕也はムーシコスでは無いからムーシカは肉声でなければ聴こえない。
「演奏も必要らしい」
柊矢が答えた。
ムーシコスには歌手と演奏家がいる。
〝歌〟はムーソポイオスが歌った時だけ、〝演奏〟はキタリステースが専用の楽器で演奏した時だけ、その場に居ないムーシコス全員に聴こえる。
裕也はムーシコスではないから普通の楽器でも良いのかもしれないが、どちらにしろ今は手元に楽器がない。
一旦家に戻る必要があるのだ。
数日後の夕方、裕也が大学の門を出ると人だかりが出来ていた。
歌声が聴こえてくる。
大学の前で路上ライブなんて珍し……。
声の方に視線を向けて目を剥いた。
この前の四人がいた。
楸矢、柊矢、椿矢が見慣れない楽器を弾いている。
そして小夜が歌っていた。
知らない言語の不思議な旋律だったが何故か惹き付けられて思わず足を止めて聴き入ってしまった。
その夜、裕也が眠りにつくといつものようにあの星の夢を見た。
だが今日はいつもと違った。
荒れ果てた大地にどこからか歌声が聴こえてくる。
大学の前で聴いたあの歌だ。
澄んだソプラノの歌声が風のように流れていく。
荒涼とした惑星に空から銀色のものが無数に降ってきている。
まるで雪のようだ。
それは本来なら人間の目には見えないほど微細な有機物。
それがゆっくりと落ちて地上に降り積もっていく。
大地も降り注ぐ有機物――生命の源――で覆われて淡く光っていた。
突如、轟音がして空の片隅が明るく光った。
火球だ。
地響きと共に地面が揺れた。
その間にも空を次々と流星が流れていく。
この星の大地はどこも乾いて草一本生えていない。
水がほとんど無いからだ。
今ある水だけでは生命を育む事は出来ない。
この惑星は隕石によって壊滅した。
だが隕石は破滅だけではなく生命に必要な水ももたらす。
隕石の表面の酸素原子と恒星から吹き付けられる高エネルギーの水素イオンが反応して水になるのだ。
それが隕石として落ちてくる事で惑星上に水が溜まっていく。
隕石によってもたらされた水が海になった時、これらの有機物は生命となり、雨が降り注いで大地を潤し、やがてこの惑星も地球と同じように緑豊かな惑星になる――以前のような生命の溢れる大地に。
裕也は白い惑星を見上げた。
そうだ、自分が想いを伝えたかった相手はあの白い惑星だ。
あの惑星へ、この惑星の想いを伝えなければいけない。
その使命感だけでこの風景を描き続けてきた。
けれど……。
あの惑星はとっくの昔にこの惑星の想いを知っている。
歌が教えてくれた。
知らない言葉なのに何故かそれが分かった。
もう、この景色を描く必要はない。
好きに描いていい、と。
絵で想いを伝えるべき相手はあの惑星ではない。
裕也は目を覚ました。
窓の外を見ると東の地平線が淡く輝いていた。
夜明けだ。
天頂付近はまだ青墨の夜空だが、徐々にその範囲が狭くなって薄い青になっていく。
この星にはこんなに綺麗な色が溢れてたんだな……。
『普通の絵はこんなに綺麗なのに……』
あの時の言葉はそう言う事だったのだ。
あの惑星の呪縛に捕らわれて何も見えてなかった。
謝ろう。
裕也は仕舞ってあった理沙の肖像画を取り出した。
唯一裕也が描いた人物画だ。
理沙と会わなくなってしばらく経ってから描いたものである。
受け取ってくれるだろうか。
それ以前に口を利いてもらえるだろうか。
裕也は首を振った。
許してくれなくても仕方ない。
まずは謝らなければ許してもらうことも出来ないのだ。
絵を抱えると理沙の家に向かって歩き出した。
* * *
いくつかの点についてサイエンスライターの彩恵りりさんに相談しました。ただし全てについて確認をしたわけではないため、考証に間違いがあればそれは私の責任です。