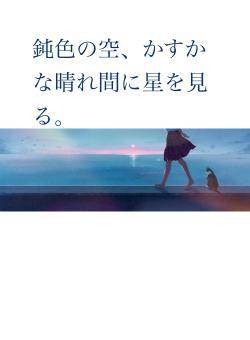使用人から、礼葉が自室で荷物をまとめていると聞き、楊は慌てて礼葉の部屋へ向かった。
「なにをしているんだ?」
思わず感情の籠った聞き方をしてしまって恥ずかしさが込み上げたが、今はそれを気にしている場合ではない。
「見てのとおりです。荷物をまとめているんですよ」
礼葉は相変わらず、淡々とした声で答えた。
「だから、なぜ?」
「実家に帰るからです」
「離縁はしないと言ったはずだが」
「離縁していただけないのならば、勝手に帰るだけです」
夫婦間において、夫のほうが強いと言ったのはだれだったか。そんなことはない。
嫁だって、そこそこ強い。いや、むしろ嫁のほうが強いと思う。度胸も楊なんかよりずっとあるし、細々としたことにもよく気がつく。使用人との関係も、今では楊より礼葉のほうがずっと上手くやっている。
楊は今さらになってそれを自覚した。
「待ってくれ」
楊が礼葉の腕を掴む。
「俺は、君になにかきらわれるようなことをしたか?」
「いえ、しておりません」
「じゃあなぜ」
「私たちは合わない。それだけです」
なにを今さらと、楊がさらに口を開こうとするのを、礼葉が遮る。
「離縁を申し込んだときも言いましたが、私が楊さまとの結婚を選んだのは、ただ両親を安心させてやるためだけです。そもそも私たちは愛し合って結婚したわけでもありませんし、楊さまだって、当時は私に触れることさえ許してくれなかったでしょう」
「それは昔の話だ。今はいくらでも……それに、独り身になるのはいろいろと困る」
咄嗟に口から出た言葉だが、嘘ではない。
実際、近頃の日本は結婚していてこそ一人前という風潮が顕著だ。
特に、楊は人間だけでなく、あやかしの間でも有名人。天月家の当主が妻から逃げられたとなれば、変な噂が流れかねない。
しかし、そんな噂よりも楊が危惧しているのは礼葉のことだった。
社交の場で、礼葉はすこぶるモテたのだ。となりに楊がいても、男から声をかけられた。
礼葉の容姿は華やかな社交界でもずば抜けていた。この国では珍しい金色の髪は絹のように艶やかで、赤い色の瞳は蠱惑的で色っぽい。
ふだんは袴を着ていることが多いが、たまにまとう西洋のドレス姿はオーダーメイドでもないのに、まるでドレス自体が彼女のためだけに存在するのではないかと思うほどに似合ってしまうのだ。
それでいてまったく飾らないから、さらに男は彼女の虜になる。
もし、礼葉の離縁が世間に知れたら。
求婚の話が絶え間なく彼女のもとへと舞い込むことだろう。
だからというわけではないが、とにかく楊は礼葉を手放したくないのだ。なにがあっても。
「楊さまならすぐに良い方が見つかります。私にこだわる必要はないはずです」
「俺は君がいい」
「私はいやです、困ります」
きっぱりと言う礼葉に、楊は狼狽える。
「あ……す、すみません。いやというのは、その……楊さまがいやというわけではありません」
ひびが入ったような楊の表情を見て、礼葉もさすがに言い過ぎたと思ったのか、少し慌て気味に言った。
「なにがいやなんだ? なにかあるなら言ってくれ」
詰め寄られ、礼葉は俯く。そして、珍しく弱々しい声で言った。
「……それは、言えません」
「夫にも言えないことなのか」
「たとえ夫だろうと、知られたくないことくらいあります。……いいえ。むしろ、楊さまが夫だから言えないのです」
「それは……つまり、夫が俺でなければ離縁などと言わなかったと?」
「ええ、そうですね」
はっきりと肯定され、楊は思わず笑みを零す。
「……ずいぶん、きつい物言いだな」
「楊さまと過ごした日々は、とても穏やかで……夢のようでした。ありがとうございました」
礼葉は申し訳なさそうに目を瞑ってから、これですべて終わりだとでもいうように、柔らかに微笑む。
美しい妻の笑みは、楊の心を容赦なく突き刺した。それが余計に楊の胸を締め付ける。
「妹はひとりでは生きていけません。両親がいなくなった今、妹を守れるのは私だけなんです。分かってください」
荷物をまとめ終わると、礼葉は楊に深く頭を下げた。
「今まで、お世話になりました」
「礼葉、待て」
礼葉が振り向く。
「彩葉の病が治ったら、戻ってきてくれないか」
楊の言葉に、礼葉の目が泳ぐ。しかしすぐに楊を見据える。
「……彩葉は、不治の病です。生涯、治ることはないのです」
「もし治れば、戻ってきてくれるか?」
しばらく沈黙が落ちた。礼葉はなにかを堪えるように唇を引き結ぶ。
「……ごめんなさい」
楊の手を振り払い、礼葉は天月家を出ていった。