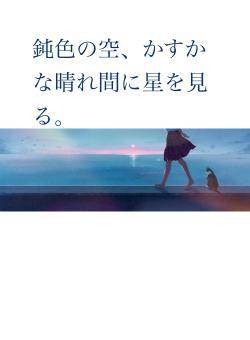西暦2085年。
世界各地で相次ぐ紛争や大戦を嘆いた神は、世界の文明をリセットすることにした。
すべてが無に帰した混沌たる世界で、人間は再び文明を築いていく。
そして、神のリセットから1914年が経った西暦3999年。
世界へ羽ばたいた文明開化の時代は過ぎ、外国から新たな文化が定着し始めた日本。
都市部では自動車やマスコミが誕生、さらに洋食や洋服が広がり、少しずつ科学が発展してきた時代。
華やかに大胆になっていく時代の裏で、それまで街中で人に紛れて生きてきたあやかしたちは、なりを潜めつつあった。
しかし、地方ではまだ人々は神やあやかしを信じ、慕い、ときに恐れながらも平和に暮らしていた。