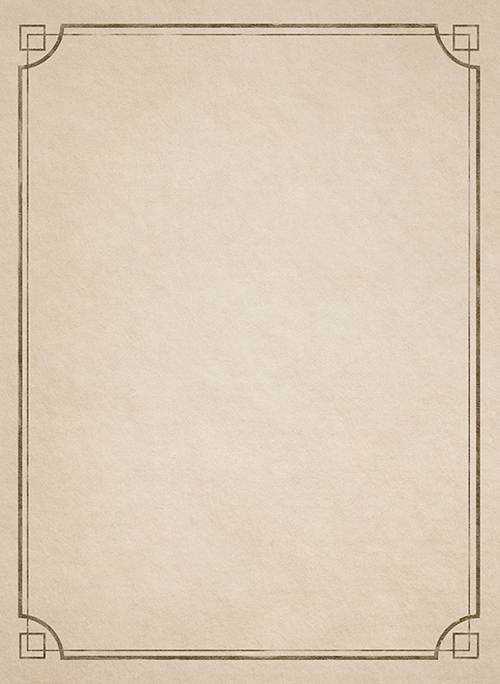僕たちはこんなにも愛し合っているのに、神も仏もこの世にはいないらしい。神頼みしても、結局無駄だったんだから。
だがせめて……僕のことだけは、覚えていてほしい。他の事は忘れてしまったって構わない。けど、僕だけは……っ。
――その悲痛な叫びは、叶う事なんて端からなかった。
「静佳?」
「…………誰、ですか?」
「……っ。」
静佳が僕のことを忘れてしまったのは、予想していたよりも遥かに速かった。
無機質なベッドの上で、何気なく僕があげた小説を読んでいる彼女の瞳には光が宿っていない。こんな事は初めてで、すぐにナースコールを押した。
嫌だ、信じられない、信じたくない。静佳が僕を忘れるなんて、そんな事あるわけがない。
きっと悪い夢を見ているだけ、そうに決まっている。
強引に自分を納得させようといくつもの絵空事を引っ張り出すけれど、医者に言われた事には希望なんてなかった。
「静佳さんはもう……記憶を取り戻す事はないでしょう。持病の喘息もあり、長くは持たないかと……。」
「そ、んな……っ。」
初めて、膝から崩れ落ちた。
だがせめて……僕のことだけは、覚えていてほしい。他の事は忘れてしまったって構わない。けど、僕だけは……っ。
――その悲痛な叫びは、叶う事なんて端からなかった。
「静佳?」
「…………誰、ですか?」
「……っ。」
静佳が僕のことを忘れてしまったのは、予想していたよりも遥かに速かった。
無機質なベッドの上で、何気なく僕があげた小説を読んでいる彼女の瞳には光が宿っていない。こんな事は初めてで、すぐにナースコールを押した。
嫌だ、信じられない、信じたくない。静佳が僕を忘れるなんて、そんな事あるわけがない。
きっと悪い夢を見ているだけ、そうに決まっている。
強引に自分を納得させようといくつもの絵空事を引っ張り出すけれど、医者に言われた事には希望なんてなかった。
「静佳さんはもう……記憶を取り戻す事はないでしょう。持病の喘息もあり、長くは持たないかと……。」
「そ、んな……っ。」
初めて、膝から崩れ落ちた。