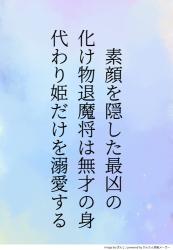女子高生の関心事ランキングが存在していたら、間違いなく恋バナは上位に入るだろう。
「玲奈は、いまの彼氏とどうやって付き合ったの~? まず、どっちからの告白?」
「智くんからー。修学旅行の自由行動のときに告られたんだっ」
「えー、なにそれいいなあぁ~~! はー……あたしも、いつまでも眺めてるだけじゃなんにもならないよなぁ」
目の前の玲奈と芽衣に限ったことじゃない。耳を澄ませると、校内の至るところに咲いている。
でも、わたしは恋バナになるといつも口を挟めなくて、無難に頷くことしかできない。
恋に興味がないわけじゃないんだ。
むしろ、強く憧れている方。
でも、手を伸ばしちゃいけないもの。
恋バナは、今のわたしにとって、陽射しのきつい夏場の太陽みたい。
「まー、芽衣はまだ想いを自覚したばっかりなんだし、焦ることはないんじゃない? タイミングも大事だしさっ」
「出た出た、彼氏持ちの余裕発言~~」
「あはっ。ちなみに、真帆はどーなのよ? 気になるひとはできた〜?」
マスカラに縁取られた四つの瞳に一斉に見つめられて、ぎくりと顔が強張る。
「えっと……、わたしは、まだ特に見つかってないかなぁ」
「えーー? 真帆かわいいのにー、もったいなぁい」
「好きなひとがいないなら、どんな男子がタイプなの? やっぱり、二組の狩野くんみたいなイケメンとかー?」
「狩野くんって軽音部に決めたんだっけ? マジでかっこいーよねぇ、顔小さいし、背も高くてさぁ」
二組の狩野くんのことは、流石に知ってる。
狩野律人。すらりとした長身と切れ長の瞳が印象的な、遠目からでも目立つ男の子。この前すれちがったとき、ギターケースらしきものを背負っていたから、よく覚えている。
良いなぁ、軽音部。
わたしも、高校に入学したら、本当はバンドをやりたかったんだけどな。
ぼんやりしていたら、玲奈と芽衣の視線を感じたので、慌てて答えた。
「狩野くんは……、モデルさんみたいでかっこいいとは思うけど、それだけかなぁ」
「まー、実際、あーいうイケメンは観賞用にしとくのに限るかもねぇ。まだ高校に入って一ヶ月なのに、もう二人に告白されたらしいし」
「ねーねー。そーいえば、智くんが彼女ほしいって言ってる男友達がいるって言ってたよ! 紹介できる子いない? って聞かれたんだよね」
「お、いーじゃんいーじゃん! 怜奈の紹介なら、奥手な真帆も安心なんじゃない?」
うわっ。この流れはマズい!
「そ、それよりさっ! 二人とも、『星空スコープ』の新曲は聴いた?」
「え……? あー……、まだ聴けてないや」
「すごくおしゃれで、素敵な曲だったの! イントロのベースが、すっごくかっこよくてね……!」
「ふうん。後で聴いてみる」
流れ出した微妙な空気をさえぎるように、昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴ってくれて助かった。
自分の席に戻ったとき、口から小さなため息がこぼれ出た。
はぁ……さっきのは、流石に不自然だと思われたかな。明らかに話をそらそうとしたってバレたよね。
脳裏から、芽衣と怜奈の鼻白んだような顔が離れてくれない。
でも……、仕方ないじゃん。
『わたしはあと三か月しか生きられないから、恋愛してみようとは思えない』なんて、馬鹿正直には打ち明けられないよ。
*
「ただいま」
「お帰り、真帆……! 体調はどう? 学校で気分が悪くなったりしていない?」
「ん。……今日は大丈夫だったよ」
「本当に?」
「本当だって」
「お母さん、真帆のことが心配で仕方ないのよ。心配して言っているんだからね。ちゃんとわかってる?」
「わかってるってば!」
お母さんは眉根を寄せて、悲しそうにうつむいた。
青白い顔に、どことなく痩せこけた頬。髪にも艶がない。すこし前に会社で働くのを辞めてから、一気に老けこんだような気がする。
泣き腫らしたような瞳に見つめられて、胸がきゅっと痛くなった。
「……部屋に、行くね」
重苦しい沈黙に耐えきれなくなって、自分の部屋へと逃げ込む。
そのままドアを背に、へたりこむように座りこんだ。頭痛までしてきた。
ここ最近、うちに帰ると毎日こんな感じで、精神的に疲弊している。
でも、お母さんばかりを責めるわけにもいかない。
お母さんをあんな風にしてしまっているのは、わたしなんだから。
「余命、三か月……」
今でも、信じられていない。
一週間前の病院での出来事は、悪い夢だったんじゃないかと思う。
前兆は、高校に入学した頃に出始めた。
朝起きたときに、頭痛がするようになったこと。
最初は単なる頭痛だと思っていたので、数週間は市販薬で誤魔化してきたけど、症状はどんどん酷くなっていった。
手足が痺れて思うように動かせなかったり、片目が見えづらくなったり。『ただの頭痛』で誤魔化すには流石に無理があると思いはじめて、お母さんに相談したら、すぐに近所のクリニックに診察を受けにいくことになった。
病院に行けば安心できると思っていたのに、結果はその真逆だった。
早急にもっと大きな病院で診察することを勧められ、大学病院を紹介されたんだ。
そして、CT検査、MRI検査と二度大学病院を訪れることになり、待っていたのは自分が想像の何百倍も深刻な状況に置かれていたという現実。
『脳に悪性の腫瘍ができています』
『娘は、助かるんですか!?』
『……残念ながら、澤田さんの腫瘍は場所が非常に悪く、進行がかなり進んでいるため手術も難しい状態です』
お母さんとお父さんが泣き崩れる傍ら、わたしだけが、ポカンとしてた。
悲しい、苦しいという以上に、ただただ自分の身に起こっていることだと信じられなかったからだ。
だって、ここに来る前まで、わたしはひとよりもすこしバンドが好きなだけの平凡な女の子だったのに。
やっと受かった高校に入学して、同じクラスに新しい友達ができたばかりのところで。ゴールデンウィークも明けて、本格的に始まる部活動を楽しみにしていたところだったのに。
全部諦めなきゃいけないかもしれないなんて、ウソだと思いたくて当然でしょ。
だけど。
悪い夢は一向に醒めてくれなくて、わたしは、目の前の医師へ現実を問いかけることしかできなかった。
『わたしは……、あと、どのぐらい生きられるんですか?』
『この進行状況ですと……、三か月程度だと覚悟してください』
心臓が、生きてきた中で、一番大きな音を立てた瞬間だった。
あと三か月。
あまりの衝撃に、その後、病院でなにを告げられてどんな会話をしたのか正直あまりよく覚えていない。
ただ、身体を楽にするために、助けてもらうために向かった病院で突きつけられたのは、十五歳の自分が向き合うにはあまりにも重たすぎる現実だったということだけだ。
*
自分があと三か月しか生きられないと知ったら、みんな、残りの人生でなにをしようと思うのだろうか。
本当は、今すぐに高校を辞めてしまっても、なんの問題もない。
余命宣告を受けたあと、お母さんとお父さんには、高校を退学することを勧められた。
『こんな状態で、学校に通わせるのは心配よ。お母さん、会社を辞めてうちにいるようにするから、うちで安静にしていたら? 真帆が出かけたいときにはいつでも付き添うし』
『真帆、そうするのが良いんじゃないかな。無理して高校に通うのは、お父さんとしても心配だよ』
お母さんとお父さんの涙ながらの提案に、わたしは頷けなかった。
『お母さん、お父さん。安静にしていても、していなくても、わたしは三か月後に死ぬんだよ』
『真帆……! そんなこと、軽々しく口にしないで!!』
『でも、お医者さんはそう言ってたよね』
家族三人そろっているのに、リビングダイニングがあれほど重苦しい沈黙に包まれたことはかつてなかった。
だけど、それでも意志を曲げたくなかった。
『……二人ともごめんね。でも、わたしは、可能な限りで高校に通いたいと思ってるんだ』
『真帆……』
『無理はしない。限界だって思ったら、うちに帰ってくる。だからそれまでは……、お願いだから、高校に通わせて』
あと三か月しか生きられないと突きつけられたときに、心に強く浮かんだ願いは、普通の高校生活を送りたいということだった。
わたしだって、みんなと同じように、高校生を体験してみたい。
死を意識する前までは、正直、高校に通えることも当たり前だと思っていた。
こうなってみて初めて、わたしにとっての今までの当たり前は奇跡だったのだと気がつくなんて、皮肉なものだ。
お母さんとお父さんは最終的に『真帆の意志を尊重する』と言って、体調が安定している間は、高校に通うことを承諾してくれた。
学校でわたしの病気のことを知っているのは一部の教師だけ。本当は誰にも知られたくなかったけど、それだと緊急時にとっさの対応ができないからと、お母さんが譲らなかった。
代わりに、生徒には、誰にもこのことは言っていない。
高校に入学して、最初に仲良くなった芽衣と怜奈にも打ち明ける気はない。
話してしまえば、良くも悪くも『余命三か月』の子だという色眼鏡で見られてしまうから。わたしが逆の立場だったら、話されたところで、接し方がわからなくなると思う。
「ねーねー、真帆。今日の放課後あいてないー?」
「どうして?」
「あたしと怜奈、二人とも、部活がオフなんだ。でさっ、今日からルタバの新作フラぺが始まるの!」
「まるごと苺味だってさ、ちょー美味しそうじゃない? 真帆も飲みにいこうよ」
良いね、美味しそう! と言いかけたそのとき、鋭い頭痛がして、喉まで出かかった言葉をのみこんだ。
「ごめん……。わたしは、用事があるから遠慮しとくね」
「えーー、そっかぁー……。じゃあ、次のオフのときにでも」
「でも、次のオフが重なる日を待ってたら、まるごと苺味は終わっちゃうよ」
「あっ。わたしのことは気にしないで良いから、二人で飲んできなよ! 明日、感想を教えてね」
「んー……。わかった。じゃー、真帆は次の機会にでも!」
「ありがとう。じゃあ、また明日ね」
微妙に納得していない顔の二人から逃げるように、スクバを肩にかけて、お手洗いへ逃げこんだ。
個室へ入って一人きりになったとき、ホッとしてため息が出てきた。
今日はあんまり薬が効いていないな。頻繁に頭痛が起こるし、吐き気もする。
あのまま無理をしてカフェに付き合って、二人の前で倒れたりしたら、悲惨なことになっていただろう。迷惑がかかるのはもちろんのこと、最悪、わたしの病気のことまで知られてしまうかもしれない。それだけは避けたかった。
友達と放課後カフェへの憧れもあったから、とても残念だけど……。
病気が、憎い。わたしが望む普通の高校生活を、ことごとく邪魔してくる。
ポーチから取りだした錠剤を飲みこみ、頭痛を落ちつかせるように深呼吸していたら、個室の外から誰かの足音が聞こえてきた。
「さっきの真帆の態度、どー思う?」
「んー……。ぶっちゃっけ、ほんとに用事があるのか微妙なところだよね」
胸に、氷の針を何百本も叩きこまれたような心地がした。全身がぞくりと冷える。
芽衣と怜奈の声だ。
「こんなこと言いたくないけどさ……、真帆って、お腹の底でなに考えてんのか、よくわかんないよね」
「そうねー。恋バナも、自分の話だけは誤魔化すしね」
「好きなひとが本当にいないのか、あたしらに隠してるだけなのか。五分五分って感じ」
心臓が、痛いほど激しく収縮する。
二人の気配が去りきるまで、わたしは個室の中で微動だにできなかった。嵐が過ぎ去るのを待つような心地で、ひたすらに息を殺した。
芽衣と怜奈に、あれほど不信感を抱かせていたなんて。
全く気がついていなかったわけじゃない。病気のことを隠すたびに、会話が不自然になっていたことは気にしていた。実際、わたしが二人に、好きなひとどころではない重大な問題を隠していることは事実だ。
だけど、ああもハッキリと嫌悪感を露わにした言葉を聞いてしまうと、心が折れそうになる。いや……、もうとっくにパキンと真っ二つに折れてるかも。
家に帰る気力すらもなくしたわたしは、お手洗いを出て、フラフラとした足取りで人気のない教室に入った。誰の机かもわからない席に座り、充電切れのロボットみたいにパタリと寝そべる。誰かが忘れ物を取りに入ってくるかもなんて、気にする余裕すらもなかった。
聞こえてくるのは、グラウンドを駆け回るサッカー部の掛け声と、吹奏楽部が練習で出している木管と金管の音だけ。
放課後、自分の好きなことへ一生懸命に打ちこめるみんなが、羨ましい。
友達と、当たり前のように、放課後に遊びにいけることも。
誰かに片想いをして、一喜一憂することも。
今のわたしには全てが眩しすぎて、直視すると目が焼け爛れそうだから、視界に入れないようにぎゅっと目をつむる。
「わたしだってさぁ……、恋、してみたかったよ」
普通の高校生活を送りたいと願ったから、この場所にいるのに。
何一つうまくやれていない。
やっぱり、無謀なことをしているんだろうか。お母さんとお父さんの言うように、退学をしたほうが良いのかな。
わたしは、すでに普通の女子高生とはかけ離れているんだから。
「じゃあ、オレと付き合って」
…………へ?
慌ててガバリと顔を上げたら、切れ長の瞳とばっちり目が合って、どうして良いのかわからなくなった。
軽い空気感を含んだマッシュヘアは、こうして間近で見ると触ってみたくなるほどサラサラで。透きとおるような肌、鼻筋の通った高い鼻、うるおいのある薄桃色の唇を見ていたら、本当にイケメンだなぁというバカみたいな感想が頭をよぎってしまった。
この、すさまじく顔が良い上に、背が高くてスタイルまで良い男子のことは、わたしも存じている。二組の狩野律人くんだ。芽衣と怜奈の間でも、新入生随一のイケメンとしてよく話題に上がっている、あの狩野くん。
その彼が、わたしに向かって「付き合って」とのたまったような気がするのは、聞き違いだろうか。
「ええと……なんて?」
「だから、オレと付き合ってほしいって言ったんだけど」
いや。いやいやいや。全く意味がわからない。
目をぱちくりとさせながら、お互い、見つめあうこと十数秒。
わたしは、状況を理解できないまま、頭を下げた。
「ええと……、ごめんなさい。お付き合いすることはできません」
「なんで? 澤田さんは、恋がしたいんじゃねえの? さっきそう言ってたじゃん」
じとりと、こめかみの辺りから汗が伝る。
いま澤田さんって言ったよね? なんで狩野くんに存在を認知されているの? 別のクラスの男子に存在を把握されるほど、高校で目立つことをした記憶はないんだけど……。
それにしても、狩野くんはとてもヘンなひとらしい。
恋がしたいというわたしの独り言をたまたま聞いていて、「じゃあ、恋してみる?」と気軽に声をかけてしまうフランクさ。いや、フランクとかいう次元で片付けられないよ。端的に言って、どうかしている。おかしいもん。
でも、いくら変人だからといって、流石にわたしの事情に巻きこむわけにはいかない。
「……したいと思っているのと、実際にしてみるのとでは、全くベツの話ですから。とにかく、わたしに恋は無理なの」
「できるよ。恋する相手がいれば、成立するし」
「しつこいよ! さっきから、なんなの? イケメンだから、とりあえず付き合おうと言っておけば女子はうなずくとでも思っているんですか!?」
思わず語気を荒めたら、狩野くんは傷ついたような顔をした。
「違うよ……。澤田さんがそう思うのも無理はないかもしれないけど、オレは……澤田さんだから付き合いたいと思ってる」
そう言う彼は、思いのほか切実そうな瞳をしていて、わたしは口をつぐんだ。
狩野くんは、口ごもったわたしを真っ直ぐに見つめながら、震える声で告げた。
「ねえ。澤田さんが、自分に恋は無理だと思っている理由は……病気のことが、原因?」
時が、止まったような気がした。
余命宣告を受けたのと同じぐらいの衝撃に襲われて、息の仕方もわからなくなる。心臓が荒れ狂って動悸が凄まじい、胸を突き破ってしまいそうなほどだ。
どうして……?
なんで、今が初対面の狩野くんが、わたしの病気のこと知っているの!?
「ちょ、澤田さん大丈夫……? 顔、真っ青じゃん。ちょっと落ちついて」
「はぁ、はぁ……。落ちつけるわけがないでしょ!!」
「あー……。ごめん。今のは、タイミングをミスったオレが悪かった」
「なんで? どうやって、そのことを知ったの!? まさか、このことを知っている先生から聞いたとか……」
「違う、違うから! すぐには事情を話せないけど、誰かが澤田さんの事情を安易に口外したわけじゃない。そこは保証する。とりあえず深呼吸しろ」
狩野くんは、すっかり怯えきったわたしをなだめるように、そっと頭を撫でてきた。
カッと頬が熱くなる。だって、男の子に頭を撫でられるのなんて、初めてだし。
でも……、どうしてか嫌じゃない。それどころか、安心してしまう。
ほぼ初対面の男子に頭を撫でられても、普通は、驚いて嫌な感じがするだけだ。気持ち悪い、触らないでって拒絶して当然なのに。
どうしてわたしは、彼の手を受けいれているんだろう。自分の心の動きに驚いて、戸惑う。
「澤田さん。澤田さんは、どうしてオレがきみの病気のことを知っているのか、知りたいと思っているよね?」
素直に、うなずいた。
「さっきも言ったけど、オレは、きみと付き合いたい。だから、澤田さん。取引をしよう」
「なにを、言っているの……?」
「オレと付き合ってくれたら、なんでオレがきみの病気のことを知っているのか教える」
「なにそれ……」
なんてズルい提案なんだろう。
ここで彼の提案を受けいれなかったら、この先ずっと、モヤモヤを抱えることになる。断ったところで、狩野くんの顔が頭をちらついて離れない未来が見えるもん。
選択肢を与えているようで、与えていない。こんな風に言われたら、誰だって、付き合わざるをえなくなる。
「付き合う。付き合うよ! はい、付き合ったからさっそく教えてくれる?」
「ふはっ、ダメだよ。ちゃんと付き合ってくれるまで教えない」
「なにそれ、詐欺じゃん! ちゃんとってなに、どういう基準?」
「三か月間」
狩野くんは、どことなく潤んだような瞳で、絶句したわたしに告げたんだ。
「三か月間オレと付き合ってくれたら、ちゃんと、真実を打ち明けるよ」
全ての音がフェードアウトして、自分の心臓の音だけが、やけにうるさく感じた。
こうして、わたしと、なぜかわたしの告げられた余命の期間まで知っている狩野くんとの奇妙な付き合いが始まった。
✳︎
昨日起こった出来事は、ぜんぶ夢だったのかな。
それなら、都合が良いや。
いっそのこと、狩野くんとのおかしな出会いよりもっともっと前から、わたしが余命宣告を受けたところから全てが夢だったいうことにできたらどれだけ良いか。
だけど、残念ながら、全て現実だったということを嫌というほど思い知らされた。
「澤田さーーん! 帰ろうぜ」
わたしを悩ませている元凶たる彼の、よく響く明るい声によって。
放課後になったとたん、教室のドアから大声で名前を呼ばれて、まだ残っていた生徒たちの視線がわたしへぎゅんと集まった。
「えっ、狩野くんじゃーん! やば! やっぱり、かっこいいーー」
「てか、澤田さんのこと呼んでなかった?」
「なんで? 二人ってどういう関係?」
狩野くんがわたしの席の方までやってこようとするので、急いでスクバを肩にかけて彼を教室から押し返しながら廊下へと出た。唖然としている芽衣と玲奈に言い訳をする間もない。
「ちょ、ちょっと待って、狩野くん! いきなり教室にやってこないでよ!」
「え、なんで? 付き合ってるんだし、このぐらいふつーじゃね?」
周囲を気にしない音量で話す狩野くんに、会話を聞いていた子たちから小さな悲鳴が上がる。あの二人付き合ってるの? なんで? いつから? てかあの女子誰? という地獄のような囁き声が伝播していき、今すぐ消えたいような気持ちになった。
「狩野くんは、やたらと目立つの! そもそも、付き合ってるなんて、絶対にみんなに知られたくなかったのに~~っ」
「ごめんって。でも、こーでもしないと、澤田さんはあっさりオレのことを無視して帰りそーだったから」
……図星だ。
昨日成行から彼と付き合う約束をしたものの、まだ、心は全く追いつけていないわけで。わたしは狩野くんのことを好いているわけでもなければ、正式に彼氏と認めたわけでもない。
付き合う約束をしたのは、あくまでも、なぜ彼がわたしのトップシークレットを知っているのかが気になったから。ただ、それだけだ。それだけのことが重要な問題なんだけど。
「図星かい、そこで黙るなよ」
「……とりあえず、外に出たいです」
「ん、りょーかい」
学校の外に出ると、ぽかぽかとあたたかい陽気に包まれた。
澄み渡る青空と、爽やかな新緑が目に眩しい。
時折、下校中の生徒に視線を向けられて、ひそひそ話をされているような気がするけど、こうなったらある程度は開きなおるしかない。どうせ明日には、あの狩野くんが一組の冴えない女子と付き合ったという噂が広まりまくっているんだろうし。
「澤田さん、すごくやるせなさそうな顔してる」
「誰のせいだと思っているの」
「んー……。オレ?」
「自信満々に言われるとムカつく」
「ごめん。これでも、ちょっと焦りすぎたなって反省はしてるよ」
しゅんと眉尻が下がった。
わかりやすく落ちこんでいる素直な反応に、毒気を抜かれる。
「でもさ……、オレは、澤田さんの願いを叶えたいんだよ。それと、一日も無駄にはしたくない」
「願いって……」
「恋したいんでしょ? だったら、一日でも早くオレのことを好きになってもらわないとじゃん」
ぶわりと顔に熱が集まった。
狩野くんが言ったからじゃない。真剣にそんなことを言われたら、誰からだとしても顔が熱くなる。
彼は、どうしてわたしのことで、こんなに必死になってくれるんだろう。問いかけてみたところで、病気の件と同じように煙に巻かれると思ったから、口にはしなかった。
高校の最寄りの駅前までやってくると、狩野くんは足を止めて、わたしの顔をのぞきこんだ。
「澤田さん。今日、体調は大丈夫?」
「うん。むしろ、結構良い方だと思う」
「それは良かった。じゃあ、これからデートしない?」
「デ、デート……!?」
「そんなに驚く? 付き合ってたら、当たり前じゃねーの」
「そ、そうかもしれないけど、いきなり……? わたし、狩野くんのこと全然よく知らないし、男の子と二人きりで出かけたこともないし、その、心の準備がまだできてないというか……」
しどろもどろになっていくわたしに、狩野くんはうれしそうに笑った。
「オレが、澤田さんの初めてのデート相手になれるってこと? なにそれ。すげーうれしい」
「なっ……!」
「オレのことを知らなくても、なんの問題もないよ。だって、互いのことを知るために、デートするんだろ」
「そっか……?」
「それとも、いきなり出かけたりしたら、ご両親が心配する?」
「それは、連絡を入れておけば大丈夫だよ。そんなに夜遅くならなければ」
「もちろん、そのつもり。やった! ねえ、澤田さんはどこに行きたい? やりたいことはある?」
「うーん……。じゃあ、カラオケとか?」
答えてから、あれ? 答えを間違えたかも、と焦り出す。
単純に、久しぶりにカラオケで歌いたい気分だったから口にしたんだけど、よくよく考えるとカラオケボックスって薄暗いし密室だ。完全に信頼を置いているわけじゃない異性と初めて二人きりで遊びにいく場所にしては、ちょっと不適切な気も……。
「ごめん、間違え「良いじゃん、カラオケ」」
食い気味で答えた狩野くんは、子供のように瞳をきらきらとさせていた。
マズい、思った以上にノリノリだ……! 早く流れを変えなきゃ、と焦ったのも束の間、狩野くんの意外すぎる発言ですぐに気が変わった。
「澤田さんは、『星空スコープ』の最新曲、もう聴いた? もしかして歌えたりするの?」
「えっ……!?」
「スクバについてるそのストラップ、スコープのグッズでしょ。見て、すぐにわかったよ」
彼が、わたしのスクバにぶら下がっている星型のゆるいマスコットキャラに反応した瞬間、わたしの中の狩野くんが、よく知らない男子から、星空スコープ同志へと一気に昇進した。
「ウソウソウソ……っ! もしかして狩野くんも、スコープファンなのっ?」
「澤田さん、テンション一気に上がりすぎでしょ」
「だって、スコープ好きに悪いひとはいないし! ねえ、ファンなの?」
「ファンだよ。スコープって、スリーピースとは思えない音圧で、すげえかっこいいよな。憧れてるバンド」
「そう、そうなのっ! えーーっ、こんな偶然ある? うれしいなぁ」
「じゃー、カラオケで、スコープの曲一緒に歌おうぜ」
「うんっ!」
スキップしたいような心地で駅近のカラオケ店に向かい、わたしと狩野くんは、宣言通り星空スコープの曲を熱唱しつづけた。
頭の中で危惧していた、ヘンに気まずい空気も、危険な甘い空気もこれっぽっちもない。今この場は、異性とかそんなことも頭から抜け落ちるほど、純粋に星空スコープ好きな二人がはしゃいで歌うだけの楽しい空間だった。
驚くべきは、狩野くんの美声だ。
ずっと高音が続いてテンポも速い星空スコープの難しいメロディを、完ぺきに歌いこなしている。
「狩野くん、すっごいね! 歌うますぎなんだけど! クオリティ高い~~!」
「どや。オレ、スコープの曲をカバーしたくて、軽音部に入ったようなもんなんだよね」
「そうだったんだ! ちなみにパートは?」
「ギタボ担当だよ。澤田さんも、全曲合いの手まで完ぺきだな。ガチファンじゃん」
「まあねっ。中学一年生のときから、ずっと聴いてるし! でも、生のライブを聴きにいけたことはなくて、高校生になったらスコープのライブに通うために、バイトもしようと思っていて……」
言葉が、続かなかった。
代わりに、瞳から涙がこぼれてきた。
学校に通うのはゆるしてもらえたけど、この身体でバイトをするのは諦めた。いつお店のひとに迷惑をかけるかもわからないし、お母さんとお父さんにも猛反対されたから。真帆はお金の心配をする必要はない、無理をするなって。
実際、お金を稼いだところで、わたしにはそのお金から恩恵を受けるための充分な時間ものこされていないのだ。
そうやって納得しようと思ったけど、本音を言えば、バイトもしてみたかった。一生懸命働いて、自分の力でお金を得て、自分にとって価値のあるものに使うこと。
それがどんなことかも知らないまま、わたしは死んでしまうんだ。
「澤田さん……」
嫌だなぁ。せっかく、新たなスコープ仲間を見つけることができて、ひたすら楽しくて幸せな空間だったのに。こんな湿っぽい空気を持ちこむ気なんて、さらさらなかったのに。
狩野くんは、涙を流しつづけるわたしを、苦しそうに見つめている。
急に静かになった室内に、隣の部屋の下手っぴな歌声が遠くから聴こえた。
「ごめ、んね……。なんか、ヘンな空気にしちゃって。えっと……、まだ入れてない曲を歌おうか」
「澤田さん。オレには、気なんて遣わないで」
「……でも」
「オレは、楽しいことだけじゃなくて、澤田さんの背負っているものも共有したいんだ」
狩野くんは、わたしの隣に静かに腰を下ろすと、流れつづける涙をそっと長い指先でぬぐった。
どうしてだろう。昨日も思ったけど、彼からもたらされる温もりは嫌じゃない。狩野くんの指には、胸を覆いつくす悲しみを溶かす魔法でもかかっているみたいだ。
「こんなこと言ってるけど、オレが澤田さんのためにできることなんて、実際はほとんどなんもない。不甲斐なくて、ごめん……。苦しみも痛みも、この指から伝わって、半分にできたら良いのにな」
「ははっ。狩野くんが、そこまでする義理はないでしょ」
「あるよ」
有無を言わせぬ断言に、なにも言えなかった。
切れ長の瞳に、涙に濡れた情けないわたしの顔が映りこむ。
「ねえ、澤田さん。オレを、澤田さんの気持ちのゴミ箱にして」
「ゴミ……? どういう、意味?」
「汚いものは捨てていかないと、ゴミでいっぱいになって溢れちまうだろ。それは、物理的なモノだけじゃなくて、感情も一緒なんだと思う」
感情も、一緒。
彼の話を聞きながら、自然と胸に手を当てていた。
「人間なんだから、プラスの感情だけで生きていることなんてできやしない。苦しい日も、悲しい日も、他人が妬ましくて仕方ない日がある。でも……、日々生まれる負の感情を誰にも吐き出せなくて、自分の胸の内いっぱいにためこんじまう人間も多い」
彼の言うとおり、わたしは今、涙になってあふれるほどの悲しみを胸のうちに押し返そうとした。
「ゴミと違って、気持ちを吐き出したところで、現実自体がきれいになるわけじゃない。しんどい状況は、しんどいままだ。誰に話したところで現実は変えられないから、自分の感情は自分だけでどうにかしようって考える気持ちもわかる。……たしかに、言葉じゃ現実を変えられないのも事実だよ。でも……、それでもオレは、吐き出させてもらえたことで、救われたから」
ドキリと、心臓が跳ねた。
狩野くんの瞳に、見ているこちらが熱くなってしまうような焔が灯っていたから。
だけど、彼は、目の前のわたしを見ているようで見ていない気がした。
まるで、わたしを通して、別の誰かを見ているような。
「狩野くんも……辛いことが、あったの?」
彼は、わたしの問いには答えずに、やさしく笑った。
「……澤田さんは、ただでさえ不安になって当然の状況なんだ。毎日、オレなんかには想像もつかないほど頑張ってる。だから……、オレの前では、頑張ろうとしないで」
止まりかけていた涙が、再びあふれ出す。
わたしは頑張っているのだと、ハッキリ言葉にして認めてもらえたことが想像以上に心に響いて。
よく知りもしない、謎だらけの男の子の前で、ただ泣いた。彼に背中をさすってもらえると、恥ずかしいよりもどうしてか安心の方が勝る。
「ごめ……ん。あり、がと……」
「謝るのも禁止」
「……っ」
しんみりとした空気のまま、カラオケの終了の時間がやってきて、わたし達は無言のまま室内を出た。
外に出ると、空は暮れなずんでいた。こんなに遅くまで遊んだのは、余命宣告を受けてからは初めてだ。
「だいぶ日ぃ暮れてんな。ご両親、心配してない?」
「たぶん、大丈夫だと思う」
……本当は、お母さんからの連絡通知がたくさんきているけど。正直にそう言ったら、狩野くんが恐縮して、今後遊びに誘ってくれなくなるかも。
って、いやいや。わたしってば、なに先のことまで期待してるの。
「今日はありがと! また明日な」
その日、彼は、わたしを家の前まで送ってくれた。わざわざ定期券外の電車にまで乗って。
そこまでしてもらう必要はないと何度も言ったのに、『オレが好きでしていることだから』と言ってきかないから諦めた。
うちに帰ったら、血相を変えたお母さんに「どこで遊んでたの? 体調は大丈夫なの!?」と心配されて、再び現実に戻ってきたような気分になった。十二時の鐘が鳴って魔法が溶けたシンデレラみたいに、この家に帰るとわたしは、余命宣告を受けたかわいそうな一人娘に戻ってしまう。
さっき別れたばかりなのに、また、狩野くんのことが頭の隅に浮かんだ。
狩野くんのそばにいるときは、息がしやすかったんだなぁって。
*
「真帆。単刀直入に聞くけど、二組の狩野くんと付き合ったって、マジなの?」
「なにがあったの? ちょっと前まで、恋愛興味ないって感じのこと言ってたのに、ウソだったってこと? なんであたしらに、ほんとのこと話してくれなかったの!?」
狩野くんとカラオケに行った翌日の昼休み。
チャイムが鳴ったとたんに、芽衣と玲奈につめよられて、わたしはタジタジになっていた。心なしか、二人以外の女子も、この会話に聞き耳を立てているような感じがする。恐るべし、狩野くん人気。
昨日の時点で、こうなることは予想がついていた。
でも、わたしは二人に嘘をついていたわけじゃない。だって、狩野くんのことに限って言えば、当のわたしですら本当に予想外だったんだから。
でも、彼と付き合った経緯をちゃんと話そうとすると、病気のことまで話さなきゃいけなくなる。だけど、またその場しのぎの誤魔化すようなことを言ったら絶対に空気悪くなるし、最悪、嫌われて仲間外れにされちゃう可能性もなくはない。
失敗した。ちゃんと言い訳を考えてくれば良かった。背筋から嫌な汗がダラダラと流れてくる。
結局なにも言えずに心拍数だけを跳ね上げながらうつむいたら、ここ数日で聴き馴染んできた声がわたし達の会話に割って入ってきた。
「澤田さんは、ウソついてないよ」
狩野くんだ。
いつの間にか、一組の教室に堂々と入ってきていた彼が、わたしの代わりに答えていた。
芽衣も、怜奈も、もちろんわたしも、呆気に取られて彼をポカンと見やることしかできなくて。
「オレが澤田さんのことを前々からずっと好きでコクったの。澤田さんには、恋には興味ないからって振られそうだったけど、オレが押して強引に付き合ってもらったんだよ。それで、今は、振られないように必死に努力中ってとこ」
「そう、だったんだ……?」
「そー。ってわけで、ちょっと澤田さんのこと借りて良い? 惚れてもらうのに、必死なもんで」
「あ……。ど、どうぞ?」
「ありがと! 今後も、ちょくちょく借りてくと思うけど、よろしくねー」
いつも、たやすく同じクラスの男子と話している芽衣と怜奈も、狩野くんに対してはちょっと緊張しているような感じで、なんだか新鮮。
二人へ隠しごとをしている罪悪感を抱きながらも、今この場を乗りきるには、彼の嘘に乗っかるしかなかった。
「えっと……。わたし、今日は、狩野くんと一緒にお昼食べるね」
「……うん。わかったよ」
狩野くんに手を引かれながら教室を出て、廊下をずっと進む。
恥ずかしいからやめてって、この手を振り払うこともできるけど。そうしたくない自分がいて、また驚く。
狩野くんと無言のまま歩いて別棟までやってきた。
彼は、音楽室の隣の部屋、『軽音部』というプレートのかかった重たそうなドアを力強く押した。
「入って良いよ。軽音部の部室なんだけど、練習入ってない昼休みの時間は基本的に誰も来ないんだ。オレ、たまに、ここで飯食ってるんだよね」
「お、お邪魔します」
中に入ると、音楽室と同じように防音仕様の部屋となっていて、部屋の奥の方の三分の一程度の面積が一段高く簡単なステージのようになっていた。ギターとベース用にそれぞれアンプが置いてあり、キーボードとドラムセット、ボーカル用のマイクとマイクスタンドも設置されている。
軽音部のみんなは、ここで練習をしたり、ライブをしたりするんだ。
さっきまでの憂鬱な気持ちが一気に吹き飛んで、思わずぴょんぴょんと飛び跳ねたいような楽しい気持ちになった。
「うわあ! すごい、すっごいんだねっ。ここが、軽音部の部室なんだ!」
「オレが最初にこの部屋に入ったときと、似たような反応じゃん。でも、すげーわかるわ。テンションぶち上がるよなぁ」
「そりゃあ、上がるよ! バンド好きの血が騒ぐもん」
「ははっ。とりあえず、飯食おうぜ。ここ、座って良いよ」
狩野くんは、ステージ前の陽当たりの良い場所に、二つ分のパイプ椅子を用意してくれた。彼が購買で買ってきたらしい焼きそばパンを頬張りはじめたので、わたしも、お母さんに持たせてもらったお弁当の風呂敷をひらく。
卵焼きをもぐもぐと頬張っていたら、狩野くんは、わたしの表情をうかがうような顔をしていた。
「さっきさ、突然、教室に行っちゃってごめんね。迷惑だった?」
「そんなことないよ! むしろ……、さっきは、助けてくれてありがとう」
「澤田さんとお昼一緒に食べれたら良いなぁと思って、たまたま突撃しただけなんだ。そしたら、澤田さんが、オレのことでなんか問いつめられてるっぽかったから、悪いことしたと思って。……澤田さんは、友達には、病気のことを言ってないんだろ?」
こくりと、うなずいた。
一番大きな隠し事を知られている彼の前では、素直に言葉が出てくる。
「……うん。できることなら、隠しとおしたいんだ。芽衣と怜奈とはね、高校に入ってからの仲なの。入学式のときに、星空スコープ聴いたことあるって話題で仲良くなったんだ。よく話を聞いたら、二人はわたしほどのスコープファンではなかったんだけど、それでも新しい友達ができて本当に嬉しかったし、新しい環境になって心細かったから安心もした」
だけど。
わたしは、その直後に余命宣告を受けた。
「あと三か月しか生きられないってわかったとき、わたしは、可能な限りで高校に通いたいって思った。普通の高校生活を、体験したかった。だから、病気のことはできる限り隠していたい。芽衣や怜奈に気を遣わせることも、気軽に接してもらえなくなることも、怖いの。でも……隠そうとすればするほどヘンな感じになって、うまくいかなくて。多分、二人の不信感を募らせてるし、ウザがられてる」
言葉にしながら、お弁当を持つ手が震えた。
『こんなこと言いたくないけどさ……、真帆って、お腹の底でなに考えてんのか、よくわかんないよね』
先日、お手洗いで思いがけず聞いてしまったあの冷たい声が、蜘蛛の巣みたいに脳裏に粘ついている。ふとした瞬間に蘇って、心臓の真ん中から冷えていく感じ。あれ以来、わたし自身も、二人がお腹の底ではなにを考えているのかわからなくて、余計に怖くなってしまった。
「そっか。澤田さんは、優しいな」
「違うよ。どっちかっていうと……わたしのエゴで、二人を戸惑わせてるだけなのかも」
「そうだとしても、二人の気持ちを考えてのことだろ。たしかに……、高校生で死を強く意識してる人間の方が少ないだろうし、打ち明けられても、最初は受けいれられなくてパニックになるだけかもしれない。すごく、悩むところだよな」
実際、狩野くんの言うとおりになると思う。誰だって、身近なひとが死ぬかもしれないなんて話を、簡単には受け止められない。お母さんとお父さんだって、わたしが余命三か月だと知ったあの日から、平静を失ってしまった。
「けどさ……、オレが相手の立場だったら、知らずに後悔するよりも、知った上で後悔する方が良いな」
どくんと、心臓が脈打った。
「もちろん、最終的には、澤田さんが決めることだよ。でも、重々しくどうしようって考えてるとそれだけで疲れちゃうから、答えが出ないうちはいったん忘れていても良いかもな。時間が過ぎたら、気持ちが変わってることだってあるし」
「なんか……、すごいね。そんな風には考えられなかった。狩野くんって、大人びたことを言うね」
「そー? そう感じてもらえるのは大歓迎。澤田さんに、好かれたいし」
へらりと笑う彼に、顔が熱くなる。
さっきまで淀んだものでいっぱいだった胸の内も、いつの間にかほんの少しは軽くなっていた。
「狩野くん。吐き出させてくれて、ありがとうね」
「こちらこそ。吐き出してくれてありがとう」
窓からさしこむ陽射しを浴びた彼の笑顔が、眩しく輝いて見える。
その屈託のない笑みに、胸が絞めつけられたようになって、ドキドキとした。
ねえ、狩野くん。ちょっと前まで恋をしてみようとは思えないとか言ってたくせにさ、わたし、もうすでにきみへ惹かれはじめてる気がする。
でもさ、たとえそうだとしても、口にはできないよ。
言葉にしてしまったら、あと戻りできないくらいに、きみを好きになってしまいそうで。
*
狩野くんと一緒に、たくさんの時間を過ごした。
放課後、彼の軽音部の練習がないときは、他愛もない話をしながら一緒に帰る。
「澤田さんは、もしバンドやることになったら、なんのパートをやってみたい?」
「うーん……。ギターボーカルをやってみたいけど、ベースでシンプルにルート弾きもしてみたい! あ、でも、安定感のあるドラムもすごーくかっこいいよねぇ」
「ふはっ、選べてねーじゃん。でも、澤田さんはドラムって感じはしねえな」
「なんで?」
「んー。運動神経悪そうだから」
「シンプルに悪口!」
「だから、はい。手、出して」
「え?」
「澤田さんが、なにもないところで転びそうになっても大丈夫なようにだよ」
「なにそれ。わたし、そこまでどんくさくないよ」
「じゃー、シンプルに、オレがまた手をつなぎたいから」
「……そこまで、言うなら。つないであげないこともないですけど」
狩野くんの飾らないストレートな言葉は心臓に悪い。ドキドキしすぎて、つい、素直な言葉が出てこなくなってしまう。
その日から、彼と手をつないで帰るのが、当たり前になった。後になって思うと、わたしがいつ体調を崩してふらついても大丈夫なように配慮しての行動だったのかもしれない。実際、抱きとめて助けてもらったことも何度かあった。
でも、そうとは口にしなかった狩野くんのやさしさに気がついたとき、胸が甘くうずいた。
六月に入ってからは、狩野くんの軽音部での練習風景を、何度か見学もさせてもらった。
「おーおー。スタジオ練に、彼女を連れてくるなんて、マジで浮かれてやがんなぁ。このお花畑野郎が!」
「まあ、否定できねえわ。でもさ、こんなにかわいい彼女がいたら、浮かれたくもなるだろ? な?」
「……うげえぇ、砂糖吐きそう。からかい甲斐のねえやつ」
バンドメンバーにからかわれても、狩野くんはなんのその。わたしばかりが羞恥心で焼け死にそうになり、来るんじゃなかったって後悔しそうになった。
でも、一度、アンプを繋いだエレキギターの音が稲妻みたいに部室に広がった瞬間、感動で鳥肌が立った。アンプとドラムセットから響く生音の迫力に、ただただ圧倒される。
ギターを弾きながら、わたしの大好きなスコープの曲を歌う狩野くんは、悔しいくらいにかっこよかった。思わず、涙ぐんじゃうほど感動して、ずっと胸が高鳴っていて。演奏が終わった瞬間、立ち上がって拍手した。
「すごかった……! ライブって、めっちゃくちゃ感動するんだね!!」
「へへ、ありがと。なんか、そんなにガチで褒められると、恥ずいな」
スタジオ練習の時間を邪魔しつづけるのは悪いかと思って、先に帰ろうとしたんだけど、みんな見学していて良いとあたたかい声をかけてくれたので、お言葉に甘えて練習風景をずっと眺めさせてもらった。
その日の帰り道は、雨が降っていた。
灰色の空の下、わたしと狩野くんは、彼の差す紺色の傘の中で肩を並べて帰った。
「わたしね、スコープのライブを生で観にいくのが夢だったんだ。でも、直近でスコープのライブの予定はないし、もう絶対に叶わないんだろうなって諦めてた」
「真帆……」
「だけどね、今日、叶っちゃったよ! 今日の狩野くんたちの演奏、そう思うくらい、ほんとにほんとにすごかったなぁ」
「おーげさすぎ。……本物は、ぜんぜん違ぇよ」
「そうかもしれないけど、すごく心に残る演奏だったよ。狩野くんのおかげで、憧れてた軽音部の雰囲気も知ることができたし、最高にハッピーな一日だった。わたしを軽音部へ連れて行ってくれてありがとう。今日のことは、死ぬ日まで忘れないと思う」
「……っ」
言葉につまって、泣きそうになっている狩野くんはなんだか新鮮で。かわいいなって頬がゆるんだ。
狩野くん。きみはね、わたしのもう一つのひそかな夢も叶えてくれたんだよ。
雨の日に、男の子と相合傘をして、ドキドキしながら隣を歩くことにも憧れていたからさ。
恥ずかしくて、そこまでは口にする勇気がなかったけど。
もちろん、幸せな日ばかりじゃない。
病気の猛烈な痛みと苦しみに襲われて、もうこんなのは嫌だって、ぜんぶ終わらせたくなる夜もある。
「もう、無理……っ。我慢できないっ。こんなに辛いなら、早く、死んじゃいたい。苦しい、苦しいよ……。助けてよ!」
「……ごめん。なにもしてやれなくて……、ほんとにごめんな」
「わたしの、ほうこそ、ごめん……。ごめんね……っ。こんな泣き言を聞かせたりして、ほんとに、ごめん……」
「謝るの禁止って言ったじゃん。それにオレは、真帆に頼ってもらえてうれしいよ。ねえ、真帆。こんなに辛いのに……、それでも、頑張ってくれていてありがとう」
親にこれ以上の心配はかけたくない。それでも、薬も効かなくてあまりのしんどさから誰かに弱音をこぼしたくなったとき、わたしは携帯で狩野くんと通話をつなげながら呪詛をまき散らした。それで身体が楽になるわけじゃなくても、わたしの頑張りを認めて寄り添ってくれるひとがいるという事実が、屈しそうになる心を支えてくれた。
病気じゃなかったら、狩野くんと関わることはなかっただろう。
身体のどこも痛くない状態で、好きなひとと同じ時間を過ごせる喜びを、奇跡とまでは思えなかっただろう。
病気のことは、変わらず憎い。胸が焦げつきそうなほど憎らしくて、消えてしまえば良いのにって毎日考えてる。
だけど……、狩野くんとの出逢いは病気があったからこそ訪れたものだと思うと、ほんのすこし位は感謝しやってもいいかって最近は考えてる。癪だけどね。
そうやって、彼と付き合いはじめてから、二か月が経った。
満ちたりていたからこそ、あっという間の二ヶ月間。
この間、芽衣と玲奈とも、つかず離れずの距離感を保てていた。わたしが狩野くんと付き合ったことで、自然と恋バナに加われるようになったから。
こんな日々が、ずっと続けば良いのにな。
でも……。
どれだけ必死に願っても、わたしの脳に巣食う病は予定通りに進行して、この充実した日々が続くことをゆるしてはくれなかった。
*
学校からの帰り道。もわもわとする夏の気怠い空気の中を歩いていたとき、いきなり耐えがたい頭痛に襲われた。
「いたたたっ……」
立っていることもできなくてうずくまったら、狩野くんは、わたしが道の往来で嘔吐しても大丈夫なようにとすぐにエチケット袋を差し出した。
「真帆。大丈夫? 吐いても大丈夫だよ」
「だい、じょうぶだよ。……ちょっと、頭痛がしただけだから」
そう答えながら、もう高校に通う余裕はないのだと、自分の体調のことだからこそよくわかっていた。すでに学校を何日も続けて休む日も出てきていて、一日座って授業を聞いているのも難しくなってきている。
「でも、顔色すっげえ悪いよ。真帆の家までもうすぐだし、家まで背負って送ろうか?」
「そんな、ことまで……、させられない」
「真帆……」
道の端によってわたしの背中をさすってくれる狩野くんが、今にも泣きそうな顔をする。最近は、彼にこんな顔をさせる日ばっかりで、本当に申し訳ない。
どれだけ願っても、奇跡は起こらない。
最初は、狩野くんがどうしてわたしの病気のことを知っているのか気になったから付き合ったけど、今は違う。
純粋に、彼のことが好きだ。
大好きで、そばにいたいから、自分の意志で付き合ってる。
でも……、これ以上は、狩野くんに迷惑しかかけられない上に、しんどい思いをさせるだけだ。今までと違って、わたしはもう、彼を笑顔にすることができない。
一緒にいても、辛い思いをさせるだけ。決して幸せにはなれない。
だから、もう、終わりにしなきゃ。
「狩野くん。……いつも、ありがとう。この二か月間、本当に本当にありがとうね」
彼の顔が、強張った。
「急に、なに? どうしたの」
「わたしね、狩野くんのことが好きだよ」
切れ長の瞳が、驚いたように見ひらかれた。
あぁ、嫌だな。
初めての告白は、もっとかわいらしくて、ドキドキとするシチュエーションで言いたかったのに。こんな、風に吹かれたら消えてしまいそうなろうそくのように頼りない声で、言いたくはなかったなぁ。
「わたしに……、恋を、教えてくれて、ありがとう」
「……なんだよ、それ。なんで今このタイミングで、……そんなことを、言うんだよ」
涙交じりの怒っているような声に、熱いものが喉にせりあがってきた。
でも、これからひどいことを口にするわたしに、泣く資格はない。ちゃんと、最後まで、わたしの言葉で伝えなきゃ。
「狩野くんも、わかってると思うけど……身体が、だいぶ限界なの。明日から、学校は休むつもり。それで……、狩野くんとも、もう二度と会わない」
彼の瞳から、涙がぼろぼろとあふれた。
「それ、本気で言ってるの? まだ、約束の三か月も、経ってないのに……」
「もう、いいの。知らないままで良いんだ」
狩野くんが、どんな理由でわたしに近づいたんどとしても、かまわない。
すこしも気にならないっていったらウソになるけど、これ以上は、背負わせられないよ。
明るい未来が開けている狩野くんを、わたしに縛りつけたくはないから。
「嫌だよっ! いきなりそんなこと言われて、納得できるわけないだろ!!」
「散々頼っておいて、急に勝手なことばかり言ってごめんね。今まで、本当に本当にありがとう。でも、もう、一緒にはいられない。だから……別れてほしい。ばいばい、狩野くん」
呆然としている狩野くんの手をすりぬけて、よろよろとした足取りでうちを目指した。
「真帆っ! クソッ、なんでこうなっちまうんだよ……っ」
胸が千切れそうなぐらいに悲しくて、涙があふれて止まらなかったけど、決して振り返りはしなかった。振りかえって彼の顔を見たら最後、その胸の中に飛び込んで泣きついてしまいそうだったからだ。
うちに帰ると、お母さんは泣き腫らした顔のわたしを見て、強く抱きしめてくれた。
「どこか痛むの? 苦しい思いをしたの?」
「……ねえ、お母さん。わたし……、学校に行くのは、もうやめる」
「そう。……わかったわ」
今ばかりは、なにがあったのかを聞かずに抱きしめてくれるお母さんの存在が、とてもありがたかった。
✳︎
学校を休むと決めて間もなく、わたしは総合病院へ入院することになった。家で療養することも考えたけど、緊急事態が起きたときに、病院にいた方がすぐに対応してもらえるからという家族の意見に従った。
最低限のものしか置かれていない病室での質素な生活は、想像以上に退屈でさびしいものだった。ちなみに、学校のみんなには、わたしは風邪をこじらせているということになっているから、お見舞いにやってくるのは身内の親族だけ。中学時代の友人も、今は高校生活に慣れることに忙しいかもと思ったら、連絡をして水を差す気にはなれなかった。
襲いくる症状は日に日にひどくなってきていて、意識を保っていられない日も出てきたから、この選択は今のわたしにとって間違っていなかったんだとも思う。
ベッドに寝転がりながら、SNSを眺めようとして携帯を手に取ったとき、狩野くんの明るい声が頭をよぎった。
ダメだなぁ、わたし。
携帯を手に取ると、どうしても狩野くんに連絡を取りたくなってしまって、胸が苦しい。歯を食いしばって、それだけはしないようにと堪えた。あんな酷い振り方をしておいて、未練がましく連絡を送ることなんてできない。していいわけがない。
携帯を手にしていたら、思いがけない人物から連絡通知がきた。
【真帆。体調、大丈夫なの?】
【先生は風邪をこじらせてるって言ってたけど、ほんと?】
芽衣と、怜奈だ。
いつもの癖で『うん、大丈夫だよ。ちょっとしんどいけど、本当にただの風邪だから』と当たり障りのない返信をしようとした手が止まる。
このまま、二人に本当のことを告げず、この世を去っても良いんだろうか。
『オレが相手の立場だったら、知らずに後悔するよりも、知った上で後悔する方が良いな』
こんなときにまで、狩野くんの言葉が蘇る。
二人に対しては、正直、複雑な思いも抱いている。陰口を言われていたショックは大きかったし、二人へ心配をかけないように良かれと思ってしたことが空回りしていた日々は辛かった。
だけど……、全てを芽衣と怜奈のせいにもしたくない。わたしが黙っている限り、二人が、わたしの個人的な事情を知る由もないんだから。
この病院に来てから、もう一週間は経っている。残された期間は、長くはない。
だからこそ、いままで出せなかった勇気を奮って、悔いのないように行動したい。
わたしは、あとは打って送信するだけの当たり障りないメッセージを全部消して、もう一度、携帯を打ちなおしはじめた。
【二人とも、心配してくれてありがとう。いきなり重たい話になっちゃって申し訳ないんだけど、本当は、命に係わる大きな病気を患っています。学校にも、もう二度と通えないと思う。大事なことなのに、ずっと黙っていてごめんね】
すぐに既読がついて、ドキリと心臓が飛び跳ねた。
返信がこなかったから、わたしは続けて、正直な気持ちをメッセージに打ちこんだ。
【本当は、芽衣と怜奈のことが、羨ましくて仕方ないときもあった。二人だけじゃなくて、学校のみんなのことも。未来あるみんなが、眩しくて仕方なかったの。なるべく普通の高校生活を送りたかったからこのことは黙っていたんだけど、結果的に、それで二人を戸惑わせてたと思う。今更、こんなことを打ち明けてごめんなさい。それから、こんなわたしと友達になってくれてありがとう】
どんな返信がくるか怖くなって、携帯を放り出したら、携帯が震えはじめた。
二人からのグループ通話の着信だ。
「真帆! いま、大丈夫!?」
「電話しても平気!?」
「うん」
少しの沈黙が訪れたあと、芽衣と玲奈のすすり泣く声が耳に流れこんできた。
「真帆の、バカ……っ」
「……ほんとに、さぁ。なんで、そんな大事なこと……、もっと早く、教えてくれないかなぁ」
涙交じりの鼻声に、胸がギュッと締めつけられた。
「ごめ、んね。二人に、気を遣わせたら、悪いなぁと思ってて……」
「あたしら、バカなんだよ……っ。真帆が……そんな状況になってたなんて、今の今まで、すこしも知らなかったっ」
「ちょっと風邪をこじらせてるのかもなってぐらいに思ってたのに、命にかかわる病気ってなんなの!? そんなの……言ってくれなきゃ、わかんないよ!!」
だって、わたしは、二人にとって取るに足らない存在だと思ってたから。
出会って、たった数ヶ月の友達に、こんな重たい事実を打ち明けて背負わせるのは、申し訳なさすぎるって……。
でも、わたしだって、言われないとわからなかった。芽衣と玲奈に、泣いて心配してもらえるほど、気にかけてもらえていたこと。
「真帆は……、やさしさから、黙ってたのに。ずっと……、なんにも気がつけなくて、ごめんね」
「あたしら、ほんとどーでもいいことばっか、喋ってたよね……。絶対、真帆の気を悪くさせてたと思う」
「それは、ほんとに気にしないで! わたしが、二人にはいつも通りでいてほしかっただけだから」
「真帆……。ねえっ、今から、お見舞いに行っても良い?」
「えっ。良いけど……、ほんとに来てくれるの? いつでも大丈夫だけど、二人とも忙しいんじゃ」
「なにバカなこと言ってんの! 部活休んでも、行くに決まってるでしょ!」
二人の行動力はすさまじく、電話をもらってからすぐに、二人は病室へと駆けつけてくれることになった。
身内以外のひとに会うのは久しぶりで、わたしも急いで、最低限の身だしなみを整えた。
芽衣と玲奈は、ベッドの上で上体を起こしたわたしを見るなり、駆け寄ってきた。
「真帆……。久しぶり、だね」
「苦しくない!? えと、えと……、今更だけど、いきなり押しかけちゃって、迷惑じゃなかった……?」
「大丈夫。今は、マシな方だよ。二人とも、こんなところにまで来てくれて、ありがとね」
「そっか……。なんかさぁ……、ここに来るまで、真帆の病気のことを若干信じられない気持ちもあったんだけど、本当、なんだね」
「ずっと黙ってて、ごめんね……?」
「謝るのはやめて。謝罪すべきは、あたしたちのほうなんだから……」
二人はメイクが崩れるのも気にせずに泣いた。
それから、最近の学校での出来事を、たくさん話してくれた。
芽衣と怜奈の話を、これまでにないくらい穏やかな気持ちで聞くことができた。
隠しごとをしている罪悪感がなくなったから。そして、わたしの普通の高校生活への未練が思っていた以上に薄れていたことにも気がついた。
二人には、最期まで病気のことを打ち明けるつもりはなかったけど、勇気を出してみて良かったな。
こんなに深く想ってくれていたことに気がつけないままこの世を去るなんて、さびしすぎるもの。
「ねえ、真帆。ひとつだけ聞いても良い?」
「なに?」
「狩野くんは……、このことを知ってる?」
ひゅっと、喉が細まった。
嫌だな。いつの間にか、名前を聞くだけで、こんなにも胸が締めつけられる。
「うん。病気のことは、知っているよ。だけど……、会ってはない」
「そっか……。会いたいと思ってないの?」
「会いたく……」
ない、と。
言いきるつもりだったのに、できなかった。
ウソでも、そんなこと言えなかった。
「……やっぱり、ウソ。ほんとはね、今すぐ会いたい。会って、ひどいこと言ってごめんねって謝りたい。それから……、大好きだよって、もっといっぱい伝えたかったっ。でも……そんなこと言う資格、わたしにはない」
とどめてはおけなかった本音が、涙とともにこぼれ出る。止められなくて、両手で顔を覆った。
短かったかもしれないけど、普通の高校生として過ごして、恋を経験することができた。
欲を言えば流星スコープのライブは一度生で観てみたかったけど、それ以上に、このまま狩野くんに会えずに死んでしまうことの方がずっと悲しい。
病気をなくす以外で、なんでもひとつだけ願いを叶えられると聞いたら、本心とエゴが剝き出しになってわたしは願ってしまうだろう。
息を引き取る最期の瞬間まで、狩野くんのそばにいたいって。
「だってさ、狩野くん」
ウソ。
芽衣と怜奈が、病室の入口へ視線をよこした瞬間、勢いよくその扉が開かれて。
涙でぐしゃぐしゃになった視界に飛びこんできたのは、大好きなひとの泣き顔だった。
「勝手に連れてきちゃってごめんね、真帆。でも、最近の狩野くん、幽霊みたいに青白い顔しつづけてたから、流石にかわいそうになっちゃって」
「真帆の病気のことを聞いて、合点がいったんだよ。おせっかいかとも思ったけど、もし真帆も狩野くんに会いたいと思ってるなら、このままで良いわけがないと思ったから」
「二人、とも……」
「じゃ、そろそろお邪魔虫は退散するから」
「また来るね、真帆っ」
芽衣と怜奈が去って、その場に取り残されたわたしと狩野くんの間には、今までにないほど重たい沈黙が訪れた。
なんということだ。心の準備も一切ないまま、また、狩野くんと顔を合わせることになるなんて。
呆然として言葉を発せないでいるわたしに、彼が、恐る恐る近づいてくる。
「……真帆。さっきのが、本音だと思って良いよね?」
「え、と……」
「諦め悪くて、ごめん。でも……、あんなの聞いたらさ、違ったとしても勘違いするよ。それに……もう、これ以上は、後悔したくないんだ」
気がつけば、わたしは、狩野くんの腕の中に閉じこめられていた。
「嫌なら、つき放して」
やさしい温もりに、ドキドキするのに安心して、いっぱい涙が流れた。悲しくてじゃない。うれしくて、ずっと求めていた場所だって心が叫んでる。
狩野くんは、ズルいよ。こんなの、拒絶できるわけないじゃん。
泣きながら、彼の背中に腕を回した。
折角、離れようって決めて、歯を食いしばってたのにさ。一度顔を見たら、どうしてそんなことを思えたのかわからないほど簡単に決意が揺らいで、愛おしくて、手放せなくなる。
「ねえ、狩野くん……。我がままを、言っても良い?」
「もちろん。なんでも聞く」
「わたしね、もう、そんなに長くないって……なんとなく、わかるんだ。狩野くんを、苦しめることになっちゃうと思う。それ、でも……わた、しは」
「うん……っ」
「狩野くんと……、最期まで一緒にいたい。……死にたくなんて、ないよぉ」
抱きしめてくれる腕に、力が、より一層こもった。
「もちろんだよ。……その言葉を、ずっと待ってた」
彼の顔が近づいてきて、唇に、やわらかいものが触れた。
ほんのすこし触れ合うだけの、羽根のようなキス。
初めてのキスは、甘く、涙の味がした。
✳︎
狩野くんは、約束どおり、ほとんど毎日学校帰りにわたしの病室へと通ってくれた。部活とか学校行事とか色々とサボっていそうだけど、あえてなにも言わなかった。今このときだけは、彼の時間を、できる限りわたしのものにしたかった。自分にそんな独占欲があったことも、狩野くんを好きになるまでは知らなかった。
時おり、芽衣と怜奈も一緒に病室へ顔を出してくれて、賑やかな日々を過ごしている。
痛みが激しく、苦しみだけが続いて、朦朧としているだけの日が多くなっているけど、わたしは最期まで抗うって決めた。
寄りそってくれる全てのひとと、一日でも長く同じときを過ごして、できる限りの愛を返すために。
「最近の真帆、穏やかな表情をすることが多くなったわね」
「そう……?」
お母さんは、横たわっているわたしの手を握りながら、弱々しく微笑んだ。
「そうよ。毎日、真帆のお見舞いに来てくれてる、かっこいい男の子のおかげかしら」
「うん、そうなの。……あのね、お母さん。わたし……、今、すごく幸せ、なんだ。心からの、本音だよ」
「……真帆」
「だから、お母さんは、もう……自分を責めないでね。間違っても、わたしを……かわい、そうな……子だったとは、思わないでね」
お母さんは、大粒の涙を流しながら、しっかりとうなずいてくれた。
「真帆が、あの子と出逢ってくれて、本当に良かったわ。中学時代から、すっごく仲が良さそうだったものね」
心臓が、バクリと大きな音を立てた。
「中、学……?」
「あれ……。そうじゃなかったかしら? 中学時代に、絶対にこのライブに一緒に行きたいひとがいるから、どうしてもペアチケットを買ってほしいって私にせがんだことがあったでしょ? そのライブに一緒に行ったのも、彼だったんじゃないの?」
なにそれ、なにそれ、なにそれ。
わたしと狩野くんは、高校じゃなくて、中学時代にすでに出逢っていたの? それも、お母さんに頼んでライブにまで一緒に行くほど特別な仲だった?
それなのに、どうしてわたしは、そんな大事なことを全部すっかり忘れてしまっているの。
疑問と、胸騒ぎとが止まらない。
とにかく、狩野くんへ、今すぐ事の真相を聞かないと。
「……っっ。痛いっ! 痛いよ……っ、苦しい……っっ」
「真帆っ!!! 待ってねっ、今すぐにお医者さんを呼ぶから!!」
だけど……、急激に襲ってきた猛烈な痛みが、今までにないほど激しくて。あまりの辛さに、意識を保っていることもできなかった。
*
「真帆っ。真帆っっ!!!」
次に目をさましたとき、ぼやけた視界へ最初に飛びこんできたのは、泣き腫らしたような顔の狩野くんだった。しっかりと、手を握ってくれている。お母さんも、お父さんも、お医者さんも、みんな強張ったような顔で、わたしを見つめてた。
「狩野、くん……?」
「真帆……。もう一回、目覚めてくれて、本当に良かった……っ。もう、三日も、意識を取り戻さなかったんだよ」
「そっ、か……」
狩野くん、と自分で呼んでおいて、なぜだか違和感を覚えた。
そうだ。
中学時代のわたしは、彼のことを、こんな他人行儀な呼び方はしていなかったからだ。
「りっ、くん。わたし……、狩野くんの、こと……りっくん、って呼んでたよね?」
彼の瞳から、大粒の涙が流れたとき、あぁ間違っていなかったんだなってホッとして頬がゆるんだ。
「……わたし……、りっくんと、スコープの、ライブに行ったことがあった、んだね……? なんで、かなぁ……ずっ、と、忘れていて、ごめん……ね」
「無理に喋らなくて良いよ!!」
「しゃべ、るよ。もう、時間ないから」
「嫌だっ。待ってよ……っ、オレ……、まだ、真帆にほんとのこと言ってない」
大丈夫。大丈夫だから、泣かないで。
りっくんの想いは、ちゃんと伝わっているよ。
記憶は、相変わらず滲んだ絵具みたいにボヤケている。だけど、一番大事なことだけは、思い出せた。全てを忘れたまま、最期を迎えることにならなくて本当に良かったな。
わたしとりっくんは、中学時代に出逢っていたんだよね。
ぜんぶを思い出せなくても、言葉にしてもらわなくても、不思議なほど信じられる。
きみは、最初から最後まで、わたしのためを想って行動してくれたこと。
わたしの記憶が欠けているのは、その行動が関係しているということ。
今この瞬間一緒にいられるのは、きみが、奇跡を起こしてくれたからなんだってこと。
「今まで、あり、がとう……。大好き、だよ」
わたしは大好きなひとたちに見守れながら、これから永久の眠りにつくとは思えないほど安らかな気持ちで目を閉じた。
***
一人、太陽を反射してきらきらと光る蒼い海を眺めながら、ぼんやりと思索にふける。夏真っ盛りの海水浴場は、カラフルな浮き輪と、浮ついたひとの群れで騒がしい。
「そこのイケメンのにーちゃん、一人? ヒマなら、あたしたちと遊ばない?」
「あー、すみません。……そーゆー気分じゃないんで」
ビキニの姉ちゃんに話しかけられても、心は微動だにしない。
オレは、なるべく誰にも話しかけられないように、人気のない岩場のほうへとやってきた。
夏休みに入って数週間が経ったけど、なんもしたいことが浮かばなくて。このまま家にいたんじゃ身体が腐りそうだと思って、唐突に海までやってきた。
久しぶりに海が見たいという、ただそれだけの理由で。
でも、本当はこんな風に一人で眺めるんじゃなくて、真帆と一緒が良かったなぁ。
「……なぁ、真帆。オレがしたことに、意味は、あったのかな」
大好きだった少女、澤田真帆は約一か月前に脳腫瘍で命を落とした。
過去にさかのぼってやりなおしても、結局オレは、真帆が病気で命を落とす未来を変えることまではできなかった。
気まぐれな神さまから、やりなおしのチャンスを与えられたにも関わらず、オレは無力だった。
真帆と、オレの本当の最初の出逢いは、中学一年生のとき。
狩野家の家庭環境は、歯に衣着せずに言えば、ずっと最悪だった。
オレのものごころついたときには、親父と母親が顔を合わせるたびに、毎日シャレにならないほどの大喧嘩をしていたから。
二人の一人息子だったオレは、一人で、二人分の愚痴を受け止めつづけた。親父は母親の悪口を、母親は親父の悪口を、毎日オレへと投げつける。いっそのこと早く離婚すれば良いのに、中々、踏ん切りがつかない二人へ苛立っていた。そんな二人を見て育ったから、一度は結婚を誓いあうほどの仲になって家庭と子供まで作ったのに、崩壊すんのはあっけないもんだなって冷めた恋愛観が形成されていった。
不満がたまって限界を迎えていた中学入学当初、オレはグレて荒れまくっていたので、学校で誰かと馴れあう気もなかった。
両親の仲が良く、家でなんの苦労もせずにのうのうと生きているであろう周囲の生徒たちが、全員妬ましくて仕方がなかった。
教室の休み時間も、わざとイヤフォンを見せびらかすように耳につけて、誰にも話しかけられないように警戒していたほどだ。
でも……、真帆は、オレの作った高い高い壁も、やすやすと乗りこえてしまう女の子だった。
『狩野くんって、音楽が好きなの?』
『……は?』
『いつも、イヤフォンをして音楽を聴いてるでしょ? なんの曲を聴いてるの?』
最初は、苦労のくの字も知らなそうな顔で、幸せそうにヘラヘラ話しかけてくる真帆にイラついた。明るくて、友達にも教師にも愛されていて、太陽みたいに明るい子。きっと家族からも、めいっぱい愛されて育っているに違いない。
毎日、ゴミ箱のように汚い言葉を投げつけられているオレとは全く違う、きれいな世界で生きているひと。自分は誰からも愛されると確信しているからこそ、オレみたいな一匹狼にも、ためらいなく話しかけてくるんだろう。
あまりに眩しくて、目が焼け爛れそうで、オレは彼女から目をそらした。
『ベツに。お前に答える義理なんてねえし』
『そっか。でも、わたしはなんの曲を聴いてるのか気になるから、また話しかけにくるね』
『…………はあ? お前、いまのオレの話、聞いてた?』
『聞いてたよ。でも、わたしは音楽聴いてるひとがいると、どうしても気になっちゃうの。ウザくて、ごめんね?』
真帆は、その言葉通り、めげずにオレへと話しかけてきた。
最初はヘンな女子だと思っていたのに、段々、無視しきれなくなっていって。
仕方なく、流星スコープというバンドが好きだと明かしたら、真帆が跳ね上がりながら『わたしも!』って喜んだから、柄にもなく、運命ってやつを感じてしまった。
最初はバンドの話で盛りあがっていたけど、すこしずつ、家庭環境の話もするようになった。
『昨日も、両親が、深夜まで怒鳴りあっててさ。オレが寝てる部屋まで響いてくるから、眠れねえんだよ……。いっそのこと、一人暮らししたい。そんな金ねえけど』
『狩野くんは……、毎日、すごく大変な思いをしてるんだね』
『……ごめん。こんな話、されても困るだけだよな』
『ううん。ねえ、狩野くん。わたしのことは、いつでも、狩野くんの気持ちのゴミ箱にして良いからね』
『はあ?』
『狩野くんが、毎日ご両親の鬱憤を受けとめてるなら、狩野くんにも、鬱憤を受け止めてもらうひとが必要だと思う。わたしには、聞くことぐらいしかできないけど……、吐き出したくなったらいつでも言ってね』
夕陽を浴びた真帆の笑顔に見惚れて、彼女への愛おしさがあふれた。
オレが、嵐のような中学時代を乗りきれたのは、真帆がいたからだと断言できる。彼女が、もう耐えられないと思ったときに、いつでもオレの呪詛を受け止めてくれたから。
根本的な状況は変わらなかったかもしれないけど、言葉に出して吐き出させてもらえたことで、オレはたしかに救われていた。
真帆は、家のことで自暴自棄になっていたオレを励ますために、サプライズで流星スコープのライブに連れていってくれたこともあった。
『どうしても、りっくんと一緒に、このライブに行きたかったんだぁ~!』
自分の誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントを前借して、親にねだり、ペアチケットを買ってもらったのだと。
憧れてるバンドの生のライブに心の底から感動して、興奮冷めやらぬまま、ライブ会場でおそろいのストラップも買った。
こんなにやさしくて、他人想いな彼女のことを、愛さないわけがなかった。
真帆は、愛なんて意味がないとひねくれきっていたオレのことを、完ぺきに変えてしまった。
中学を卒業するころ、やっと両親が離婚してくれて、オレは父親に引き取られることになった。耐え忍んでいた日々が終わり、やっとひと息つけたとき、ようやく真帆に告白する踏ん切りがついた。
頬を染めながら告白を受けいれてもらえた瞬間は、飛び上がるほどうれしかったけど、オレは高校に入学してすぐに絶望の底に叩き落とされた。
『ごめんね、りっくん。……わたし、ほかに、好きなひとができたんだ。別れてほしい』
こんなにもひとの心を奪っておいて、あっさりと他人を好きになり別れ話をしてきた真帆を、殺したくなるほど憎んだ。
表面上はものわかりの良い男を演じて『わかった』と頷いたけど、納得できるわけがない。なにが悪かったのかと思いつめ、彼女に気づかれないようにストーカー手前の行動までとったが、ついぞ、真帆の心を奪った憎き敵の情報を得ることはできなかった。
そして。
高校入学から約二か月ほど経ったころ、彼女は高校へ来なくなった。
その一か月後。
オレは、澤田真帆が脳腫瘍でこの世を去ったと、中学時代の同級生から聞いて知った。
悲しくて、苦しくて、やりきれなくて、腹が立って仕方がなかった。
なにに一番腹が立ったかって、真帆から別れ話をされたときに本音でぶつからず、かっこつけたいがために、ものわかりの良い男を演じたバカな自分にだ。彼女に真実を打ち明けてもらえなかった、不甲斐なくて、頼りない自分に。
真帆に、もう一度、会いたい。
願いが叶ったら、今度は、絶対に最期までそばにいる。
壊れそうな心で、何度も何度も、祈った。
あんなにやさしい子を十五歳という若さでこの世から去らせた世界に、神なんていやしないとわかってる。それでもオレは、なにかに縋らずには生きられなかった。
「私は、きみのしたことに、意味はあったと思う」
グラスに注いだ水のように透きとおった声に、意識が、思考の海から現実へと引っ張り上げられる。
目の前に、オレにチャンスを与えた、当の神さまが立っていた。
誰もが振りかえるほど綺麗な顔をした、男か女かもわからない、黒ずくめのマントのひと。
絶望のあまり高校にも通えなくなり、昼間から公園で虚ろにぼんやりとしていたオレの前に突如現れた、自称、神さま。
「驚いたよ。彼女は、私が彼女の周囲も含めて完全に消し去ったはずのきみとの記憶を、わずかにだが取り戻した。記憶の操作は、完ぺきだったはずなのに」
彼女だか彼だか知らないが、目の前のこいつが、超常的な存在であることは信じざるをえない。実際にオレを過去へと戻し、生きている真帆に再び逢わせてくれたのだから。
過去へ戻すための代償として提案されたのが、真帆から、オレに関わる記憶の全てを消すことだった。
真帆の中から自分と過ごした三年間の記憶が消えてしまうことに、躊躇いがなかったわけじゃない。
それでもオレは、もう一度彼女に会って、今度こそ最期の瞬間まで向き合いたかった。
「……結局、真帆は死んじまったけどな」
過去に戻すなんて、そんな大層な力があるのなら、真帆の命を救ってくれよ。
オレは、この三か月間、泣きたくなるほど幸せだった。
真帆の苦しそうな姿を目の当たりにしてキツいときもあったけど、後悔は全くしていない。
だけど、真帆は?
真帆にとって、この三か月は、どうだったんだろう。
考えはじめると、怖くなる。よく考えたら、オレは真帆から大好きなバンドのライブに行った記憶を奪い去っただけなんじゃないかと思うと、罪悪感で息が止まりそうなほどだ。
オレは、彼女のために、なにかできたのか?
一番、答えてほしい相手は、もうこの世にいない。
「……なぁ、神さま。なんで、オレを代償付きで過去へと戻すなんてクソ面倒くさいことをしてくれたんだ?」
感謝こそすれど、理不尽に責めたい気持ちをどうにか堪えながら問いかけると、奴は無表情のまま答えた。
「さあね。気まぐれだよ」
「……そーかよ」
「強いて言うなら、興味があったんだと思う」
「興味?」
「ひとの愛が、神の力に勝る奇跡を起こす瞬間を、目の当たりにしてみたかった」
神さまは、オレに向かって、口角をほんの少しだけ持ちあげた。
「どうせ無理に決まってると思いこんでいたけど、目の当たりにしてしまったさ。きみたちの愛が、奇跡を引き寄せたんだろう。それに、彼女は、きみがやりなおす前の過去よりもずっと幸せそうだったよ」
運命は、変えられなかったかもしれない。
それでも、オレは目の前の神さまの言葉に、救われたような気持ちがした。【完】
「玲奈は、いまの彼氏とどうやって付き合ったの~? まず、どっちからの告白?」
「智くんからー。修学旅行の自由行動のときに告られたんだっ」
「えー、なにそれいいなあぁ~~! はー……あたしも、いつまでも眺めてるだけじゃなんにもならないよなぁ」
目の前の玲奈と芽衣に限ったことじゃない。耳を澄ませると、校内の至るところに咲いている。
でも、わたしは恋バナになるといつも口を挟めなくて、無難に頷くことしかできない。
恋に興味がないわけじゃないんだ。
むしろ、強く憧れている方。
でも、手を伸ばしちゃいけないもの。
恋バナは、今のわたしにとって、陽射しのきつい夏場の太陽みたい。
「まー、芽衣はまだ想いを自覚したばっかりなんだし、焦ることはないんじゃない? タイミングも大事だしさっ」
「出た出た、彼氏持ちの余裕発言~~」
「あはっ。ちなみに、真帆はどーなのよ? 気になるひとはできた〜?」
マスカラに縁取られた四つの瞳に一斉に見つめられて、ぎくりと顔が強張る。
「えっと……、わたしは、まだ特に見つかってないかなぁ」
「えーー? 真帆かわいいのにー、もったいなぁい」
「好きなひとがいないなら、どんな男子がタイプなの? やっぱり、二組の狩野くんみたいなイケメンとかー?」
「狩野くんって軽音部に決めたんだっけ? マジでかっこいーよねぇ、顔小さいし、背も高くてさぁ」
二組の狩野くんのことは、流石に知ってる。
狩野律人。すらりとした長身と切れ長の瞳が印象的な、遠目からでも目立つ男の子。この前すれちがったとき、ギターケースらしきものを背負っていたから、よく覚えている。
良いなぁ、軽音部。
わたしも、高校に入学したら、本当はバンドをやりたかったんだけどな。
ぼんやりしていたら、玲奈と芽衣の視線を感じたので、慌てて答えた。
「狩野くんは……、モデルさんみたいでかっこいいとは思うけど、それだけかなぁ」
「まー、実際、あーいうイケメンは観賞用にしとくのに限るかもねぇ。まだ高校に入って一ヶ月なのに、もう二人に告白されたらしいし」
「ねーねー。そーいえば、智くんが彼女ほしいって言ってる男友達がいるって言ってたよ! 紹介できる子いない? って聞かれたんだよね」
「お、いーじゃんいーじゃん! 怜奈の紹介なら、奥手な真帆も安心なんじゃない?」
うわっ。この流れはマズい!
「そ、それよりさっ! 二人とも、『星空スコープ』の新曲は聴いた?」
「え……? あー……、まだ聴けてないや」
「すごくおしゃれで、素敵な曲だったの! イントロのベースが、すっごくかっこよくてね……!」
「ふうん。後で聴いてみる」
流れ出した微妙な空気をさえぎるように、昼休みの終わりを告げるチャイムが鳴ってくれて助かった。
自分の席に戻ったとき、口から小さなため息がこぼれ出た。
はぁ……さっきのは、流石に不自然だと思われたかな。明らかに話をそらそうとしたってバレたよね。
脳裏から、芽衣と怜奈の鼻白んだような顔が離れてくれない。
でも……、仕方ないじゃん。
『わたしはあと三か月しか生きられないから、恋愛してみようとは思えない』なんて、馬鹿正直には打ち明けられないよ。
*
「ただいま」
「お帰り、真帆……! 体調はどう? 学校で気分が悪くなったりしていない?」
「ん。……今日は大丈夫だったよ」
「本当に?」
「本当だって」
「お母さん、真帆のことが心配で仕方ないのよ。心配して言っているんだからね。ちゃんとわかってる?」
「わかってるってば!」
お母さんは眉根を寄せて、悲しそうにうつむいた。
青白い顔に、どことなく痩せこけた頬。髪にも艶がない。すこし前に会社で働くのを辞めてから、一気に老けこんだような気がする。
泣き腫らしたような瞳に見つめられて、胸がきゅっと痛くなった。
「……部屋に、行くね」
重苦しい沈黙に耐えきれなくなって、自分の部屋へと逃げ込む。
そのままドアを背に、へたりこむように座りこんだ。頭痛までしてきた。
ここ最近、うちに帰ると毎日こんな感じで、精神的に疲弊している。
でも、お母さんばかりを責めるわけにもいかない。
お母さんをあんな風にしてしまっているのは、わたしなんだから。
「余命、三か月……」
今でも、信じられていない。
一週間前の病院での出来事は、悪い夢だったんじゃないかと思う。
前兆は、高校に入学した頃に出始めた。
朝起きたときに、頭痛がするようになったこと。
最初は単なる頭痛だと思っていたので、数週間は市販薬で誤魔化してきたけど、症状はどんどん酷くなっていった。
手足が痺れて思うように動かせなかったり、片目が見えづらくなったり。『ただの頭痛』で誤魔化すには流石に無理があると思いはじめて、お母さんに相談したら、すぐに近所のクリニックに診察を受けにいくことになった。
病院に行けば安心できると思っていたのに、結果はその真逆だった。
早急にもっと大きな病院で診察することを勧められ、大学病院を紹介されたんだ。
そして、CT検査、MRI検査と二度大学病院を訪れることになり、待っていたのは自分が想像の何百倍も深刻な状況に置かれていたという現実。
『脳に悪性の腫瘍ができています』
『娘は、助かるんですか!?』
『……残念ながら、澤田さんの腫瘍は場所が非常に悪く、進行がかなり進んでいるため手術も難しい状態です』
お母さんとお父さんが泣き崩れる傍ら、わたしだけが、ポカンとしてた。
悲しい、苦しいという以上に、ただただ自分の身に起こっていることだと信じられなかったからだ。
だって、ここに来る前まで、わたしはひとよりもすこしバンドが好きなだけの平凡な女の子だったのに。
やっと受かった高校に入学して、同じクラスに新しい友達ができたばかりのところで。ゴールデンウィークも明けて、本格的に始まる部活動を楽しみにしていたところだったのに。
全部諦めなきゃいけないかもしれないなんて、ウソだと思いたくて当然でしょ。
だけど。
悪い夢は一向に醒めてくれなくて、わたしは、目の前の医師へ現実を問いかけることしかできなかった。
『わたしは……、あと、どのぐらい生きられるんですか?』
『この進行状況ですと……、三か月程度だと覚悟してください』
心臓が、生きてきた中で、一番大きな音を立てた瞬間だった。
あと三か月。
あまりの衝撃に、その後、病院でなにを告げられてどんな会話をしたのか正直あまりよく覚えていない。
ただ、身体を楽にするために、助けてもらうために向かった病院で突きつけられたのは、十五歳の自分が向き合うにはあまりにも重たすぎる現実だったということだけだ。
*
自分があと三か月しか生きられないと知ったら、みんな、残りの人生でなにをしようと思うのだろうか。
本当は、今すぐに高校を辞めてしまっても、なんの問題もない。
余命宣告を受けたあと、お母さんとお父さんには、高校を退学することを勧められた。
『こんな状態で、学校に通わせるのは心配よ。お母さん、会社を辞めてうちにいるようにするから、うちで安静にしていたら? 真帆が出かけたいときにはいつでも付き添うし』
『真帆、そうするのが良いんじゃないかな。無理して高校に通うのは、お父さんとしても心配だよ』
お母さんとお父さんの涙ながらの提案に、わたしは頷けなかった。
『お母さん、お父さん。安静にしていても、していなくても、わたしは三か月後に死ぬんだよ』
『真帆……! そんなこと、軽々しく口にしないで!!』
『でも、お医者さんはそう言ってたよね』
家族三人そろっているのに、リビングダイニングがあれほど重苦しい沈黙に包まれたことはかつてなかった。
だけど、それでも意志を曲げたくなかった。
『……二人ともごめんね。でも、わたしは、可能な限りで高校に通いたいと思ってるんだ』
『真帆……』
『無理はしない。限界だって思ったら、うちに帰ってくる。だからそれまでは……、お願いだから、高校に通わせて』
あと三か月しか生きられないと突きつけられたときに、心に強く浮かんだ願いは、普通の高校生活を送りたいということだった。
わたしだって、みんなと同じように、高校生を体験してみたい。
死を意識する前までは、正直、高校に通えることも当たり前だと思っていた。
こうなってみて初めて、わたしにとっての今までの当たり前は奇跡だったのだと気がつくなんて、皮肉なものだ。
お母さんとお父さんは最終的に『真帆の意志を尊重する』と言って、体調が安定している間は、高校に通うことを承諾してくれた。
学校でわたしの病気のことを知っているのは一部の教師だけ。本当は誰にも知られたくなかったけど、それだと緊急時にとっさの対応ができないからと、お母さんが譲らなかった。
代わりに、生徒には、誰にもこのことは言っていない。
高校に入学して、最初に仲良くなった芽衣と怜奈にも打ち明ける気はない。
話してしまえば、良くも悪くも『余命三か月』の子だという色眼鏡で見られてしまうから。わたしが逆の立場だったら、話されたところで、接し方がわからなくなると思う。
「ねーねー、真帆。今日の放課後あいてないー?」
「どうして?」
「あたしと怜奈、二人とも、部活がオフなんだ。でさっ、今日からルタバの新作フラぺが始まるの!」
「まるごと苺味だってさ、ちょー美味しそうじゃない? 真帆も飲みにいこうよ」
良いね、美味しそう! と言いかけたそのとき、鋭い頭痛がして、喉まで出かかった言葉をのみこんだ。
「ごめん……。わたしは、用事があるから遠慮しとくね」
「えーー、そっかぁー……。じゃあ、次のオフのときにでも」
「でも、次のオフが重なる日を待ってたら、まるごと苺味は終わっちゃうよ」
「あっ。わたしのことは気にしないで良いから、二人で飲んできなよ! 明日、感想を教えてね」
「んー……。わかった。じゃー、真帆は次の機会にでも!」
「ありがとう。じゃあ、また明日ね」
微妙に納得していない顔の二人から逃げるように、スクバを肩にかけて、お手洗いへ逃げこんだ。
個室へ入って一人きりになったとき、ホッとしてため息が出てきた。
今日はあんまり薬が効いていないな。頻繁に頭痛が起こるし、吐き気もする。
あのまま無理をしてカフェに付き合って、二人の前で倒れたりしたら、悲惨なことになっていただろう。迷惑がかかるのはもちろんのこと、最悪、わたしの病気のことまで知られてしまうかもしれない。それだけは避けたかった。
友達と放課後カフェへの憧れもあったから、とても残念だけど……。
病気が、憎い。わたしが望む普通の高校生活を、ことごとく邪魔してくる。
ポーチから取りだした錠剤を飲みこみ、頭痛を落ちつかせるように深呼吸していたら、個室の外から誰かの足音が聞こえてきた。
「さっきの真帆の態度、どー思う?」
「んー……。ぶっちゃっけ、ほんとに用事があるのか微妙なところだよね」
胸に、氷の針を何百本も叩きこまれたような心地がした。全身がぞくりと冷える。
芽衣と怜奈の声だ。
「こんなこと言いたくないけどさ……、真帆って、お腹の底でなに考えてんのか、よくわかんないよね」
「そうねー。恋バナも、自分の話だけは誤魔化すしね」
「好きなひとが本当にいないのか、あたしらに隠してるだけなのか。五分五分って感じ」
心臓が、痛いほど激しく収縮する。
二人の気配が去りきるまで、わたしは個室の中で微動だにできなかった。嵐が過ぎ去るのを待つような心地で、ひたすらに息を殺した。
芽衣と怜奈に、あれほど不信感を抱かせていたなんて。
全く気がついていなかったわけじゃない。病気のことを隠すたびに、会話が不自然になっていたことは気にしていた。実際、わたしが二人に、好きなひとどころではない重大な問題を隠していることは事実だ。
だけど、ああもハッキリと嫌悪感を露わにした言葉を聞いてしまうと、心が折れそうになる。いや……、もうとっくにパキンと真っ二つに折れてるかも。
家に帰る気力すらもなくしたわたしは、お手洗いを出て、フラフラとした足取りで人気のない教室に入った。誰の机かもわからない席に座り、充電切れのロボットみたいにパタリと寝そべる。誰かが忘れ物を取りに入ってくるかもなんて、気にする余裕すらもなかった。
聞こえてくるのは、グラウンドを駆け回るサッカー部の掛け声と、吹奏楽部が練習で出している木管と金管の音だけ。
放課後、自分の好きなことへ一生懸命に打ちこめるみんなが、羨ましい。
友達と、当たり前のように、放課後に遊びにいけることも。
誰かに片想いをして、一喜一憂することも。
今のわたしには全てが眩しすぎて、直視すると目が焼け爛れそうだから、視界に入れないようにぎゅっと目をつむる。
「わたしだってさぁ……、恋、してみたかったよ」
普通の高校生活を送りたいと願ったから、この場所にいるのに。
何一つうまくやれていない。
やっぱり、無謀なことをしているんだろうか。お母さんとお父さんの言うように、退学をしたほうが良いのかな。
わたしは、すでに普通の女子高生とはかけ離れているんだから。
「じゃあ、オレと付き合って」
…………へ?
慌ててガバリと顔を上げたら、切れ長の瞳とばっちり目が合って、どうして良いのかわからなくなった。
軽い空気感を含んだマッシュヘアは、こうして間近で見ると触ってみたくなるほどサラサラで。透きとおるような肌、鼻筋の通った高い鼻、うるおいのある薄桃色の唇を見ていたら、本当にイケメンだなぁというバカみたいな感想が頭をよぎってしまった。
この、すさまじく顔が良い上に、背が高くてスタイルまで良い男子のことは、わたしも存じている。二組の狩野律人くんだ。芽衣と怜奈の間でも、新入生随一のイケメンとしてよく話題に上がっている、あの狩野くん。
その彼が、わたしに向かって「付き合って」とのたまったような気がするのは、聞き違いだろうか。
「ええと……なんて?」
「だから、オレと付き合ってほしいって言ったんだけど」
いや。いやいやいや。全く意味がわからない。
目をぱちくりとさせながら、お互い、見つめあうこと十数秒。
わたしは、状況を理解できないまま、頭を下げた。
「ええと……、ごめんなさい。お付き合いすることはできません」
「なんで? 澤田さんは、恋がしたいんじゃねえの? さっきそう言ってたじゃん」
じとりと、こめかみの辺りから汗が伝る。
いま澤田さんって言ったよね? なんで狩野くんに存在を認知されているの? 別のクラスの男子に存在を把握されるほど、高校で目立つことをした記憶はないんだけど……。
それにしても、狩野くんはとてもヘンなひとらしい。
恋がしたいというわたしの独り言をたまたま聞いていて、「じゃあ、恋してみる?」と気軽に声をかけてしまうフランクさ。いや、フランクとかいう次元で片付けられないよ。端的に言って、どうかしている。おかしいもん。
でも、いくら変人だからといって、流石にわたしの事情に巻きこむわけにはいかない。
「……したいと思っているのと、実際にしてみるのとでは、全くベツの話ですから。とにかく、わたしに恋は無理なの」
「できるよ。恋する相手がいれば、成立するし」
「しつこいよ! さっきから、なんなの? イケメンだから、とりあえず付き合おうと言っておけば女子はうなずくとでも思っているんですか!?」
思わず語気を荒めたら、狩野くんは傷ついたような顔をした。
「違うよ……。澤田さんがそう思うのも無理はないかもしれないけど、オレは……澤田さんだから付き合いたいと思ってる」
そう言う彼は、思いのほか切実そうな瞳をしていて、わたしは口をつぐんだ。
狩野くんは、口ごもったわたしを真っ直ぐに見つめながら、震える声で告げた。
「ねえ。澤田さんが、自分に恋は無理だと思っている理由は……病気のことが、原因?」
時が、止まったような気がした。
余命宣告を受けたのと同じぐらいの衝撃に襲われて、息の仕方もわからなくなる。心臓が荒れ狂って動悸が凄まじい、胸を突き破ってしまいそうなほどだ。
どうして……?
なんで、今が初対面の狩野くんが、わたしの病気のこと知っているの!?
「ちょ、澤田さん大丈夫……? 顔、真っ青じゃん。ちょっと落ちついて」
「はぁ、はぁ……。落ちつけるわけがないでしょ!!」
「あー……。ごめん。今のは、タイミングをミスったオレが悪かった」
「なんで? どうやって、そのことを知ったの!? まさか、このことを知っている先生から聞いたとか……」
「違う、違うから! すぐには事情を話せないけど、誰かが澤田さんの事情を安易に口外したわけじゃない。そこは保証する。とりあえず深呼吸しろ」
狩野くんは、すっかり怯えきったわたしをなだめるように、そっと頭を撫でてきた。
カッと頬が熱くなる。だって、男の子に頭を撫でられるのなんて、初めてだし。
でも……、どうしてか嫌じゃない。それどころか、安心してしまう。
ほぼ初対面の男子に頭を撫でられても、普通は、驚いて嫌な感じがするだけだ。気持ち悪い、触らないでって拒絶して当然なのに。
どうしてわたしは、彼の手を受けいれているんだろう。自分の心の動きに驚いて、戸惑う。
「澤田さん。澤田さんは、どうしてオレがきみの病気のことを知っているのか、知りたいと思っているよね?」
素直に、うなずいた。
「さっきも言ったけど、オレは、きみと付き合いたい。だから、澤田さん。取引をしよう」
「なにを、言っているの……?」
「オレと付き合ってくれたら、なんでオレがきみの病気のことを知っているのか教える」
「なにそれ……」
なんてズルい提案なんだろう。
ここで彼の提案を受けいれなかったら、この先ずっと、モヤモヤを抱えることになる。断ったところで、狩野くんの顔が頭をちらついて離れない未来が見えるもん。
選択肢を与えているようで、与えていない。こんな風に言われたら、誰だって、付き合わざるをえなくなる。
「付き合う。付き合うよ! はい、付き合ったからさっそく教えてくれる?」
「ふはっ、ダメだよ。ちゃんと付き合ってくれるまで教えない」
「なにそれ、詐欺じゃん! ちゃんとってなに、どういう基準?」
「三か月間」
狩野くんは、どことなく潤んだような瞳で、絶句したわたしに告げたんだ。
「三か月間オレと付き合ってくれたら、ちゃんと、真実を打ち明けるよ」
全ての音がフェードアウトして、自分の心臓の音だけが、やけにうるさく感じた。
こうして、わたしと、なぜかわたしの告げられた余命の期間まで知っている狩野くんとの奇妙な付き合いが始まった。
✳︎
昨日起こった出来事は、ぜんぶ夢だったのかな。
それなら、都合が良いや。
いっそのこと、狩野くんとのおかしな出会いよりもっともっと前から、わたしが余命宣告を受けたところから全てが夢だったいうことにできたらどれだけ良いか。
だけど、残念ながら、全て現実だったということを嫌というほど思い知らされた。
「澤田さーーん! 帰ろうぜ」
わたしを悩ませている元凶たる彼の、よく響く明るい声によって。
放課後になったとたん、教室のドアから大声で名前を呼ばれて、まだ残っていた生徒たちの視線がわたしへぎゅんと集まった。
「えっ、狩野くんじゃーん! やば! やっぱり、かっこいいーー」
「てか、澤田さんのこと呼んでなかった?」
「なんで? 二人ってどういう関係?」
狩野くんがわたしの席の方までやってこようとするので、急いでスクバを肩にかけて彼を教室から押し返しながら廊下へと出た。唖然としている芽衣と玲奈に言い訳をする間もない。
「ちょ、ちょっと待って、狩野くん! いきなり教室にやってこないでよ!」
「え、なんで? 付き合ってるんだし、このぐらいふつーじゃね?」
周囲を気にしない音量で話す狩野くんに、会話を聞いていた子たちから小さな悲鳴が上がる。あの二人付き合ってるの? なんで? いつから? てかあの女子誰? という地獄のような囁き声が伝播していき、今すぐ消えたいような気持ちになった。
「狩野くんは、やたらと目立つの! そもそも、付き合ってるなんて、絶対にみんなに知られたくなかったのに~~っ」
「ごめんって。でも、こーでもしないと、澤田さんはあっさりオレのことを無視して帰りそーだったから」
……図星だ。
昨日成行から彼と付き合う約束をしたものの、まだ、心は全く追いつけていないわけで。わたしは狩野くんのことを好いているわけでもなければ、正式に彼氏と認めたわけでもない。
付き合う約束をしたのは、あくまでも、なぜ彼がわたしのトップシークレットを知っているのかが気になったから。ただ、それだけだ。それだけのことが重要な問題なんだけど。
「図星かい、そこで黙るなよ」
「……とりあえず、外に出たいです」
「ん、りょーかい」
学校の外に出ると、ぽかぽかとあたたかい陽気に包まれた。
澄み渡る青空と、爽やかな新緑が目に眩しい。
時折、下校中の生徒に視線を向けられて、ひそひそ話をされているような気がするけど、こうなったらある程度は開きなおるしかない。どうせ明日には、あの狩野くんが一組の冴えない女子と付き合ったという噂が広まりまくっているんだろうし。
「澤田さん、すごくやるせなさそうな顔してる」
「誰のせいだと思っているの」
「んー……。オレ?」
「自信満々に言われるとムカつく」
「ごめん。これでも、ちょっと焦りすぎたなって反省はしてるよ」
しゅんと眉尻が下がった。
わかりやすく落ちこんでいる素直な反応に、毒気を抜かれる。
「でもさ……、オレは、澤田さんの願いを叶えたいんだよ。それと、一日も無駄にはしたくない」
「願いって……」
「恋したいんでしょ? だったら、一日でも早くオレのことを好きになってもらわないとじゃん」
ぶわりと顔に熱が集まった。
狩野くんが言ったからじゃない。真剣にそんなことを言われたら、誰からだとしても顔が熱くなる。
彼は、どうしてわたしのことで、こんなに必死になってくれるんだろう。問いかけてみたところで、病気の件と同じように煙に巻かれると思ったから、口にはしなかった。
高校の最寄りの駅前までやってくると、狩野くんは足を止めて、わたしの顔をのぞきこんだ。
「澤田さん。今日、体調は大丈夫?」
「うん。むしろ、結構良い方だと思う」
「それは良かった。じゃあ、これからデートしない?」
「デ、デート……!?」
「そんなに驚く? 付き合ってたら、当たり前じゃねーの」
「そ、そうかもしれないけど、いきなり……? わたし、狩野くんのこと全然よく知らないし、男の子と二人きりで出かけたこともないし、その、心の準備がまだできてないというか……」
しどろもどろになっていくわたしに、狩野くんはうれしそうに笑った。
「オレが、澤田さんの初めてのデート相手になれるってこと? なにそれ。すげーうれしい」
「なっ……!」
「オレのことを知らなくても、なんの問題もないよ。だって、互いのことを知るために、デートするんだろ」
「そっか……?」
「それとも、いきなり出かけたりしたら、ご両親が心配する?」
「それは、連絡を入れておけば大丈夫だよ。そんなに夜遅くならなければ」
「もちろん、そのつもり。やった! ねえ、澤田さんはどこに行きたい? やりたいことはある?」
「うーん……。じゃあ、カラオケとか?」
答えてから、あれ? 答えを間違えたかも、と焦り出す。
単純に、久しぶりにカラオケで歌いたい気分だったから口にしたんだけど、よくよく考えるとカラオケボックスって薄暗いし密室だ。完全に信頼を置いているわけじゃない異性と初めて二人きりで遊びにいく場所にしては、ちょっと不適切な気も……。
「ごめん、間違え「良いじゃん、カラオケ」」
食い気味で答えた狩野くんは、子供のように瞳をきらきらとさせていた。
マズい、思った以上にノリノリだ……! 早く流れを変えなきゃ、と焦ったのも束の間、狩野くんの意外すぎる発言ですぐに気が変わった。
「澤田さんは、『星空スコープ』の最新曲、もう聴いた? もしかして歌えたりするの?」
「えっ……!?」
「スクバについてるそのストラップ、スコープのグッズでしょ。見て、すぐにわかったよ」
彼が、わたしのスクバにぶら下がっている星型のゆるいマスコットキャラに反応した瞬間、わたしの中の狩野くんが、よく知らない男子から、星空スコープ同志へと一気に昇進した。
「ウソウソウソ……っ! もしかして狩野くんも、スコープファンなのっ?」
「澤田さん、テンション一気に上がりすぎでしょ」
「だって、スコープ好きに悪いひとはいないし! ねえ、ファンなの?」
「ファンだよ。スコープって、スリーピースとは思えない音圧で、すげえかっこいいよな。憧れてるバンド」
「そう、そうなのっ! えーーっ、こんな偶然ある? うれしいなぁ」
「じゃー、カラオケで、スコープの曲一緒に歌おうぜ」
「うんっ!」
スキップしたいような心地で駅近のカラオケ店に向かい、わたしと狩野くんは、宣言通り星空スコープの曲を熱唱しつづけた。
頭の中で危惧していた、ヘンに気まずい空気も、危険な甘い空気もこれっぽっちもない。今この場は、異性とかそんなことも頭から抜け落ちるほど、純粋に星空スコープ好きな二人がはしゃいで歌うだけの楽しい空間だった。
驚くべきは、狩野くんの美声だ。
ずっと高音が続いてテンポも速い星空スコープの難しいメロディを、完ぺきに歌いこなしている。
「狩野くん、すっごいね! 歌うますぎなんだけど! クオリティ高い~~!」
「どや。オレ、スコープの曲をカバーしたくて、軽音部に入ったようなもんなんだよね」
「そうだったんだ! ちなみにパートは?」
「ギタボ担当だよ。澤田さんも、全曲合いの手まで完ぺきだな。ガチファンじゃん」
「まあねっ。中学一年生のときから、ずっと聴いてるし! でも、生のライブを聴きにいけたことはなくて、高校生になったらスコープのライブに通うために、バイトもしようと思っていて……」
言葉が、続かなかった。
代わりに、瞳から涙がこぼれてきた。
学校に通うのはゆるしてもらえたけど、この身体でバイトをするのは諦めた。いつお店のひとに迷惑をかけるかもわからないし、お母さんとお父さんにも猛反対されたから。真帆はお金の心配をする必要はない、無理をするなって。
実際、お金を稼いだところで、わたしにはそのお金から恩恵を受けるための充分な時間ものこされていないのだ。
そうやって納得しようと思ったけど、本音を言えば、バイトもしてみたかった。一生懸命働いて、自分の力でお金を得て、自分にとって価値のあるものに使うこと。
それがどんなことかも知らないまま、わたしは死んでしまうんだ。
「澤田さん……」
嫌だなぁ。せっかく、新たなスコープ仲間を見つけることができて、ひたすら楽しくて幸せな空間だったのに。こんな湿っぽい空気を持ちこむ気なんて、さらさらなかったのに。
狩野くんは、涙を流しつづけるわたしを、苦しそうに見つめている。
急に静かになった室内に、隣の部屋の下手っぴな歌声が遠くから聴こえた。
「ごめ、んね……。なんか、ヘンな空気にしちゃって。えっと……、まだ入れてない曲を歌おうか」
「澤田さん。オレには、気なんて遣わないで」
「……でも」
「オレは、楽しいことだけじゃなくて、澤田さんの背負っているものも共有したいんだ」
狩野くんは、わたしの隣に静かに腰を下ろすと、流れつづける涙をそっと長い指先でぬぐった。
どうしてだろう。昨日も思ったけど、彼からもたらされる温もりは嫌じゃない。狩野くんの指には、胸を覆いつくす悲しみを溶かす魔法でもかかっているみたいだ。
「こんなこと言ってるけど、オレが澤田さんのためにできることなんて、実際はほとんどなんもない。不甲斐なくて、ごめん……。苦しみも痛みも、この指から伝わって、半分にできたら良いのにな」
「ははっ。狩野くんが、そこまでする義理はないでしょ」
「あるよ」
有無を言わせぬ断言に、なにも言えなかった。
切れ長の瞳に、涙に濡れた情けないわたしの顔が映りこむ。
「ねえ、澤田さん。オレを、澤田さんの気持ちのゴミ箱にして」
「ゴミ……? どういう、意味?」
「汚いものは捨てていかないと、ゴミでいっぱいになって溢れちまうだろ。それは、物理的なモノだけじゃなくて、感情も一緒なんだと思う」
感情も、一緒。
彼の話を聞きながら、自然と胸に手を当てていた。
「人間なんだから、プラスの感情だけで生きていることなんてできやしない。苦しい日も、悲しい日も、他人が妬ましくて仕方ない日がある。でも……、日々生まれる負の感情を誰にも吐き出せなくて、自分の胸の内いっぱいにためこんじまう人間も多い」
彼の言うとおり、わたしは今、涙になってあふれるほどの悲しみを胸のうちに押し返そうとした。
「ゴミと違って、気持ちを吐き出したところで、現実自体がきれいになるわけじゃない。しんどい状況は、しんどいままだ。誰に話したところで現実は変えられないから、自分の感情は自分だけでどうにかしようって考える気持ちもわかる。……たしかに、言葉じゃ現実を変えられないのも事実だよ。でも……、それでもオレは、吐き出させてもらえたことで、救われたから」
ドキリと、心臓が跳ねた。
狩野くんの瞳に、見ているこちらが熱くなってしまうような焔が灯っていたから。
だけど、彼は、目の前のわたしを見ているようで見ていない気がした。
まるで、わたしを通して、別の誰かを見ているような。
「狩野くんも……辛いことが、あったの?」
彼は、わたしの問いには答えずに、やさしく笑った。
「……澤田さんは、ただでさえ不安になって当然の状況なんだ。毎日、オレなんかには想像もつかないほど頑張ってる。だから……、オレの前では、頑張ろうとしないで」
止まりかけていた涙が、再びあふれ出す。
わたしは頑張っているのだと、ハッキリ言葉にして認めてもらえたことが想像以上に心に響いて。
よく知りもしない、謎だらけの男の子の前で、ただ泣いた。彼に背中をさすってもらえると、恥ずかしいよりもどうしてか安心の方が勝る。
「ごめ……ん。あり、がと……」
「謝るのも禁止」
「……っ」
しんみりとした空気のまま、カラオケの終了の時間がやってきて、わたし達は無言のまま室内を出た。
外に出ると、空は暮れなずんでいた。こんなに遅くまで遊んだのは、余命宣告を受けてからは初めてだ。
「だいぶ日ぃ暮れてんな。ご両親、心配してない?」
「たぶん、大丈夫だと思う」
……本当は、お母さんからの連絡通知がたくさんきているけど。正直にそう言ったら、狩野くんが恐縮して、今後遊びに誘ってくれなくなるかも。
って、いやいや。わたしってば、なに先のことまで期待してるの。
「今日はありがと! また明日な」
その日、彼は、わたしを家の前まで送ってくれた。わざわざ定期券外の電車にまで乗って。
そこまでしてもらう必要はないと何度も言ったのに、『オレが好きでしていることだから』と言ってきかないから諦めた。
うちに帰ったら、血相を変えたお母さんに「どこで遊んでたの? 体調は大丈夫なの!?」と心配されて、再び現実に戻ってきたような気分になった。十二時の鐘が鳴って魔法が溶けたシンデレラみたいに、この家に帰るとわたしは、余命宣告を受けたかわいそうな一人娘に戻ってしまう。
さっき別れたばかりなのに、また、狩野くんのことが頭の隅に浮かんだ。
狩野くんのそばにいるときは、息がしやすかったんだなぁって。
*
「真帆。単刀直入に聞くけど、二組の狩野くんと付き合ったって、マジなの?」
「なにがあったの? ちょっと前まで、恋愛興味ないって感じのこと言ってたのに、ウソだったってこと? なんであたしらに、ほんとのこと話してくれなかったの!?」
狩野くんとカラオケに行った翌日の昼休み。
チャイムが鳴ったとたんに、芽衣と玲奈につめよられて、わたしはタジタジになっていた。心なしか、二人以外の女子も、この会話に聞き耳を立てているような感じがする。恐るべし、狩野くん人気。
昨日の時点で、こうなることは予想がついていた。
でも、わたしは二人に嘘をついていたわけじゃない。だって、狩野くんのことに限って言えば、当のわたしですら本当に予想外だったんだから。
でも、彼と付き合った経緯をちゃんと話そうとすると、病気のことまで話さなきゃいけなくなる。だけど、またその場しのぎの誤魔化すようなことを言ったら絶対に空気悪くなるし、最悪、嫌われて仲間外れにされちゃう可能性もなくはない。
失敗した。ちゃんと言い訳を考えてくれば良かった。背筋から嫌な汗がダラダラと流れてくる。
結局なにも言えずに心拍数だけを跳ね上げながらうつむいたら、ここ数日で聴き馴染んできた声がわたし達の会話に割って入ってきた。
「澤田さんは、ウソついてないよ」
狩野くんだ。
いつの間にか、一組の教室に堂々と入ってきていた彼が、わたしの代わりに答えていた。
芽衣も、怜奈も、もちろんわたしも、呆気に取られて彼をポカンと見やることしかできなくて。
「オレが澤田さんのことを前々からずっと好きでコクったの。澤田さんには、恋には興味ないからって振られそうだったけど、オレが押して強引に付き合ってもらったんだよ。それで、今は、振られないように必死に努力中ってとこ」
「そう、だったんだ……?」
「そー。ってわけで、ちょっと澤田さんのこと借りて良い? 惚れてもらうのに、必死なもんで」
「あ……。ど、どうぞ?」
「ありがと! 今後も、ちょくちょく借りてくと思うけど、よろしくねー」
いつも、たやすく同じクラスの男子と話している芽衣と怜奈も、狩野くんに対してはちょっと緊張しているような感じで、なんだか新鮮。
二人へ隠しごとをしている罪悪感を抱きながらも、今この場を乗りきるには、彼の嘘に乗っかるしかなかった。
「えっと……。わたし、今日は、狩野くんと一緒にお昼食べるね」
「……うん。わかったよ」
狩野くんに手を引かれながら教室を出て、廊下をずっと進む。
恥ずかしいからやめてって、この手を振り払うこともできるけど。そうしたくない自分がいて、また驚く。
狩野くんと無言のまま歩いて別棟までやってきた。
彼は、音楽室の隣の部屋、『軽音部』というプレートのかかった重たそうなドアを力強く押した。
「入って良いよ。軽音部の部室なんだけど、練習入ってない昼休みの時間は基本的に誰も来ないんだ。オレ、たまに、ここで飯食ってるんだよね」
「お、お邪魔します」
中に入ると、音楽室と同じように防音仕様の部屋となっていて、部屋の奥の方の三分の一程度の面積が一段高く簡単なステージのようになっていた。ギターとベース用にそれぞれアンプが置いてあり、キーボードとドラムセット、ボーカル用のマイクとマイクスタンドも設置されている。
軽音部のみんなは、ここで練習をしたり、ライブをしたりするんだ。
さっきまでの憂鬱な気持ちが一気に吹き飛んで、思わずぴょんぴょんと飛び跳ねたいような楽しい気持ちになった。
「うわあ! すごい、すっごいんだねっ。ここが、軽音部の部室なんだ!」
「オレが最初にこの部屋に入ったときと、似たような反応じゃん。でも、すげーわかるわ。テンションぶち上がるよなぁ」
「そりゃあ、上がるよ! バンド好きの血が騒ぐもん」
「ははっ。とりあえず、飯食おうぜ。ここ、座って良いよ」
狩野くんは、ステージ前の陽当たりの良い場所に、二つ分のパイプ椅子を用意してくれた。彼が購買で買ってきたらしい焼きそばパンを頬張りはじめたので、わたしも、お母さんに持たせてもらったお弁当の風呂敷をひらく。
卵焼きをもぐもぐと頬張っていたら、狩野くんは、わたしの表情をうかがうような顔をしていた。
「さっきさ、突然、教室に行っちゃってごめんね。迷惑だった?」
「そんなことないよ! むしろ……、さっきは、助けてくれてありがとう」
「澤田さんとお昼一緒に食べれたら良いなぁと思って、たまたま突撃しただけなんだ。そしたら、澤田さんが、オレのことでなんか問いつめられてるっぽかったから、悪いことしたと思って。……澤田さんは、友達には、病気のことを言ってないんだろ?」
こくりと、うなずいた。
一番大きな隠し事を知られている彼の前では、素直に言葉が出てくる。
「……うん。できることなら、隠しとおしたいんだ。芽衣と怜奈とはね、高校に入ってからの仲なの。入学式のときに、星空スコープ聴いたことあるって話題で仲良くなったんだ。よく話を聞いたら、二人はわたしほどのスコープファンではなかったんだけど、それでも新しい友達ができて本当に嬉しかったし、新しい環境になって心細かったから安心もした」
だけど。
わたしは、その直後に余命宣告を受けた。
「あと三か月しか生きられないってわかったとき、わたしは、可能な限りで高校に通いたいって思った。普通の高校生活を、体験したかった。だから、病気のことはできる限り隠していたい。芽衣や怜奈に気を遣わせることも、気軽に接してもらえなくなることも、怖いの。でも……隠そうとすればするほどヘンな感じになって、うまくいかなくて。多分、二人の不信感を募らせてるし、ウザがられてる」
言葉にしながら、お弁当を持つ手が震えた。
『こんなこと言いたくないけどさ……、真帆って、お腹の底でなに考えてんのか、よくわかんないよね』
先日、お手洗いで思いがけず聞いてしまったあの冷たい声が、蜘蛛の巣みたいに脳裏に粘ついている。ふとした瞬間に蘇って、心臓の真ん中から冷えていく感じ。あれ以来、わたし自身も、二人がお腹の底ではなにを考えているのかわからなくて、余計に怖くなってしまった。
「そっか。澤田さんは、優しいな」
「違うよ。どっちかっていうと……わたしのエゴで、二人を戸惑わせてるだけなのかも」
「そうだとしても、二人の気持ちを考えてのことだろ。たしかに……、高校生で死を強く意識してる人間の方が少ないだろうし、打ち明けられても、最初は受けいれられなくてパニックになるだけかもしれない。すごく、悩むところだよな」
実際、狩野くんの言うとおりになると思う。誰だって、身近なひとが死ぬかもしれないなんて話を、簡単には受け止められない。お母さんとお父さんだって、わたしが余命三か月だと知ったあの日から、平静を失ってしまった。
「けどさ……、オレが相手の立場だったら、知らずに後悔するよりも、知った上で後悔する方が良いな」
どくんと、心臓が脈打った。
「もちろん、最終的には、澤田さんが決めることだよ。でも、重々しくどうしようって考えてるとそれだけで疲れちゃうから、答えが出ないうちはいったん忘れていても良いかもな。時間が過ぎたら、気持ちが変わってることだってあるし」
「なんか……、すごいね。そんな風には考えられなかった。狩野くんって、大人びたことを言うね」
「そー? そう感じてもらえるのは大歓迎。澤田さんに、好かれたいし」
へらりと笑う彼に、顔が熱くなる。
さっきまで淀んだものでいっぱいだった胸の内も、いつの間にかほんの少しは軽くなっていた。
「狩野くん。吐き出させてくれて、ありがとうね」
「こちらこそ。吐き出してくれてありがとう」
窓からさしこむ陽射しを浴びた彼の笑顔が、眩しく輝いて見える。
その屈託のない笑みに、胸が絞めつけられたようになって、ドキドキとした。
ねえ、狩野くん。ちょっと前まで恋をしてみようとは思えないとか言ってたくせにさ、わたし、もうすでにきみへ惹かれはじめてる気がする。
でもさ、たとえそうだとしても、口にはできないよ。
言葉にしてしまったら、あと戻りできないくらいに、きみを好きになってしまいそうで。
*
狩野くんと一緒に、たくさんの時間を過ごした。
放課後、彼の軽音部の練習がないときは、他愛もない話をしながら一緒に帰る。
「澤田さんは、もしバンドやることになったら、なんのパートをやってみたい?」
「うーん……。ギターボーカルをやってみたいけど、ベースでシンプルにルート弾きもしてみたい! あ、でも、安定感のあるドラムもすごーくかっこいいよねぇ」
「ふはっ、選べてねーじゃん。でも、澤田さんはドラムって感じはしねえな」
「なんで?」
「んー。運動神経悪そうだから」
「シンプルに悪口!」
「だから、はい。手、出して」
「え?」
「澤田さんが、なにもないところで転びそうになっても大丈夫なようにだよ」
「なにそれ。わたし、そこまでどんくさくないよ」
「じゃー、シンプルに、オレがまた手をつなぎたいから」
「……そこまで、言うなら。つないであげないこともないですけど」
狩野くんの飾らないストレートな言葉は心臓に悪い。ドキドキしすぎて、つい、素直な言葉が出てこなくなってしまう。
その日から、彼と手をつないで帰るのが、当たり前になった。後になって思うと、わたしがいつ体調を崩してふらついても大丈夫なように配慮しての行動だったのかもしれない。実際、抱きとめて助けてもらったことも何度かあった。
でも、そうとは口にしなかった狩野くんのやさしさに気がついたとき、胸が甘くうずいた。
六月に入ってからは、狩野くんの軽音部での練習風景を、何度か見学もさせてもらった。
「おーおー。スタジオ練に、彼女を連れてくるなんて、マジで浮かれてやがんなぁ。このお花畑野郎が!」
「まあ、否定できねえわ。でもさ、こんなにかわいい彼女がいたら、浮かれたくもなるだろ? な?」
「……うげえぇ、砂糖吐きそう。からかい甲斐のねえやつ」
バンドメンバーにからかわれても、狩野くんはなんのその。わたしばかりが羞恥心で焼け死にそうになり、来るんじゃなかったって後悔しそうになった。
でも、一度、アンプを繋いだエレキギターの音が稲妻みたいに部室に広がった瞬間、感動で鳥肌が立った。アンプとドラムセットから響く生音の迫力に、ただただ圧倒される。
ギターを弾きながら、わたしの大好きなスコープの曲を歌う狩野くんは、悔しいくらいにかっこよかった。思わず、涙ぐんじゃうほど感動して、ずっと胸が高鳴っていて。演奏が終わった瞬間、立ち上がって拍手した。
「すごかった……! ライブって、めっちゃくちゃ感動するんだね!!」
「へへ、ありがと。なんか、そんなにガチで褒められると、恥ずいな」
スタジオ練習の時間を邪魔しつづけるのは悪いかと思って、先に帰ろうとしたんだけど、みんな見学していて良いとあたたかい声をかけてくれたので、お言葉に甘えて練習風景をずっと眺めさせてもらった。
その日の帰り道は、雨が降っていた。
灰色の空の下、わたしと狩野くんは、彼の差す紺色の傘の中で肩を並べて帰った。
「わたしね、スコープのライブを生で観にいくのが夢だったんだ。でも、直近でスコープのライブの予定はないし、もう絶対に叶わないんだろうなって諦めてた」
「真帆……」
「だけどね、今日、叶っちゃったよ! 今日の狩野くんたちの演奏、そう思うくらい、ほんとにほんとにすごかったなぁ」
「おーげさすぎ。……本物は、ぜんぜん違ぇよ」
「そうかもしれないけど、すごく心に残る演奏だったよ。狩野くんのおかげで、憧れてた軽音部の雰囲気も知ることができたし、最高にハッピーな一日だった。わたしを軽音部へ連れて行ってくれてありがとう。今日のことは、死ぬ日まで忘れないと思う」
「……っ」
言葉につまって、泣きそうになっている狩野くんはなんだか新鮮で。かわいいなって頬がゆるんだ。
狩野くん。きみはね、わたしのもう一つのひそかな夢も叶えてくれたんだよ。
雨の日に、男の子と相合傘をして、ドキドキしながら隣を歩くことにも憧れていたからさ。
恥ずかしくて、そこまでは口にする勇気がなかったけど。
もちろん、幸せな日ばかりじゃない。
病気の猛烈な痛みと苦しみに襲われて、もうこんなのは嫌だって、ぜんぶ終わらせたくなる夜もある。
「もう、無理……っ。我慢できないっ。こんなに辛いなら、早く、死んじゃいたい。苦しい、苦しいよ……。助けてよ!」
「……ごめん。なにもしてやれなくて……、ほんとにごめんな」
「わたしの、ほうこそ、ごめん……。ごめんね……っ。こんな泣き言を聞かせたりして、ほんとに、ごめん……」
「謝るの禁止って言ったじゃん。それにオレは、真帆に頼ってもらえてうれしいよ。ねえ、真帆。こんなに辛いのに……、それでも、頑張ってくれていてありがとう」
親にこれ以上の心配はかけたくない。それでも、薬も効かなくてあまりのしんどさから誰かに弱音をこぼしたくなったとき、わたしは携帯で狩野くんと通話をつなげながら呪詛をまき散らした。それで身体が楽になるわけじゃなくても、わたしの頑張りを認めて寄り添ってくれるひとがいるという事実が、屈しそうになる心を支えてくれた。
病気じゃなかったら、狩野くんと関わることはなかっただろう。
身体のどこも痛くない状態で、好きなひとと同じ時間を過ごせる喜びを、奇跡とまでは思えなかっただろう。
病気のことは、変わらず憎い。胸が焦げつきそうなほど憎らしくて、消えてしまえば良いのにって毎日考えてる。
だけど……、狩野くんとの出逢いは病気があったからこそ訪れたものだと思うと、ほんのすこし位は感謝しやってもいいかって最近は考えてる。癪だけどね。
そうやって、彼と付き合いはじめてから、二か月が経った。
満ちたりていたからこそ、あっという間の二ヶ月間。
この間、芽衣と玲奈とも、つかず離れずの距離感を保てていた。わたしが狩野くんと付き合ったことで、自然と恋バナに加われるようになったから。
こんな日々が、ずっと続けば良いのにな。
でも……。
どれだけ必死に願っても、わたしの脳に巣食う病は予定通りに進行して、この充実した日々が続くことをゆるしてはくれなかった。
*
学校からの帰り道。もわもわとする夏の気怠い空気の中を歩いていたとき、いきなり耐えがたい頭痛に襲われた。
「いたたたっ……」
立っていることもできなくてうずくまったら、狩野くんは、わたしが道の往来で嘔吐しても大丈夫なようにとすぐにエチケット袋を差し出した。
「真帆。大丈夫? 吐いても大丈夫だよ」
「だい、じょうぶだよ。……ちょっと、頭痛がしただけだから」
そう答えながら、もう高校に通う余裕はないのだと、自分の体調のことだからこそよくわかっていた。すでに学校を何日も続けて休む日も出てきていて、一日座って授業を聞いているのも難しくなってきている。
「でも、顔色すっげえ悪いよ。真帆の家までもうすぐだし、家まで背負って送ろうか?」
「そんな、ことまで……、させられない」
「真帆……」
道の端によってわたしの背中をさすってくれる狩野くんが、今にも泣きそうな顔をする。最近は、彼にこんな顔をさせる日ばっかりで、本当に申し訳ない。
どれだけ願っても、奇跡は起こらない。
最初は、狩野くんがどうしてわたしの病気のことを知っているのか気になったから付き合ったけど、今は違う。
純粋に、彼のことが好きだ。
大好きで、そばにいたいから、自分の意志で付き合ってる。
でも……、これ以上は、狩野くんに迷惑しかかけられない上に、しんどい思いをさせるだけだ。今までと違って、わたしはもう、彼を笑顔にすることができない。
一緒にいても、辛い思いをさせるだけ。決して幸せにはなれない。
だから、もう、終わりにしなきゃ。
「狩野くん。……いつも、ありがとう。この二か月間、本当に本当にありがとうね」
彼の顔が、強張った。
「急に、なに? どうしたの」
「わたしね、狩野くんのことが好きだよ」
切れ長の瞳が、驚いたように見ひらかれた。
あぁ、嫌だな。
初めての告白は、もっとかわいらしくて、ドキドキとするシチュエーションで言いたかったのに。こんな、風に吹かれたら消えてしまいそうなろうそくのように頼りない声で、言いたくはなかったなぁ。
「わたしに……、恋を、教えてくれて、ありがとう」
「……なんだよ、それ。なんで今このタイミングで、……そんなことを、言うんだよ」
涙交じりの怒っているような声に、熱いものが喉にせりあがってきた。
でも、これからひどいことを口にするわたしに、泣く資格はない。ちゃんと、最後まで、わたしの言葉で伝えなきゃ。
「狩野くんも、わかってると思うけど……身体が、だいぶ限界なの。明日から、学校は休むつもり。それで……、狩野くんとも、もう二度と会わない」
彼の瞳から、涙がぼろぼろとあふれた。
「それ、本気で言ってるの? まだ、約束の三か月も、経ってないのに……」
「もう、いいの。知らないままで良いんだ」
狩野くんが、どんな理由でわたしに近づいたんどとしても、かまわない。
すこしも気にならないっていったらウソになるけど、これ以上は、背負わせられないよ。
明るい未来が開けている狩野くんを、わたしに縛りつけたくはないから。
「嫌だよっ! いきなりそんなこと言われて、納得できるわけないだろ!!」
「散々頼っておいて、急に勝手なことばかり言ってごめんね。今まで、本当に本当にありがとう。でも、もう、一緒にはいられない。だから……別れてほしい。ばいばい、狩野くん」
呆然としている狩野くんの手をすりぬけて、よろよろとした足取りでうちを目指した。
「真帆っ! クソッ、なんでこうなっちまうんだよ……っ」
胸が千切れそうなぐらいに悲しくて、涙があふれて止まらなかったけど、決して振り返りはしなかった。振りかえって彼の顔を見たら最後、その胸の中に飛び込んで泣きついてしまいそうだったからだ。
うちに帰ると、お母さんは泣き腫らした顔のわたしを見て、強く抱きしめてくれた。
「どこか痛むの? 苦しい思いをしたの?」
「……ねえ、お母さん。わたし……、学校に行くのは、もうやめる」
「そう。……わかったわ」
今ばかりは、なにがあったのかを聞かずに抱きしめてくれるお母さんの存在が、とてもありがたかった。
✳︎
学校を休むと決めて間もなく、わたしは総合病院へ入院することになった。家で療養することも考えたけど、緊急事態が起きたときに、病院にいた方がすぐに対応してもらえるからという家族の意見に従った。
最低限のものしか置かれていない病室での質素な生活は、想像以上に退屈でさびしいものだった。ちなみに、学校のみんなには、わたしは風邪をこじらせているということになっているから、お見舞いにやってくるのは身内の親族だけ。中学時代の友人も、今は高校生活に慣れることに忙しいかもと思ったら、連絡をして水を差す気にはなれなかった。
襲いくる症状は日に日にひどくなってきていて、意識を保っていられない日も出てきたから、この選択は今のわたしにとって間違っていなかったんだとも思う。
ベッドに寝転がりながら、SNSを眺めようとして携帯を手に取ったとき、狩野くんの明るい声が頭をよぎった。
ダメだなぁ、わたし。
携帯を手に取ると、どうしても狩野くんに連絡を取りたくなってしまって、胸が苦しい。歯を食いしばって、それだけはしないようにと堪えた。あんな酷い振り方をしておいて、未練がましく連絡を送ることなんてできない。していいわけがない。
携帯を手にしていたら、思いがけない人物から連絡通知がきた。
【真帆。体調、大丈夫なの?】
【先生は風邪をこじらせてるって言ってたけど、ほんと?】
芽衣と、怜奈だ。
いつもの癖で『うん、大丈夫だよ。ちょっとしんどいけど、本当にただの風邪だから』と当たり障りのない返信をしようとした手が止まる。
このまま、二人に本当のことを告げず、この世を去っても良いんだろうか。
『オレが相手の立場だったら、知らずに後悔するよりも、知った上で後悔する方が良いな』
こんなときにまで、狩野くんの言葉が蘇る。
二人に対しては、正直、複雑な思いも抱いている。陰口を言われていたショックは大きかったし、二人へ心配をかけないように良かれと思ってしたことが空回りしていた日々は辛かった。
だけど……、全てを芽衣と怜奈のせいにもしたくない。わたしが黙っている限り、二人が、わたしの個人的な事情を知る由もないんだから。
この病院に来てから、もう一週間は経っている。残された期間は、長くはない。
だからこそ、いままで出せなかった勇気を奮って、悔いのないように行動したい。
わたしは、あとは打って送信するだけの当たり障りないメッセージを全部消して、もう一度、携帯を打ちなおしはじめた。
【二人とも、心配してくれてありがとう。いきなり重たい話になっちゃって申し訳ないんだけど、本当は、命に係わる大きな病気を患っています。学校にも、もう二度と通えないと思う。大事なことなのに、ずっと黙っていてごめんね】
すぐに既読がついて、ドキリと心臓が飛び跳ねた。
返信がこなかったから、わたしは続けて、正直な気持ちをメッセージに打ちこんだ。
【本当は、芽衣と怜奈のことが、羨ましくて仕方ないときもあった。二人だけじゃなくて、学校のみんなのことも。未来あるみんなが、眩しくて仕方なかったの。なるべく普通の高校生活を送りたかったからこのことは黙っていたんだけど、結果的に、それで二人を戸惑わせてたと思う。今更、こんなことを打ち明けてごめんなさい。それから、こんなわたしと友達になってくれてありがとう】
どんな返信がくるか怖くなって、携帯を放り出したら、携帯が震えはじめた。
二人からのグループ通話の着信だ。
「真帆! いま、大丈夫!?」
「電話しても平気!?」
「うん」
少しの沈黙が訪れたあと、芽衣と玲奈のすすり泣く声が耳に流れこんできた。
「真帆の、バカ……っ」
「……ほんとに、さぁ。なんで、そんな大事なこと……、もっと早く、教えてくれないかなぁ」
涙交じりの鼻声に、胸がギュッと締めつけられた。
「ごめ、んね。二人に、気を遣わせたら、悪いなぁと思ってて……」
「あたしら、バカなんだよ……っ。真帆が……そんな状況になってたなんて、今の今まで、すこしも知らなかったっ」
「ちょっと風邪をこじらせてるのかもなってぐらいに思ってたのに、命にかかわる病気ってなんなの!? そんなの……言ってくれなきゃ、わかんないよ!!」
だって、わたしは、二人にとって取るに足らない存在だと思ってたから。
出会って、たった数ヶ月の友達に、こんな重たい事実を打ち明けて背負わせるのは、申し訳なさすぎるって……。
でも、わたしだって、言われないとわからなかった。芽衣と玲奈に、泣いて心配してもらえるほど、気にかけてもらえていたこと。
「真帆は……、やさしさから、黙ってたのに。ずっと……、なんにも気がつけなくて、ごめんね」
「あたしら、ほんとどーでもいいことばっか、喋ってたよね……。絶対、真帆の気を悪くさせてたと思う」
「それは、ほんとに気にしないで! わたしが、二人にはいつも通りでいてほしかっただけだから」
「真帆……。ねえっ、今から、お見舞いに行っても良い?」
「えっ。良いけど……、ほんとに来てくれるの? いつでも大丈夫だけど、二人とも忙しいんじゃ」
「なにバカなこと言ってんの! 部活休んでも、行くに決まってるでしょ!」
二人の行動力はすさまじく、電話をもらってからすぐに、二人は病室へと駆けつけてくれることになった。
身内以外のひとに会うのは久しぶりで、わたしも急いで、最低限の身だしなみを整えた。
芽衣と玲奈は、ベッドの上で上体を起こしたわたしを見るなり、駆け寄ってきた。
「真帆……。久しぶり、だね」
「苦しくない!? えと、えと……、今更だけど、いきなり押しかけちゃって、迷惑じゃなかった……?」
「大丈夫。今は、マシな方だよ。二人とも、こんなところにまで来てくれて、ありがとね」
「そっか……。なんかさぁ……、ここに来るまで、真帆の病気のことを若干信じられない気持ちもあったんだけど、本当、なんだね」
「ずっと黙ってて、ごめんね……?」
「謝るのはやめて。謝罪すべきは、あたしたちのほうなんだから……」
二人はメイクが崩れるのも気にせずに泣いた。
それから、最近の学校での出来事を、たくさん話してくれた。
芽衣と怜奈の話を、これまでにないくらい穏やかな気持ちで聞くことができた。
隠しごとをしている罪悪感がなくなったから。そして、わたしの普通の高校生活への未練が思っていた以上に薄れていたことにも気がついた。
二人には、最期まで病気のことを打ち明けるつもりはなかったけど、勇気を出してみて良かったな。
こんなに深く想ってくれていたことに気がつけないままこの世を去るなんて、さびしすぎるもの。
「ねえ、真帆。ひとつだけ聞いても良い?」
「なに?」
「狩野くんは……、このことを知ってる?」
ひゅっと、喉が細まった。
嫌だな。いつの間にか、名前を聞くだけで、こんなにも胸が締めつけられる。
「うん。病気のことは、知っているよ。だけど……、会ってはない」
「そっか……。会いたいと思ってないの?」
「会いたく……」
ない、と。
言いきるつもりだったのに、できなかった。
ウソでも、そんなこと言えなかった。
「……やっぱり、ウソ。ほんとはね、今すぐ会いたい。会って、ひどいこと言ってごめんねって謝りたい。それから……、大好きだよって、もっといっぱい伝えたかったっ。でも……そんなこと言う資格、わたしにはない」
とどめてはおけなかった本音が、涙とともにこぼれ出る。止められなくて、両手で顔を覆った。
短かったかもしれないけど、普通の高校生として過ごして、恋を経験することができた。
欲を言えば流星スコープのライブは一度生で観てみたかったけど、それ以上に、このまま狩野くんに会えずに死んでしまうことの方がずっと悲しい。
病気をなくす以外で、なんでもひとつだけ願いを叶えられると聞いたら、本心とエゴが剝き出しになってわたしは願ってしまうだろう。
息を引き取る最期の瞬間まで、狩野くんのそばにいたいって。
「だってさ、狩野くん」
ウソ。
芽衣と怜奈が、病室の入口へ視線をよこした瞬間、勢いよくその扉が開かれて。
涙でぐしゃぐしゃになった視界に飛びこんできたのは、大好きなひとの泣き顔だった。
「勝手に連れてきちゃってごめんね、真帆。でも、最近の狩野くん、幽霊みたいに青白い顔しつづけてたから、流石にかわいそうになっちゃって」
「真帆の病気のことを聞いて、合点がいったんだよ。おせっかいかとも思ったけど、もし真帆も狩野くんに会いたいと思ってるなら、このままで良いわけがないと思ったから」
「二人、とも……」
「じゃ、そろそろお邪魔虫は退散するから」
「また来るね、真帆っ」
芽衣と怜奈が去って、その場に取り残されたわたしと狩野くんの間には、今までにないほど重たい沈黙が訪れた。
なんということだ。心の準備も一切ないまま、また、狩野くんと顔を合わせることになるなんて。
呆然として言葉を発せないでいるわたしに、彼が、恐る恐る近づいてくる。
「……真帆。さっきのが、本音だと思って良いよね?」
「え、と……」
「諦め悪くて、ごめん。でも……、あんなの聞いたらさ、違ったとしても勘違いするよ。それに……もう、これ以上は、後悔したくないんだ」
気がつけば、わたしは、狩野くんの腕の中に閉じこめられていた。
「嫌なら、つき放して」
やさしい温もりに、ドキドキするのに安心して、いっぱい涙が流れた。悲しくてじゃない。うれしくて、ずっと求めていた場所だって心が叫んでる。
狩野くんは、ズルいよ。こんなの、拒絶できるわけないじゃん。
泣きながら、彼の背中に腕を回した。
折角、離れようって決めて、歯を食いしばってたのにさ。一度顔を見たら、どうしてそんなことを思えたのかわからないほど簡単に決意が揺らいで、愛おしくて、手放せなくなる。
「ねえ、狩野くん……。我がままを、言っても良い?」
「もちろん。なんでも聞く」
「わたしね、もう、そんなに長くないって……なんとなく、わかるんだ。狩野くんを、苦しめることになっちゃうと思う。それ、でも……わた、しは」
「うん……っ」
「狩野くんと……、最期まで一緒にいたい。……死にたくなんて、ないよぉ」
抱きしめてくれる腕に、力が、より一層こもった。
「もちろんだよ。……その言葉を、ずっと待ってた」
彼の顔が近づいてきて、唇に、やわらかいものが触れた。
ほんのすこし触れ合うだけの、羽根のようなキス。
初めてのキスは、甘く、涙の味がした。
✳︎
狩野くんは、約束どおり、ほとんど毎日学校帰りにわたしの病室へと通ってくれた。部活とか学校行事とか色々とサボっていそうだけど、あえてなにも言わなかった。今このときだけは、彼の時間を、できる限りわたしのものにしたかった。自分にそんな独占欲があったことも、狩野くんを好きになるまでは知らなかった。
時おり、芽衣と怜奈も一緒に病室へ顔を出してくれて、賑やかな日々を過ごしている。
痛みが激しく、苦しみだけが続いて、朦朧としているだけの日が多くなっているけど、わたしは最期まで抗うって決めた。
寄りそってくれる全てのひとと、一日でも長く同じときを過ごして、できる限りの愛を返すために。
「最近の真帆、穏やかな表情をすることが多くなったわね」
「そう……?」
お母さんは、横たわっているわたしの手を握りながら、弱々しく微笑んだ。
「そうよ。毎日、真帆のお見舞いに来てくれてる、かっこいい男の子のおかげかしら」
「うん、そうなの。……あのね、お母さん。わたし……、今、すごく幸せ、なんだ。心からの、本音だよ」
「……真帆」
「だから、お母さんは、もう……自分を責めないでね。間違っても、わたしを……かわい、そうな……子だったとは、思わないでね」
お母さんは、大粒の涙を流しながら、しっかりとうなずいてくれた。
「真帆が、あの子と出逢ってくれて、本当に良かったわ。中学時代から、すっごく仲が良さそうだったものね」
心臓が、バクリと大きな音を立てた。
「中、学……?」
「あれ……。そうじゃなかったかしら? 中学時代に、絶対にこのライブに一緒に行きたいひとがいるから、どうしてもペアチケットを買ってほしいって私にせがんだことがあったでしょ? そのライブに一緒に行ったのも、彼だったんじゃないの?」
なにそれ、なにそれ、なにそれ。
わたしと狩野くんは、高校じゃなくて、中学時代にすでに出逢っていたの? それも、お母さんに頼んでライブにまで一緒に行くほど特別な仲だった?
それなのに、どうしてわたしは、そんな大事なことを全部すっかり忘れてしまっているの。
疑問と、胸騒ぎとが止まらない。
とにかく、狩野くんへ、今すぐ事の真相を聞かないと。
「……っっ。痛いっ! 痛いよ……っ、苦しい……っっ」
「真帆っ!!! 待ってねっ、今すぐにお医者さんを呼ぶから!!」
だけど……、急激に襲ってきた猛烈な痛みが、今までにないほど激しくて。あまりの辛さに、意識を保っていることもできなかった。
*
「真帆っ。真帆っっ!!!」
次に目をさましたとき、ぼやけた視界へ最初に飛びこんできたのは、泣き腫らしたような顔の狩野くんだった。しっかりと、手を握ってくれている。お母さんも、お父さんも、お医者さんも、みんな強張ったような顔で、わたしを見つめてた。
「狩野、くん……?」
「真帆……。もう一回、目覚めてくれて、本当に良かった……っ。もう、三日も、意識を取り戻さなかったんだよ」
「そっ、か……」
狩野くん、と自分で呼んでおいて、なぜだか違和感を覚えた。
そうだ。
中学時代のわたしは、彼のことを、こんな他人行儀な呼び方はしていなかったからだ。
「りっ、くん。わたし……、狩野くんの、こと……りっくん、って呼んでたよね?」
彼の瞳から、大粒の涙が流れたとき、あぁ間違っていなかったんだなってホッとして頬がゆるんだ。
「……わたし……、りっくんと、スコープの、ライブに行ったことがあった、んだね……? なんで、かなぁ……ずっ、と、忘れていて、ごめん……ね」
「無理に喋らなくて良いよ!!」
「しゃべ、るよ。もう、時間ないから」
「嫌だっ。待ってよ……っ、オレ……、まだ、真帆にほんとのこと言ってない」
大丈夫。大丈夫だから、泣かないで。
りっくんの想いは、ちゃんと伝わっているよ。
記憶は、相変わらず滲んだ絵具みたいにボヤケている。だけど、一番大事なことだけは、思い出せた。全てを忘れたまま、最期を迎えることにならなくて本当に良かったな。
わたしとりっくんは、中学時代に出逢っていたんだよね。
ぜんぶを思い出せなくても、言葉にしてもらわなくても、不思議なほど信じられる。
きみは、最初から最後まで、わたしのためを想って行動してくれたこと。
わたしの記憶が欠けているのは、その行動が関係しているということ。
今この瞬間一緒にいられるのは、きみが、奇跡を起こしてくれたからなんだってこと。
「今まで、あり、がとう……。大好き、だよ」
わたしは大好きなひとたちに見守れながら、これから永久の眠りにつくとは思えないほど安らかな気持ちで目を閉じた。
***
一人、太陽を反射してきらきらと光る蒼い海を眺めながら、ぼんやりと思索にふける。夏真っ盛りの海水浴場は、カラフルな浮き輪と、浮ついたひとの群れで騒がしい。
「そこのイケメンのにーちゃん、一人? ヒマなら、あたしたちと遊ばない?」
「あー、すみません。……そーゆー気分じゃないんで」
ビキニの姉ちゃんに話しかけられても、心は微動だにしない。
オレは、なるべく誰にも話しかけられないように、人気のない岩場のほうへとやってきた。
夏休みに入って数週間が経ったけど、なんもしたいことが浮かばなくて。このまま家にいたんじゃ身体が腐りそうだと思って、唐突に海までやってきた。
久しぶりに海が見たいという、ただそれだけの理由で。
でも、本当はこんな風に一人で眺めるんじゃなくて、真帆と一緒が良かったなぁ。
「……なぁ、真帆。オレがしたことに、意味は、あったのかな」
大好きだった少女、澤田真帆は約一か月前に脳腫瘍で命を落とした。
過去にさかのぼってやりなおしても、結局オレは、真帆が病気で命を落とす未来を変えることまではできなかった。
気まぐれな神さまから、やりなおしのチャンスを与えられたにも関わらず、オレは無力だった。
真帆と、オレの本当の最初の出逢いは、中学一年生のとき。
狩野家の家庭環境は、歯に衣着せずに言えば、ずっと最悪だった。
オレのものごころついたときには、親父と母親が顔を合わせるたびに、毎日シャレにならないほどの大喧嘩をしていたから。
二人の一人息子だったオレは、一人で、二人分の愚痴を受け止めつづけた。親父は母親の悪口を、母親は親父の悪口を、毎日オレへと投げつける。いっそのこと早く離婚すれば良いのに、中々、踏ん切りがつかない二人へ苛立っていた。そんな二人を見て育ったから、一度は結婚を誓いあうほどの仲になって家庭と子供まで作ったのに、崩壊すんのはあっけないもんだなって冷めた恋愛観が形成されていった。
不満がたまって限界を迎えていた中学入学当初、オレはグレて荒れまくっていたので、学校で誰かと馴れあう気もなかった。
両親の仲が良く、家でなんの苦労もせずにのうのうと生きているであろう周囲の生徒たちが、全員妬ましくて仕方がなかった。
教室の休み時間も、わざとイヤフォンを見せびらかすように耳につけて、誰にも話しかけられないように警戒していたほどだ。
でも……、真帆は、オレの作った高い高い壁も、やすやすと乗りこえてしまう女の子だった。
『狩野くんって、音楽が好きなの?』
『……は?』
『いつも、イヤフォンをして音楽を聴いてるでしょ? なんの曲を聴いてるの?』
最初は、苦労のくの字も知らなそうな顔で、幸せそうにヘラヘラ話しかけてくる真帆にイラついた。明るくて、友達にも教師にも愛されていて、太陽みたいに明るい子。きっと家族からも、めいっぱい愛されて育っているに違いない。
毎日、ゴミ箱のように汚い言葉を投げつけられているオレとは全く違う、きれいな世界で生きているひと。自分は誰からも愛されると確信しているからこそ、オレみたいな一匹狼にも、ためらいなく話しかけてくるんだろう。
あまりに眩しくて、目が焼け爛れそうで、オレは彼女から目をそらした。
『ベツに。お前に答える義理なんてねえし』
『そっか。でも、わたしはなんの曲を聴いてるのか気になるから、また話しかけにくるね』
『…………はあ? お前、いまのオレの話、聞いてた?』
『聞いてたよ。でも、わたしは音楽聴いてるひとがいると、どうしても気になっちゃうの。ウザくて、ごめんね?』
真帆は、その言葉通り、めげずにオレへと話しかけてきた。
最初はヘンな女子だと思っていたのに、段々、無視しきれなくなっていって。
仕方なく、流星スコープというバンドが好きだと明かしたら、真帆が跳ね上がりながら『わたしも!』って喜んだから、柄にもなく、運命ってやつを感じてしまった。
最初はバンドの話で盛りあがっていたけど、すこしずつ、家庭環境の話もするようになった。
『昨日も、両親が、深夜まで怒鳴りあっててさ。オレが寝てる部屋まで響いてくるから、眠れねえんだよ……。いっそのこと、一人暮らししたい。そんな金ねえけど』
『狩野くんは……、毎日、すごく大変な思いをしてるんだね』
『……ごめん。こんな話、されても困るだけだよな』
『ううん。ねえ、狩野くん。わたしのことは、いつでも、狩野くんの気持ちのゴミ箱にして良いからね』
『はあ?』
『狩野くんが、毎日ご両親の鬱憤を受けとめてるなら、狩野くんにも、鬱憤を受け止めてもらうひとが必要だと思う。わたしには、聞くことぐらいしかできないけど……、吐き出したくなったらいつでも言ってね』
夕陽を浴びた真帆の笑顔に見惚れて、彼女への愛おしさがあふれた。
オレが、嵐のような中学時代を乗りきれたのは、真帆がいたからだと断言できる。彼女が、もう耐えられないと思ったときに、いつでもオレの呪詛を受け止めてくれたから。
根本的な状況は変わらなかったかもしれないけど、言葉に出して吐き出させてもらえたことで、オレはたしかに救われていた。
真帆は、家のことで自暴自棄になっていたオレを励ますために、サプライズで流星スコープのライブに連れていってくれたこともあった。
『どうしても、りっくんと一緒に、このライブに行きたかったんだぁ~!』
自分の誕生日プレゼントとクリスマスプレゼントを前借して、親にねだり、ペアチケットを買ってもらったのだと。
憧れてるバンドの生のライブに心の底から感動して、興奮冷めやらぬまま、ライブ会場でおそろいのストラップも買った。
こんなにやさしくて、他人想いな彼女のことを、愛さないわけがなかった。
真帆は、愛なんて意味がないとひねくれきっていたオレのことを、完ぺきに変えてしまった。
中学を卒業するころ、やっと両親が離婚してくれて、オレは父親に引き取られることになった。耐え忍んでいた日々が終わり、やっとひと息つけたとき、ようやく真帆に告白する踏ん切りがついた。
頬を染めながら告白を受けいれてもらえた瞬間は、飛び上がるほどうれしかったけど、オレは高校に入学してすぐに絶望の底に叩き落とされた。
『ごめんね、りっくん。……わたし、ほかに、好きなひとができたんだ。別れてほしい』
こんなにもひとの心を奪っておいて、あっさりと他人を好きになり別れ話をしてきた真帆を、殺したくなるほど憎んだ。
表面上はものわかりの良い男を演じて『わかった』と頷いたけど、納得できるわけがない。なにが悪かったのかと思いつめ、彼女に気づかれないようにストーカー手前の行動までとったが、ついぞ、真帆の心を奪った憎き敵の情報を得ることはできなかった。
そして。
高校入学から約二か月ほど経ったころ、彼女は高校へ来なくなった。
その一か月後。
オレは、澤田真帆が脳腫瘍でこの世を去ったと、中学時代の同級生から聞いて知った。
悲しくて、苦しくて、やりきれなくて、腹が立って仕方がなかった。
なにに一番腹が立ったかって、真帆から別れ話をされたときに本音でぶつからず、かっこつけたいがために、ものわかりの良い男を演じたバカな自分にだ。彼女に真実を打ち明けてもらえなかった、不甲斐なくて、頼りない自分に。
真帆に、もう一度、会いたい。
願いが叶ったら、今度は、絶対に最期までそばにいる。
壊れそうな心で、何度も何度も、祈った。
あんなにやさしい子を十五歳という若さでこの世から去らせた世界に、神なんていやしないとわかってる。それでもオレは、なにかに縋らずには生きられなかった。
「私は、きみのしたことに、意味はあったと思う」
グラスに注いだ水のように透きとおった声に、意識が、思考の海から現実へと引っ張り上げられる。
目の前に、オレにチャンスを与えた、当の神さまが立っていた。
誰もが振りかえるほど綺麗な顔をした、男か女かもわからない、黒ずくめのマントのひと。
絶望のあまり高校にも通えなくなり、昼間から公園で虚ろにぼんやりとしていたオレの前に突如現れた、自称、神さま。
「驚いたよ。彼女は、私が彼女の周囲も含めて完全に消し去ったはずのきみとの記憶を、わずかにだが取り戻した。記憶の操作は、完ぺきだったはずなのに」
彼女だか彼だか知らないが、目の前のこいつが、超常的な存在であることは信じざるをえない。実際にオレを過去へと戻し、生きている真帆に再び逢わせてくれたのだから。
過去へ戻すための代償として提案されたのが、真帆から、オレに関わる記憶の全てを消すことだった。
真帆の中から自分と過ごした三年間の記憶が消えてしまうことに、躊躇いがなかったわけじゃない。
それでもオレは、もう一度彼女に会って、今度こそ最期の瞬間まで向き合いたかった。
「……結局、真帆は死んじまったけどな」
過去に戻すなんて、そんな大層な力があるのなら、真帆の命を救ってくれよ。
オレは、この三か月間、泣きたくなるほど幸せだった。
真帆の苦しそうな姿を目の当たりにしてキツいときもあったけど、後悔は全くしていない。
だけど、真帆は?
真帆にとって、この三か月は、どうだったんだろう。
考えはじめると、怖くなる。よく考えたら、オレは真帆から大好きなバンドのライブに行った記憶を奪い去っただけなんじゃないかと思うと、罪悪感で息が止まりそうなほどだ。
オレは、彼女のために、なにかできたのか?
一番、答えてほしい相手は、もうこの世にいない。
「……なぁ、神さま。なんで、オレを代償付きで過去へと戻すなんてクソ面倒くさいことをしてくれたんだ?」
感謝こそすれど、理不尽に責めたい気持ちをどうにか堪えながら問いかけると、奴は無表情のまま答えた。
「さあね。気まぐれだよ」
「……そーかよ」
「強いて言うなら、興味があったんだと思う」
「興味?」
「ひとの愛が、神の力に勝る奇跡を起こす瞬間を、目の当たりにしてみたかった」
神さまは、オレに向かって、口角をほんの少しだけ持ちあげた。
「どうせ無理に決まってると思いこんでいたけど、目の当たりにしてしまったさ。きみたちの愛が、奇跡を引き寄せたんだろう。それに、彼女は、きみがやりなおす前の過去よりもずっと幸せそうだったよ」
運命は、変えられなかったかもしれない。
それでも、オレは目の前の神さまの言葉に、救われたような気持ちがした。【完】