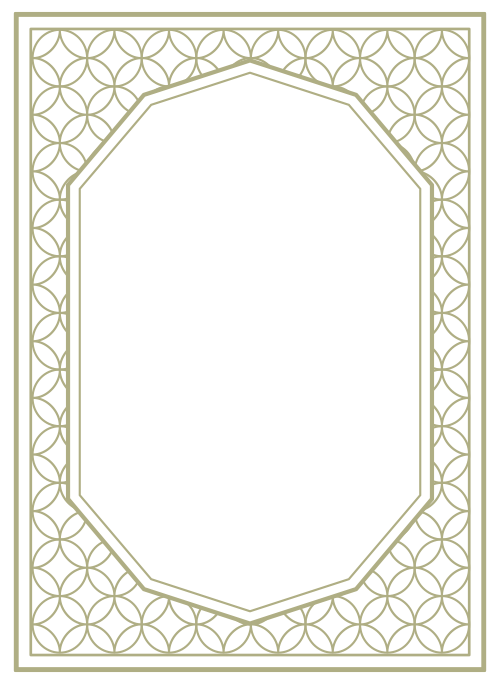「……そうなのですか?」
「心護様、琴理様と年齢が近い者が、宮旭日にはいないのです。そのため心護様も、学内に護衛はいません」
主彦の言葉に、涙子が続ける。
「中枢の家で言えば、わたしと主彦が一番お二人に近いくらいになってしまうのです。もっと末端まで広げれば見つかることは見つかるのですが、幹部の話をどこまで守秘出来るか……幹部の家出身だから信頼できる、ということではありませんが、末端にいけばいくほど、不安要素は大きくなります」
――つまり、学内にいるときの琴理の護衛が、宮旭日家にとっては穴だということだ。
(なるほど……学生の今、学校にいる時間が大半を占めます。心護様は武術もお強いと聞いていますが、わたしはそれほどではありません……)
そこまで考えて、ん? と思考が停まった。ちょっと待て。何かおかしい。
「あの……通常とか普通と言ってはダメなことだとわかっていますが、中枢の家に心護様と年齢が近い方が、本当に誰もいないのですか?」
――琴理も、各家の面々を書類上は知っている。会う機会があった人物もいる。だが、本当にいないのか。
心護のように宗家の跡取りともなれば、将来的に支えることになる者を、近い年齢で望まれるはずだ。
主彦は二十三歳、心護は十七歳。六歳差は開きすぎではないけれど、鳴上家だけに望まれることはないはず。
鳴上は宮旭日の最側近だが、側近格の家はほかにもある。
花園は側近格でこそないが、役割のある家柄で、琴理と愛理がいる。
「いないのです。心護様のご年齢に近い者だけが」
答えた主彦の声は緊張しているように聞こえる。
まだ口にしていない意味があるように聞こえてしまうのは、琴理の考えすぎではないはずだ。
琴理は詩に視線を向ける。