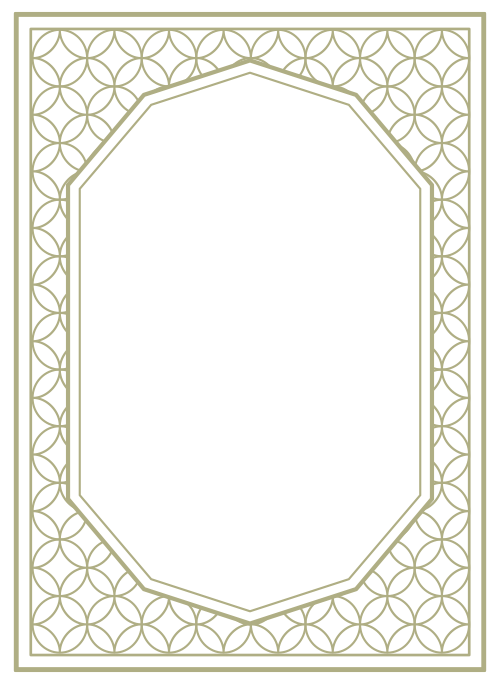+++
――妹の愛理の方が宮旭日家の次代の花嫁に相応しい。
それは琴理が言われ続けていることだった。
――だが身体が弱いらしい。姉と取り換えられていたらよかったのに。
そう、続けられることが常だった。
夜半のこと。
花園の屋敷を抜け出した琴理は、邸(いえ)から一番近い森の中にいた。
最低限、部屋義ではない恰好と靴を履いて、一冊の本を手にしていた。
森の中に開けた場所を見つけたので、月の光がさすそこで、本を両手にしてごくりと唾を呑んだ。
(……魔導書)
琴理自身は花嫁修業を優先され、退鬼師としての修行は積んでいないため退鬼師ではないが、あやかしや魔物を見る力はあった。
そしてこの本は、何年も前に古書店で手にしたもの。
花嫁修業の一環で街へ出たとき、気になって購入していたのだ。
それが魔導書なるものだとは知ったときは驚き、本棚の奥へ封印していた。
仮にも退鬼師の家に魔導書が無造作に置かれているなんて誤解を招きかねない。
だがその本が『魔導書』であるため、処分方法も思いつかず眠らせていたのだ。
(それがこんな風に役立つ日がくるとは……人生わかりませんね……)
琴理は地面に膝をつき、本を開いた。
魔法陣が書いてあるページを開き、目線を落とす。
「――――――の悪魔と、契約を願う――」
そこに書いてある『呪文』を口にする。
半信半疑だったが、現実には何も起こらなかった。
「……まあ、そんなものでしょう。……ほかに方法を探すしかないですね……」
ため息をついた琴理が腰をあげたとき――
「んで? お前の願いはなに?」
(え?)
立ち上がるために地面についていた手に向かっていた琴理の目が、ふっと上へ向く。誰かが近くにいたっけ? と。
そして上を向いた琴理は――凍り付いた。
足を組んだ格好で空中にふよふよと浮く人間がいたのだ。
「え、じゃねえよ。お前が喚(よ)んだんだろーが」