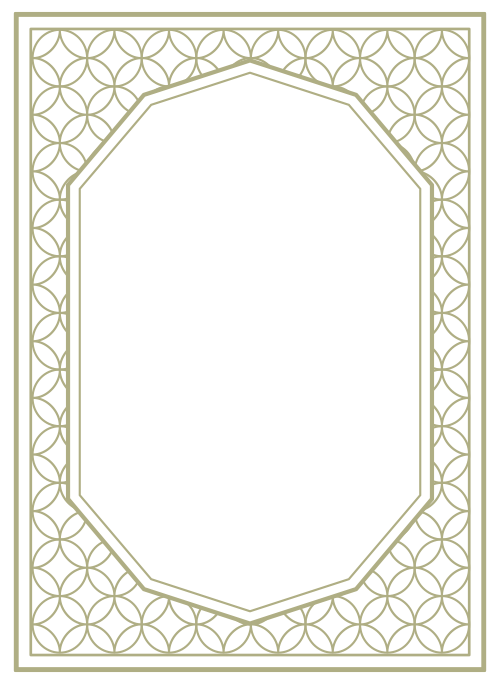「はい。いずれは嫁ぐ身ですから、早めに馴染むのもよいかと」
『そうか……』
父が、はあ、とため息をついたので、おや? と思う琴理。
父はそういった気持ちを表に出すことはしない人だったのに。
『宮旭日の家で、粗相のないように』
「はい。気を付けます」
父はすぐにいつもの様子に変わったので、琴理の聞き間違いだったかもしれない。
気を取り直して背筋を伸ばした。
『宮旭日の当主夫妻とは、私たちも同席する形で今度逢うことになると思う。高校生の娘を預けるのだから、相応の挨拶の場は必要になるだろう』
「はい。ご当主夫妻様とは、わたしも数えるほどしか逢ったことはありませんが……」
『心配しなくて大丈夫だ、悪い人たちではない。……また悪癖が出てないといいんだが……』
悪い人たちではない、のあとに父がボソッと何か言ったが、琴理にははっきりとは聞こえなかった。
琴理は、こくりと唾を呑んだ。
「あの、父様、愛理は大丈夫ですか? 先ほど電話をしたのですが……」
『あ、ああ……心配しなくて大丈夫だ』
(やはり怒らせてしまったようです……)
父の歯切れの悪い答えに見えるのは、愛理が荒れている様子だ。
「申し訳ありません、父様……」
『いや、愛理も姉離れしなくちゃいけない。むしろ今まで引き留めて悪かった。宮旭日から再三要請があったのに……』
再び、父の声音に感情が見えた。
「? 要請、ですか?」
『あ。……それは気にするな。まあ、心護様がいらっしゃるなら大丈夫だ。ちなみにいつでも帰って来ていいからな』
「はい……っ」
――眼差しをほしいと思ってしまった。
でも、きっと自分は眼差しとは違う愛情をもらっている。
琴理を否定しない、という。
琴理が決めたことなら、それがいい。と、背中を押してくれた。
嫁ぐための勉強に時間を縛られていたけれど、一度も琴理を否定することは言わなかった両親。