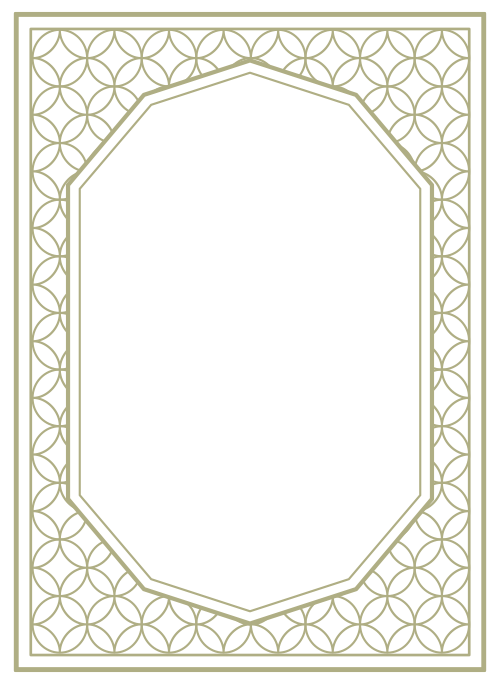「もともと、琴理さんはもう宮旭日の家で暮らしていて問題はなかったはずです。それを今まで、ご両親と愛理さんが引き留めるので延ばし延ばしになっていた話でしょう」
『………』
無言なことで愛理が、電話の向こうでぶすーっとむくれているのが琴理の目に浮かんだ。
が、両親と愛理が、というのは、琴理は初耳だった。電話が終わったら心護に訊いてみようと決める。
『……姉様が、そちらにいることをよしとされたのですか?』
「うん、わたしが決めたことよ、愛理」
『………姉様がそう仰るのなら……ああ! でもまだ姉様をお嫁にやりたくない……!』
愛理が、花嫁の親のようなことを言っている。
琴理はだんだん微笑ましくなってきた。
「大丈夫よ、愛理。花園の家にも帰るようにするから」
『本当ですね!? 約束ですよ!』
愛理はなんとか折れたが――電話が終わったあと、うわーん! と大泣きして愛理のお付きたちが大変な目に遭っていた。
「今のは妹君の個人的な電話か?」
「はい。両親より先に電話しておきたかったので。父様の携帯にもかけようと思います」
そう言って琴理は、次に父の電話にかけた。
『琴理か?』
琴理が「もしもし」と言う前に父の声がした。
厳しい父。厳格な、花園の当主。琴理の背筋が伸びた。
「はい、琴理です。ご迷惑をおかけして申し訳ありません、父様」
言葉とともに深く頭を下げる。
目の前にいるわけではないし、父から見えているわけでもないが、自然とそうしていた。
『いや、無事ならいいんだ』
「……はい」
父の感情の読めない反応に、琴理は委縮する。
言葉だけ聞けば優しいが、温度のない声音は他を圧倒する雰囲気がある。
だが、父も昔はこういう人ではなかったらしい。
陽気というほどではないが、人並に明るく、態度も柔らかかったと周囲から聞く。
一変させたのは、やはり琴理の母がたおれた件だ。
妻を失いかけると同時に、父は友人を失った。
すべては誤解させるような態度があった自分のせいだと己を戒め、琴理の母以外に笑みを向けることはなくなった。
琴理でさえ、あの一件以来自分に向けられた記憶はない。
父はすぐに話題を移した。
『心護様のお屋敷にいるとのことだったけど、琴理はそれでいいのか?』