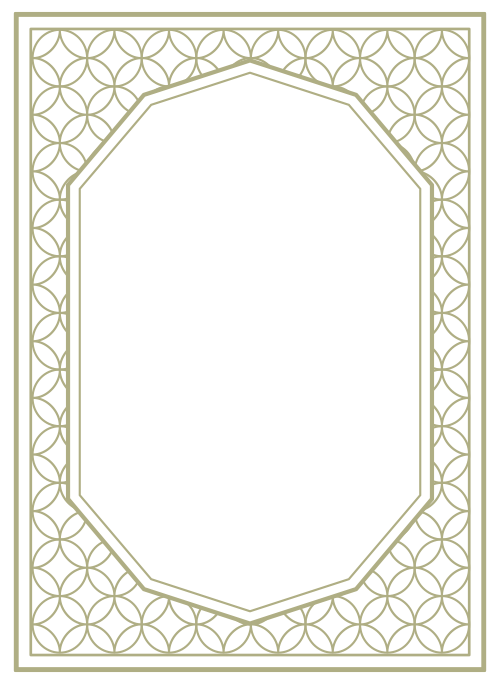左腕で琴理を抱きしめた心護が、右手のひらを上に向け、符(ふ)を構えている。
「なるほど、貴様が悪魔ですか。どうします? 若君」
公一と詩に両側から首のあたりに刃を当てられている悪魔だが、焦った様子はない。
「まあまあ、おれも退鬼師の家だってわかっててやってくるしかなかったんだからちょっとくらい甘く見てくれ」
「どういうつもりだ」
「その娘に呼び出された以上、何かしないといけないわけよ。契約しちまったしな」
「………」
(わ、わたしはなんてことを……!)
やはり悪魔なんて存在を頼ろうとした代償が発生してしまった。
琴理は、自分の命を愛理にあげてほしいという契約を交わしたのだ。
自分の命が存在してもいいのかもしれない、なんて思い始めた矢先とはいえ、この悪魔に対して琴理はそう契約することを望んでしまっている。
「し、心護様! 申し訳ございません……! わたし――」
「いい、琴理。少し俺に話させてもらっていいか?」
心護の腕の中で見あげた琴理に向けられたのは、『心配いらない』と優しく語る眼差しだった。
琴理は居たたまれなくなってうつむく。
こんな自分のために、どうして心護は、公一は、詩は、宮旭日の人たちは――心を砕いてくれるのだろう。
こんな、独りよがりしか出来ない、無能な小娘なんかのために。
「本当に琴理は、完全なる形で契約をしたか?」
「おおっと、これは痛い。どういう意味かな?」
小鳥が、すっと影から抜け出て琴理と心護の前にあるテーブルに乗った。
若月夫妻は変わらず鋭い視線で刀を小鳥の近くに突きつけている。
「琴理がお前に託したものは、完全な形で『契約』されたものか、と訊いている。一か所でも不備があるなら、それは『契約』したことにならない」
「んん~、まあ、さすが退鬼師の跡取りといったところか。抜け目ない。だがそれをおれが簡単に話すと思うか?」
ひょいっと片羽を動かすと、即座に両側から刃先を突きつけられて、小鳥は一瞬びくっとした。
「言いなさい」
「刎ねた首を持って帰りますか? 悪魔なのだから何回刎ねることが出来るのでしょうね?」
「二人とも俺よりキレるのやめて」