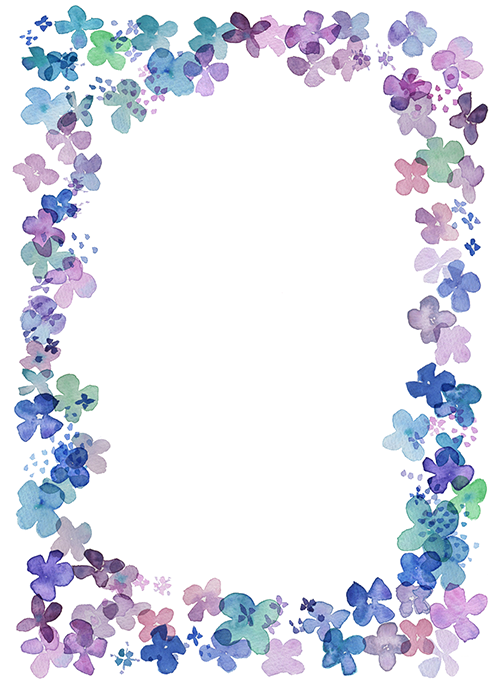私が伝えたい言葉は「ごめんなさい」、それだけだった。
私は半年前までソフトテニス部に所属していた。当時の私は毎日泣いていた。休日なんてほとんどなくて、半強制的に加入させられたクラブチームの練習では他県まで行って試合をし、土日はもちろん平日の夜九時まで練習に明け暮れていた。
私は正直部活が好きではなかった。
こんなに体力も精神も消耗するなんて部活に入る前は想像もできなかったし、何より私の親は教育にも厳しい人だった。部活に精を出せば勉強が疎かになってしまう、ただ勉強に励めばテニスの技術や感覚なんて三日やらないだけで失われる。
だから私は何事にもがむしゃらに取り組んだ。
その結果、周りの人から浴びせられた言葉は「何ムキになってやってるの?」「もしかして……がり勉?ウケるんだけど~」だった。
私はもう何かをがむしゃらに取り組むのは辞めにしようと思った。
頑張っているのに評価もされず、蔑まれ嘲笑われる。他人から見た自分は滑稽なんだと気づいた瞬間涙が止まらなかった。
なんでこんなにも辛いことを続けているんだろうと思っていた。逃げればいいと思う人もいるかもしれない。しかし私が部活から抜ければ団体戦においてきっとチームは負けてしまう。今まで必死に頑張ってきたチームメイトを見殺しにして自分だけが楽になるなんて、許されるわけなかった。
そんな時に出会ったのがとある少女だ。
私が彼女と出会ったのはとある他県での試合だった。私は一瞬にして彼女の動きに見とれた。無駄のないフォームに、どれだけ相手に振り回されてもボロボロになるまでボールを打ち返すために走り続ける忍耐力。呼吸が苦しそうだった、ベンチからじっと彼女のことだけを見ていた私には、震える喉から彼女が今にも倒れそうだということが分かった。けれど君はそれでもコートを駆けていた。
見とれている間に試合は終わっていた。審判が審判台から降りてきて、結果を伝える。
彼女のペアの勝ちだった。律儀にお辞儀をしたあと、ふらつきながらもベンチに戻ってきた君は満面の笑みを浮かべている。
その瞬間、私は恋に落ちた。
人がひたむきに努力する姿はこんなにも美しいのだと知った。ずっと動き回っていたせいで紅潮した頬、息切れしながら上下する肩、顎を伝う汗。全てが愛おしかった。がむしゃらな姿は決して滑稽なんかじゃない。君の姿は証明してくれた。努力というものを肯定してくれた。凄く、凄く、好きだ。馬鹿みたいに真っすぐな気持ちが溢れて止まらなかった。
それから私たちは何度か共に試合をし、仲良くなっていった。
いつの間にかテニス以外の話もできるようになり、プライベートの相談も互いにするようになった。
親しみと比例するように私の好きという気持ちも肥大していった。
けれど頭の片隅から消えない事実、君は女の子なのだ。
君の姿を見る度に咄嗟に浮かんだ言葉は「ごめんなさい」だった。
一緒にペアを組んだ時に上手くできなくてごめんなさい、緊張して時々うまく話せなくてごめんなさい。
好きになってごめんなさい。
真っ直ぐで時々厳しいことも言うけれど、本当は誰よりも優しい彼女は私がきっと想いを伝えてもあからさまに引いたりはしないだろう。
けれど傷つけてしまうかもしれない。
懸念はずっと消えず、君と何か話す度に肺を圧迫した。
そんな矢先ある出来事が起こった。
その日はいつにもなく彼女は不調だった。狙う球全てがコート外に飛んで行ってしまっている。食いしばりながらも必死にラケットを振り続ける彼女を見て、能天気な私は今日も頑張っているなぁとしか感じなかった。
お昼休憩になり彼女を探しに行くと、君は一人で泣いていた。
校舎の横の狭いスペースで小さな背中を震わせる姿を見つけた瞬間、私は全身が硬直した。
気まずい、一人にしてあげよう。そういう感情ではない。
言葉通り私はどうすればいいのか分からなくなってしまった。
このまま見ないフリをして、後で合流してきた君に何でもなかったように笑いかければいいのか。
今声を掛けて、話を聞いてあげればいいのか。
何もかもが分からず頭が真っ白になってその場に立ち尽くすほかなかった。
気配に気づいたのか小さな背中はもぞもぞと動いて、私を視線を絡ませる。
すると、彼女の潤む瞳に引き寄せられるかのように私は体の赴くままに歩き、やがて君の隣に腰かけた。
暫くの沈黙のあと、君はため息を零すように言った。
「うまくできない。頑張ってるのに、うまくいかない。……自分のことが嫌いになりそうだよ」
私は今まで、彼女と別に付き合いたいなんて思わなかった。
思えなかった。
言ってしまえば全部終わるからだ。
信頼も、友情も、恋心も。
けれどその瞬間、どうしようもなく「好きだ」と伝えたかった。
あなたが例え自分自身のことを好きでなくても、君のことを好きな人はちゃんとここにいるよと伝えたかった。
私はその場で何も言えなかった。気が付けば隣で泣いていたはずの君はいなくなっていた。数メートル先を一人で、足を引きずりながらも歩いている影だけがその場にこびりついていた。
私はいつまでも意気地なしだ。
苦しんでいる好きな人に対し、何か言葉を掛けてあげることすらできない。
どの言葉を掛けたって彼女の苦しみを全て除くことはできない、そんなの分かっている。
彼女が背負う重圧は私なんかでは到底理解できなくて、そんな私が何か言ったところで君は立ち直れるか?と問われれば、そうではないと分かっている。
けれど、何か一つでも言えたら。
あの場で無責任にも「大丈夫だよ」と言えたら。
君は救われたのではないだろうか。
考えれば考えるほど、目があった瞬間の、息切れをしながら試合をしている時よりも苦しそうに歪む瞳が頭から離れなくて、私は何も言わず午後の練習をせずに帰ってしまった。
数日後
華奢な背中を見つけた私は咄嗟に声を掛ける。
「あの日は、ごめん」
振り向いて笑いかける君の目尻は、もう赤くなかった。
首を振って私の謝罪を否定する表情は、私が出会った誰よりもあたたかかった。
「ううん。傍にいてくれてありがとう。他の人にも私のこと話さなかったんでしょ?それだけで救われたよ」
その言葉を聞いた刹那、私の中で何か弾けたような気がした。
今まで沢山救われてきたのは、私のほうだと言うのに。
私は幸せ者だと思った。相手が男でも女でも関係ないじゃないか。こんなに素敵な人を好きになれたことが、幸せで堪らない。
私が伝えるべきなのは初めから「ごめんなさい」ではないだろう。
ゆっくり口を開くと同時に、君が言葉を被せる。
「うわっ、ごめん。コーチに呼ばれてるわ……。またね!」
あれからというもの受験があり、彼女には会えていない。
しかし、私は無事に部活を最後までやりきることができた。
辛いことはあれからも沢山あったが、その度に君の姿を思い出して最後まで頑張った結果、最後の大会は県大会まで進むことが出来た。全て君のお陰だ。
部活の後輩から度々現状を耳にすることがあるが、どうやら元気にやっているそうだ。先日も何か大きい大会で入賞するほどの成績を収めたらしい。
今でも私の憧れは変わらず、君だ。
何カ月も会っていないのに、未だに部活のことを思い出そうとすると頭を過るのは辛い練習ではなく君の姿だった。
思い出すのは、あの日のように泣き腫らす顔ではなく、いつだって愚直に努力し続けた君の背中だ。
努力は惨めなものではないと教えてくれた汗だくでも走り続けていた、君の背中だ。
今度、会いにいってもいいかな。
君のお気に入りのお菓子を持って行ってさ、もう高校生なんだよって他愛のない談笑もしたいな。
でもその前にどうか、一言言わせてほしい。
照れていても、噛んでしまっても、いつもみたいに笑って許して。
「あの日は、ありがとう」
私は半年前までソフトテニス部に所属していた。当時の私は毎日泣いていた。休日なんてほとんどなくて、半強制的に加入させられたクラブチームの練習では他県まで行って試合をし、土日はもちろん平日の夜九時まで練習に明け暮れていた。
私は正直部活が好きではなかった。
こんなに体力も精神も消耗するなんて部活に入る前は想像もできなかったし、何より私の親は教育にも厳しい人だった。部活に精を出せば勉強が疎かになってしまう、ただ勉強に励めばテニスの技術や感覚なんて三日やらないだけで失われる。
だから私は何事にもがむしゃらに取り組んだ。
その結果、周りの人から浴びせられた言葉は「何ムキになってやってるの?」「もしかして……がり勉?ウケるんだけど~」だった。
私はもう何かをがむしゃらに取り組むのは辞めにしようと思った。
頑張っているのに評価もされず、蔑まれ嘲笑われる。他人から見た自分は滑稽なんだと気づいた瞬間涙が止まらなかった。
なんでこんなにも辛いことを続けているんだろうと思っていた。逃げればいいと思う人もいるかもしれない。しかし私が部活から抜ければ団体戦においてきっとチームは負けてしまう。今まで必死に頑張ってきたチームメイトを見殺しにして自分だけが楽になるなんて、許されるわけなかった。
そんな時に出会ったのがとある少女だ。
私が彼女と出会ったのはとある他県での試合だった。私は一瞬にして彼女の動きに見とれた。無駄のないフォームに、どれだけ相手に振り回されてもボロボロになるまでボールを打ち返すために走り続ける忍耐力。呼吸が苦しそうだった、ベンチからじっと彼女のことだけを見ていた私には、震える喉から彼女が今にも倒れそうだということが分かった。けれど君はそれでもコートを駆けていた。
見とれている間に試合は終わっていた。審判が審判台から降りてきて、結果を伝える。
彼女のペアの勝ちだった。律儀にお辞儀をしたあと、ふらつきながらもベンチに戻ってきた君は満面の笑みを浮かべている。
その瞬間、私は恋に落ちた。
人がひたむきに努力する姿はこんなにも美しいのだと知った。ずっと動き回っていたせいで紅潮した頬、息切れしながら上下する肩、顎を伝う汗。全てが愛おしかった。がむしゃらな姿は決して滑稽なんかじゃない。君の姿は証明してくれた。努力というものを肯定してくれた。凄く、凄く、好きだ。馬鹿みたいに真っすぐな気持ちが溢れて止まらなかった。
それから私たちは何度か共に試合をし、仲良くなっていった。
いつの間にかテニス以外の話もできるようになり、プライベートの相談も互いにするようになった。
親しみと比例するように私の好きという気持ちも肥大していった。
けれど頭の片隅から消えない事実、君は女の子なのだ。
君の姿を見る度に咄嗟に浮かんだ言葉は「ごめんなさい」だった。
一緒にペアを組んだ時に上手くできなくてごめんなさい、緊張して時々うまく話せなくてごめんなさい。
好きになってごめんなさい。
真っ直ぐで時々厳しいことも言うけれど、本当は誰よりも優しい彼女は私がきっと想いを伝えてもあからさまに引いたりはしないだろう。
けれど傷つけてしまうかもしれない。
懸念はずっと消えず、君と何か話す度に肺を圧迫した。
そんな矢先ある出来事が起こった。
その日はいつにもなく彼女は不調だった。狙う球全てがコート外に飛んで行ってしまっている。食いしばりながらも必死にラケットを振り続ける彼女を見て、能天気な私は今日も頑張っているなぁとしか感じなかった。
お昼休憩になり彼女を探しに行くと、君は一人で泣いていた。
校舎の横の狭いスペースで小さな背中を震わせる姿を見つけた瞬間、私は全身が硬直した。
気まずい、一人にしてあげよう。そういう感情ではない。
言葉通り私はどうすればいいのか分からなくなってしまった。
このまま見ないフリをして、後で合流してきた君に何でもなかったように笑いかければいいのか。
今声を掛けて、話を聞いてあげればいいのか。
何もかもが分からず頭が真っ白になってその場に立ち尽くすほかなかった。
気配に気づいたのか小さな背中はもぞもぞと動いて、私を視線を絡ませる。
すると、彼女の潤む瞳に引き寄せられるかのように私は体の赴くままに歩き、やがて君の隣に腰かけた。
暫くの沈黙のあと、君はため息を零すように言った。
「うまくできない。頑張ってるのに、うまくいかない。……自分のことが嫌いになりそうだよ」
私は今まで、彼女と別に付き合いたいなんて思わなかった。
思えなかった。
言ってしまえば全部終わるからだ。
信頼も、友情も、恋心も。
けれどその瞬間、どうしようもなく「好きだ」と伝えたかった。
あなたが例え自分自身のことを好きでなくても、君のことを好きな人はちゃんとここにいるよと伝えたかった。
私はその場で何も言えなかった。気が付けば隣で泣いていたはずの君はいなくなっていた。数メートル先を一人で、足を引きずりながらも歩いている影だけがその場にこびりついていた。
私はいつまでも意気地なしだ。
苦しんでいる好きな人に対し、何か言葉を掛けてあげることすらできない。
どの言葉を掛けたって彼女の苦しみを全て除くことはできない、そんなの分かっている。
彼女が背負う重圧は私なんかでは到底理解できなくて、そんな私が何か言ったところで君は立ち直れるか?と問われれば、そうではないと分かっている。
けれど、何か一つでも言えたら。
あの場で無責任にも「大丈夫だよ」と言えたら。
君は救われたのではないだろうか。
考えれば考えるほど、目があった瞬間の、息切れをしながら試合をしている時よりも苦しそうに歪む瞳が頭から離れなくて、私は何も言わず午後の練習をせずに帰ってしまった。
数日後
華奢な背中を見つけた私は咄嗟に声を掛ける。
「あの日は、ごめん」
振り向いて笑いかける君の目尻は、もう赤くなかった。
首を振って私の謝罪を否定する表情は、私が出会った誰よりもあたたかかった。
「ううん。傍にいてくれてありがとう。他の人にも私のこと話さなかったんでしょ?それだけで救われたよ」
その言葉を聞いた刹那、私の中で何か弾けたような気がした。
今まで沢山救われてきたのは、私のほうだと言うのに。
私は幸せ者だと思った。相手が男でも女でも関係ないじゃないか。こんなに素敵な人を好きになれたことが、幸せで堪らない。
私が伝えるべきなのは初めから「ごめんなさい」ではないだろう。
ゆっくり口を開くと同時に、君が言葉を被せる。
「うわっ、ごめん。コーチに呼ばれてるわ……。またね!」
あれからというもの受験があり、彼女には会えていない。
しかし、私は無事に部活を最後までやりきることができた。
辛いことはあれからも沢山あったが、その度に君の姿を思い出して最後まで頑張った結果、最後の大会は県大会まで進むことが出来た。全て君のお陰だ。
部活の後輩から度々現状を耳にすることがあるが、どうやら元気にやっているそうだ。先日も何か大きい大会で入賞するほどの成績を収めたらしい。
今でも私の憧れは変わらず、君だ。
何カ月も会っていないのに、未だに部活のことを思い出そうとすると頭を過るのは辛い練習ではなく君の姿だった。
思い出すのは、あの日のように泣き腫らす顔ではなく、いつだって愚直に努力し続けた君の背中だ。
努力は惨めなものではないと教えてくれた汗だくでも走り続けていた、君の背中だ。
今度、会いにいってもいいかな。
君のお気に入りのお菓子を持って行ってさ、もう高校生なんだよって他愛のない談笑もしたいな。
でもその前にどうか、一言言わせてほしい。
照れていても、噛んでしまっても、いつもみたいに笑って許して。
「あの日は、ありがとう」