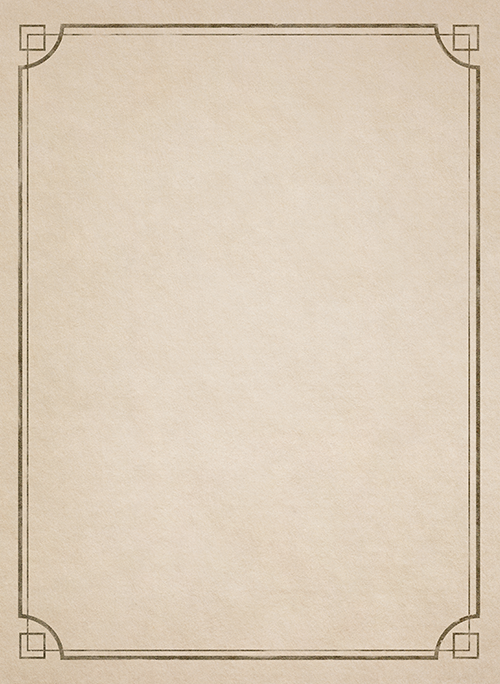俺のクラスはいつも席がひとつぽっかり空いていた。
その席の主の名前は――七海葵。
生まれつきの持病があって、入退院を繰り返している俺の――幼馴染みだった。
「学校はどう? 楽しい?」
「……楽しいよ」
俺は毎日のように葵の見舞いにいった。
小中、そして高校になってもその日課は変わらない。
でも――俺は嘘をつくようになった。
「高校生になるとやっぱり放課後とかみんなで遊びに行くの? クレープ食べたり、ゲームセンター行ったり」
「そうだね。たまに、行くことあるよ」
嘘だ。
俺は友達なんか一人もいない。
息をひそめて教室にいて、囁かれる陰口や、クラスの一軍からの嫌なからかいをへらへらしながらかわしている。
「ほら、この間狸小路に水族館が出来たんだ。今度、そこに行くんだ。ペンギンがいてさあ……」
嘘だ。
ニュースで見ただけだ。
でも、そうやって笑うと葵はいつも楽しそうに笑うから。彼女の笑顔が見たかったから。俺は嘘をつく。
「いいなあ……私も行ってみたいなあ」
「退院したら一緒に行こう」
「でも……私がまた学校に行ける頃には、柊くんは他の友達と遊ぶんだろうな」
「そんなことない!」
強くいうと、葵は目を丸くした。
「俺は、葵が一番だから!」
「柊くん……」
「約束! 葵が退院したら、一緒に学校行くんだ! 次の手術で、きっちり治して……それで、学校行けるようになったら一日も休まないで行くんだ!」
「ええ……いけるかなあ?」
困ったように彼女はヘラリと笑う。
「そうだな。葵は寝ぼすけだから。俺、毎日起こしに行くよ。それで……一緒に行くんだ。絶対だよ」
「……柊くんは、優しいねえ」
そういって、彼女はいつものように笑うんだ。
そんな約束果たせない。もう子供じゃない俺たちは理解していた。
葵の寿命が迫っていること。もう、学校には行けないかも知れないこと。
だから俺はなんとしても学校に行くんだ。
虐められても、無視されても。どれだけ辛くても――。
あれだけ学校に行きたいと願っている葵のぶんまで、俺がなんとしてでも通うんだ。
そうしないと、葵に申し訳ないから。
でも――。
「――なにを、してるの」
ある朝、学校に行くと葵の席に花が置かれていた。
「えー、お花だよ。どうせあの子もうすぐ死んじゃうんでしょう?」
「入学して一日も来てない死にかけのクラスメイトなんて、いないのも同然だろ」
そうやって一軍共は笑う。
俺は生まれて初めて、頭に血が上った。
「――っ! ふざけんなっ!」
思い切り、殴ってしまった。
そして俺は一週間の停学処分。それが開けると、さらなる地獄が待っていた。
「よお、暴力陰キャ。慰謝料寄越せよ」
奴らが俺に金を無心するようになった。
「この間、お前に殴られたところが痛くてよぉ……存分にやり返さなくっちゃなあ!」
陰湿に、見えないところを何度も何度も殴られた。
「あははっ! 動画撮っておこ!」
霰もしない動画を撮られて、加工されて世界中にばら撒かれた。
教師も、クラスメイトも見て見ぬ振り。まさに地獄だ。
「柊くん、学校楽しい?」
「……………………うん」
それでも、葵の前では懸命に笑って見せた。
心配なんてさせたくなかったから。
だって……今の彼女は、もう起き上がる気力も無くて。
点滴に繋がれていて。腕は細くて。
いつ、その目を閉じてもおかしくない状態だったから。
「柊くん……ごめんね。一緒に、学校いけないね……」
息も絶え絶えになりながら、彼女は俺の手を握る。
「諦めるなよ……まだ、まだ治るって……約束しただろ。一緒に学校行くって!」
「あのね、あのね……柊くん。約束があるの――」
そう、か細い声で呟いた。
「――私を、看取って」
「え?」
「人は死ぬ間際になると死神さんが見えるんだって」
「なに……いってんだよ」
震えながらそう言うと、彼女はヘラリと笑う。
「……だから、柊くんが死神さんだったらいいのになあって。そうしたら、私は柊くんが看取ってくれるから」
「……やめろよ。そんなこと、いうなって」
「柊くん。私を看取って、それで……私の魂を刈り取ってよ」
耳元で呟かれた言葉。
そして彼女はそれきり目を覚まさなくなった。
唯一の心の支えだった。そんな彼女がこの世からもうすぐ消える。
俺に残されるのは地獄だけだ。
そんな日々耐えられない。
俺の心はぽっきり折れて――ある日の早朝、俺の足はあの場所に向かっていた。
*
「――や、来てくれると思ったよ」
「葵」
彼女は立っていた。
そこは学校の屋上。フェンスの向こうに葵が立っている。
「どんな感じなんだろうね、ここから飛び降りるの」
「……やめるんだ」
風が彼女の髪を揺らす。
俺は震えながら、葵の名を呼んだ。
「――死神さん、思い出した?」
フェンス越しに、彼女が微笑む。
俺は走って、彼女の手を掴んだ。がしゃんと音が鳴る。
「やめろ、やめるんだ葵――そこから飛び降りたのは――」
俺だ。
それ以上生きるのが辛くなって、俺は早朝に家を抜けだして……。
いつも一人逃げ込んできていたこの屋上から、朝焼けの空を見ながら飛び降りたんだ。
全員から無視されていたのは、俺だ。
命を絶とうとしていたのは、俺だ。
「私は……もうすぐ死んじゃう。それは変えられない。でも……君は違うよね、柊くん」
彼女は真っ直ぐ、俺を見る。
死の淵に立とうとしている俺を、君は救おうとしてくれていたんだ。
自分の最後の命を使って、今すぐあの世に行こうとしている俺を引き留めてくれていたのか。
「私、知ってたよ。柊くんが嘘ついてたの。気付かないと思った?」
君は嘘が下手だね、と彼女は笑う。
「私も君を追い詰めていた一人だったのかもしれない。でも……」
葵は俺を見る。その眼差しには怒りと悲しみの色が滲んでいた。
「命を無駄にする人、私大嫌いだよ」
「――っ!」
強い言葉に俺は、フェンスを強く握る。
「じゃあどうしろっていうんだよ! 無視されて、暴力振るわれて……どうやって、どうやって生きていけば良いんだ! それに、葵までいなくなったら、俺……生きる意味なんかないんだよ!」
「でも、柊くんはまだ生きてる! それなら君の寿命、私にちょうだいよっ!」
同じように叫んだ。
「いつも柊くんの話を聞いてて辛かった。私は外に出られないのに! 私もみんなと同じように学校に行きたいだけなのに! どうして私だけ死ななきゃいけないの!?」
俺も、葵も泣いていた。
「葵……」
「やっといえた……私の本心。やっと聞けた……柊くんの本心」
涙を拭いながら、葵はフェンス越しに俺の手を握る。
「悪いのは柊くんじゃない。地獄に無理に立ち向かう必要も無い。つきたくもない嘘をつく必要も無い。逃げても良い。でも……柊くんが死ぬ必要はない」
「……でも、どうしたら」
「病室が、学校だけが世界じゃない。外を見たら、世界は広いんだよ。空はこんなにも高い。柊くんを縛るものはなにもない。そして柊くんの寿命は今じゃない。君が死ぬのはずっとずっと先だよ」
「……なんでそんなことがわかるんだ」
そうして彼女はいつものように笑うのだ。
「わかるよ。だって、君はまだ生きてるから」
そして葵は両手を広げ、そのまま背中から落ちた。
「葵!」
「生きて。生きてよ、柊くん」
それは彼女の願い。
「私は、明日死ぬよ。柊くんはどうするの?」
手を伸ばすが届かない。
そして彼女の体はゆっくりとゆっくりと地面へと落ちていく。
「――約束だよ。私の最期を、ちゃんと看取ってね」
――七海葵が死ぬまで、あと数時間。
その席の主の名前は――七海葵。
生まれつきの持病があって、入退院を繰り返している俺の――幼馴染みだった。
「学校はどう? 楽しい?」
「……楽しいよ」
俺は毎日のように葵の見舞いにいった。
小中、そして高校になってもその日課は変わらない。
でも――俺は嘘をつくようになった。
「高校生になるとやっぱり放課後とかみんなで遊びに行くの? クレープ食べたり、ゲームセンター行ったり」
「そうだね。たまに、行くことあるよ」
嘘だ。
俺は友達なんか一人もいない。
息をひそめて教室にいて、囁かれる陰口や、クラスの一軍からの嫌なからかいをへらへらしながらかわしている。
「ほら、この間狸小路に水族館が出来たんだ。今度、そこに行くんだ。ペンギンがいてさあ……」
嘘だ。
ニュースで見ただけだ。
でも、そうやって笑うと葵はいつも楽しそうに笑うから。彼女の笑顔が見たかったから。俺は嘘をつく。
「いいなあ……私も行ってみたいなあ」
「退院したら一緒に行こう」
「でも……私がまた学校に行ける頃には、柊くんは他の友達と遊ぶんだろうな」
「そんなことない!」
強くいうと、葵は目を丸くした。
「俺は、葵が一番だから!」
「柊くん……」
「約束! 葵が退院したら、一緒に学校行くんだ! 次の手術で、きっちり治して……それで、学校行けるようになったら一日も休まないで行くんだ!」
「ええ……いけるかなあ?」
困ったように彼女はヘラリと笑う。
「そうだな。葵は寝ぼすけだから。俺、毎日起こしに行くよ。それで……一緒に行くんだ。絶対だよ」
「……柊くんは、優しいねえ」
そういって、彼女はいつものように笑うんだ。
そんな約束果たせない。もう子供じゃない俺たちは理解していた。
葵の寿命が迫っていること。もう、学校には行けないかも知れないこと。
だから俺はなんとしても学校に行くんだ。
虐められても、無視されても。どれだけ辛くても――。
あれだけ学校に行きたいと願っている葵のぶんまで、俺がなんとしてでも通うんだ。
そうしないと、葵に申し訳ないから。
でも――。
「――なにを、してるの」
ある朝、学校に行くと葵の席に花が置かれていた。
「えー、お花だよ。どうせあの子もうすぐ死んじゃうんでしょう?」
「入学して一日も来てない死にかけのクラスメイトなんて、いないのも同然だろ」
そうやって一軍共は笑う。
俺は生まれて初めて、頭に血が上った。
「――っ! ふざけんなっ!」
思い切り、殴ってしまった。
そして俺は一週間の停学処分。それが開けると、さらなる地獄が待っていた。
「よお、暴力陰キャ。慰謝料寄越せよ」
奴らが俺に金を無心するようになった。
「この間、お前に殴られたところが痛くてよぉ……存分にやり返さなくっちゃなあ!」
陰湿に、見えないところを何度も何度も殴られた。
「あははっ! 動画撮っておこ!」
霰もしない動画を撮られて、加工されて世界中にばら撒かれた。
教師も、クラスメイトも見て見ぬ振り。まさに地獄だ。
「柊くん、学校楽しい?」
「……………………うん」
それでも、葵の前では懸命に笑って見せた。
心配なんてさせたくなかったから。
だって……今の彼女は、もう起き上がる気力も無くて。
点滴に繋がれていて。腕は細くて。
いつ、その目を閉じてもおかしくない状態だったから。
「柊くん……ごめんね。一緒に、学校いけないね……」
息も絶え絶えになりながら、彼女は俺の手を握る。
「諦めるなよ……まだ、まだ治るって……約束しただろ。一緒に学校行くって!」
「あのね、あのね……柊くん。約束があるの――」
そう、か細い声で呟いた。
「――私を、看取って」
「え?」
「人は死ぬ間際になると死神さんが見えるんだって」
「なに……いってんだよ」
震えながらそう言うと、彼女はヘラリと笑う。
「……だから、柊くんが死神さんだったらいいのになあって。そうしたら、私は柊くんが看取ってくれるから」
「……やめろよ。そんなこと、いうなって」
「柊くん。私を看取って、それで……私の魂を刈り取ってよ」
耳元で呟かれた言葉。
そして彼女はそれきり目を覚まさなくなった。
唯一の心の支えだった。そんな彼女がこの世からもうすぐ消える。
俺に残されるのは地獄だけだ。
そんな日々耐えられない。
俺の心はぽっきり折れて――ある日の早朝、俺の足はあの場所に向かっていた。
*
「――や、来てくれると思ったよ」
「葵」
彼女は立っていた。
そこは学校の屋上。フェンスの向こうに葵が立っている。
「どんな感じなんだろうね、ここから飛び降りるの」
「……やめるんだ」
風が彼女の髪を揺らす。
俺は震えながら、葵の名を呼んだ。
「――死神さん、思い出した?」
フェンス越しに、彼女が微笑む。
俺は走って、彼女の手を掴んだ。がしゃんと音が鳴る。
「やめろ、やめるんだ葵――そこから飛び降りたのは――」
俺だ。
それ以上生きるのが辛くなって、俺は早朝に家を抜けだして……。
いつも一人逃げ込んできていたこの屋上から、朝焼けの空を見ながら飛び降りたんだ。
全員から無視されていたのは、俺だ。
命を絶とうとしていたのは、俺だ。
「私は……もうすぐ死んじゃう。それは変えられない。でも……君は違うよね、柊くん」
彼女は真っ直ぐ、俺を見る。
死の淵に立とうとしている俺を、君は救おうとしてくれていたんだ。
自分の最後の命を使って、今すぐあの世に行こうとしている俺を引き留めてくれていたのか。
「私、知ってたよ。柊くんが嘘ついてたの。気付かないと思った?」
君は嘘が下手だね、と彼女は笑う。
「私も君を追い詰めていた一人だったのかもしれない。でも……」
葵は俺を見る。その眼差しには怒りと悲しみの色が滲んでいた。
「命を無駄にする人、私大嫌いだよ」
「――っ!」
強い言葉に俺は、フェンスを強く握る。
「じゃあどうしろっていうんだよ! 無視されて、暴力振るわれて……どうやって、どうやって生きていけば良いんだ! それに、葵までいなくなったら、俺……生きる意味なんかないんだよ!」
「でも、柊くんはまだ生きてる! それなら君の寿命、私にちょうだいよっ!」
同じように叫んだ。
「いつも柊くんの話を聞いてて辛かった。私は外に出られないのに! 私もみんなと同じように学校に行きたいだけなのに! どうして私だけ死ななきゃいけないの!?」
俺も、葵も泣いていた。
「葵……」
「やっといえた……私の本心。やっと聞けた……柊くんの本心」
涙を拭いながら、葵はフェンス越しに俺の手を握る。
「悪いのは柊くんじゃない。地獄に無理に立ち向かう必要も無い。つきたくもない嘘をつく必要も無い。逃げても良い。でも……柊くんが死ぬ必要はない」
「……でも、どうしたら」
「病室が、学校だけが世界じゃない。外を見たら、世界は広いんだよ。空はこんなにも高い。柊くんを縛るものはなにもない。そして柊くんの寿命は今じゃない。君が死ぬのはずっとずっと先だよ」
「……なんでそんなことがわかるんだ」
そうして彼女はいつものように笑うのだ。
「わかるよ。だって、君はまだ生きてるから」
そして葵は両手を広げ、そのまま背中から落ちた。
「葵!」
「生きて。生きてよ、柊くん」
それは彼女の願い。
「私は、明日死ぬよ。柊くんはどうするの?」
手を伸ばすが届かない。
そして彼女の体はゆっくりとゆっくりと地面へと落ちていく。
「――約束だよ。私の最期を、ちゃんと看取ってね」
――七海葵が死ぬまで、あと数時間。