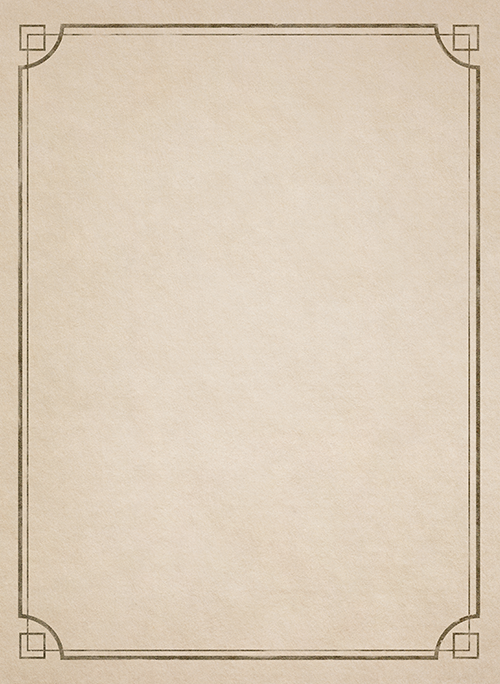「……ただいま」
七海葵の両親が帰ってきたのは深夜一時を回った頃だった。
とうの本人はといえば、ベッドで俺に背中を向けてすやすやと寝息を立てている。
俺の体はどうやら睡眠を必要としていないようで、この二日間一切眠気は襲ってこない。
(――随分遅い帰りだな。子供を放って両親揃って夜遊びか?)
なんて悪態を心の中で呟きながら、俺はそっと七海葵の部屋を出た。
この三日間、彼女は心底楽しそうに過ごしているが俺はそれが不可解極まりなかった。
学校といい、両親といい――彼女の周辺は最悪だ。
どうして彼女がへらへらと笑えているのか到底理解に苦しむ。
そしてなにより、そんな彼女や周囲の環境に対して本人以上に苛立ちを覚えている自分に腹が立つ。
(俺は七海葵の死を看取ればいいだけのはずだ)
彼女はどう足掻いたって明後日には亡くなる。
それだというのに、 自分でも何故こんなに苛立っているのか理解できず余計に苛立ちは募っていくばかり。
憤りながら、俺は階段を降りリビングへと向かう。
扉のすき間からそっと中の様子を伺うと、彼女の母親がダイニングテーブルに突っ伏していた。
(酔っ払って帰ってきたのかよ。良いご身分で……)
相手に自分の姿が見えていないのをいいことに、俺はずかずかとリビングに上がり込む。突っ伏している母親の背中を、父親がやるせなさそうに撫でている。
「……ううっ。どうして……」
(…………泣いてる?)
酔っているわけじゃない。
母親は泣いていた。そしてその泣いている母を父が慰めている。
「わ、私がもっとあの子を見てあげなかったから。私のせいよ……」
祈るように組んだ手は力を込めすぎて真っ白になっている。
(そこで泣くなら今すぐ娘と向き合ったらどうだ)
彼女がどれだけ懸命に笑顔を浮かべているのかこの親はわかっているのだろうか。
俺が今すぐ七海を起せば和解できるかもしれない。
部屋に戻ろう。そうして背を向けたとき、母親がまた口を開いた。
「――柊」
「――――は?」
聞き覚えのない名前だった。
シュウ? 誰だ? 呼ぶべきは葵じゃないのか?
いや――違う。
これは――。
「――っ!?」
ずきんと頭が痛んだ。
「柊……柊……私を一人にしないで……」
母親がその名を呼ぶ度に、頭痛が酷くなる。
まるで頭に心臓があるみたいだ。
どくんどくんと脈を打って、平衡感覚を失う。
「……っ、なんだよ……これは!」
壁伝いに必死に階段を上る。
部屋までが異様に遠く感じた。
「……柊……シュウ……」
名を呟きながらこれまでのことを思い出す。
記憶を失った自分。
三日後に看取らなければいけない少女。
「……っ、ぐ!」
ずきんと頭が脈打つ度、妙な記憶が頭に流れ込む。
「病室……女の子……」
夕方の病室。
制服姿の少年と、ベッドの背もたれに凭れかかりながら微笑んでいる少女。
少年は俺で……少女は葵だ……。
「これは……俺の記憶」
息も絶え絶えに部屋の扉を開けた。
その瞬間、冷たい夜風がびゅうっと吹き抜けていく。
「……葵?」
ベッドで眠っていたはずの七海の姿が消えている。
開け放たれた窓。カーテンが揺れ、一枚の紙がひらひらと俺の元へ飛んできた。
《死神さん あの場所で待ってるよ》
七海の字。
「あの場所って……」
どこだよ、そういいかけた時また頭痛が酷くなった。
「…………ぐっ!」
そのまま倒れた。
目の前がぐるぐると周り、意識を保っていられない。
倒れた視界の端っこに、ベッドが見える。
ベッドの下に、いつか無くしたキーホルダーが落ちていた。
よく見舞いにいっていたあの子が作ったという、シマエナガの編みぐるみ。
「こんなところにあったんだ……」
手を伸ばそうとするが体が動かない。
あれ――どうして俺の物がここに?
いや、違う。
男物の部屋。見えないクラスメイト。帰ってこない家族。
七海葵ではない、聞き覚えのある名前――これは――。
「ああ――俺だ」
思い出した。
俺の名前は市川柊。
この家も、あの両親も、あの学校も、全部全部、俺のものだ。
なら、七海葵は――?
彼女は一体――?
手に握り締めたメモを見る。
『――約束、だよ』
脳裏に彼女の声が響く。
ああ、いかなきゃ。彼女の元へ。
もう、時間がないから。
俺は痛む体を引きずって、外に出た。
七海葵――彼女が、葵が俺を待ってる。
――七海葵が死ぬまで、あと一日。
七海葵の両親が帰ってきたのは深夜一時を回った頃だった。
とうの本人はといえば、ベッドで俺に背中を向けてすやすやと寝息を立てている。
俺の体はどうやら睡眠を必要としていないようで、この二日間一切眠気は襲ってこない。
(――随分遅い帰りだな。子供を放って両親揃って夜遊びか?)
なんて悪態を心の中で呟きながら、俺はそっと七海葵の部屋を出た。
この三日間、彼女は心底楽しそうに過ごしているが俺はそれが不可解極まりなかった。
学校といい、両親といい――彼女の周辺は最悪だ。
どうして彼女がへらへらと笑えているのか到底理解に苦しむ。
そしてなにより、そんな彼女や周囲の環境に対して本人以上に苛立ちを覚えている自分に腹が立つ。
(俺は七海葵の死を看取ればいいだけのはずだ)
彼女はどう足掻いたって明後日には亡くなる。
それだというのに、 自分でも何故こんなに苛立っているのか理解できず余計に苛立ちは募っていくばかり。
憤りながら、俺は階段を降りリビングへと向かう。
扉のすき間からそっと中の様子を伺うと、彼女の母親がダイニングテーブルに突っ伏していた。
(酔っ払って帰ってきたのかよ。良いご身分で……)
相手に自分の姿が見えていないのをいいことに、俺はずかずかとリビングに上がり込む。突っ伏している母親の背中を、父親がやるせなさそうに撫でている。
「……ううっ。どうして……」
(…………泣いてる?)
酔っているわけじゃない。
母親は泣いていた。そしてその泣いている母を父が慰めている。
「わ、私がもっとあの子を見てあげなかったから。私のせいよ……」
祈るように組んだ手は力を込めすぎて真っ白になっている。
(そこで泣くなら今すぐ娘と向き合ったらどうだ)
彼女がどれだけ懸命に笑顔を浮かべているのかこの親はわかっているのだろうか。
俺が今すぐ七海を起せば和解できるかもしれない。
部屋に戻ろう。そうして背を向けたとき、母親がまた口を開いた。
「――柊」
「――――は?」
聞き覚えのない名前だった。
シュウ? 誰だ? 呼ぶべきは葵じゃないのか?
いや――違う。
これは――。
「――っ!?」
ずきんと頭が痛んだ。
「柊……柊……私を一人にしないで……」
母親がその名を呼ぶ度に、頭痛が酷くなる。
まるで頭に心臓があるみたいだ。
どくんどくんと脈を打って、平衡感覚を失う。
「……っ、なんだよ……これは!」
壁伝いに必死に階段を上る。
部屋までが異様に遠く感じた。
「……柊……シュウ……」
名を呟きながらこれまでのことを思い出す。
記憶を失った自分。
三日後に看取らなければいけない少女。
「……っ、ぐ!」
ずきんと頭が脈打つ度、妙な記憶が頭に流れ込む。
「病室……女の子……」
夕方の病室。
制服姿の少年と、ベッドの背もたれに凭れかかりながら微笑んでいる少女。
少年は俺で……少女は葵だ……。
「これは……俺の記憶」
息も絶え絶えに部屋の扉を開けた。
その瞬間、冷たい夜風がびゅうっと吹き抜けていく。
「……葵?」
ベッドで眠っていたはずの七海の姿が消えている。
開け放たれた窓。カーテンが揺れ、一枚の紙がひらひらと俺の元へ飛んできた。
《死神さん あの場所で待ってるよ》
七海の字。
「あの場所って……」
どこだよ、そういいかけた時また頭痛が酷くなった。
「…………ぐっ!」
そのまま倒れた。
目の前がぐるぐると周り、意識を保っていられない。
倒れた視界の端っこに、ベッドが見える。
ベッドの下に、いつか無くしたキーホルダーが落ちていた。
よく見舞いにいっていたあの子が作ったという、シマエナガの編みぐるみ。
「こんなところにあったんだ……」
手を伸ばそうとするが体が動かない。
あれ――どうして俺の物がここに?
いや、違う。
男物の部屋。見えないクラスメイト。帰ってこない家族。
七海葵ではない、聞き覚えのある名前――これは――。
「ああ――俺だ」
思い出した。
俺の名前は市川柊。
この家も、あの両親も、あの学校も、全部全部、俺のものだ。
なら、七海葵は――?
彼女は一体――?
手に握り締めたメモを見る。
『――約束、だよ』
脳裏に彼女の声が響く。
ああ、いかなきゃ。彼女の元へ。
もう、時間がないから。
俺は痛む体を引きずって、外に出た。
七海葵――彼女が、葵が俺を待ってる。
――七海葵が死ぬまで、あと一日。