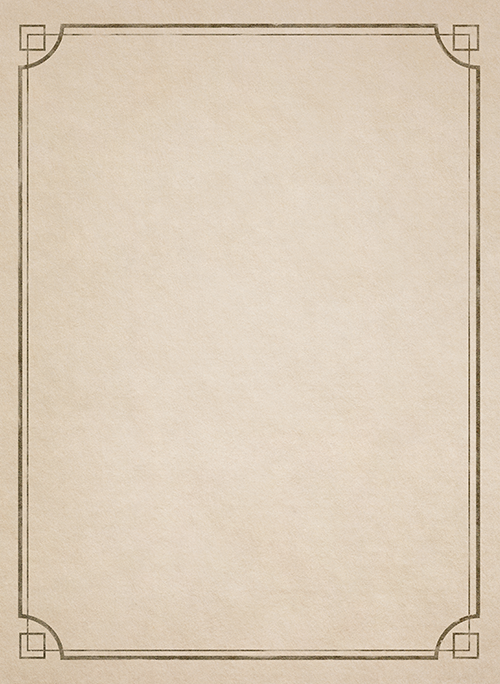その次の日も、私は学校に行った。
相変わらずクラスメイトは私を見ない振り。先生もなにもいわない。
それでも私は無事学校での一日を終えられた。
死神さんは学校にいる間ずーっとふて腐れた顔をしていたけれど、それでも黙って私の傍にいてくれた。
「――ねえ」
そしてまた今日も彼は私に疑問を投げかける。
「アンタは一体なにをしてるの?」
「ん? 見ての通り、遊びに来たんだよ!」
放課後。間もなく初雪の季節を迎えるであろう北海道は日が暮れるのも早い。
だけど、ここ狸小路は日が暮れれば暮れるほど眩いほど明るくなる。
そう。私は死神さんを連れて放課後デートに繰り出したのだ!
大きなディスカウントストアにゲームセンター。
最近出来た新しい商業施設にはなんとなんと水族館もあるそうな。
「後数日で死ぬっていうのに律儀に学校に通う優等生が、こんな夜遅くまで制服姿で遊んでていいわけ?」
「あははっ、こうやって放課後の街に繰り出すの夢だったんだよね!」
一応、私だってやりたいことはあった。
放課後、こうやって街に繰り出して時間を忘れて遊んでみたかった。まあ、そんな友達もいなかったんだけど。
「帰らなくても家族は心配しないのか?」
「大丈夫だよ。あ、もしかして私の死因って外にいることに関係するの?」
「…………いえない」
自然な流れで聞いてみたけれど、死神さんは私の死因を教えてはくれなかった。
「ま、いっか。毎日学校の行き来だけじゃつまらないし、今日はとことん付き合ってもらうよ、死神さん!」
そうして私は死神さんの手を引いて街を駆け巡った。
目的もなくウィンドウショッピングをしてみたり。
ゲームセンターで遊んだり。
そうして今は二人で、水族館のペンギンを眺めていた。
「……楽しいねえ、死神さん」
「俺としか一緒にいないけど、本当にいいの?」
「うん。私は死神さんと一緒にいたいんだよ」
ぎゅっ、と死神さんの手を握ると彼は驚いたように私を見た。
「……アンタが死ぬまであと二日だ」
「うん」
「こんな当たり前みたいな日常でいいの?」
「こんな当たり前の日常を過ごしたくても過ごせない人もいるんだよ……」
ぽつりと呟くと死神さんは不思議そうに目を瞬かせた。
「ううん。なんでもない。付き合ってくれてどうもありがとう。最後にいい思い出ができたよ。死神さんとデートできたこと、忘れない」
「好きな人がいるんだろ? その人とじゃなくていいの?」
「はは……その人は私の想いには気付いてくれてないからなあ」
へらりと笑いながら、私は死神さんの手を引いて帰路についたのだった。
*
「ただいまー!」
元気に帰ったけれど、家の中は真っ暗でしんと静まり返っていた。
私は電気もつけず、そのまま階段を上る。
「……なあ、親は?」
「うーん。きっと今日は帰ってこないと思うよ」
「…………え?」
死神さんはまた目を丸くした。
私は何食わぬ顔で死神さんの手を引いて、部屋に入った。
「いやあ、今日は楽しかったねえ! こんなに遊んだのはじめてだよ!」
クッションにぼすりと腰を下ろして肩をぐるりと回す。
だけど死神さんは扉の前に立ったまま、複雑そうな顔をして動かない。
「アンタは家族からも……」
その言葉の続きは言われずともわかった。
――アンタは家族からも嫌われているのか。
そんな死神さんの顔は険しくて。今にも泣き出してしまいそうなほど悲しそうだった。
「どうだろうね……きっと、そんなことないと思うよ」
曖昧に答えれば、彼はきっと私を睨んだ。
「君は辛くないの?」
「……どうしてそう思うの?」
「だって……いつも笑ってるから。学校では無視されて、家に帰ってきても出迎えてくれる家族はいない」
本当に彼は自分のことのように怒るんだ。
私と君はたった三日の関係。そうしたら私は君の前から消えるっていうのに。
「ごまかすな! せめて……せめて、俺にだけは本当のことをいってほしい。君は辛く……ないのか」
「死神さんは本当に優しいね」
私はぽつりと呟いた。
「私は……生きたいよ。できることなら、もっと。でも、ここで私が泣いていたら……みんなも泣いちゃう」
私はぎゅっと拳を握った。
「私が笑うと、みんなも笑ってくれる。私、死ぬときは笑って死にたいの。だから、私はどれだけ辛くても、苦しくても笑うんだ」
それが私の本心。
だけど、私が言葉を紡げば紡ぐほど、目の前にいる彼の顔は苦しそうに歪んでいく。
そんな顔、させたいわけじゃないんだけどなあ。
「ね、死神さん。ベッド使っていいよ?」
「は!?」
話題を変えるように私が部屋のベッドを指さすと、死神さんが顔を真っ赤にした。
「それとも一緒に寝てあげようか?」
「な、ななななっ! なにいってるんだ!」
彼は顔を真っ赤にして扉にどんっと背中をつけた。
「あははははっ、冗談! 冗談だよ!」
「人をからかうのもいい加減にしてよ……ったく、真面目な雰囲気じゃなくなったじゃん」
「いいんだよ。せめて死神さんとは明るく楽しく過ごしたいから!」
そんな反応が私は面白くてお腹を抱えて笑った。
死神さんは呆れ混じりにため息をつきながら、ぐるりと部屋を見回した。
「……なんか、君らしくない部屋だね」
「――そうだね」
その部屋はあまり物が多くなかった。
シンプルな机に、きっちりと教科書や参考書が並んでいて。
本棚には漫画が幾つか。それとゲーム機とソフトが数本。
ベッドカバーはシンプルにネイビー。
――なんというか、女の子の部屋とは少し違う。
「だって、ここは私の部屋じゃないから」
「――え?」
――私が死ぬまで、あと二日。
相変わらずクラスメイトは私を見ない振り。先生もなにもいわない。
それでも私は無事学校での一日を終えられた。
死神さんは学校にいる間ずーっとふて腐れた顔をしていたけれど、それでも黙って私の傍にいてくれた。
「――ねえ」
そしてまた今日も彼は私に疑問を投げかける。
「アンタは一体なにをしてるの?」
「ん? 見ての通り、遊びに来たんだよ!」
放課後。間もなく初雪の季節を迎えるであろう北海道は日が暮れるのも早い。
だけど、ここ狸小路は日が暮れれば暮れるほど眩いほど明るくなる。
そう。私は死神さんを連れて放課後デートに繰り出したのだ!
大きなディスカウントストアにゲームセンター。
最近出来た新しい商業施設にはなんとなんと水族館もあるそうな。
「後数日で死ぬっていうのに律儀に学校に通う優等生が、こんな夜遅くまで制服姿で遊んでていいわけ?」
「あははっ、こうやって放課後の街に繰り出すの夢だったんだよね!」
一応、私だってやりたいことはあった。
放課後、こうやって街に繰り出して時間を忘れて遊んでみたかった。まあ、そんな友達もいなかったんだけど。
「帰らなくても家族は心配しないのか?」
「大丈夫だよ。あ、もしかして私の死因って外にいることに関係するの?」
「…………いえない」
自然な流れで聞いてみたけれど、死神さんは私の死因を教えてはくれなかった。
「ま、いっか。毎日学校の行き来だけじゃつまらないし、今日はとことん付き合ってもらうよ、死神さん!」
そうして私は死神さんの手を引いて街を駆け巡った。
目的もなくウィンドウショッピングをしてみたり。
ゲームセンターで遊んだり。
そうして今は二人で、水族館のペンギンを眺めていた。
「……楽しいねえ、死神さん」
「俺としか一緒にいないけど、本当にいいの?」
「うん。私は死神さんと一緒にいたいんだよ」
ぎゅっ、と死神さんの手を握ると彼は驚いたように私を見た。
「……アンタが死ぬまであと二日だ」
「うん」
「こんな当たり前みたいな日常でいいの?」
「こんな当たり前の日常を過ごしたくても過ごせない人もいるんだよ……」
ぽつりと呟くと死神さんは不思議そうに目を瞬かせた。
「ううん。なんでもない。付き合ってくれてどうもありがとう。最後にいい思い出ができたよ。死神さんとデートできたこと、忘れない」
「好きな人がいるんだろ? その人とじゃなくていいの?」
「はは……その人は私の想いには気付いてくれてないからなあ」
へらりと笑いながら、私は死神さんの手を引いて帰路についたのだった。
*
「ただいまー!」
元気に帰ったけれど、家の中は真っ暗でしんと静まり返っていた。
私は電気もつけず、そのまま階段を上る。
「……なあ、親は?」
「うーん。きっと今日は帰ってこないと思うよ」
「…………え?」
死神さんはまた目を丸くした。
私は何食わぬ顔で死神さんの手を引いて、部屋に入った。
「いやあ、今日は楽しかったねえ! こんなに遊んだのはじめてだよ!」
クッションにぼすりと腰を下ろして肩をぐるりと回す。
だけど死神さんは扉の前に立ったまま、複雑そうな顔をして動かない。
「アンタは家族からも……」
その言葉の続きは言われずともわかった。
――アンタは家族からも嫌われているのか。
そんな死神さんの顔は険しくて。今にも泣き出してしまいそうなほど悲しそうだった。
「どうだろうね……きっと、そんなことないと思うよ」
曖昧に答えれば、彼はきっと私を睨んだ。
「君は辛くないの?」
「……どうしてそう思うの?」
「だって……いつも笑ってるから。学校では無視されて、家に帰ってきても出迎えてくれる家族はいない」
本当に彼は自分のことのように怒るんだ。
私と君はたった三日の関係。そうしたら私は君の前から消えるっていうのに。
「ごまかすな! せめて……せめて、俺にだけは本当のことをいってほしい。君は辛く……ないのか」
「死神さんは本当に優しいね」
私はぽつりと呟いた。
「私は……生きたいよ。できることなら、もっと。でも、ここで私が泣いていたら……みんなも泣いちゃう」
私はぎゅっと拳を握った。
「私が笑うと、みんなも笑ってくれる。私、死ぬときは笑って死にたいの。だから、私はどれだけ辛くても、苦しくても笑うんだ」
それが私の本心。
だけど、私が言葉を紡げば紡ぐほど、目の前にいる彼の顔は苦しそうに歪んでいく。
そんな顔、させたいわけじゃないんだけどなあ。
「ね、死神さん。ベッド使っていいよ?」
「は!?」
話題を変えるように私が部屋のベッドを指さすと、死神さんが顔を真っ赤にした。
「それとも一緒に寝てあげようか?」
「な、ななななっ! なにいってるんだ!」
彼は顔を真っ赤にして扉にどんっと背中をつけた。
「あははははっ、冗談! 冗談だよ!」
「人をからかうのもいい加減にしてよ……ったく、真面目な雰囲気じゃなくなったじゃん」
「いいんだよ。せめて死神さんとは明るく楽しく過ごしたいから!」
そんな反応が私は面白くてお腹を抱えて笑った。
死神さんは呆れ混じりにため息をつきながら、ぐるりと部屋を見回した。
「……なんか、君らしくない部屋だね」
「――そうだね」
その部屋はあまり物が多くなかった。
シンプルな机に、きっちりと教科書や参考書が並んでいて。
本棚には漫画が幾つか。それとゲーム機とソフトが数本。
ベッドカバーはシンプルにネイビー。
――なんというか、女の子の部屋とは少し違う。
「だって、ここは私の部屋じゃないから」
「――え?」
――私が死ぬまで、あと二日。