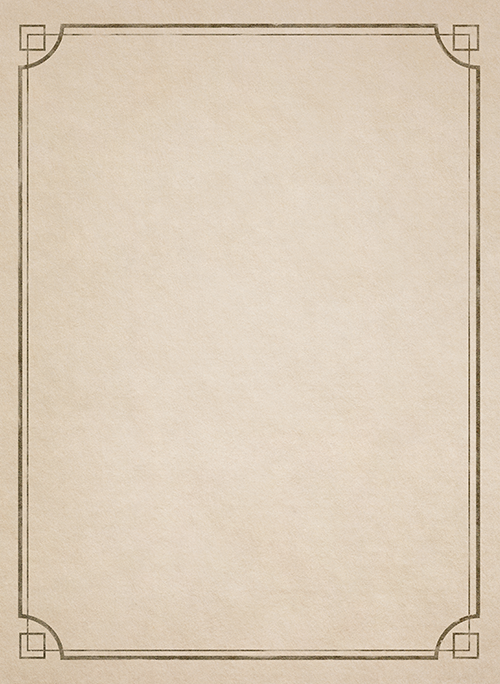それから私は死神さんを連れて学校に向かった。
だけど死神さんの足取りはどことなく重い。
「どうしたの?」
「いや……君、三日後に死ぬんだよ?」
「そうだね」
「学校なんか行ってる場合?」
死神さんは眉をひそめてそういった。
「死神さんは学校嫌いなの?」
「死神は学校なんかいかない」
それもそうか。
だけど、そんな死神さんの表情はどこかふて腐れているようにも見える。
「なんかこう……やりたいこととしたり、食べたいもの食べたり、遊んだりとかするんじゃないのか普通」
死神さんは眉をひそめてそういった。
「思い切りハメを外しても、三日後私はまだ生きてるかもしれないじゃん?」
「だから君は絶対に三日後に――」
「とにかく、なにがあってもいつも通りの日常を過ごすのが一番なの! ほら、行こう」
私は死神さんの手を引いて走り出した。
風を切って走れる。空はこんなにも高くて、綺麗な青空が広がっている。
私は元気だ。とてもじゃないが自分が三日後に死ぬなんて想像も出来なかった。
*
「……ねえ」
死神さんの声は相変わらず重かった。
遅刻寸前に登校して教室に入った。そこまでは良かったけれど、死神さんは信じられないように私の目の前をじっと見つめていた。
「…………ああ」
その視線の先には机。正しくは、その上に乗った花瓶と花。
「ちょっとやめなよ、不謹慎すぎじゃん!」
「えー、だって近々そうなるかもしれないじゃん。この間、ひとつ席がなくなってここだけはみ出してるし……これもなくなっちゃえば、教室スッキリするっしょ!」
騒がしい教室で、クラスメイトが戯けて笑いながら机の上から乱暴に花瓶を取り去っていった。
反動で落ちた水滴。その机をよく見ると、うっすらと「死ね」とか「消えろ」とかあまりにも酷すぎる悪戯書きが読めた。
「――なんで」
ぽつりと苦しそうな声。
「なんでアンタは平気な顔でこんなところにいるんだ!」
死神さんが叫んだ。だけど、その声は誰にも聞こえていないようだ。
それもそうだろう。私以外のみんなには死神さんの姿は見えていないんだから。
「……っ、ちょっと来て!」
「うわっ!」
死神さんは私の手を取ると教室を出て行った。
突然見えないなにかに腕を引っ張られていく私を呼び止める人は誰もいなかった。
死神さんはホームルーム前の騒がしい廊下をずんずんと進み、屋上まで私を連れてきた。
「ちょっと……死神さん、どうしたの!」
「どうしたのじゃない!」
屋上についてようやく私の手を離した死神さんは怒りながら叫ぶ。
「どうかしてるのはアンタのほうだ! だって、あんなの……」
「……そうだね。私は、みんなに見えていないみたいだから」
まるで自分のことのように死神さんの顔は私以上に苦しそうだった。
いつからなのかはわからない。
クラスメイトに無視をされるようになって。
教科書や私物を壊されて、隠されて。落書きをされて。
直接暴力を振るわれたわけじゃない。
でも、学校に来るたびに遠くから笑われて、蔑まれて、冷たい目を向けられた。
辛くなる度に、よくこうして屋上で気持ちいい風を浴びていた。
するとチャイムの音が聞こえてきた。
「――さ、そろそろ教室帰らないと。先生がくるよ?」
「はあっ!?」
私の反応に死神さんは理解が出来ないと、苛立たしげに髪を掻き毟った。
「何度もいってるけど、アンタあと三日で死ぬんだぞ!」
「そうみたいだね」
「それなのに……こんなクソみたいなところにきて、へらへら笑って、一日無駄にするつもりか!? なに考えてんだよ!」
「……それが、約束だから」
私の言葉に、死神さんは「は?」とぽかんと口を開けた。
「ある人と約束したんだ。なにがあっても毎日学校に行くって」
「それって……」
「好きな人」
照れくさそうに笑うと、死神さんは呆れたように言葉を失った。
「そんな約束のために、アンタはあんな目にあってもここにくるのかよ」
「私にとっては命よりも大切な約束だもん」
「……意味、わかんねえ」
ますます信じられないと、死神さんは頭を抱えてしゃがみこんでしまった。
「死神さんはやっぱり学校が嫌いなんだね」
「え?」
「だって、自分のことみたいに怒ってるから」
私は死神さんの隣にしゃがみ、その顔を覗き込んだ。
真っ直ぐ見つめると、彼は居心地悪そうに視線を泳がせる。
「……わかんないんだ」
「学校に行ったことがないから?」
違う、と死神さんは零す。
「それすらもわからないんだ。俺には……アンタと出会う前の記憶がないから。どこから来て、なにをしていたのかもわからない。ただ、三日後にアンタが死ぬ。そして俺はアンタの魂を刈り取る。そのことしか覚えてない。なにか大切なことをずっと忘れている気がするのに」
「……そっか。思い出したくても、思い出せないのは辛いね」
慰めるように私は死神さんの背中を擦った。
「いつか、思い出せるといいね」
「チャイム、とっくに鳴り終わったけど……行かなくていいのか?」
「死神さんは行きたい?」
そう尋ねると、彼はいや、と小さく首を振った。
「正直いうと、私もあの教室は居心地が悪いんだよねー。だからここで少しサボってからいこう」
「いいの? 君、真面目そうなのに」
自分でも言動があべこべだと思う。でも、これでいいんだ。
「あと三日で死ぬかもしれないんでしょう? なら、死神さんのいうとおり、少しぐらい好きなことしてもいいと思って。学校サボるって楽しいんだね」
誰もいない屋上。二人で見上げる空。
それがこんなにも綺麗だなんて、私ははじめて知ったのだった。
――私が死ぬまで、あと三日。
だけど死神さんの足取りはどことなく重い。
「どうしたの?」
「いや……君、三日後に死ぬんだよ?」
「そうだね」
「学校なんか行ってる場合?」
死神さんは眉をひそめてそういった。
「死神さんは学校嫌いなの?」
「死神は学校なんかいかない」
それもそうか。
だけど、そんな死神さんの表情はどこかふて腐れているようにも見える。
「なんかこう……やりたいこととしたり、食べたいもの食べたり、遊んだりとかするんじゃないのか普通」
死神さんは眉をひそめてそういった。
「思い切りハメを外しても、三日後私はまだ生きてるかもしれないじゃん?」
「だから君は絶対に三日後に――」
「とにかく、なにがあってもいつも通りの日常を過ごすのが一番なの! ほら、行こう」
私は死神さんの手を引いて走り出した。
風を切って走れる。空はこんなにも高くて、綺麗な青空が広がっている。
私は元気だ。とてもじゃないが自分が三日後に死ぬなんて想像も出来なかった。
*
「……ねえ」
死神さんの声は相変わらず重かった。
遅刻寸前に登校して教室に入った。そこまでは良かったけれど、死神さんは信じられないように私の目の前をじっと見つめていた。
「…………ああ」
その視線の先には机。正しくは、その上に乗った花瓶と花。
「ちょっとやめなよ、不謹慎すぎじゃん!」
「えー、だって近々そうなるかもしれないじゃん。この間、ひとつ席がなくなってここだけはみ出してるし……これもなくなっちゃえば、教室スッキリするっしょ!」
騒がしい教室で、クラスメイトが戯けて笑いながら机の上から乱暴に花瓶を取り去っていった。
反動で落ちた水滴。その机をよく見ると、うっすらと「死ね」とか「消えろ」とかあまりにも酷すぎる悪戯書きが読めた。
「――なんで」
ぽつりと苦しそうな声。
「なんでアンタは平気な顔でこんなところにいるんだ!」
死神さんが叫んだ。だけど、その声は誰にも聞こえていないようだ。
それもそうだろう。私以外のみんなには死神さんの姿は見えていないんだから。
「……っ、ちょっと来て!」
「うわっ!」
死神さんは私の手を取ると教室を出て行った。
突然見えないなにかに腕を引っ張られていく私を呼び止める人は誰もいなかった。
死神さんはホームルーム前の騒がしい廊下をずんずんと進み、屋上まで私を連れてきた。
「ちょっと……死神さん、どうしたの!」
「どうしたのじゃない!」
屋上についてようやく私の手を離した死神さんは怒りながら叫ぶ。
「どうかしてるのはアンタのほうだ! だって、あんなの……」
「……そうだね。私は、みんなに見えていないみたいだから」
まるで自分のことのように死神さんの顔は私以上に苦しそうだった。
いつからなのかはわからない。
クラスメイトに無視をされるようになって。
教科書や私物を壊されて、隠されて。落書きをされて。
直接暴力を振るわれたわけじゃない。
でも、学校に来るたびに遠くから笑われて、蔑まれて、冷たい目を向けられた。
辛くなる度に、よくこうして屋上で気持ちいい風を浴びていた。
するとチャイムの音が聞こえてきた。
「――さ、そろそろ教室帰らないと。先生がくるよ?」
「はあっ!?」
私の反応に死神さんは理解が出来ないと、苛立たしげに髪を掻き毟った。
「何度もいってるけど、アンタあと三日で死ぬんだぞ!」
「そうみたいだね」
「それなのに……こんなクソみたいなところにきて、へらへら笑って、一日無駄にするつもりか!? なに考えてんだよ!」
「……それが、約束だから」
私の言葉に、死神さんは「は?」とぽかんと口を開けた。
「ある人と約束したんだ。なにがあっても毎日学校に行くって」
「それって……」
「好きな人」
照れくさそうに笑うと、死神さんは呆れたように言葉を失った。
「そんな約束のために、アンタはあんな目にあってもここにくるのかよ」
「私にとっては命よりも大切な約束だもん」
「……意味、わかんねえ」
ますます信じられないと、死神さんは頭を抱えてしゃがみこんでしまった。
「死神さんはやっぱり学校が嫌いなんだね」
「え?」
「だって、自分のことみたいに怒ってるから」
私は死神さんの隣にしゃがみ、その顔を覗き込んだ。
真っ直ぐ見つめると、彼は居心地悪そうに視線を泳がせる。
「……わかんないんだ」
「学校に行ったことがないから?」
違う、と死神さんは零す。
「それすらもわからないんだ。俺には……アンタと出会う前の記憶がないから。どこから来て、なにをしていたのかもわからない。ただ、三日後にアンタが死ぬ。そして俺はアンタの魂を刈り取る。そのことしか覚えてない。なにか大切なことをずっと忘れている気がするのに」
「……そっか。思い出したくても、思い出せないのは辛いね」
慰めるように私は死神さんの背中を擦った。
「いつか、思い出せるといいね」
「チャイム、とっくに鳴り終わったけど……行かなくていいのか?」
「死神さんは行きたい?」
そう尋ねると、彼はいや、と小さく首を振った。
「正直いうと、私もあの教室は居心地が悪いんだよねー。だからここで少しサボってからいこう」
「いいの? 君、真面目そうなのに」
自分でも言動があべこべだと思う。でも、これでいいんだ。
「あと三日で死ぬかもしれないんでしょう? なら、死神さんのいうとおり、少しぐらい好きなことしてもいいと思って。学校サボるって楽しいんだね」
誰もいない屋上。二人で見上げる空。
それがこんなにも綺麗だなんて、私ははじめて知ったのだった。
――私が死ぬまで、あと三日。