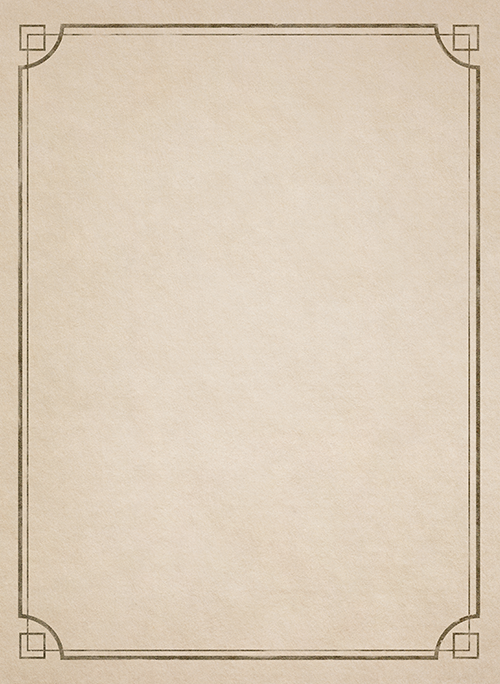「――こんにちは、俺は死神です。七海葵さん。突然だけど、君は三日後に死ぬ」
ある朝、死神さんはインターホンを鳴らして現れた。
その死神さんは鋭い鎌も黒いマントも被っていない。
黒いフーディーを着た、綺麗な顔をした男の子だった。
「宗教勧誘ならお断りしてるんですけど」
即扉を閉めようとしたが、彼は体をねじ込んで玄関に上がり込んできた。
「違う。僕は本物の死神で、君は本当に三日後に死ぬんだ」
「死ぬって、一体どうやって?」
「……それは機密事項だ。いえない決まりになっている」
彼の目が泳ぐ。
私が怪訝そうに見つめると、彼はいたたまれなさそうに視線を泳がせる。
なんだか益々あやしく見えてきた。
「はーい、どちらさまですか~?」
玄関先で睨めっこをしていると、家の奥からお母さんの声が聞こえてきた。
パタパタと足音が近づいてくる。
「こっちきて!」
私は慌てて彼の手を引いて、二階の部屋に走った。
彼を部屋に放り込んで、私は扉に背を預けてふう、と息をつく。
「……ふう。これで一安心。お母さんが会ったら腰抜かしちゃうかもしれないし」
「別に慌てなくても……生きている人間に俺の姿は見えないよ」
「ん? それならなんで私は君のこと見えてるの?」
「それは君が死に近づいているから」
ちらりと鏡を見ていると、そこに姿は映っていない。
どうやら他人に姿が見えないというのは本当らしい。
「ふぅん、じゃあ私は本当に三日後に死んじゃうんだね」
「さっきまであれだけ怪しんでたのに、受け入れるの早くない?」
「だって、私が死ぬっていったのは死神さんじゃない」
あまりにも余命宣告をあっさりと受け入れた私に彼が驚いている。
「普通、死ぬっていったら嫌がったり怯えたりすると思うんだけど」
「今死ぬわけでもないのに、慌てても仕方がないじゃん。それに、三日後になってみないと本当に死ぬとも限らないし」
私は運命とか、余命とか、お告げは信じない。
私が信じるのは私だけ。この目で見て、この体で体験したことが全てだから。
「さて、ようやく落ち着いて話せるね。君は私を殺しにきたの?」
「違う。死神に人は殺せない。俺は三日後に死ぬ君の最期を看取って、その魂を刈り取るためにきた」
「じゃあ、私が死ぬまで君はずっと一緒にいてくれるの?」
「君が嫌といえば姿を消しているし、いいといえば傍にいる。ただ、君が三日後に死ぬときはどちらにせよ俺は君の前に姿を見せる」
「え、どのみち監視されるなら一緒にいてよ。君だけ私のこと詳しくて、私だけ君のことなにも知らないなんて不公平だ」
あっけらかんとした私の態度に、さっきから彼の目は丸くなりっぱなしだ。
「……君は変わってるね」
「ふふ、よくいわれる」
変わった子、不思議ちゃん。それは私にとっては褒め言葉だ。
「これからしばらく一緒にいるのに『君』って呼び合うのも変だよね。お名前、教えてよ」
「俺は死神。名前はないよ」
「じゃあ、死神さん。これから三日間、よろしくね?」
こうして私と死神さんの三日間がはじまったのだ。
ある朝、死神さんはインターホンを鳴らして現れた。
その死神さんは鋭い鎌も黒いマントも被っていない。
黒いフーディーを着た、綺麗な顔をした男の子だった。
「宗教勧誘ならお断りしてるんですけど」
即扉を閉めようとしたが、彼は体をねじ込んで玄関に上がり込んできた。
「違う。僕は本物の死神で、君は本当に三日後に死ぬんだ」
「死ぬって、一体どうやって?」
「……それは機密事項だ。いえない決まりになっている」
彼の目が泳ぐ。
私が怪訝そうに見つめると、彼はいたたまれなさそうに視線を泳がせる。
なんだか益々あやしく見えてきた。
「はーい、どちらさまですか~?」
玄関先で睨めっこをしていると、家の奥からお母さんの声が聞こえてきた。
パタパタと足音が近づいてくる。
「こっちきて!」
私は慌てて彼の手を引いて、二階の部屋に走った。
彼を部屋に放り込んで、私は扉に背を預けてふう、と息をつく。
「……ふう。これで一安心。お母さんが会ったら腰抜かしちゃうかもしれないし」
「別に慌てなくても……生きている人間に俺の姿は見えないよ」
「ん? それならなんで私は君のこと見えてるの?」
「それは君が死に近づいているから」
ちらりと鏡を見ていると、そこに姿は映っていない。
どうやら他人に姿が見えないというのは本当らしい。
「ふぅん、じゃあ私は本当に三日後に死んじゃうんだね」
「さっきまであれだけ怪しんでたのに、受け入れるの早くない?」
「だって、私が死ぬっていったのは死神さんじゃない」
あまりにも余命宣告をあっさりと受け入れた私に彼が驚いている。
「普通、死ぬっていったら嫌がったり怯えたりすると思うんだけど」
「今死ぬわけでもないのに、慌てても仕方がないじゃん。それに、三日後になってみないと本当に死ぬとも限らないし」
私は運命とか、余命とか、お告げは信じない。
私が信じるのは私だけ。この目で見て、この体で体験したことが全てだから。
「さて、ようやく落ち着いて話せるね。君は私を殺しにきたの?」
「違う。死神に人は殺せない。俺は三日後に死ぬ君の最期を看取って、その魂を刈り取るためにきた」
「じゃあ、私が死ぬまで君はずっと一緒にいてくれるの?」
「君が嫌といえば姿を消しているし、いいといえば傍にいる。ただ、君が三日後に死ぬときはどちらにせよ俺は君の前に姿を見せる」
「え、どのみち監視されるなら一緒にいてよ。君だけ私のこと詳しくて、私だけ君のことなにも知らないなんて不公平だ」
あっけらかんとした私の態度に、さっきから彼の目は丸くなりっぱなしだ。
「……君は変わってるね」
「ふふ、よくいわれる」
変わった子、不思議ちゃん。それは私にとっては褒め言葉だ。
「これからしばらく一緒にいるのに『君』って呼び合うのも変だよね。お名前、教えてよ」
「俺は死神。名前はないよ」
「じゃあ、死神さん。これから三日間、よろしくね?」
こうして私と死神さんの三日間がはじまったのだ。