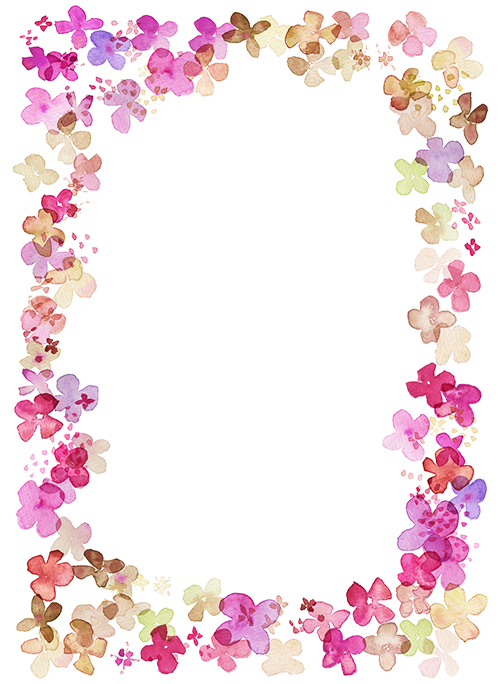三日後、私は性懲りも無く同じクラブへと足を運んだ。
「今日は一人でいいよ。勝手もわかったから」
また誰か子分に面倒を見させようとしていた兄を振り切って、隅の方へと歩いて行く。
壁に背を預けて、私は鉄骨の剥き出しになっている天井を仰ぐ。
何があったということもない。でも何も変わっていない。
「あ、沙世さん。お久しぶりです」
「うん」
この間来たときに話し相手になってくれたテツに適当な挨拶を返して、私は腕を組む。
じゃあなぜここへ来たのかと考える。
ミラーボールに埃臭いフロア、揺れる若者に眩しい照明。私にとって、さほど愛着があるとはいえないものの数々。
それでも兄がここにいるのだと思うと、どうしても私は寂しさを紛らわすために足を運ぶのを止められなかった。
「あれ?」
ふと隣に立ったままのテツをまじまじと見つめる。
「な、何ですか?」
「ピアス、新しくつけたね」
「あ、はい」
彼の口元を指差すと、少年はにこやかに頷く。
「ついでに穴も大きくして」
「へぇ」
「拓磨さんに開けてもらいました。どうっすか?」
違和感の正体はそれかと、私は照れる少年を見つめながら納得する。
「私ピアス嫌い」
「……容赦ないっす」
仕方ないじゃないかと思いながらも私は面倒くさそうに付け加える。
「でもそれは似合ってるよ。シルバーのやつ」
ぞんざいな答えだけど、テツは満足したようだった。まだ高校生だからかもしれないけど、頷き方が随分と幼く見える。
「ピアスって面白いのかな」
何気なく訊いてみると、彼は指先で軽く新調のピアスを弾きつつ答える。
「面白いっていうか。男でイヤリングってのも変ですし」
「でも女の人もしてるね。そういうもの?」
「そうっすね。皆やってるし」
言われてみれば、その辺で踊っている人たちの耳には男女問わずピアスが光っていた。兄ほど数多くはつけてないけど、ここではピアスは当たり前のようだ。
ピアスはきらきらとライトを反射して光っていた。熱帯魚の尾ひれのようにゆらりと揺れて過ぎていく、その一瞬で確かな存在感が目に映る。
嫌いなのは間違いないけど、ここの世界では常識だ。それを思うと、私は少しだけ眉を寄せた。
「あ」
ポケットの中で携帯が鳴る。私は反射的に携帯を見た。
『最近遅いけど、どこに行ってんの?』
ほっといてよと呟いて、私は即座に携帯をポケットに仕舞いなおす。
だいたい自分が頻繁に朝帰りしてるくせに、人がちょっと遅いくらいで変な顔をするのはよしてほしい。もっとも彼の場合は仕事なんだろうけど。
「え、沙世さん。今のは?」
露骨に顔を引きつらせたテツに、私はそっけなく答える。
「友達」
「あー……そうっすか。拓磨さんにばれないといいっすね」
テツは自分で勝手に納得する。
私は腕を組んで目を閉じてみた。もちろん居眠りをするつもりじゃなくて、少し考え事がしたかった。
「ねぇ」
何か足りない。確かな何かが、私は欲しい。
……それをどうやって得るのかは、わからなくても。
「あなたが沙世?」
呼ばれて私は顔を上げた。目を開いて、正面に立つ女性に気づく。
品のいいブラウスにデニムのスカート、ここでは珍しい黒髪に、薄いメイクで整えられた、顔立ちも体型も綺麗な人だった。
「そうです。拓磨の」
「妹でしょ。もう何度も聞いたわよ」
棘のある遮り方に、私は眉を寄せる。一瞬で、この人が私にあまり良い感情は持っていないのが伝わってきた。
「何しに来たの? 場違いだとわからない?」
きつい口調だった。それは言葉も目つきも同じだったけど、不思議と私は怒りを感じることはなかった。
「わかります、絵梨さん」
ほとんど同じ高さから彼女を見返しながら、私は頷いた。
「でも隅で大人しくしてるので、大目に見てください。邪魔しないので」
「あなたがいるってことが邪魔なの」
「ちょっと。絵梨さん、失礼っすよ」
慌てたようにテツが止めに入ったけど、私はまだ彼女をみつめていた。
「拓磨が迷惑なの。わかるでしょ?」
たぶんこの人は兄が好きなのだ。
それを感じ取って、私はこくんと素直に頷く。
「はい。小さい頃から迷惑かけてます」
「なら……」
「だから」
自分で言葉にしてみて初めて、私は胸に溜まっていた思いに気づいた。
「兄ちゃんが出てけって言うまで、ここにいます」
私は今も子どものつもりでいる。
寂しくなるとずっとそうしてきたように、兄にくっつきたくて仕方がない。馬鹿だな、しょうがねぇな、と呆れられながらも甘やかしてくれるのを信じている。
ずっとそれに守られてきた。だから私は、自分からそれを断ち切れない。断ち切りたくない。
いっぱいに伸ばした手を、決して彼は振り払ったりしなかったから。
「生意気なこと言わないで。すぐ飽きられるにきまってるのに!」
言葉を返した直後、乱暴に耳を引っ張られた。
「絵梨さん、ちょ、やばいっすよ」
痛いと思った時には、もう彼女の綺麗な爪が耳の後ろに引っかかって傷がついていた。
挑発したのは私だ。どうしても自分の思いを口にせずにはいられなかった。ここにいる理由を、自分の中で確かなものにしたかった。
「つ……」
だから抵抗せずにそれを受け止めたけど、やっぱり痛いものは痛い。すぐにテツが彼女の手を引き剥がしてくれたけど、そっと自分で右耳に手を当てたら、少しだけど血が流れていた。
「何の騒ぎだ?」
周りがざわめいたのに反応して、兄がこちらを振り向く。私はさっと血のついた手を背中の後ろに隠したけど、兄は訝しげに彼女の爪先に目を細める。
「血?」
おもむろに絵梨の手を取ると、彼はそれを掴んだまま平坦な声を出す。絵梨が何か言おうと口を開く前に、兄は素早く私の方へと目を移した。
その目つきが酷くぎらついて見えて、私は思わず後ずさっていた。
「ごめん」
こちらへ近づこうとした兄に短く返して、私は首を横に振る。
この静かな怒りは私に向けられたものじゃない。それはわかってる。
「見せろ。どこをやられた」
……けど、怖いのだ。
「何でもない」
「嘘言うな」
兄は手を伸ばす。私はそれを右手で振り払って、だけどその手首を掴まれてはっとなる。
赤い指先に兄は目を細めて、そして肩口へ移動した。私は思わず肩に血がついているのかと目を走らせてしまい、その動きで彼は目ざとく事態を察知して私の耳を掴む。
「切れてる。絵梨か?」
「違う」
否定したのに、兄はもう絵梨を振り返っていた。誰もが怯えるような怒りの眼差しを向ける。
その場にいる兄以外の誰もが動けなかった。図体が大きいだけじゃなくて、圧倒的な気迫と存在感が、兄の周りを取り巻いていた。
だから兄が恐れられるのだと、私はその時やっと理解した。
「違うよ、違う!」
私はぐっと兄の腕を掴む。
いけないと思った。このままじゃ、間違いなく兄は絵梨に手を上げると直感した。
「ちょっと引っ掛かっただけだよ。ほら、ピアス開ける時だって血くらい出るし!」
脈絡のない言葉を並べ立てて、私はぐいぐいと兄の腕を両手で引っ張る。
少しだけ兄が思考をめぐらせたのがわかった。その気になれば簡単に私を振り払えるはずなのに、彼はその場を一歩も動かなかったからだ。
「絵梨」
「な、何?」
兄は短く、本当にそっけなく言った。
「出てけ。二度と来るな」
その言葉で、私は絵梨が二番手だと言うことにようやく確信を持った。
皆の噂するナンバーワンは別にいる。これは本当のことのようだ。
それにほっとしたような、不謹慎にも更に興味が積もるような、そんな複雑な思いが私の中を駆け巡ったのだった。
「今日は一人でいいよ。勝手もわかったから」
また誰か子分に面倒を見させようとしていた兄を振り切って、隅の方へと歩いて行く。
壁に背を預けて、私は鉄骨の剥き出しになっている天井を仰ぐ。
何があったということもない。でも何も変わっていない。
「あ、沙世さん。お久しぶりです」
「うん」
この間来たときに話し相手になってくれたテツに適当な挨拶を返して、私は腕を組む。
じゃあなぜここへ来たのかと考える。
ミラーボールに埃臭いフロア、揺れる若者に眩しい照明。私にとって、さほど愛着があるとはいえないものの数々。
それでも兄がここにいるのだと思うと、どうしても私は寂しさを紛らわすために足を運ぶのを止められなかった。
「あれ?」
ふと隣に立ったままのテツをまじまじと見つめる。
「な、何ですか?」
「ピアス、新しくつけたね」
「あ、はい」
彼の口元を指差すと、少年はにこやかに頷く。
「ついでに穴も大きくして」
「へぇ」
「拓磨さんに開けてもらいました。どうっすか?」
違和感の正体はそれかと、私は照れる少年を見つめながら納得する。
「私ピアス嫌い」
「……容赦ないっす」
仕方ないじゃないかと思いながらも私は面倒くさそうに付け加える。
「でもそれは似合ってるよ。シルバーのやつ」
ぞんざいな答えだけど、テツは満足したようだった。まだ高校生だからかもしれないけど、頷き方が随分と幼く見える。
「ピアスって面白いのかな」
何気なく訊いてみると、彼は指先で軽く新調のピアスを弾きつつ答える。
「面白いっていうか。男でイヤリングってのも変ですし」
「でも女の人もしてるね。そういうもの?」
「そうっすね。皆やってるし」
言われてみれば、その辺で踊っている人たちの耳には男女問わずピアスが光っていた。兄ほど数多くはつけてないけど、ここではピアスは当たり前のようだ。
ピアスはきらきらとライトを反射して光っていた。熱帯魚の尾ひれのようにゆらりと揺れて過ぎていく、その一瞬で確かな存在感が目に映る。
嫌いなのは間違いないけど、ここの世界では常識だ。それを思うと、私は少しだけ眉を寄せた。
「あ」
ポケットの中で携帯が鳴る。私は反射的に携帯を見た。
『最近遅いけど、どこに行ってんの?』
ほっといてよと呟いて、私は即座に携帯をポケットに仕舞いなおす。
だいたい自分が頻繁に朝帰りしてるくせに、人がちょっと遅いくらいで変な顔をするのはよしてほしい。もっとも彼の場合は仕事なんだろうけど。
「え、沙世さん。今のは?」
露骨に顔を引きつらせたテツに、私はそっけなく答える。
「友達」
「あー……そうっすか。拓磨さんにばれないといいっすね」
テツは自分で勝手に納得する。
私は腕を組んで目を閉じてみた。もちろん居眠りをするつもりじゃなくて、少し考え事がしたかった。
「ねぇ」
何か足りない。確かな何かが、私は欲しい。
……それをどうやって得るのかは、わからなくても。
「あなたが沙世?」
呼ばれて私は顔を上げた。目を開いて、正面に立つ女性に気づく。
品のいいブラウスにデニムのスカート、ここでは珍しい黒髪に、薄いメイクで整えられた、顔立ちも体型も綺麗な人だった。
「そうです。拓磨の」
「妹でしょ。もう何度も聞いたわよ」
棘のある遮り方に、私は眉を寄せる。一瞬で、この人が私にあまり良い感情は持っていないのが伝わってきた。
「何しに来たの? 場違いだとわからない?」
きつい口調だった。それは言葉も目つきも同じだったけど、不思議と私は怒りを感じることはなかった。
「わかります、絵梨さん」
ほとんど同じ高さから彼女を見返しながら、私は頷いた。
「でも隅で大人しくしてるので、大目に見てください。邪魔しないので」
「あなたがいるってことが邪魔なの」
「ちょっと。絵梨さん、失礼っすよ」
慌てたようにテツが止めに入ったけど、私はまだ彼女をみつめていた。
「拓磨が迷惑なの。わかるでしょ?」
たぶんこの人は兄が好きなのだ。
それを感じ取って、私はこくんと素直に頷く。
「はい。小さい頃から迷惑かけてます」
「なら……」
「だから」
自分で言葉にしてみて初めて、私は胸に溜まっていた思いに気づいた。
「兄ちゃんが出てけって言うまで、ここにいます」
私は今も子どものつもりでいる。
寂しくなるとずっとそうしてきたように、兄にくっつきたくて仕方がない。馬鹿だな、しょうがねぇな、と呆れられながらも甘やかしてくれるのを信じている。
ずっとそれに守られてきた。だから私は、自分からそれを断ち切れない。断ち切りたくない。
いっぱいに伸ばした手を、決して彼は振り払ったりしなかったから。
「生意気なこと言わないで。すぐ飽きられるにきまってるのに!」
言葉を返した直後、乱暴に耳を引っ張られた。
「絵梨さん、ちょ、やばいっすよ」
痛いと思った時には、もう彼女の綺麗な爪が耳の後ろに引っかかって傷がついていた。
挑発したのは私だ。どうしても自分の思いを口にせずにはいられなかった。ここにいる理由を、自分の中で確かなものにしたかった。
「つ……」
だから抵抗せずにそれを受け止めたけど、やっぱり痛いものは痛い。すぐにテツが彼女の手を引き剥がしてくれたけど、そっと自分で右耳に手を当てたら、少しだけど血が流れていた。
「何の騒ぎだ?」
周りがざわめいたのに反応して、兄がこちらを振り向く。私はさっと血のついた手を背中の後ろに隠したけど、兄は訝しげに彼女の爪先に目を細める。
「血?」
おもむろに絵梨の手を取ると、彼はそれを掴んだまま平坦な声を出す。絵梨が何か言おうと口を開く前に、兄は素早く私の方へと目を移した。
その目つきが酷くぎらついて見えて、私は思わず後ずさっていた。
「ごめん」
こちらへ近づこうとした兄に短く返して、私は首を横に振る。
この静かな怒りは私に向けられたものじゃない。それはわかってる。
「見せろ。どこをやられた」
……けど、怖いのだ。
「何でもない」
「嘘言うな」
兄は手を伸ばす。私はそれを右手で振り払って、だけどその手首を掴まれてはっとなる。
赤い指先に兄は目を細めて、そして肩口へ移動した。私は思わず肩に血がついているのかと目を走らせてしまい、その動きで彼は目ざとく事態を察知して私の耳を掴む。
「切れてる。絵梨か?」
「違う」
否定したのに、兄はもう絵梨を振り返っていた。誰もが怯えるような怒りの眼差しを向ける。
その場にいる兄以外の誰もが動けなかった。図体が大きいだけじゃなくて、圧倒的な気迫と存在感が、兄の周りを取り巻いていた。
だから兄が恐れられるのだと、私はその時やっと理解した。
「違うよ、違う!」
私はぐっと兄の腕を掴む。
いけないと思った。このままじゃ、間違いなく兄は絵梨に手を上げると直感した。
「ちょっと引っ掛かっただけだよ。ほら、ピアス開ける時だって血くらい出るし!」
脈絡のない言葉を並べ立てて、私はぐいぐいと兄の腕を両手で引っ張る。
少しだけ兄が思考をめぐらせたのがわかった。その気になれば簡単に私を振り払えるはずなのに、彼はその場を一歩も動かなかったからだ。
「絵梨」
「な、何?」
兄は短く、本当にそっけなく言った。
「出てけ。二度と来るな」
その言葉で、私は絵梨が二番手だと言うことにようやく確信を持った。
皆の噂するナンバーワンは別にいる。これは本当のことのようだ。
それにほっとしたような、不謹慎にも更に興味が積もるような、そんな複雑な思いが私の中を駆け巡ったのだった。