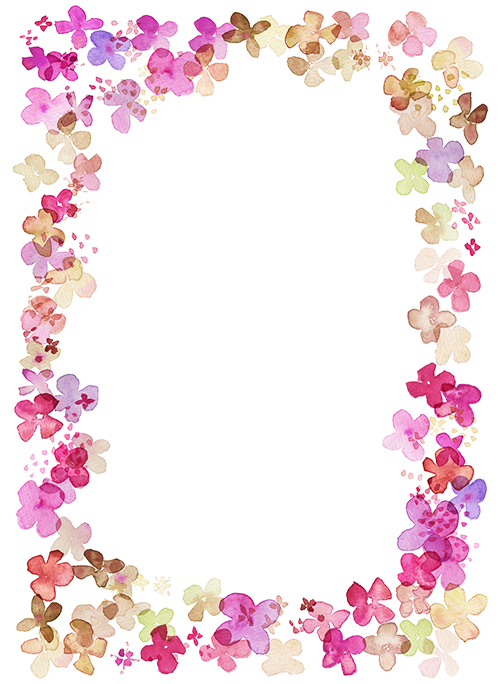テンポがいいというよりは狂ってるんじゃないかと思う音楽の中で、私は食事を口に運んでいた。
今日の夕食はナポリタン。美味くもなんともない普通の味だけど、タダだと思えば重みは全く違う。
窓が一つもない地下の薄暗い店内を潜り抜けて、一人の大男が水の入ったコップを私の前に置いた。
「食ってばっかだな、お前。よく太らねぇの」
「太ったよ。見ればわかるでしょ。このやけ食い」
「おーおー。言ってろ。どうせチビのままだ」
大男はだらっとしたティーシャツの上に、店のロゴの入ったエプロンを引っ掛けていた。そのバイトスタイルのままで、彼はどさりと私の向かい側に座った。
「やめて。私ハウスダストに弱いの」
「俺にその嘘通用すっか?」
浅黒い肌に彫りの深い顔立ち、そして無駄なく筋肉のついた二メートル近い長身。普通に面と向かえば裸足で逃げ出したくなるような強烈な迫力だけど、私にとってはあまり関係ない。
だって私が生まれてから、親よりも長い時間一緒にいた存在なのだから。
男の後ろから、店員なのか遊び仲間なのかわからないお姉さんが声を上げた。
「拓磨ー、酒はぁ?」
「んじゃ、ビール二本」
私はナポリタンを口につけたまま、じろりと彼に照準を合わせた。
「未成年に飲ませるな。私、酒いらない」
「へいよ。やっぱ一本で」
「はーい」
間延びした声で、化粧の濃いお姉さんは奥に引っ込んでいく。
ただその辺でイカれた音楽に乗ってる姉さん兄さんに比べれば、お姉さんはましな方だった。
息が詰まるような狭い室内で、ほとんど裸の兄さんやら、ゴスロリみたいな姉さんが、ギラギラの光と騒音みたいな音楽で揺れている。なんだか古臭い水族館みたいで、少し息がつまりそうになる。
食べてるのは私だけ。パイプ椅子に座ってるのも私と彼だけ。元々ここは踊ったり歌ったりするクラブで、私みたいにがつがつ物を食べに来る場所じゃない。
「また寂しいのかよ、沙世」
低く耳に響く声に、私はほんの少しだけ目を上げて呟く。
「そんなことない。私、もう十八歳だし」
私はあからさまな嘘とばれる言葉を彼に返していた。
「一人暮らしだってもう慣れたし」
向かい側で、彼は私の水を勝手に飲んでいた。私は文句にも聞こえる言葉を吐き出していた。
「兄ちゃんなんてもう十年、地元から離れてるじゃないか」
彼……私の兄はくだらないことのように薄く口元を歪めて、赤茶色の頭の後ろで両手を組みながら体を逸らした。
「俺は道逸れちまったからな。お前とは違ぇよ」
兄と私は連れ子同士だ。それに昔から不良連中とつるんでいた兄と、優等生じみた私は、必ずしも同じ時間軸を生きてこなかった。
私は口元についたナポリタンを安っぽい紙ティッシュで拭う。その隙に、兄は私の頭に手を置いていた。
振り払おうとする私を軽くいなして、兄は乱暴に私の頭を掻き混ぜる。
紫やら赤やらに変化する照明の中で、浅黒い兄の顔は次々と別の色に塗れていった。
それを私は顔をしかめながら見上げていたけど、手を振り払おうとはしなかった。
「兄ちゃん」
自然と言葉は私の口から零れ落ちた。
「遊びに連れてって。兄ちゃんのいつも行くとこでいいから」
思いつきだったけれど、言ってみてから良い考えかもしれないと思った。
上京生活に、疲れていた。兄のように都会を楽しんでいなかった。私はまるで、吸い寄せられるように兄の前にうずくまっている子どもだった。
駄々っ子のように呟いた私に、短いため息が返される。
呆れたような間があって、兄はつまらなそうに口を開いた。
「行くか」
そう言われて、私は久しぶりに自然と笑っていた。
今日の夕食はナポリタン。美味くもなんともない普通の味だけど、タダだと思えば重みは全く違う。
窓が一つもない地下の薄暗い店内を潜り抜けて、一人の大男が水の入ったコップを私の前に置いた。
「食ってばっかだな、お前。よく太らねぇの」
「太ったよ。見ればわかるでしょ。このやけ食い」
「おーおー。言ってろ。どうせチビのままだ」
大男はだらっとしたティーシャツの上に、店のロゴの入ったエプロンを引っ掛けていた。そのバイトスタイルのままで、彼はどさりと私の向かい側に座った。
「やめて。私ハウスダストに弱いの」
「俺にその嘘通用すっか?」
浅黒い肌に彫りの深い顔立ち、そして無駄なく筋肉のついた二メートル近い長身。普通に面と向かえば裸足で逃げ出したくなるような強烈な迫力だけど、私にとってはあまり関係ない。
だって私が生まれてから、親よりも長い時間一緒にいた存在なのだから。
男の後ろから、店員なのか遊び仲間なのかわからないお姉さんが声を上げた。
「拓磨ー、酒はぁ?」
「んじゃ、ビール二本」
私はナポリタンを口につけたまま、じろりと彼に照準を合わせた。
「未成年に飲ませるな。私、酒いらない」
「へいよ。やっぱ一本で」
「はーい」
間延びした声で、化粧の濃いお姉さんは奥に引っ込んでいく。
ただその辺でイカれた音楽に乗ってる姉さん兄さんに比べれば、お姉さんはましな方だった。
息が詰まるような狭い室内で、ほとんど裸の兄さんやら、ゴスロリみたいな姉さんが、ギラギラの光と騒音みたいな音楽で揺れている。なんだか古臭い水族館みたいで、少し息がつまりそうになる。
食べてるのは私だけ。パイプ椅子に座ってるのも私と彼だけ。元々ここは踊ったり歌ったりするクラブで、私みたいにがつがつ物を食べに来る場所じゃない。
「また寂しいのかよ、沙世」
低く耳に響く声に、私はほんの少しだけ目を上げて呟く。
「そんなことない。私、もう十八歳だし」
私はあからさまな嘘とばれる言葉を彼に返していた。
「一人暮らしだってもう慣れたし」
向かい側で、彼は私の水を勝手に飲んでいた。私は文句にも聞こえる言葉を吐き出していた。
「兄ちゃんなんてもう十年、地元から離れてるじゃないか」
彼……私の兄はくだらないことのように薄く口元を歪めて、赤茶色の頭の後ろで両手を組みながら体を逸らした。
「俺は道逸れちまったからな。お前とは違ぇよ」
兄と私は連れ子同士だ。それに昔から不良連中とつるんでいた兄と、優等生じみた私は、必ずしも同じ時間軸を生きてこなかった。
私は口元についたナポリタンを安っぽい紙ティッシュで拭う。その隙に、兄は私の頭に手を置いていた。
振り払おうとする私を軽くいなして、兄は乱暴に私の頭を掻き混ぜる。
紫やら赤やらに変化する照明の中で、浅黒い兄の顔は次々と別の色に塗れていった。
それを私は顔をしかめながら見上げていたけど、手を振り払おうとはしなかった。
「兄ちゃん」
自然と言葉は私の口から零れ落ちた。
「遊びに連れてって。兄ちゃんのいつも行くとこでいいから」
思いつきだったけれど、言ってみてから良い考えかもしれないと思った。
上京生活に、疲れていた。兄のように都会を楽しんでいなかった。私はまるで、吸い寄せられるように兄の前にうずくまっている子どもだった。
駄々っ子のように呟いた私に、短いため息が返される。
呆れたような間があって、兄はつまらなそうに口を開いた。
「行くか」
そう言われて、私は久しぶりに自然と笑っていた。