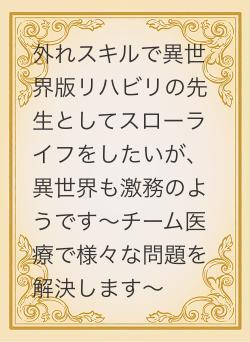「私達貴族夫人って本当に女性として正しい行動なのかしら?」
「それはどういうことかしら?」
「私は今まで公爵家夫人として、公爵家様に尽くして、子ども達の教育に力を注いできたつもりです。それはサゲスーム伯爵家夫人も変わらないでしょう」
私の言葉に伯爵家夫人も頷いている。
「私も今までそれが貴族の女性として生まれたら当たり前だと思っていました」
私はマリアと出会うまで、女性が生き生きと働く姿を想像できなかった。平民街にいる一般の女性は働いている人も多い。ただ、それは生きるためには仕方ないことだし、生まれた時から彼女の運命は決まっていた。
ただ、マリアを見ていると本当にその運命に従ってもいいのかと考えさせられてしまう。
病気で余命わずかと言われたマリアは兄のために、兄に少しでも恩返しがしたいと必死にドレスを作っていた。
疲れても毎日毎日泣きながら、必死に糸を編み込んでいた。
それは唯一の家族のために何かを残したいという彼女なりの気持ちだろう。
それが彼女の運命を変えた。
彼女が作ったドレスが貴族界に衝撃を与えて、今も早くあのドレスが手に入らないかと話が殺到するぐらいだ。
私もその姿を見て、貴族界で生まれた女性の運命を変えたいと思ってしまった。
「それが本当に私のやりたいことだったのかと思い出すきっかけになりました。私はきっと貴族夫人になったばかりの方達よりも早く亡くなるでしょ?」
「公爵夫人そんなことは――」
「いえ、それが事実なんです。私は私という存在が生きていたことを少しでも残して貴族女性がもっと豊かに楽しく暮らせる時代を作りたいと思ったんです」
きっと私が死ねば元公爵夫人と言われるだけだ。男性なら死んでもちゃんと名前が残る。
今回違う意味で名前を残したオオバッカも、ちゃんとオオバッカとして貴族界に名前が残る。
決してアリミアの名前が残るわけではない。
それが貴族に生まれた女性の運命なのだ。
「だからその一歩として商会を作ったんですよ。まぁ、初めは子を思う親馬鹿の気持ちからですけどね」
私が微笑みかけると、お茶会の会場から拍手が鳴り響いていた。いつのまにかその場で涙を流す人。私に握手を求めて来ようとする人。
意地悪な王妃も満面な笑みで手を叩いている。
「王妃の私はアリミアを応援するわ」
この王妃の言葉は公爵夫人ではなく、アリミアという貴族の生まれである女性の私に与えられた言葉だ。
やっぱりあの子は私のことをわかっているわね。
「それで私にもそのハンカチーフと香水はいつ買えるのかしら? こんなに良い匂いがするのに使わない女性はいないわよね?」
「さすが、王妃様! 私もハンカチーフと香水を一つください」
次々と手と声が上がっていく。宣伝活動はこれぐらいで良さそうだ。
この先のガーデン商会の活動も上手くいくだろう。
「ふふふ、やっぱりアリミアは昔から変わらないんだから」
小さくつぶやく王妃の声は私には聞こえなかった。
「それはどういうことかしら?」
「私は今まで公爵家夫人として、公爵家様に尽くして、子ども達の教育に力を注いできたつもりです。それはサゲスーム伯爵家夫人も変わらないでしょう」
私の言葉に伯爵家夫人も頷いている。
「私も今までそれが貴族の女性として生まれたら当たり前だと思っていました」
私はマリアと出会うまで、女性が生き生きと働く姿を想像できなかった。平民街にいる一般の女性は働いている人も多い。ただ、それは生きるためには仕方ないことだし、生まれた時から彼女の運命は決まっていた。
ただ、マリアを見ていると本当にその運命に従ってもいいのかと考えさせられてしまう。
病気で余命わずかと言われたマリアは兄のために、兄に少しでも恩返しがしたいと必死にドレスを作っていた。
疲れても毎日毎日泣きながら、必死に糸を編み込んでいた。
それは唯一の家族のために何かを残したいという彼女なりの気持ちだろう。
それが彼女の運命を変えた。
彼女が作ったドレスが貴族界に衝撃を与えて、今も早くあのドレスが手に入らないかと話が殺到するぐらいだ。
私もその姿を見て、貴族界で生まれた女性の運命を変えたいと思ってしまった。
「それが本当に私のやりたいことだったのかと思い出すきっかけになりました。私はきっと貴族夫人になったばかりの方達よりも早く亡くなるでしょ?」
「公爵夫人そんなことは――」
「いえ、それが事実なんです。私は私という存在が生きていたことを少しでも残して貴族女性がもっと豊かに楽しく暮らせる時代を作りたいと思ったんです」
きっと私が死ねば元公爵夫人と言われるだけだ。男性なら死んでもちゃんと名前が残る。
今回違う意味で名前を残したオオバッカも、ちゃんとオオバッカとして貴族界に名前が残る。
決してアリミアの名前が残るわけではない。
それが貴族に生まれた女性の運命なのだ。
「だからその一歩として商会を作ったんですよ。まぁ、初めは子を思う親馬鹿の気持ちからですけどね」
私が微笑みかけると、お茶会の会場から拍手が鳴り響いていた。いつのまにかその場で涙を流す人。私に握手を求めて来ようとする人。
意地悪な王妃も満面な笑みで手を叩いている。
「王妃の私はアリミアを応援するわ」
この王妃の言葉は公爵夫人ではなく、アリミアという貴族の生まれである女性の私に与えられた言葉だ。
やっぱりあの子は私のことをわかっているわね。
「それで私にもそのハンカチーフと香水はいつ買えるのかしら? こんなに良い匂いがするのに使わない女性はいないわよね?」
「さすが、王妃様! 私もハンカチーフと香水を一つください」
次々と手と声が上がっていく。宣伝活動はこれぐらいで良さそうだ。
この先のガーデン商会の活動も上手くいくだろう。
「ふふふ、やっぱりアリミアは昔から変わらないんだから」
小さくつぶやく王妃の声は私には聞こえなかった。