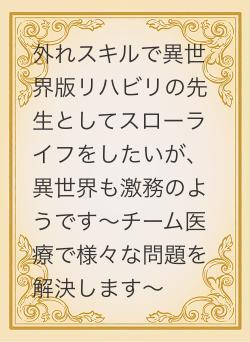パーティーが始まると公爵家の人達は、たくさんの貴族に挨拶をしていた。その間、関係ない僕達はオーブナーと共に美味しいご飯を食べていた。
「おい、リックこれも食べろよ。マリアはこれだ」
オーブナーがたくさん料理を運んでくるため、僕達は必死に食べている。全体的にパーティーの食事だからか、気軽に食べられる物が多い。
「美味しいか?」
「んー、僕はオーブナーさんのご飯の方が好きですね」
「私もそう思います」
どれを食べても豪華で美味しいが、オーブナーが作った料理には敵わない気がする。それだけ僕達がオーブナーの料理に慣れたってことだ。
実際に公爵家の人達と食べる機会があっても、オーブナーが料理を作ってくれることが多かった。
「ふん、今度はデザートを持って来る」
オーブナーはデザートを取りに行く。その後ろ姿はどこかウキウキとしていた。
僕達はオーブナーが戻ってくるのを待っていると誰かに声をかけられた。
「あっ、マリアちゃんいたいた」
キラキラなドレスに身を包んだデンカだ。彼女はずっと貴族の令嬢達に詰め寄られていたが、隙を見て逃げ出してきたらしい。
今まで見たことのない真新しい種類のドレスに令嬢達は興味深々だと言っていた。
「マリアちゃんのお兄ちゃんってもふもふの王子様だったんだね」
もふもふの王子様?
確かにこの間会った時にそんなことを言っていた気がする。
「それを言ったらデンカさんが王族だと思わなかったですよ?」
僕の言葉にマリアは驚いていた。そんなに驚くことなんだろうか。
「お兄ちゃん……殿下って名前ではないよ?」
「ふふふ、もふもふの王子様は天然なんだね。改めて自己紹介をします」
カーテシーが出来ないため、静かにお辞儀をする。
彼女の本当の名前はソフィアと言うらしい。
殿下は王族の人の呼び名のようなもので、名前ではないことを今知った。
何も知らずに関わっていたことが恥ずかしくなってしまう。
もし、ソフィアが礼儀に厳しい王族なら、僕は何かしらの罰を与えられていたかもしれない。
今まで食べていくのに精一杯で、生きる手段しか知らない。これからはしっかりとした教養も必要になるのだろう。
「お前らデザートを――」
そんな中、ケーキをたくさん持ってきたオーブナーが帰ってきた。この光景に驚いてたのか立ち止まっている。それはソフィアも同じようだ。
「ソフィア殿下お久しぶりです」
どこかよそよそしいオーブナーにソフィア殿下が戸惑っている。
さっきまで話していた貴族冒険者とは、また違った対応だ。
「用がなければ私はこれで失礼します」
オーブナーは僕達にケーキを渡すと、どこかへ行ってしまった。取り残された僕とマリアはソフィアを見つめる。
「追いかけないんですか?」
「私が追いかけても……」
ソフィアの顔は、初めて庭で会った時と同じ顔をしていた。
「あの時と同じ顔をしてますよ?」
「あの時と?」
「今すごく後悔している顔です」
きっとあの時言っていた後悔はオーブナーに対してなんだろう。
詳しい事情はわからないが、後悔しているのならちゃんと気持ちを伝えた方が良いはずだ。
後悔した時にはもう遅い。それは僕も感じている。
ソフィアは自分の中で考えているのだろう。それでも中々動くことが出来ないでいた。
「ソフィア殿下、私からも一ついいですか?」
「はい」
マリアも真剣な顔でソフィアを見つめる。それを感じたのか、ソフィアの表情が変わった。
「私が作ったドレスを着ているソフィア殿下は、このパーティー会場にいるどんな女性でも綺麗で美しいです」
周囲を見渡して優しく微笑むマリア。彼女も僕と同じ気持ちなんだろう。
今ここで動かないと、またきっと後悔することになる。
「だから行ってきてください!」
僕とマリアは優しくソフィアの背中を押す。ひらりと揺れ動くドレスが、まるで羽ばたく妖精……いや、モススのようだった。
「おい、リックこれも食べろよ。マリアはこれだ」
オーブナーがたくさん料理を運んでくるため、僕達は必死に食べている。全体的にパーティーの食事だからか、気軽に食べられる物が多い。
「美味しいか?」
「んー、僕はオーブナーさんのご飯の方が好きですね」
「私もそう思います」
どれを食べても豪華で美味しいが、オーブナーが作った料理には敵わない気がする。それだけ僕達がオーブナーの料理に慣れたってことだ。
実際に公爵家の人達と食べる機会があっても、オーブナーが料理を作ってくれることが多かった。
「ふん、今度はデザートを持って来る」
オーブナーはデザートを取りに行く。その後ろ姿はどこかウキウキとしていた。
僕達はオーブナーが戻ってくるのを待っていると誰かに声をかけられた。
「あっ、マリアちゃんいたいた」
キラキラなドレスに身を包んだデンカだ。彼女はずっと貴族の令嬢達に詰め寄られていたが、隙を見て逃げ出してきたらしい。
今まで見たことのない真新しい種類のドレスに令嬢達は興味深々だと言っていた。
「マリアちゃんのお兄ちゃんってもふもふの王子様だったんだね」
もふもふの王子様?
確かにこの間会った時にそんなことを言っていた気がする。
「それを言ったらデンカさんが王族だと思わなかったですよ?」
僕の言葉にマリアは驚いていた。そんなに驚くことなんだろうか。
「お兄ちゃん……殿下って名前ではないよ?」
「ふふふ、もふもふの王子様は天然なんだね。改めて自己紹介をします」
カーテシーが出来ないため、静かにお辞儀をする。
彼女の本当の名前はソフィアと言うらしい。
殿下は王族の人の呼び名のようなもので、名前ではないことを今知った。
何も知らずに関わっていたことが恥ずかしくなってしまう。
もし、ソフィアが礼儀に厳しい王族なら、僕は何かしらの罰を与えられていたかもしれない。
今まで食べていくのに精一杯で、生きる手段しか知らない。これからはしっかりとした教養も必要になるのだろう。
「お前らデザートを――」
そんな中、ケーキをたくさん持ってきたオーブナーが帰ってきた。この光景に驚いてたのか立ち止まっている。それはソフィアも同じようだ。
「ソフィア殿下お久しぶりです」
どこかよそよそしいオーブナーにソフィア殿下が戸惑っている。
さっきまで話していた貴族冒険者とは、また違った対応だ。
「用がなければ私はこれで失礼します」
オーブナーは僕達にケーキを渡すと、どこかへ行ってしまった。取り残された僕とマリアはソフィアを見つめる。
「追いかけないんですか?」
「私が追いかけても……」
ソフィアの顔は、初めて庭で会った時と同じ顔をしていた。
「あの時と同じ顔をしてますよ?」
「あの時と?」
「今すごく後悔している顔です」
きっとあの時言っていた後悔はオーブナーに対してなんだろう。
詳しい事情はわからないが、後悔しているのならちゃんと気持ちを伝えた方が良いはずだ。
後悔した時にはもう遅い。それは僕も感じている。
ソフィアは自分の中で考えているのだろう。それでも中々動くことが出来ないでいた。
「ソフィア殿下、私からも一ついいですか?」
「はい」
マリアも真剣な顔でソフィアを見つめる。それを感じたのか、ソフィアの表情が変わった。
「私が作ったドレスを着ているソフィア殿下は、このパーティー会場にいるどんな女性でも綺麗で美しいです」
周囲を見渡して優しく微笑むマリア。彼女も僕と同じ気持ちなんだろう。
今ここで動かないと、またきっと後悔することになる。
「だから行ってきてください!」
僕とマリアは優しくソフィアの背中を押す。ひらりと揺れ動くドレスが、まるで羽ばたく妖精……いや、モススのようだった。