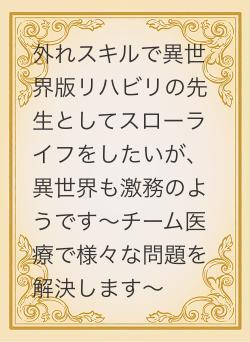私は兄達と別れて部屋に招かれた。今日は事前に公爵夫人からパーティー用のドレスを作って欲しいと言われている。
ドレスなんて見たこともないし、作ったこともない。ただ、公爵家お抱えの洋裁師が手伝ってくれることになっている。
今まで経験したことがないドレス作りができるせっかくのチャンスだ。
すでに私は病気で夢を諦めてしまった。
いつか私が稼いだお金でお兄ちゃんにたくさん美味しいものを食べさせてあげる。
いつもお腹いっぱいだからと、私にご飯を譲っていたのは知っている。
寝ている時にお腹を鳴らして耐えていたのを知っている。
そんなお兄ちゃんを今度は私が幸せにしたい。
それが私の小さい頃からの夢だった。
「きっと大丈夫だけど、しっかり挨拶するのよ」
事前に挨拶の仕方を聞いて練習している。今回ドレスを作るのは、この国の王族であるソフィア殿下のドレスだ。
扉から凛とした立ち姿で、華麗なドレスを纏った綺麗な女性が入ってきた。
目に入った瞬間、あまりの美しさに時間が止まったように感じた。
「ご機嫌麗しゅうございます。ソフィア殿下」
公爵夫人はドレスの端を持って足を少し引いてお辞儀をする。
これは貴族特有の挨拶の仕方でカーテシーと言う挨拶方法だ。私もそれに合わせて同じような動きをする。
慣れていないため少し動きにくい。それでもソフィア殿下は優しく微笑んでいた。
すごく優しい方なんだろう。
「お目にかかれて光栄です。ソフィア殿下」
「あなたがマリアさんかしら」
私は小さく頷く。それを見て公爵夫人は笑っていた。
「まだまだマナーがわからない子だから許してちょうだいね」
どうやら頷いて返事をしたらいけないらしい。すぐに公爵夫人がフォローしたが、ソフィア殿下は特に気にしていないようだ。
「ふふふ、今日は可愛い子達に元気をもらえる日ね。それで私のドレスが見たいってことよね?」
「はい! いつもどのようなお召し物を着ているのか参考にさせて頂きたいです」
今回はソフィア殿下がどのようなドレスを好んでいるのか、直接話を聞く予定になっている。
ソフィア殿下は近くにいた使用人に声をかけると、たくさんのドレスを持ってきた。見たことないドレスの形や色に私は興味津々だ。
「基本的に皆さんと変わりないですね」
「王族だから少し豪華なのが特徴かしら」
確かに公爵夫人が言うように、ドレスにはたくさんのレースがついており、大きく広がるドレスが多い。
色は赤や黄、青と言った目立つ色ばかりだ。
「白色のドレスってないですか?」
その中で唯一白色のドレスがなかった。モススの糸は白色のため、色がついたドレスが必要なら染める必要が出てくる。
「貴族は基本的に目立つために白は着ないのよ。私も赤いドレスを着ているのはそういうことよ」
公爵夫人が赤いドレスを着ているのは、基本的に人よりも目立つためらしい。それはそれで似合っている。
ただ、ソフィア殿下のように金色の髪の毛に青の瞳なら、白色のドレスも似合いそうな気がする。
「あとはこういうタイプのドレスはありますか? ソフィア殿下はすごく綺麗な体をしているので似合いそうですが――」
私は形を手で表すがどうやら伝わらないようだ。
「紙とペンを持ってきて頂戴!」
使用人に頼むとすぐに何かを持ってきた。使ったことのない道具に戸惑っていると、ソフィア殿下が直接使い方を教えてくれた。
「ソフィア殿下の胸のところからお尻までは密着する形で、足元に向かって大きく広がるのはどうですか? レースもいらないですし、これなら無駄な生地もなく足りると思います」
二人は私が書いた紙を見て驚いた表情をしている。まるで魚のようなドレスだと言っていた。
私は魚を見たことはないが、似たような形があるのだろう。
色も染められない可能性を考えて白になっても良いと言っていた。特に白のドレスに抵抗はないらしい。
誰とも被らないデザインと色のため、ある意味画期的なアイデアだと言っていた。
寝たきりで動けなかった私が王女様のドレスを作るなんて夢のようだ。
ドレスが決まれば今日の話は終わりだ。高鳴る気持ちを抑えて、私達はリックが待つ部屋に向かうことにした。
ドレスなんて見たこともないし、作ったこともない。ただ、公爵家お抱えの洋裁師が手伝ってくれることになっている。
今まで経験したことがないドレス作りができるせっかくのチャンスだ。
すでに私は病気で夢を諦めてしまった。
いつか私が稼いだお金でお兄ちゃんにたくさん美味しいものを食べさせてあげる。
いつもお腹いっぱいだからと、私にご飯を譲っていたのは知っている。
寝ている時にお腹を鳴らして耐えていたのを知っている。
そんなお兄ちゃんを今度は私が幸せにしたい。
それが私の小さい頃からの夢だった。
「きっと大丈夫だけど、しっかり挨拶するのよ」
事前に挨拶の仕方を聞いて練習している。今回ドレスを作るのは、この国の王族であるソフィア殿下のドレスだ。
扉から凛とした立ち姿で、華麗なドレスを纏った綺麗な女性が入ってきた。
目に入った瞬間、あまりの美しさに時間が止まったように感じた。
「ご機嫌麗しゅうございます。ソフィア殿下」
公爵夫人はドレスの端を持って足を少し引いてお辞儀をする。
これは貴族特有の挨拶の仕方でカーテシーと言う挨拶方法だ。私もそれに合わせて同じような動きをする。
慣れていないため少し動きにくい。それでもソフィア殿下は優しく微笑んでいた。
すごく優しい方なんだろう。
「お目にかかれて光栄です。ソフィア殿下」
「あなたがマリアさんかしら」
私は小さく頷く。それを見て公爵夫人は笑っていた。
「まだまだマナーがわからない子だから許してちょうだいね」
どうやら頷いて返事をしたらいけないらしい。すぐに公爵夫人がフォローしたが、ソフィア殿下は特に気にしていないようだ。
「ふふふ、今日は可愛い子達に元気をもらえる日ね。それで私のドレスが見たいってことよね?」
「はい! いつもどのようなお召し物を着ているのか参考にさせて頂きたいです」
今回はソフィア殿下がどのようなドレスを好んでいるのか、直接話を聞く予定になっている。
ソフィア殿下は近くにいた使用人に声をかけると、たくさんのドレスを持ってきた。見たことないドレスの形や色に私は興味津々だ。
「基本的に皆さんと変わりないですね」
「王族だから少し豪華なのが特徴かしら」
確かに公爵夫人が言うように、ドレスにはたくさんのレースがついており、大きく広がるドレスが多い。
色は赤や黄、青と言った目立つ色ばかりだ。
「白色のドレスってないですか?」
その中で唯一白色のドレスがなかった。モススの糸は白色のため、色がついたドレスが必要なら染める必要が出てくる。
「貴族は基本的に目立つために白は着ないのよ。私も赤いドレスを着ているのはそういうことよ」
公爵夫人が赤いドレスを着ているのは、基本的に人よりも目立つためらしい。それはそれで似合っている。
ただ、ソフィア殿下のように金色の髪の毛に青の瞳なら、白色のドレスも似合いそうな気がする。
「あとはこういうタイプのドレスはありますか? ソフィア殿下はすごく綺麗な体をしているので似合いそうですが――」
私は形を手で表すがどうやら伝わらないようだ。
「紙とペンを持ってきて頂戴!」
使用人に頼むとすぐに何かを持ってきた。使ったことのない道具に戸惑っていると、ソフィア殿下が直接使い方を教えてくれた。
「ソフィア殿下の胸のところからお尻までは密着する形で、足元に向かって大きく広がるのはどうですか? レースもいらないですし、これなら無駄な生地もなく足りると思います」
二人は私が書いた紙を見て驚いた表情をしている。まるで魚のようなドレスだと言っていた。
私は魚を見たことはないが、似たような形があるのだろう。
色も染められない可能性を考えて白になっても良いと言っていた。特に白のドレスに抵抗はないらしい。
誰とも被らないデザインと色のため、ある意味画期的なアイデアだと言っていた。
寝たきりで動けなかった私が王女様のドレスを作るなんて夢のようだ。
ドレスが決まれば今日の話は終わりだ。高鳴る気持ちを抑えて、私達はリックが待つ部屋に向かうことにした。