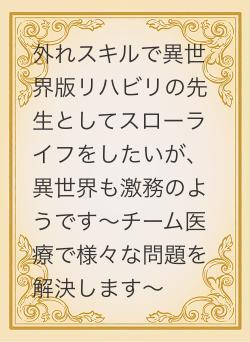家に息子が帰ってきてから、少し家の中が明るくなった気がする。あんな事件があった息子の笑顔を見ることが、再び来るとは思いもしなかった。
「今日はお茶会にお招き頂きありがとうございます」
「あら、お元気でしたか」
今日公爵家夫人の私がお茶会を開くことになっている。挨拶をしてきたのは、同じ公爵家夫人だ。
彼女とは昔から気が合わないことで有名だ。同じ公爵家として誘わないわけにはいかないため、声をかけているがなぜか毎回参加してくる。
正直この女性はめんどくさい。
「そういえば、息子さんはお元気かしら」
「ええ、最近楽しそうに子ども達と遊んでいるわ」
彼女は蔑むように笑っている。きっと私の言っていることが嘘だと思っているのだろう。
本当に朝からオーブナーは楽しそうに訓練場で遊んでいたわ。
リックは死にそうな顔で逃げていたけど、息子ってああいうことには手を抜かないタイプだから心配になってしまう。
「公爵夫人聞いてます?」
「あっ、すみません。考えごとをしていましたわ」
「ふふふ、息子さんがあんなことを犯さなければ、今頃騎士団長になっていただろうに……」
悲しそうにしているその顔面に指を突っ込みたいぐらいムカつく顔をしている。
あなたの大きな鼻は指を突っ込むためにあるようなものね。
オーブナーは元々王族である殿下を守る立場の職についていた。しかし、殿下は視察の時に魔物に襲われてしまった。
殿下を守るために、一人で抱えて逃げた。息子は立派に役目を果たしたと私は思っている。
実際に息子へ褒美が与えられたのだ。王からもその行動は認められたはずなのに、息子はそれを辞退した。
周囲からの目がそうさせなかったのだ。
殿下を抱えて逃げた息子に非難の声が上がった。その背景に同じ貴族出身である騎士が命をかけて殿下を守ったという理由があった。
もちろん王はその人達にも言葉をかけていた。それでも逃げるという行動に周りは納得できないのだろう。
きっとほとんどの貴族は公爵家である私達を陥れるためとはわかっている。それでも息子は責任を取るために騎士をやめた。
本人は元々宿屋の経営をしたいと言っていたが、それは騎士という仕事から離れるためだったと思っている。
それでも帰ってきた息子の顔を見たら、本当に宿屋がやりたかったのかと思ってしまう。
あの子達が落ちぶれていた息子を救ってくれた。本当に感謝しかない。
「それでこの間冒険者として勉強している息子が、ミスリルを持ってかえってきたのよ! あのミスリルよ!」
自分の息子は実力があると言いたいのだろう。そんな話を一刀両断する人が現れた。
「皆様ご機嫌よう」
私達は立ち上がり一礼して挨拶をする。彼女こそがオーブナーが助けたソフィア殿下だ。
殿下が来るからみんなこのお茶会に参加している。むしろ殿下は私が開催するお茶会にしか来ないのが特徴だ。
彼女の中に息子に対する思いがあるのだろう。
お茶会は普段通りに始まり、各々最近の流行を話し出した。
もちろん鼻に指を突っ込みたくなる公爵夫人は、息子がミスリルを持って帰ってきた話だ。
何度も同じ話をして、正直飽きないのだろうか。
「アリミア夫人は何かありますか?」
ソフィア殿下は私に息子の話が聞きたいのだろう。
「最近息子が子どもを連れて帰ってきてね。その子達が天使なのよ」
「お子さんが生まれたんですか?」
「いえ、我が家で面倒を見ているだけです」
私の言葉に他の夫人たちは鼻で笑っている。みんな嘘だと思っているのだろう。
ただ、ソフィア殿下だけは違った。
「私も会いたいですわ」
彼女は本当に性格が良い女性だ。王族なのに傲慢にならず、貴族達の誇りに値する。
それを他の貴族達は気付かないようだ。
「ソフィア殿下! きっと悲しみに暮れたアリミア夫人の戯言――」
「今度遊びに来るといいですわ。これはあの子達がソフィア殿下にプレゼントするって手作りで用意していたのよ」
いつまでも黙っている私ではない。今度は息子を救ったあの子達を私が助ける番だ。
箱に入ったハンカチーフを取り出す。ハンカチーフの縁には王族である証の獅子が刻まれている。
「初めて見る生地ですわね」
ソフィア殿下も初めて見る生地のハンカチーフに興味津々だ。マリアは私達が驚くほどの裁縫技術を持っていた。
何かわからない糸を自分で編み込んで生地にするぐらいだ。
正直洋裁職人でも難しいだろう。
「本当にお邪魔してもよろしいんですか?」
「ええ、子ども達も喜ぶわ」
ソフィア殿下が興味を示したハンカチーフとなれば、他の夫人達は黙っていない。全員がうちに遊びに来たいと声をかけてくる。
「ごめんなさいね。生地が足りないのよ」
実際にマリアからは糸が足りないと聞いている。だから、ソフィア殿下しか誘えないのだ。
視線を感じた私は横を見ると、公爵夫人が悔しそうな顔をしていた。
ふふふ、惨めなのはあなたよ。
サゲスーム公爵夫人。
「今日はお茶会にお招き頂きありがとうございます」
「あら、お元気でしたか」
今日公爵家夫人の私がお茶会を開くことになっている。挨拶をしてきたのは、同じ公爵家夫人だ。
彼女とは昔から気が合わないことで有名だ。同じ公爵家として誘わないわけにはいかないため、声をかけているがなぜか毎回参加してくる。
正直この女性はめんどくさい。
「そういえば、息子さんはお元気かしら」
「ええ、最近楽しそうに子ども達と遊んでいるわ」
彼女は蔑むように笑っている。きっと私の言っていることが嘘だと思っているのだろう。
本当に朝からオーブナーは楽しそうに訓練場で遊んでいたわ。
リックは死にそうな顔で逃げていたけど、息子ってああいうことには手を抜かないタイプだから心配になってしまう。
「公爵夫人聞いてます?」
「あっ、すみません。考えごとをしていましたわ」
「ふふふ、息子さんがあんなことを犯さなければ、今頃騎士団長になっていただろうに……」
悲しそうにしているその顔面に指を突っ込みたいぐらいムカつく顔をしている。
あなたの大きな鼻は指を突っ込むためにあるようなものね。
オーブナーは元々王族である殿下を守る立場の職についていた。しかし、殿下は視察の時に魔物に襲われてしまった。
殿下を守るために、一人で抱えて逃げた。息子は立派に役目を果たしたと私は思っている。
実際に息子へ褒美が与えられたのだ。王からもその行動は認められたはずなのに、息子はそれを辞退した。
周囲からの目がそうさせなかったのだ。
殿下を抱えて逃げた息子に非難の声が上がった。その背景に同じ貴族出身である騎士が命をかけて殿下を守ったという理由があった。
もちろん王はその人達にも言葉をかけていた。それでも逃げるという行動に周りは納得できないのだろう。
きっとほとんどの貴族は公爵家である私達を陥れるためとはわかっている。それでも息子は責任を取るために騎士をやめた。
本人は元々宿屋の経営をしたいと言っていたが、それは騎士という仕事から離れるためだったと思っている。
それでも帰ってきた息子の顔を見たら、本当に宿屋がやりたかったのかと思ってしまう。
あの子達が落ちぶれていた息子を救ってくれた。本当に感謝しかない。
「それでこの間冒険者として勉強している息子が、ミスリルを持ってかえってきたのよ! あのミスリルよ!」
自分の息子は実力があると言いたいのだろう。そんな話を一刀両断する人が現れた。
「皆様ご機嫌よう」
私達は立ち上がり一礼して挨拶をする。彼女こそがオーブナーが助けたソフィア殿下だ。
殿下が来るからみんなこのお茶会に参加している。むしろ殿下は私が開催するお茶会にしか来ないのが特徴だ。
彼女の中に息子に対する思いがあるのだろう。
お茶会は普段通りに始まり、各々最近の流行を話し出した。
もちろん鼻に指を突っ込みたくなる公爵夫人は、息子がミスリルを持って帰ってきた話だ。
何度も同じ話をして、正直飽きないのだろうか。
「アリミア夫人は何かありますか?」
ソフィア殿下は私に息子の話が聞きたいのだろう。
「最近息子が子どもを連れて帰ってきてね。その子達が天使なのよ」
「お子さんが生まれたんですか?」
「いえ、我が家で面倒を見ているだけです」
私の言葉に他の夫人たちは鼻で笑っている。みんな嘘だと思っているのだろう。
ただ、ソフィア殿下だけは違った。
「私も会いたいですわ」
彼女は本当に性格が良い女性だ。王族なのに傲慢にならず、貴族達の誇りに値する。
それを他の貴族達は気付かないようだ。
「ソフィア殿下! きっと悲しみに暮れたアリミア夫人の戯言――」
「今度遊びに来るといいですわ。これはあの子達がソフィア殿下にプレゼントするって手作りで用意していたのよ」
いつまでも黙っている私ではない。今度は息子を救ったあの子達を私が助ける番だ。
箱に入ったハンカチーフを取り出す。ハンカチーフの縁には王族である証の獅子が刻まれている。
「初めて見る生地ですわね」
ソフィア殿下も初めて見る生地のハンカチーフに興味津々だ。マリアは私達が驚くほどの裁縫技術を持っていた。
何かわからない糸を自分で編み込んで生地にするぐらいだ。
正直洋裁職人でも難しいだろう。
「本当にお邪魔してもよろしいんですか?」
「ええ、子ども達も喜ぶわ」
ソフィア殿下が興味を示したハンカチーフとなれば、他の夫人達は黙っていない。全員がうちに遊びに来たいと声をかけてくる。
「ごめんなさいね。生地が足りないのよ」
実際にマリアからは糸が足りないと聞いている。だから、ソフィア殿下しか誘えないのだ。
視線を感じた私は横を見ると、公爵夫人が悔しそうな顔をしていた。
ふふふ、惨めなのはあなたよ。
サゲスーム公爵夫人。