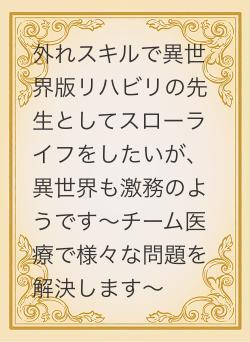王都が近くなると空いている土地に一度降りる。なんと馬車の中に馬がいたのだ。
みんなで馬車の中を探検した時に見つけた時はすごく嬉しかった。
毎日もふもふしていたら、モスス達は嫉妬していたのか、もふもふを強要することが増えた。
僕にとっては全てがご褒美で、空の旅は楽しかった。
馬を馬車に取り付けると、王都に向かって馬車を走らせる。
基本的に街の中に空飛ぶ馬車で入るのは禁止されているらしい。
「うわー、壁が大きいですね」
あまりにも大きな外壁と中に入る人の多さに驚いた。王都の入り口は貴族用と一般用の二つに分かれている。
そして、王都の中にも外壁があり貴族街と平民街で分かれて作られている。
貴族用の入り口から入ると、そのまま貴族街の城門へ一直線で行けるらしい。
一般用の入り口では、長い時間待つことになるため、そのままオーブナーの家まで馬車を走らせることになった。
「綺麗……」
マリアも目を輝かせて貴族街を見ていた。女の子は何歳になってもキラキラしたところが好きなんだろう。
それだけ貴族街はどこを見てもキラキラとしている街中だった。きっと僕達では関わることがない街なんだろう。
「天使様、あの辺一帯なら買いましょうか?」
ロンリーコンは相変わらず訳のわからないことを言っていた。この間もハンカチーフを販売するようになったら、買い占めると言っていたぐらいだ。
何でそんなにハンカチーフを使うのだろうか。
僕もSランク冒険者になったら、不自由なくずっともふもふできる生活がしたい。
「お前らついたぞ」
そんなことを思っていると、どうやらオーブナーの家に着いたようだ。
「これが家ですか……?」
オーブナーを先頭に馬車から降りると、あまりの家の大きさに僕達は驚きを隠せない。目の前にあるのは家ではない。小さな町だ。
「ははは、家だな」
「驚いているリックも可愛いな」
「驚いている天使様も素敵です」
そんな僕達を大人達は楽しそうに見ていた。
「オーブナー様お待ちしておりました」
「ああ、クリス久しぶりだな」
出迎えてくれたのは見たこともない黒い服をきた白髪が似合う初老の男性だ。彼はここの家で働く、使用人らしい。
「数日お世話になりますリックです」
「マリアです」
僕達はすぐに挨拶をすると、優しそうな顔で微笑んでいる。
「昔のオーブナー様より礼儀正しいですね」
「うるせーよ」
オーブナーも久しぶりに会う人達なのか、楽しそうに話していた。
昔はヤンチャな男の子だったらしい。
クリスに案内されるがまま家の中に入って行くと、たくさんの人達が忙しそうに働いている。
家の中が綺麗だからか、働いている人の白い服の汚れが目立っている。
「替え服ってこういうところでも使えそうだね」
マリアも同じことを思っていたのだろう。マリアはオーブナーのために替え服を内緒で作っている。
きっと宿屋を続けるために帰るだろう。だから、そんなオーブナーのために、使える替え服を僕達で今までのお礼としてプレゼントする予定だ。
僕達は広い部屋に案内されると、しばらくそこで待つように言われた。
「じゃあ、俺達王都にいるから外に行きたくなったら呼んでくれ」
そう言ってロンリーコンとショタッコンは部屋から出て行ってしまった。
しばらくすると、執事のクリスがカートにたくさんの食事を乗せて戻ってきた。
目の前には美味しそうなパンや見たこともない食べ物がたくさん置いてある。良い匂いを放っているが、勝手に食べても良いのだろうか。
オーブナーもいないため、どうするのが正しいのかもわからない。
貴族相手に変なことをしたら、命の危険もあると冒険者に聞いたこともある。
せっかく食べるならいつもみたいに、オーブナーと一緒に食べた方が楽しいだろう。
あまりにも広い部屋に案内された僕達は居心地が悪くなり、部屋の隅で固まるように待つことにした。
もふもふしていたらいつのまにか時間も経っているだろう。
「おい、お前達ちゃんと食べて――」
僕達が待っていると綺麗な装いをしたオーブナーが戻ってきた。今まで宿屋で見ていたオーブナーとは別人で、貴族と言われても納得できるような姿に改めて貴族だと再認識した。
壁際で待っている僕達を見てオーブナーは眉間にシワを寄せて走ってきた。
「あっ、おかえりなさい……?」
久しぶりに見たオーブナーの怒っている顔に僕達は困惑する。
「そんなに気を使わなくていい」
オーブナーは僕達を優しく抱き込んだ。どうやらオーブナーは怒っているわけではないようだ。
オーブナーはそのまま僕達を抱えて椅子に座らせた。
目の前にはさっきクリスが持ってきたパン達が並べられる。
「勝手に食べて良かったんだぞ?」
きっとオーブナーは何か変な勘違いをしているのだろう。
別に気を使っているわけではない。
ただこの広い部屋のどこにいればいいのかわからないし、食べてないのはオーブナーを待っていた。
「オーブナーさんと一緒に食べようと思って待ってました。お兄ちゃんもそうだよね?」
「オーブナーさんの料理が美味しいのもあるけど、いつも一緒だから美味しんですよ」
マリアも僕と同じ気持ちだった。そんな僕達を見て、オーブナーの目は少しうるうるとしていた。
僕達と視線が合うとオーブナーは目を逸らす。風邪を引いているのか、少し鼻をすすっていた。
「あらあら、こんなオーブナーが見れるようになるとはね」
声がする方に目を向けると、綺麗な服に身を包んだ女性が入り口で微笑んでいた。
「うるせぇよ」
どうやら今日のオーブナーはどこかぶっきらぼうのようだ。
みんなで馬車の中を探検した時に見つけた時はすごく嬉しかった。
毎日もふもふしていたら、モスス達は嫉妬していたのか、もふもふを強要することが増えた。
僕にとっては全てがご褒美で、空の旅は楽しかった。
馬を馬車に取り付けると、王都に向かって馬車を走らせる。
基本的に街の中に空飛ぶ馬車で入るのは禁止されているらしい。
「うわー、壁が大きいですね」
あまりにも大きな外壁と中に入る人の多さに驚いた。王都の入り口は貴族用と一般用の二つに分かれている。
そして、王都の中にも外壁があり貴族街と平民街で分かれて作られている。
貴族用の入り口から入ると、そのまま貴族街の城門へ一直線で行けるらしい。
一般用の入り口では、長い時間待つことになるため、そのままオーブナーの家まで馬車を走らせることになった。
「綺麗……」
マリアも目を輝かせて貴族街を見ていた。女の子は何歳になってもキラキラしたところが好きなんだろう。
それだけ貴族街はどこを見てもキラキラとしている街中だった。きっと僕達では関わることがない街なんだろう。
「天使様、あの辺一帯なら買いましょうか?」
ロンリーコンは相変わらず訳のわからないことを言っていた。この間もハンカチーフを販売するようになったら、買い占めると言っていたぐらいだ。
何でそんなにハンカチーフを使うのだろうか。
僕もSランク冒険者になったら、不自由なくずっともふもふできる生活がしたい。
「お前らついたぞ」
そんなことを思っていると、どうやらオーブナーの家に着いたようだ。
「これが家ですか……?」
オーブナーを先頭に馬車から降りると、あまりの家の大きさに僕達は驚きを隠せない。目の前にあるのは家ではない。小さな町だ。
「ははは、家だな」
「驚いているリックも可愛いな」
「驚いている天使様も素敵です」
そんな僕達を大人達は楽しそうに見ていた。
「オーブナー様お待ちしておりました」
「ああ、クリス久しぶりだな」
出迎えてくれたのは見たこともない黒い服をきた白髪が似合う初老の男性だ。彼はここの家で働く、使用人らしい。
「数日お世話になりますリックです」
「マリアです」
僕達はすぐに挨拶をすると、優しそうな顔で微笑んでいる。
「昔のオーブナー様より礼儀正しいですね」
「うるせーよ」
オーブナーも久しぶりに会う人達なのか、楽しそうに話していた。
昔はヤンチャな男の子だったらしい。
クリスに案内されるがまま家の中に入って行くと、たくさんの人達が忙しそうに働いている。
家の中が綺麗だからか、働いている人の白い服の汚れが目立っている。
「替え服ってこういうところでも使えそうだね」
マリアも同じことを思っていたのだろう。マリアはオーブナーのために替え服を内緒で作っている。
きっと宿屋を続けるために帰るだろう。だから、そんなオーブナーのために、使える替え服を僕達で今までのお礼としてプレゼントする予定だ。
僕達は広い部屋に案内されると、しばらくそこで待つように言われた。
「じゃあ、俺達王都にいるから外に行きたくなったら呼んでくれ」
そう言ってロンリーコンとショタッコンは部屋から出て行ってしまった。
しばらくすると、執事のクリスがカートにたくさんの食事を乗せて戻ってきた。
目の前には美味しそうなパンや見たこともない食べ物がたくさん置いてある。良い匂いを放っているが、勝手に食べても良いのだろうか。
オーブナーもいないため、どうするのが正しいのかもわからない。
貴族相手に変なことをしたら、命の危険もあると冒険者に聞いたこともある。
せっかく食べるならいつもみたいに、オーブナーと一緒に食べた方が楽しいだろう。
あまりにも広い部屋に案内された僕達は居心地が悪くなり、部屋の隅で固まるように待つことにした。
もふもふしていたらいつのまにか時間も経っているだろう。
「おい、お前達ちゃんと食べて――」
僕達が待っていると綺麗な装いをしたオーブナーが戻ってきた。今まで宿屋で見ていたオーブナーとは別人で、貴族と言われても納得できるような姿に改めて貴族だと再認識した。
壁際で待っている僕達を見てオーブナーは眉間にシワを寄せて走ってきた。
「あっ、おかえりなさい……?」
久しぶりに見たオーブナーの怒っている顔に僕達は困惑する。
「そんなに気を使わなくていい」
オーブナーは僕達を優しく抱き込んだ。どうやらオーブナーは怒っているわけではないようだ。
オーブナーはそのまま僕達を抱えて椅子に座らせた。
目の前にはさっきクリスが持ってきたパン達が並べられる。
「勝手に食べて良かったんだぞ?」
きっとオーブナーは何か変な勘違いをしているのだろう。
別に気を使っているわけではない。
ただこの広い部屋のどこにいればいいのかわからないし、食べてないのはオーブナーを待っていた。
「オーブナーさんと一緒に食べようと思って待ってました。お兄ちゃんもそうだよね?」
「オーブナーさんの料理が美味しいのもあるけど、いつも一緒だから美味しんですよ」
マリアも僕と同じ気持ちだった。そんな僕達を見て、オーブナーの目は少しうるうるとしていた。
僕達と視線が合うとオーブナーは目を逸らす。風邪を引いているのか、少し鼻をすすっていた。
「あらあら、こんなオーブナーが見れるようになるとはね」
声がする方に目を向けると、綺麗な服に身を包んだ女性が入り口で微笑んでいた。
「うるせぇよ」
どうやら今日のオーブナーはどこかぶっきらぼうのようだ。