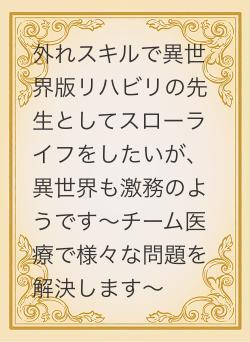「スパイダーって猫のことを言うんだね」
「ネコ……だと?」
オーブナーに剣を向けられても、僕がもふもふとしていたら逃げることもなく、その場で丸まってゴロゴロと鳴いている。
「ほら、ゴロゴロと言っているよ」
オーブナーがゆっくりと近づくと、猫は存在に気づき遠くへ逃げてしまった。猫って知らない人が来ると逃げる習性があるからな。
「オーブナーさんが驚かして逃げちゃったよ」
「あっ……すまない」
僕が怒るとオーブナーはおどおどとしている。再び猫に近づくと、オーブナーには警戒しているものの僕には近づいてきて体を擦り付けている。
やはり犬も可愛いが、猫も気ままで可愛い。
今後この野良猫と触れ合う機会がないと思い、僕はさらにもふもふとしていく。
ゴロゴロと地響きのように低い声が鳴り響くと、猫の体は輝き出した。
あれ……?
猫って光る生き物だったのか?
「リック!?」
あまりの眩しさに目を閉じる。その瞬間、体が持ち上げられた。
目を開けると木の後ろに身を潜めていた。
どうやら心配になってオーブナーが僕を抱えて、木のところまで逃げてきたのだろう。
「大丈夫か?」
「僕は大丈夫だけど、猫は大丈夫かな?」
ゆっくりと木の後ろから猫がいたところを見ると、もう姿は消えていた。
その場にあるのは黄土色に輝く大きなコイン。
なぜかガチャコインが猫がいた場所に落ちていたのだ。
突然いなくなった猫に悲しい気持ちになってくる。
別れの挨拶もできないまま、どこかに行ってしまった。
「これはなんだ?」
「これがガチャコインです。この間の謎の大きいやつを呼び出すのに必要で」
「ああ、例の毛玉を吐き出したやつか」
それだけ聞いたら謎の大きな物体も猫のような気もしてきた。猫もよくオエオエとして毛玉を吐き出していた。
僕はガチャコインを鞄に入れると、オーブナーに手を繋がれる。
「リックは手を繋いでおかないとすぐにどっかいくからな」
「もう12歳だからそんな心配しなくても――」
「お前はすぐにどこかへ行くからダメだ」
頑なにオーブナーは拒否をして手を離さないようだ。
「オーブナーさんの手って大きいですね」
久しぶりに大きな手に握られると、小さい頃に父と手を繋いで買い物に行っていたのを思い出す。
「そうか?」
「うん! 大きくてゴツゴツしてて、頑張っている手です!」
鍋を振っていることが多いからか、手には潰れたマメがたくさんあった。毎日僕達の料理を作るのも大変なんだろう。
どこかオーブナーは恥ずかしそうに照れていた。
「おーい、リックは見つかったか?」
遠くからロンリーコンの声も聞こえてきた。僕が手を振ると、わずかに見えていたのだろう。笑いながら近寄ってきた。
「お前達手を繋いでどうしたんだ?」
「リックはすぐに迷子になるからな」
「んっ……それって僕が悪いんですか?」
僕はちゃんと薬草を採取していただけだ。全て僕のせいにされたら納得できない。
「あー、俺達もちゃんと見てなかったからな。これで迷子になることもないだろう」
反対の手をロンリーコンが握ってきた。これで僕の両手は塞がってしまった。
「糸は見つかったから帰るぞ」
どうやら糸が見つかったところで、僕がいないことに気づいたらしい。ロンリーコンが遅れたのは糸を回収していたかららしい。
「これでマリアも喜ぶね」
「ああ、そうだな」
僕は再び迷子にならないように、手を繋ぎながら帰ることにした。二人とも背が高いからか、少し足が浮いていた。
決して嬉しくて浮いていたわけではない。僕はもう12歳だからね。
帰った後にショタッコンが泣き叫びながら、僕と手を繋ぎたいと言ったのはここだけの秘密だ。
「ネコ……だと?」
オーブナーに剣を向けられても、僕がもふもふとしていたら逃げることもなく、その場で丸まってゴロゴロと鳴いている。
「ほら、ゴロゴロと言っているよ」
オーブナーがゆっくりと近づくと、猫は存在に気づき遠くへ逃げてしまった。猫って知らない人が来ると逃げる習性があるからな。
「オーブナーさんが驚かして逃げちゃったよ」
「あっ……すまない」
僕が怒るとオーブナーはおどおどとしている。再び猫に近づくと、オーブナーには警戒しているものの僕には近づいてきて体を擦り付けている。
やはり犬も可愛いが、猫も気ままで可愛い。
今後この野良猫と触れ合う機会がないと思い、僕はさらにもふもふとしていく。
ゴロゴロと地響きのように低い声が鳴り響くと、猫の体は輝き出した。
あれ……?
猫って光る生き物だったのか?
「リック!?」
あまりの眩しさに目を閉じる。その瞬間、体が持ち上げられた。
目を開けると木の後ろに身を潜めていた。
どうやら心配になってオーブナーが僕を抱えて、木のところまで逃げてきたのだろう。
「大丈夫か?」
「僕は大丈夫だけど、猫は大丈夫かな?」
ゆっくりと木の後ろから猫がいたところを見ると、もう姿は消えていた。
その場にあるのは黄土色に輝く大きなコイン。
なぜかガチャコインが猫がいた場所に落ちていたのだ。
突然いなくなった猫に悲しい気持ちになってくる。
別れの挨拶もできないまま、どこかに行ってしまった。
「これはなんだ?」
「これがガチャコインです。この間の謎の大きいやつを呼び出すのに必要で」
「ああ、例の毛玉を吐き出したやつか」
それだけ聞いたら謎の大きな物体も猫のような気もしてきた。猫もよくオエオエとして毛玉を吐き出していた。
僕はガチャコインを鞄に入れると、オーブナーに手を繋がれる。
「リックは手を繋いでおかないとすぐにどっかいくからな」
「もう12歳だからそんな心配しなくても――」
「お前はすぐにどこかへ行くからダメだ」
頑なにオーブナーは拒否をして手を離さないようだ。
「オーブナーさんの手って大きいですね」
久しぶりに大きな手に握られると、小さい頃に父と手を繋いで買い物に行っていたのを思い出す。
「そうか?」
「うん! 大きくてゴツゴツしてて、頑張っている手です!」
鍋を振っていることが多いからか、手には潰れたマメがたくさんあった。毎日僕達の料理を作るのも大変なんだろう。
どこかオーブナーは恥ずかしそうに照れていた。
「おーい、リックは見つかったか?」
遠くからロンリーコンの声も聞こえてきた。僕が手を振ると、わずかに見えていたのだろう。笑いながら近寄ってきた。
「お前達手を繋いでどうしたんだ?」
「リックはすぐに迷子になるからな」
「んっ……それって僕が悪いんですか?」
僕はちゃんと薬草を採取していただけだ。全て僕のせいにされたら納得できない。
「あー、俺達もちゃんと見てなかったからな。これで迷子になることもないだろう」
反対の手をロンリーコンが握ってきた。これで僕の両手は塞がってしまった。
「糸は見つかったから帰るぞ」
どうやら糸が見つかったところで、僕がいないことに気づいたらしい。ロンリーコンが遅れたのは糸を回収していたかららしい。
「これでマリアも喜ぶね」
「ああ、そうだな」
僕は再び迷子にならないように、手を繋ぎながら帰ることにした。二人とも背が高いからか、少し足が浮いていた。
決して嬉しくて浮いていたわけではない。僕はもう12歳だからね。
帰った後にショタッコンが泣き叫びながら、僕と手を繋ぎたいと言ったのはここだけの秘密だ。